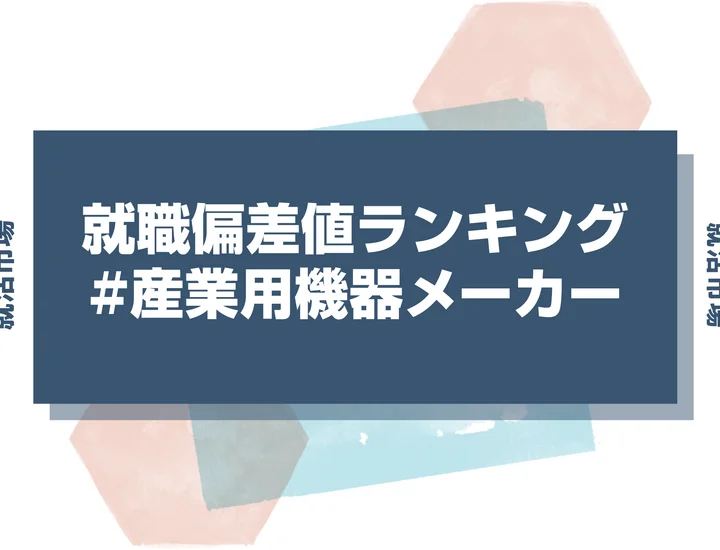『特に何もしてません』と正直に答えて最終面接を突破した話
地方鋀志望なのに「特に何もしてません」な現実
文学部社会学科で学んでいた私は、将来は地方の政策や地域作りに関わる仕事がしたいと考えていました。神奈川の実家から都内の大学に通う中で、地方と都市部の違いを実感していました。
しかし、就活を始める段階で、自分の大学生活を振り返って不安になりました。「学生時代に頑張ったこと」が、本当に思い浮かばなかったのです。
映画研究サークルには2年間所属していましたが、途中でフェードアウト。アルバイトは家庭教師を2年半続けていましたが、「画期的な指導法」や「特別な成果」と呼べるようなものはありませんでした。
社会学のゼミでは「地方都市の人口減少問題」というテーマで研究を進めていましたが、深く掘り下げた内容ではなく、成績も可もなく不可もなく。TOEICも615点と、特筆すべき数字ではありませんでした。
就活サイトで地方鋀員や地方自治体の内定者体験談を読むと、みな「ボランティア活動で地域振興」「学生団体でリーダーシップを発揮」「研究活動で革新的な提案」など、華々しい経験を持っていました。
「普通の大学生活しか送っていない私が、本当に地方鋀や自治体を目指せるのだろうか」──この不安と向き合うのに、かなりの時間がかかりました。
社会学ゼミの教授からのアドバイスで気づいたこと
就活について悩んでいた私に、ゼミの指導教授がかけてくれた言葉が転機となりました。
「地方行政の仕事は、華々しい経験よりも着実さや誠実さが求められる。地域の住民の日常的な困りごとに、素直に耳を傾けられる人が必要なんだよ」
この言葉で、私は「普通」であることの価値を初めて理解しました。特別な経験や華々しい実績がなくても、私には私なりの良さがあるのではないか。素直に等身大の自分で勝負してみよう、と思えるようになったのです。
中学3年生と高校1年生を担当。特別な指導法があったわけではないが、生徒との関係は良好で、継続して指導を依頼された。成績向上への工夫よりも、生徒が勉強に向かう環境作りを重視していた。
1-2年生の2年間所属。役職には就いていないが、月1回の上映会には必ず参加。自分から企画を提案することはなかったが、他のメンバーが提案する企画には積極的に協力していた。
「地方経済の活性化」というテーマで卒論を執筆。深く掘り下げた研究ではないが、基本的なデータ収集と分析は行った。教授からは「堅実な内容」と評価されたが、特別な賞賛は得ていない。
TOEIC受験(615点)、普通自動車免許取得、読書(月2-3冊程度)。どれも「普通」の範囲内で、特筆すべき成果や困難の克服エピソードはない。
冷静に自分を分析してみると、確かに華々しい経験はありません。しかし、「何もしていない」わけでもない。ただ、それらが就活の場で語るような「感動的なエピソード」になるかどうかは別問題でした。
そこで私は決めました。「無理に話を盛るのではなく、等身大の自分で勝負してみよう」と。
ここから逆転したこの世の誰でも実践できる方法
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート