冬インターンシップは、本選考に向けて業界研究や企業理解を深める絶好のチャンスです。
特にサントリーホールディングスは、「やってみなはれ」の精神で知られ、食品・飲料業界を牽引する存在として、毎年多くの就活生から絶大な人気を集めています。
その人気ゆえに、インターンの選考も狭き門となっています。
この記事では、サントリーの冬インターンシップに焦点を当て、その概要から選考対策、本選考への影響まで、皆さんが知りたい情報を徹底的に解説していきます。
しっかりと準備して、貴重な経験を掴み取りましょう。
【サントリーの冬インターン】サントリーの企業情報
サントリーと聞くと、多くの人が「プレミアム・モルツ」や「ボス」、「伊右衛門」といった飲料を思い浮かべるかもしれません。
しかし、サントリーグループは飲料・食品事業に留まらず、健康食品や外食、花など、非常に多角的な事業を展開しているグローバル企業です。
創業以来の「やってみなはれ」という挑戦の精神と、「利益三分主義」(社会への貢献、得意先・取引先への貢献、会社への貢献)といった独自の価値観を大切にしています。
インターン選考に臨む上では、こうした製品ラインナップだけでなく、企業理念や社会貢献活動(例:「水と生きる」)への深い理解が不可欠です。
【サントリーの冬インターン】サントリーの冬インターンはいつ実施される?
サントリーの冬インターンシップは、その年の採用スケジュールによって多少の変動はありますが、例年大学3年生(あるいは修士1年生)の10月頃から11月下旬にかけて募集が行われることが一般的です。
そして、実際のインターンシップ実施時期は、冬休み期間中である12月下旬から翌年の2月頃にかけて、数日間のプログラムとして開催されます。
募集開始のアナウンスは、サントリーの採用マイページや各種就活情報サイトで一斉に告知されます。
非常に人気が高く応募が殺到するため、募集開始と同時にエントリーシート(ES)を提出できるよう、早め早めの情報収集と準備を心がけることが重要です。
【サントリーの冬インターン】サントリーの冬インターンの内容
サントリーの冬インターンは、画一的な内容ではなく、職種理解を深めるための多様なコースが用意されているのが大きな特徴です。
営業(セールス)、マーケティング、研究開発(R&D)、生産技術、SCM(サプライチェーンマネジメント)など、サントリーの幅広い事業領域を体感できるプログラムが揃っています。
いずれのコースも「やってみなはれ」の精神に基づき、社員が実際に向き合っている課題に取り組む内容が多く、非常に実践的です。
単なる企業説明会とは一線を画し、濃密なフィードバックを受けられるため、参加できれば自己成長に直結する貴重な機会となるでしょう。
ここでは、代表的なコースの内容をいくつか紹介します。
マーケティングコースの体験
サントリーの「顔」とも言えるマーケティング職のインターンでは、新商品の企画立案や既存ブランドの戦略策定といったテーマにグループワークで取り組むことが多いです。
単に奇抜なアイデアを出すのではなく、市場データや消費者インサイトを分析し、論理的な戦略を組み立てるプロセスを徹底的に学びます。
例えば、「若年層向けの新しい無糖茶飲料を企画し、そのプロモーション戦略を立案せよ」といった具体的な課題が与えられます。
最終日には、現役のマーケターである社員に対してプレゼンテーションを行い、厳しいながらも愛のあるフィードバックを受けます。
サントリーのマーケターに求められる思考の深さや、ブランドへの情熱を肌で感じることができ、広告や商品開発に興味がある学生にとっては非常に刺激的な内容です。
営業(セールス)コースの体験
営業(セールス)コースでは、サントリーのビジネスの最前線を体感できます。
単なる「モノ売り」ではない、課題解決型の営業スタイルを学ぶことが中心です。
例えば、特定の小売店や飲食店といった得意先に対し、「どのような売り場を作れば売上が向上するか」「どんなメニューを提案すればお客様に喜ばれるか」といったソリューションを考えるワークが実施されます。
過去には、社員に同行して実際の商談の雰囲気を感じたり、オンラインで得意先との折衝をロールプレイング形式で学んだりするプログラムもありました。
自社の商品を通じていかにして得意先の課題を解決し、市場を創造していくかという、サントリー営業のダイナミズムと難しさを深く理解できるでしょう。
研究開発(R&D)・生産技術コースの体験
理系学生を対象とした研究開発(R&D)や生産技術コースは、サントリーの「ものづくり」の根幹に触れる内容です。
研究開発では、研究所の社員と交流しながら、「美味しさ」や「健康」といった価値を科学的に追求するプロセスの一部を体験します。
例えば、新しい香味成分の探索や、既存商品の改良といったテーマに取り組みます。
一方、生産技術コースでは、高品質な製品を安定的に製造するための生産ラインの効率化や、環境負荷の低減といった、工場が抱えるリアルな課題解決に挑みます。
いずれも専門性が高く、大学での研究内容がどのように実際のビジネスに応用されるかを知る絶好の機会であり、技術者としてのキャリアを考える上で非常に有益な時間となります。
【サントリーの冬インターン】サントリーの冬インターンの選考フロー
サントリーの冬インターン選考は、本選考さながらのステップを踏むことが特徴です。
まず、採用マイページへの登録後、エントリーシート(ES)の提出が求められます。
ここでは「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」や「インターンシップへの志望動機」などが問われます。
ESが通過すると、次にSPIや玉手箱といった形式のWebテスト(適性検査)が待っています。
この段階で応募者の多くが絞り込まれます。
Webテストを通過すると、グループディスカッション(GD)や複数回の面接(オンラインまたは対面)が実施されます。
志望動機だけでなく、サントリーの「やってみなはれ」精神に共感できる人物かどうかが厳しく見られます。
【サントリーの冬インターン】サントリーの冬インターンの倍率
サントリーは就活生からの人気が非常に高く、インターンシップの倍率も極めて高い水準にあります。
具体的な倍率の数字は公式には発表されていませんが、採用予定人数に対して、国内トップクラスの学生からの応募が数千、数万単位で集まることを考えると、その倍率は数十倍から、職種によっては100倍を超えるとも言われています。
特に、先ほど紹介したマーケティング職や、採用枠の少ない研究開発職などは、本選考以上の激戦となることを覚悟しなければなりません。
単なる「記念受験」ではまず通過できないため、後述する対策を万全に講じて臨む必要があります。
サントリーの冬インターンに受かるコツ
この狭き門を突破するためには、徹底した準備が不可欠です。
まず、エントリーシート(ES)の段階で、「なぜ競合他社(例:アサヒ、キリン)ではなくサントリーなのか」を明確に言語化する必要があります。
サントリー独自の価値観、例えば「やってみなはれ」の精神や「水と生きる」という理念に、自身の経験をどう結びつけるかが鍵です。
「やってみなはれ」を体現したエピソードとして、自ら高い目標を掲げ、周囲を巻き込みながら困難を乗り越えた具体的な経験を、状況(Situation)、課題(Task)、行動(Action)、結果(Result)の「STAR法」を用いて論理的に説明できるように整理しておきましょう。
面接では、その経験を深掘りされるため、暗記した内容を話すのではなく、自分の言葉で情熱を持って語ることが重要です。
【サントリーの冬インターン】サントリーの冬インターンは本選考優遇あり?
インターンシップに参加する上で、本選考への優遇措置があるのかは非常に気になるところです。
結論から言うと、サントリーの冬インターンシップ参加者には、何らかの本選考優遇がある可能性が高いです。
過去の例では、インターン参加者限定の早期選考ルートに案内されたり、本選考の面接回数が一部免除されたりといったケースがありました。
ただし、注意点として、インターンに参加したからといって「内定(内々定)」が確約されるわけではありません。
インターン中のパフォーマンスや取り組み姿勢も厳しく評価されており、そこでの評価が良くなければ、優遇が受けられない可能性もあります。
あくまでも「本選考への切符の一つ」と捉え、参加できた場合も気を抜かないことが肝心です。
【サントリーの冬インターン】まとめ
サントリーの冬インターンシップは、その人気と内容の濃さから、就職活動における非常に価値ある経験となります。
選考倍率は非常に高いですが、「なぜサントリーなのか」という問いを突き詰め、自らの「やってみなはれ」経験を整理するプロセスは、たとえ選考に通過しなかったとしても、必ず本選考の糧となります。
インターンシップは、企業が皆さんを見極める場であると同時に、皆さんが企業を見極める場でもあります。
この記事で解説した情報を参考に、万全の準備でサントリーの門を叩き、自身の可能性を試してみてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート




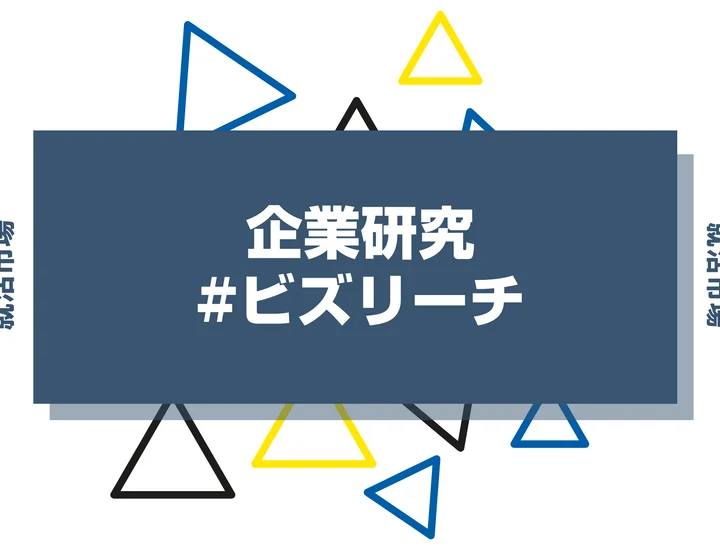
_720x550.webp)





_720x550.webp)