はじめに
理系学生のキャリアパスは、研究職だけにとどまりません。
大学で培った論理的思考力や分析能力、専門知識は、多様な業界や職種で高く評価されています。
しかし、研究以外の道に進むことに不安を感じたり、どのような選択肢があるのか分からなかったりする方も多いのではないでしょうか。
本記事では、理系学生が研究職以外を選ぶ理由から、活躍できる具体的な職種、そして就職活動を成功させるための戦略まで、幅広く解説します。
自身の可能性を広げ、最適なキャリアを見つけるための一助となれば幸いです。
理系が研究職以外を選ぶ理由
理系の大学院生や学部生が、研究職以外のキャリアを選択する理由は多岐にわたります。
自身の興味や価値観、将来のキャリアプランを深く考えた結果、研究とは異なる分野に魅力を感じる学生は少なくありません。
ここでは、理系学生が研究職以外の道を選ぶ、代表的な5つの理由について掘り下げていきます。
自身の考えと照らし合わせながら、キャリア選択の参考にしてください。
専門分野を広げたい
大学での研究は、特定のテーマを深く掘り下げるため、専門性が高まる一方で、視野が狭くなってしまう可能性もあります。
自身の専門分野だけに留まらず、より幅広い知識やスキルを習得したいという思いから、研究職以外を志望するケースは少なくありません。
例えば、IT業界でプログラミングスキルを身につけたり、コンサルティング業界で経営戦略を学んだりすることで、自身の専門性と新たなスキルを掛け合わせ、独自の価値を発揮したいと考えるのです。
未知の分野へ挑戦し、自身の可能性を広げたいという知的好奇心も、この選択を後押しする大きな要因と言えるでしょう。
社会貢献をより実感したい
基礎研究は、将来の科学技術の発展に不可欠ですが、その成果が社会に還元されるまでには長い年月を要することがあります。
そのため、自身の仕事がどのように社会の役に立っているのかを、より直接的に、そして早期に実感したいという思いから、研究職以外の道を選ぶ学生もいます。
例えば、メーカーの技術者として製品開発に携わったり、ITエンジニアとして人々の生活を便利にするシステムを構築したりすることで、自分の仕事の成果を身近に感じることができます。
社会との繋がりを重視し、人々の暮らしに直接貢献したいという価値観が、この選択の根底にあるのです。
成果を早く出したい
研究活動は、仮説検証を繰り返し、時には数年単位で一つのテーマに取り組むなど、成果が出るまでに時間がかかることが一般的です。
こうした研究の特性に対し、よりスピーディーに成果を出し、自身の成長を実感したいと考える人にとって、研究職以外の仕事は魅力的に映ります。
例えば、営業職やマーケティング職では、自身の働きかけが売上という明確な数字に直結し、短期間で成果を確認できます。
IT業界のプロジェクトも、数ヶ月単位で完結するものが多く、達成感を得やすい環境です。
自身の努力や工夫が、目に見える成果として早期に現れる環境を求めることも、キャリア選択の重要な動機の一つです。
人と関わる仕事がしたい
研究活動は、個人で黙々と実験や分析に取り組む時間が長くなる傾向があります。
もちろん、学会発表や共同研究などで他者と関わる機会もありますが、キャリアを考えた際に、より多くの人とコミュニケーションを取りながら仕事を進めたいと考える学生は少なくありません。
例えば、技術営業(セールスエンジニア)は、専門知識を活かして顧客の課題を解決する仕事であり、高いコミュニケーション能力が求められます。
また、コンサルタントとして多様な業界のクライアントと協働したり、チームで製品開発に取り組んだりすることも、人と深く関わる働き方と言えるでしょう。
研究活動に疲れた
学部や大学院での研究活動は、知的な探求心を満たす一方で、精神的・体力的に大きな負担を伴うことも事実です。
思うように実験結果が出ない焦りや、長時間労働、人間関係の悩みなどから、研究そのものに疲れを感じてしまうケースもあります。
必ずしも研究が嫌いになったわけではなくても、一度研究室という環境から離れ、新たなフィールドで自分の可能性を試したいと考えるのは自然なことです。
心機一転、ワークライフバランスを整えながら、これまで培ってきた能力を異なる形で発揮したいという思いが、研究職以外のキャリアを選択するきっかけになるのです。
理系出身者が活躍する職種
理系出身者の活躍の場は、研究室や開発部門に限定されません。
論理的思考能力、数的処理能力、課題解決能力といった、研究活動を通じて培われた素養は、多様な業界で高く評価されています。
ここでは、理系出身者がその専門性を活かし、大きな成果を上げている代表的な業界を4つ紹介します。
これらの業界では、研究とは異なる形で社会に貢献し、自身のキャリアを築いていくことが可能です。
IT・Web業界
IT・Web業界は、理系出身者の論理的思考力や情報処理能力が存分に活かせる分野です。
プログラミングにおけるアルゴリズムの構築や、膨大なデータから価値ある知見を導き出すデータサイエンスなど、理系的な素養が直接的に求められる職種が数多く存在します。
また、この業界は技術革新のスピードが速く、常に新しい知識を学び続ける探求心が不可欠です。
大学で培った学習能力や知的好奇心は、新しい技術をキャッチアップし、サービス開発に貢献する上で大きな強みとなります。
情報系の学生はもちろん、物理や数学、生物など、多様な専門分野の出身者が活躍しているのが特徴です。
医療・製薬業界
医療・製薬業界は、人の生命や健康に直結する分野であり、理系出身者の専門知識が不可欠です。
研究職以外にも、新薬の開発プロセスを管理する臨床開発モニター(CRA)や、医療従事者に医薬品の情報を提供する医薬情報担当者(MR)など、多様な職種が存在します。
これらの仕事では、医学・薬学に関する高度な知識に加え、データ分析能力や倫理観が求められます。
また、製造現場における品質管理や生産技術のポジションも、化学や生物系の知識を活かせる重要な役割です。
自身の専門性を社会貢献に直結させたいと考える理系出身者にとって、大きなやりがいを感じられる業界と言えるでしょう。
金融・コンサル業界
一見、文系のイメージが強い金融・コンサル業界ですが、実は高度な数理能力や分析能力を持つ理系出身者が数多く活躍しています。
金融業界では、金融商品の開発やリスク管理を行うクオンツやアクチュアリーといった専門職で、数学や物理学の知識が求められます。
また、企業の財務状況を分析するアナリストも、データに基づいた客観的な判断力が不可欠です。
コンサルティング業界では、クライアントが抱える複雑な課題に対し、論理的な思考力で解決策を導き出す能力が問われます。
研究で培った仮説検証のプロセスは、まさにコンサルタントの思考法そのものと言えるでしょう。
メーカー
メーカー(製造業)は、理系出身者にとって最もイメージしやすい業界の一つかもしれません。
研究開発職以外にも、製品の生産ラインを設計・改善する生産技術、製品の品質を保証する品質管理・品質保証、自社の技術力を顧客に提案する技術営業(セールスエンジニア)など、活躍の場は多岐にわたります。
これらの職種では、製品に関する深い知識はもちろんのこと、製造プロセス全体を俯瞰する視点や、顧客の課題を解決するための提案力が求められます。
自身の専門知識を活かして、ものづくりという形で社会に貢献したいと考える人にとって、非常に魅力的な選択肢と言えます。
IT・Web業界の研究職以外の仕事
急速な技術革新が進むIT・Web業界では、理系出身者の論理的思考力や問題解決能力が高く評価されています。
研究職以外にも、システムの設計から開発、運用、さらにはデータ分析やプロジェクトの進行管理まで、活躍のフィールドは非常に広いです。
ここでは、IT・Web業界における代表的な4つの職種を紹介し、それぞれの仕事内容や求められるスキルについて解説します。
プログラマ・システムエンジニア
プログラマは、システムエンジニアが作成した設計書に基づき、プログラミング言語を用いて実際にシステムやソフトウェアを開発する職種です。
一方、システムエンジニア(SE)は、顧客の要求をヒアリングし、どのようなシステムを構築すべきかという要件定義から、設計、開発、テスト、運用保守まで、プロジェクト全体に携わります。
どちらの職種も、論理的な思考力や、複雑な問題を分解して考える能力が不可欠であり、理系出身者が持つ素養と非常に親和性が高いです。
特に、情報科学系の学生はもちろん、数学や物理で培ったアルゴリズム的思考も大いに役立ちます。
データサイエンティスト
データサイエンティストは、事業活動によって得られる膨大なデータ(ビッグデータ)を分析し、ビジネス上の課題解決や意思決定に役立つ知見を導き出す専門職です。
統計学や情報科学、機械学習などの知識を駆使して、データの収集、加工、分析、モデル構築、そして結果の可視化までを一貫して行います。
研究活動におけるデータ解析や、統計的なアプローチに慣れ親しんだ理系出身者にとって、その経験を直接活かせる職種と言えるでしょう。
企業のマーケティング戦略立案や新サービスの開発など、データに基づいた意思決定の重要性が増す現代において、非常に需要の高い仕事です。
インフラエンジニア
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤となるサーバーやネットワーク、データベースなどの設計、構築、運用、保守を担当する技術者です。
ウェブサイトやアプリケーションが24時間365日安定して稼働するためには、彼らの存在が欠かせません。
物理的な機器の知識から、OSやミドルウェア、クラウド技術に関する深い理解まで、幅広いスキルが求められます。
システムの安定稼働というミッションに対し、地道な作業をこなし、トラブル発生時には冷静に原因を特定し解決する能力が重要です。
縁の下の力持ちとして、社会の情報インフラを支えることにやりがいを感じる人に向いています。
Webディレクター・デザイナー
Webディレクターは、ウェブサイトやWebサービスの制作プロジェクト全体を統括する責任者です。
クライアントの要望をヒアリングし、企画立案、デザイナーやエンジニアへの指示出し、スケジュール管理、品質管理など、その役割は多岐にわたります。
一方、Webデザイナーは、ユーザーにとって魅力的で使いやすいウェブサイトの見た目や操作性を設計・制作します。
どちらの職種も、論理的な思考力に加えて、ユーザーの視点に立つ共感力や創造性が求められます。
理系的な分析能力を活かして、データに基づいたサイト改善提案を行うなど、独自の価値を発揮することが可能です。
医療・製薬業界の研究職以外の仕事
医療・製薬業界は、人々の健康を支えるという大きな社会的使命を担っており、理系、特に生命科学系の専門知識を持つ人材が不可欠です。
研究開発職が注目されがちですが、新薬を世に送り出し、患者さんの元へ届けるまでには、数多くの職種が連携しています。
ここでは、研究職以外で理系の専門性を活かせる代表的な4つの仕事を紹介します。
臨床開発モニター
臨床開発モニター(CRA:Clinical Research Associate)は、製薬会社や医療機器メーカーが新しい医薬品や医療機器の承認を得るために行う「治験」が、ルール(GCP:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)に従って適切に行われているかを確認・サポートする専門職です。
医療機関を訪問し、医師や治験コーディネーターと協力しながら、治験の進捗管理やデータの信頼性確保に努めます。
医学・薬学に関する高度な専門知識はもちろん、高いコミュニケーション能力や正確な事務処理能力が求められます。
新薬誕生の最終段階に携わる、非常にやりがいの大きい仕事です。
医薬情報担当者(MR)
医薬情報担当者(MR:Medical Representative)は、製薬会社に所属し、自社の医薬品に関する情報を医療従事者(医師、薬剤師など)に提供する役割を担います。
医薬品の有効性や安全性、副作用といった専門的な情報を正確に伝え、適正な使用を推進することが主な業務です。
単なる営業職とは異なり、高度な医学・薬学の知識が不可欠であり、常に最新の医療情報を学び続ける姿勢が求められます。
医療従事者との信頼関係を築き、自社の医薬品を通じて患者さんの治療に貢献できることが、この仕事の大きな魅力と言えるでしょう。
品質管理・品質保証
品質管理・品質保証は、医薬品や医療機器が、常に一定の高い品質を保って製造されるように管理・保証する重要な仕事です。
品質管理は、製造された製品が規格通りであるかを、様々な試験や分析を通じて検証する役割を担います。
一方、品質保証は、製品の企画開発から製造、出荷、市販後に至るまで、品質を担保するための仕組み(システム)を構築し、適切に運用されているかを監督します。
化学や生物学の知識、分析技術が直接活かせる職種であり、患者さんの安全を守るという強い責任感が求められる仕事です。
製造技術・生産管理
製造技術・生産管理は、医薬品を安定的かつ効率的に製造するためのプロセスを担う仕事です。
製造技術は、研究所で開発された製造法を、実際の工場で大量生産できるスケールに落とし込み、製造プロセスの改善や効率化を図ります。
一方、生産管理は、需要予測に基づき、いつ、どの製品を、どれだけ製造するかという生産計画を立案し、原材料の調達から製品の出荷までを管理します。
化学工学や生物工学などの知識に加え、生産ライン全体を最適化するための管理能力や問題解決能力が求められる職種です。
金融・コンサル業界の研究職以外の仕事
金融・コンサル業界は、高い専門性と論理的思考力が求められるフィールドであり、理系出身者が持つ数理能力や分析能力を最大限に活かせる業界です。
目に見えるモノではなく、情報や知識、戦略といった無形の価値を提供し、企業や社会が抱える課題を解決に導きます。
ここでは、理系出身者が特に活躍している5つの専門的な職種について、その仕事内容と魅力を解説します。
アナリスト
アナリストは、企業や業界の財務状況、成長性などを分析・評価し、株式や債券などの金融商品の投資価値を判断する専門職です。
証券会社や資産運用会社に所属し、企業の財務諸表の分析、業界動向のリサーチ、経営者へのインタビューなどを通じて、詳細なレポートを作成します。
このレポートは、機関投資家や個人投資家の投資判断における重要な情報源となります。
膨大なデータを基に、客観的かつ論理的に結論を導き出す能力が不可欠であり、研究で培ったデータ分析力や仮説検証能力を直接的に活かすことができる仕事です。
アクチュアリー
アクチュアリーは、生命保険や損害保険、年金などの分野で、確率論や統計学といった数理的な手法を用いて、将来のリスクや不確実性を評価・分析する専門家です。
保険商品の設計に不可欠な保険料の算定や、将来の保険金支払いに備えるための準備金の計算などを行います。
高度な数学の知識が求められるため、数学科や物理学科出身者などが多く活躍しています。
資格試験の難易度が非常に高いことでも知られていますが、その分、高い専門性と社会貢献性を兼ね備えた、やりがいの大きな仕事と言えるでしょう。
投資銀行業務
投資銀行部門(IBD)では、企業の資金調達のサポート(株式や債券の発行)や、M&A(企業の合併・買収)のアドバイザリー業務などを行います。
企業の価値を正しく評価する企業価値評価(バリュエーション)においては、精緻な財務モデルを構築する必要があり、高い数理能力や分析力が求められます。
また、大型のM&A案件など、社会的にインパクトの大きなプロジェクトに若いうちから携われる機会も多く、知的好奇心や成長意欲の高い理系出身者にとって魅力的な環境です。
激務である一方、それに見合う高い専門性と報酬を得ることができます。
FA・FAS
FA(フィナンシャル・アドバイザー)やFAS(フィナンシャル・アドバイザリー・サービス)は、主にM&Aに関する専門的なアドバイスを提供する職種です。
コンサルティングファームや会計事務所系の専門会社に所属し、M&A戦略の立案から、買収対象企業の調査(デューデリジェンス)、企業価値評価、交渉のサポートまで、一連のプロセスを支援します。
複雑な利害関係を調整し、高度な財務・会計知識を駆使してクライアントの利益を最大化することがミッションです。
論理的思考力はもちろん、高いコミュニケーション能力も求められる、難易度の高い仕事です。
経営コンサルタント
経営コンサルタントは、企業が抱える様々な経営課題に対し、外部の専門家として客観的な分析を行い、戦略の立案から実行支援までを手がける仕事です。
クライアントは多様な業界にわたり、扱うテーマも事業戦略、組織改革、DX推進など多岐にわたります。
どのような課題に対しても、まずは現状を分析して本質的な課題を特定し、仮説を立てて検証し、具体的な解決策を導き出すというプロセスを辿ります。
この思考プロセスは、まさに理系の研究活動そのものであり、理系出身者が持つ課題解決能力や論理的思考力を存分に発揮できる職種と言えます。
メーカーの研究職以外の仕事
日本の基幹産業であるメーカー(製造業)は、理系人材の活躍の場として非常に大きなフィールドです。
最先端の技術を生み出す研究開発職が花形とされがちですが、その技術を製品として形にし、顧客の元へ届け、さらにはサポートするまでには、多様な職種の連携が不可欠です。
ここでは、メーカーにおいて研究職以外で理系の専門性を活かせる、4つの重要な仕事を紹介します。
技術営業・セールスエンジニア
技術営業(セールスエンジニア)は、自社製品に関する高度な技術的知識を活かして、顧客の課題解決をサポートする営業職です。
一般的な営業担当者と同行し、技術的な側面から製品の優位性を説明したり、顧客の専門的な質問に答えたり、ニーズに合わせた技術的な提案を行ったりします。
顧客と開発部門の橋渡し役を担うことも多く、市場のニーズを開発現場にフィードバックするという重要な役割も持ちます。
専門知識とコミュニケーション能力の両方が求められるため、人と関わることが好きで、かつ自身の専門性を活かしたい理系出身者に最適な職種です。
フィールドエンジニア・サービスエンジニア
フィールドエンジニアやサービスエンジニアは、自社製品を導入した顧客先へ出向き、設置、保守、点検、修理などを行う技術者です。
製品が常に最適な状態で稼働するようサポートし、トラブル発生時には迅速に原因を特定し、復旧作業にあたります。
顧客と直接対話し、感謝の言葉をかけてもらえる機会も多く、やりがいを感じやすい仕事です。
製品に関する深い知識はもちろん、現場での臨機応変な対応力や、顧客との信頼関係を築くコミュニケーション能力が求められます。
機械、電気電子、情報系など、幅広い分野の理系出身者が活躍しています。
知的財産・特許技術者
知的財産(知財)部門は、企業が創出した発明や技術、デザイン、ブランドなどを、特許権や商標権といった知的財産権として保護し、活用する役割を担います。
特許技術者は、研究開発部門が生み出した発明の内容を理解し、特許として権利化するための書類(明細書)を作成したり、特許庁への出願手続きを行ったりします。
他社の特許を調査し、自社製品が権利を侵害していないかを確認することも重要な業務です。
自身の専門知識を活かして、企業の競争力の源泉である技術を守る、非常に専門性の高い仕事です。
生産技術・品質保証
生産技術は、研究開発部門が設計した製品を、工場で効率的かつ安定的に、そして高品質に量産するための生産体制を構築する仕事です。
最適な生産ラインの設計、製造設備の選定・導入、製造工程の改善など、その業務は多岐にわたります。
一方、品質保証は、製品が設計通りの品質基準を満たしているかを保証するための仕組みを作り、管理する役割です。
原材料の受け入れから製品の出荷まで、すべての工程で品質が保たれるよう監視します。
どちらも、ものづくりの根幹を支える重要な職種であり、機械、化学、材料系などの理系知識が不可欠です。
研究職以外で成功する就活戦略
理系学生が研究職以外のキャリアを目指す場合、文系の学生とは異なる視点での就職活動戦略が求められます。
自身の研究活動で培った強みを、ビジネスの世界でどのように活かせるのかを明確に言語化し、効果的にアピールすることが成功の鍵となります。
ここでは、自己分析から面接対策まで、研究職以外の就職活動を成功に導くための具体的な戦略を4つのステップで解説します。
自己分析で見つける強み
まずは自己分析を徹底的に行い、自身の強みを明確にしましょう。
理系学生の場合、研究活動の経験を深掘りすることが有効です。
例えば、「〇〇という課題に対し、△△という仮説を立て、□□という手法で粘り強く検証し続けた結果、◇◇という成果を得た」というように、研究のプロセスを具体的に振り返ります。
この経験から、課題解決能力、論理的思考力、粘り強さ、情報収集能力といった、ビジネスシーンでも通用するポータブルスキルを抽出することができます。
専門知識だけでなく、これらの汎用的な強みを自覚し、言葉で説明できるように準備しておくことが重要です。
企業研究の進め方
研究職以外の職種を目指す場合、企業研究はより丁寧に行う必要があります。
まずは、少しでも興味を持った業界について幅広く調べ、どのようなビジネスモデルで成り立っているのか、どのような職種があるのかを理解しましょう。
その上で、個別の企業について深掘りしていきます。
企業のウェブサイトや採用ページだけでなく、有価証券報告書で事業内容や財務状況を確認したり、OB・OG訪問で現場の社員から具体的な仕事内容や働きがいを聞いたりすることも有効です。
なぜその業界なのか、そしてなぜその企業なのかを、自身の強みやキャリアプランと結びつけて語れるようにすることがゴールです。
履歴書・ESの書き方
履歴書やエントリーシート(ES)では、なぜ研究職ではなく、その企業・職種を志望するのかを明確に、そして説得力を持って伝える必要があります。
単に「人と関わる仕事がしたいから」といった抽象的な理由ではなく、自己分析で見つけた自身の強みと、企業研究で理解した事業内容や仕事内容を結びつけて記述しましょう。
例えば、「研究で培った粘り強い課題解決能力を活かし、貴社の技術営業として、お客様が抱える複雑な課題に真摯に向き合い、最適なソリューションを提案したい」といったように、具体的に記述することで、志望度の高さと入社後の活躍イメージを伝えることができます。
面接でのアピール方法
面接では、ESの内容をさらに深掘りされます。
特に、「なぜ研究職ではないのか」という質問は頻出するため、準備が不可欠です。
ネガティブな理由(研究が嫌になったから等)を述べるのではなく、ポジティブな理由に転換して話すことが重要です。
例えば、「研究を通じて培った専門知識や論理的思考力を、より社会に近い場所で、スピード感を持って活かしたいと考えたため」といったように、将来のキャリアを見据えた前向きな動機として説明しましょう。
また、自身の研究内容を、専門知識のない面接官にも分かりやすく、簡潔に説明する練習もしておきましょう。
論理的な説明能力を示す絶好の機会となります。
なぜ研究職以外なのかと聞かれたときの対処法
理系学生が研究職以外の職種を志望する際、面接でほぼ確実に問われるのが「なぜ研究職ではないのですか」という質問です。
この質問に対し、いかに説得力のある回答ができるかが、選考を突破する上で非常に重要なポイントとなります。
単に研究が合わなかったというようなネガティブな伝え方ではなく、自身のキャリアプランに基づいた、前向きで論理的な回答を準備しておく必要があります。
理由を将来のキャリアプランと結びつける
この質問に答える最も効果的な方法は、自身の将来のキャリアプランと結びつけて説明することです。
例えば、「将来的には、技術的な知見と経営的な視点の両方を兼ね備えた人材になりたいと考えています。
その第一歩として、まずは〇〇職でお客様のニーズを直接理解し、ビジネスの最前線を経験することが不可欠だと考えました」といったように、研究職以外の職種を選ぶことが、自身のキャリア目標達成のための戦略的な選択であることを示します。
これにより、単なる消極的な理由ではなく、明確な目的意識を持った主体的なキャリア選択であることをアピールできます。
専門性を活かしながら社会に貢献したい
自身の専門知識を活かしつつ、研究とは異なる形で社会に貢献したいという意欲を示すことも有効な回答です。
例えば、「大学院で学んだ〇〇の知識は、貴社の△△という製品開発において、品質保証の観点から貢献できると考えています。
研究という形で新たな知を創出するだけでなく、既存の技術を応用して製品の安全性を高めることで、より直接的に社会に貢献したいです」のように、具体的な貢献イメージを伝えることが重要です。
研究で培った専門性を捨てるのではなく、それを別のフィールドで活かしたいという前向きな姿勢は、面接官に好印象を与えるでしょう。
研究とは異なる〇〇を身に着けたい
研究活動では得られにくい特定のスキルや経験を積みたい、という意欲を伝えるのも一つの方法です。
例えば、「研究活動を通じて、論理的思考力や課題解決能力は身につきました。
今後は、これに加えて、多様な立場の人と協働し、プロジェクトを推進していくマネジメント能力を身につけたいと考えています。
貴社の〇〇職は、若手のうちからチームを率いる機会が多いと伺っており、自身の成長にとって最適な環境だと感じました」といったように、具体的なスキル名を挙げ、それがなぜその企業・職種で得られると考えるのかを論理的に説明します。
成長意欲の高さを示すとともに、企業理解の深さもアピールできます。
まとめ
理系学生のキャリアパスは、研究職という一つの道だけではありません。
大学で培った論理的思考力、課題解決能力、そして専門知識は、IT、医療、金融、メーカーなど、あらゆる業界で価値を発揮するポテンシャルを秘めています。
研究職以外の道を選ぶことは、決して逃げではなく、自身の可能性を広げるための前向きな挑戦です。
大切なのは、なぜその道を選ぶのかを深く考え、自身の強みや将来のキャリアプランと結びつけて、説得力のある言葉で語ることです。
本記事で紹介した情報を参考に、自己分析と企業研究を丁寧に進め、あなたに最適なキャリアを見つけ出してください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

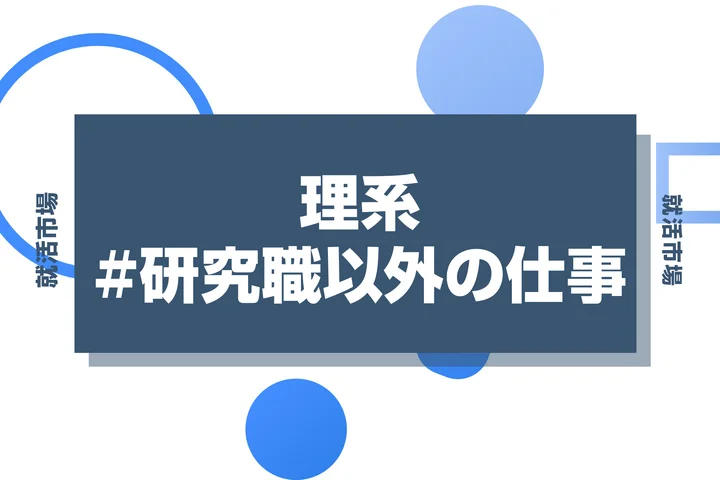








_720x550.webp)