本記事では、5月までにまだ内定がないのは手遅れなのか、まだ何もしてない状態でも巻き返せるのか、という点について解説していきます。
目次[目次を全て表示する]
【5月に内定なし】5月に内定がないのは手遅れ?今から巻き返せる?
多くの就活生は、大学3年生のうちに就活を始め、大学4年生に入る時点では順調に就活を進めているかと思います。しかし、部活動やサークル、ゼミ、アルバイトなどに専念していた学生など、5月時点でまだ内定がなくて焦っている方もいらっしゃるでしょう。
結論、5月にまだ何もしていなくても大丈夫です。ただし、危機感を持って始めなければ、手遅れになってしまう可能性があります。
まずは自分が27卒の中でどんな位置にいるのかを理解した上で、いまやるべき行動や内定が取りやすい業界、今すぐ内定を取るための行動を頭に入れて動いていきましょう。
【5月に内定なし】先輩(26卒)の5月の内定率(2025年5月時点)

就職みらい研究所(リクルート)が2025年5月14日に発表した「就職プロセス調査(2026年卒)」によると、2026年卒業予定の大学生(大学院生除く)の5月1日時点での就職内定率(※1)は75.8%でした 。
この数値は、4月1日時点の61.6%から14.2ポイントも増加しており、多くの就活生が選考を経て内定を得ていることがわかります 。また地域別に見ると、特に「関東」で78.9%、「近畿」では80.0%と、内定率が約8割に達しています 。
「75.8%が内定を持っているということは、自分は少数派なの…?」と不安に思った方もいるかもしれません。しかし、注目していただきたいデータは、就職活動実施率です。
5月1日時点で、就職活動を続けている就活生は全体で51.9% 。つまり、半数以上の学生さんが、まだ就職活動を積極的に行っているということがわかります。
また、進路が確定した就活生の割合を示す「進路確定率」は55.1%で、こちらも前月の39.9%から15.2ポイント増加しています 。これは、多くの就活生が進路を決定し就活を終わってきている証拠ですが、裏を返せばまだ活動中の就活生も多いということです。
25卒はどうだった?4年5月時点の内定率

リクルートが運営する就職みらい研究所の調査「就職プロセス調査(2025卒)」によると、去年の4年5月時点での内定獲得率は72.4%で、4月と比べる約15%伸びる形となっていました。
| 時期 | 25卒 内定獲得率 | 26卒 内定獲得率 |
|---|---|---|
| 4月1日時点 | 58.1% | 61.6% |
| 5月1日時点 | 72.4% | 75.8% |
| 6月1日時点 | 82.4% | - |
| 7月1日時点 | 88.0% | - |
| 8月1日時点 | 91.2% | - |
| 9月1日時点 | 94.2% | - |
| 10月1日時点 | 95.9% | - |
| 12月1日時点 | 96.6% | - |
比べると、昨年よりも約3%ずつ多いものの就活の早期化と同じほど就活の終了が早期化しているわけではない、ということがわかります。
4年の3月までに内定が取れれば大丈夫!焦る必要はない
就活のゴールは「早く内定を取ること」ではなく、「納得できる企業から内定を取ること」です。
もちろん5月時点で内定が出ていないと不安になるのは当然ですが、実際にはこれからが本番という学生も少なくありません。
企業によっては、春採用後に再募集を行ったり、5月以降に本格的な採用活動をスタートしたりするケースもあります。
さらに、大学4年の夏~秋にかけて内定を獲得する学生も一定数いるため、「5月時点で内定がない=手遅れ」というわけではないのです。
ただし、これ以上の遅れを取らないためにも、5月からは戦略的に行動することが重要になります。
ここからは、5月時点で内定がない就活生がやるべき具体的な対策を詳しく解説していくので、焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
【5月に内定なし】まずは内定がない原因を把握しよう
5月時点で内定がないと、自分だけ出遅れているのでは…と不安になる方も多いかもしれません。
しかし、まず大切なのは、その焦りの原因となっているなぜ内定が取れていないのかを正しく理解することです。
- 就活の軸が決まっていない
- エントリー数が少ない
- 選考対策が不十分
- 企業の難易度が高すぎる
- ひとりで就活を進めている
就活は、ただ数をこなせば良いというわけではなく、自分自身の状況や課題に合った対策が必要になります。
内定が出ない理由は人それぞれですが、いくつかの共通した傾向があります。
たとえば、就活の軸がまだ定まっていないエントリー数が少なく、選考対策が十分ではない企業選びの基準が偏っているなどです。
これらは、どれか一つが原因であるというよりも、複数が重なって内定につながっていないケースが多く見られます。
だからこそ、自分自身の就活を一度振り返り、立ち止まって整理することが、今後の巻き返しの第一歩になるのです。
それでは、ここからは内定が出にくくなる主な要因を一つひとつ解説していきます。
就活の軸が決まっていないと、内定獲得は難しい
就活の軸とは、企業選びや自己PRをする際の基準となる、自分なりの価値観や目指す方向性のことです。
この軸が曖昧なまま就職活動を進めてしまうと、企業選びに一貫性がなくなり、志望動機や自己アピールが浅くなってしまう恐れがあります。
その結果、企業から、なんとなく受けていると見られてしまい、内定に結びつきにくくなってしまうのです。
5月時点で内定が出ていない方の中には、自分が本当に何をしたいのかがまだ分からないと感じている方も多いかもしれません。
しかし、これはあなただけではありません。
実際、多くの学生が就活を進めるなかで迷いを感じながら、自分なりの軸を見つけていきます。
大切なのは、今からでも遅くないということ。
自己分析を通じて自分の価値観や興味を整理し、少しずつ軸を固めていけば、志望企業へのアピールも明確になり、選考通過率がぐんと上がります。
これからの行動が、未来を変える第一歩になりますので、焦らず着実に進んでいきましょう。
企業とのミスマッチが起こる可能性が高い
就活の軸が定まっていないと、自分にとって何を大切にしたいかが明確でないまま企業選びをしてしまい、結果として企業とのミスマッチが生じやすくなります。
たとえば、大手だから安心、有名企業だから将来も安泰といった漠然とした理由でエントリーしても、実際に選考を進める中で仕事内容や職場の雰囲気が自分の価値観と合わないと感じ、違和感を覚えることがあります。
また、面接で志望動機を問われた際にも、軸が定まっていないと説得力のある答えができず、うちの会社でなければならない理由が伝わってこないと評価されてしまうこともあります。
企業側にとっても、ミスマッチによって早期離職されるリスクが高まるため、選考通過はより厳しくなってしまうのです。
だからこそ、自分にとって、どんな働き方が理想なのか、仕事を通じて何を実現したいのかといった視点を持ち、自分の中での優先順位を整理しておくことが重要です。
軸が明確になれば、自ずと志望する企業も絞られていき、より納得感のある就活につながっていきます。
正確な業界・企業研究ができない
就活の軸が曖昧な状態では、業界や企業を調べる際にも目的意識が持ちづらく、表面的な情報収集にとどまりがちです。
たとえば、なんとなく安定していそうだから金融業界、華やかなイメージがあるから広告業界といった感覚的な理由だけで情報を集めても、その企業の本質的な魅力や自分との相性を見極めるのは難しいでしょう。
業界・企業研究は、自分が何を重視して働きたいのかを明確にしたうえで進めることで、はじめて意味を持ちます。
たとえば、人の役に立てる仕事がしたいという軸を持っているなら、医療・福祉業界やBtoCのサービス業に関心が向きやすくなり、調査の視点も、どのように顧客と関わるかといった具体的な点に絞られていきます。
逆に軸が決まっていないまま調べても、すべての企業が似たように見えてしまい、比較することも難しくなります。
今からでも、自分の価値観や興味を整理して、軸に沿った情報収集を行えば、志望度の高い企業をより深く理解することができ、説得力のある志望動機にもつながります。
エントリー数が少ない
選考に進むチャンスそのものが少なければ、当然内定を得る確率も下がってしまいます。
これはエントリー数が少ないというシンプルな理由で、案外見落としがちなポイントでもあります。
就活はある意味確率のゲームとも言えます。
一社一社にかける時間や労力も大切ですが、母数が少ないと、たとえ良い準備ができていても、結果につながりにくくなってしまうのです。
特に、最初のうちは選考慣れもしていないため、最初から数社に絞ってしまうのはリスクが高いといえるでしょう。
目安としては、5月時点で20社以上にエントリーしておくと、選考の幅が広がります。
もちろん、自分に合った企業を見つける努力も必要ですが、まずは視野を広く持ち、複数の企業にアプローチすることで、自信をつけていくことも可能になります。
選考対策が不十分
自己PRや志望動機を書いているのに通らない面接でうまく話せないと感じている場合、それは選考対策が不十分であることが原因かもしれません。
就活は、試験のように準備すればするほど成果が出やすい活動です。
書類選考では、伝えたい内容が明確で、かつ企業ごとの特徴を押さえた文章が求められます。
面接では、自分の経験を整理して伝える力や、相手の質問意図をくみ取る力が問われます。

これらのスキルは一朝一夕で身につくものではありませんが、練習やフィードバックを重ねることで、確実に上達していきます。キャリアセンターの模擬面接や、就活エージェントのサポート、友人同士の面接練習など、使えるリソースは積極的に活用していきましょう。自分ではできているつもりだったという思い込みに気づくことが、対策の第一歩になります。
企業の難易度が高すぎる
受験と同じように、企業にも難易度のようなものがあります。
人気企業や大手企業、有名ブランド企業は倍率が非常に高く、どんなに準備をしても簡単に内定をもらえるわけではありません。
こうした企業ばかりにエントリーしていると、なかなか選考が通らず、モチベーションも下がってしまいます。
大切なのは、自分の志向やスキルに合った企業を見極めること、そして難易度のバランスを考えながら選考に臨むことです。
受かりやすい企業=ブラック企業と考える方もいますが、決してそうではありません。
中堅企業や地方企業、成長中のベンチャー企業などは、教育体制や働きやすさが整っているところも多く、自分に合った働き方を実現できる可能性があります。
企業選びの幅を持たせることで、視野が広がり、自分にとって本当に合った企業と出会えるチャンスも増えていきます。
漠然と大手を志望するのはやめましょう
就職活動では、とりあえず大手を受けておけば安心と考える方も多いかもしれません。
確かに大手企業は、知名度があり、給与や福利厚生も充実している場合が多いため、魅力を感じるのも自然なことです。
しかし、なんとなく大手だからという理由だけで志望するのは、実は危険な選択にもなり得ます。
というのも、大手企業には全国から多くの就活生が応募しており、競争率は非常に高い傾向があります。
そのため、どんなに熱意があっても、なぜこの企業なのか、自分がどう貢献できるのかが明確でないと、選考を突破するのは簡単ではありません。
さらに、実際に大手企業に内定を得た学生の中には、選考過程で中小企業やベンチャー企業も数多く見てきたという方が多くいます。
そうした企業を見ることで、自分にとっての、働きやすさや、やりがいとは何かを考えるきっかけとなり、結果的に納得のいく就職先を選べているのです。
大手企業が絶対に悪いわけではありませんが、選択肢をそこに限定してしまうことで、視野が狭まり、自分に合った企業を見逃してしまうリスクもあります。
たとえば、ベンチャー企業や中堅企業の中には、若手にも多くの裁量が与えられ、スピーディに成長できる環境が整っている企業もあります。
就活は、自分の人生における、働く第一歩を決める大切な機会です。
企業のブランド力や条件面だけで判断するのではなく、自分の価値観や将来像に照らし合わせて、本当に納得できる企業を見極めることが大切です。
そのためにも、大手企業だけにこだわらず、幅広い選択肢を持ちながら就活を進めていきましょう。
就職偏差値について簡単に図表でまとめたのでぜひ参考にしてみてください。

下の記事では文理別・大学別で就職偏差値を解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
ひとりで就活を進めている
就活をひとりで黙々と進めていると、このやり方で合っているのかな、他の人はどれくらい進んでいるのだろうといった不安に苛まれることがあります。
周囲と比較しづらいため、自分の課題や改善点にも気づきにくく、結果として効率の悪い就活になってしまう恐れもあるのです。
とくに、選考で不合格が続くと、その理由がわからず自己分析や志望動機の書き方が曖昧なままになってしまい、同じ失敗を繰り返してしまうこともあります。
こうした状況はモチベーションの低下にもつながり、さらに就活に対する不安感が大きくなってしまいがちです。
そのため、就活はできるだけ、誰かと一緒に進めることが重要です。
たとえば、大学のキャリアセンターを活用したり、友人同士で模擬面接をしたり、就活支援サービスを利用したりと、頼れる存在を見つけることで、自分では気づかなかった課題や改善点に出会うことができます。
また、他の人の進め方を知ることで、効率的な就活スケジュールや選考対策のヒントも得られます。
自分だけ取り残されているかも…という孤独感を軽減し、前向きに取り組めるようになるという意味でも、大きな助けになるでしょう。
就活は確かに個人戦の側面もありますが、同時に情報戦でもあります。
自分ひとりで抱え込むのではなく、信頼できる人とつながりながら進めていくことで、より確実に、そして納得のいく就活ができるようになります。
今からでも遅くありませんので、まずはひとつ、誰かに相談してみることから始めてみてください。
【5月に内定なし】5月に内定なしの就活生が実践すべき対処法8選
5月の時点で内定なしの人は、現状を理解したうえで何らかの対策をとる必要があります。
これまで就活を行ってきたにもかかわらず内定が出ないということは、就活のやり方・選考対策の方法などを、積極的に見直したほうが良いといえます。
5月に内定ゼロの人がやるべき就活は、以下のとおりです。
- 現状把握と今後のスケジュール整理
- 就活の軸を見つめなおす
- 業界を絞ってエントリー数を増やす
- エントリーする企業の条件を緩めてみる
- 落ちた要因を分析して選考対策をする
- 就活サイトや逆求人サイトに積極的に登録してみる
- 就活イベントに参加する
- 就活のプロに頼る
このようにスケジュールを整理したり積極的にエントリーしたりしながら、就活の進め方を見直していきましょう。
必要に応じて就活のプロに相談することも重要です。
では、それぞれの詳細をチェックしていきましょう。
現状把握と今後のスケジュール整理
4年生の5月を迎えたにもかかわらず、内定なしの人は、まず現状把握が必要です。
就活のやり方を見直すためにも、はじめに、どの企業にエントリーしているのか・次回の選考の予定は何かなどをしっかり把握しましょう。
現状を把握すれば、その予定に応じてやるべきことや必要な対策が見えてきます。
そのうえで、スケジュールの整理が必要です。
例えば面接などの選考の予定が近日中にある場合は、内定につなげられるように、面接対策を改めて見直すと良いでしょう。
これまで内定が出なかった原因は何かを考えたうえで、足りていなかった面接対策をこのタイミングで実践してみましょう。
現状を把握したうえで、ほとんど就活の予定が入っていない場合は、エントリーを増やすなどの行動が必要です。
就活の軸を見つめなおす
5月のこの時期だからこそ、改めて自分はなぜこの企業を志望しているのか将来、どんな働き方をしたいのかといった就活の軸を見直すことが大切です。
就活を始めた当初に決めた軸が、経験や情報収集を重ねるなかで無意識のうちにズレてきていることは少なくありません。
たとえば、最初は安定性を重視していたはずが、説明会や面接を通してやりがいや成長環境のほうに関心が移っているかもしれません。
こうした価値観の変化を放置してしまうと、志望動機に一貫性がなくなり、企業にも熱意が伝わりづらくなってしまいます。

まずは、紙に書き出すなどして、自分が大切にしている仕事観・人生観を整理してみましょう。そして、なぜそれが自分にとって重要なのかそれを満たす環境とはどういう企業なのかを考えることで、自分の軸がより明確になっていきます。軸が定まると、企業選びやエントリーの方向性もブレなくなり、選考の準備も格段に進めやすくなります。また、面接でもなぜこの企業なのかという問いに対して、自分の言葉でしっかり答えられるようになります。今後の選考突破のカギは、実はこの軸の再確認にあるかもしれません。
業界を絞ってエントリー数を増やす
5月に内定なしの人が内定獲得を目指すなら、業界を絞ってエントリー数を増やしましょう。
エントリーした企業がなくなることが最も怖いため、興味のある業界に絞り、積極的にエントリーすると良いでしょう。
ただし、春採用のエントリー締め切りは3月~4月がピークであるため、5月はすでに締め切り後であるケースも多いです。
そのため、実際のところ、5月から新たに春採用にエントリーできる企業はあまり多くありません。
もちろんゼロではありませんが、3月の情報解禁時と比べて採用活動を終えている企業も増えているため、注意が必要であることは理解しておきましょう。
なお、その際はエントリーできる企業を無作為に増やし過ぎないことも大切です。
確かに積極的にエントリーすることは必要ですが、むやみやたらにエントリーしても、1社ごとの対策の質は落ちるだけです。
ミスマッチが起こる可能性も否定できないでしょう。
あくまで管理できる範囲からは出ないように注意しながら、エントリー数を増やしていきましょう。
業界を1つに絞るメリット
業界を1つに絞る最大のメリットは、就活全体に一貫性と深みが出ることです。
企業研究や業界研究に時間を集中できるため、志望動機や自己PRの説得力が増し、「この業界に本気で入りたい」という思いが企業側にも伝わりやすくなります。
また、同じ業界の企業では選考の傾向や求める人物像に共通点があるため、効率的な対策が可能になります。
さらに、自分の強みや価値観と業界との相性を整理しやすくなり、面接でも納得感のある受け答えができるようになります。
迷いが減ることで、自信を持って就活に臨めるのも大きな利点です。

エントリーする企業数の目安としては10社前後がよいでしょう。 まずは、志望する業界を一つに絞りましょう。 その次に選んだ業界の企業説明会に15社程度参加して、最後にその中の10社前後にエントリーをすることをおすすめします。 このようなステップを踏むことで、業界に対する理解を深めながら、自身とマッチする企業を見つけることができます。 また、エントリーをする際には、企業のなかで順位付けをしておきましょう。 優先順位を明確にすることで、志望度の低い企業を練習として使うことができ、第一志望までに十分な選考経験を重ねることができます。
就活のプロに頼る
5月の時点で内定なしの人が行うべき就活は、積極的に就活のプロに頼ることです。
大学のキャリアセンターや就活エージェントなどに相談すれば、現状の問題点を確認できたり、より実践的な模擬面接をしてもらえたりします。
大学のキャリアセンターは、学内にあるからこそ気軽に利用できるうえに、同級生の就活がどのような状況なのか把握するうえで役立ちます。
大学を卒業した先輩とのつながりで、OBOG訪問のアポが取りやすくなる場合もあります。
就活エージェントは、自己分析や企業・業界研究、求人紹介、選考対策などさまざまな面で就活のサポートをしてもらえる点が強みです。
自分に担当者が付く形で手厚く支援してもらえるため、不安なことやわからないことは、担当者に気軽に相談できます。
就活がうまくいかないときは客観的な視点からのアドバイスが重要になるため、就活のプロを積極的に頼りましょう。
エントリーする企業の条件を緩めてみる
5月時点で内定がない場合、これまでの企業選びの条件を見直してみることも大切です。
たとえば、「大手企業にこだわりたい」「福利厚生が充実していないとイヤ」など、条件が厳しすぎると、選択肢が大きく制限されてしまい、結果としてエントリーできる企業が少なくなってしまいます。
業界を絞ることで対策しやすくなりますが、企業の規模や知名度、勤務地、福利厚生などの条件面については少し柔軟に考えてみるのも一つの手です。
中小企業やベンチャー企業の中にも、働きやすい環境が整っていたり、成長できるフィールドがあったりする企業はたくさんあります。
「絶対に譲れない条件」と「実は妥協できる条件」を整理することで、内定獲得のチャンスはぐっと広がります。
落ちた要因を分析して選考対策をする
ここまでいくつか選考を受けてきたにもかかわらず内定が出ていない場合は、過去の選考を振り返って、なぜ落ちたのかを客観的に分析することが非常に重要です。
- 面接でうまく話せなかった
- 志望動機があいまいだった
- ガクチカに具体性がなかった
このように、自分のどこに改善点があるのかを把握できれば、次の選考で同じミスを繰り返さずに済みます。
面接練習は一人でやるよりも、キャリアセンターや就活エージェント、信頼できる友人に協力してもらうことがおすすめです。
自分では気づけなかった改善点が見えてくることも多いため、積極的に第三者からのフィードバックを活用していきましょう。
「なんとなく」で受け続けるのではなく、毎回の選考を経験値として積み重ねていく意識が、内定獲得への近道です。
就活サイトや逆求人サイトに積極的に登録してみる
就活を効率よく進めるためには、就活サイトや逆求人サイトを活用するのが効果的です。
特に5月以降は、「エントリーを受け付けている企業を探すのが大変」という声も増えてきます。
そのようなときに頼りになるのが、企業情報の更新やメール通知機能がある就活サイトです。
また、逆求人サイトでは、企業側から学生にオファーが届くため、自分では思いつかなかった業界や企業と出会える可能性もあります。
複数のサイトに登録しておくことで、視野が広がり、より多くのチャンスを掴むことができるでしょう。
時間がない中でも、プロフィール登録を済ませておくだけでスカウトが届くようになるため、今のうちに積極的に活用してみてください。
就活イベントに参加する
5月は、春採用の選考が一段落し、採用枠を再調整する企業が動き出す時期でもあります。
このタイミングで行われる就活イベントには、27卒向けの合同説明会や選考直結型イベント、インターンマッチングイベントなど、さまざまな形式のものがあります。
オンラインで参加できるイベントも多いため、気軽に情報収集ができるのも嬉しいポイントです。
また、1日で複数の企業と出会えることは、就活後半戦では非常に貴重な機会です。
これまで知らなかった企業や業界の魅力に気づけることもあるでしょう。
イベントを通じて人事担当者と直接会話できる機会も多いため、印象を残せれば選考に進む確率も高まります。
「まだ動けていない」「どこを受けるべきか分からない」と悩んでいる方こそ、まずはイベントに参加することから始めてみてください。
【5月に内定なし】5月に内定なしの就活生がすべき対策を選考フロー別に解説
5月の時点で内定なしの人は、内定獲得のためにさまざまな対策を実践する必要があります。
しかし人によっては、どのような対策が自分にとって良いのかわからないことも少なくありません。
そのためここからは、以下の選考フロー別に、内定獲得のためにすべきこと・落ちないための対策をまとめていきます。
- ES・履歴書
- Webテスト
- グループディスカッション
- 面接
例えば「いつも面接で落ちてしまう」と悩んでいる場合は、面接の項目からチェックしておくと良いでしょう。
まだ就活を始めておらず何もしていない学生は、5月からの就活の始め方についてこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ES・履歴書で落ちてしまう場合
選考対策を十分に行ったうえでエントリーしても、ESや履歴書で落ちてしまう人は、志望動機・ガクチカ・自己PR(強み)のいずれかに問題があると考えられます。
そのため、ES・履歴書で落ちてしまう人は、以下の対策を徹底しましょう。
- ES・履歴書で落ちてしまう人がすべき対策
- 自己分析をする
- 業界・企業分析をする
- PREP法を使う
- 誤字脱字チェックをする
- 人に読んでもらう
魅力的なアピール文章を書くうえで、特に自己分析や業界・企業研究は重要な工程になります。
もしくは、意外と単純なミスが影響しており、誤字脱字が多いことなどが原因なのかもしれません。
そのため、ES・履歴書などの提出書類は、徹底的に見直したうえで提出することが必要です。
特に焦っている中で選考対策を行うと、見直しや添削を省いてしまうことがあるため注意しましょう。
以下からは上記の対策について詳しく解説するため、ESの通過率を高めたいときは参考にしてみてください。
また、ESの具体的な書き方については、こちらの記事も積極的にチェックしておきましょう。
自己分析をする
企業から高い評価を受けるESを作成するには、前もって自己分析をしっかり行っておく必要があります。
自己分析とは、自己理解を深めるための重要なプロセスであり、就活を始めるうえでは必ず行うべきことといえます。
自分とは何が得意な人で、何に興味があるのか、どのような場面で活躍できる人材なのかを客観的に理解していなければ、説得力のあるアピールはできないからです。
裏を返せば、魅力的なESが書ける人は、事前に自己分析を徹底しています。
そのため、ESで書くことがない・良いアピールができない…と悩んでいる人は、そもそも自己分析が足りていない可能性があります。
自分の性格や価値観をよく考えたうえでこれまでの経験を振り返り、強みや弱み、目指すべき方向性を見極めたうえで、自分のアピールポイントを把握しましょう。
うまく自己分析が進まないときは、必要に応じて自己分析のサポートツールや性格診断などを活用することもおすすめです。
業界・企業分析をする
魅力のあるES・履歴書を作成するには、業界・企業分析をしっかりと行うことも重要です。
前もって業界・企業分析を行えば、その業界・企業の特徴や求められるスキル、キャリアビジョンなどが見えてくるため、自分がそこでどう活躍できるのか見極めやすくなります。
結果として、説得力のあるアピールをするうえで、業界・企業分析は大きく役立つでしょう。
企業分析では、特に競合他社との違いを理解し、その企業ならではの特徴や価値観を理解することが大切です。
ほかの企業には見られない独自性を把握していなければ、具体的な志望動機も書けないでしょう。
そのうえで志望企業ではどのような人物が求められるのかを整理し、具体的な内容を志望動機や自己PR、ガクチカに反映させることが重要です。
PREP法を使う
ESを書くときにはPREP法を使って書くことをおすすめします。
PREP法とはPoint→Reason→Example→Pointの順番で文章を構成する方法で、論理的かつ端的に文章を作成することができます。
まず「結論(Point)」を最初に述べることで、読み手は話の要点をすぐに理解できます。
次に「理由(Reason)」を示し、「具体例(Example)」で裏付けることで説得力が生まれます。
最後に再度「結論(Point)」で締めることで、文章にまとまりが出て印象が強まります。
この構成を使うことで、「何が言いたいのか分からない」といった評価を避けることができ、人事の記憶に残る自己PRやガクチカを作成できます。
誤字脱字チェックをする
魅力的なESで選考を通過するには、誤字脱字をチェックすることも忘れないでください。
誤字脱字の見られるES・履歴書は、どれだけ魅力的なアピール文章を書いても、「真摯にアピールしている姿勢」が見られなくなります。
あわてて仕上げた印象、雑に書いた印象がぬぐえないため、不真面目・不誠実なイメージにつながる可能性があります。
ほかには注意力が足りない印象もあるため、例えば集中力や正確な作業を求められる仕事などでは、マイナスな評価につながる可能性が高いです。
誤字脱字チェックは、自分で音読して見直すことがおすすめです。
黙読でもチェックはできますが、音読のほうがより「読むこと」に集中するため、誤字脱字を発見しやすくなります。
また、Web上には誤字脱字チェッカーもたくさんあるため、簡単なチェックとしてツールを活用することもおすすめです。
人に読んでもらう
ES・履歴書で落ちてしまう人は、周りの人に作成した書類を読んでもらい、感想やフィードバックをもらうことがおすすめです。
実際に人に読んでもらえば、人の胸を打つ文章であるかがわかるからです。
自分ではよくわかる部分も、表現がわかりにくくなかなかニュアンスが伝わらない場合があります。
そのような細かい部分は、人に読んでもらいながら直していくと良いでしょう。
読んでもらう人は、周りの友達や家族、先輩など、忌憚ない意見をくれる相手であれば誰でも問題ありません。
周りの人に読んでもらうことが難しい場合は、就活エージェントなどのサポートサービスを積極的に活用することも考えましょう。
就活エージェントでES・履歴書をチェックしてくれるのは就活のプロであるため、よりわかりやすいアドバイスがもらえます。
Webテストで落ちてしまう場合
選考を受ける中で、Webテストで落ちてしまう場合は、やはりWebテスト対策が足りていない可能性が高いです。
就活の選考対策といえば、ESや面接に重きを置きがちであるため、Webテスト対策をおろそかにしてしまう人は意外と少なくありません。
確かにWebテストは、資格試験などのように専門的な勉強が必要というわけではないため、難易度自体は高くありません。
とはいえ、対策が不十分だと受からない可能性が出てくるため、選考対策を進める際は注意が必要です。
そのためここからは、Webテスト対策として、以下の点を解説していきます。
- 事前にテストの種類を調べる
- 何度も繰り返し解く
- 時間をはかって解く
- 苦手な分野から潰していく
いつもWebテストでふるいにかけられてしまい、なかなか選考に通らない人は、上記の点を押さえて対策を強化しましょう。
では、それぞれのポイントの重要な点をまとめていきます。
事前にテストの種類を調べる
Webテストで落ちてしまう人は、具体的な対策を行うためにも、事前にテストの種類を調べる必要があります。
企業が新卒採用の際に取り入れる適性試験は、企業によって異なるからです。
テストの種類によって対策すべきことやテストの性質は違うため、そのテストに合った対策を徹底する必要があります。
前もって出題される形式を把握しておけば、その形式に慣れることができるため、よりスムーズに解答できるようになります。
例えば、Webテストとして代表的な種類である「SPI」は、問題数が多いため時間配分に注意して解答していくことが必要です。
なお、Webテストの種類は、受験の案内リンクのURLをチェックすることで、事前に見分けられます。
代表的なWebテストの見分け方は以下のとおりです。
- 代表的なWebテストの見分け方
- URL内に「arorua」がある:SPI
- URL内に「e-exam」・「nsvs」・「tsvs」がある:玉手箱、WebGAB、C-GAB、TG-WEB、CAB
- URL内に「c-personal」・「e-gitest」がある:TG-WEB
このように事前にリンクからWebテストの種類を把握し、徹底的に対策しましょう。
何度も繰り返し解く
Webテストは「慣れ」がスコアに直結します。
新しい問題集を次々に解くよりも、同じ問題を何度も繰り返し解くことで出題形式に自然と適応できるようになります。
最初はミスが多くても、解き直しを通じて理解が深まり、問題のパターンが読めるようになります。
特にSPIなどは出題傾向が似ているため、問題ごとの「型」を把握することで解答スピードが格段に上がります。
間違えた問題には必ずチェックを入れ、原因を分析しながら復習を繰り返すことが、確実なスコアアップへの近道です。
また、繰り返し解く時間を作るためにも2週間前から対策を始めるようにしましょう。
時間をはかって解く
Webテストは時間内に解き終えるスピードも重要です。
普段から時間をはかって練習することで、問題を解くペース配分が身につきます。
どの問題にどれだけ時間をかけるか、自分なりの「時間感覚」を持つことが本番での焦りを防ぎます。
特にSPIの非言語分野や玉手箱の計数問題などは、時間内にすべて解くのが難しい構成になっているため、完璧を目指すより「解ける問題から解く」判断力も重要です。
本番と同じ制限時間で模擬練習を繰り返し、常に本番を意識した訓練を心がけましょう。
苦手な分野から潰していく
全体の得点を上げるには、苦手分野の克服が不可欠です。
SPIで毎回ミスする非言語問題や、玉手箱の図表読解など、自分がつまずきやすい分野
を把握し、そこを重点的に対策することで効率的にスコアを伸ばせます。
得意な分野を繰り返しやるだけでは、全体の点数は頭打ちになります。
苦手を避けず、なぜ苦手なのかを分析し、基礎からやり直すことが重要です。
場合によっては動画教材や講座を活用するのも効果的です。
1つひとつの弱点に正面から向き合い、バランスの取れた得点力を目指しましょう。
グループディスカッションで落ちてしまう場合
就活の選考では、グループディスカッション(GD)が行われるケースも珍しくないため、グループディスカッションへの対策も必要になります。
GDで落ちることが多い…と悩んでいる人は、まずはディスカッションの流れや高評価を得るコツなどを押さえたうえで、重点的に対策することが重要です。
GDへの対策を強化したい場合は、主に以下のポイントを実践しましょう。
- GDの知識をつける
- 企業の事業内容に関する知識を持っておく
- フレームワークを覚える
- 友人と対策する
このように、まずはGDとは何かという基礎的なポイントから整理したうえで、コツを把握していく必要があります。
また、ディスカッションのテーマは志望企業の事業内容に関連するものが多いため、事業内容に関する知識・情報を多く持っておくことも重要です。
そのうえで意見を述べる練習を重ね、グループディスカッションでの高評価を目指しましょう。
では、詳細を以下からまとめていきます。
GDの知識をつける
グループディスカッションで落ちてしまう人は、まず、グループディスカッションについて基礎的な知識をまとめておきましょう。
そもそもディスカッションはどのような流れで進むのか、役職には何があるのかなどのポイントが重要です。
就活の選考で実施されるグループディスカッションは、基本的に、以下の流れで進む場合が多いです。
- 役職や時間配分の決定
- テーマの確認・認識共有
- 現状の把握と課題の洗い出し
- 解決策について意見を出し合う
- まとまった意見についての検証
- 結論をまとめる
- 発表
このような流れが大まかなグループディスカッションの流れであり、事前に整理しておけば、次にやるべきことが整理されるため積極的な行動・発言につながりやすいでしょう。
また、主な役職・役割には以下が挙げられます。
- 進行役
- タイムキーパー
- 現状の把握と書記課題の洗い出し
- アイデアマン
- 発表者
グループディスカッションでは、周りより抜きん出て目立つことより、決められた役割をしっかりとこなすことが大切です。
企業の事業内容に関する知識を持っておく
グループディスカッションで高評価を得るには、企業の事業内容について、さまざまな知識・情報を持っておくことが大切です。
なぜならディスカッションの議題・テーマは、その企業に関係することがほとんどだからです。
前もって議題について知見があれば、積極的に意見を出すことができ、議論をスムーズに進められるでしょう。
もちろん、知識がない状態でも議論はできますが、事前知識・情報はあるに越したことはないといえます。
万が一まったく知らない業界用語が出てきたら、その用語の意味から調べることになってしまうため、時間を多く使ってしまうことになります。
業界・企業研究を進めるときなどに、事業内容については、自ら深い話ができるくらい研究しておきましょう。
フレームワークを覚える
フレームワークとは、思考の軸や視点を整理する「型」のことです。
たとえば3C(市場・競合・自社)やSWOT分析、MECE(モレなくダブりなく)といった基本的なフレームワークを覚えておくことで、議論の抜け漏れを防ぎ、説得力ある発言がしやすくなります。
フレームを意識すると、自分の意見が論理的に伝えられるようになり、発言の質が格段に向上します。
リーダーや書記などの役割に関わらず、議論の方向性を整える姿勢が評価につながるため、GDの対策としてフレームワークの習得は非常に効果的です。
友人と対策する
グループディスカッションで落ちてしまう場合は、友人と事前にディスカッションをシミュレーションすることで、練習を重ねることも重要です。
友人と対策すれば、お互いにグループディスカッションに慣れることができ、良い練習の機会になります。
また、自分に向いている役職を見つけたり、意見を聞く際のリアクションを練習したりすることもできます。
自分の発言の仕方や進行方法などについて、友人からフィードバックをもらうこともできるでしょう。
グループディスカッションも面接と同様に、ある程度は「慣れ」が関係してきます。
空気に慣れていないと、まともに発言できず時間が終わってしまうことも多いため、とにかく慣れるという意味でも友人と一緒に練習することは大切です。
面接で落ちてしまう場合
就活の面接で落ちてしまう人は、用意する回答を改めて見直したり、ひたすら面接練習・模擬面接を重ねたりすることが大切です。
多くの就活生にとって、面接をうまく乗り切ることは大きな壁になります。
実際に「面接が不安」「どうしても面接は苦手」と感じている就活生は多いでしょう。
就活では、面接は複数回行われることがほとんどであり、最終選考も基本的には面接になります。
対策は必須となるため、苦手な人・不安な人は、必ず対策を強化しておきましょう。
主に対策すべきことは、以下のとおりです。
- 自己分析・企業分析をする
- 必須質問に対する答えを作っておく
- 一次・二次・最終面接ごとの対策をする
- 面接の壁打ちをする
面接をうまく乗り切るうえでも、事前の自己分析や企業分析は重要です。
そのうえで必須質問の答えをシミュレーションしながら用意し、壁打ち練習も繰り返し行いましょう。
では、次の項目から面接対策の3つのポイントをそれぞれ解説していきます。
また、面接でよく聞かれる質問については、以下を確認してみてください。
自己分析・企業分析をする
面接対策を強化する際は、あらかじめ自己分析や企業分析をしっかりと行っておくことも大事です。
自己分析や企業分析を徹底的に行っておけば、自分の強みや将来のビジョンなどを明確に把握できるため、説得力をもって自分自身をアピールできます。
就活の軸と企業に対する深い理解がある状態で、質問に対して回答できるため、基本的にはどのような質問をされても落ち着いて答えられるでしょう。
一つひとつの回答に対して一貫性も見られるため、より説得力が加わり、企業からは魅力を感じてもらいやすくなります。
矛盾したことを伝えてしまったり論点がずれたりする場合は、改めて自己分析・企業分析を見直しましょう。
面接はESや履歴書と違って事前に回答をきれいに整えられるわけではないため、しっかりと自分自身や企業に対して理解が深まっていないと、スムーズな回答につながりません。
必須質問に対する答えを作っておく
就活の面接で落ちないためには、必須質問に対する答えをまとめておくことが大切です。
面接では、業界・企業問わず必ずといって良いほど聞かれる質問があるため、それらの答えを事前にまとめておくことは最低限必要なことです。
回答を考えたうえで答え方を練習しておけば、答えに詰まってしまうことはなくなります。
面接でよく聞かれる質問といえば、主に以下が挙げられます。
- 自己紹介
- 志望動機
- 自己PR
- ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)
- 長所・短所
- 就活の軸
これらの質問は対策必須の質問であるため、スラスラ回答できるように、対策を完璧にしておくことが重要です。
必須質問である志望動機や自己PRすらまともに答えられないのでは、真面目に就活と向き合っていない印象がついてしまうため注意しましょう。
一次・二次・最終面接ごとの対策をする
一次・二次・最終面接には、それぞれ特徴があり、対策方法も異なります。
企業が知りたいことやアピールすべきポイントなどをまとめたので参考にしてみてください。
| 面接段階 | 特徴 | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 一次面接 (人事や若手社員) |
・人物像・マナーの確認 ・志望動機や自己PRなど基本的な質問が中心 ・グループ面接の場合もある |
・自己紹介・志望動機・自己PRを準備 ・企業研究をして「なぜこの会社か」を話せるように ・話す内容はPREPやSTARで構成する ・清潔感・敬語・表情に注意 |
| 二次面接 (現場責任者・中堅社員) |
・実務的なスキルや経験を深堀りされる ・配属予定部署との相性を見られる ・長期的に働けるかを判断 |
・過去の経験をSTAR法で整理して伝える ・業務内容や職種の理解を深める ・協調性や柔軟性、主体性を示す ・質問には具体的なエピソードで回答 |
| 最終面接 (社長・役員) |
・企業理念とのマッチングを重視 ・抽象的な質問(「あなたにとって仕事とは?」など)もあり ・内定の決定権を持つ |
・志望動機をもう一段深掘りして語る ・自分の価値観やビジョンを明確に ・誠実な態度で自分の言葉で話す ・逆質問では経営目線を意識 |
面接の壁打ちをする
就活の面接で落ちないように対策するなら、面接の壁打ちを何度も行い、練習を徹底することが大切です。
完璧に回答を準備しても、実際に話すことに慣れていなければ、スムーズな回答につながりません。
また、用意した回答を暗唱するような答え方もNGなので、自然に話せるように意識することも大事です。
話すときはアイコンタクトや明るい表情、明るい声のトーンも重要なので、鏡を見たり録画したりしながらブラッシュアップを重ねることも必要です。
せっかく良い回答を準備しても、答えるときの振る舞いにネガティブな印象が多いと、アピールは台無しになってしまいます。
面接の練習では、就活エージェントを活用するなどして積極的に模擬面接を重ねることも重要です。
回答内容や答え方について具体的なアドバイスをもらえるため、面接が苦手な人は、積極的にエージェントに相談してみましょう。
【5月に内定なし】5月以降もエントリーできる企業
前述のとおり、5月になると多くの企業がエントリーを締め切っている状態になるため、エントリーできる業界・企業は限られる場合があります。
そのため5月に新たにエントリーする際は、5月以降でもエントリーできる業界を事前にチェックしておくことが重要です。
5月以降もエントリーできる企業は、以下が挙げられます。
- 上場企業・大手グループ企業
- 中小企業・ベンチャー企業
- 二次募集をしている企業
このような企業・業界は5月以降もエントリーできるケースが多いため、エントリーを増やす際は積極的にチェックしておきましょう。
では、それぞれの特徴やエントリー時の注意点などを見ていきます。
上場企業・大手グループ企業
5月時点で内定がない就活生でも、上場企業・大手グループ企業は選択肢のひとつです。
就活のピークを過ぎた5月以降でも、実は上場企業や大手グループ企業の中には、エントリーを継続している企業があります。
大手はもう締め切っているのでは?と思われがちですが、全ての企業が同じスケジュールで採用を進めているわけではありません。
特にグループ企業の場合は、本社採用とは別枠で選考を実施していることがあり、5月以降も採用活動を行っているケースも多く見られます。
さらに、上場企業の中でも人材確保に向けて二次募集や追加募集を行うこともあるため、諦めずに情報収集を続けることが大切です。
また、大手グループ企業の魅力は、安定した経営基盤と充実した教育体制にあります。
自分には大手は無理かも…と感じる方でも、グループ会社であれば自分に合った環境で働ける可能性が高く、安心してキャリアをスタートできるでしょう。
5月以降は、企業の採用ページだけでなく、就活サイトや逆求人型サービス、企業説明会なども活用し、こまめに情報をチェックするようにしましょう。
まだまだチャンスはあります。
自分の可能性を狭めず、柔軟に選択肢を広げていくことが、内定への近道になります。
中小企業・ベンチャー企業
5月以降の就活では、中小企業やベンチャー企業にも積極的に応募しましょう
5月以降、就職活動を巻き返すうえで特に注目したいのが、中小企業やベンチャー企業です。
こうした企業は、採用活動の時期が比較的柔軟であるため、5月以降もエントリーや選考を受け付けていることが多くあります。
中小企業やベンチャー企業の魅力は、何といっても成長のスピード感と柔軟な社風です。
若手のうちから責任ある仕事を任されたり、自分の意見が反映されやすい風土があるため、主体的に働きたい方にはとても合った環境といえるでしょう。
また、経営陣との距離が近く、組織の方向性や意思決定のプロセスを間近で学べる点も大きなメリットです。
一方で、ネームバリューがないから不安…という声もありますが、実は働きやすさや福利厚生が整っている企業も多く、実力主義で成果をしっかり評価してくれる職場も増えています。
就職後のキャリアアップや転職市場での評価にもつながる経験を積める場として、十分に魅力的です。
大手企業だけにこだわるのではなく、自分の価値観や働き方に合った企業を見つけるためにも、中小企業やベンチャー企業にも目を向けてみましょう。
5月からの就活こそ、視野を広げて柔軟な発想で動くことが、納得のいく内定につながっていきます。
二次募集をしている企業
5月以降でもエントリーできる企業を探すなら、やはりねらい目は二次募集を始めている企業です。
選考の途中で採用枠が空いた場合での二次募集、もしくは初回エントリー後の再募集などがあります。
企業の二次募集は決して珍しくないため、大手であっても、5月以降に再度エントリーを受け付けるケースはあるものです。
二次募集のタイミングでエントリーし、徹底的に対策して選考に臨めば、今からでも内定を勝ち取れる可能性はあります。
そのため、二次募集にエントリーするには、企業の公式ホームページをこまめにチェックする必要があります。
二次募集の要項は随時更新されるため、積極的にアンテナを張ったうえで、情報をキャッチすることが大切です。
【5月に内定なし】最短で内定をとる方法
5月の時点で内定なしの状態は、ほかの人と比べて遅れを取っていると言わざるを得ないため、内定は可能な限り5月までには取っておきたいところです。
そのためまずは、5月中に内定を取り、6月に焦るような状況にしないための方法をまとめていきます。
5月中に内定獲得までつなげられれば、無事に1件の就職先を確保した状態になり、その後就活を続けるとしても安心感が生まれます。
そういった安心を得るためには、5月中に、以下のような行動・対処を意識する必要があります。
- ベンチャーや中小企業を狙う
- 就活エージェントを利用して効率的に探す
とにかく積極的な行動を心がけたうえで、企業選びに徹底的にこだわることが重要なポイントです。
では、それぞれどのような点に注意すべきなのか、詳細をチェックしてみましょう。
ベンチャーや中小企業を狙う
5月中に内定獲得までこぎつけたい場合は、早めに内定を取れる企業を効率よく絞り込む必要があります。
事前に早めに内定を取れる企業をチェックしておけば、自分に合う企業をスムーズに探せるでしょう。
基本的には、ベンチャー企業などの選考期間の短い企業に照準を絞って探すことが重要であり、反対に選考期間が長い企業は避けるべきといえます。
5月中に素早く内定を取れる可能性がある企業は、主に、ベンチャー企業や中小企業、大企業のグループ会社などが挙げられます。
これらの企業は、大手企業と比べて選考期間が短かったり面接回数も少なかったりするため、早めに内定が出る可能性があります。
そのため、エントリーから1か月ほどで内定を勝ち取れる場合もあり、内定なしの状態で悩んでいる人にはおすすめといえます。
ベンチャー企業・中小企業・大企業のグループ会社は、総合的に見て、選考の形式やスケジュールも柔軟な傾向です。
そのため、さまざまなタイミングで募集をかけており、比較的エントリーしやすいこともメリットと言えるでしょう。
1か月で内定を勝ち取りたい場合は、大手に目を向けるのは避け、主にベンチャー企業や中小企業の採用情報をチェックしてみましょう。
効率的な探し方は就活エージェント
1か月で内定を取るには、効率的に、選考がスピーディーな企業を見つけることが必要です。
しかし自分で1社ずつ企業の採用情報をチェックし、自分に合う企業をリストアップしていくのは、かなり骨が折れることも事実です。
そのため、効率良く選考の早い企業を見つけるうえでは、就活エージェントに相談することがおすすめです。
就活エージェントでは、就活生に対して企業の求人紹介も行っています。
就活エージェントはさまざまな業界の就活事情に精通しているため、どの企業・業界がスピーディーに選考を行ってくれるのかは、しっかりと把握しているものです。
特に、就活エージェントが紹介する企業は、エージェントとのつながりが深いことも特徴です。
実際にエントリーする際は、その企業がどういった特徴を持つ企業なのか、選考では何に注意すべきなのか、より具体的なアドバイスをもらえる可能性が高いです。
効率的にすぐ内定を取れる企業を見つけるなら、積極的に就活エージェントを頼ってみましょう。
【5月に内定なし】5月から挽回したい人が意識すべき6つのこと
5月時点で内定がないと、「自分だけが遅れているのでは」と不安になってしまうこともあるかもしれません。
ですが、就活はまだまだ巻き返せる時期です。
大切なのは、今からの行動です。
ここでは、5月から挽回を目指す方に向けて、意識すべき5つのポイントをご紹介します。
心の持ちようや行動の軸を整えることで、内定にぐっと近づけるはずです。
就活スケジュールには余裕を持たせる
今すぐにでも内定がほしいがためにとにかく就活の予定を詰め込みたい気持ちはよくわかりますが、スケジュールを詰め込みすぎると逆効果になる可能性があります。
特に選考の質を高めたいときには、面接対策や企業研究にしっかり時間を取ることが不可欠です。
また、リラックスして臨むことも大切な要素のひとつです。
面接やエントリーが重なりすぎて疲弊してしまうと、表情や受け答えにも影響が出やすくなります。
スケジュールには必ず「余白」をつくり、準備や休息に充てる時間を確保しましょう。
焦りすぎず、地に足をつけて就活を進めていくことが、長い目で見たときに納得のいく結果につながります。
就活の軸を決めてブラさない
就活が長引いてしまう原因のひとつに、「就活の軸が定まっていない」というケースがあります。
軸が曖昧だと、エントリーする企業ごとに志望動機がブレてしまい、結果として説得力のないアピールになってしまうことが少なくありません。
「なぜその業界なのか」「どんな働き方をしたいのか」「自分は何を大切にしているのか」など、自分なりの軸を一度しっかりと言語化しておきましょう。
そのうえで、軸からズレすぎない企業を選ぶことで、一貫性のある就活が可能になり、面接でも説得力を持って話せるようになります。
迷いがあるときこそ、自分の原点に立ち返ってみることが大切です。
アピールポイントは無理に変えない
選考がうまくいかないと、「今の自己PRじゃ通らないのかも…」と不安になり、企業ごとに伝える内容を大きく変えてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、企業に合わせようとしすぎてアピール内容が毎回バラバラになると、かえって自分の本当の強みが伝わりづらくなってしまいます。
まずは自分が最も自信を持てるエピソードや強みをベースに、伝え方を調整する程度にとどめておくのがおすすめです。
一貫した軸や強みがある学生は、企業から見ても信頼感があります。
自分らしさを大切にしながら、伝え方を工夫していくことが、最短で内定に近づくためのポイントです。
就活以外でリラックスをする
5月に内定がないと、どうしても「一刻も早く結果を出さなければ」と思い詰めてしまいがちですが、心の余裕がなくなると、視野が狭まり、本来の自分の魅力が出しづらくなってしまいます。
就活がうまくいかないときほど、あえて就活から少し離れてリフレッシュする時間を作ることも必要です。
友人と会ったり、趣味に没頭したり、自然の中でリフレッシュしたり……そんな時間が、結果的に気持ちの切り替えやパフォーマンス向上につながります。
ストレスや疲れは面接の表情や話し方にも表れやすいため、健康的な生活とメンタルケアも就活成功のカギになります。
面接の振り返りをする
面接を受けたあとに、そのまま次の選考に進んでしまっていませんか? 内定に近づくためには、面接の振り返りを習慣にすることがとても大切です。
面接は、ただ受ければ良いというものではなく、経験を通じて改善点を見つけていくことが重要です。
面接後は、なるべく早いうちに内容を思い出し、どんな質問があったか自分はどう答えたか答えに詰まった部分はなかったかもっと良い伝え方があったかなどをメモに残しておきましょう。
このメモは、次の面接対策に大きく役立ちます。
また、複数社を受けるうちに、同じような質問をされることも多くあります。
たとえば学生時代に力を入れたことや志望理由自己PRなど、頻出の質問には自信を持って答えられるよう、回答の質を高めていくことがポイントです。
さらに、面接官の反応にも注目してみましょう。
話している最中に興味を持ってくれた部分や、逆にあまり響いていないように見えた点など、自分では気づきにくいヒントが得られることもあります。

そうした観察も含めて、次にどう活かすかを考えることで、面接力は確実に上がっていきます。振り返りは地道な作業ですが、選考を重ねる中で確かな成長を実感できるようになります。面接の一つひとつを糧にして、自分らしいアピール方法を磨いていきましょう。
就活サービスを毛嫌いしない
「エージェントに頼るのはなんだか気が引ける」「いろんなサイトに登録するのが面倒」と感じてしまう方は少なくないでしょう。
ですが、就活サービスを上手に使うことで、時間や労力をぐっと節約できることは事実です。
特に、エージェントや逆求人サイトなどは、自分では見つけにくい企業との出会いにつながることもあり、内定獲得のきっかけになるケースも多くあります。
不安な方は、就活専用のメールアドレスを作って登録することで、情報管理もしやすくなります。
必要がなくなれば登録を解除すればいいだけなので、まずは気軽に使ってみることをおすすめします。
行動の幅を広げることで、思いがけないチャンスを手にできるかもしれません。
【5月に内定なし】内定獲得が遠のくNG行動
5月に入り、内定がまだないととにかく行動しなければと焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
確かに行動量は大切ですが、やみくもに動くことで逆効果になってしまうこともあります。
- やみくもにエントリーする
- 過度に周りと比較する
- 独りよがりの就活をする
- 内定の時期にこだわる
- 内定の数にこだわる
効率よく、そして納得のいく内定を得るためには、やってはいけない行動=NG行動を避けることも重要なポイントです。
自分では頑張っているつもりでも、方向性を間違えてしまっていては成果に結びつかず、時間と気力ばかりが消耗されてしまいます。
ここでは、内定獲得を遠ざけてしまいがちな行動について、よくある3つのパターンをご紹介します。
ご自身の行動を振り返りながら、思い当たるかもと感じたところがあれば、ぜひ今日から意識を変えてみてください。
やみくもにエントリーする
とにかく内定がほしい持ち駒を増やさなきゃという思いから、興味の薄い企業やよく知らない業界にも片っ端からエントリーしていませんか? 一見、行動力があるように思えるこの行動ですが、実は就活がうまくいかない原因の一つになることがあります。
というのも、やみくもなエントリーでは企業研究が浅くなり、志望動機や自己PRも表面的な内容になりがちです。
企業側は、応募者が本当に自社を理解し、興味を持っているかを敏感に見ています。
そのため、数撃ちゃ当たる方式では、選考通過率が下がり、自信を失ってしまうリスクもあります。

本当に大切なのは、自分の価値観や軸に合った企業を選び、その企業に合わせた丁寧な対策をすることです。エントリー数が多いことが悪いわけではありませんが、質を意識したエントリーが、結果的に効率的な就活につながります。
過度に周りと比較する
SNSや友人との会話を通じて、周囲の内定状況を知るたびに自分は遅れているのではこのまま内定が出ないのではと不安になる方も多いと思います。
しかし、過度に他人と比べすぎると、焦りや自己否定につながり、冷静な判断ができなくなってしまいます。
就活は、スタート時期も志望業界も選考ペースも、人それぞれまったく異なります。
周囲の成功体験は参考にはなっても、それがあなたにとっての正解とは限りません。
むしろ、あの人と自分は違うという前提を持つことが、落ち着いて自分に合った企業選びをするためには必要なのです。
大切なのは、他人のペースではなく自分の納得のいく就活ができているかどうか。
比べるなら、昨日の自分と比べて成長できているかを意識してみましょう。
他人の内定より、自分の未来を大切にしてください。
独りよがりの就活をする
自分のことは自分が一番よくわかっていると、すべてを一人で完結させてしまっていませんか? もちろん自分自身と向き合うことは大切ですが、就活は他者の視点や意見を取り入れることで、ぐっと可能性が広がるものです。
特に、自己PRや志望動機などは、第三者の視点でフィードバックをもらうことで、より伝わる内容にブラッシュアップすることができます。
また、面接対策では、模擬面接を通じて実際のやりとりを体感することで、答え方や話し方の改善点が見えてきます。

キャリアセンター、就活エージェント、OB・OG、友人など、頼れる存在はたくさんあります。恥ずかしい迷惑かもと遠慮する必要はありません。多くの人が、同じように悩みながら就活を乗り越えてきています。一人で抱え込まず、周囲の力を借りながら進めることが、結果的に自信を持って選考に臨むための近道になります。
内定の時期にこだわる
内定をもらうことを目的にすることは避けましょう。
周りがもう内定をもらっているのに、自分だけまだ…という不安から、とにかく早く内定をもらわなきゃと焦ってしまう気持ち、よくわかります。
しかし、内定をもらう時期にこだわりすぎることは、かえって自分を追い込んでしまい、間違った方向に進んでしまうことにもつながります。
本来、就職活動の目的は、自分が納得できる企業から内定をもらうことであり、誰よりも早く内定を取ることではありません。
早い時期に出た内定であっても、自分に合わない企業であれば、入社後に後悔するリスクもあります。
就活のスピードは人それぞれで、夏や秋以降に内定を得る学生も少なくありません。
企業によって選考スケジュールは大きく異なり、5月以降に本格的な採用を始める企業も多く存在します。
焦る気持ちが強くなればなるほど、内定が出やすそうな企業に目を向けがちになり、自分の軸と合わない選択をしてしまうこともあります。
納得のいく一社に出会うには、じっくりと自己分析を重ね、企業理解を深めながら進めることが重要です。
時期にこだわるよりも、自分が自信を持って入社できる企業を見つけること。
その姿勢が、結果的に良いご縁を引き寄せてくれるはずです。
内定の数にこだわる
内定の数を稼ごうとするのはやめましょう。
何社内定をもらったかが話題になることも多い就職活動ですが、実際に就職する企業は1社だけです。
内定の数が多いことが成功の証のように思われがちですが、それはあくまで表面的な結果にすぎません。
大切なのは、内定の数ではなく、中身です。
数を意識しすぎると、とりあえず受かりそうなところを増やそうと質より量に走ってしまい、自分に合わない企業ばかりを受けることになります。
その結果、選考に時間や労力を取られてしまい、本当に志望する企業の対策が疎かになるという本末転倒な状態に陥ることも。
また、複数内定を得た場合、どれを選ぶべきかで悩んでしまい、選考の段階での判断軸が曖昧だったことを後悔することも少なくありません。
最終的に選ぶ1社を、自分が本気で行きたいと思える企業にするためには、ひとつひとつの選考に真剣に向き合う姿勢が大切です。
内定が多ければ安心と思う気持ちは自然なことですが、それよりも、この会社で働きたいと心から思える企業との出会いを目指しましょう。
そのためには、自分の就活の目的を見失わず、納得感を大切にする姿勢が何よりも重要です。
まとめ
5月の時点で内定なしの場合、就活生としては、かなり心もとない状態といえます。
過半数以上の学生が5月に入る時点で内定を獲得しているため、内定ゼロの人は、就活の進め方を見直すなどの対策が必要です。
また、何もしていない人はとにかく早く就活の準備に取り掛かりましょう。
5月に内定なしの状態でも、エントリーできる企業を見つけて就活に向き合えば、良い結果につながる可能性はあります。
その際は最短で内定を取る方法や、必ずやるべき選考対策のポイントなどは、しっかりとチェックしておきましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート








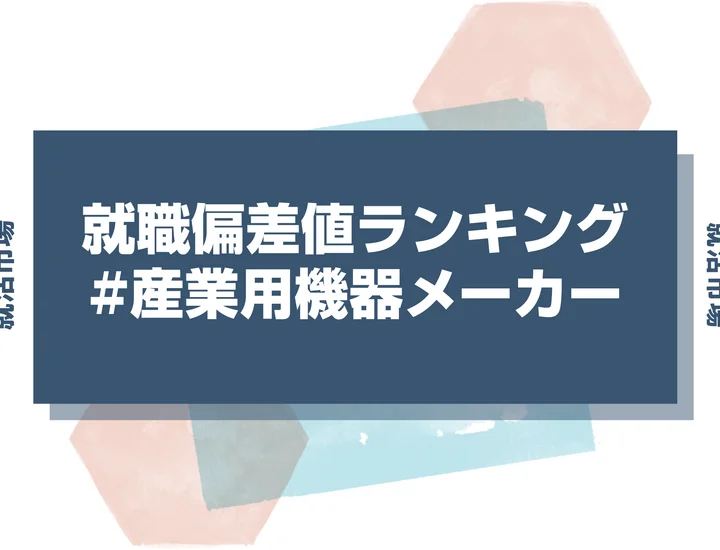







柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
まずは、自分が仕事に何を求めているのか、どんな環境で成長したいのか、どんな人と働きたいのかといった問いに向き合ってみましょう。自分の中にしっかりとした軸ができると、企業選びもスムーズになり、自然と説得力のある志望動機が書けるようになります。