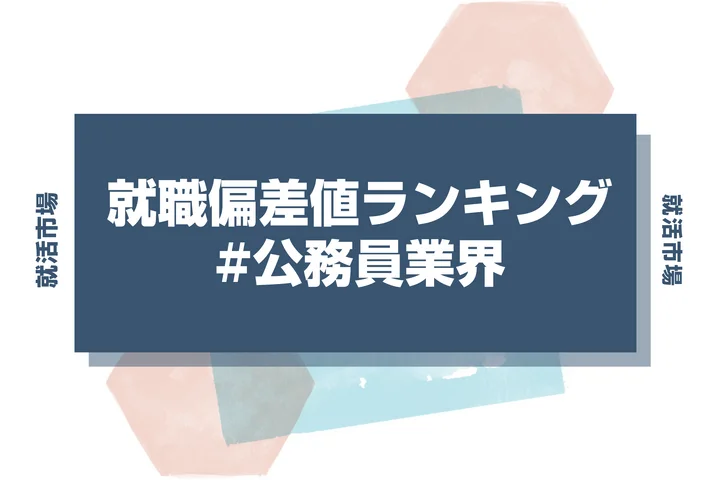目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業や業界の採用難易度を示す指標として学生に用いられる言葉です。
倍率や選考プロセスの厳しさ、人気度、報酬やブランド力などを総合的に判断して表されます。
就職偏差値はあくまで参考値であり、受験偏差値のような公的な数値ではありません。
ランキングとして公表される場合もありますが、年度や媒体によって基準が異なるのが特徴です。
そのため、就職活動においては偏差値を参考にしつつも、自分の適性や価値観と照らし合わせて判断することが重要です。
公務員業界の就職偏差値ランキング
公務員業界の就職偏差値ランキングは、職種ごとの採用試験の難易度や就任の難しさを示した目安です。
国家公務員、地方公務員、専門職といった区分ごとに異なり、採用プロセスや求められる能力が多岐にわたります。
上位ランクでは国家の意思決定に関わる職が中心であり、下位ランクでは教育機関や地方の現場職が含まれます。
学力試験だけでなく、体力検査や面接、小論文など多面的な評価がなされるのが特徴です。
ランキングは目安であり、実際の就職活動では自身の志望動機やキャリアプランに合わせた戦略を立てることが必要です。
【公務員業界】Sランク(就職偏差値75以上)
【75】内閣総理大臣
国家の最高権力者であり、政治家としても最難関のポジションです。
入職するためには国政選挙での当選を重ね、党内での強い支持を獲得する必要があります。
一般的な就職試験対策とは異なり、政治活動・選挙活動・人脈形成が重要です。
【公務員業界】Aランク(就職偏差値70以上)
Aランク以降の企業を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると27卒向けの公務員の就職偏差値ランキング全公開(Aランク〜Eランク)
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ自分の就職偏差値と企業ランクをチェックしましょう!
【公務員業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【74】副総理 最高裁判所長官 議長(衆議院・参議院)
【73】内閣官房長官 財務大臣 外務大臣 防衛大臣
【72】経済産業大臣 厚生労働大臣 会計検査院長 人事院総裁
【71】その他の国務大臣 国家公安委員会委員長 自民党派閥領袖 野党党首
【70】衆議院議員 参議院議員 副大臣 都道府県知事 地域政党党首 内閣法制局長官 内閣官房副長官 金融庁長官 警察庁長官 会計検査院長 公正取引委員会委員長 国家安全保障局長 国家公務員倫理審査会長
主要省庁や国会のトップ層が中心となるランクです。
選挙で選ばれる職や、官僚としての長いキャリアを経て就任する役職が多いです。
高度な政策立案力やリーダーシップ、法律や経済の深い知識が求められます。
【公務員業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】省庁長官 大臣政務官 警視総監 自衛隊(統合幕僚長) 内閣情報通信政策監 宮内庁(侍従長) 原子力規制委員会委員長 外務省(特命全権大使)
【68】財務省(官僚) 外務省(官僚) 裁判官 検察官 自衛隊(将官) 海上保安監 国立大学職員(教授)
【67】経済産業省(官僚) 防衛省(官僚) 総務省(官僚)
【66】内閣府(官僚) 厚生労働省(官僚) 金融庁(官僚) 警察庁(官僚) 教育委員長 国会議員政策担当秘書
キャリア官僚や司法試験合格者が多いランクです。
国家公務員総合職試験の突破が必須であり、大学在学中から徹底的な勉強が求められます。
また、語学力や国際感覚も重要となり、海外経験や研究実績も評価されやすい傾向です。
【公務員業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】国土交通省(官僚) 農林水産省(官僚) 文部科学省(官僚) 法務省(官僚) 公安調査庁(官僚) 外務省(専門職員) 衆議院事務局職員 参議院事務局職員
【64】環境省(官僚) デジタル庁(官僚) 宮内庁(官僚) 海上保安庁(官僚) 消防庁(官僚) 裁判所事務菅(総合職) 自衛隊(佐官) 国公立学校(校長) 教育委員 警察(警視長) 自衛隊(医官) 航空自衛隊(パイロット)
【63】地方上級職員(東京) 国公立学校(教頭) 皇宮護衛官 国立国会図書館職員(総合職) 議員速記者(廃止) 警視庁(特別捜査官)
【62】地方上級職員(大阪) 復興庁(官僚) 特許審査官 国税専門官 財務専門官 労働基準監督官 防衛省専門職員 防衛大学校(職員) 防衛医科大学校(職員)
【61】地方上級職員(北海道・名古屋・神奈川・福岡) 家庭裁判所調査官 航空管制官 警察(警部) 消防吏(消防司令)
国家公務員総合職や地方上級職が多くを占める層です。
専門知識に加えて、論理的思考力や人物面も重視される傾向があります。
大学院での研究や資格取得が役立つ場合も多く、幅広い学習が必要です。
【公務員業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】地方上級職員(政令指定都市) 警察官(警部補) 消防吏(消防司令補) 自衛隊(尉官) 公務員薬剤師 麻薬取締官
【59】地方上級職員(中核市) 国公立学校(教師) 消防吏(消防士長) 法務技官(心理) 食品衛生監視員 海上自衛隊(特殊警備隊) 陸上自衛隊(特殊作戦群・第一空挺団)
【58】地方上級職員(その他の市町村) 海上自衛隊(サブマリーナ) 検察事務官 公務員看護婦
【57】消防吏(消防士長) 警察(巡査部長) 航空自衛隊(曹士) 海上自衛隊(曹士) 警察(巡査長) 法務教官 入国警備官 公務員保健師
【56】陸上自衛隊(曹士) 警察(巡査) 消防吏(消防士) 海上保安士 公務員保育士 学校事務公務員 国公立学校(非常勤講師) 学校用務員 学校給食調理員
地方自治体職員や警察・消防・自衛隊など、現場での活躍が求められる職が中心です。
筆記試験と体力試験の両方に対応する必要があり、バランスの良い準備が求められます。
人物評価や面接での誠実さも重要なポイントとなります。
【公務員業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】防衛大学校(学生) 海上保安大学校(学生) 航空保安大学校(学生) 海上保安学校(学生) 陸上自衛隊高等工科学校(学生)
防衛や治安維持に直結する教育機関への進学が中心です。
高い身体能力や規律性が求められ、学業成績も一定以上が必要です。
入試段階から適性試験や面接が実施され、幅広い資質が評価されます。
【公務員業界】とは
公務員業界とは、国や自治体で働き、社会や住民の生活を支える役割を担う職種全般を指します。
まず大きくは国家公務員と地方公務員に分かれ、それぞれ政策立案から住民サービスまで幅広い業務を担います。
安定性や社会貢献性の高さから人気があり、就職偏差値ランキングでも常に注目される業界といえます。
国家公務員の役割
国家公務員は国の中枢機関に所属し、政策の立案や実行を担います。
省庁ごとに専門性が異なり、法律、経済、外交、安全保障など幅広い分野で活躍します。
国家公務員は国の方向性を左右する存在であり、国民全体の利益を守る使命を持ちます。
採用は国家公務員総合職試験や一般職試験を通じて行われ、高度な知識と論理力が求められます。
さらに国際舞台で活躍する場面も多く、語学力や多文化理解も重要なスキルとなります。
地方公務員の役割
地方公務員は都道府県や市区町村に所属し、住民に直結するサービスを提供します。
福祉、教育、都市整備、防災など、地域ごとの課題に密接に関わる業務が中心です。
地域に根差した活動を行うため、住民目線でのコミュニケーション力が重視されます。
また採用は地方公務員試験を通じて行われ、筆記試験や面接、適性検査が評価対象となります。
地域行政は地道な取り組みの積み重ねが多く、継続性と誠実さが活躍のカギになります。
専門職の存在
公務員業界には警察官、消防官、自衛官、裁判所職員、教員など専門職も多数含まれます。
それぞれに高度な知識や訓練が必要で、筆記試験に加えて体力や実技試験が課される場合もあります。
専門職は社会の安全や教育を支える要として、安定した需要があります。
また医療や技術系の職種も多く、専門資格を活かして地域や国に貢献できます。
結果として専門性を磨くことでキャリアの幅を広げ、長期的に社会に役立てる魅力があります。
公務員業界の将来性・課題
公務員業界は安定した職業として長年人気を集めていますが、社会構造の変化に伴い課題も浮き彫りになっています。
近年では行政のデジタル化が進み、業務効率化や新たなスキル習得が求められています。
また、人口減少や地方財政の厳しさから、従来の体制だけでは対応しきれない状況も増えています。
今後は安定だけでなく、社会の変化に対応できる柔軟性と改革意識を持った人材が重要視されていくでしょう。
行政のデジタル化による業務変化
政府が推進するデジタル庁の設立やマイナンバー制度の普及により、行政サービスは大きく変化しています。
従来の紙中心の業務からデジタル化が進み、システム管理やデータ分析の知識を持つ職員が求められています。
これにより、単なる事務処理だけでなく、ITスキルや企画力が公務員にも不可欠な要素となっています。
さらに、民間企業との連携やデジタル技術の活用によって、より効率的で透明性の高い行政運営が目指されています。
デジタル行政に適応できる人材こそ、これからの公務員業界で活躍できる存在といえるでしょう。
人口減少と地方自治体の役割変化
日本全体で人口減少が進む中、地方自治体の役割はますます重要になっています。
地域の人口流出や高齢化への対応、産業振興など、多岐にわたる課題が自治体にのしかかっています。
こうした中で、職員は単に行政手続きを行うだけでなく、地域活性化の企画立案者としての役割を担う必要があります。
また、他自治体や民間企業との連携が求められるケースも増え、従来の枠を超えた柔軟な発想が欠かせません。
地域課題を解決へ導く実行力が、これからの地方公務員に必要とされる資質といえます。
公務員に求められるスキルの変化
これまでの公務員像は「正確さ」や「安定性」が重視されてきましたが、現代ではそれだけでは不十分になっています。
行政の効率化や市民ニーズの多様化に対応するため、企画力やコミュニケーション能力が必要不可欠です。
また、デジタル化に伴い、データ分析や情報発信などのスキルを持つ職員が重宝されています。
さらに、変化を恐れず挑戦する姿勢も求められており、受け身ではなく主体的に行動できる人材が活躍しています。
自ら学び成長し続ける意欲が、今後の公務員として成功する鍵になるでしょう。
公務員業界の職種
公務員業界には多様な職種が存在し、それぞれの分野で異なる魅力とやりがいがあります。
国家公務員、地方公務員、専門職などのカテゴリーに分かれ、求められるスキルや働き方も異なります。
安定性や社会的意義の高さに加え、キャリアアップや地域貢献のしやすさが職種選びのポイントとされています。
ここでは、公務員業界で代表的な3つの職種について詳しく解説します。
国家公務員の職種
国家公務員は、国の政策立案や制度運営に携わる仕事で、高い専門性と責任感が求められます。
主な職種には、総合職・一般職・専門職(国税専門官、労働基準監督官など)があり、それぞれ役割が明確に分かれています。
国の中枢で働くことができるため、影響力の大きさややりがいを感じやすい点が魅力です。
また、転勤や出向を通じて幅広い経験を積めることから、キャリア志向の学生にも人気があります。
社会全体に影響を与える仕事をしたい人に向いている職種です。
地方公務員の職種
地方公務員は、地域に密着して住民サービスを提供する職種です。
市役所・県庁職員などが代表的で、教育、福祉、まちづくり、観光など多彩な分野で活躍できます。
地域住民と直接関わる機会が多く、成果が目に見えやすいため、やりがいを実感しやすい点も魅力です。
また、地元で働ける安定感やワークライフバランスの良さも人気とされています。
地域のために貢献したいという想いを持つ人にぴったりの職種です。
専門職の職種
専門職公務員は、特定分野の知識やスキルを活かして社会に貢献する職種です。
代表的なものに、警察官、消防官、教員、技術職、公立病院の医療職などがあります。
それぞれの分野で市民の安全や教育、生活を支える重要な役割を担っています。
特に最近では、心理職やデジタル関連職など新たな専門職への需要も高まっています。
専門知識を活かして人や社会を支えたい人に最適な職種といえるでしょう。
【公務員業界】特徴
公務員業界の特徴は安定した雇用と社会貢献性、そして透明性の高い制度運営にあります。
景気に左右されにくく、長期的に働ける点が多くの学生に評価されています。
さらに福利厚生の手厚さもあり、ワークライフバランスを重視したキャリア形成が可能です。
安定性の高さ
公務員業界の最大の特徴は、景気の影響を受けにくい雇用形態です。
不況期であっても解雇リスクが低く、長期的に働ける安心感があります。
安定した収入と雇用はライフプランを立てやすく、将来設計の基盤になります。
また昇給制度や退職金制度も整備されており、経済的に安心できる環境です。
したがって長期的な視点でキャリア形成を考える学生にとって大きな魅力となります。
社会貢献性の高さ
公務員は政策や行政サービスを通じて社会の仕組みを支えています。
住民の安全、福祉、教育、都市環境など、幅広い領域で役割を果たしています。
社会貢献を実感できる仕事であり、やりがいの大きさが魅力です。
また地域社会に密着した仕事は、多くの人々の生活を直接的に改善します。
そのため使命感を持ち、長期的に取り組む姿勢が求められます。
制度と透明性
公務員の採用や昇進は法律や規則に基づき、公正で透明性の高い仕組みで行われます。
評価基準が明確で、努力が反映されやすいキャリア形成が可能です。
公平性を重視した制度が整っており、信頼性の高い組織運営が行われます。
さらに不正防止や監査の体制もあり、説明責任が常に伴う点も特徴です。
そのため社会からの信頼を得るためには、誠実さと責任感を持って行動する姿勢が必要です。
【公務員業界】向いている人
公務員業界に向いているのは、安定志向だけでなく、公共の利益を優先できる人です。
また地道な努力を継続できる人や倫理観を持つ人が求められます。
したがって社会に貢献したいという意欲を持つ学生に適したキャリアといえます。
公共性を意識できる人
公務員は国民全体の利益を優先し、社会の公平性を保つ役割があります。
そのため個人の利益よりも公共の利益を重視できる人が適しています。
公平性や誠実さを大切にする姿勢は、公務員に欠かせない資質です。
倫理観や責任感を持ち、透明性のある行動ができることが信頼につながります。
最終的に地域や国に対して誇りを持ち、長期的に貢献したい人に向いています。
継続力と忍耐力がある人
行政業務は短期で成果が出にくく、長期間の努力が必要です。
そのため地道な作業や書類業務に取り組み続ける粘り強さが求められます。
継続して努力できる力がある人は、公務員として高く評価されます。
一つひとつの業務を正確に積み重ねることで、やがて成果につながります。
つまり大きな成果は長期的な積み上げによって実現されるのが特徴です。
協調性と調整力がある人
公務員は多くの関係者と協力しながら仕事を進める必要があります。
そのため部署や外部組織との調整が多く、協調性のある姿勢が欠かせません。
チームワークと調整力が求められるため、人間関係を大切にできる人が活躍します。
意見が異なる場合でも冷静に対応し、合意形成を進められる柔軟性が必要です。
結果として協力体制を築きながら課題解決を進められる人材が評価されます。
【公務員業界】内定をもらうためのポイント
公務員試験に合格するためには計画的な学習と人物評価対策が必要です。
具体的には筆記試験対策に加え、面接や小論文への準備も欠かせません。
このように幅広い知識と実務適性を示すことが内定獲得につながります。
筆記試験の対策
筆記試験は一般知識や専門科目が幅広く出題されます。
そのため基礎力を固め、過去問演習で出題傾向を把握することが重要です。
効率的な学習計画を立て、得意科目で得点を伸ばす戦略が有効です。
一方で苦手科目は早めに対策し、全体で合格点を確保する必要があります。
さらに日常的にニュースや時事問題に触れることも得点力向上につながります。
面接試験の対策
面接試験では志望動機や人物面が評価されます。
そのため志望先の業務理解と自己分析を徹底し、具体的なエピソードを用意しましょう。
誠実さや責任感を示す回答が評価につながります。
また模擬面接や練習を重ね、自然なコミュニケーションを心がけることが大切です。
さらに逆質問では組織理解や学習意欲を示せると好印象を持たれます。
小論文試験の対策
小論文試験は論理的思考力や政策理解を確認するために実施されます。
したがって課題に対して背景、問題点、解決策を整理して書くことが重要です。
論理的で簡潔な表現ができると評価が高まります。
また日頃から新聞記事を要約する習慣を持つと文章力が向上します。
加えて社会課題に関する知識を幅広く蓄積しておくことが有効です。
【公務員業界】よくある質問
公務員業界を志望する学生からは、年収やキャリアパス、転勤についての質問が多いです。
しかし制度や職種ごとに異なるため、募集要項や説明会で最新情報を確認することが大切です。
ここではよくある質問の一部を解説します。
年収はどのくらいか
公務員の年収は職種や学歴、勤続年数によって異なります。
一般的に初任給は安定しており、昇給制度も整っています。
年功序列的な給与体系が基本ですが、成果や役職で上昇幅が変わります。
また地方と国家で水準に差があり、地域手当なども影響します。
このように全体として安定した収入が期待できる点が特徴です。
転勤はあるのか
国家公務員は全国転勤の可能性が高く、地方公務員は地域内での異動が中心です。
一方で専門職は勤務地が限定される場合もあります。
勤務地の柔軟性を理解し、ライフプランと合わせて検討することが大切です。
また転勤はキャリア形成や人脈拡大の機会にもつながります。
さらに希望調書で意思を示すことで、ある程度調整できる場合もあります。
キャリアパスはどうなるか
公務員はローテーションを通じて幅広い経験を積みます。
まず若手期は現場や基礎業務を経験し、中堅以降は企画や管理職の役割が強まります。
専門性を高めるキャリアパスも存在し、資格や研究活動が評価されます。
また昇進は勤務実績や評価に基づき、公平な基準で決定されます。
結果として長期的な成長を見据えて、計画的にキャリアを形成できます。
まとめ
公務員業界は安定性と社会貢献性の高さから、多くの学生に支持されています。
一方で筆記試験や面接、小論文など多面的な対策が必要であり、継続的な準備が欠かせません。
最終的に自分の強みを活かし、組織や社会にどう貢献できるかを明確にすることが内定獲得につながります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート