目次[目次を全て表示する]
面接で話すガクチカ
ガクチカはほとんど全てといっていいほど全てのESやその他選考書類に必ず質問項目が存在します。
「ガクチカ」とはESと面接で何か評価が変わるのでしょうか?
この記事ではポイントや参考になる例文など、面接に特化した視点でガクチカについて紹介していきます。
【大学3年生必見】AI模擬面接ツールで面接対策しよう
就活で必ず通る「面接」。ただ面接対策ってどうやってやるのだろう、と何から始めればいいのか悩んだり、進め方がわからなかったりと、意外とハードルが高いです。
そこで、今回「いつでもどこでもAI模擬面接ツール」をご用意しました。
頻出問題から変わった問題までAIが人事目線で添削するので、すきま時間であなたの面接力をあげることができます。
メンバー登録後すぐに使用可能なため、ぜひあなたもこの「AI模擬面接ツール」を活用して選考通過率を上げましょう!
※画像の質問はイメージです。
面接とES、同じガクチカを話してもいい?

面接で話すガクチカはESと同じ内容のもので構いません。
むしろ、面接はESの内容を元に進められるため、ESと同じでないと「一貫性がない」とマイナスの評価を受けることもあります。
面接ではガクチカの内容について深掘りされることが多いので、しっかりとエピソードを整理し、説得力や一貫性のある回答に仕上げることがポイントです。
ただし、エントリーシートの内容を丸暗記して面接でそのまま話すのは避けましょう。
面接官は応募者の本当の姿や考え方を知りたいと思っています。
同じ内容をただ再度述べるだけではなく、より具体的な内容を提供できると理想です。
エントリーシートと面接での話の整合性を確認し、自己PRや学生時代の頑張ったことについて深掘りされることを想定して準備しましょう。
面接中にESを見ながら話すことは可能?
結論として、面接中にESを読みながら話すことはあまりおすすめできません。
ESを読みながら話してしまうと、どうしてもただの棒読みになってしまい、あなたの伝えたいことも抑揚を持って話せなくなってしまいます。
また、ESばかり読んでいるとコミュニケーションを取る意志がないとみなされ、評価が下がることも多いです。
面接はあなたの用意してきたことを棒読みで一気に喋り倒すものではなく、面接官とお互いを理解するための時間です。
よって、面接中にESを呼んで良いと言われたとしても基本的には読まずに話せるように対策しましょう。
面接で話すガクチカの目安時間は?
結論として、面接でガクチカについて聞かれた際の回答の目安時間は1分から3分程度と思っておけば良いでしょう。
もちろん、面接官が時間を指定してくれる場合もありますが、特に時間が指定されなかった場合は、1分から3分程度を目安に回答することをおすすめします。
あまりにも短すぎると内容が薄くなってしまい、伝わりにくくなりますし、長すぎると自分も面接官も何を言っているのかだんだんわからなくなってしまいます。
「あなたが学生時代に取り組んだこと」
「どのような工夫をしたのか」
「どのような能力を身につけたのか」
の3点であるため、長ったらしく説明する必要はありませんが、あまりにも簡潔すぎる説明は避けましょう。
企業が面接でガクチカを聞くのはなぜ?
ガクチカを作成する際、企業が質問する意図を理解しておくことが重要です。
的外れな回答では、採用担当者から「質問の意味を理解していない」と判断されるためです。
採用担当者にネガティブな印象を与えると、選考が不利になります。
本章で質問する理由を解説するので、参考にしてください。
企業が面接でガクチカを聞く理由は以下の3つです。
- 論理的思考ができているか
- 一貫性があるかどうか
- 自社に合う人材か判断するため
論理的思考ができているか
まずは、論理的思考ができているかをチェックするためです。
採用担当者は、根拠に基づいた思考や行動ができるのかを重要視しています。
たとえば、20代向けの商品を販売するなら、20代がよく利用するSNSに広告を出すことで効率よく宣伝できます。
しかし、なんの根拠もなしに新聞にチラシを折り込んでも、20代の目に届く確率はSNSと比較して下がってしまうでしょう。
上記のように、採用担当者は根拠やデータを参考にした思考ができるかに注目しています。
ガクチカを作成する際は文章に矛盾がないか、論理破綻していないか、など細かくチェックしましょう。
その結果、採用担当者に簡潔でわかりやすいアピールができます。
一貫性があるかどうか
次は一貫性があるかどうかに注目しています。
採用担当者は、就活生の人柄や価値観を見極めたいからです。
たとえばガクチカで「私はチームワークの重要性を学びました」と伝えたとします。
一方で自己PRでもチームワークについて言及したとしましょう。
採用担当者は「チームワークの重要性をよく理解している」と判断します。
なぜなら、ガクチカと自己PRで同じことを述べているからです。
就活全体を通して主張が一貫しているため、就活生の発言に説得力があります。
また採用担当者は、同じ内容の質問を角度は変えますが、何度も質問することがあります。
就活生の考えに一貫性があるか確かめるためです。
ガクチカは、一貫性が求められることを理解しておきましょう。
自社に合う人材か判断するため
最後は、自社に合う人材か判断するためです。
企業は入社した人材が、早期離職するのを防ぎたいからです。
もし、自社の価値観に合わない人材を入社させてしまうと、さまざまなデメリットが生まれます。
たとえば「仕事に主体性がない」「仕事のモチベーションが低い」などです。
仕事はチーム単位で取り組みます。
モチベーションの低さが周りに悪影響を与えるかもしれません。
そのため、企業は経営理念や経営方針を理解している人材を求めています。
就活生は、企業研究を通して企業が求める人物像を正確に把握しておきましょう。
ガクチカの文章に盛り込むことで、採用担当者に好印象を与えられます。
面接におけるガクチカの評価基準
ガクチカは学生時代の経験を通じて自己PRを行う重要な要素ですが、面接では単に頑張った内容を聞かれているわけではありません。
- 学生時代に力を入れたことからどんなことを学んだのか
- 学びを入社後に企業で活かすことができるか
- どんな仕事と相性がいいのか
- 人柄や性格が求める人物像にマッチしているか
- 論理的に話すことができているか
企業はガクチカのエピソードの中から、思考力・行動力・成長力・自社との相性など、さまざまな観点で評価を行います。
そのため、ガクチカを語る際には、何を学びどう成長したのか、社会人として活かせる力はあるか、という観点で整理することが大切です。
本章では、企業がどのような視点でガクチカを評価しているのか、その基準を5つの切り口から解説していきます。
学生時代に力を入れたことからどんなことを学んだのか
この評価ポイントは、単なる経験の事実ではなく、その経験を通じてどのような学びを得たかを重視する意図があります。
企業は、課題や壁を乗り越える中で得られた気づきや成長を見て、その人物が入社後も成長できる人材かどうかを判断しています。
ガクチカを話す際は、経験の説明にとどまらず、そこで学んだ考え方・姿勢・スキルを明確に示すことが大切です。
注意点は、学びが抽象的だったり、実体験と結びついていないと説得力に欠けてしまうことです。
たとえば協調性を学んだと述べる場合も、どのような出来事があってその学びに至ったのか、背景やエピソードを具体的に語ることで、より深い理解を企業に伝えることができます。
面接では、経験と学びがセットになって語られているかが評価の分かれ目です。
また、「だからこそ御社で○○として貢献できる」といった未来志向の言葉で締めくくるとなお良いです。
人柄や性格が求める人物像にマッチしているか
この評価軸では、就活生の価値観や性格が企業文化やチームとフィットするかを見ています。
いくら優れた経験があっても、社風に合わない人物は早期離職のリスクが高まるため、企業側は慎重に見極めます。
ポイントは、ガクチカの中に自分らしさがにじみ出ているか、素直に伝えているかということです。
注意点は、自己演出に偏りすぎて、本来の自分と違う人物像を無理に作り上げてしまうことです。
企業は誠実な人柄や、社内で協働できるかといった雰囲気も見ています。
たとえば、周囲との連携や調整を大切にしてきた経験があれば、協調性や柔軟性といった企業が好む資質を自然に伝えられます。
最終的に面接官がこの人と一緒に働きたいと思えるかどうかがカギとなるため、人柄の伝わり方が評価を大きく左右します。
論理的に話すことができているか
面接では、経験の中身だけでなく、それをどう順序立てて説明できるかという論理性も評価対象になります。
企業がこの点を見る理由は、実際の業務でも報告・連絡・相談や資料作成において論理的思考力が不可欠だからです。
評価されるためには、結論→理由→具体例→結果・学びといった構成を意識して話すことが重要です。
注意点は、話が冗長になったり、時系列が行き来するような話し方だと、聞き手にストレスを与えてしまうことです。
たとえば、経験を語る際に時系列や因果関係が明確であれば、聞き手は内容をスムーズに理解できます。
逆に話の流れに一貫性がないと、内容そのものへの評価も下がってしまうリスクがあります。
論理的に話せるかどうかは、ガクチカを通して伝える構成力・思考力の総合力として見られているのです。
面接でガクチカを話す際のポイント4つ
続いて、面接でガクチカについて話す際のポイントを大きく分けて4つ紹介します。
面接は特に時間が限られていることが多いため、以下の3点を意識した上で簡潔に話すことを心がけるようにしましょう。
結論から話す
面接官に要点を迅速に理解してもらうためには、結論から話すことが非常に重要です。
面接は限られた時間内で行われるため、最初に結論を述べて、話の主題を念頭に置いて聞いてもらえるように工夫しましょう。
ビジネスの現場においては基本的にどのような場面でも結論ファーストな話し方が好まれるため、この対策は自己PRや志望動機においても有効です。
結論を先に話すことで、面接官もあなたが何に力を入れたかを念頭に置いた上で話を聞けるため、どのようなポイントを質問しようか考えながらあなたの説明を聞くことができます。
結論から話すことで、話が冗長にならず、さらに要点も明確に伝わるため、より概要を理解してもらいやすくなるでしょう。
自分の言葉で話す
自分の言葉で話すことは面接官にあなたの熱意を伝えるために非常に重要なポイントの1つです。
書いた内容をそのまま暗記して話すような伝え方をしてしまうと、機械的で感情のこもらない表現になってしまいがちです。
しかし、面接官はあなたの個性やモチベーションの高さを見極めるためにあなた自身の言葉で話してほしいと考えています。
自分の言葉で話すことで自然な表情で話せるだけでなく、声のトーンなども熱意がこもるため、あなたの人間性や情熱を伝えやすいです。
また、自分の言葉で話すことで思い出しやすくなり、質問に対する応答も柔軟に対応できるようになります。
結果として面接官に強い印象を与えられるでしょう。
取り組みに対しての熱意を伝える
取り組みに対しての熱意を伝えることは、あなたの積極性と成果への貢献度を強調するために非常に重要です。
単に指示されたことをこなしたかのように話すのではなく、自ら積極的に努力してきた姿勢に関して説明することで、あなたの熱意や情熱が面接官に伝わりやすくなります。
熱意を持って取り組んだ経験は面接官に対して強い印象を与え、あなたがどれだけ真剣に物事に取り組む人であるかを示す証拠となるのです。
また、熱意を持って取り込むことで得られた成果や学びについて話すことは、面接官に対してあなたの成長意欲や問題解決能力をアピールすることにもつながります。
具体的なエピソードを交えて自分の熱意をしっかりと伝えることで、面接官に好印象を与え、評価を高めるようにしましょう。
深掘り質問に対しての対策をしておく
面接での深掘り質問に備えるためには、ガクチカについて、事前に想定される質問を準備し、それに対する回答を具体的に考えておくことが効果的です。
深掘り質問とは、初めの回答に対してさらなる詳細や背景、理由を問われるもので、応募者の価値観や思考プロセスを評価する目的があります。
例えば、「なぜその活動に取り組んだのか」「その結果に満足していますか」「その経験から何を学びましたか」などが挙げられます。
深掘り質問への対策として、まず自身のエピソードを振り返り、活動の動機や背景、具体的な行動、結果、学びを整理することが重要です。
5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)を活用して、回答を詳細に準備することで、論理的で説得力のある内容を作ることができます。
深掘り質問についてさらに気になる方は、こちらの記事もチェック!
面接でガクチカを話す際の注意点4つ
面接でガクチカについて話す際にはいくつかの注意点が存在します。
これらを念頭に置きながら本番に臨むことで、よりマイナスな印象を与える可能性が低く、適切な回答を提示できます。
以下の4点の内容を踏まえた上で、面接官に良い印象を与えられる回答を心がけましょう。
噓をつかないようにする
面接で自分の経験を語る際には嘘をつかないようにしましょう。
面接官はこれまで何人もの就活生を相手にしてきたプロフェッショナルであり、嘘を見抜く技術も持っています。
仮に最初は嘘がバレなかったとしても、面接が進むにつれて深掘りされる質問が増え、その中で整合性が取れない部分が出てくると、すぐにバレてしまいます。
また、一度嘘がバレると信頼関係が崩れ、採用される可能性は大幅に下がってしまいます。
正直に自分の経験や成果を話し、面接官との信頼関係を築き、ポジティブな印象を与えるようにしましょう。
たとえ小さな成功や経験であっても、正直に話すことで自己成長への努力をアピールすることは可能です。
高校以前の話は使わない
「大学時代、本当に何も経験していない」という人はなかなか難しいかもしれませんが、高校以前の話は可能な限り使わないようにしましょう。
直近の経験の方が、現在のあなたにそれらの取り組みの要素が反映されている可能性が高いからです。
また、高校以前の話をするということは、「大学時代に何も努力をしていなかった人材である」とみなされてしまう可能性もあります。
高校時代のエピソードは成長過程の一部としては十分かもしれませんが、大学時代のエピソードに比べるとインパクトが弱く、十分な印象を与えにくいです。
もし本当に大学でのガクチカが無く、高校の話をすることになったとしても、「その経験が大学生活、そして現在の自分にどのような影響を与えたのか」については、多少なりとも言及することが大切です。
丸暗記で面接に挑まない
特に緊張してしまいがちな人は、回答を丸暗記して本番に臨もうと思うかもしれませんが、これは多くの就活生が犯してしまいがちな悪手の1つです。
面接は自分が用意してきた内容を、ただ棒読みで一気に話して伝えるものではありません。
それならばESで十分であり、面接を実施する必要はないはずです。
面接を通じて企業はあなたのコミュニケーション能力や、対話ができるか、人柄が企業に合っているかなど、「ESの内容だけでは判断できないこと」を確認しようとしています。
確かにガクチカや志望動機、自己PRなどよく聞かれる質問は回答の下書きを用意し、暗記しておくことは大切です。
しかし、覚えた内容をそのまま全て話すのではなく、概要を覚えた上で、臨場感を持って話せるようにしましょう。
成果を残してない話は使わない
確かにガクチカはその過程やどのような経験をしたのか、どのように成長したのかに焦点を当てています。
したがって、必ずしも部活で全国制覇やTOEIC900点以上など、圧倒的な成績を収めている必要はありません。
しかし、いくつかあるエピソードの中で、内容が似たようなものが複数ある場合は、わざわざ成果を残していない話を活用する必要は全くありません。
自己PRの方が成果を求められる傾向は強いですが、ガクチカにおいても、成果を残していない話よりは、成果を残している話をした方が印象が良いのは当然のことです。
したがって、エピソードを選ぶ上で、成果を残した話とそうでないものがあるならば、前者を選ぶようにしましょう。
面接頻出!基本の質問&回答例10選
就活の面接において、学生時代に力を入れたこと、いわゆるガクチカは定番の質問項目です。
- 自己紹介をしてください
- 学生時代最も頑張ったこと(力を入れたこと)を教えてください
- 学生時代に取り組んだことについて、なぜ取り組んだのか教えてください
- 学生時代に取り組んだことの魅力について、知らない人にも理解できるように説明してください
- 学生時代の取り組みにおける目標とその目標を設定した理由を教えてください
- 学生時代の取り組みにおける最大の困難について教えてください
- 学生時代の取り組みにおける課題について、それに気づいた背景やきっかけを教えてください
- 学生時代の取り組みにおける困難及び課題をどのように乗り越えたのか、結果も踏まえて教えてください
- 学生時代の取り組みにおける反省点と、当時に戻れるとしたら改善したいと思うことを教えてください
- 学生時代の取り組みにおける学びとそれを社会でどのように活かすか教えてください
企業がガクチカを通じて知りたいのは、単なる経験そのものではなく、その経験を通じてどんな価値観や能力を持っているのか、どのように考え行動する人物なのかという点です。
特に面接では、ESでは見えなかった思考の深さや人柄が表れやすいため、質問の意図を理解したうえでの準備が重要です。
本章では、面接でよく聞かれるガクチカ関連の質問を10個厳選し、それぞれの意図や回答のポイント、注意点、例文まで詳しく解説します。
1. 自己紹介をしてください
この質問をされる理由は、就活生の第一印象を確認し、論理的に自己表現できるか、コミュニケーション能力があるかを見極めるためです。
回答のポイントは、基本情報(大学名・学部・学年)を述べた後、学生時代に力を入れたことの要約や自分の強みを含めて、1分程度で簡潔にまとめることです。
注意点は、単なる経歴紹介で終わらせず、相手にどんな人なのかを印象付ける構成にすることです。
ガクチカ例文
〇〇大学△△学部の□□と申します。
私は現在、学業と並行して飲食店でのアルバイトに力を入れており、接客リーダーとして新人教育や店舗運営に携わっています。
特に、スタッフ間の連携不足によるクレームが課題となっていたため、マニュアルを見直し、朝礼での共有を徹底することで、クレーム件数を半減させることができました。
この経験を通じて、課題を見つけ、周囲を巻き込んで改善に取り組む力が養われたと感じています。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
2. 学生時代最も頑張ったこと(力を入れたこと)を教えてください
この質問は、就活生がどのような目標を持ち、それに向けてどのように行動したのかを見るために行われます。
回答のポイントは、エピソードの中で課題にどう向き合い、どのような工夫や行動で成果を上げたかを具体的に説明することです。
注意点として、単に頑張っただけの感情的な表現や抽象的な言葉に終始せず、数字や成果を交えて客観的に伝えることが求められます。
ガクチカ例文
私は大学2年から所属する◯◯ゼミで、地域活性化をテーマにしたプロジェクトに最も力を入れました。
中でも地元の商店街と連携したイベント企画では、参加者が集まらず苦戦しました。
そこでSNSを活用してターゲット層を絞った告知方法を提案し、イベント内容もファミリー層向けに再構成しました。
その結果、来場者数は前回比で1.8倍に増加し、地域の方々からも好評を得ました。
この経験を通じて、課題に対して柔軟にアプローチし、チームで成果を生み出す力を身につけることができました。
「学生時代最も頑張ったこと(力を入れたこと)を1分で話してください」といった時間指定があることも多いです。
特にグループ面接ではよくあるので欠かさずに対策するようにしましょう。
3. 学生時代に取り組んだことについて、なぜ取り組んだのか教えてください
この問いでは、就活生の行動の背景にある価値観や問題意識を探る意図があります。
ポイントは、なぜその活動を選んだのかを、自分の興味や課題意識、目指す姿と関連づけて説明することです。
注意点として、他人に誘われたから、なんとなく始めたからといった受け身な動機だけでは説得力に欠けてしまいます。
ガクチカ例文
私は大学の国際交流サークルで、留学生支援に力を入れてきました。
そのきっかけは、高校時代に短期で海外研修に行った際、自分が現地で孤独を感じた経験から、日本に来る留学生にも同じ思いをさせたくないと感じたからです。
特に、新学期に孤立しやすい留学生のサポート体制が不十分であると気づき、週1回の相談会や日本語サロンの立ち上げを提案・実施しました。
その結果、参加者から『心の拠り所になった』という声をもらい、大きなやりがいを感じました。
この経験を通して、自分の経験を人の役に立てる喜びを実感しました。
4. 学生時代に取り組んだことの魅力について、知らない人にも理解できるように説明してください
この質問は、専門的な活動やユニークな経験をわかりやすく伝える説明力を測る意図があります。
重要なのは、活動内容を知らない第三者でも理解できるように、背景や目的、取り組みの内容を噛み砕いて話すことです。
注意点として、専門用語や内輪ネタを使いすぎると伝わりにくくなるため、誰にでも伝わる表現を心がけましょう。
ガクチカ例文
私は大学でデータサイエンスの勉強をしており、統計的手法を使って地元の観光データを分析するゼミ活動に参加していました。
これは、地域の観光業の課題をデータで見える化し、改善提案を行うプロジェクトです。
例えば、観光客数の季節変動を分析したところ、平日集客に課題があると判明しました。
そこで、SNSで平日限定クーポンを配布する施策を提案し、実際に平日の来客数が15%増加しました。
このように、難しい印象のある統計を、地域貢献に活かすことができたのが最大の魅力でした。
5. 学生時代の取り組みにおける目標とその目標を設定した理由を教えてください
この質問では、目標を立てて物事に取り組む姿勢と、その理由の明確さを見ています。
回答のポイントは、数値や期限などを用いた具体的な目標を示し、それを設定した背景や思いをしっかり伝えることです。
注意点は、漠然とした理想や曖昧な基準を用いないこと。
目標が具体的であるほど、計画性と実行力が伝わります。
ガクチカ例文
私はカフェでのアルバイトにおいて、スタッフ教育の質を改善することを目標にしていました。
新人スタッフの定着率が低いという課題があり、その原因を探った結果、教育内容がマニュアルに偏りすぎていることに気づきました。
そこで『3か月以内に教育満足度を80%以上にする』という目標を掲げ、OJT制度の見直しや先輩スタッフによるフィードバック面談の導入を実施しました。
その結果、アンケートで満足度は85%に上がり、離職率も低下しました。
この経験から、明確な目標があれば、周囲を巻き込みながら組織を改善できることを学びました。
6. 学生時代の取り組みにおける最大の困難について教えてください
このような質問は、壁に直面したときの対応力や粘り強さ、成長意欲を確認する目的があります。
回答のポイントは、どんな困難だったのか、なぜそれが難しかったのか、どう乗り越えたのかを筋道立てて説明することです。
注意点として、苦労を美談化しすぎたり、感情的に話すだけでは本質が伝わりません。
ガクチカ例文
私はゼミでのチーム研究において、メンバー間の意見の対立に直面しました。
特に、研究テーマの方向性について意見が真っ二つに割れ、議論が平行線をたどる事態に。
私はこのままでは研究が進まないと感じ、まずメンバー全員と1対1で話す時間を設け、各自の意見の背景を丁寧に聞くことから始めました。
その上で、両者の考えを統合できる新たな視点を提案し、最終的には全員が納得する形でテーマを決定した結果、研究発表も無事に成功しました。
この経験を通じて、利害が異なる中でも合意形成を図る調整力を培うことができました。
7. 学生時代の取り組みにおける課題について、それに気づいた背景やきっかけを教えてください
この質問は、課題を発見する視点を持っているか、そしてそれに気づくまでの思考や観察力を知るために行われます。
回答のポイントは、どのような場面で課題に気づき、その課題をどのように認識したかを具体的に示すことです。
注意点は、問題に気づいたことを漠然と語らず、背景やきっかけを論理的に説明できるかどうかです。
ガクチカ例文
私は、学園祭の実行委員としてSNSによる集客を担当していましたが、イベント直前のアンケートで『開催自体を知らなかった』という回答が多く、集客効果に課題があることに気づきました。
そのきっかけは、投稿頻度や掲載内容が実行委員の間で曖昧なまま進んでいたこと、対象者が明確に定まっていなかったことでした。
私はそこで投稿内容を学生の関心テーマに絞り込み、1日1回の定期投稿に切り替えることで反応率の向上を図りました。
結果として、イベント当日の来場者数は前年比120%となり、情報発信の重要性と課題発見の視点を学ぶことができました。
8. 学生時代の取り組みにおける困難及び課題をどのように乗り越えたのか、結果も踏まえて教えてください
この質問の意図は、実際の課題や困難をどう分析し、改善・行動につなげたかという課題解決力や行動力を見極めることにあります。
ポイントは、具体的な課題と乗り越えるために取った行動、最終的な結果までを一貫して語ることです。
注意点として、行動の工夫や変化が見えないと説得力に欠け、単なる出来事の羅列にならないよう注意が必要です。
ガクチカ例文
私はアパレル店でのアルバイト経験の中で、売上が伸び悩んでいたキャンペーン商品の販売促進に取り組みました。
当初はPOPやディスプレイだけで訴求していましたが、顧客の反応が薄く、スタッフ同士でも『目立たない』との声が出ていました。
そこで私は、実際の着用イメージをSNSで投稿し、スタッフ自身が商品を紹介する接客トークを研修で共有する施策を提案・実行しました。
その結果、該当商品の売上は週ごとに上昇し、月末には目標の1.3倍を達成しました。
この経験から、困難に対して分析・改善・行動のプロセスを自ら動かして進める力が身についたと感じています。
9. 学生時代の取り組みにおける反省点と、当時に戻れるとしたら改善したいと思うことを教えてください
この質問は、失敗や課題をどう受け止め、次にどう活かそうとする姿勢があるかを見るために行われます。
回答のポイントは、自分の課題を素直に認めたうえで、改善策や今後への意識を明確に述べることです。
注意点として、単なる自己否定で終わらず、改善の視点と前向きな姿勢がセットで語られていることが求められます。
ガクチカ例文
私はゼミのグループ研究でリーダーを務めましたが、初期段階で役割分担を曖昧にしてしまったことで、進行が遅れ、メンバー間の不満が募る結果となってしまいました。
スケジュールの遅れに気づいた段階で話し合いを行い、改めて明確なタスク管理と進捗確認の仕組みを導入したことで持ち直しましたが、もっと早い段階で問題に気づき、対処すべきだったと反省しています。
もし当時に戻れるなら、最初から明確なフローを設け、メンバーとの定期的なコミュニケーションを強化しておきたかったです。
この経験を通じて、マネジメントの重要性と、問題を早期に可視化する力の必要性を学びました。
10. 学生時代の取り組みにおける学びとそれを社会でどのように活かすか教えてください
この質問の目的は、就活生が取り組みを通じて何を得たか、そしてその学びを企業でどう活かせるかを確認することです。
ポイントは、経験から得た学びを具体的に説明したうえで、それを志望企業や職種にどう活かせるかを結びつけて伝えることです。
注意点として、学びだけを語って終わってしまわず、入社後の活用方法までを明示することが重要です。
ガクチカ例文
私は飲食店のアルバイトで、新人教育と接客の質の向上に取り組んだ経験から、相手目線で考える力の大切さを学びました。
業務に慣れない新人スタッフの不安を減らすためには、何に困っているのかを事前に察知し、説明方法を工夫する必要があると実感しました。
また、お客様の立場に立って言葉選びや対応の順番を変えることで、クレームが激減しました。
このような経験は、顧客との信頼関係が重視される御社の営業職においても大いに活かせると考えています。
お客様のニーズを丁寧にくみ取り、信頼関係を築きながら長期的に成果を出す人材を目指していきたいと思っています。
深掘り対策はツールがおすすめ!
ガクチカが面接で聞かれる際にはここまでで紹介した10の質問をされることがほとんどですが、基本的にはこれらの質問から派生した深掘り質問が必ず問われます。
自分のガクチカについてよく理解していなければ、深掘り質問に対応できず、面接本番で想定外の質問に戸惑ってしまう、なんてことも少なくありません。
そこでおすすめなのが、「ガクチカAI想定質問作成ツール」です。
このツールは学生時代に力を入れたことと志望先を入力するだけで AIが実際に面接で想定される質問を作成してくれるツールとなっており、現在無料で利用可能です。
ガクチカには自信があるけど面接本番で自分のガクチカがどのような深掘りをされるのかわからない、という方はぜひこちらから一度利用してみてください。
ガクチカ深掘り質問&回答例10選
ガクチカのエピソードを準備して面接に臨んでも、面接官から次々と飛んでくる深掘り質問に戸惑ってしまった経験はありませんか。
面接官は、あなたが話すエピソードの裏側にある、あなたの思考プロセスや価値観、人柄を深く知りたいと考えています。
そのため、単に「何をしたか」だけでなく、「なぜそうしたのか」「その時どう考えたのか」といった部分を徹底的に質問してくるのです。
ここでしっかり答えられるかどうかで、あなたの評価は大きく変わります。
一貫性のある論理的な回答は、あなたという人材の信頼性を高めるでしょう。
これから紹介する10個の深掘り質問は、面接対策としてはもちろん、あなた自身が自分の経験を深く理解するための自己分析ツールとしても非常に役立ちます。
質問の意図を正しく理解し、あなたらしい言葉で語れるように万全の準備を整えましょう。
1. なぜその活動を選んだのですか
この質問で面接官が知りたいのは、あなたの行動の源泉にある価値観や判断基準です。
何に興味を持ち、どのようなことに問題意識を感じるのか、あなたの根本的な人柄を探る意図があります。
ここで「なんとなく」「友人に誘われたから」といった受け身の理由を答えてしまうと、主体性がない人物だと評価されかねません。
大切なのは、その活動を始めるに至ったあなた自身の内的な動機を明確に語ることです。
- 高校時代に感じた課題を大学で解決したいと思った
- 自分の苦手分野を克服するために、あえて挑戦する環境を選んだ
具体的な問題意識や成長意欲から始まった経緯を説明できると、あなたの行動に説得力が生まれます。
あなた自身のストーリーとして語ることで、単なる経験の羅列ではなく、目的意識を持った行動であったことをアピールできるでしょう。
2. 最も大変だった瞬間はいつですか?
面接官は、あなたが困難な状況に直面したときに、どのように感じ、考え、行動するのか、そのストレス耐性や課題解決への姿勢を見ています。
単に「大変だった」というだけでなく、どのような状況が、なぜ自分にとって困難だったのかを具体的に描写することが重要です。
「特に大変なことはなかった」という回答は、本気で取り組んでいなかったか、課題発見能力が低いと見なされる可能性があり、避けるべきです。
- チームの意見が対立し、計画が停滞してしまった瞬間
- 予期せぬトラブルで、計画の大幅な見直しを迫られた時
具体的な場面を挙げた上で、その困難を乗り越えるために、自分がどのように考え、どのような行動を起こしたのかというプロセスを筋道立てて説明することで、あなたの粘り強さや問題解決能力を効果的に示すことができます。
3. チームでのあなたの役割は何でしたか?
この質問は、組織の中であなたがどのような立ち位置で貢献できる人物なのか、その協調性や自己認識力を確認する目的があります。
単に「みんなで頑張りました」といった曖昧な答えでは、あなたの個性や貢献度が見えてきません。
リーダー、サポート役、ムードメーカー、アイデアマンなど、チームの中で自分がどのような役割を担い、具体的にどう貢献したのかを客観的に説明することが求められます。
- 私はメンバー間の意見調整役として、対立する意見の共通点を探し、合意形成を促しました
- データ分析を担当し、議論の方向性を客観的な事実に基づいて示すことで、チームの意思決定をサポートしました
具体的な担当業務と、その行動がチームに与えたプラスの影響をセットで語りましょう。
自分の強みをどのように発揮したのかを明確に伝えることが、入社後の活躍イメージを面接官に持たせる鍵となります。
4. 他にはどんな選択肢がありましたか?
この質問の意図は、あなたが課題に直面した際に、一つの考えに固執せず、多角的な視点から物事を考えられるかどうか、その思考の柔軟性や視野の広さを確認することにあります。
「これしか思いつかなかった」という回答は、思考が浅い、あるいは検討が不十分であるという印象を与えかねません。
重要なのは、課題解決に向けて複数の選択肢を検討し、それらを比較した上で最適な手段を選んだというプロセスを具体的に示すことです。
- A案は即効性があるがコストが高い、B案は時間はかかるが根本的な解決につながる、といった形で各案のメリット・デメリットを比較し、チームの状況を考慮して最終的にB案を選択しました
なぜその選択肢が最適だと判断したのか、その理由を明確に語ることが、あなたの意思決定能力をアピールする上で不可欠です。
5. 具体的にどのくらいの成果でしたか?
ガクチカの成果を伝える際、面接官はあなたの自己評価ではなく、客観的な事実に基づいた結果を知りたいと考えています。
「すごく良くなった」「頑張って成功させた」といった抽象的な表現では、成果の大きさが伝わらず、アピールとしては不十分です。
この質問には、具体的な数値を活用して定量的に説明することが最も効果的です。
- 私の提案を実行した結果、ウェブサイトのアクセス数が施策実行前の月間5,000から8,000へと1.6倍に増加しました
上記の回答のように、beforeとafterの数値を比較して示すことで、誰が聞いても成果のインパクトを理解できます。
もし数値化が難しい活動であっても、「お客様アンケートで『満足』と回答した方の割合が20%向上した」「作業工程を見直したことで、準備にかかる時間を1時間短縮できた」など、何らかの形で客観的な指標を用いて説明する工夫をしましょう。
6. その経験から何を学びましたか?
この質問は、あなたが経験を通じてどれだけ成長できたか、そしてその学びを次に活かす力があるかを見極めるためのものです。
ここで「チームワークの大切さを学びました」のような、誰もが言いそうな抽象的な回答で終わらせてしまうと、他の就活生との差別化は図れません。
面接官が聞きたいのは、あなたならではの具体的な気づきです。
その経験を通して、あなたの考え方や行動がどのように変化したのかを語ることが重要です。
- 当初は自分の意見を主張することばかり考えていましたが、多様な意見に耳を傾けることで、より良い結論にたどり着けることを実感し、まずは相手の話を聞く姿勢を徹底するようになりました
スキル面での成長と、人間的な成長の両面から語ることで、あなたの深みや成長意欲を効果的にアピールできます。
7. 同じ状況になったら、また同じ行動をしますか?
この質問は、あなたの反省力と改善意欲、そして未来志向の姿勢を確かめるためのものです。
「はい、同じことをします」と単純に答えてしまうと、経験から学ぶ姿勢がない、あるいは思考が停止していると捉えられかねません。
たとえ成功体験であっても、完璧な行動はあり得ないという前提に立ちましょう。
重要なのは、その経験を客観的に振り返り、改善点を見つけ出す視点を持っていることを示すことです。
「基本的な方向性は間違っていなかったと思いますが、今振り返ると、もっと早い段階で周囲に協力を仰ぐべきでした。次は初期段階から情報共有を徹底し、よりスムーズに計画を進めたいです」のように、学びを活かした具体的な改善案を提示できると、あなたの成長意欲や向上心が高く評価されます。
成功体験に安住せず、常により良い方法を模索する姿勢をアピールすることが、この質問を乗り越える鍵となります。
8. 周りからはどう評価されていましたか?
この質問は、あなたの自己評価と他者評価にギャップがないか、そして客観的に自分を捉える力があるかを確認する意図があります。
自分で自分の強みを語るだけでなく、第三者からのフィードバックを交えることで、あなたの人物像に説得力と信頼性が加わります。
「みんな喜んでくれました」といった曖昧な表現では、信憑性がありません。
サークルの仲間やアルバイト先の店長、ゼミの教授など、具体的な人物からの評価コメントやエピソードを引用して話しましょう。
- アルバイト先の店長からは、『君はいつも周りをよく見ていて、仲間が困っている時に一番に気づいてサポートしてくれるね』と言われたことがあります
感謝された経験や、表彰された実績などがあれば、それも積極的に盛り込むことで、あなたの貢献度をより強く印象づけることができるでしょう。
9. 他の活動との両立はどうしていましたか?
この質問を通じて、面接官はあなたのタイムマネジメント能力や自己管理能力、そして複数のタスクを同時にこなす力があるかを見ています。
特に学業や他のアルバイトなど、複数の活動を並行して行っていた場合、この質問は頻出です。
「なんとか頑張りました」といった根性論だけでは、計画性のなさを露呈してしまいます。
重要なのは、時間をどのように配分し、何を優先して取り組んでいたのか、その具体的な工夫を説明することです。
毎週日曜日の夜に翌週1週間のタスクを全て洗い出し、学業、サークル、アルバイトの優先順位をつけて手帳に書き込んでいました。特に試験前はアルバイトのシフトを減らすなど、柔軟に調整していました
目標達成のために、どのようにリソースを管理し、効率的に時間を使っていたかをアピールすることが、社会人として必要な計画性や実行力を示すことにつながります。
10. この経験を弊社でどう活かしますか?
ガクチカに関する質問の締めくくりとして、最も重要な質問です。
この質問の意図は、あなたの経験と企業の事業内容や求める人物像が、いかにマッチしているかを確認することにあります。
単に「頑張って働きます」「コミュニケーション能力を活かしたいです」といった抽象的な意気込みだけでは、入社後の活躍イメージを伝えることはできません。
徹底した企業研究に基づいて、あなたの学びやスキルが、具体的にどの部署のどの業務で貢献できるのかを明確に結びつけて語ることが不可欠です。
例えば、「ゼミ活動で培ったデータ分析力は、御社のマーケティング部門で顧客データの解析や施策立案に直接活かせると考えております」のように、職種や事業内容と関連付けて話すことで、あなたの志望度の高さと企業への理解度を強くアピールできます。
自分の強みを企業のどのフィールドで発揮したいのかを具体的に提示することが、内定を勝ち取るための最後の決め手となります。
ガクチカ深掘りの面接対策方法
ガクチカは面接で必ずと言っていいほど聞かれる定番質問だからこそ、しっかりと対策することが内定獲得への近道です。
しかし、どれだけ綿密に準備したとしても、面接官からの予期せぬ深掘り質問に戸惑ってしまうことは少なくありません。
ここではガクチカの深堀りへの具体的な対策を紹介します。
第三者にESを読んでもらい、質問をしてもらう
深堀り対策として最も効果的な方法の一つが、家族や友人、大学のキャリアセンター職員など、第三者にESを読んでもらい、質問をしてもらうことです。
自分一人で対策していると、どうしても主観的な視点から抜け出すことができず、話が飛んでいることや説明不足に気づかないことがあります。
第三者の視点を取り入れることで、面接官が疑問に感じるであろうポイントを客観的に洗い出すことができます。
例えば、「なぜその活動を選んだの?」「その時、他に選択肢はなかったの?」といった、自分では当たり前だと思っていた部分が、実は説明不足だったと気づくことができるでしょう。
質問された内容に対して、その場で即座に回答する練習を繰り返すことで、本番でどのような深掘り質問が来ても冷静に対応できる力が身につきます。
フィードバックをもとに、さらに深く自分の考えを掘り下げておくことで、本番での回答に厚みを持たせることができます。
ESを詳細に書きすぎない
ガクチカのESを作成する際、ついついエピソードの詳細を詰め込みたくなりますが、実はこれが深掘り質問への対応力を下げる原因になることがあります。
ESは、あくまで面接の導入であり、面接官があなたに興味を持ち、「もっと話を聞きたい」と思わせるための入口だと考えましょう。
ESには、「何を目標に、何をして、どんな結果を得たか」という大まかな流れと、その成果や得られた学びを簡潔にまとめましょう。
詳細なプロセスや具体的な行動は、面接で話す内容として残しておきましょう。
例えば、「チーム内の意見対立を解決するために、個別に意見を聞きまとめた」といった具体的な行動をESに書かず、「チームの円滑な活動のためにサポートを行った」とだけ記載することで、面接官は「具体的にどうやって?」という深掘り質問をしたくなります。
面接官の興味を引くような余白を残すことで、質問を誘導し、自分が最も伝えたい部分に焦点を当てて話せるようになります。
ガクチカを構成する要素を分解しておく
ガクチカのエピソードは、複数の要素から成り立っています。
この要素を一つひとつ分解して整理することが、深掘り質問への対応力を高める上で非常に重要です。
具体的には、「動機=なぜその活動を始めたか」「目標=何を達成しようとしたか」「行動=目標達成のために何をしたか」「結果=どのような成果を得たか」「学び=経験から何を得たか」「汎用性=その学びを仕事でどう活かしたいか」といった要素に分けます。
例えば、「なぜその活動を選んだのですか?」と聞かれたら「動機」の部分を、「具体的にどんな行動を?」と聞かれたら「行動」の部分を答える、というように、質問に合わせて対応する要素を瞬時に引き出せるようにしておくのです。
要素ごとにエピソードを整理しておけば、どのような角度から質問されても、軸がぶれずに説得力のある回答ができます。
面接で話すガクチカに自信がないときの対処法
「自分には誇れるようなすごいガクチカがない…」と悩んでいる就活生は少なくありません。
しかし、アルバイトやサークル、ボランティアなど、誰もが経験するような日常的な出来事でも、そこから得られた学びや考え方を深く掘り下げることができれば、立派なガクチカになります。
ここでは、ガクチカにどうしても自信が持てない時の対処法を紹介します。
エピソードの「深み」を掘り下げる
ガクチカに自信がないと感じている人は、まずは自分のエピソードの「深み」を徹底的に掘り下げてみましょう。
例えば、アルバイトの経験を話す際、「接客を頑張ってお客様に喜んでもらいました」だけで終わらせていませんか?大切なのは、その「喜んでもらう」ために、あなたが具体的にどのような工夫をしたか、どのような困難に直面し、それをどう乗り越えたかです。
「お客様の表情を観察し、ニーズを先回りして提案するように心がけた」「クレーム対応で失敗したが、その経験から謝罪の仕方だけでなく、根本的な原因を探る姿勢を学んだ」といったように、成功の裏側にある苦労や失敗、そこからの学びを語ることで、エピソードに深みが生まれます。
失敗談は、あなたの自己分析力や成長意欲をアピールする絶好のチャンスです。
複数のガクチカを用意する
面接では、ガクチカ一つに絞って話すことが多いですが、「他に力を入れたことはありますか?」「学業について聞かせてもらえますか?」といった質問をされるケースも珍しくありません。
一つのエピソードに依存するのではなく、複数のガクチカを用意しておくことが、面接を有利に進めるための賢い戦略です。
特に、自分のアピールしたい部分を裏付けるガクチカと、一つ目のガクチカとは違った能力をアピールするガクチカを最低でも二つは用意しましょう。
こうすることで、面接官の反応によってどちらを話すのか選択でき、面接官にあなたの多面的な魅力を伝えることができます。
自分の言葉で「伝える練習」をする
どんなに素晴らしいガクチカがあっても、それを自分の言葉で自信を持って伝えられなければ、面接官にあなたの魅力は伝わりません。
特に、ESに書いた内容が浅いと感じている人ほど、言葉で伝える練習が重要になります。
面接官は、あなたの話す内容だけでなく、その話し方や表情、声のトーンからも熱意や人柄を感じ取ろうとしています。
丸暗記した言葉ではなく、自分の感情や考えを、自分の言葉で話すことで、熱意や人間性が面接官にダイレクトに伝わります。
家族や友人に聞いてもらうだけでなく、スマートフォンなどで自分の話し方を録音・録画してみるのも効果的です。
自信のなさが滲み出てしまうと、せっかくの魅力が半減してしまいます。
何度も練習を重ねて、自信をもって話せるようになりましょう。
面接のガクチカ質問最新トレンド
就職活動の面接で聞かれる質問は、時代と共に変化しています。
これまでのガクチカ質問に加えて、近年では社会情勢やテクノロジーの進化を背景とした、新しい切り口の質問が増加傾向にあります。
特に、AIの活用やサステナビリティへの関心、オンライン環境での働き方といったテーマは、現代のビジネスシーンと密接に関わっており、学生の皆さんの意識や適応力を測る上で重要な指標となっています。
これらのトレンド質問への準備が、他の就活生との差別化につながることは間違いありません。
現代社会に対する感度の高さや、未来志向の視点を持っていることをアピールする絶好の機会と捉えましょう。
ここでは、特に注目すべき最新トレンドの質問を4つのカテゴリーに分けて解説します。
自分の経験とこれらのテーマを結びつけ、自分なりの考えを語れるように準備しておきましょう。
AIツール活用に関する質問
- ChatGPTなどのAIを学習や活動で使いましたか?
- AIが普及する中で、あなたの強みはどう活かせますか?
面接官の意図は、あなたが新しいテクノロジーに対してどのようなスタンスで、どの程度使いこなせるのか、そしてAIには代替できない人間ならではの価値をどう考えているのかを知ることにあります。
単に「レポート作成で使いました」と答えるだけでなく、AIをどのように活用して、学習や活動の質を向上させたのかという具体的なプロセスを語ることが重要です。
例えば、「情報収集の効率化にAIを活用し、生まれた時間でより深い考察や議論に時間を割くことができました」といった回答は、主体的な活用姿勢を示せます。
さらに、AI時代における自分の強みについては、創造性や課題発見能力、他者との共感力といった、AIにはない人間的なスキルと結びつけて説明することで、あなたの付加価値を効果的にアピールできるでしょう。
サステナビリティ・社会課題への関心に関する質問
- SDGsや環境問題について、学生時代に取り組んだことはありますか?
- 社会課題解決のために何かアクションを起こした経験は?
企業の社会的責任(CSR)への意識の高まりを背景に増えています。
面接官は、あなたが自社の利益だけでなく、より広い視野で社会全体への貢献を考えられる人材かどうかを見ています。
ボランティア活動のような直接的な経験がなくても、問題ありません。
重要なのは、社会で起きている課題に対して自分なりの問題意識を持ち、それについて学んだり考えたりした経験を語ることです。
例えば、「ゼミでフードロス問題について学び、日常生活で食品を無駄にしない工夫を始めました」といった身近なアクションでも、あなたの関心の高さを示すことができます。
企業のサステナビリティに関する取り組みを事前に調べ、それと自分の考えを結びつけて話すことができれば、企業理念への深い共感を伝えることができ、高く評価されるでしょう。
オンライン環境での取り組みに関する質問
- リモート環境でのチームワークで工夫したことは?
- オンライン学習で自己管理をどう行いましたか?
この質問で問われているのは、物理的に離れた環境でも円滑にコミュニケーションを取り、自律的にタスクを進めることができるか、その適応力です。
チームワークに関する質問では、「テキストコミュニケーションでは意図が伝わりにくいと考え、定期的なオンラインミーティングでの対話を心がけました」など、オンライン特有の課題を認識し、それを乗り越えるために主体的に工夫した点を具体的に話しましょう。
自己管理については、「誰かの目がない環境だからこそ、1日のタスクを細分化し、ポモドーロテクニックを使って集中力を維持していました」のように、自分なりのルールやメソッドを確立して学習効率を高めた経験を語ることで、あなたの自律性や計画性を強くアピールできます。
Z世代特有の価値観や働き方に関する深掘り
- ワークライフバランスをどう考えていますか?
- あなたの世代特有の価値観を教えてください
多様な価値観を持つ人材を組織に活かしたいという企業の意図の表れです。
面接官は、あなたが自分の価値観を客観的に理解し、それを組織の中でどのように発揮していきたいと考えているのかを知りたがっています。
ワークライフバランスについては、単に「プライベートを重視したい」と答えるのではなく、「仕事の生産性を高めて限られた時間で成果を出し、プライベートも充実させることで、相乗効果を生み出したい」といった前向きな姿勢を示すことが大切です。
また、Z世代の価値観を問われた際は、「SNSなどを通じて多様な価値観に触れる機会が多く、個性を尊重する文化があると感じます」のように、自分の世代を客観的に分析し、その特性が企業にどのような新しい視点やメリットをもたらせるのかを接続して語ることで、あなたの俯瞰的な視点や貢献意欲を伝えることができるでしょう。
面接でガクチカを話す際の構成方法
面接で話すガクチカは、以下の順番で構成しましょう。
- 1. ガクチカが何か伝える
- 2. 目標と課題を伝える
- 3. 課題解決の工夫と結果を伝える
- 4. 学びと活かし方を伝える
面接ではわかりやすくかつ、簡潔に伝えることが重要です。
そのため、本章で解説する内容を意識することで、面接官にガクチカが伝わりやすくなります。
「ガクチカを魅力的に伝えたい」「ガクチカの構成を知りたい」などと考えている就活生は、ぜひ参考にしてください。
1. ガクチカが何か伝える
まずは、あなたのガクチカが何か伝えることから始めてください。
結論ファーストで話すことで、面接官の頭に内容が入ってきやすくなるからです。
たとえば「私は、学生時代にボランティア活動に力を入れました」のように伝えてください。
冒頭に結論を持ってくることで、面接官は「今からボランティア活動の経験を話すつもりなのか」と構えることが可能です。
もし、いきなりエピソードから始めると、面接官は何が言いたいのか混乱する可能性があります。
そのため、ガクチカの最初は、自分の主張から展開するようにしましょう。
面接での回答には、わかりやすさと簡潔さが求められます。
とくに集団面接では、1人あたりの回答時間が限られるため注意してください。
2. 目標と課題を伝える
次に目標と課題を伝えてください。
結論に加えて、学生時代の取り組む様子が鮮明になり、ガクチカに具体性が生まれるからです。
目標や課題は、チームや個人のどちらでも問題ありません。
目標であれば「全国大会出場を目標にしました」のように伝えましょう。
さらに、課題なら「メンバー同士のコミュニケーション不足が課題として残っていました」と説明してください。
目標と課題をセットで伝えることで、現状を適切に理解しつつ、目標に向かって積極的に行動できる人物だとアピールできます。
冒頭の結論で述べた内容に奥行きが生まれ、面接官が当時の様子を想像しやすくなるでしょう。
3. 課題解決の工夫と結果を伝える
さらに、課題解決の工夫と結果も忘れずに伝えてください。
面接官は、目標や課題に対して、どのように乗り越えたのかに興味があるからです。
コミュニケーション不足を解決するにあたって、練習終わりにミーティングを開催した経験があれば、面接官に伝えましょう。
ほかにも「メンバーの話を最後まで聞くように努めました」なども効果的です。
そして、ミーティングを設けた結果、チームがどのように変化したのかも伝えましょう。
試合に勝てるようになったのか、目標達成に貢献したのかなどです。
目標と課題のみを伝えるだけでは、面接官に中途半端な印象を与えます。
もし、結果がない場合、追加で質問されることが予想されるため、あらかじめ課題解決の工夫と結果はセットにしましょう。
4. 学びと活かし方を伝える
最後は、ガクチカから得た学びと仕事への活かし方を伝えてください。
面接官は、あなたを採用した場合、自社にどのように貢献してくれるのかチェックしているからです。
面接官はあなたの学生時代を通じて、仕事に活かせる強みやスキルがないか確かめています。
そこで、ガクチカから得た学びを伝えることで、面接官に採用する価値を提示することが可能です。
たとえば、コミュニケーションを学んだ人なら営業職でスキルを発揮できるでしょう。
ほかにも、リーダーシップを身につけた人は、将来のリーダー候補として採用されるかもしれません。
ガクチカの最後には、入社後の姿や将来を期待させる内容を盛り込みましょう。
【ガクチカ】面接で緊張を和らげる2つの方法
本章では緊張を和らげる対策は以下の2つです。
緊張を和らげる対策
- 面接の流れを把握しておく
- 事前準備は万全に
面接は、人生の中でも非常に緊張する瞬間です。
対策せずに参加すると、後悔の残る結果になるでしょう。
緊張は、自分次第で大きく変えられる項目の1つです。
自分の魅力を適切に伝えるためにも、本章の解説を参考にしてください。
面接では自分のすべてを出し切れるように、今から準備しておきましょう。
面接の流れを把握しておく
まずは、面接の流れを把握しましょう。
全体像を把握することで、不明点をなくせるからです。
もし、面接の流れを知らないまま参加すると、次の流れが心配になり、質問を聞く余裕がなくなります。
その結果、内容がうまく理解できず、曖昧な回答になるでしょう。
もちろん緊張感は、悪い意味ばかりではありません。
適度な緊張は、集中力を生みます。
また、緊張は面接を良いものにしたい、と考えている証拠とも言えるでしょう。
面接での緊張とうまく付き合っていくためには、全体の流れを把握することが重要です。
面接の質問内容は、企業によって異なります。
しかし、流れはどの企業でもパターン化されています。
キャリアセンターや就活エージェントと模擬面接し、流れを把握しておきましょう。
事前準備は万全に
面接は事前準備を万全にしておきましょう。
面接直前は、緊張が原因で準備する余裕がないためです。
たとえば、想定質問の回答作成や持ち物の準備が挙げられます。
さらに余裕があれば、面接会場の行き方や当日の天気を調べておきましょう。
もちろん当日の朝に準備することも可能です。
しかし、面接は非日常のイベントになります。
普段とは違う状況になるため、予想しないトラブルが発生するかもしれません。
もし、ミスが発覚すると、パニックになるでしょう。
落ち着いた状態で面接に参加するためにも、事前準備は万全にしておくことをおすすめします。
面接のガクチカでよくある質問
続いて、就活生の方からよくいただく、面接でガクチカについて聞かれた場合に備えた対策方法などに関する質問に回答します。
これらの質問は就活生の方からよくいただくため、この記事を読んでくれているあなたも気になる項目なはずです。
ぜひ参考にしてみてください。
話す長さはどのくらいがいいですか?
結論として、1分で話せるようにまとめると、要点を簡潔に伝えられるため、面接官にとっても理解しやすく、好印象を与えることができます。
しかし、深掘りされる可能性がある面接や、エピソードを詳しく説明する必要がある場面では、2〜3分で掘り下げて話せる準備をしておきましょう。
具体的なエピソードを盛り込み、取り組んだ背景や苦労した点、工夫した方法、そして結果や学びを丁寧に説明することで、面接官に伝わりやすくなります。
また、1分バージョンでは「結論」と「成果」を中心に話し、深掘りされた場合に備えて詳細な内容を準備しておきましょう。
「短いバージョン」と「長いバージョン」の両方を用意しておけば安心です。
特に、時間指定が無い場合は長々と話してしまいがちですが、あくまで具体性と要点を意識しつつ、相手の反応を見て柔軟に調整することが求められます。
逆質問は考えていくべきですか?
逆質問は絶対に考えていきましょう。
「特にありません」などと答えてしまうと、面接官に「弊社に対する興味が薄いのではないか」や「やる気がないのではないか」といった印象を与えてしまいます。
また、企業に対する理解を深め、自分に合っているかを確認するためにも、事前に逆質問を準備しておくことは必須です。
例えば「御社の中で特に重視されている価値観について教えていただけますか」や「入社後、最初の1年間で期待される役割はどのようなものでしょうか」といった質問は、企業理解を深めるだけでなく、自身の意欲をアピールする機会となります。
また、逆質問を通じて自分の成長意欲やキャリアビジョンを伝えることもできるため、企業側にも積極性を印象づけることが可能です。
余裕があれば企業の公式サイトやインタビュー記事、求人情報について調べ、それらに関する質問をすると「この人はしっかり調べて来ているな」という印象を与えられます。
面接でガクチカの深掘りはどのようなことを聞かれますか?
面接でガクチカの深掘りが行われる際には、取り組みの背景や目的、課題の克服方法など、具体的な点について詳しく尋ねられることが多いです。
面接官はあなたがなぜその活動を選び、どのような目標を設定して取り組んだのか、そしてその過程で直面した課題について知りたいと思っています。
例えば「その活動を始めたきっかけは何ですか?」や「どのような問題が発生し、それをどう解決したのですか?」などと聞かれるでしょう。
また、ガクチカの経験を別の場面で活かせるかについての質問も多く「その経験をどのように今後の仕事に活かしたいですか?」などと聞かれることもあります。
企業はこうした質問を通じて、応募者の問題解決能力や行動力、そして結果を出せるかを確認しています。
聞かれやすい深掘り質問について、全てスラスラと回答できるようになっておきましょう。
面接の時間はどれくらいですか?
面接の時間は一般的に30分から1時間程度です。
特にガクチカが重要視されるのは一次面接で、30分から1時間の中で今までの職務経験やスキル、基本的な適性などが確認されます。
質問に答えるときは何秒くらいで答えればいいの?
質問に対して何秒で答えればいいのかわからないといった時間に関する疑問も持つでしょう。
まず、自己紹介や自己PRなどの簡単な質問の場合は30秒から1分を目安にするといいでしょう。
答えるときは要点を絞って話しましょう。
具体的なエピソードを聞かれたときには1分から1分30秒が理想です。
ここでは話が長くならないように、背景→行動→結果の順にまとめると面接官に伝わりやすくなります。
【面接のガクチカ】まとめ

ガクチカを書く際には、
- 結論から記入する(何を頑張ったのか)
- どうして頑張ることができたのか(行動の背景)
- どういった取り組みをしたのか(具体的な行動)
- 最終的にどうなったのか(結果と感想)
上記のポイントを意識しながら書いてみてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート


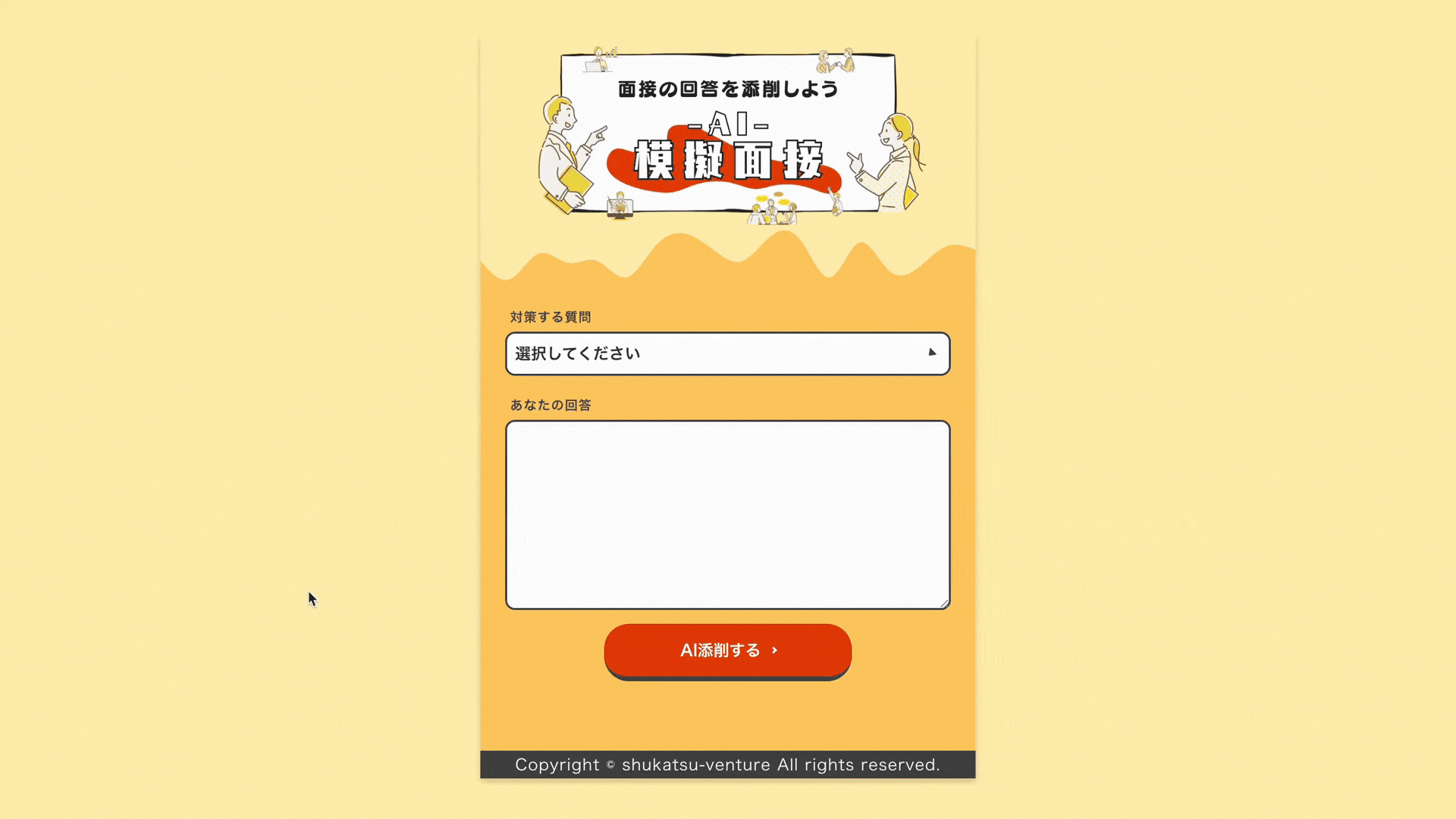
_720x480.webp)









