目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
大手企業の就職偏差値ランキング
就職活動を進める上で、大手企業の就職偏差値ランキングは、自分の実力と志望企業の難易度を測るための重要な指標の一つとなります。
このランキングは、企業のブランド力、採用の倍率、求められる学生のレベルなどを総合的に判断して算出されるため、高い偏差値の企業ほど、選考の難易度が高く、優秀な学生からの人気が集中していることを示します。
このセクションでは、SSランクからDランクまでの大手企業の偏差値帯別に、どのような特徴があるのかを具体的に解説していきます。
自分の目指す企業がどのランクに位置するのかを把握し、適切な選考対策を立てるための具体的な目標設定に役立ててください。
ただし、偏差値はあくまで目安であり、企業や採用年度によって難易度は変動する可能性があるため、一つの情報として参考にする姿勢が大切です。
【大手企業】SSランク(就職偏差値78以上)
- 全国的に倍率が極めて高く、難関選考を突破する総合力が必要
- 学歴・適性・語学・ケース面接など複数の評価軸がある
- 待遇・ブランド・社会的影響力が圧倒的に高い
- 早期選考・ジョブ型採用が多く、準備期間も長い
【80】三菱商事 / 三井物産 / 伊藤忠商事
【79】トヨタ(本社部門)/ 三菱UFJ銀行(総合職)
【78】キーエンス / 野村證券(法人営業)/ 大手外資メーカー
SSランクは難易度・ブランド・待遇の全てがトップクラスで、選考の厳しさは国内最高峰のレベルである。
総合商社・外資メーカー・大手金融などが中心で、多様な能力が求められる。
ES対策・時事理解・英語力・ガクチカ深掘りなど準備項目が多い。
高い成長環境でキャリア価値を最大化したい学生から強い人気を集める。
【大手企業】Sランク(就職偏差値73〜77)
大手企業の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、大手企業の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ大手企業の就職偏差値をチェックしましょう!
- 全国的大手で採用人数は多いが、倍率は依然として高い
- 専門職・総合職ともに評価基準が厳しく、一定のアピール力が必要
- 研修・福利厚生・給与水準が高くキャリアの安定性も高い
- 選考はオーソドックスだが完成度の高い志望動機が求められる
【77】NTTデータ(総合職)/ ソニー / パナソニック
【75】味の素 / 資生堂 / サントリー
【73】JR東日本 / KDDI / 大手鉄道会社
Sランクは業界大手が中心で、配属先の幅や教育体制が整っており新卒人気が非常に高い。
専門性よりも総合的なバランスが重視される企業が多い。
選考は標準的だが、志望理由の明確さと職種理解が評価の分岐点になる。
安定性とキャリアを両立したい学生が多く目指す層である。
【大手企業】Aランク(就職偏差値68〜72)
- 業界上位の大手企業で、採用基準はやや高いが狙いやすい
- 企業規模が大きく、配属部署が多いためマッチングの幅が広い
- 給与・福利厚生は十分高く、働きやすさも担保されている
- 選考は複数回の面接が中心で、ロジックと実績を問われる
【72】富士通 / 日立製作所 / NEC
【70】オリンパス / キヤノン / リコー
【68】京王電鉄 / 東京ガス / 大手食品メーカー
Aランクは業界大手として安定性と待遇がバランス良く揃い、就活生にとって現実的な目標となる層である。
技術系・事務系ともに採用枠が広く、適性が合えば内定が狙える。
ただし人気は高く、企業研究の深さが結果を左右する。
堅実なキャリアを積みたい学生に向いている。
【大手企業】Bランク(就職偏差値63〜67)
- 準大手・業界2番手〜3番手で待遇と働きやすさのバランスが良い
- 選考難易度はやや下がるが、業界知識や志望理由は重視される
- 幅広い業界で多数の採用があり、選択肢が豊富
- 中長期的に安定したキャリアを築きやすい
【67】大和ハウス・積水ハウス(営業職)
【65】森永乳業 / 明治 / ロッテ
【63】CTC / YKK AP / SUBARU
Bランクは準大手として安定性も高く、多くの就活生が最初に内定を得やすいゾーンである。
企業理解と経験の言語化ができれば十分勝負できる。
面接は穏やかだが、ロジックと再現性のあるガクチカが求められる。
待遇・成長・安定のバランス重視の学生に人気がある。
【大手企業】Cランク(就職偏差値58〜62)
- 大手グループ会社・準大手の事務系職種が多い
- 選考難易度は中程度で、企業理解がしっかりしていれば突破可能
- 安定志向の学生にとって狙いやすいポジション
- 教育体制は整っており、新卒でも安心して働ける
【62】山崎製パン / ライオン / アスクル
【60】バンダイナムコ / コナミ / タカラトミー
【58】富士フイルムBI / 関連グループ企業
Cランクは大手グループを中心とした安定層で、就活全体の中では比較的挑戦しやすい領域である。
人気企業も含まれるが、尖った評価基準は少ない。
面接対策と企業理解ができていれば十分戦えるボリュームゾーンである。
堅実に内定を得たい学生に適している。
【大手企業】Dランク(就職偏差値50〜57)
- 大手グループの地域企業・サポート職が中心
- 選考プロセスは穏やかで、人物重視の傾向が強い
- 負荷の少ない働き方やワークライフバランスを重視できる
- 正社員として安定して働けるが、昇進スピードは穏やか
【57】大手メーカーの地域採用枠
【54】大手小売チェーンの本部事務職
【50】大手グループ会社のサポート職
Dランクは大手グループの働きやすい職場が中心で、人物重視で採用される点が特徴である。
専門性が高くないため未経験でも挑戦しやすい。
大手系列の安心感がありつつもプレッシャーは少ない。
安定を重視しながら無理なく働きたい学生に向いている。
大手企業の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
大手企業の就職偏差値ランキングを分析すると、特定の業界が全体的に高い偏差値を示す傾向にあることがわかります。
これは、業界構造、企業の事業内容、そして学生からの人気度が深く関係しているからです。
業界ごとの傾向を理解することで、自分が本当に目指すべき分野の難易度を具体的に把握でき、効率的な対策を練ることができます。
例えば、総合商社やメガバンクといった伝統的な人気業界は高い偏差値帯に集中する一方で、近年急速に成長しているIT・Web業界も、特定の技術職や企画職では難易度が急上昇しています。
このセクションでは、主要な業界別にどのような傾向が見られるのかを詳しく解説し、あなたの業界研究の一助とします。
総合商社・外資系企業は最難関のSSランクに集中
大手企業の就職偏差値ランキングにおいて、総合商社や外資系コンサルティングファーム、外資系メーカーなどは、一貫してSSランクやSランクといった最上位層に位置しています。
これは、これらの企業が提供する圧倒的な高待遇と、グローバルな舞台で活躍できるキャリアパスに、非常に優秀な学生からの応募が殺到するためです。
採用倍率は極めて高く、選考では論理的思考力や語学力、そして地頭の良さなど、総合的な能力が厳しく問われます。
例えば、総合商社では海外駐在の機会や、ダイナミックな事業投資に関わるチャンスが多く、ハイレベルな環境で自身の市場価値を高めたいと考える学生にとって、最大の目標の一つとなっています。
対策としては、ケース面接への準備や、ボランティアや留学経験など、具体的な実績に基づいた自己PRの深掘りが不可欠です。
金融・インフラ業界は安定志向でS〜Aランクが中心
金融業界、特にメガバンクや大手証券会社、そしてインフラ業界のJR各社や電力・ガス会社などは、SランクからAランクに位置することが多く、安定性と待遇のバランスの良さから依然として高い人気を誇っています。
これらの業界は、社会の基盤を支える公共性の高い事業が多く、倒産リスクが低いという安心感があります。
採用人数が比較的多いことも特徴ですが、倍率は高水準を維持しています。
特に総合職採用では、高い倫理観や責任感、そしてチームで働く協調性が重視される傾向にあります。
選考では、ESや面接を通じて、「なぜその企業でなければならないのか」という強固な志望動機と企業への深い理解が求められます。
安定したキャリアを築きたい学生は、これらの業界を志望することが多く、業界研究とOB・OG訪問を通じたリアルな情報収集が内定への鍵となります。
大手メーカーは技術系と事務系で偏差値帯に幅がある
大手メーカーは、家電、自動車、化学、食品など業界が多岐にわたり、偏差値帯にも幅が見られます。
Sランクに位置するグローバルなトップメーカーもあれば、B〜Cランクに位置する準大手メーカーもあります。
ここで特筆すべきは、同じ企業内でも職種によって難易度が異なる傾向があることです。
研究開発職や技術職は、特定の専門知識や理系の高い学歴が求められるため、事務職と比較して採用難易度が上がるケースがあります。
一方で、事務系総合職は、文系学生からの人気が高く、応募者数が多いため倍率が上がりやすい傾向があります。
メーカーを志望する場合、まずは自分が持つ専門性と企業の事業内容とのマッチングをしっかりと見極めることが重要です。
技術の進歩が早い分野では、最新の業界動向を追う姿勢や、大学での研究内容を具体的に説明できる準備が、高評価につながります。
大手企業の就職偏差値が「高い」理由
大手企業の就職偏差値が総じて高くなるのには、明確な理由があります。
単に「有名だから」というだけではなく、その裏には企業が提供する経済的な魅力、キャリアの可能性、そして社会的信用など、複合的な要因が絡み合っています。
就活生がなぜこれらの企業に集まるのかを理解することは、あなたが自身の就職活動の軸を定める上でも非常に重要です。
高い偏差値の裏付けとなっている要素を知ることで、「なんとなく大手」ではなく「なぜこの大手なのか」という明確な理由を見つけられるようになります。
このセクションでは、大手企業の就職偏差値が高い主な理由を掘り下げ、難関企業への挑戦を志す上でのインサイトを提供します。
給与水準・福利厚生が充実しているため
大手企業の就職偏差値が高い最大の理由の一つは、その圧倒的に高い給与水準と手厚い福利厚生にあります。
特にSSランクやSランクの企業では、初任給が高く設定されているだけでなく、その後の昇給ペースも速い傾向にあり、安定した経済基盤を築きたいと考える学生にとって非常に魅力的です。
さらに、住宅手当、社員食堂、育児・介護休業制度の充実など、社員の生活をサポートする福利厚生が整備されており、中長期的なキャリア形成における安心感を提供しています。
たとえば、財形貯蓄制度や企業型DC(確定拠出年金)といった制度が整っていることも多く、学生はこれらの待遇を総合的に判断し、競争率の高い大手企業へと集まるのです。
企業のネームバリューが高く、社会的信用が高い
大手企業は、そのネームバリューの高さからくる社会的信用が非常に高い点も、偏差値が高くなる要因です。
企業名を聞いただけで、その事業内容や業界での地位がイメージできるほどのブランド力は、就職活動における優位性だけでなく、その後の人生においても多くのメリットをもたらします。
例えば、クレジットカードや住宅ローンの審査、賃貸契約など、社会生活の様々な場面でその信用力が影響することがあります。
また、大手企業で働くという事実は、自己肯定感や周囲からの評価にも繋がりやすく、学生にとって大きな魅力となります。
この社会的信用は、その企業の社員であることの「付加価値」となり、難易度が高いにも関わらず多くの学生が挑戦する動機付けの一つです。
成長環境と豊富なキャリアパスが約束されているため
高偏差値の大手企業は、充実した研修制度や多様な事業領域を有しているため、学生に高い成長環境と豊富なキャリアパスを約束します。
グローバル展開している企業であれば、若いうちから海外での勤務経験を積むチャンスがあったり、複数の事業部門を経験するジョブローテーション制度が整っていたりします。
これにより、新卒として入社した後も、自身の能力を継続的に高めていけるという期待感があります。
例えば、入社数年で新規事業の立ち上げに携わるチャンスを得られるなど、裁量の大きな仕事に挑戦できる可能性も高いです。
こうした「成長できる場」としての魅力が、特に向上心のある優秀な学生を惹きつけ、結果として選考の難易度を引き上げているのです。
大手企業の高偏差値企業に内定するための対策
高偏差値の企業に内定するためには、ただ漠然と選考に臨むのではなく、戦略的かつ具体的な対策を講じることが不可欠です。
これらの難関企業は、学生に高いレベルの準備と深い自己理解を求めてきます。
一般的な就職活動の対策を超えた、個々の企業に合わせた綿密な計画と実行力が求められるのです。
特にSSランクやSランクの企業では、選考の初期段階から高い倍率となるため、いかに他の学生との差別化を図り、自分の強みを最大限にアピールできるかが鍵となります。
このセクションでは、難関企業の内定を勝ち取るために実践すべき具体的かつ効果的な対策を、項目ごとに詳しく解説していきます。
企業独自の選考形式に対応した徹底的な準備を行う
高偏差値企業の内定を獲得するためには、各企業が採用する独自の選考形式に対する徹底的な準備が最も重要です。
例えば、総合商社や外資系コンサルでは、通常の面接に加えて、論理的思考力や問題解決能力を試す「ケース面接」が課されることが一般的です。
また、IT企業では技術的な知識やコーディングスキルを問う選考が行われることもあります。
これらの選考形式は、付け焼き刃の対策では通用しません。
過去の出題傾向を分析し、模擬演習を繰り返し行うことで、本番で冷静に対応できる能力を養う必要があります。
企業によってはインターンシップが実質的な早期選考の場となっていることも多いため、積極的に参加し、選考の流れや求められる資質を肌で感じ取ることも重要です。
志望動機とキャリアプランの論理的な繋がりを深める
難関企業では、単に「入社したい」という熱意だけでなく、志望動機と自身の長期的なキャリアプランとの論理的な繋がりを深く掘り下げて説明できることが求められます。
「貴社でなければならない理由」と「貴社で成し遂げたいこと」、そしてそれが「自分の経験やスキルとどう結びつくのか」を明確に言語化する必要があります。
採用担当者は、学生がその企業で働くことで、企業側にもどのようなメリットをもたらすのかを具体的に知りたいと考えています。
例えば、「貴社の〇〇というグローバル事業戦略に、私の留学経験で培った異文化間コミュニケーション能力を活かし、△△国市場でのシェア拡大に貢献したい」といった具体的な貢献イメージを示すことができれば、説得力が増します。
大学での活動や学業実績を定量的にアピールする
高偏差値企業の内定を得るためには、エントリーシートや面接において、大学での活動や学業実績を単なる経験談ではなく、定量的な成果をもってアピールすることが非常に有効です。
多くの学生が「頑張りました」と精神論を語る中で、「サークルの参加率を3ヶ月で20%向上させた」「ゼミの研究で学内コンテストにて〇位に入賞した」といった具体的な数字を用いることで、あなたの実行力や課題解決能力が客観的に証明されます。
実績を語る際は、単に結果だけでなく、その過程で直面した困難と、それを乗り越えるためにどのような工夫をしたのかを「STAR(状況-課題-行動-結果)」のフレームワークに沿って説明すると、より論理的で説得力のある自己PRとなります。
OB・OG訪問を徹底し、リアルな企業理解を深める
高偏差値企業の内定者は、ほぼ例外なくOB・OG訪問を徹底し、企業のリアルな情報や社員の価値観を深く理解しています。
企業説明会や採用サイトの情報だけでは得られない、現場の具体的な業務内容、職場の雰囲気、キャリアパスの実態などを直接聞くことで、志望動機や入社後の目標をより具体的に、そして現実に即したものにすることができます。
これは、面接官に対して「入社後のイメージが明確である」という強いメッセージとなり、本気度を示す重要な要素です。
訪問回数を重ね、複数の社員から話を聞くことで、企業文化や事業戦略に対する多角的な視点を持つことができ、これが選考の場での鋭い逆質問や深い洞察につながり、他の学生との差別化に繋がります。
大手企業の就職偏差値に関するよくある質問
就職偏差値は、就職活動における目標設定や企業選定の一つの基準として非常に便利ですが、その解釈や活用方法について、多くの新卒就活生が疑問を持っています。
「偏差値が全てではない」と理解しつつも、実際に選考の場でどれほど影響があるのか、気になる点は多いでしょう。
このセクションでは、大手企業の就職偏差値にまつわる、就活生から特によく寄せられる質問に、「Webライターとして活躍する就活アドバイザー」としての専門的な視点からお答えしていきます。
これらのQ&Aを通じて、就職偏差値という指標を適切に理解し、あなたの就職活動に役立てるための知識を深めてください。
就職偏差値が低い企業=悪い企業ということですか?
結論から言うと、就職偏差値が低い企業が「悪い企業」であるというわけでは全くありません。
就職偏差値は、あくまで「学生からの人気度や採用の難易度」を示す指標であり、企業の優劣や社員の満足度を測るものではないからです。
偏差値が低い企業の中には、BtoB(企業間取引)で高いシェアを誇る優良企業や、地域社会に深く根付いた安定性の高い企業が数多く存在します。
また、ワークライフバランスを重視しているため、あえて採用人数を絞ったり、派手な広報活動を行わなかったりする企業もあります。
重要なのは、偏差値の高低ではなく、その企業の事業内容、社風、そしてあなたのキャリアプランとのマッチング度です。
偏差値に囚われず、自分の価値観に合った企業を見つけるための視野の広さが大切です。
自分の大学のレベルと偏差値の高い企業は関係しますか?
就職偏差値の高い企業ほど、採用大学の傾向として難関大学の学生の割合が高くなる傾向は確かにあります。
これは、偏差値の高い企業が求める論理的思考力や基礎学力、そしてこれまでの活動実績などが、結果として難関大学の学生に多く備わっていることが多いためです。
しかし、近年では、学歴フィルターが以前ほど強固ではなくなってきており、「学歴は一つの評価軸に過ぎない」というのが実態です。
特にSSランクやSランクの企業でも、その選考を突破するためには、出身大学に関わらず、独自の強み、高いコミュニケーション能力、そして企業への熱意を具体的に示すことが必須となります。
大学名で諦めるのではなく、自分の経験をいかに論理的にアピールできるかが、内定を勝ち取るための真の勝負所となります。
志望企業がランキングにない場合はどう判断すれば良いですか?
志望企業が特定の就職偏差値ランキングに記載されていない場合でも、その企業を深く知るための判断材料は他にもたくさんあります。
ランキングはあくまで一部の人気企業を中心としたものであり、すべての企業を網羅しているわけではありません。
判断のポイントとしては、まず「業界内での地位」や「競合他社との比較」を行うことです。
業界地図や四季報などを参考に、売上高、利益率、従業員数などの客観的なデータを分析しましょう。
また、「平均年収」「採用倍率」といった具体的な数値も、難易度を測る一つの目安になります。
企業が公開している採用情報や社員の声、インターンシップの難易度など、複数の情報を総合的に見て、その企業の実力を判断することが重要です。
就職偏差値を参考にするときの注意点はありますか?
就職偏差値を参考にすることは有用ですが、その際に最も注意すべき点は「絶対的な基準として捉えないこと」です。
偏差値は、学生の志望度や人気度といった変動しやすい要素に基づいて算出されており、実際の仕事の「やりがい」や「働きやすさ」を正確に示すものではありません。
高い偏差値の企業に入社したとしても、配属された部署や職種が自分の価値観と合わなければ、充実したキャリアを築くことは困難です。
したがって、偏差値は「企業研究の初期段階での目標設定」や「客観的な難易度の把握」といったあくまで参考情報の一つとして活用し、最終的な企業選びは、企業理念、事業内容、社風、そして社員との相性といったより本質的な要素に基づいて行うべきです。
まとめ
本記事では、新卒就活生が気になる大手企業の就職偏差値ランキングを、SSランクからDランクまで具体的に解説し、なぜこれらの企業が人気を集めるのか、そして難関企業に内定するための具体的な対策までを詳細に掘り下げました。
就職偏差値は、企業の人気度や採用難易度を示す有用な一つの目安ではありますが、あなたのキャリアを決める「全て」ではないことを忘れないでください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

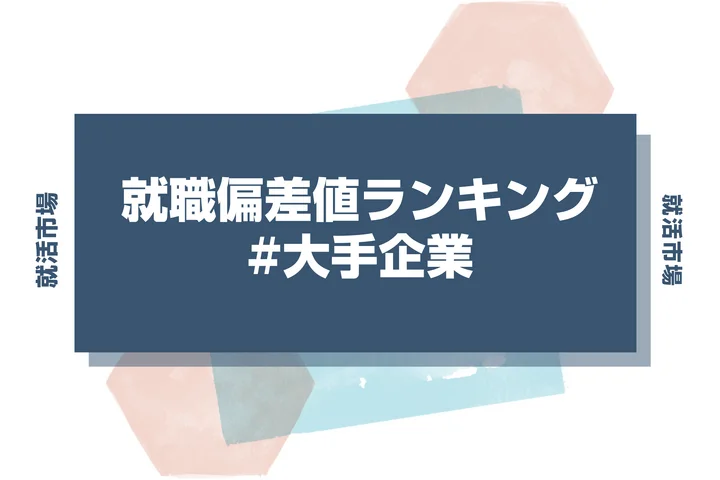




_720x550.webp)




