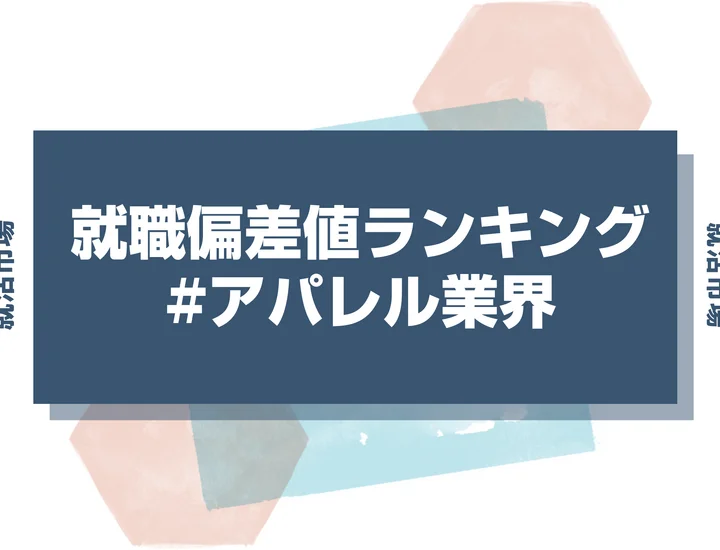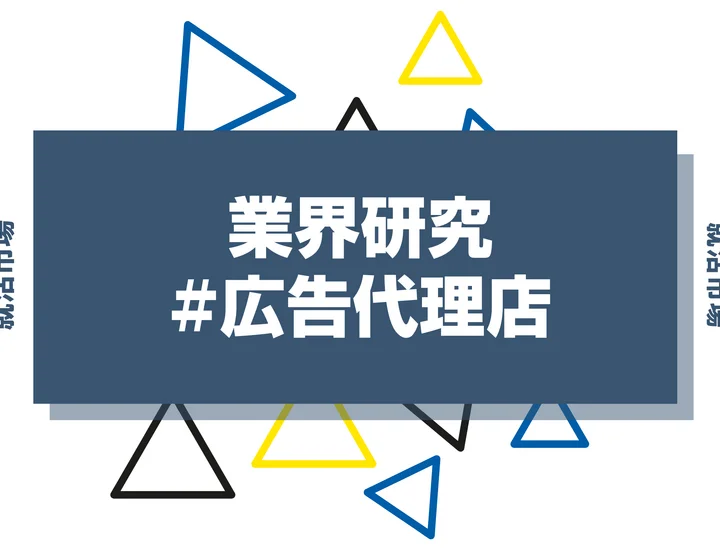企業研究を進める中で、「トヨタ自動車」という名前を聞かない日はないかもしれません。
日本を代表するグローバル企業であり、多くの就活生が憧れる存在ですよね。
しかし、「トヨタって具体的に何をしている会社?」「どんな人が働いているの?」と聞かれると、意外と答えに詰まる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、トヨタがどんな会社なのか、その仕事内容から選考対策まで、就活生の皆さんが知りたい情報を徹底的に解説していきます。
目次[目次を全て表示する]
【トヨタはなんの会社】トヨタはどんな会社なのか
トヨタ自動車(トヨタ)は、単なる「自動車メーカー」という言葉だけでは表しきれない、非常に大きな存在です。
中核となるのはもちろん、乗用車や商用車の開発・生産・販売ですが、その事業領域は多岐にわたります。
近年では、従来の自動車製造に留まらず、「モビリティ・カンパニー」への変革を宣言しています。
これは、自動運転技術やコネクティッドカー、さらには人々が移動するためのあらゆるサービス(MaaS)を提供する企業へと進化していくという強い意志の表れです。
また、住宅事業や金融サービスなども手掛けており、私たちの生活の様々な場面を支えるグローバル企業と言えるでしょう。
【トヨタはなんの会社】トヨタの仕事内容
トヨタと聞くと、工場の生産ラインや車の設計をイメージする人が多いかもしれませんが、実際には非常に多様な職種が存在し、多くのプロフェッショナルが働いています。
「モビリティ・カンパニー」への変革を目指すトヨタでは、従来の枠組みを超えた新しい仕事も次々と生まれています。
例えば、自動運転技術の開発にはAIやソフトウェアの専門家が不可欠ですし、新しいモビリティサービスを企画・推進するためには、マーケティングや事業開発の知識も求められます。
大きく分けると、企画・営業・管理などを担う「事務系」、研究・開発・生産などを担う「技術系」、そして特定の業務を支える「業務職」がありますが、それぞれの分野で高い専門性が求められるのが特徴です。
ここでは、代表的な仕事内容をいくつかピックアップして、具体的にどのような業務を行っているのかを見ていきましょう。
自分の専攻や興味がどの分野で活かせるかを考えながら読み進めてみてください。
事務系総合職(企画・営業・管理部門など)
事務系総合職は、会社の経営戦略立案から日々のオペレーションまで、幅広い領域で活躍する職種です。
例えば、営業・マーケティング部門では、国内外の市場動向を分析し、どのような車を、どの地域で、どのように販売していくかの戦略を立てます。
単に車を売るだけでなく、お客様のニーズを先読みし、新しいカーライフを提案する役割も担います。
また、人事や経理、法務といった管理部門(コーポレート部門)も重要です。
優秀な人材を採用・育成する仕組みを作ったり、グローバルな事業活動を財務面や法的な側面から支えたりと、会社全体の基盤を強固にする役割を果たします。
近年では、新しいモビリティサービスの企画開発や、サステナビリティ(持続可能性)に関する取り組みを推進する部門など、未来のトヨタを創る仕事も増えています。
文系出身者が多く活躍する分野ですが、論理的思考力や高いコミュニケーション能力、そして変化を恐れないチャレンジ精神が求められます。
技術系総合職(研究・開発・生産技術など)
技術系総合職は、トヨタの「モノづくり」の根幹を支える非常に重要な役割を担います。
研究部門では、数年先、数十年先を見据えた最先端技術、例えば全固体電池や人工知能、未来のエネルギー技術などの基礎研究を行います。
開発部門では、その研究成果をもとに、具体的な「クルマ」という形に落とし込みます。
デザイン、設計、実験・評価などを通じて、お客様に感動してもらえるような魅力的で安全な製品を生み出すことがミッションです。
生産技術部門は、開発された車を高品質かつ効率的に量産するための生産ラインや工法を開発します。
トヨタ生産方式(TPS)に代表されるように、常に「カイゼン」を続け、世界最高水準の生産体制を追求する仕事です。
理系の知識が直接活かせる分野であり、自動車工学はもちろん、機械、電気電子、情報工学、化学、物理など、多様なバックグラウンドを持つ人材が結集し、イノベーションを起こし続けています。
CASE領域(コネクティッド・自動運転・シェアリング・電動化)
近年、トヨタが最も力を入れているのが「CASE」と呼ばれる新しい技術領域です。
これは、Connected(コネクティッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング/サービス)、Electric(電動化)の頭文字を取ったもので、自動車業界の「100年に一度の大変革期」を象徴するキーワードです。
この領域では、従来の自動車開発とは異なるスキルセットが求められます。
例えば「コネクティッド」では、車と情報インフラを繋ぎ、新しい価値を生み出すためのソフトウェア開発やデータ分析が中心となります。
「自動運転」では、AIやセンサー技術を駆使し、安全で快適な移動を実現するためのシステム開発が進められています。
これらの分野は、既存の自動車メーカーだけでなく、IT企業なども含めた熾烈な競争が繰り広げられており、トヨタの未来を左右する極めて重要な仕事と言えます。
情報系やAI関連の知識を持つ学生はもちろん、新しいサービスを考えるのが得意な企画系の人材にとっても、非常にチャレンジングで魅力的なフィールドです。
【トヨタはなんの会社】トヨタ選ばれる理由と競合比較
日本国内だけでなく、世界中に数多くの自動車メーカーが存在する中で、なぜトヨタは多くの就活生から選ばれ、そして世界トップクラスの販売台数を維持し続けているのでしょうか。
その理由は、単に「大きな会社だから」「給与や福利厚生が良いから」といった表面的なものだけではありません。
トヨタには、他社にはない独自の強みや、人々を惹きつける企業文化があります。
例えば、世界的に有名な「トヨタ生産方式(TPS)」や「カイゼン」の文化は、高品質なモノづくりを支える哲学として深く根付いています。
また、グローバルに事業を展開しているため、若いうちから世界を舞台に活躍できるチャンスが豊富にあることも大きな魅力でしょう。
ここでは、トヨタが選ばれる理由を深掘りするとともに、国内の主要な競合他社であるホンダや日産とどのような違いがあるのかを比較し、トヨタの独自性を明らかにしていきます。
圧倒的なブランド力とグローバルな事業展開
トヨタが選ばれる最大の理由の一つは、その圧倒的なブランド力とグローバルな事業展開にあります。
「TOYOTA」ブランドは、品質と信頼性の象徴として世界中で認知されており、その販売ネットワークは世界170以上の国と地域に広がっています。
これは、社員にとって「世界中の人々の生活を支えている」という大きな誇りに繋がります。
また、事業規模が大きいということは、それだけ多様な仕事やキャリアパスが存在することを意味します。
例えば、若いうちから海外駐在を経験し、異なる文化や価値観の中でビジネスを推進するチャンスも豊富にあります。
特定の地域や製品だけでなく、地球規模での課題解決、例えば環境問題への対応(ハイブリッド車や燃料電池車など)や、新興国のモビリティ課題に取り組むといった、スケールの大きな仕事に挑戦できる環境は、他の企業ではなかなか得られないトヨタならではの魅力と言えるでしょう。
競合他社(ホンダ・日産)との違い
国内の競合としてよく比較されるのが、ホンダ(本田技研工業)や日産自動車です。
これらの企業も世界的に有名なメーカーですが、トヨタとは異なる特徴を持っています。
例えば、ホンダは創業者である本田宗一郎氏のチャレンジ精神が色濃く残る企業文化で知られ、自動車だけでなく二輪車や航空機(ホンダジェット)など、多角的なモビリティ事業を展開しているのが特徴です。
「技術のホンダ」とも呼ばれ、独創的な技術やデザインを追求する傾向があります。
一方、日産自動車は、フランスのルノーとのアライアンス(企業連合)を組んでいる点が最大の特徴です。
グローバルな連携が深く、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍する環境であり、特に電気自動車(EV)の「リーフ」を早期から市場に投入するなど、先進技術への取り組みも積極的です。
これに対しトヨタは、全方位的なラインナップとトヨタ生産方式に裏打ちされた「品質と信頼性」、そして強固な財務基盤を強みとしています。
どの企業が優れているというわけではなく、それぞれ異なる個性と強みを持っているのです。
「トヨタ生産方式(TPS)」と「カイゼン」の文化
トヨタの強さの根幹にあるのが、「トヨタ生産方式(TPS)」と「カイゼン」の文化です。
TPSは、「ジャスト・イン・タイム」と「自働化(ニンベンのついたジドウカ)」を二本柱とする、ムダを徹底的に排除し、高品質な製品を効率的に生み出すための独自の生産システムです。
これは単なる工場の仕組みではなく、トヨタで働くすべての人に浸透している「考え方」や「哲学」でもあります。
「カイゼン」も同様で、現状に満足せず、常により良い方法を考え、実行し続けるという文化です。
役職や経験に関わらず、誰もが問題点に気づき、改善提案を行うことが奨励されています。
このような文化が、現場の力を最大限に引き出し、困難な状況でも乗り越えていける強靭な組織を創り上げています。
就活生の皆さんにとっては、入社後も常に学び続け、自ら考えて行動することが求められる環境とも言えますが、それこそが自己成長に繋がる最大の魅力だと感じる人も多いでしょう。
【トヨタはなんの会社】トヨタの求める人物像
世界をリードするグローバル企業であるトヨタは、いったいどのような人材を求めているのでしょうか。
多くの就活生が気にするポイントだと思います。
トヨタは「モビリティ・カンパニー」への変革という、まさに「100年に一度の大変革期」の真っ只中にいます。
このような変化の激しい時代においては、単に優秀なだけでなく、変化を楽しみ、自ら未来を切り拓いていける人材が不可欠です。
トヨタが大切にしている価値観や行動指針は、「Toyota Way 2020」として明文化されています。
ここには、「知恵とカイゼン」や「人間性尊重」といった、トヨタが長年培ってきた強さの源泉が示されています。
選考においては、皆さんの経験やスキルだけでなく、この「Toyota Way」にどれだけ共感し、体現できる可能性があるかという点も重視されるでしょう。
ここでは、トヨタが公式に発信している情報や、これまでの採用傾向から読み取れる「求める人物像」を具体的に解説していきます。
「Toyota Way 2020」への共感と実践
トヨタが求める人物像を理解する上で欠かせないのが、「Toyota Way 2020」です。
これはトヨタグループ共通の価値観・行動指針であり、「知恵とカイゼン」と「人間性尊重」という2つの大きな柱で構成されています。
「知恵とカイゼン」とは、常に問題意識を持ち、現状に満足せず、より良い方法を追求し続ける姿勢のことです。
一方、「人間性尊重」とは、仲間やお客様、関わるすべての人々を尊重し、チームワークを大切にしながら仕事を進めることを意味します。
トヨタは、これらの価値観に心から共感し、自らの行動として実践できる人材を求めています。
学生時代の経験、例えばサークル活動やアルバイト、研究などで、困難な課題に対してチームで協力しながら改善に取り組んだ経験や、多様な意見を尊重しながら物事を進めた経験などがあれば、それは大きなアピールポイントになります。
単に「共感します」と言うだけでなく、具体的なエピソードを交えて、自分がどのように「Toyota Way」を体現できるかを語れるように準備しておくことが重要です。
高い当事者意識と「やり抜く力」
トヨタは、若手であっても大きな仕事を任せ、挑戦を促す文化があります。
しかし、それは決して簡単なことではありません。
特にグローバルなビジネスや「CASE」のような最先端領域では、前例のない課題や困難な壁にぶつかることも日常茶飯事です。
そこで求められるのが、高い当事者意識と、最後まで諦めずに「やり抜く力」です。
誰かからの指示を待つのではなく、「これは自分の仕事だ」と捉え、自ら課題を見つけ、解決策を考え、周囲を巻き込みながら行動できる人材が評価されます。
面接では、「学生時代に最も困難だった経験」や「自ら目標を立てて挑戦したこと」などを深掘りされることが多いです。
その際、単に「頑張りました」と結果を述べるだけでなく、どのような困難があり、それをどう乗り越えようと考え、実際に行動したのか、そのプロセスを具体的に説明できるようにしておきましょう。
失敗した経験であっても、そこから何を学び、次どう活かそうとしているかを語れれば、それは立派な「やり抜く力」の証明になります。
チームワークと多様性の尊重
トヨタの仕事は、決して一人で完結するものではありません。
一台の車を世に送り出すためには、研究、開発、生産、営業、管理部門など、社内の非常に多くの部署が連携する必要があります。
さらに、グローバルに事業を展開しているため、国籍や文化、価値観の異なる人々と協力して仕事を進める機会も豊富にあります。
だからこそ、トヨタはチームワークを大切にし、多様性を尊重できる人材を強く求めています。
「人間性尊重」という「Toyota Way」の柱にも通じる部分ですが、自分の意見を主張するだけでなく、相手の意見に耳を傾け、異なる考えを受け入れ、チーム全体として最善の成果を出そうとする姿勢が重要です。
サークル活動やグループワークなどで、異なる立場のメンバーの意見を調整したり、チームの士気を高めるために工夫したりした経験は、トヨタで働く上でも大いに役立つ素養です。
自分とは異なる強みを持つ仲間と協力し、より大きな力を生み出したいと考える人にとって、トヨタは非常にやりがいのある環境と言えるでしょう。
【トヨタはなんの会社】トヨタに向いてる・向いていない人
ここまでトヨタの仕事内容や求める人物像について解説してきましたが、それを踏まえて、自分がトヨタに向いているのか、それとも向いていないのか、気になっている人も多いでしょう。
もちろん、これはあくまで一般的な傾向であり、最終的には皆さん自身の価値観やキャリアプランと照らし合わせて判断することが大切です。
トヨタは、安定した大企業という側面と、変革期にあるチャレンジングな企業という側面の両方を持ち合わせています。
そのため、例えば「大きな目標に向かってチームで協力するのが好き」という人もいれば、「決められたルールの中で着実に仕事を進めたい」という人も、活躍の場は見つかるかもしれません。
しかし、会社全体として求められる基本的なスタンスや企業文化というものは存在します。
自分自身の特性や志向性を深く理解した上で、トヨタという環境が自分にフィットするかどうかを見極めることは、入社後のミスマッチを防ぐためにも非常に重要です。
トヨタに向いている人の特徴
トヨタに向いている人の特徴としてまず挙げられるのは、「カイゼン」の精神に共感し、常に向上心を持って物事に取り組める人です。
現状維持を良しとせず、常により良い方法はないかと自ら考え、行動に移せる人は、トヨタの文化に非常にマッチするでしょう。
また、スケールの大きな仕事にやりがいを感じる人にも向いています。
トヨタの仕事は、日本国内に留まらず、世界中の人々の生活や社会インフラに影響を与えるものがほとんどです。
自分の仕事が社会に与える影響の大きさを実感したい、地球規模の課題解決に貢献したい、という強い想いを持つ人にとっては、これ以上ない環境です。
さらに、チームワークを重視し、多様なバックグラウンドを持つ人々と協力しながら成果を出すことに喜びを感じる人も、トヨタで活躍できる可能性が高いです。
個人の成果だけでなく、チーム全体の成功を第一に考えられる協調性や、異なる意見を尊重できる柔軟性が求められます。
トヨタに向いていない可能性のある人の特徴
一方で、トヨタの環境が合わない可能性のある人の特徴も考えてみましょう。
まず、変化よりも安定を最優先に考える人や、決められた業務をルーティンとしてこなしたいと考える人は、少し窮屈に感じるかもしれません。
トヨタは安定した大企業ではありますが、現在は「モビLEDカンパニー」への変革期であり、社内では常に新しい挑戦や変化が求められています。
「カイゼン」の文化も、裏を返せば常に変化し続けることが求められる環境とも言えます。
また、個人の裁量でスピーディーに物事を進めたいという志向性が強すぎる人も、トヨタの働き方が合わない可能性があります。
トヨタの仕事は、多くの部署や関係者との調整(「根回し」と呼ばれることもあります)を必要とすることが多く、チーム全体の合意形成を重視する文化があります。
個人のアイデアでどんどん突き進むよりも、周囲と協調しながら慎重に物事を進めるプロセスが多いため、そこにストレスを感じる人もいるかもしれません。
【トヨタはなんの会社】トヨタに受かるために必要な準備
日本を代表するグローバル企業であるトヨタは、当然ながら就活生からの人気も非常に高く、選考の倍率も高いことで知られています。
内定を勝ち取るためには、付け焼き刃の対策ではなく、しっかりとした準備が不可欠です。
多くの優秀な学生が応募する中で、人事が「この学生と一緒に働きたい」と感じるためには、何が必要なのでしょうか。
それは、単に学歴やTOEICのスコアが高いことではありません。
もちろん、基礎的な能力は必要ですが、それ以上に「なぜトヨタなのか」という問いに対して、自分自身の言葉で、具体的な根拠を持って答えられることが重要です。
そのためには、徹底的な企業研究と深い自己分析が欠かせません。
トヨタが今どのような課題に直面し、どこへ向かおうとしているのかを理解し、その上で自分自身の強みや経験をどのように活かせるのかを論理的に説明する必要があります。
ここでは、トヨタの選考を突破するために最低限準備しておくべきことを3つのポイントに分けて解説します。
徹底的な企業研究と「なぜトヨタか」の明確化
トヨタの選考において最も重要視されると言っても過言ではないのが、「なぜ他の自動車メーカーではなく、トヨタなのか」という志望動機の明確さです。
トヨタは「モビリティ・カンパニー」への変革を掲げていますが、これはホンダや日産、あるいは海外のメーカーも同様に取り組んでいることです。
その中で、あえてトヨタを志望する理由を、自分自身の経験や価値観と結びつけて具体的に語る必要があります。
そのためには、トヨタの公式ウェブサイトやIR情報、最新のニュースリリースなどを読み込み、トヨタが現在どのような戦略を打ち出し、どのような製品やサービスに力を入れているのかを深く理解することがスタートラインです。
特に「Toyota Way 2020」や、豊田章男会長のメッセージなどには、トヨタの根幹にある価値観が表れています。
競合他社の取り組みとも比較しながら、「トヨタのこういう点に強く共感した」「自分のこの経験はトヨタでこそ活かせる」という、あなただけの「トヨタでなければならない理由」を見つけ出してください。
自己分析と「トヨタで活かせる強み」の言語化
「なぜトヨタか」と同時に、「トヨタであなたは何ができるのか」も非常に重要な問いです。
これに答えるためには、深い自己分析が欠かせません。
まずは、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)や、困難を乗り越えた経験などを棚卸ししましょう。
その際、単に「何をやったか」だけでなく、「なぜそれをやろうと思ったのか(動機)」「どのような課題があり(課題発見)」「どう考えて行動したのか(計画・実行)」「結果どうなり、何を学んだのか(結果・学び)」という一連のプロセスを詳細に書き出してみてください。
そうすることで、あなたの行動特性や強み、価値観が明確になってきます。
次に、その強みが、先ほど解説したトヨタの「求める人物像」(例えば「やり抜く力」や「チームワーク」)とどのように結びつくのかを考えます。
例えば、「サークルの課題をチームで改善した経験」は、「カイゼン」や「チームワーク」の素養を示すエピソードとして使えるかもしれません。
自分の言葉で、具体的に、論理的に自分の強みを説明できるように準備しましょう。
OB・OG訪問やインターンシップへの積極的な参加
企業研究や自己分析を深める上で、非常に有効な手段がOB・OG訪問やインターンシップへの参加です。
ウェブサイトや説明会だけでは得られない、実際に働く社員の「生の声」を聞くことは、トヨタという会社を多角的に理解するために不可欠です。
OB・OG訪問では、仕事の具体的なやりがいや厳しさ、社内の雰囲気、キャリアパスなど、気になることを積極的に質問してみましょう。
そこで得られた情報は、あなたの「なぜトヨタか」を補強する強力な材料になります。
また、トヨタは様々な部門でインターンシップを開催しています。
インターンシップに参加できれば、実際の職場の雰囲気を肌で感じたり、社員と協働して課題に取り組んだりする貴重な経験が得られます。
これは、自分とトヨタとの相性を見極める絶好の機会であると同時に、選考においても「トヨタへの本気度」を示す強いアピールとなります。
積極的に行動し、一次情報を集める努力を惜しまないことが、内定への近道です。
【トヨタはなんの会社】トヨタの志望動機の書き方
トヨタの選考、特にエントリーシート(ES)や面接において、志望動機は合否を分ける最も重要な要素の一つです。
「なぜトヨタなのか」を明確に伝えられなければ、他の学生との差別化は図れません。
多くの学生が「世界トップクラスの企業だから」「安定しているから」といった理由を考えがちですが、それでは人事の心には響きません。
トヨタは今、「モビリティ・カンパニー」への変革という大きな挑戦の最中にあり、その未来を一緒に創っていける仲間を求めています。
したがって、志望動機では、「トヨタの現在の姿」だけでなく、「トヨタが目指す未来」に自分がどう貢献できるのかを示す必要があります。
そのためには、これまでに準備してきた企業研究と自己分析の結果を、論理的かつ情熱的に組み合わせることが求められます。
ここでは、人事に「この学生に会ってみたい」と思わせるような、説得力のある志望動機を作成するためのポイントと、具体的な構成例について解説していきます。
評価される志望動機の3つのポイント
トヨタの選考で評価される志望動機には、大きく分けて3つの重要なポイントがあります。
一つ目は、「なぜ自動車業界か」そして「なぜその中でもトヨタなのか」が明確であることです。
競合他社との比較を踏まえ、トヨタ独自の強みやビジョン(例えば「Toyota Way」への共感や「モビリティ・カンパニー」への変革への魅力など)に惹かれた理由を具体的に述べましょう。
二つ目は、「入社後に何を成し遂げたいか」が具体的であることです。
漠然と「社会に貢献したい」と言うのではなく、「トヨタの○○という技術(あるいは事業)に携わり、こんな未来を実現したい」というように、自分のやりたいこととトヨタの事業を結びつけて語ることが重要です。
三つ目は、その「成し遂げたいこと」を実現できる根拠として、自分自身の強みや経験が示されていることです。
「学生時代の○○の経験で培ったこの力を活かして、このように貢献できる」と、過去の経験と未来への貢献意欲を一貫性を持って説明することで、志望動機の説得力が格段に高まります。
避けるべき志望動機と具体的な構成例
一方で、避けるべき志望動機もあります。
例えば、「給与や福利厚生が良いから」「安定しているから」といった待遇面を前面に出すものや、「車が好きだから」というだけの漠然とした理由は評価されにくいでしょう。
「車が好き」なのは素晴らしいことですが、それはあくまで動機の一つであり、「好きだから、トヨタで何がしたいのか」まで踏み込む必要があります。
また、「学ばせてもらいたい」という受け身の姿勢も望ましくありません。
会社に貢献する意欲を前面に出しましょう。
説得力のある志望動機の構成例としては、まず「(1)結論:私がトヨタを志望する理由は○○です」と明確に述べます。
次に「(2)理由・背景:なぜそう思うようになったのか(原体験や問題意識など)」を説明します。
続いて「(3)なぜトヨタか:他社ではなく、トヨタの○○という点に魅力を感じている」と差別化を図り、最後に「(4)入社後の貢献:私の○○という強みを活かして、トヨタでこのように貢献したい」と締めくくります。
この流れを意識し、あなた自身の言葉で熱意を込めて作成してみてください。
【トヨタはなんの会社】トヨタについてよくある質問
ここまでトヨタの企業研究や選考対策について詳しく解説してきましたが、就活生の皆さんからは、他にも様々な質問をいただきます。
特に、採用に関する具体的な疑問や、入社後の働き方についての不安など、なかなか表に出てこない情報については気になるところですよね。
例えば、「学歴フィルターは実際にあるのか?」「英語力はどれくらい必要なのか?」といった選考に関する質問や、「転勤や海外勤務の頻度は?」といったキャリアに関する質問は、毎年多くの学生から寄せられます。
もちろん、すべての質問に明確な答えがあるわけではありませんが、トヨタが公式に発信している情報や、これまでの採用傾向から読み取れることも多くあります。
ここでは、就活生の皆さんが特に疑問に思いがちな「よくある質問」をいくつかピックアップし、就活アドバイザーとしての視点から、できるだけ具体的にお答えしていきます。
皆さんの不安を少しでも解消できれば幸いです。
Q. 採用大学に学歴フィルターはありますか?
「トヨタほどの企業になると、いわゆる学歴フィルターがあるのではないか」と心配する学生さんは非常に多いです。
結論から言うと、トヨタは公式には「学歴フィルターはない」と明言しており、実際に多様な大学からの採用実績があります。
もちろん、旧帝大や早慶といった難関大学からの採用者が多いのは事実ですが、それは結果としてトヨタが求める高い基準(論理的思考力、やり抜く力、専門性など)を満たした学生の中に、それらの大学の出身者が多かったという側面が強いです。
重要なのは、大学名ではなく、あなたが学生時代に何に取り組み、どのような力を身につけ、それをトヨタでどう活かそうとしているかを、エントリーシートや面接で説得力を持って伝えられるかどうかです。
大学名に臆することなく、自信を持って自分の強みをアピールしてください。
ただし、技術系総合職の場合は、特定の専攻(機械、電気電子、情報など)が求められるケースが多いため、自分の専攻と募集職種がマッチしているかを確認することは重要です。
Q. 英語力はどの程度必要ですか?
トヨタはグローバルに事業を展開しているため、英語力の必要性について気になる人も多いでしょう。
職種や部署によって求められるレベルは異なりますが、一定レベルの英語力はあった方が間違いなく有利です。
特に事務系総合職で海外営業や調達、グローバルな企画部門などを目指す場合や、技術系総合職で海外の拠点やサプライヤーとやり取りする場合には、ビジネスレベルの英語力が求められます。
エントリーシートの段階でTOEICのスコア提出を求められることも多く、一つの目安として一般的には700点以上、できれば800点以上あるとアピールしやすいでしょう。
ただし、スコアが全てではありません。
大切なのは、英語を「ツール」として使い、異なる文化を持つ人々と臆せずコミュニケーションを取ろうとする姿勢です。
現時点でスコアが低くても、入社後も継続的に学習する意欲を示すことができれば、ポテンシャルとして評価される可能性もあります。
まとめ
今回は、「トヨタはなんの会社か」というテーマで、トヨタの事業内容から仕事内容、選考対策までを詳しく解説してきました。
トヨタが単なる自動車メーカーではなく、「モビリティ・カンパニー」への変革を目指すダイナミックな企業であることがお分かりいただけたかと思います。
世界トップクラスの企業でありながら、常に「カイゼン」を続け、変化に挑み続ける姿勢は、働く社員にとっても大きなやりがいと成長の機会を与えてくれるはずです。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート