目次[目次を全て表示する]
【大学3年の就活】大学3年で何もしてないと手遅れ?
「大学3年生にもなったけど、就活らしいこと何もしてないな…」「周りはインターンとか行ってるみたいだけど、もう手遅れなのかな?」そんな風に焦りや不安を感じている大学3年生のあなた。
安心してください、まだ手遅れということは決してありません。
確かに、周囲の動き出しが早いと耳にしたり、就活の情報が溢れてきたりすると、何もしていない自分に危機感を覚えるのは当然のことです。
しかし、大切なのは「いつ始めるか」よりも「これからどう動くか」です。
まずは小さな一歩からで大丈夫。
この記事を読み進めて、何から始めれば良いのか、一緒に確認していきましょう。
【大学3年の就活】最新情報!何もしてない学生の割合は?ライバルは動き出してる?
「自分はまだ何もしていないけど、周りのみんなはどれくらい就活を進めているんだろう?」そう気になっている大学3年生も多いのではないでしょうか。
特に、インターンシップへの参加状況や、内定獲得の時期など、具体的なデータは気になるところですよね。
周囲の状況を知ることは、自分の立ち位置を把握し、今後の就活戦略を立てる上で非常に重要です。
そこで今回、就活市場の長期インターン生42名にアンケートを実施しました。
「何もしてない」学生の割合、ライバルの動き出し状況をデータで直視しましょう。
なにもしてない学生は7人に1人だけ
_800xAuto.webp)
まず「現在の就活状況」です。
「なにもしてない」と答えた学生は14.29%(6人)でした。
約7人に1人と思うと、まだ仲間がいると安心しますか?
しかし、現実は甘くありません。
「インターンシップに参加」が33.33%、「早期選考に参加」が26.19%と、合計で約6割の学生がすでに応募や選考という具体的なアクションを起こしています。
さらに驚くべきことに、「就活を終了」した学生も7.14%(3人)います。
あなたが「まだ大丈夫」と傍観している間にも、ライバルたちは着実に駒を進め、ゴールしている人さえいるのです。
6割以上の学生が早期選考・本選考のいづれかに参加
_800xAuto.webp)
次に「早期選考・本選考への参加社数」を見てみましょう。
「選考に参加していない」学生は35.71%(15人)でした。
まだ3割以上が未参加ですが、逆に言えば、なんと6割以上の学生がすでに何らかの選考を受けている、ということです。
「1~3社」参加が40.48%(17人)と最も多く、まずは動き出している層が厚いことがわかります。
さらに「4~8社」(19.05%)、「9社以上」(4.76%)と、すでに複数の選考を経験している学生も合計で約24%います。
すでに内定を獲得した27卒は4人に1人
_800xAuto.webp)
最後に「内定獲得数」です。
「内定を獲得していない」が76.19%(32人)と大多数を占めており、ここで少し安心したかもしれませんね。
しかし、見方を変えてください。
すでに23.81%、つまり約4人に1人の学生が「内定を1社以上獲得している」という衝撃的な結果が分かります。
【大学3年の就活】何もしてない学生は今すぐ就活を始めよう
「まだ大丈夫だろう」「何から手をつければいいかわからない」と、就職活動への第一歩をためらっている27卒大学3年生の皆さん。
もし、あなたが少しでも就活に対して意識が向いているのなら、結論からお伝えします。
今すぐ動き出すことを強くお勧めします。
なぜなら、早期に準備を始めることで得られるアドバンテージは非常に大きく、それがあなたの就活全体を有利に進めることに繋がるからです。
今すぐ始めるメリット
「就活はまだ先のこと」と考えている大学3年生もいるかもしれませんが、実は「今すぐ」就活の準備を始めることには、計り知れないメリットが隠されています。
大きく分けると具体的なメリットは以下の3つです。
- 就活準備に時間をかけることができる
- すでに募集が締め切られているという事態を防げる
- 早期選考に参加できる
これらのメリットは、それぞれが密接に関連し合い、あなたの就職活動をよりスムーズに、そしてより納得のいくものへと導いてくれるでしょう。
以下では、これらのメリットについて一つひとつ詳しく解説していきますので、ぜひ読み進めて、早期スタートの重要性を実感してください。
就活準備に時間をかけることができる
今すぐ就活を始めると得られる最大のメリットの一つは、何と言っても就活準備に十分な時間をかけることができる点です。
就職活動は、単にエントリーシートを提出して面接を受けるだけではありません。
その前段階には、自分自身を深く理解するための自己分析、世の中にどんな仕事や企業があるのかを知るための業界・企業研究、そして筆記試験対策や面接練習など、やるべきことが山積みです。
もし、就活本番が迫ってから慌ててこれらの準備を始めるとどうなるでしょうか。
時間が足りず、自己分析が浅いままで自分に合わない企業を選んでしまったり、企業研究が不十分で面接で熱意を伝えきれなかったり、といった事態に陥りかねません。
しかし、早期から準備を始めれば、一つひとつのステップにじっくりと時間を費やすことができます。
例えば、自己分析では過去の経験を丁寧に振り返り、自分の強みや価値観を明確にすることができます。
業界・企業研究では、表面的な情報だけでなく、企業の文化や将来性まで深く掘り下げて調べることが可能です。
このように、時間をかけて丁寧に行った準備は、あなたの自信となり、選考での説得力を格段に高めてくれるでしょう。
すでに募集が締め切られているという事態を防げる
「本格的な就活は大学3年生の3月から」というイメージを持っていると危険です。
実は、外資系のコンサルティングファームや金融機関、一部のIT・ベンチャー企業は、大学3年生の夏や秋には選考を開始し、年内に内々定を出してしまうケースも珍しくありません。
気づいた時には「応募したかった企業の募集が終わっていた…」なんてことも。
自分の可能性を狭めないためにも、早期からの情報収集と行動が不可欠なのです。
早期選考に参加できる
就職活動の早期化が進む現代において、企業が通常よりも早い時期に選考を行う「早期選考」の機会が増えています。
この早期選考に参加できることも、今すぐ就活を始める大きなメリットの一つです。
早期選考は、主にインターンシップ参加者や、企業が独自に設けるセミナーの参加者などを対象に行われることが多く、通常の選考ルートとは異なるプロセスで進むこともあります。
早期選考の最大の魅力は、早い段階で内定を獲得できる可能性があることです。
内定を早期に確保できれば、複数の企業から内定を得て、じっくりと比較検討する時間も生まれるだけでなく、精神的な余裕が生まれ、残りの学生生活を学業や自己研鑽、あるいは趣味などに安心して打ち込むことができます。
また、仮にその場ではうまくいかなかったとしても、選考の場数を踏むことで面接慣れができます。
そこで得た経験は、本選考に向けた大きなアドバンテージになりますよ。
挑戦の機会を増やすためにも、今すぐ始めましょう。

サマーインターンや早期選考のメリットが非常に丁寧に整理されていて、読者にとってわかりやすい構成ですね。「早く始めた人が得をする」という事実は確かにありますが、大切なのは「どれだけ早く始めるか」以上に「どれだけ準備を重ねられるか」です。今の時点でまだ動き出せていない方も、今日から情報収集や自己分析を始めれば十分に間に合います。インターンの選考や早期選考に向けて準備を進める過程そのものが、あなたの就活力を確実に高めてくれますので、少しずつでも行動を始めてみましょう。
【大学3年の就活】何もしてない学生必見!月別の就活スケジュール
「就職活動って、いつから何をすればいいの?」多くの大学3年生が抱えるこの疑問。
特に、まだ何も手をつけていないと焦りを感じてしまいますよね。
以下では、大学3年生の1年間が、就職活動においてどのような時期にあたるのか、月別の具体的なスケジュールとやるべきことを分かりやすく紹介します。
一般的な就活の大きな流れを掴むことで、漠然とした不安を解消し、計画的に準備を進めることができます。
もちろん、ここで紹介するのはあくまで一例であり、業界や企業、そして個人の状況によってスケジュールは異なります。
しかし、大まかな目安を知っておくことは、あなたが就活の波に乗り遅れず、納得のいく進路選択をするための大きな助けとなるはずです。
さあ、一緒に1年間の就活の流れを確認し、今からできることを見つけていきましょう。

何もしていない大学3年生が4月から7月にすべきこと
この時期、特に大手企業のサマーインターンの選考は4月から6月がピークを迎えており、まさに「待ったなし」の状況です。
まだ何もしていない状態が続けば、この夏最大のチャンスであるサマーインターンに参加する機会を逃し、後々「あの時やっておけば」と後悔することになりかねません。
しかし、今からでも間に合う行動はあります。
大学3年の4月:情報収集のアンテナを張ろう
新学期がスタートする大学3年の4月は、27卒のインターンシップが公開される時期です。
特に、外資系企業を目指す学生にとっては、この時期から企業の採用情報を積極的に収集する必要があります。
まだ具体的な業界や企業が決まっていなくても、まずは就職情報サイトに登録したり、気になる企業のホームページをチェックしたりして、情報収集のアンテナを高く張っておくことが大切です。
この時期に、少しでも「就職」というキーワードを意識しておくことで、今後の動き出しをスムーズにすることができます。
「まだ早い」と思わずに、まずはどんな企業がどんな情報を発信しているのか、軽い気持ちで眺めてみることから始めてみましょう。
また、大学のキャリアセンターが開催するガイダンスに参加して、基本的な就活の進め方や情報収集の方法を学んでおくのもおすすめです。
大学3年の5月:ES対策の第一歩を踏み出そう
4月に募集が始まった外資系企業や一部のサマーインターンシップで、エントリーシート(ES)の提出が求められ始める時期です。
ESは、企業に自分という人間を理解してもらい、興味を持ってもらうための最初の関門となります。
そのため、自己分析を少しずつ始め、自分の強みや学生時代に力を入れたことなどを整理しておくことが重要になります。
インターンシップのESは、本選考の練習にもなるので、積極的にチャレンジしてみることをおすすめします。
大学3年の6月:サマーインターン戦線本格化!早期内定も?
6月は就職活動においてはサマーインターンシップの募集がピークを迎える、まさに「戦線本格化」のタイミングです。
特に、多くの学生が注目する大手企業のサマーインターンシップの募集がこの時期に集中します。
人気のインターンシップは倍率も高いため、早めの情報収集と準備が欠かせません。
また、企業が複数集まって開催される合同説明会も各地で行われ始め、様々な業界や企業を一度に知る良い機会となります。
そして驚くかもしれませんが、この時期に早くも内定を獲得し始める学生が出始めるのも近年の就活の特徴です。
主に外資系企業や一部のベンチャー企業などでは選考スケジュールが早く、サマーインターンシップを経て早期選考に進み、6月頃に内定が出るケースがあります。
こうした動きを知ると焦るかもしれませんが、周りと比較しすぎず、まずはサマーインターンシップへの応募や合同説明会への参加を通じて、自分に合う企業や仕事を見つけるための行動を続けましょう。
大学3年の7月:夏休みを有意義に!行動と振り返りの月
7月はこれまで行ってきた自己分析や業界研究をさらに深め、実際の行動に移していく大切な期間です。
サマーインターンシップの選考結果が出揃い始め、参加が決まった人はその準備を進めましょう。
残念ながら希望通りにいかなかった人も、落ち込んでいる暇はありません。
なぜ上手くいかなかったのかを振り返り、秋以降のインターンシップや本選考に向けて軌道修正をすることが重要です。
また、この時期は積極的に社会人と話す機会を作るのもおすすめです。
大学のOB・OG訪問はもちろん、キャリアセンターが主催するイベントや、企業の小規模な座談会などに参加してみましょう。
夏休みを目前に控え、計画的に時間を使って、自己分析、業界研究、そして実際の行動と、バランス良く就活準備を進めていきましょう。
何もしていない大学3年生が8月から11月にすべきこと
サマーインターンシップが一区切りつく8月からは、本格的な準備期間へと移行します。
この8月から11月は、就活の基礎を固めつつ、秋冬インターン選考に滑り込むための非常に重要な4ヶ月間です。
サマーインターンの機会を逃した方は特に、この期間に自己分析の精度をさらに高めることと、志望業界の幅を広げることが求められます。
大学3年の8月:インターンシップ本番!経験から学びを深めよう
8月は多くの学生にとってサマーインターンシップへの参加が本格化する時期です。
実際に企業のオフィスに足を運び、社員の方々と一緒に業務の一部を体験したり、グループワークに取り組んだりと、座学だけでは得られない貴重な経験を積むことができます。
インターンシップ中は、ただ参加するだけでなく、積極的に質問したり、周囲とコミュニケーションを取ったりして、多くのことを吸収しようという姿勢が大切です。
インターンシップに参加していない期間も、時間は有効に使いましょう。
引き続き業界研究や企業研究を深掘りしたり、SPIなどの筆記試験対策を進めたりするのも良いでしょう。
また、一部の企業では、この時期から本選考が始まることもあります。
特にIT企業やベンチャー企業などでは、夏に本選考を実施し、早期に内定を出すケースも見られます。
インターンシップで得た気づきや学びを整理し、今後の就職活動にどう活かしていくか考えることが、この時期の重要なポイントとなります。
大学3年の9月:夏を越えて、秋冬インターンへシフトチェンジ
9月はサマーインターンシップの経験を振り返り、そこから得た学びや課題を整理する大切なタイミングといえます。
良かった点、改善すべき点などを明確にし、今後の自己PRや企業選びに活かしていきましょう。
そして、サマーインターンシップで思うような成果が得られなかった人や、さらに多くの企業を見てみたいと考えている人は、秋冬インターンシップに目を向ける時期でもあります。
多くの企業が、秋から冬にかけてもインターンシップを実施しています。
サマーインターンとは異なるプログラム内容であったり、より本選考に近い内容であったりすることもあるため、積極的に情報を集めて応募してみましょう。
夏に得た経験を踏まえて、より目的意識を持って秋冬インターンに参加することで、大きな成長に繋がるはずです。
大学3年の10月:選考と準備、両睨みで進めよう
秋も深まる10月は、就職活動において二つの大きな動きが出てくる時期です。
一つは、外資系企業や一部の国内企業で、本選考が本格的にスタートすること。
エントリーシートの提出や筆記試験、面接などが始まり、内々定が出始める企業も出てきます。
もう一つは、冬期インターンシップの募集が開始されることです。
冬期インターンシップは、年末年始や春休み期間中に実施されることが多く、企業の理解を深める最後のチャンスとなることもあります。
この時期は、一部の学生にとっては選考に臨みながら、同時に次のインターンシップの準備も進めるという、少し忙しい期間になるかもしれません。
選考対策としては、自己分析や企業研究を再度見直し、面接練習などにも力を入れましょう。
冬期インターンシップの情報収集も怠らず、興味のある企業があれば積極的にエントリーしていくことが大切です。
大学3年の11月:情報収集と実践!選考対策を本格化
11月は就職活動においても情報収集と実践的な対策が活発になる時期です。
引き続き、秋冬インターンシップに参加する学生も多いでしょう。
また、早期選考を実施する企業の説明会や、大規模な合同説明会、さらには面接対策やグループディスカッション対策といった選考対策に特化したイベントも数多く開催されます。
この時期は、積極的にこれらのイベントに参加し、多くの情報を得るとともに、実践的なスキルを磨くことが重要です。
企業説明会では、企業の雰囲気や事業内容を直接聞くことで理解を深め、選考対策イベントでは、模擬面接などを通じて自分の課題を発見し、改善に繋げることができます。
また、同じように就職活動に取り組む他の学生と情報交換をすることも、モチベーション維持や新たな気づきを得る上で有益です。
何もしていない大学3年生が12月から3月にすべきこと
12月から3月にかけては、いよいよ本選考に向けた最終準備期間となります。
この時期は、積極的に冬のインターンシップに参加すると並行して、3月からの本選考に向けてESと面接の準備を一気に進める必要があります。
冬のインターンシップは、本選考に直結するケースが多いため、内定獲得の大きなチャンスとなります。
大学3年の12月:冬インターン本番!年末年始の過ごし方も計画的に
12月は、冬のインターンシップがいよいよ本格化する時期です。
年末年始を挟むため、短期集中のプログラムも多く見られます。
また、引き続き企業説明会や合同説明会、各種セミナーも開催されており、年内にできる限りの情報収集や企業理解を進めておきたいところです。
また、年末年始の休暇期間は、就職活動から少し離れてリフレッシュする良い機会ですが、一方で、自己分析をじっくりと深めたり、OB・OG訪問のアポイントメントを取ったりと、時間を有効に活用することも可能です。
年明けからの本格的な就職活動に向けて、心身ともに準備を整えていきましょう。
大学3年の1月:選択肢を広げる!ベンチャー選考も視野に
1月は、ベンチャー企業を中心に選考活動が活発になる時期です。
大手企業だけでなく、成長著しいベンチャー企業に目を向けることで、自身のキャリアの選択肢を大きく広げることができます。
また、冬期インターンシップも引き続き実施されており、参加を通じて企業の理解を深めたり、自己PRの材料を得たりする最後のチャンスとなる学生もいるでしょう。
この時期は、寒さも厳しく、体調を崩しやすい季節でもあります。
インフルエンザなども流行り始めるため、健康管理にはいつも以上に気を配りましょう。
また、エントリーシートの準備や筆記試験対策など、3月からの本格的なエントリー開始に向けて、具体的な準備を着実に進めていくことが求められます。
大学3年の2月:本番直前!最終準備と個別アプローチ
2月はいよいよ本番直前といった様相を呈してきます。
引き続き冬期インターンシップに参加する学生もいますが、多くの学生にとっては、3月からのエントリー開始に向けた最終準備期間となります。
自己分析の再確認、エントリーシートのブラッシュアップ、面接練習など、やるべきことは多岐にわたります。
また、この時期には、企業の人事担当者や若手社員が個別に学生と接触を持つ「リクルーター面談」が行われることもあります。
リクルーター面談は、選考の一環として位置づけられることも多く、企業への理解を深めるとともに、自分自身をアピールする絶好の機会となります。
企業からの案内に注意し、もし機会があれば積極的に参加しましょう。
いよいよ始まる本格的な就職活動に向けて、万全の準備を整える大切な1ヶ月です。
大学3年の3月:いよいよ本番!エントリーと説明会ラッシュ
大学3年生の3月。
多くの企業で採用情報が一斉に公開され、エントリー受付が開始される、まさに就職活動本番の幕開けです。
企業のウェブサイトや就職情報サイトは最新情報で溢れ、連日のように会社説明会が開催されます。
この時期は、興味のある企業へのエントリーはもちろんのこと、エントリーシートの作成・提出に追われる日々となるでしょう。
説明会への参加は、企業の雰囲気や事業内容を直接知る貴重な機会ですが、やみくもに参加するのではなく、事前に企業研究を行い、質問事項を準備しておくなど、目的意識を持って臨むことが大切です。
また、提出するエントリーシートは、誤字脱字がないか、企業の求める人物像と自分の強みが合致しているかなど、細部までしっかりと確認しましょう。
いよいよ始まった就職戦線、体調管理に気を付けながら、これまで準備してきた力を存分に発揮してください。
【大学3年の就活】何もしてない学生がすべきこと
「具体的にどのような行動をすればいいかわからない」という学生は多いと思います。
このような状態から抜け出すためには、まず就職活動の全体像を掴み、やるべきことを具体的に理解することが重要です。
この記事では、これまで就職活動に手をつけてこなかった大学3年生の皆さんが、今すぐ取り組むべき具体的な行動ステップを、分かりやすく解説していきます。
- 就活サイトに登録する
- 自己分析=就活の軸を決める
- 業界研究・企業研究をする
- 冬インターンにエントリーする
- 早期選考にエントリーする
- ESを作成する
- Webテストの対策をする
- 面接の対策をする
一つひとつは決して難しいことではありません。
この記事を読み終える頃には、あなたの「何をすればいいの?」という疑問が解消され、「よし、やってみよう!」という前向きな気持ちになっているはずです。
一緒に、納得のいく就職活動へのスタートを切りましょう!
就活サイトに登録する
まず、就職活動を始めるにあたって、情報収集の基盤となるのが「就活サイト」への登録です。
就活サイトには多くの企業情報や採用スケジュール、インターンシップ情報などが集約されており、効率的に情報を集めるためには必須のツールと言えるでしょう。
大手企業が運営する総合的な就活サイトから、特定の業界や職種に特化したサイト、あるいはベンチャー企業専門のサイトなど、様々な種類があります。
まずはいくつかの主要なサイトに登録し、どのような情報が掲載されているのか、サイトの使い勝手などを確認してみるのがおすすめです。
登録後は、気になる企業のページをブックマークしたり、興味のある業界の情報を定期的にチェックしたりする習慣をつけましょう。
また、多くのサイトにはスカウト機能があり、あなたのプロフィールに興味を持った企業から直接連絡が来ることもあります。
情報収集のアンテナを広げる第一歩として、まずは気軽に登録から始めてみてください。
自己分析=就活の軸を決める
就職活動を進める上で、最も重要と言っても過言ではないのが「自己分析」です。
自己分析とは、これまでの自分の経験や考え方、価値観などを深く掘り下げ、自分自身を客観的に理解すること。
そして、その結果から「自分はどんな仕事に興味があるのか」「どんな働き方をしたいのか」「仕事を通じて何を成し遂げたいのか」といった「就活の軸」を明確にしていく作業です。
この「就活の軸」が定まっていないと、数多くの企業の中から自分に合った企業を見つけ出すのは非常に困難ですし、エントリーシートや面接で一貫性のあるアピールをすることも難しくなります。
逆に、就活の軸が明確であれば、企業選びに迷いがなくなり、自信を持って選考に臨むことができるでしょう。
時間はかかるかもしれませんが、じっくりと自分自身と向き合うことが、納得のいく就職活動への近道となるのです。
過去経験を整理する
自己分析の具体的な手法として、まずは「過去経験を整理する」ことから始めてみましょう。
これは、これまでの人生で経験してきた様々な出来事を振り返り、その時々に自分が何を考え、どう行動し、何を感じたのかを客観的に見つめ直す作業です。
小学校時代から現在に至るまで、楽しかったこと、辛かったこと、頑張ったこと、失敗したことなど、印象に残っているエピソードを時系列で書き出してみる「自分史」の作成や、モチベーションが上がった時期と下がった時期をグラフにする「モチベーショングラフ」の作成などが有効です。
特に、学業、アルバイト、サークル活動、ボランティア活動など、大学時代に力を入れた経験は重点的に掘り下げてみましょう。
その経験から何を学び、どのようなスキルが身につき、それが今の自分にどう繋がっているのかを具体的にすることで、自分の強みや価値観が見えてきます。
成功体験だけでなく、失敗体験から何を学び、どう乗り越えたのかという視点も非常に重要です。
将来のキャリア像を明確にする
過去の経験を整理し、自分自身の価値観や強みがある程度見えてきたら、次に「将来のキャリア像を明確にする」ステップに進みましょう。
これは、5年後、10年後、あるいはもっと先の将来に、自分がどのような社会人になっていたいか、どのような働き方をしていたいか、仕事を通じて何を成し遂げていたいか、といった具体的なイメージを描く作業です。
「将来のことなんてまだ分からない」と思うかもしれませんが、完璧なキャリアプランを立てる必要はありません。
現時点での理想や願望で構わないので、例えば「専門性を高めてその道のプロフェッショナルになりたい」「チームをまとめるリーダーシップを発揮したい」「社会貢献できる仕事に就きたい」「ワークライフバランスを重視したい」など、ぼんやりとでも良いので考えてみましょう。
この将来像が、あなたが企業を選ぶ上での重要な判断基準となり、就職活動のモチベーション維持にも繋がります。
説得力のあるガクチカを作成する
学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)を作成する際、多くの学生が陥りがちな間違いは、何をやったかという事実の羅列で終わってしまうことです。
採用担当者が知りたいのは、その経験を通じて、あなたがどう考え、どう行動し、何を学んだかという部分です。
ただ頑張ったという話ではなく、あなたが直面した課題、それに対してあなたがどのような目標を設定し、どのような独自の工夫や行動をもって乗り越え、最終的にどのような結果と学びを得たのかを具体的に示すことが、説得力のあるガクチカの鍵となります。
たとえば、居酒屋のアルバイトという一般的な経験でも、売上が低迷している状況で、お客様のニーズを分析し、提案マニュアルを作成・導入することで、売上を前年比120%に引き上げたといったように、課題解決プロセスと成果を具体的に示せば、あなたの主体性や論理的思考力が伝わります。
経験の大小ではなく、その経験から得た学びが、入社後にどう活かせるかという視点を持つことが重要です。
業界研究・企業研究をする
自己分析で「就活の軸」がある程度定まってきたら、次に取り組むべきは「業界研究・企業研究」です。
世の中には本当にたくさんの業界や企業が存在します。
その中から、自分の興味や価値観に合致し、将来のキャリア像を実現できそうな場所を見つけ出すためには、それぞれの業界がどのような役割を担い、どのような企業がどのような事業を展開しているのかを深く理解する必要があります。
業界研究では、その業界全体の動向や将来性、ビジネスモデルなどを調べます。
一方、企業研究では、個別の企業について、事業内容、経営理念、社風、待遇、将来のビジョンなどを詳しく調べていきます。
これらの研究を通じて、「この業界で働いてみたい」「この企業の理念に共感できる」といった具体的な志望動機が形成されていくのです。
また、ミスマッチを防ぎ、入社後に後悔しないためにも、表面的な情報だけでなく、その企業で働くことのリアルな側面まで知ろうと努めることが大切です。
合同説明会に参加
業界研究や企業研究を進める上で、手軽に多くの情報を得られる機会の一つが「合同説明会」です。
合同説明会には、様々な業界から多くの企業が一堂に会し、それぞれのブースで会社説明を行っています。
まだ志望業界や企業が明確に定まっていない人にとっては、一度にたくさんの企業の話を聞くことで、視野を広げ、新たな興味を発見する良い機会となるでしょう。
参加する際には、事前に出展企業をチェックし、話を聞きたい企業をいくつかピックアップしておくと効率的です。
また、ただ説明を聞くだけでなく、積極的に質問をすることも大切です。
企業のウェブサイトだけでは分からない、社風や社員の方の雰囲気などを直接感じ取れるのも合同説明会のメリットです。
気になることがあれば遠慮せずに質問し、メモをしっかり取るように心がけましょう。
服装はスーツが基本ですが、私服可の場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

業界研究や企業研究は、「なんとなく」で進めてしまうと表面的な理解に留まってしまいがちですが、自分の価値観や将来像と照らし合わせながら掘り下げていくことで、志望理由にも深みが出てきます。また、合同説明会は、企業との出会いの場であると同時に、自分の「知らなかった興味」を発見できる場でもあります。情報収集を目的とするだけでなく、「人に話を聞く姿勢」や「メモの取り方」も就活力の一部として磨かれていきますので、小さな行動の積み重ねを大切にしてくださいね。
大学のキャリアセンターも利用する
業界研究や企業研究を進める上で、ぜひ活用してほしいのが「大学のキャリアセンター」です。
キャリアセンターには、就職活動に関する専門知識を持った相談員が常駐しており、個別の相談に応じてくれるだけでなく、様々な情報提供やサポートプログラムを実施しています。
例えば、過去の卒業生の就職先データや、OB・OGの連絡先情報、大学に寄せられる独自の求人情報など、学外では得られない貴重な情報が手に入ることもあります。
また、キャリアセンターが主催する業界研究セミナーや企業説明会、OB・OG訪問会なども積極的に活用しましょう。
同じ大学の先輩から直接話を聞くことで、よりリアルな企業情報や就職活動のアドバイスを得られるはずです。
エントリーシートの添削や模擬面接など、選考対策のサポートも行っている場合が多いので、困ったことがあれば遠慮なく相談に行ってみることをおすすめします。
身近にある貴重なリソースを最大限に活用しましょう。
冬インターンにエントリーする
自己分析や業界・企業研究と並行して、ぜひ積極的に取り組んでほしいのが「冬インターンシップ(ウィンターインターンシップ)へのエントリー」です。
もしあなたが「サマーインターンは参加しそびれた」「まだ本格的に何も動けていない」という状況なら、この冬インターンは、本選考前に社会との接点を持つための非常に重要な経験となります。
多くの企業が冬休み期間中や、大学3年生の2月〜3月頃に実施しており、実際の業務を体験したり、社員の方と交流したりする絶好の機会です。
冬インターンシップでは、企業の雰囲気や仕事内容を肌で感じることで、入社後のミスマッチを防ぐことができますし、本選考で使える自己PRの材料となる具体的なエピソードを得ることもできます。
また、この時期のインターンシップはサマーインターン以上に「早期選考」に直結しているケースが多く、参加者限定の選考ルートが用意されるなど、本選考を有利に進められる可能性が高まります。
インターンシップ選考の結果と本選考は関係ない
サマーインターンシップにエントリーする際には、選考が行われることが一般的です。
エントリーシートの提出や適性検査、面接などを経て参加者が決定されます。
もし、インターンシップの選考に落ちてしまったとしても、決して落ち込む必要はありません。
大切なのは、「インターンシップの選考結果と本選考の結果は必ずしも直結しない」ということを理解しておくことです。
インターンシップの選考に落ちたからといって、その企業の本選考も諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
インターンシップの選考基準と本選考の基準が異なる場合もありますし、インターンシップ選考での経験を活かして、本選考でリベンジすることも十分に可能です。
選考に落ちた場合は、何が足りなかったのかを冷静に分析し、次の機会に向けて改善していくことが重要です。
インターンシップはあくまでも就業体験の機会であり、本選考とは別物だと割り切って、積極的にエントリーしましょう。
早期選考にエントリーする
大学3年生の冬は、いよいよ本選考が目前に迫る時期です。
このタイミングで始まる早期選考は、他の学生に先駆けて内定を得られるチャンスであり、就職活動の方向性を決定づける上で非常に重要なステップとなります。
多くの企業が、冬インターンシップ参加者向けや、特定の優秀な学生向けに、本選考とは別のルートで選考を実施します。
早期選考では、本選考よりも少ないライバルの中で選考を受けられるため、じっくりと自分をアピールできますし、選考の場数を踏むことで面接慣れすることもできます。
また、仮に早期選考で内定を得られれば、心に余裕を持って本選考や残りの学生生活に臨むことができます。
まずはアンテナを高く張り、興味のある企業や業界の早期選考情報を探し、積極的に挑戦してみましょう
ESを作成する
就職活動において、多くの企業で最初の関門となるのが「エントリーシート(ES)」の提出です。
ESは、あなたの個性や能力、企業への熱意などを文章で伝えるための重要な書類であり、自己分析や業界・企業研究の成果を形にするものと言えるでしょう。
企業はこのESを通じて、あなたが自社で活躍できる人材かどうかを判断するため、内容はもちろんのこと、書き方や表現にも細心の注意を払う必要があります。
ESでよく問われる項目としては、「自己PR」「学生時代に最も力を入れたこと(ガクチカ)」「志望動機」などが挙げられます。
これらの項目に対して、具体的なエピソードを交えながら、あなた自身の言葉で、分かりやすく、かつ魅力的に伝えることが求められます。
自己分析で明らかになった自分の強みや価値観、業界・企業研究で深めた企業への理解などを総動員し、熱意のこもったESを作成しましょう。
書き上げたら添削してもらおう
エントリーシートを自分なりに一生懸命書き上げたとしても、それで完成ではありません。
必ず誰かに読んでもらい、客観的な意見をもらう「添削」のプロセスを経ることが非常に重要です。
自分では完璧だと思っていても、他人から見ると分かりにくい表現があったり、誤字脱字があったり、アピールポイントが十分に伝わっていなかったりすることはよくあります。
添削をお願いする相手としては、大学のキャリアセンターの相談員、ゼミの先生、就職活動を経験した先輩、信頼できる友人などが挙げられます。
複数の人に見てもらうことで、様々な視点からのアドバイスを得られ、より完成度の高いエントリーシートに仕上げることができます。
添削してもらう際には、ただ読んでもらうだけでなく、「どこが分かりにくいか」「もっとこうした方が良いのではないか」といった具体的なフィードバックをもらうようにしましょう。
そして、もらったアドバイスを真摯に受け止め、改善していく素直さも大切です。
Webテストの対策をする
多くの企業の選考プロセスで導入されているのが「Webテスト」です。
これは、自宅や大学のパソコンからインターネット経由で受験する形式の適性検査のことで、言語能力や計算能力、論理的思考力などを測る問題が出題されます。
SPIや玉手箱、TG-WEBなど様々な種類があり、企業によって採用しているテストが異なります。
| Webテストの種類 | 特徴 | 使われやすい業界・職種 |
|---|---|---|
| SPI(Synthetic Personality Inventory) | 言語・非言語・性格の3領域。問題の難易度は標準的で、多くの企業が導入。 | 大手企業全般(商社・金融・メーカーなど) |
| 玉手箱 | 言語・計数・英語の3領域。時間制限が厳しく、速読力が求められる。 | 外資系企業、総合商社、コンサル、金融系など |
| TG-WEB | 難易度が高く、思考力・読解力を重視。問題形式が独特。 | コンサル、広告、IT、難関企業など |
| CAB(Computer Aptitude Battery) | 図形の法則性や命令表処理など、情報処理スキルを測る。IT系職種向け。 | SIer、IT企業、エンジニア職など |
| GAB(General Aptitude Battery) | 言語・計数・性格の3領域。玉手箱と似ているが形式が異なる。 | 外資系企業、商社、コンサルなど |
このWebテストの結果は、エントリーシートの内容と合わせて、次の選考ステップに進めるかどうかを判断する材料となるため、決して軽視できません。
Webテストの対策としては、まず自分が志望する企業がどの種類のテストを導入しているのかを調べ、それに対応した問題集を繰り返し解くことが基本となります。
問題の形式や時間配分に慣れることが重要です。
また、多くの問題集には模擬テストが付いているので、本番さながらの環境で時間を計って解いてみるのも効果的です。
苦手な分野があれば重点的に復習し、少しでも正答率を上げられるように努力しましょう。
計画的に対策を進めることが、Webテスト攻略の鍵となります。
面接の対策をする
書類選考やWebテストを通過すると、いよいよ「面接」が待っています。
面接は、企業の人事担当者や現場の社員と直接対話し、あなたの人物像や能力、企業への適性などを総合的に評価される場です。
エントリーシートだけでは伝えきれないあなたの魅力や熱意をアピールする絶好の機会であると同時に、あなた自身も企業との相性を見極める重要な場となります。
面接対策としては、まずエントリーシートに書いた内容を深掘りし、どんな質問がきても具体的に答えられるように準備しておくことが基本です。
自己PRや志望動機はもちろんのこと、学生時代に力を入れたこと、長所・短所、キャリアプランなど、よく聞かれる質問については、自分の言葉でしっかりと語れるように練習しておきましょう。
また、企業の事業内容や理念、業界の動向などについても理解を深めておくことが、的確な受け答えに繋がります。
模擬面接が効果的
面接対策として非常に効果的なのが「模擬面接」です。
模擬面接とは、本番の面接を想定して、実際に誰かに面接官役をやってもらい、質疑応答の練習をすることです。
頭の中でシミュレーションするだけでは気づけない、自分の話し方の癖や表情、視線、姿勢といった非言語的な部分についても客観的なフィードバックをもらうことができます。
模擬面接の相手としては、大学のキャリアセンターの相談員、就職支援サービスのキャリアアドバイザー、あるいは友人や家族などにお願いしてみましょう。
できれば、様々なタイプの人に面接官役をしてもらうことで、多様な質問や雰囲気に対応できる力が養われます。
模擬面接を終えた後は、必ずフィードバックをもらい、良かった点や改善すべき点を把握し、次の練習に活かすことが大切です。
回数を重ねることで、本番の面接でも緊張しすぎることなく、自然体で臨めるようになるでしょう。
何もしてない学生が陥りがちな状態と対処法
「何をしたらいいかわからない」「やりたい事がない」「ガクチカが何もない」。
こうした悩みは多くの学生が抱えています。
しかし、焦り続けるのではなく、その状態から抜け出す「最初の一歩」が肝心です。
この記事では、就活で何もしていないと悩む学生が陥りがちな状態別に、今すぐできる対処法を具体的にアドバイスします。
「何をしたらいいかわからない」ときの対処法
道筋が見えない時は、一人で悩まず大学のキャリアセンターや就活エージェントなど、プロに相談するのが一番の近道です。
彼らはあなたの現状に合わせた最適なアドバイスをくれます。
もし、まずは一人で進めたいなら、リクナビやマイナビなどの就活サイトに登録し、気になる企業のマイページをいくつか登録してみましょう。
強制的に就活情報に触れる環境を作ることで、次に何をすべきかが見えてきやすくなりますよ。
「やりたい事がない」時の対処法
やりたい事がないのは、まだ「知らない」だけかもしれません。
まずは業界を絞らず、オンライン説明会に片っ端から参加してみましょう。
少しでも「面白い」と感じたら、なぜそう感じたのかを深掘りしてください。
それが生きた自己分析になります。
どうしても「やりたい事」が見つからなければ、「嫌いなこと・やりたくないこと」を明確にし、それを避けられる企業を選ぶというのも、立派な企業選びの軸になりますよ。
「業界や企業がわからない」時の対処法
世の中にはBtoB企業など、あなたの知らない仕事が溢れています。
「会社四季報 業界地図」などを活用し、まずは全体像を把握しましょう。
どんな業界があり、どんな企業が活躍しているのかを知るだけでも視野が広がります。
また、就活市場の「適職診断」を受けてみるのも一つの手です。
「ガクチカがなにもない」時の対処法
ESや面接で必ず聞かれるガクチカ。
就活を始めたばかりで何もしてない学生は、「本当にガクチカが何もない」「どう話せばいいかわからない」と悩む人も多いでしょう。
そこで今回「AIガクチカ作成ツール」をご用意しました。
質問に回答するだけであなたの強みや経験を活かしたガクチカを作成することができます。
無料ですぐに使用可能なため、ぜひあなたも就活市場のAIガクチカ作成ツールを活用して選考通過率をUPさせちゃいましょう!
ガクチカをいまから作ることはできるのか?
「ガクチカがないなら今から作ろう」と考えるかもしれませんが、大学3年のこの時期から就活のためだけに新しい活動を始めるのは推奨しません。
短期間の活動では深掘りできるエピソードになりにくく、面接官にも意図が見透かされがちです。
それよりも、今までの大学生活を丹念に振り返り、些細な経験から自分の強みや考え方を見つけ出す作業に時間を使う方が、よほど効果的な対策になりますよ。
【大学3年の就活】選考フローを短くする方法
就職活動は、ES提出、Webテスト、複数回の面接、そして最終面接と、長く複雑なフローを経て内定に至るのが一般的です。
しかし、実は企業の状況や採用したい人材によって、この選考フローを短くするための方法はいくつか存在します。
選考フローが短縮されれば、その分早く内定を獲得できるため、他の選考に時間を割けたり、精神的な余裕が生まれたりといったメリットがあります。
選考フローを短縮するアプローチは、企業が**「確実に採用したい」**と判断する要素を事前に提供することに繋がります。
ここでは、大学3年生のうちから意識的に利用できる、選考フローを短縮する具体的な方法を解説します。
リファラル採用を受ける
リファラル採用とは、企業で働く社員からの紹介によって選考に進む採用手法のことです。
このリファラル採用の最大の強みは、社員による事前のふるい分けがなされているという点です。
紹介者はあなたの能力や人柄を理解した上で企業に推薦しているため、企業側から見れば、通常の選考ルートで来る応募者よりも、ミスマッチのリスクが低く、信頼性が高いと判断されます。
これを最大限に活かすことで、書類選考や一次面接など、選考の一部が大幅に短縮・免除される可能性が高まります。
リファラル採用のルートに乗るためには、まずはOB・OG訪問などを通じて企業の社員と積極的に接点を持つことが第一歩です。
その際に、熱意や自分の強みをしっかり伝え、「この人なら安心して推薦できる」と思ってもらえるような信頼関係を築くことが重要です。
社員の紹介というプロセスは、あなたのポテンシャルや人間性に対する強力な推薦状となるため、選考の初期段階における企業の評価を大きく高めることができます。
知人や大学の先輩などで、志望企業で働いている方がいれば、積極的にコンタクトを取ってみましょう。
1Day選考を受ける
1Day選考とは、その名の通り、選考フローを極限まで短縮し、書類選考後の面接やグループディスカッションなどをわずか1日で集中的に実施する採用イベントです。
企業によっては、この1日の選考で内定まで至る可能性があり、就活生にとっては大幅な時間短縮と早期内定のチャンスとなります。
企業側も、優秀な人材を競合他社に先駆けて確保したいという意図があるため、このような形式を取ることがあります。
1Day選考は、参加する時点で企業への志望度が高いことが前提とされる場合が多いため、参加前には徹底した企業研究と、質の高い自己PRの準備が不可欠です。
限られた時間の中で、自分の強みや入社意欲を最大限にアピールしなければなりません。
特に、面接やGDが連続するため、高い集中力と即座に対応できる思考力が求められます。
この選考方式は、短期間で内定を得たい就活生にとっては非常に魅力的ですが、一度のチャンスに全てをかけるという覚悟が必要となるでしょう。
本選考直結イベントに参加する
企業が主催する説明会、インターンシップ、ワークショップなどの中には、その後の本採用選考の一部が免除・優遇される本選考直結型イベントがあります。
これらは、企業が優秀な学生と早期に接触し、自社の魅力を深く理解してもらった上で、選考プロセスを効率化するために設計されています。
これらのイベントに参加し、高い評価を得ることができれば、その後のES提出が免除されたり、一次・二次面接がスキップされたりするなどの優遇措置を受けられる可能性があります。
この種のイベントを見つけ出すためには、企業の採用情報や就活サイトをこまめにチェックすることが重要です。
参加する際は、「選考の一環である」という意識を強く持ち、イベント内のグループワークや質疑応答で積極的に発言し、企業への熱意と貢献意欲を示すことが大切です。
ただ参加するだけでなく、イベント内で企業が求めている資質(例:リーダーシップ、論理的思考力、チームワークなど)を発揮できるよう意識して行動しましょう。
イベントでの実績が、そのまま選考を有利に進めるための強力な武器となります。
【大学3年の就活】何もしてない人が今すぐ準備するもの
大学3年生になり、就職活動という言葉を耳にする機会が増え、「まだ何もしていない…」と焦りを感じている方もいるかもしれません。
しかし、今からでも準備を始めれば、十分に間に合います。
ここでは、就職活動をスムーズに進めるために、今すぐ準備すべき具体的なアイテムについて詳しく解説していきます。
- 就活の服装一式(リクルートスーツなど)
- 証明写真
- スケジュール帳
- 就活用ノート
- 履歴書
- 筆記用具
これらの準備を整えることで、いざという時に慌てずに済み、選考に集中できる環境を整えることができます。
就活の服装一式(リクルートスーツなど)
就職活動において、まず必要となるのが服装です。
特に、面接や企業説明会といった場面では、リクルートスーツの着用が基本となります。
リクルートスーツは、黒や紺の無地のものが一般的で、サイズが合っているかどうかも非常に重要です。
男性であればワイシャツ(白無地が基本)、ネクタイ、革靴、そしてシンプルな腕時計を準備しましょう。
女性であればブラウス(白が基本)やカットソー、スカートまたはパンツスーツ、パンプス、そして就活用のバッグ(A4ファイルが収まるビジネスバッグ)が必要になります。
これらは一式揃えておくことで、急な面接や説明会にも対応できます。
証明写真
エントリーシートや履歴書には、証明写真の添付が求められます。
以前に撮影したものでも良いと考えるかもしれませんが、就職活動では最新の証明写真を使用することをおすすめします。
髪型やメイク、表情が今のあなたを最もよく表している写真を選ぶことで、企業に好印象を与えることができます。
写真館でプロに撮影してもらうと、より質の高い写真が手に入り、自信を持って提出できます。
清潔感があり、明るい表情の写真を準備し、あなたの真剣さをアピールしましょう。
スケジュール帳
就職活動が本格化すると、複数の企業のインターンシップや選考が並行して進むことが多くなります。
説明会や面接、ES提出の締め切りなど、管理すべきスケジュールは膨大です。
そのため、就活専用のスケジュール帳を用意することを強くおすすめします。
紙の手帳でもスマートフォンのアプリでも構いませんが、一目で全体の流れが把握でき、抜け漏れがないように管理できるものが良いでしょう。
企業の名称や日時、持ち物などを詳細に書き込み、常に最新の状態に保つことで、大切な機会を逃すことなく、効率的に就職活動を進めることができます。
就活用ノート
企業研究や選考対策を進める上で、情報が整理されているかは非常に重要です。
そこで役立つのが「就活用ノート」です。
エントリーした企業ごとに、企業情報、事業内容、求める人物像、選考プロセス、面接で聞かれたこと、感想などをまとめて記録しておきましょう。
これにより、企業ごとの対策を効率的に行えるだけでなく、志望動機や自己PRを考える際の材料にもなります。
また、説明会やインターンシップで得た情報もすぐにメモすることで、記憶の新しいうちに整理でき、後から見返す際に役立ちます。
履歴書
多くの企業で提出を求められるのが履歴書です。
企業によってはエントリーシート(ES)とは別に履歴書の提出が必要となる場合もあります。
ESのように企業ごとにフォーマットが指定されていることは少なく、汎用的なフォーマットで事前に1枚作成しておくと、急な提出にも慌てずに対応できます。
学歴や職歴(アルバイト経験など)、資格、自己PR、志望動機などを整理して記入することで、自身の基本情報をいつでも提出できる状態にしておきましょう。
誤字脱字がないよう丁寧に作成し、複数のコピーを準備しておくと便利です。
筆記用具
オンラインでの選考が増えている現代においても、筆記用具は就職活動において必須アイテムです。
企業説明会でのメモ取り、筆記試験、あるいは面接前のアンケート記入など、様々な場面で必要となります。
特に、就職活動では、集中して情報を書き留める場面が多いため、使い慣れたペンを複数本、そして消しゴムやシャープペンシルなども含め、一式揃えておくことをおすすめします。
いざという時に慌てないよう、普段から持ち歩くカバンに入れておくなど、準備を怠らないようにしましょう。
【大学3年の就活】よくある質問
就活に向けてまだ何も手をつけていない、あるいは出遅れたと感じている方が抱える不安は非常に大きいでしょう。
この漠然とした不安を解消し、一歩踏み出すためのきっかけとなるよう、ここでは多くの就活生が抱える疑問にお答えします。
安心して、今からできることに集中しましょう。
今から始めて間に合いますか?
「もう手遅れではないか」という不安が最も大きいと思いますが、結論として今から始めても十分に間に合います。
特に大学3年生のこの時期は、周りの学生も本格的な準備を始めたばかりの人が多く、自分自身のこれからの行動量と質でいくらでも巻き返すことが可能です。
大切なのは、焦って形だけの準備をするのではなく、自己分析や業界研究といった基礎固めから着実に進めることです。
一歩ずつ具体的な行動に移せば、不安は必ず解消されていきます。
インターンシップに参加していなくても大丈夫ですか?
インターンシップは、特に早期選考のチャンスに繋がるため、「行くべき」というアドバイスが多いのは事実です。
参加していない場合は、早期選考の機会を減らしてしまう可能性があります。
しかし、参加していなくても内定獲得は十分に可能です。
行かなかった分、他の部分で情報収集の質を上げることが重要になります。
OB・OG訪問を増やす、企業説明会に積極的に参加するなど、他の方法で企業への理解と熱意を示し、選考に臨むことで十分に挽回できます。
就活に不安を抱えていたらプロに相談しよう
就活に漠然とした不安や「何から始めたらいいか分からない」という状態であれば、プロの就活アドバイザーやキャリアセンターに相談することをお勧めします。
プロに相談することで、何から始めたらいいのかが明確になり、無駄のない就活の効率化が図れます。
また、自己PRやES、面接対策について客観的なフィードバックを得ることができ、選考の通過率向上に直結します。
一人で悩まず、専門家の力を借りて、安心して就活を進めてください。
まとめ
今回は、大学3年生で「まだ何も就活をしていない」と不安を感じているあなたに向けて、今からでも間に合う具体的な行動ステップや、サマーインターンシップの重要性、そして就職活動を進める上での心構えなどを解説してきました。
「もう手遅れかもしれない…」そんな風に思っていたかもしれませんが、この記事を読んで、少しでも「今から頑張ってみよう!」という気持ちになっていただけたなら幸いです。
大切なのは、過去を悔やむことではなく、今日この瞬間から未来に向けて一歩を踏み出すことです。
まずは、就活サイトに登録してみる、自己分析を始めてみる、気になる業界のサマーインターンシップ情報を調べてみる、といった小さな行動からで構いません。
一つひとつの積み重ねが、必ずあなたの自信に繋がり、納得のいく企業との出会いを引き寄せてくれるはずです。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート















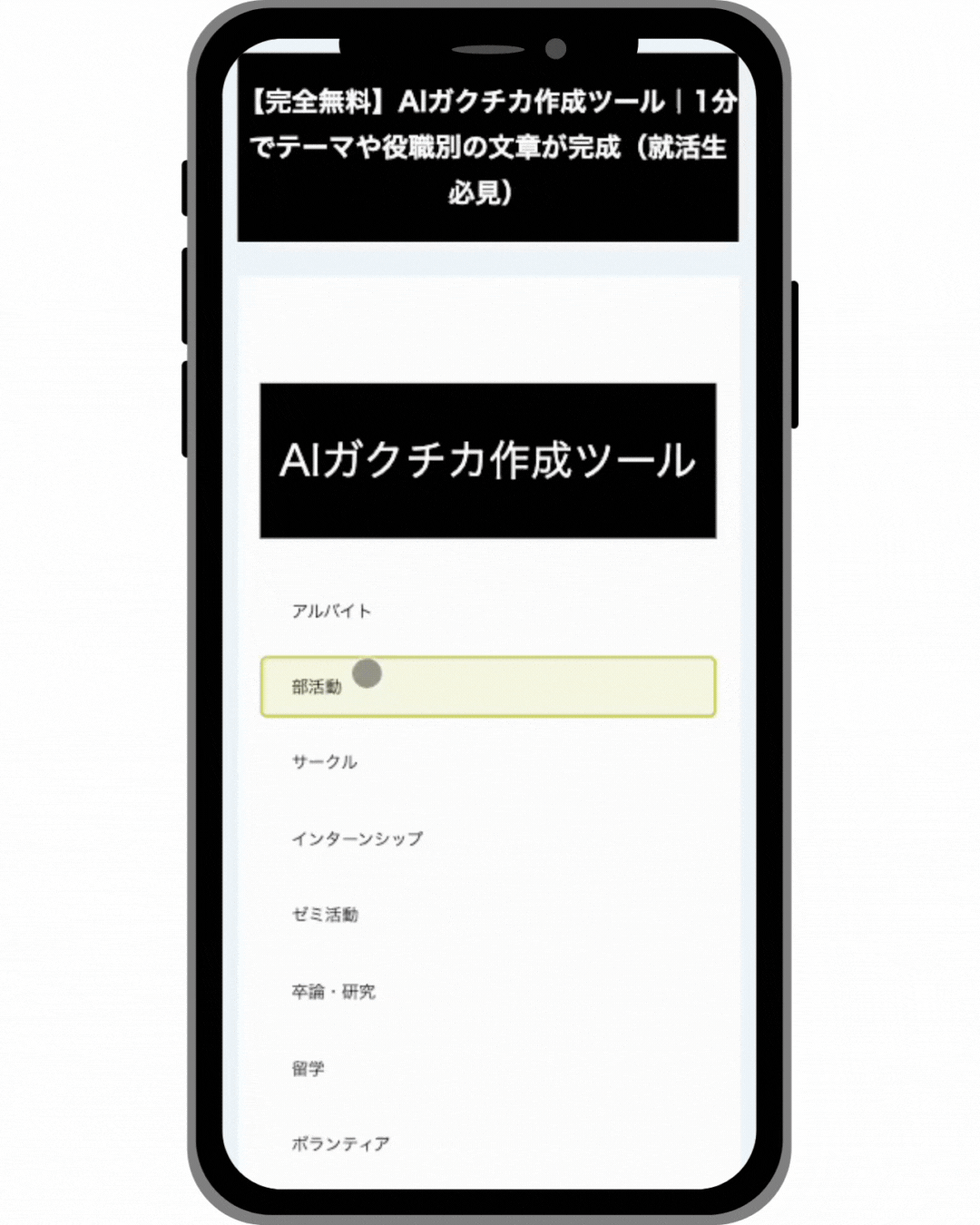



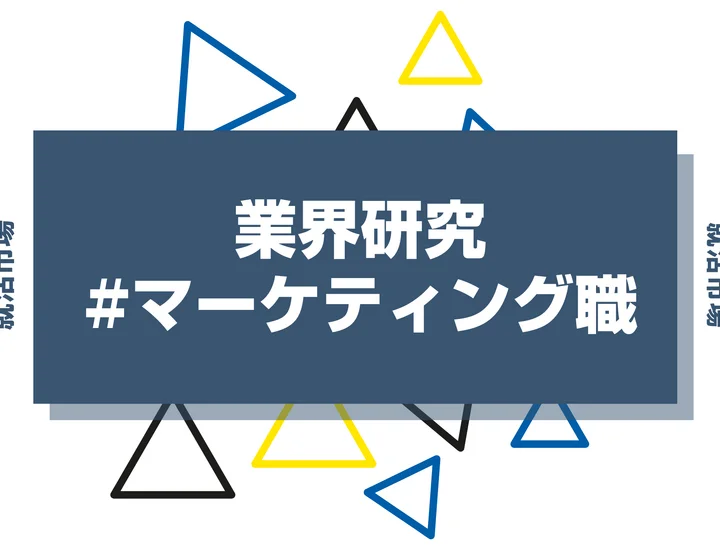
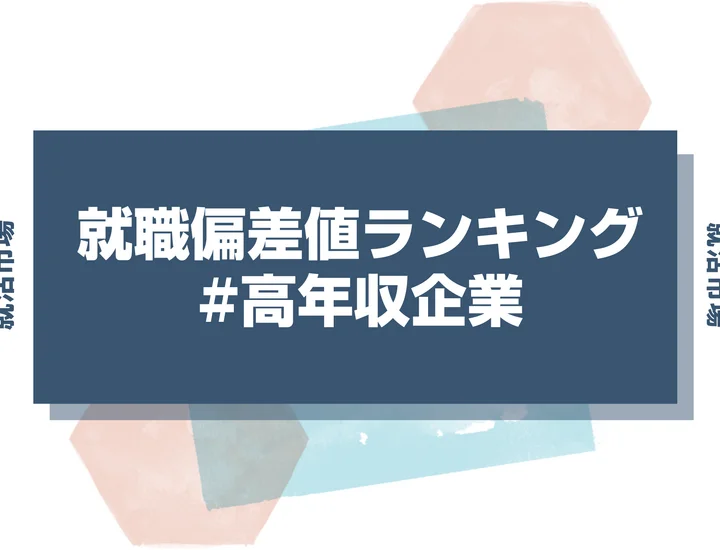





柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
ご指摘の通り、就職活動の早期化は年々進んでおり、「まだ大学3年生だから大丈夫」とは言い切れない状況になっています。とはいえ、焦る必要はありません。今このタイミングで準備を始めることで、しっかりと自分の軸を持ち、納得のいく選択ができるようになります。自己分析や情報収集を丁寧に行うことで、視野が広がり、意外な企業との出会いも生まれるものです。周囲と比べすぎず、自分のペースで「今できること」から一歩ずつ進めていきましょう。