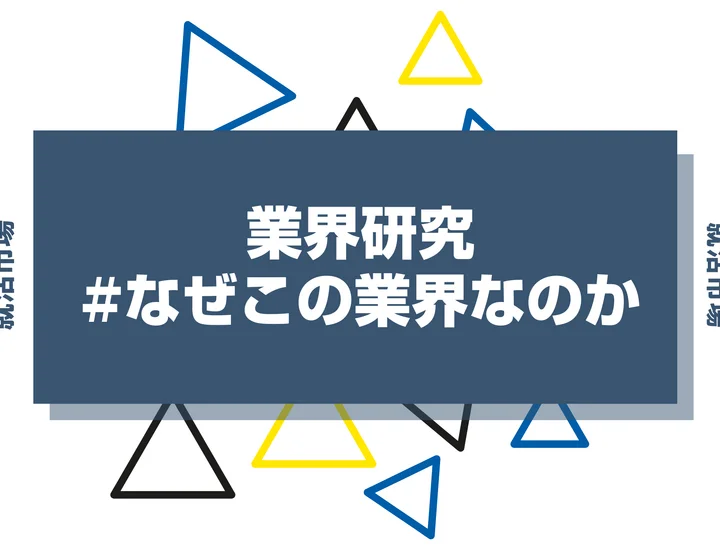今回は、世界中の就活生が憧れる企業の一つ、Googleの27卒向け本選考について、皆さんが今知りたい情報を徹底的に解説していきます。
Googleの選考は、その独自性と難易度の高さで知られていますが、一方で非常に透明性が高く、求める人物像も明確です。
しかし、情報が多岐にわたるため、「いつから始まるの?」「選考フローは?」「インターンに行ってないと不利?」など、不安や疑問も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした皆さんの疑問を解消し、今から何を準備すべきか、具体的なアクションプランが見えるように、最新の予測と例年の傾向を交えて詳しくお伝えします。
世界最先端の企業への挑戦権、その切符を掴むために、まずは正しい情報をインプットすることから始めましょう。
この記事を読んで、ライバルより一歩早いスタートを切ってくださいね。
【Google 本選考】27卒本選考の採用スケジュール
さて、まず皆さんが最も気になるであろう、27卒向け本選考のスケジュールについて解説していきます。
Googleのような外資系テック企業は、日系企業と比べて採用スケジュールが早い傾向にあり、情報解禁やエントリー開始時期も異なります。
特にGoogleは、職種別採用(技術職、ビジネス職など)を行っており、ポジションごとに募集開始時期や締切が細かく分かれているのが特徴です。
そのため、「いつの間にか募集が終わっていた…」なんてことにならないよう、常に最新の採用情報をキャッチアップする姿勢が欠かせません。
「まだ大学3年生(修士1年生)になったばかり」と油断していると、あっという間にチャンスを逃してしまう可能性もあります。
ここでは、例年の傾向を踏まえつつ、27卒の皆さんがいつ頃から動き出すべきか、その具体的な日程感と締切について、詳しく見ていきましょう。
早期準備と迅速な行動が、Google本選考突破の最初の鍵となりますよ。
本選考の日程
27卒のGoogle本選考の日程ですが、現時点(2025年11月)で確定的な情報はまだ発表されていません。
しかし、例年の傾向から予測することは十分に可能です。
Googleの本選考は、大きく分けて技術職(ソフトウェアエンジニアなど)とビジネス職(セールス、マーケティングなど)でスケジュールが異なる場合があります。
特に技術職は、サマーインターンからの接続や、早期の採用活動が活発です。
例年、早いポジションでは大学3年生(修士1年生)の秋口、つまり前年の10月〜12月頃からエントリーが開始されるケースが多く見られます。
年が明けて、大学3年生の1月〜3月頃にかけて、その他のポジションの募集も本格化し、春先(4月〜5月)まで続くというのが一般的な流れです。
ただし、これはあくまで目安であり、27卒採用ではさらに早期化する可能性も否定できません。
最も重要なのは、Googleの採用ページをこまめにチェックすることです。
キャリア登録をしておけば、関連するポジションの募集が開始された際に通知を受け取れる場合もあるため、今すぐにでも登録しておくことを強くおすすめします。
本選考の締切
本選考の締切についても、ポジションごとに個別に設定されるため、一概に「いつまで」とは言えません。
しかし、Googleの採用で非常に重要な特徴が一つあります。
それは、「ローリング・ベース(Rolling Basis)」と呼ばれる方式を採用している可能性が高いことです。
これは、エントリーが開始された順に選考を行い、採用枠が埋まり次第、そのポジションの募集を締め切るという方式です。
つまり、締切日が設定されていたとしても、その日よりずっと前に募集が終了してしまうリスクがあるのです。
例えば、4月30日が締切だとしても、3月中に優秀な学生で枠が埋まってしまえば、それ以降のエントリーは実質的に見送られる可能性が高くなります。
ですから、「締切までまだ時間がある」と悠長に構えるのは非常に危険です。
特に人気のあるポジションは、募集開始と同時に応募が殺到します。
本選考の日程を把握したら、エントリーシート(ES)や履歴書の準備を万全にし、募集が開始されたらできるだけ早い段階で応募する「早期応募」が、Google本選考においては鉄則と言えるでしょう。
【Google 本選考】27卒本選考の選考フロー
Googleの選考フローは、論理的思考力、問題解決能力、そして「Googliness(グーグリネス)」と呼ばれるGoogle独自の価値観への適合性を多角的に評価するために、非常に練り込まれています。
27卒本選考も、基本的には例年のフローを踏襲すると予想されますが、細かな変更点には注意が必要です。
一般的なフローとしては、まず「オンライン応募(英文レジュメ・ES提出)」から始まります。
ここで提出された書類がスクリーニングされ、通過者には次に「オンラインアセスメント(Webテスト)」が課されます。
このテストをクリアすると、いよいよ「面接」フェーズに進みます。
面接は複数回行われるのが特徴で、技術職ではコーディング面接が、ビジネス職では行動面接(過去の経験を深掘りするもの)やケース面接(特定の課題に対する解決策を問うもの)が中心となります。
コロナ禍以降、面接はオンラインで実施されることが主流になりましたが、27卒選考で対面面接が復活するかどうかは注目すべき点です。
例年との違いとしては、選考プロセスのさらなる効率化や、オンラインツールの活用が進む可能性があります。
各フェーズで求められる能力が明確であるため、一つひとつの対策を丁寧に行うことが不可欠です。
【Google 本選考】27卒本選考はWebテスト実施あり?
結論から言うと、27卒本選考でもWebテスト(オンラインアセスメント)は実施されると考えて間違いありません。
Googleの選考におけるWebテストは、単なる足切りではなく、応募者の基本的な認知能力や、職種に応じた専門スキルを測るための重要なプロセスと位置づけられています。
例年との違いですが、形式自体は大きく変わらないと予想されます。
ビジネス職の場合は、「GCA (General Cognitive Ability)」と呼ばれる、論理的思考力、数的処理能力、空間認識能力などを問う、Google独自の適性検査が実施される傾向にあります。
これは一般的なSPIや玉手箱とは異なるため、過去の受験者の情報を集めるなど、特化した対策が必要になるでしょう。
一方、技術職(ソフトウェアエンジニアなど)の場合は、コーディングテストが課されます。
オンライン上で与えられた課題に対し、実際にコードを書いて問題を解決する能力が試されます。
アルゴリズムやデータ構造に関する基礎知識が必須であり、こちらも「LeetCode」や「AtCoder」といったプログラミングコンテストサイトなどで、日頃から実践的な練習を積んでおくことが突破の鍵となります。
いずれの職種においても、このWebテストは選考の初期段階における大きな関門となるため、十分な準備をして臨みましょう。
【Google 本選考】27卒本選考のESで聞かれる項目
Googleの本選考で提出するエントリーシート(ES)やレジュメ(履歴書)は、日本企業のものとは少し毛色が異なります。
特に英文レジュメの提出を求められるケースが多く、学歴や職歴(インターン含む)に加え、スキルやプロジェクト経験を簡潔かつ具体的にまとめる能力が問われます。
ESで聞かれる項目については、27卒でも例年の傾向を踏襲し、応募者の内面や価値観を深く知ろうとする質問が多いと予想されます。
例えば、「困難な課題をどのように乗り越えましたか?」「チームでリーダーシップを発揮した経験について教えてください」「Googleのどの点に魅力を感じ、どのように貢献したいですか?」といった、具体的なエピソードを求める質問が中心です。
これらは、単に「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」を聞いているだけではありません。
その経験を通じて、あなたがどのように考え、行動し、何を学んだのか、そしてその経験がGoogleのカルチャー(「Googliness」)とどう合致するのかを見ています。
抽象的な自己PRではなく、「(状況)の中で、(課題)に対して、(行動)を起こし、(結果)を出した」というように、STARメソッドなどを意識した論理的かつ具体的な記述を心がける必要があります。
例年との大きな違いはないと予想されますが、常にGoogleが発信しているミッションや価値観を再確認し、それに沿ったエピソードを選定することが重要です。
【Google 本選考】27卒本選考のインターン優遇
Googleのインターンシップ(技術職のSTEPインターンシップや、ビジネス職のBOLDインターンシップなど)に参加した場合の本選考への優遇措置は、多くの就活生が気になるところでしょう。
結論として、インターン参加者に対する優遇は存在する可能性が非常に高いです。
Googleに限らず、多くの外資系企業では、インターンシップを単なる就業体験ではなく、優秀な学生を早期に発掘し、入社への意欲を高めてもらうための「選考プロセスの一部」として位置づけています。
具体的な優遇の内容としては、インターン期間中のパフォーマンスが一定の基準を満たした場合、本選考の一部プロセスが免除される(例えば、書類選考やWebテスト、一部の面接がスキップされる)ケースや、通常よりも早い時期に選考が進む「早期選考ルート」に案内されるケースなどが考えられます。
ただし、重要なのは「インターンに参加すれば誰でも優遇されるわけではない」という点です。
あくまで、インターン中に高い成果を出し、Googleの社員として活躍できるポテンシャルを明確に示せた学生が対象となります。
27卒でもこの傾向は続くと見られ、インターンは本選考への最短ルートの一つであると同時に、実力が試される場でもあると認識しておきましょう。
【Google 本選考】27卒本選考はインターン落ち学生でも応募できる?
これは非常によくいただく質問ですが、安心してください。
Googleのインターン選考に落ちてしまった学生でも、本選考に再応募することは全く問題ありません。
むしろ、積極的にチャレンジすべきです。
多くの企業、特にGoogleのような規模の大きい企業では、インターン選考と本選考は、別々の採用枠や基準で判断されているケースが一般的です。
インターンは募集枠が非常に少なく、本選考よりも倍率が高くなることも珍しくありません。
そのため、インターン選考で不合格だったからといって、あなたの能力が本選考の基準に達していないと判断されたわけでは決してありません。
大切なのは、インターン選考でなぜ落ちてしまったのかを自分なりに分析し、その反省点を本選考までに改善することです。
例えば、「Webテストの対策が不十分だった」「面接でうまく自分の経験を伝えられなかった」など、具体的な課題が見つかるはずです。
その弱点を克服し、成長した姿を見せることができれば、本選考で合格を掴み取るチャンスは十分にあります。
インターン落ちは「終わり」ではなく、本選考に向けた「スタートライン」だと捉え、前向きに準備を進めましょう。
【Google 本選考】27卒本選考を突破するためのポイント
さて、これまでGoogleの27卒本選考に関する様々な情報をお伝えしてきましたが、ここからは最も重要な「本選考を突破するための具体的なポイント」について、3つの側面に絞って徹底的に解説していきます。
Googleの選考は、単に学歴が高いから、あるいはプログラミングが得意だからという理由だけで通過できるほど甘くはありません。
Googleが掲げるミッションへの共感、高い問題解決能力、そして「Googliness」と呼ばれる独自のカルチャーへのフィット感が、選考のあらゆる場面で厳しく評価されます。
これらのポイントは、一夜漬けで身につくものではなく、日々の意識と継続的な努力によって培われるものです。
しかし、裏を返せば、今からしっかりと準備をすれば、誰にでもチャンスがあるということです。
選考プロセス全体を通して一貫した自分の軸を持ち、それを論理的に伝えられるかどうかが合否を分けます。
これからお話しする3つのポイントを深く理解し、今日から具体的な行動に移していきましょう。
Googleのカルチャーと価値観への深い理解
Google本選考を突破するための最初の、そして最も根本的なポイントは、「Googleのカルチャーと価値観への深い理解」です。
これは、単に「Googleの10の事実」を暗記することではありません。
なぜGoogleが「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」と考えるのか、なぜ「完璧を目指すより、まずやってみることが大切」だとされるのか、その背景にある思想や哲学を自分なりに解釈し、共感できるレベルまで落とし込む必要があります。
そして、その価値観が自分のこれまでの経験や行動原理とどのようにリンクしているのかを、具体的なエピソードで語れなくてはなりません。
例えば、ESや面接で「なぜGoogleなのか?」と問われた際、「最先端の技術に触れたいから」といった表面的な理由だけでは不十分です。
「ユーザーファーストの姿勢に強く共感しており、私自身もサークル活動で常にメンバーの意見を最優先に考えて課題解決に取り組んできた」といったように、自分の実体験とGoogleの価値観を結びつけて説明することが求められます。
企業研究を超え、自分とGoogleとの「共通言語」を見つけ出す作業だと思ってください。
圧倒的な論理性と問題解決能力のアピール
次に重要なのが、「圧倒的な論理性と問題解決能力」です。
これは特に面接フェーズで強く求められます。
Googleの面接、特に技術職のコーディング面接やビジネス職のケース面接では、「正解」そのものよりも、「正解に至るまでの思考プロセス」が何よりも重視されます。
面接官は、あなたが未知の課題に直面したとき、どのように問題を分解し、仮説を立て、検証し、論理的に結論を導き出していくかを見ています。
例えばケース面接で「日本のEC市場におけるGoogleの新たな戦略を提案してください」と問われたら、すぐに「広告を増やします」と答えるのではなく、「まず市場規模と競合の動向を整理します。
その上で、Googleの強みである検索データとAI技術を活かせる領域はどこか、仮説を立てて検証します」といったように、思考のステップを明確に示しながら回答することが重要です。
技術職の面接でも同様で、単にコードを書けるだけでなく、「なぜそのアルゴリズムを選んだのか」「他のアプローチと比較して、どのようなメリット・デメリットがあるのか」を論理的に説明できることが合格の鍵となります。
日頃から「なぜ?」を繰り返し、物事を構造的に捉える訓練を積んでおきましょう。
「Googliness」を体現する具体的なエピソードの準備
最後に、Googleの選考において避けては通れないのが「Googliness(グーグリネス)」です。
これは、Google社員に共通して求められる資質やマインドセットを指す言葉で、具体的には「好奇心旺盛であること」「謙虚であること」「不確実な状況でも主体的に行動できること」「チームプレイヤーであること」「倫理観が高いこと」など、様々な要素を含んでいます。
選考では、「あなたはGooglinessを持っていますか?」と直接的に問われることはありません。
そうではなく、あなたの過去の経験に関する深掘り質問を通じて、間接的にGooglinessの有無が判断されます。
したがって、あなたは自分の過去の経験(学業、アルバイト、インターン、サークル活動など)を棚卸しし、その中でGooglinessを発揮した具体的なエピソードを複数準備しておく必要があります。
例えば、「チームで意見が対立した際、一方的に主張するのではなく、まず相手の意見を傾聴し(謙虚さ)、共通のゴールを見出すために粘り強く議論をファシリテートした(チームワーク)」といった具合です。
抽象的な自己PRではなく、あなたの行動事実が「Googliness」を自然と物語るようなエピソードを選び、論理的に説明できるように整理しておきましょう。
まとめ
今回は、27卒の皆さんに向けて、Googleの本選考スケジュールから選考フロー、そして突破するための重要なポイントまで、幅広く解説してきました。
Googleの選考は、外資系企業の中でも特に準備が求められる、長丁場で難易度の高いプロセスであることは間違いありません。
しかし、その分、求められる人物像は明確です。
Googleの価値観への深い共感、論理的な問題解決能力、そして「Googliness」を、具体的なエピソードと言葉で示すこと。
これらを徹底的に準備することが、合格への最短距離となります。
インターンに落ちてしまったとしても、本選考でリベンジするチャンスは十分にあります。
大切なのは、早くから情報をキャッチアップし、自分自身の経験を深く掘り下げ、Googleという企業と真剣に向き合うことです。
この記事が、皆さんのGoogleへの挑戦を後押しする一助となれば幸いです。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート