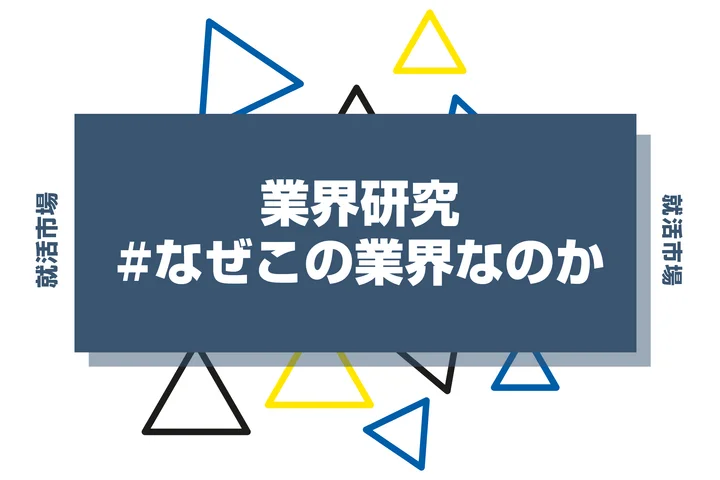はじめに
業界研究をしたが、その内容が面接官に浅いと思われてしまっているのではないか心配である。
業界研究をして就職活動を終えた先輩と議論したが、業界研究が浅いと言われてしまった。
そんな人を対象に面接官に「浅い!」と言われない業界研究は何が違うかをお教えします。
業界研究のそもそもの目的とは
就活を始める最初の一歩は業界研究です。
もっとも、やりたい仕事や希望する職種、入りたい企業がすでに決まっている方は業界研究は必要ないと省略したくなるかもしれません。
ですが、このプロセスを省くと、面接官から仕事に関する考え方や理解が浅い人と思われてしまいます。
なぜ、業界研究をする必要があるのか、その目的をしっかり理解しましょう。
志望業界を絞るため
やりたいことが定まっていない方やあれもこれも興味があると迷っている方にとっては、志望業界を絞るために役立ちます。
志望業界における勢力図や志望する企業のシェアやライバル関係の知識も得ることで、自分がどのように志望企業に貢献していけばよいのかなど、志望動機や自己PRを作る際にもより深い話ができるようになるのもメリットです。
志望業界の中に数ある企業の中で、なぜ他社ではなく自社を選んだのか、面接官が知りたい理由にしっかりと答えるためにも、業界研究は欠かせません。
知らない業界を知るため
業界研究はやりたい仕事の業界だけでなく、周辺業界や他の業界も含めて行うことがオススメです。
自分が知らない業界の中に、よりあなたのニーズに合う仕事や職種が見つかることも多いです。
自分がチャレンジしたいことが、漠然と志望していた業界より、別の業界でより自分の理想の形で実現できることを知る機会にもなります。
また、志望する業界との関連性などを知ることで、志望業界についてより深い知識を得ることもできます。
他の業界とのつながりやライバル業界などの知識を得て話をすることができれば、面接官にも業界の立ち位置をよく理解していると納得させることができるでしょう。
志望業界の知識を得るため
志望業界を絞り込んでいる方にとっては、より深い知識を得るための時間になります。
志望するからには何らかの興味やこの仕事がしたいというきっかけがあったはずです。
ですが、それだけに囚われて、すべてをわかった気になってはいけません。
たとえば、保険会社の営業職になりたい方は、保険といえば営業のイメージしか持てなくなる方がいます。
ですが、保険会社には保険の商品を開発する仕事、保険商品を金融庁に申請する仕事、保険の引き受けをする仕事や支払いをする仕事、契約の事務手続きを担う仕事や契約後の保全などを担う仕事など、多彩な仕事があります。
業界についてあらゆる角度から知識を備えることで、自分がやりたいと考える仕事の位置付けを明確にし、自分がどう企業に貢献できるかをよりしっかり伝えられるようになります。
業界研究が浅いとはどういうことか?
浅い業界研究とはそもそもどんな業界研究結果でしょうか。
私自身が何度も就活性の相談にのっていて感じた実例ベースでご紹介します。
浅い業界研究結果から導き出された志望動機集
この中に、あなたの業界研究結果に近い志望動機はありませんか?
- 私が御社、コンサルティング企業を志望するのは、企業の大きな問題を解決したいからです。
コンサルティング業界は企業の大きな問題を解決するチャンスがあふれていると考えており、チャレンジの機会がたくさんあると考えております。
- 私が○○商事株式会社を志望するのは、世界を股にかけるビジネスを手掛けたいからです。
なぜなら学生時代から海外旅行などにも何度も行っており、海外と日本をつなぐ橋渡しがしたいからです。
- 私が御社、ITスタートアップ企業を志望するのは成長できると考えるからです。
スタートアップ企業は膨大なタスクを少ない人数で賄う必要があるため、とても成長できると考えています。
上記の志望動機は何が浅いのでしょうか。
少し時間をとって考えてみてください。
浅い理由が分かったら、次は浅くない志望動機に考え直してみてください。
業界研究が浅い実例とその理由
さて、前の章で浅い志望動機を確認していただき、その理由を考えていただきました。
答えが出た方はおめでとうございます。
自分の志望動機もそうならないように、業界研究結果を活用してください。
答えが出なかった方は残念ながら答えが出た方と既に差がついています。
その差を埋められるように下記の解答を見て努力しましょう。
下記では、先ほどの志望動機に関して1つ1つコメントしていきます。
そのコメントを確認して、自分の志望動機にも同じことが当てはまらないか注意してください。
- 私が御社、コンサルティング企業を志望するのは、企業の大きな問題を解決したいからです。
コンサルティング業界は企業の大きな問題を解決するチャンスがあふれていると考えており、チャレンジの機会がたくさんあると考えております。
- コメント
コンサルティング企業が企業の大きな問題を解決することは仕事というのは、「そうですよね。」という感じで業界研究でも何でもない認識。
次に「企業の大きな問題を解決機会が多いから、チャレンジの機会がたくさんある」と言っている。
これも、「そうですよね」という感じで業界研究でも何でもない認識です。
- 修正例
コンサルティングは企業の大きな課題を解決する機会が多い。
それは顧客との対話を通じて解決が必要で、問題解決能力と対話力、コミュニケーション能力などの多岐にわたる能力が必要だと私は考えている。
それらの多岐にわたる能力を同時に鍛えられる業界はコンサルティングの他にないと考えているため、私は御社を志望する
- 修正内容
コンサルティングは企業の大きな課題を解決する機会が多いと言っているが、それにはどのような能力が求められるのかを一段深堀りしています。
また、コンサルティングでなければいけない。という主張に変更しました。
※チャレンジの機会がたくさんある企業・業界であれば多岐にわたるため
- 私が○○商事株式会社を志望するのは、世界を股にかけるビジネスを手掛けたいからです。
なぜなら学生時代から海外旅行などにも何度も行っており、海外と日本をつなぐ橋渡しがしたいからです。
- コメント
典型的な浅い業界研究結果と言われかねない内容です。
というのも、世界を股にかけるビジネスを手掛けたいというのは、商社のHP等にも記載されていそうな内容であり特に業界研究をしなくても導き出せそうですよね。
海外旅行に何度もということも、事象を述べているだけであり、志望動機とのつながりは見えないです。
- 修正例
私が○○商事株式会社を志望するのは、海外と日本をつなぐ架け橋になることができると考えるためです。
なぜならば、御社のビジネスは日本の長所を海外に輸出し、海外の長所を日本に取り込むものだと考えているためです。
そのビジネスに参加したい理由としては、自分が学生時代に発展途上国に行き、現地の技術やノウハウだけでは解決できない問題がたくさんあり、解決したいと考えたこと。
また日本にはないが、海外が進んでいる技術も多くみたため、それを日本に輸入し、日本を豊かにする手助けをしたいと考えているためです。
- 修正内容
自分の体験を深堀りしました。
コンサルティングの事例もそうでしたが、自分の記載が浅くないかを確認するうえで、主張の深堀りができないかは検討してみてください。
- 私が御社、ITスタートアップ企業を志望するのは成長できると考えるからです。
スタートアップ企業は膨大なタスクを少ない人数で賄う必要があるため、とても成長できると考えています。
- コメント
俗に言われる意識高い系のような人が解答してしまいそうな内容ですね。
面接官をしている際にこのコメントをされた場合は、「意識高い人来たな」「なんか志望動機も浅いし、特に面接を通過させる理由もないか」と自分が面接官だったら考えてしまいそうな内容です。
※筆者は就活生を評価する機会や経験があります
- 修正例
私が御社、ITスタートアップ企業を志望するのは成長できると考えるからです。
具体的にはIT企業は情報のアップデートのスピードが早いと考えており、常に最新の情報をキャッチアップしていく必要があると考えるためです。
またIT業界で働いた知識は他業界にも転用可能であると考えており、多業界にも通じる万能なスキルを習得できると考えております。
またスタートアップ企業は膨大なタスクを少ない人数で賄う必要があるため一人一人の視野、権限が広く他企業よりも早いスピードで企業を動かしていく能力を身に着けることができると考えています。
- 修正内容
もともとの文章ではスタートアップ企業で習得できる内容のメリットは記載がありましたが、IT企業の面は触れられておりませんでした。
そのためIT企業のメリット、スタートアップ企業のメリットの両方に関して記載するようにしました。
業界研究を浅いと思わせないためにやるべき3つのこと
就活において業界研究は志望動機の土台となる重要なプロセスです。
しかし調査が浅いと表面的な回答しかできず、採用担当者に納得感を与えられません。
そこで意識すべきは「この業界を選んだ理由を整理する」「なぜこの業界かを自分の言葉で語る」「他社との違いを比較して説明する」という3つの観点です。
これらを押さえることで、業界への理解の深さや本気度を効果的にアピールでき、志望動機の説得力を高められます。
この業界を選んだ理由を整理する
まず取り組むべきは、自分がなぜその業界に関心を持ったのかを明確にすることです。
漠然と「人気があるから」や「安定しているから」では、業界研究が浅いと見なされやすくなります。
大学で学んだ分野やこれまでの経験、価値観と関連付けて整理することで、一貫性のある志望理由に結び付けられます。
例えば、研究やアルバイトを通して得た学びが業界の課題解決にどう役立つかを考えると具体性が増します。
選んだ理由を整理することは自己分析と業界研究を結び付ける重要なステップであり、面接での回答に説得力を与えます。
なぜこの業界かを自分の言葉で語れるようにする
次に重要なのは、なぜその業界を志望するのかを自分の言葉で表現できるようにすることです。
ネットや参考書の情報をそのまま使うと、誰でも答えられるような印象を与えてしまいます。
実際に企業説明会やOB訪問で得た具体的な情報を交え、自分なりの視点を加えて話すことが差別化につながります。
また、業界の社会的役割や将来性を踏まえて、自分がどう貢献できるかを明確にすると説得力が高まります。
自分の言葉で語る姿勢は誠実さを感じさせ、選考担当者にポジティブな印象を与える大切なポイントです。
他社との違いを比較して説明できるようにする
最後に欠かせないのは、同じ業界に属する他社との違いを理解し、比較できるようにしておくことです。
どの企業にも共通する一般的な魅力だけで志望理由を語ると、説得力が弱まりがちです。
そのため、業界全体の特徴を踏まえつつ、対象企業が持つ強みや独自性を見極めることが必要です。
例えば、事業領域の広さ、海外展開の実績、技術力、働き方改革の取り組みなど、企業ごとに異なる点を把握すると差別化が可能になります。
他社との違いを比較する力を持つことで、業界全体を理解しているだけでなく、企業研究も進んでいると評価されます。
この業界を選んだ理由の回答例5つ
業界研究を進めるうえで、自分がなぜその業界を志望するのかを明確に答えられることが重要です。
ここでは就活生が実際に使える具体的な回答例を5つ紹介します。
回答例を参考にしつつ、自分の経験や価値観と関連づけてカスタマイズすることで、オリジナリティのある志望動機を作ることができます。
社会貢献度の高さに魅力を感じた回答例
私は人々の生活を支える社会インフラに携わりたいと考え、この業界を志望しています。
特に日常生活に直結するサービスを提供している点に大きな魅力を感じています。
大学で学んだ知識を生かしながら、社会全体の利便性を高める取り組みに関わりたいと考えています。
業界全体として公共性が高く、多くの人に影響を与えられる点が自身の価値観と一致しているため、この業界を選びました。
成長性と将来性を重視した回答例
私は変化の激しい時代の中で成長を続ける業界に身を置きたいと考えています。
特にこの業界は技術革新や市場拡大の可能性が大きく、今後も社会における重要性が高まると感じました。
自分のキャリアを通じて業界の発展に貢献できることにやりがいを見出しています。
常に挑戦が求められる環境に身を置くことで、自身の成長も加速させたいと考え、この業界を選びました。
自分の経験との関連を示した回答例
私は大学での研究活動を通じて、この業界に深い関心を持つようになりました。
特に研究で扱ったテーマが業界の課題解決に直結しており、自分の学びを実務に生かせると確信しました。
経験を踏まえて業界全体に還元できるスキルを培いたいと考えています。
これまでの取り組みと将来のキャリアがつながる点に強い魅力を感じ、この業界を志望しました。
人との関わりを重視した回答例
私は人と直接関わり、その成長や生活を支援できる環境に魅力を感じています。
この業界は顧客や利用者と向き合いながら価値を提供する機会が多く、仕事を通じて社会貢献を実感できると考えています。
人との信頼関係を築きながら成果を上げる働き方が、自分の強みを発揮できる場になると確信しています。
そのため、この業界でのキャリアを志望しました。
グローバルな視点を意識した回答例
私は国際的な舞台で活躍できる環境に強い関心を持っています。
この業界は海外展開やグローバルビジネスの機会が多く、多様な文化や価値観に触れながら働ける点に魅力を感じました。
大学での留学経験や語学力を生かし、世界規模の事業に携わりたいと考えています。
国際社会に貢献できる点にやりがいを見出し、この業界を志望しました。
この業界を選んだ理由のNG回答例3選
業界研究を行っていても、回答の仕方によっては浅く見られてしまう場合があります。
ここでは避けるべきNG回答例を紹介します。
採用担当者にマイナスの印象を与える回答は信頼を損なうため、注意が必要です。
安定しているからという単純な理由
この業界は安定しているから志望しますといった回答は説得力に欠けます。
誰にでも言える理由であり、自分とのつながりが全く見えないため、印象が薄くなります。
具体的なエピソードや価値観と結びつけなければ、業界理解が浅いと判断されてしまいます。
給与や待遇面だけを強調する理由
給与が高いから志望しますという回答は、志望度の低さを疑われやすいです。
待遇だけに焦点を当てた志望動機では、業界で働く意欲や将来の展望が伝わりません。
働く目的が自己利益のみと受け取られる可能性があるため避けるべきです。
漠然とした人気や知名度を理由にする回答
有名だからという回答は業界研究をしていない証拠と見られます。
知名度に依存した志望動機は浅く、志望度が高いとは受け取られません。
具体的な理解や自分との関連性を示さない限り、説得力のある回答にはなりません。
なぜこの業界かを答える時のポイント3つ
なぜこの業界かと問われた際、納得感を持たせるためにはポイントを押さえる必要があります。
ここでは特に重要な3つを紹介します。
意識的に取り入れることで回答の質が向上し、採用担当者に強い印象を与えることができます。
業界の特徴と自分の経験を結びつける
自分の経験や学びが業界でどのように活かせるかを具体的に説明することが大切です。
抽象的な表現ではなく、自分ならではのストーリーを交えることで説得力が増します。
その結果、志望動機の一貫性が強調されます。
将来のビジョンを含める
志望理由に将来の展望を盛り込むことで、長期的に業界で活躍する意思を示せます。
自分がどのように業界に貢献していくかを明確にすることで、具体性のある回答になります。
継続的な成長意欲をアピールできるため、面接官にポジティブな印象を与えます。
企業ごとの差別化を意識する
業界全体の魅力だけでなく、志望する企業特有の強みにも言及することが重要です。
その企業でなければならない理由を語ることで、説得力が増します。
差別化を意識することで志望度の高さを示すことができます。
なぜこの業界かを答える時の回答例5つ
なぜこの業界を選んだのかを答える際には、自分の価値観や経験に基づいた具体的な理由が必要です。
ここでは参考になる回答例を5つ紹介します。
志望業界ごとに自分に合った表現へアレンジすることで活用できます。
技術革新に挑戦したい回答例
私は新しい技術を取り入れながら社会を変革していくこの業界に大きな魅力を感じています。
変化の速い環境に身を置き、自分自身の成長とともに社会に影響を与えられることにやりがいを感じています。
技術的な知識を磨き、実務で活かすことで業界の発展に貢献したいと考えています。
人々の生活を支える回答例
私は人々の生活基盤を支える役割を担うこの業界に強い魅力を感じています。
日常に直結するサービスを通じて多くの人に貢献できる点にやりがいがあります。
社会的な責任の大きさを意識し、自分の力を最大限発揮したいと考えています。
グローバルな環境で働きたい回答例
私は国際的な舞台で働くことに関心があり、この業界の海外展開に魅力を感じています。
語学力や異文化理解を活かして、世界規模での事業に貢献したいと考えています。
グローバルな視点を持つことで、多様な価値観を受け入れながら成長したいと思っています。
人との関係性を重視する回答例
私は人と直接関わりながら価値を提供できるこの業界に魅力を感じています。
顧客や利用者と信頼関係を築きながら成果を上げる仕事にやりがいを見出しています。
人との関わりを通じて社会に貢献できる点が、自分の目指すキャリアと一致しています。
社会課題解決に取り組みたい回答例
私は社会課題の解決に直接携われるこの業界に強い関心を持っています。
大学での学びを生かし、環境や福祉など多様な分野で貢献できる点に魅力を感じています。
自分の知識と行動を社会のために役立てることを目標に、この業界を志望しました。
なぜこの業界かを答える時の注意点
なぜこの業界かと問われた際には、伝え方によって印象が大きく変わります。
ここでは注意すべき点を3つ紹介します。
意識して回答を準備することで、浅い業界研究と見なされるリスクを防げます。
抽象的な表現だけに頼らない
社会に貢献したいなどの抽象的な表現だけでは説得力がありません。
具体的な経験や学びを交えて、自分なりの理由を示すことが大切です。
採用担当者に納得感を与えるためには、具体性を意識する必要があります。
情報の受け売りにしない
説明会やサイトで見た情報をそのまま答えると浅い印象を与えます。
必ず自分の言葉に置き換え、体験や価値観と関連づけて答えることが求められます。
自分なりの考えを盛り込むことで志望度の高さを示せます。
企業と業界の違いを混同しない
業界全体の志望理由と企業特有の志望理由を混同すると一貫性がなくなります。
業界としての魅力と、企業としての強みを分けて語ることが重要です。
両方を整理して答えることで説得力のある志望動機になります。
まとめ
業界研究を深めることは、説得力のある志望動機を作成する上で不可欠です。
この業界を選んだ理由やなぜこの業界かを自分の言葉で語れるようにし、具体例や将来ビジョンと結びつけることが大切です。
浅い業界研究にとどまらず、自分の経験や価値観と関連づけた回答を準備することで、選考で高い評価を得られる可能性が高まります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート