今回は、就活生から絶大な人気を誇る「富士フイルム」の冬インターンシップについて、徹底的に解説していきます。
富士フイルムは、写真フィルムのイメージが強いかもしれませんが、現在ではヘルスケアや高機能材料など、多岐にわたる事業を展開するグローバル企業です。
そんな富士フイルムのインターンは、企業理解を深めるだけでなく、本選考にも影響する可能性があるため、非常に注目度が高いです。
この記事では、インターンの実施時期や具体的な内容、選考フロー、そして気になる倍率や突破のコツまで、皆さんが知りたい情報を余すところなくお届けします。
ライバルに差をつけるためにも、ぜひ最後まで読んで準備を進めてくださいね。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの企業情報
まず、富士フイルムがどのような会社なのか、基本情報を押さえておきましょう。
富士フイルムホールディングスの中核を担う企業で、その歴史は写真フィルムから始まりました。
しかし、デジタル化の波を見事に乗り越え、長年培ってきた技術力を応用し、現在は大きく「ヘルスケア」「マテリアルズ」「イメージング」の3つの領域で事業を展開しています。
特にヘルスケア分野では、医薬品や医療機器、再生医療といった領域で目覚ましい成長を遂げており、社会貢献性の高さも魅力の一つです。
また、「Value from Innovation」をスローガンに掲げ、常に新しい価値を創造しようとする企業文化があります。
伝統と革新を併せ持つ、非常に将来性のある企業として、多くの就活生から人気を集めているのです。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの冬インターンはいつ実施される?
富士フイルムの冬インターンは、例年、大学3年生や修士1年生の冬休み期間(1月〜2月頃)に実施されることが多いです。
この時期は、就職活動が本格化する直前であり、志望業界や企業を絞り込む上で非常に重要なタイミングと言えます。
募集開始はそれよりも早く、秋頃(10月〜11月頃)からエントリーが始まるのが一般的です。
人気のインターンは応募が殺到し、すぐに締め切られてしまうことも少なくありません。
そのため、富士フイルムを少しでも視野に入れている人は、秋になったらこまめに企業の採用ページや就活情報サイトをチェックし、募集要項を見逃さないようにすることが肝心です。
早めの情報収集と準備が、冬インターン参加への第一歩となります。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの冬インターンの内容
富士フイルムの冬インターンは、職種やテーマ別に複数のコースが用意されているのが特徴です。
どのコースも、単なる会社説明会とは異なり、実践的なワークや社員との交流を通じて、富士フイルムの事業や社風を深く理解できるように設計されています。
技術系の学生向けには、最先端の研究開発に触れられるプログラムが、事務系の学生向けには、マーケティングや事業戦略を体感できるプログラムが用意される傾向にあります。
いずれのコースも参加できる人数は限られており、選考を突破する必要がありますが、その分、得られる経験は非常に濃密なものになるでしょう。
ここでは、代表的なコースの内容について、具体的に見ていきましょう。
事務系コースのインターン内容
事務系コースでは、主にマーケティング、営業、経営企画といった職種の仕事を体験できるプログラムが中心です。
例えば、「新規事業立案ワークショップ」や「既存事業の課題解決ケーススタディ」などが挙げられます。
これらのワークでは、数人のグループに分かれ、富士フイルムが実際に直面しているようなリアルな課題に取り組みます。
社員の方がメンターとしてサポートしてくれるため、現場の社員と同じ視点で物事を考える訓練ができます。
最終日には役員や幹部社員の前でプレゼンテーションを行う機会もあり、実践的なフィードバックをもらえるのが大きな魅力です。
論理的思考力やチームワークが試される、非常にやりがいのある内容となっています。
技術系コースのインターン内容
技術系コースは、富士フイルムの強みである研究開発や生産技術の現場を深く知ることができる内容です。
多くの場合、参加者の専攻や希望に合わせて、特定の研究テーマや技術分野に分かれて実習が行われます。
例えば、AI技術を活用した画像解析、高機能材料の開発プロセス、再生医療の研究サポートなど、最先端の技術に触れられるのが最大の魅力です。
研究所や工場の見学だけでなく、実際に研究者やエンジニアの指導のもとで実験やデータ解析を行うこともあります。
現場で活躍する社員と直接ディスカッションする時間も豊富にあり、自分の専門性がどのように社会で活かせるのかを具体的にイメージできる、理系学生にとって見逃せない機会です。
デザイン系コースのインターン内容
富士フイルムでは、製品のデザインやUI/UXデザインを担当するデザイナー職のインターンも実施されることがあります。
このコースでは、同社のデザインフィロソフィーを学びながら、実践的なデザインワークに取り組みます。
単に見た目を美しくするだけでなく、「ユーザーにとっての価値は何か」を深く掘り下げるプロセスを重視しているのが特徴です。
現役のデザイナーから直接指導を受けながら、コンセプト立案からプロトタイピングまでの一連の流れを体験できます。
自分の作品に対して具体的なフィードバックをもらえるため、デザイナーとしてのスキルアップにも直結します。
デザイン思考を実践的に学びたいと考えている学生にとっては、非常に貴重な経験となるでしょう。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの冬インターンの選考フロー
富士フイルムの冬インターンに参加するためには、厳しい選考を通過する必要があります。
選考フローはコースによって若干異なる場合がありますが、一般的には「エントリーシート(ES)の提出」と「Webテストの受検」、そして「面接」という流れが基本です。
ESでは、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)に加え、「なぜ富士フイルムのインターンに参加したいのか」という志望動機が非常に重視されます。
Webテストは、SPIや玉手箱など、一般的な形式のものが採用されることが多いです。
面接は、オンラインでのグループディスカッションや個人面接が実施される傾向にあります。
人気企業ゆえに選考ステップも多く、それぞれの段階でしっかりと対策を練ることが合格の鍵となります。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの冬インターンの倍率
富士フイルムの冬インターンは、その企業人気とプログラムの充実度から、毎年非常に高い倍率となっています。
具体的な倍率は公表されていませんが、本選考同様、あるいはそれ以上に狭き門であると覚悟しておいた方がよいでしょう。
特に技術系やデザイン系の専門職コースは、募集枠自体が少ないため、競争は熾烈を極めます。
早期から企業研究と自己分析を進め、万全の準備で臨まなければ、選考を通過することは難しいのが現実です。
この高い倍率を突破するためには、他の就活生との差別化を図る明確な戦略が必要になります。
次のセクションで、そのための具体的なコツを詳しく見ていきましょう。
NTIの冬インターンに受かるコツ
このNTI(※便宜上、富士フイルムのインターンを指すものとして解説します)のような難関インターンに受かるためには、付け焼き刃の対策では通用しません。
まず最も重要なのは、「なぜ富士フイルムでなければならないのか」を自分の言葉で明確に語れるようにすることです。
同社の多岐にわたる事業の中で、特にどの分野に魅力を感じ、自分の経験や強みをどう活かしたいかを具体的に結びつける必要があります。
そのためには、徹底した企業研究と自己分析が不可欠です。
ESや面接では、インターンで何を学びたいのか、その経験を将来どう活かしたいのかという未来志向のビジョンを熱意を持って伝えましょう。
ありきたりな志望動機ではなく、あなた自身の「個」が伝わるエピソードを盛り込むことが、選考突破の鍵となります。
【富士フイルムの冬インターン】富士フイルムの冬インターンは本選考優遇あり?
就活生の皆さんにとって、インターン参加が本選考にどう影響するかは、非常に気になるところですよね。
結論から言うと、富士フイルムの冬インターンは、本選考への優遇措置につながる可能性が高いと考えられます。
インターンシップでのパフォーマンスが優秀だと認められた場合、早期選考の案内が来たり、本選考の一次面接が免除されたりといったケースが過去にもあったようです。
ただし、注意点もあります。
まず、優遇が「確約」されているわけではないこと。
そして、優遇を得るためには、インターン期間中の積極的な姿勢や成果が求められるということです。
単に参加するだけではなく、グループワークでリーダーシップを発揮したり、鋭い質問をしたりするなど、社員の方に「この学生と一緒に働きたい」と思わせるような活躍が重要になります。
【富士フイルムの冬インターン】まとめ
今回は、富士フイルムの冬インターンについて、企業情報から選考のコツ、本選考への影響まで幅広く解説してきました。
富士フイルムは、革新的な技術力と多角的な事業展開で、世界を舞台に活躍する優良企業です。
そのインターンシップは、会社のリアルな姿を知る絶好の機会であると同時に、非常に競争率の高い狭き門でもあります。
参加を勝ち取るためには、早期からの徹底した企業研究と自己分析が欠かせません。
この記事で紹介したポイントを参考に、しっかりと準備を進めてください。
インターンで得られる経験は、皆さんの就職活動、そして将来のキャリアにとって、間違いなく大きな財産となるはずです。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート



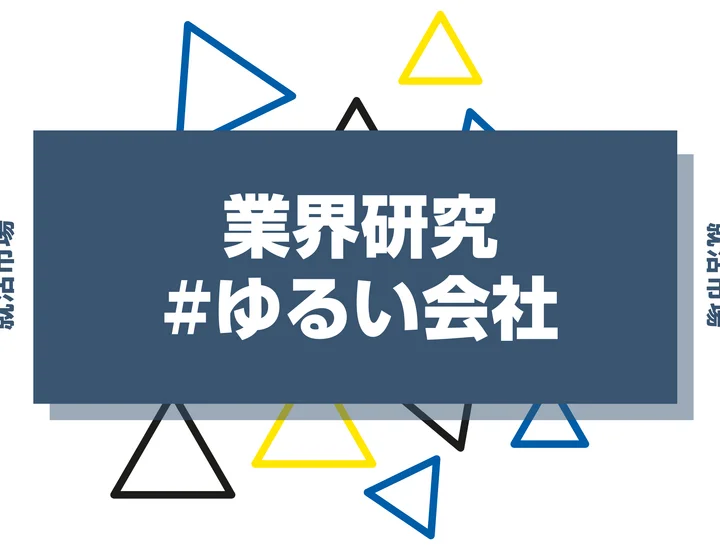







_720x550.webp)