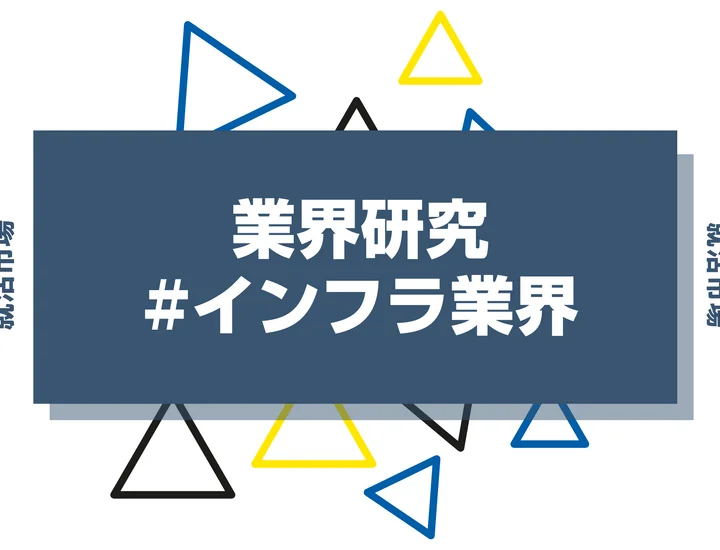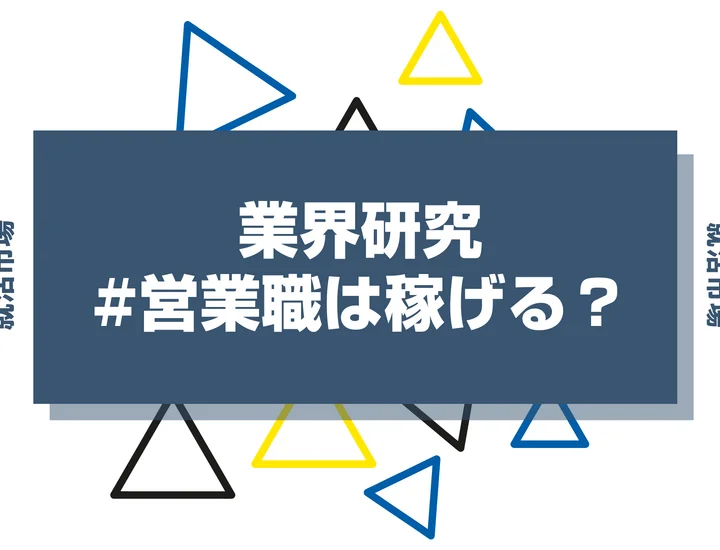イベント業界は、音楽ライブや展示会、スポーツ大会といった多種多様な催しを通じて、人々に非日常的な体験と感動を提供する魅力的な仕事です。
華やかな舞台の裏側では、緻密な企画力、関係者をまとめる調整力、そして予期せぬ事態に対応する柔軟性が求められます。
この業界を目指す就活生の皆さんは、そのキラキラしたイメージだけでなく、仕事の厳しさや求められるスキルについても深く理解しておくことが重要です。
本記事では、イベント業界の全体像を明らかにするため、ビジネスモデルや市場の動向、具体的な仕事内容、そして業界で活躍するために必要な適性まで、幅広く、そして具体的に解説していきます。
目次[目次を全て表示する]
イベント業界とは
イベント業界への就職を考えるなら、まずはこの業界がどのように成り立っているのか、その仕組みを正確に理解することが不可欠です。
多くの企業や専門家が関わり合って一つのイベントを創り上げるこの業界は、独特のビジネスモデルと収益構造を持っています。
ここからは、イベント業界の「リアル」を解き明かすための基本的な知識を解説していきます。
ビジネスモデル
イベント業界のビジネスモデルは、BtoB(企業向け)とBtoC(一般消費者向け)の二つの側面を持ち、収益構造も多岐にわたります。
BtoBイベントの代表例は、企業が出展する展示会や新商品発表会、国際会議などです。
これらの主な収益源は、出展企業から得られる出展料や協賛金、そしてイベント全体の企画・運営を受託することによる企画費や運営管理費です。
一方、BtoCイベントには、音楽フェスやコンサート、スポーツの試合、地域のお祭りなどが含まれます。
こちらの収益の柱は、参加者からのチケット収入や、会場で販売されるグッズの売上、そしてイベントのブランド価値を活用した広告費などです。
近年では、オンライン配信を組み合わせたハイブリッドイベントも増えており、有料の配信チケットやデジタルコンテンツ販売など、新たな収益モデルも確立されつつあります。
市場規模と業界の成長性
あなたが志望する業界の市場規模と成長性も理解しておきましょう。
面接で志望動機を伝える際、説得力のある回答ができるからです。
まず、イベント業界の市場規模は一般社団法人日本イベント産業振興協会が2024年に公表したデータによると、コロナ禍で約2.6兆円から、1.1兆円まで落ち込みました。
しかし、近年ではコロナが落ち着いたことで、ほぼ同水準にまで回復しています。
また、イベント業界の市場規模は右肩上がりが予想されます。
2025年は大阪で万博が開催され、大きな賑わいを見せているからです。
来年には野球の世界一を決めるWBCが開催されます。
ほかにもサッカーのW杯もあるため、スポーツイベントは大いに盛り上がるでしょう。
つまり、2025年以降もイベント業界は成長を続ける可能性が高いです。
イベント業界市場規模推移
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 総計(億円) | 26,136 | 11,896 | 14,999 | 20,804 | 26,337 |
参考:2023年イベント産業規模推計|一般社団法人日本イベント産業振興協会
平均年収と労働環境
厚生労働省が運営するjobtagによると、イベントの企画・運営に携わる人の平均年収は690.7万円です。
国税庁が公表している日本人の平均年収は460万円です。
つまり、イベント業界の年収は高水準にあることが予想できます。
ただし、企業の事業規模や賞与の有無などによって、年収は大きく変わります。
あなたが志望する企業の年収がどれくらいなのかは、事前にチェックしておきましょう。
また、イベント業界の労働環境は不規則です。
イベントの本番が土日にあれば、週末も出勤する必要が生まれます。
さらに、当日が近づくほど業務量が多くなり、残業時間も増えるでしょう。
「定時に必ず退社したい」「土日は休みたい」と考える就活生には合わない可能性があります。
参考:職業情報提供サイトjobtag|厚生労働省
参考:令和5年分 民間給与実態統計調査
就職難易度と採用傾向
イベント業界は、その華やかなイメージから就活生に非常に人気が高く、特に大手広告代理店系のイベント制作会社や有名イベントを多数手掛ける企業は、極めて高い倍率になることが予想されます。
そのため、就職難易度は全体的に高いと言えるでしょう。
採用選考では、単なる「イベントが好き」という熱意だけでは不十分で、なぜこの業界でなければならないのか、そして入社後にどのように貢献できるのかを具体的に示すことが求められます。
特に重視されるのが、学生時代に主体的に何かを企画し、周囲を巻き込みながら実行した経験です。
面接では、その経験の中でどのような困難があり、どう乗り越えたのかを自分の言葉で語れるかどうかが評価の分かれ目となるでしょう。
イベント業界に向いている人の特徴
イベント業界は、その華やかなイメージとは裏腹に、泥臭い努力や臨機応応変な対応力が求められる、非常にタフな仕事です。
そのため、誰もが活躍できるわけではなく、この業界ならではの特殊な環境に適応できる特定の素養が求められます。
ここでは、イベント業界で生き生きと働き、大きな成果を上げている人々に共通する3つの特徴を解説します。
人を喜ばせることにやりがいを感じる人
イベント業界の仕事の根幹にあるのは、「誰かを楽しませたい、喜ばせたい」という純粋な想いです。
自分の仕事の成果は、給与や役職といった形だけでなく、来場者の笑顔や感動の声、SNSでのポジティブな反響といった形で現れます。
そのため、他者の喜びを自分自身の喜びとして心から感じられるホスピタリティ精神の持ち主は、この業界に非常に向いています。
イベントの準備期間は、地味で大変な作業の連続です。
しかし、「この先に待っている来場者の笑顔のためなら頑張れる」と思えるかどうかが、大きな分かれ道となります。
自分の働きが、誰かの幸せな時間や忘れられない思い出に繋がっているという実感に、何よりも大きな価値を感じられる人にとって、イベント業界は最高の舞台となるでしょう。
臨機応変に対応できる柔軟な人
イベントの現場は「生物」です。
どれだけ入念に準備をしても、当日は予期せぬトラブルが必ずと言っていいほど発生します。
そんな時、マニュアル通りの対応しかできずにパニックに陥ってしまう人では、現場を任せることはできません。
予期せぬ事態に直面しても、冷静に状況を分析し、その場で最善の解決策を判断し、すぐに行動に移せる「臨機応変な対応力」が不可欠です。
この能力は、単なるスキルというよりも、一種の「胆力」や「メンタルの強さ」と言えるかもしれません。
常に複数の選択肢を考え、プランB、プランCを用意しておく周到さと、何が起きても動じない柔軟な思考を持つ人が、この業界では高く評価されます。
チームでの協働を楽しめる人
イベント制作は、個人の力だけで完結することは決してありません。
企画、制作、技術、運営、広報など、様々な専門分野のプロフェッショナルが数十人、時には数百人規模で関わる壮大なチームプロジェクトです。
そのため、自分の意見を主張するだけでなく、異なる立場の人の意見にも真摯に耳を傾け、尊重し、チーム全体の目標達成のために協力できる「協調性」が極めて重要になります。
自分一人で黙々と作業を進めたい、自分のやり方だけで物事を進めたいというタイプの人は、この業界の働き方にストレスを感じるかもしれません。
むしろ、多様な才能を持つ仲間たちと議論を重ね、互いの強みを活かしながら一つのものを創り上げていくプロセスそのものを楽しめる人が、この業界で輝くことができます。
チームの一員としての自覚を持ち、周囲への感謝とリスペクトを忘れずにコミュニケーションを取れる力が、プロジェクトを成功に導く鍵となるのです。
最後まで責任を持って取り組める人
イベントに携わる人は、最後まで責任を持って取り組む必要があります。
イベントは無事に成功して初めて価値が生まれるからです。
とくに長期間にわたって準備が必要になるイベントは、集中力を切らさず取り組む姿勢が求められます。
たとえば、学園祭の実行委員を最後まで務めた経験があれば、イベント業界に向いている可能性があるでしょう。
ほかにも、アルバイトで指示された仕事を完璧に遂行した経験も有効です。
自己分析の結果、責任感が強みだと自覚した就活生は、自信を持ってエントリーしましょう。
プレッシャーがある中でも成果を残した経験や人の期待に応えることにやりがいを感じる人は、イベント業界で活躍できます。
体力に自信がある人
イベントを成功に導くには体力も必要です。
イベントの当日は、会場を走り回ることがあります。
たとえば、会場設営や備品の移動などです。
受付を担当すれば、1日立ちっぱなしになることもあるでしょう。
さらに、予期せぬトラブルがあれば、じっと座るタイミングがない可能性があります。
イベントを企画する段階では、斬新なアイデアや柔軟な発想が求められます。
しかし、企画を実行に移す段階になれば、人手が必要です。
ただし、ムキムキの筋肉が必須なわけではありません。
台車やトラックなどをうまく活用することで、必要な体力を軽減できます。
学生時代にスポーツを経験した人や日頃から運動している人は、イベント業界で活用できるでしょう。
好奇心が旺盛な人
イベント業界は、流行を押さえる必要があるため、好奇心旺盛な人が向いています。
海外でブームになっている競技や商品、音楽などを日本に持ち込むことで、独自性のあるイベントにすることが可能です。
さらに、日本の文化や価値観を加えることで、より日本人向けになるでしょう。
つまり、現状のイベントに満足せず、情報収集する人は活躍できる可能性が高いです。
好奇心のアンテナは、さまざまな角度に設置しましょう。
1つの方向だけでは情報に偏りが生まれます。
あなたが所属する業界に加えて、隣接する分野やまったく関係のない範囲も網羅しましょう。
一見関係のないトレンドに感じても、自分の業務に結びつくアイデアが生まれる可能性があります。
イベント業界が取り扱う主なジャンル
「イベント」と一言で言っても、その内容は実に多岐にわたります。
多くの人がイメージする華やかな音楽ライブやフェスティバルはもちろんのこと、企業のビジネスを加速させる展示会や国際会議、さらには地域の活性化に貢献するお祭りやスポーツイベントまで、すべてがイベント業界のフィールドです。
自分がどのような価値を社会に提供したいのかを考えることが、業界理解の第一歩となります。
ここからは、イベント業界が手掛ける代表的なジャンルを3つに分けて紹介し、それぞれの特徴や仕事の魅力を解説していきます。
音楽・ライブ・舞台などのエンタメ系イベント
エンタメ系イベントは、イベント業界の中でも特に人気が高く、多くの就活生が憧れるジャンルです。
音楽ライブ、演劇、ミュージカル、ファンミーティングなど、アーティストや演者のパフォーマンスを最大限に引き出し、観客の感情を動かすことが最大のミッションとなります。
この分野で求められるのは、単にイベントを滞りなく進行させる運営能力だけではありません。
音響、照明、映像、特殊効果といった専門技術を駆使し、五感に訴えかける空間を創り出すクリエイティブな発想力や演出力が不可欠です。
観客が「また来たい」と感じるような感動的な体験や、SNSで思わずシェアしたくなるような記憶に残る仕掛けを企画することが、成功の鍵を握ります。
展示会・セミナーなどのビジネス系イベント
ビジネス系イベントは、企業の製品やサービスを紹介する展示会、業界の最新動向を共有するセミナーやカンファレンス、そして国際的な議論の場となる国際会議など、主にBtoB(企業間取引)の領域で展開されます。
このジャンルの目的は、エンタメ系とは異なり、新たなビジネスチャンスの創出や、企業のブランディング、業界の発展に貢献することにあります。
華やかさよりも、論理的な企画構成力や、出展者と来場者の双方にとって価値のある出会いの場をいかに設計するかが重要視されます。
一見地味に見えるかもしれませんが、自分が手掛けたイベントがきっかけで新たなイノベーションが生まれたり、企業の成長をダイレクトに支援できたりする点は、大きなやりがいと言えるでしょう。
地域・行政・スポーツなどの社会貢献型イベント
社会貢献型のイベントは、地域の活性化を目的としたお祭りや物産展、市民の交流を促進する文化・芸術イベント、そして大規模なスポーツ大会の運営などが含まれます。
このジャンルの最大の特徴は、営利目的だけでなく、地域社会への貢献や、文化の振興、スポーツを通じた健康増進といった公共性の高い目的を持っている点です。
仕事を進める上では、地方自治体や地域のNPO、商店街、そして多くのボランティアスタッフといった、多様な立場の人々と協力し合う必要があります。
そのため、利害関係の異なる人々の意見をまとめ上げ、一つの目標に向かってチームを導く高度な調整能力やコミュニケーション能力が求められます。
社会的な課題解決に直接的に関わり、多くの人々と一体感を感じながら地域を盛り上げていくことにやりがいを感じる人にとって、非常に魅力的なフィールドです。
イベント業界の企業・プレイヤーの種類
一つのイベントが成功裏に終わるまでには、実に多くの企業やプロフェッショナルが関わっています。
イベント業界を志望する際は、こうした様々なプレイヤーの役割を理解し、自分がどの領域でスキルを発揮したいのかを明確にすることが重要です。
自分が将来、イベント制作のどの部分で輝きたいのかをイメージするためにも、ここからは各プレイヤーの具体的な役割と特徴について詳しく見ていきましょう。
イベント企画・制作会社
イベント企画・制作会社は、まさにイベント業界の中核を担う存在です。
クライアントの要望をヒアリングし、「何を目的とし、誰に、どのような体験を届けるのか」というイベントの根幹となるコンセプトを策定します。
そして、そのコンセプトを基に、具体的なプログラムの構成、会場の選定、出演者のキャスティング、空間デザイン、演出プランなどを考え、企画書としてまとめ上げます。
この「アイデアを形にする」プロセスこそが、企画・制作会社の最大の魅力であり、最もクリエイティビティが問われる部分です。
プロジェクト全体の予算管理や進行管理も担当し、広告代理店や技術会社といった外部のパートナー企業を取りまとめる司令塔の役割も担います。
会場運営・設営会社
会場運営・設営会社は、イベント当日の「現場」を支える重要なプレイヤーです。
企画・制作会社が描いたプランを、現実の空間に安全かつ円滑に創り上げる役割を担います。
具体的な業務としては、ステージやブースの設営、音響・照明・映像機材のセッティング、電源や通信インフラの確保などが挙げられます。
イベント当日は、来場者の誘導や案内、受付業務、警備、そして万が一のトラブル発生時の対応など、運営全般を取り仕切ります。
広告代理店・プロモーション会社
どれだけ素晴らしい企画のイベントでも、その存在が世の中に知られ、人々が足を運んでくれなければ意味がありません。
広告代理店やプロモーション会社は、イベントの「集客」と「認知拡大」を担うマーケティングのプロフェッショナルです。
テレビCMや新聞広告、Web広告、SNSキャンペーンといった様々な手法を駆使して、ターゲットとなる層にイベントの魅力を効果的に伝えます。
単に広告を打つだけでなく、どのようなメッセージを発信すれば人々の心を動かせるか、どのメディアを使えばターゲットに届くのかを分析し、戦略を立てるのが彼らの腕の見せ所です。
舞台・照明・音響など技術専門会社
イベントの感動的な演出は、専門的な技術を持つプロフェッショナルたちの力によって支えられています。
舞台、照明、音響、映像といった各分野の技術専門会社は、まさに「職人集団」と言える存在です。
音響会社は、会場の隅々までクリアで迫力のあるサウンドを届け、ライブの熱狂を創り出します。
彼らは、イベントプランナーやディレクターの描く演出プランを、専門的な知識と技術、そして研ぎ澄まされた感性で具現化していく重要なパートナーです。
最新の機材に関する深い知識はもちろんのこと、現場での瞬時の判断力や対応力も求められます。
自分の持つ専門技術を突き詰めることで、他には真似できない唯一無二の感動体験を創り出せるのが、この仕事の最大の醍醐味です。
イベント業界の大手企業5選
イベント業界には、それぞれ異なる強みを持つ魅力的な企業が数多く存在します。
業界研究を深める第一歩として、まずは業界を牽引するリーディングカンパニーを知ることから始めましょう。
大手企業は、手掛けるイベントの規模や種類、そして働き方においても、その企業ならではの特徴を持っています。
ここでは、就活生の皆さんからの知名度も高く、それぞれに際立った個性を持つ大手企業を5社ピックアップして紹介します。
博報堂プロダクツ
博報堂プロダクツは、広告業界大手の博報堂グループに属する総合制作事業会社です。
その強みは、イベント・プロモーション領域における圧倒的な実績と、企画から制作、運営、実施までをワンストップで手掛けられる総合力にあります。
企業の新作発表会や大規模な展示会、PRイベントなど、特にビジネス関連のイベントで数多くの成功事例を持っています。
博報堂グループの広範なネットワークと連携し、広告キャンペーン全体の一部としてイベントを位置づけ、効果を最大化する戦略的な提案ができる点が大きな特徴です。
イベント単体で完結させるのではなく、デジタル施策や他のメディアと連動させた立体的なプロモーションの設計に携わりたいと考える人にとっては、非常に魅力的な環境でしょう。
多様な専門性を持つ社員が社内に在籍しており、チームで協力しながら大規模で質の高いアウトプットを目指すことができるのも、同社ならではの働きがいです。
電通ライブ
電通ライブは、国内最大の広告代理店である電通グループにおいて、イベントおよびスペース領域を専門に担う会社として設立されました。
その名の通り、「ライブ」感、すなわち人々がその場でしか味わえない「体験価値」の創造に徹底的にこだわっているのが最大の特徴です。
最新のデジタルテクノロジーと独創的なアイデアを駆使した、没入感の高い空間演出やインタラクティブな体験設計を得意としています。
彼らが目指すのは、単なるイベントの実施ではなく、参加者の心を揺さぶり、長く記憶に残り、そして世の中にポジティブな影響を与えるような「体験」そのものを創り出すことです。
そのため、前例のないような新しい表現や、クリエイティビティの高い企画に挑戦したいという意欲を持つ人にとって、刺激的な環境が用意されています。
企業のマーケティング課題に対して、リアルな体験を軸としたソリューションを提供することに強みを持っており、課題解決志向の強い人にも向いている企業と言えるでしょう。
コングレ
コングレは、イベント業界の中でも特にMICE(マイス)領域に強みを持つ企業として知られています。
MICEとは、Meeting(会議・研修)、Incentive(招待旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition(展示会)の頭文字を取った造語で、ビジネスイベントの総称です。
同社は、政府関連の国際会議や、医学会などの学術会議、大規模な産業見本市など、公共性が高く、極めて専門的な知識が求められるイベントを数多く手掛けてきました。
その長年の実績から、国内外の政府機関や地方自治体、学術団体から厚い信頼を得ており、安定した事業基盤を築いています。
イベントの企画・運営だけでなく、会議施設の運営も手掛けている点も大きな特徴です。
社会的な意義の大きな仕事に携わりたい、国際的なコミュニケーションの舞台を創り出したい、そして専門性を高めながら着実にキャリアを築きたいと考える人に最適な企業の一つと言えるでしょう。
誠実さと正確性が求められる仕事に、誇りを持って取り組める人材が活躍しています。
テー・オー・ダブリュー(TOW)
テー・オー・ダブリュー(TOW)は、企業の販売促進活動、すなわちセールスプロモーション領域に特化したイベント制作会社として、業界内で確固たる地位を築いています。
彼らの最大の強みは、人々の注目を集め、メディアで取り上げられるような「話題性のあるイベント」を創り出す企画力と実行力です。
SNSでの拡散を狙ったPRイベントや、消費者の購買意欲を直接的に刺激する体験型の販促イベントなどを得意としています。
どうすればニュースになるか、どうすれば人々の口コミを誘発できるか、というマーケティング視点に基づいた戦略的なイベントプランニングが特徴です。
常に世の中のトレンドや人々のインサイトを捉え、クライアントのビジネス成果に直結するヒット企画を生み出し続けることが求められます。
世の中にムーブメントを巻き起こすような仕掛けづくりに挑戦したい、そして自分のアイデアで商品やサービスをヒットさせることに喜びを感じる人にとって、これ以上ないほどエキサイティングな職場でしょう。
ネイキッド
ネイキッドは、従来のイベント制作会社の枠にとらわれず、プロジェクションマッピングなどのデジタル技術と空間演出を融合させた、新しい形の体験を創造するクリエイティブカンパニーです。
彼らが手掛けるのは、単なるイベントではなく、光や音、映像が一体となった「アート作品」とも言える空間そのものです。
城や歴史的建造物を舞台にした光の祭典や、商業施設の空間演出、未来をテーマにした体験型アート展など、その活動は多岐にわたります。
彼らの最大の武器は、テクノロジーとアートを掛け合わせることで、人々の想像力を掻き立て、非日常的な感動を生み出す独創的な表現力です。
常に新しい技術を取り入れ、これまでにない表現方法を模索し続ける姿勢が、多くの人々を魅了しています。
最先端のデジタルアートや空間演出の世界に興味がある人、そして自らの手で人々をあっと驚かせるような、アーティスティックな体験を創り出したいと考える人にとって、他に類を見ないユニークなキャリアを築ける企業です。
イベント業界の現状と課題
華やかな成功事例の裏で、イベント業界は今、大きな変革期を迎えています。
長かったコロナ禍を乗り越え、市場は力強い回復を見せていますが、それは単純にコロナ以前の状態に戻ることを意味しません。
オンラインとの融合が新たなスタンダードとなり、働き方や求められるスキルも変化しています。
ここからは、業界が直面する「再始動」「デジタル化」「人手不足」という3つのキーワードを軸に、そのリアルな現状と課題を掘り下げていきます。
コロナ禍を経た再成長フェーズ
新型コロナウイルスの影響で、イベント業界は一時、壊滅的な打撃を受けました。
しかし、行動制限の緩和とともに、人々がリアルな場での体験や交流を強く求めるようになり、業界は力強い再成長フェーズに入っています。
各地で音楽フェスや展示会が復活し、コロナ禍以前を上回るほどの熱気を見せている事例も少なくありません。
この動きは、人々にとってリアルイベントがいかに価値のあるものか、その本質的な魅力が再認識された結果と言えるでしょう。
デジタルイベント・ハイブリッドイベントの普及
コロナ禍をきっかけに、オンライン上で開催されるデジタルイベントや、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッドイベントが急速に普及し、今や業界のスタンダードとなりつつあります。
これにより、主催者は地理的な制約なく、世界中から参加者を集めることが可能になりました。
しかし、このデジタル化は新たな課題も生んでいます。
オンラインでは、リアルのような一体感や熱狂を演出しづらく、参加者の集中力を維持させることが難しいという問題です。
そのため、単にリアルイベントを中継するだけでなく、チャット機能やアンケート機能を活用した双方向のコミュニケーション設計や、オンラインならではの魅力的なデジタルコンテンツの企画が不可欠となっています。
これからのイベント業界で活躍するには、リアルな現場での運営能力に加え、こうしたデジタル技術への深い理解と、オンライン空間で人々を惹きつける企画力が必須のスキルとなるでしょう。
人手不足と業務の属人化
イベント業界は、長年にわたり人手不足という課題を抱えています。
特に、現場の設営スタッフや当日の運営スタッフの確保は、多くの企業にとって深刻な問題です。
ベテランプランナーの頭の中にしかない企画のコツや、特定のディレクターしか知らない現場の回し方など、組織として知識やスキルが共有・蓄積されにくい構造になっているのです。
この状態は、担当者が不在になると業務が滞るリスクを抱えているだけでなく、若手が育ちにくいという問題にもつながっています。
この課題を解決するため、業界では業務マニュアルの整備や、プロジェクト管理ツールの導入による情報共有の効率化など、業務の標準化とDX(デジタルトランスフォーメーション)化が急務となっています。
イベント業界の今後の動向
イベント業界は、社会の変化やテクノロジーの進化を敏感に捉え、常に新しい形へと変容を続けています。
コロナ禍を経て、人々が求める体験価値はどのように変化したのか。
そして、XRやメタバースといった新技術は、イベントの表現をどこまで拡張するのか。
未来のトレンドを予測し、それを自らの企画に活かせる人材が、業界の次世代を担うことになるでしょう。
ここでは、今後のイベント業界の行方を占う上で特に重要な3つの潮流について解説します。
リアルイベント回帰と体験価値の再評価
オンラインの利便性が広く浸透した一方で、人々は「そこでしか味わえない体験」の価値を再認識するようになりました。
同じ空間で同じ音楽に熱狂する一体感、画面越しでは伝わらないアートの迫力、偶然の出会いから生まれる新しいビジネスチャンス。
こうしたリアルならではの価値が、今、改めて高く評価されています。
この流れを受けて、今後のイベントは、単に参加するだけでなく、来場者が能動的に関われる「参加型・体験型」のコンテンツがますます重要になっていくでしょう。
XR・メタバースなど新技術との融合
XR(VR/AR/MRの総称)やメタバースといった仮想空間技術は、イベントの可能性を飛躍的に拡張するポテンシャルを秘めています。
スマートフォンのカメラをかざすと、現実の風景にキャラクターや情報が浮かび上がるARスタンプラリー。
そして、アバターとなって仮想空間上のイベント会場を自由に歩き回り、世界中の人々と交流できるメタバースイベント。
これらの新技術は、リアルとデジタルの境界を曖昧にし、これまでにない全く新しいエンターテインメント体験を生み出します。
現時点ではまだ発展途上の技術ですが、今後、これらの技術をいかに自社のイベントに効果的に取り入れ、ユニークな体験価値を創出できるかが、企業の競争力を左右する重要な要素となることは間違いありません。
SDGsや地域共創を軸にした事業展開
現代の企業活動において、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献は無視できない重要なテーマとなっています。
イベント業界も例外ではなく、環境負荷の低減やダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)、地域社会との共存共栄といった視点が、企画段階から強く意識されるようになっています。
具体的には、イベントで発生するゴミを削減する取り組み、再生可能エネルギーの利用、地元の食材を活用したフード提供、そして地域の文化や伝統を活かしたコンテンツ開発などが挙げられます。
こうした社会課題の解決に貢献するイベントは、企業のブランドイメージを向上させるだけでなく、社会貢献意識の高い現代の生活者の共感を呼び、結果として集客にもつながります。
イベント業界の職種・仕事内容
イベント業界の仕事は、一人のスーパースターによって成り立つものではなく、多様な専門性を持つプロフェッショナルたちの連携プレーによって初めて成功します。
イベントの骨格を創り上げる企画・営業担当の「イベントプランナー」から、現場のすべてを取り仕切る制作・進行の「ディレクター」、そしてイベントを世に広める「広報・マーケティング」担当まで、それぞれの役割が有機的に結びついています。
ここでは、イベント業界を代表する4つの職種を取り上げ、それぞれの具体的な仕事内容と役割について詳しく解説していきます。
イベントプランナー(企画・営業)
イベントプランナーは、イベント制作の最上流を担う、まさにプロジェクトの起点となる存在です。
主な仕事は、クライアントが抱える課題や要望を深くヒアリングし、「何のために、誰に、どんなイベントを行うのか」という根幹を定めることから始まります。
市場のトレンドやターゲット層のインサイトを分析し、斬新なアイデアと論理的な思考を掛け合わせて、イベントのコンセプトや基本構想を企画書にまとめ、クライアントに提案します。
この企画が通らなければ、プロジェクトは始まりません。
予算の見積もりや、プロジェクト全体のスケジュール策定もプランナーの重要な役割です。
ディレクター・プロデューサー(制作・進行)
イベントプランナーが描いた企画という「設計図」を基に、それを現実の形に創り上げていくのが、ディレクターやプロデューサーの役割です。
彼らは、イベント制作における「現場監督」や「総責任者」であり、実行の要となる存在です。
具体的な仕事は、会場のレイアウト決定、舞台・音響・照明などの技術スタッフとの打ち合わせ、出演者との交渉、マニュアルの作成、そして当日の進行管理(キューシート作成など)まで、多岐にわたります。
プロジェクト全体の進捗状況と品質を管理し、予算内で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全ての要素をコントロールします。
スタッフ・運営・設営(当日対応)
イベント当日の成功は、現場で働く運営・設営スタッフ一人ひとりの力にかかっています。
彼らは、イベントという非日常空間の最前線で、来場者が安全かつ快適に過ごせる環境を提供するという重要な使命を担っています。
具体的な業務は、会場の設営・撤収作業、機材の搬入・搬出、来場者の受付や案内、列の整理、クローク対応、そして会場内の警備など、非常に幅広いです。
広報・マーケティング・SNS運用
どれだけ素晴らしいイベントを企画しても、その魅力がターゲットに伝わらなければ、会場が満員になることはありません。
広報・マーケティング担当は、イベントの「集客」と「話題化」をミッションとし、その成功を左右する重要な役割を担います。
テレビや雑誌、Webメディアなどに向けたプレスリリースの作成・配信、SNSアカウントでの情報発信、インフルエンサーとの連携、Web広告の運用など、その手法は様々です。
単に情報を発信するだけでなく、どのような切り口で伝えればニュースとして取り上げてもらえるか、どのような投稿をすればSNSで「バズる」かを戦略的に考える力が求められます。
イベント開催前から開催後まで、継続的に情報を発信し、ファンの熱量を高め、ブランド価値を向上させていくことも大切な仕事です。
世の中のトレンドを敏感に察知し、情報戦略を駆使してムーブメントを創り出すことに面白さを感じる人にとって、非常にエキサイティングな職種と言えるでしょう。
イベント業界の魅力・やりがい
イベント業界は、時にハードで不規則な働き方が求められる厳しい世界です。
それでもなお、多くの人々がこの仕事に情熱を注ぎ続けるのは、他では決して得られない特別な魅力とやりがいにあふれているからです。
仕事の成果が、来場者の反応という目に見える形で返ってくるダイレクト感は、この業界で働く最大の醍醐味と言えるでしょう。
ここでは、イベント業界が持つ「感情」「創造」「共感」という3つのキーワードから、その尽きない魅力とやりがいの源泉を深掘りしていきます。
多くの人の感情を動かす仕事
イベント業界の仕事の最大のやりがいは、何と言っても「多くの人の感情を直接動かすことができる」点にあります。
自分が何か月もかけて準備してきたイベントで、会場が観客の熱気に包まれた瞬間。
アーティストのパフォーマンスに、数万人が一体となって歓声を上げる光景。
企業の未来を語るプレゼンテーションに、参加者が真剣な眼差しで聞き入る姿。
こうした来場者のリアルな反応を、肌で感じることができるのがこの仕事の特権です。
自分のアイデアが世の中に形として出る
イベント業界は、自らの創造性を存分に発揮できるフィールドです。
頭の中で描いた漠然としたアイデアが、チームのメンバーや多くのパートナーとの協力を経て、多くの人が集まる「空間」や「時間」として、目に見える形になる。
このプロセスは、まさにクリエイターとしての醍醐味を味わえる瞬間です。
そうした自分のアイデアやこだわりが、イベントの成功に直結し、多くの人々の体験価値を高めることに繋がります。
チームで一体感をもって作り上げる達成感
一つのイベントを成功させるためには、多種多様なプロフェッショナルの力が必要不可欠です。
企画、制作、営業、技術、運営など、異なる役割を持つメンバーが、それぞれの専門性を持ち寄り、一つのゴールに向かって協力し合います。
プロジェクトの進行中は、意見の対立やすれ違い、予期せぬトラブルなど、様々な困難が待ち受けています。
しかし、そうした壁を乗り越えるために、夜遅くまで議論を重ね、互いに知恵を出し合い、助け合う中で、チームには強い絆と一体感が生まれます。
そして、全ての苦労を乗り越え、イベント本番が無事に成功した瞬間。
その喜びを、共に戦ってきた仲間たちと分かち合う時の感動は、言葉では言い表せないほど大きなものです。
イベント業界を目指すためにすべきこと
イベント業界への就職は、人気が高い分、決して簡単な道のりではありません。
しかし、しっかりと準備をすれば、内定を勝ち取るチャンスは十分にあります。
重要なのは、憧れやイメージだけで志望するのではなく、「なぜイベント業界なのか」「なぜこの会社なのか」「入社して何を成し遂げたいのか」を、具体的な根拠をもって語れるようになることです。
ここからは、イベント業界を目指すあなたが今すぐ始めるべき、具体的かつ効果的なアクションプランを3つ紹介します。
業界・企業研究を進める
まずは、イベント業界の全体像と、その中でどのような企業が存在するのかを徹底的にリサーチすることから始めましょう。
本記事で紹介したようなビジネスモデルや職種、大手企業の情報はもちろんのこと、さらに一歩踏み込んで、中小企業や特定のジャンルに特化したユニークな企業についても調べてみてください。
企業のウェブサイトや採用ページを見るだけでなく、各社が過去に手掛けたイベント事例を詳しく調べることを強くお勧めします。
どのようなクライアントと、どのような目的で、どんなイベントを成功させたのか。
その実績を見ることで、その企業の強みや社風、仕事のスタイルが具体的に見えてきます。
学園祭・地域イベントなどの現場経験を積む
イベント業界の採用選考で、何よりも強力なアピール材料となるのが「実体験」です。
もしあなたが学生であれば、学園祭の実行委員会や、サークル・部活でのイベント企画、地域のお祭りやボランティア活動などに、ぜひ主体的に関わってみてください。
企画段階から、仲間と意見をぶつけ合い、予算やスケジュールを管理し、当日の運営で発生するトラブルに対応する。
この一連の経験は、イベント制作の仕事の面白さと大変さの両方を肌で感じることができる、何物にも代えがたい学びの機会となります。
インターンシップ・説明会に参加する
業界・企業研究や現場経験と並行して、積極的に企業のインターンシップや説明会に参加しましょう。
特にイベント業界では、実際の仕事を体験できる長期インターンシップや、現場社員と深く話せる座談会形式の説明会が開催されることがあります。
こうした機会は、ウェブサイトだけでは得られない、企業のリアルな雰囲気や社員の人柄、仕事の具体的な進め方を知ることができる絶好のチャンスです。
少しでも興味を持った企業があれば、臆することなく積極的にアプローチし、自分を売り込んでいく姿勢が、内定への道を切り拓きます。
就職エージェントに相談する
イベント業界への就職を希望する人は、就職エージェントに相談しましょう。
就職のプロに依頼することで、内定獲得の強力な味方になってくれるからです。
具体的なサポートには、書類添削や面接対策などが挙げられます。
もちろん、自己流で進める方法はあります。
しかし、時間効率が悪く、誤った方向に進むかもしれません。
効率よく内定を獲得したい就活生は、ジョブコミットに登録してください。
あなたに合った企業探しをサポートしてくれます。
また、就職エージェントと会話することで、あなたの強みや価値観などが言語化できます。
「自分の強みがわからない」「やりたい仕事が見つからない」といった悩みがある人ほど、一度相談してみましょう。
ジョブコミットに興味が湧いた就活生は、こちらのページをご覧ください。
ジョブコミットの魅力をより詳しく解説しています。
おわりに
本記事では、イベント業界の全体像から、具体的な仕事内容、求められる適性、そして就職活動で何をすべきかまでを網羅的に解説してきました。
この業界は、人々に感動と非日常体験を提供するという、非常に大きなやりがいのある仕事です。
その一方で、華やかなイメージの裏側には、地道な努力とタフな精神力が求められる厳しい現実も存在します。
大切なのは、これらの光と影の両面を正しく理解した上で、「それでも自分はこの業界で挑戦したい」と心から思えるかどうかです。
この記事で得た知識を元に、改めて自己分析を深め、あなたがイベント業界という舞台で本当に輝けるのかを見極めてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート