学業やアルバイト、大学で忙しく、志望動機を書く時間が取れない!
志望動機は就職活動で重要ですが、 何を書けばいいのか悩むことが多いですよね。
そこでおすすめしたいのが、「AI志望動機作成ツール」です。このツールを使えば、 あなたの部活動をもとにわずか1分でAIが自動的に志望動機を作成してくれます。アイデア不足や時間のない就活生にはぴったりです!(web完結)
そこでおすすめしたいのが、「AI志望動機作成ツール」です。このツールを使えば、あなたの部活動をもとに わずか1分でAIが自動的に志望動機を作成してくれます。アイデア不足や時間のない就活生にはぴったりです!(web完結)
このツールを活用して、あなたの過去経験をしっかり伝える志望動機を手軽に作成しましょう。
例:IT・ソフトウェア業界の志望動機例文
私が貴社を志望する理由は、興味のあるIT・ソフトウェア業界で、私の問題解決能力を活かして貢献したいと考えているからです。アルバイトでは、既存のやり方では解決できない課題に対し、新たなアイデアを積極的に提案し、実行することで、売上向上などの成果に繋げることができました。その過程で、困難な問題に直面しても、チームで協力し、知恵を出し合うことの重要性を学びました。貴社では、チーム開発を通じて、より複雑な課題に挑戦し、社会に貢献できる革新的なソフトウェアを生み出したいと考えております。培ってきた問題解決能力とチームワークを活かし、貴社の発展に貢献できるよう、精一杯努力いたします。
例:IT・ソフトウェア業界の志望動機例文
私が貴社を志望する理由は、興味のあるIT・ソフトウェア業界で、私の問題解決能力を活かして貢献したいと考えているからです。アルバイトでは、既存のやり方では解決できない課題に対し、新たなアイデアを積極的に提案し、実行することで、売上向上などの成果に繋げることができました。その過程で、困難な問題に直面しても、チームで協力し、知恵を出し合うことの重要性を学びました。貴社では、チーム開発を通じて、より複雑な課題に挑戦し、社会に貢献できる革新的なソフトウェアを生み出したいと考えております。培ってきた問題解決能力とチームワークを活かし、貴社の発展に貢献できるよう、精一杯努力いたします。 。
【国家公務員の志望動機】国家公務員とは
国家公務員とは、国の行政機関で働き、政策の立案や実行を通じて社会全体の仕組みを支える仕事です。国民一人ひとりの生活に関わる法律や制度の運用に携わるため、社会貢献性の高い職業として知られています。
一口に国家公務員といっても、その職種や役割は多岐にわたります。
所属する省庁や部局、職種によって求められるスキルや働き方は大きく異なり、自分に合った道を選ぶことが重要です。
また、民間企業とは異なる評価軸やキャリア形成があるため、安定志向だけでなく、自身の関心や価値観に合っているかどうかを見極めながら志望動機を固めていくことが求められます。
【国家公務員の志望動機】国家公務員の職種
国家公務員と一口に言っても、その職種は多岐にわたります。
政策の企画立案に関わる「国家総合職」、行政の現場を支える「国家一般職」、理系の専門知識を活かす「国家技術職」、そして特定の分野に特化した「国家専門職」など、それぞれの職種ごとに役割や求められる人物像が異なります。
そのため、志望動機を考える際には、自分がどの職種に向いているのか、どのような貢献ができるのかを明確にすることが重要です。職種ごとの特徴をしっかりと理解し、自分の経験や関心とどう結びつくかを考えることで、説得力のある志望動機につながります。
ここでは、国家公務員の代表的な4つの職種について、業務内容や特徴、志望動機の考え方のポイントを解説します。自分に合った職種を見極めるための参考にしてください。
国家総合職
財務省・経済産業省・農林水産省・環境省・国土交通省・文部科学省・総務省・警察庁
国家総合職は、国の中枢で政策の立案や企画を行う、いわば頭脳の役割を担う職種です。霞が関の各省庁をはじめとした中央省庁で勤務し、国の未来を左右するような政策づくりに携わることになります。
そのため、論理的思考力や課題解決能力に加え、幅広い行政知識と高い専門性が求められます。
将来的には幹部候補としてのキャリアパスが用意されており、入省から数年で重要なポジションに就くことも珍しくありません。全国転勤や海外赴任の可能性もあるため、柔軟な働き方への対応力も必要です。
志望動機としては、社会全体に影響を与える仕事がしたい国の方向性に関与できる責任ある立場で働きたいといった大きな視点を持つ姿勢が評価されやすい傾向にあります。
ただし、仕事内容は非常にハードで、長時間労働が発生することもあります。だからこそ、自分がなぜその道を選ぶのか、強い意志をもって言語化することが大切です。
国家一般職
国税庁・法務局・厚生労働省の出先機関・総務省の地方支分部局
国家一般職は、各省庁や地方出先機関で、行政の実務や事務処理を行う職種です。政策の企画よりも、それを現場で実行に移す実働部隊としての役割を果たします。
例えば、書類の審査や窓口業務、地域の課題に向き合う支援策の運用など、国民と直接関わる場面も多くあります。
この職種の大きな特徴は、転勤の頻度が比較的少ない点にあります。地元での勤務が可能な場合も多く、地元に貢献したい安定した環境で働きたいと考える方に向いています。
また、業務には正確な事務処理能力や、部署内外との連携をスムーズに行う協調性が求められます。職場の人間関係や、チームで物事を進めることが得意な方には適した職種と言えるでしょう。
志望動機では、現場での実務を通じて社会に貢献したい市民に近い立場で支援を行いたいといった、具体的かつ実行的な姿勢を示すことがポイントです。
国家技術職
農林水産省(農業土木・水産系など)・国土交通省(建設・機械・電気など)・環境省
国家技術職は、理系の知識や技術を活かして行政を支える職種です。専門分野は多岐にわたり、土木、建築、情報、電気、機械などがあります。
主にインフラの整備やシステムの構築、安全対策などを担当し、行政の現場を技術面から支える存在です。この職種は技術×行政という独自の立ち位置にあり、専門知識に加えて公共性を意識した判断力が求められます。
例えば、災害対策におけるインフラ整備や、デジタル化の推進といった分野では、その専門性が大いに発揮されます。勤務地は全国にわたり、出先機関や工事現場への赴任もあるため、柔軟な対応力やフィールドワークに抵抗のない姿勢が重要です。
志望動機では、自身の専門性をどのように行政に活かすのかを明確に伝えることが鍵になります。
大学で学んだ知識を社会に還元したい技術者として公共事業に関わりたいというように、具体的な経験や関心と結びつけることで説得力が増します。
国家専門職
国税専門官(国税庁)・財務専門官(財務省)・労働基準監督官(厚生労働省)・入国審査官・皇宮護衛官
国家専門職は、特定の分野において高い専門性を活かして活躍する職種です。代表的なものとして、国税専門官、労働基準監督官、入国警備官、法務教官などが挙げられます。
これらの職種は、それぞれに固有の使命と職責を持ち、強い責任感と専門知識が求められます。
例えば、国税専門官であれば税務調査や徴収業務、労働基準監督官であれば労働環境の是正指導など、国民生活を守る最前線で働く仕事です。
いずれも、現場での判断力や粘り強い対応が必要とされます。
この職種では、職務に対する使命感や社会正義への意識を持っているかが問われます。
志望動機においても、税の公平性を守りたい労働者の安全を支えたいといった、その職種特有の意義を理解し、自分の言葉で語ることが重要です。
また、採用後の研修や現場経験を通じて、専門性をさらに高めていく環境が整っているため、向上心のある方に向いていると言えるでしょう。
地方公務員との違い
最後に地方公務員との違いを押さえておくことで、より国家公務員の理解を深めることができるので、押さえておきましょう!
| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 勤務先 | 中央省庁や出先機関 | 都道府県庁や市区町村役場 |
| 業務範囲 | 国全体の政策・制度に関わる | 地域に密着した行政サービスを担当 |
| 採用試験 | 国家公務員試験(総合職・一般職など) | 自治体ごとの公務員試験 |
| 転勤 | 全国転勤あり | 基本的に同一自治体内で異動 |
| 役割 | 法律・制度の企画と全国展開 | 地域に応じた施策や住民対応 |
| 給与体系 | 国の基準(人事院)に基づく | 自治体ごとに異なる |
| 代表的な職種 | 中央省庁職員、国税専門官など | 市役所職員、保健師、消防士など |
【国家公務員の志望動機】省庁の種類
国家公務員として働く際には、どの省庁でどのような業務に携わるのかによって、仕事内容や関わる政策の分野が大きく異なります。
内閣府をはじめ、総務省、外務省、財務省など、各省庁はそれぞれ独自のミッションと役割を持ち、国の運営を支えています。
省庁一覧
・内閣府:内閣を支援する役割や、総合的な政策の立案、推進を行います。
・総務省:国全体の行政機関の組織と運営に関わる事務を行います。
・法務省:司法行政に関する事務や、刑事政策、刑法改正などを担当します。
・外務省:国際関係に関する事務や、外交政策、国際協力などを担当します。
・財務省:財政政策、金融政策、税制、会計など、国の財政に関わる事務を行います。
・文部科学省:科学技術政策、教育政策、文化振興などを担当します。
・厚生労働省:社会保障、労働政策、保健衛生などを担当します。
・農林水産省:農林水産業に関する政策、食品安全などを担当します。
・経済産業省:産業政策、資源エネルギー政策、中小企業支援などを担当します。
・国土交通省:土地区画整理、公共交通機関、道路、港湾、航空など、国土交通に関する事務を行います。
・環境省:環境保護政策、地球温暖化対策などを担当します。
・防衛省:国の防衛に関する事務を行います。
・警察庁:警察に関する事務を行います。
志望動機を考える際には、漠然と国家公務員になりたいとするのではなく、どの省庁で、どんな政策に関わりたいのかを明確にすることがとても大切です。
そのためには、自分が関心を持っている社会課題や興味のある分野と、それに対応する省庁の役割を照らし合わせていく視点が欠かせません。
ここでは、代表的な省庁の役割や特徴に触れながら、志望動機を考えるヒントをお伝えします。
【国家公務員の志望動機】国家公務員に求められる人物像
国家公務員は、国の政策に関わる責任ある立場として、専門的な知識やスキルだけでなく、高い倫理観と使命感を持って働くことが求められます。
変化が激しい現代社会においては、従来の枠にとらわれない柔軟な発想や、さまざまな立場の人々と協力して課題を解決する姿勢も重要な資質とされています。
また、国家公務員の業務は単なる事務作業や制度運用ではなく、国民の生活に直接影響を与える仕事であり、その分、強い責任感や高い公共意識が求められるのが特徴です。
ここでは、国家公務員として期待される人物像を3つの観点から整理し、それぞれどのように志望動機へと結びつけていくかのポイントをご紹介していきます。
公共の利益を最優先に考える使命感と責任感のある人
国家公務員の最も根本的な資質として求められるのが、公共の利益を最優先に考える姿勢です。
国家の政策に携わる以上、自分自身の利益や立場だけでなく、常に国民全体のことを考えた行動が求められます。
誰かの役に立ちたいという思いを持つ方にとっては、やりがいのある仕事といえるでしょう。
実際の業務では、多様な立場や価値観に配慮しながら、公平な判断を下す場面が数多くあります。
時には、利害関係の調整や、社会的にセンシティブな課題に対して意見をまとめる役割を担うこともあるため、高い倫理観と冷静な判断力が問われます。
志望動機を考える際には、なぜ自分は公共性の高い仕事に携わりたいのか、どのような社会課題に貢献したいのかを明確にしておくことが大切です。
過去の経験や学びと照らし合わせて、自分なりの使命感を言葉にできると、説得力のある志望理由になります。
変化に柔軟に対応できる課題解決力のある人
近年の行政現場では、従来のやり方が通用しない場面も増えており、変化に柔軟に対応できる人材が強く求められています。
グローバル化や少子高齢化、デジタル技術の進展など、社会はめまぐるしく変化しており、国家公務員にも新たな視点や発想が必要とされています。
たとえば、従来の制度が現代のニーズに合わないと判断された場合には、法制度の見直しや新たな仕組みづくりに取り組む必要があります。
そのような局面で重要になるのが、問題を的確にとらえ、関係者と連携しながら実行に移す課題解決力です。
志望動機では、どのような変化をチャンスととらえ、どう対応していきたいかといった柔軟な姿勢や、これまでに課題解決に取り組んだ経験を交えて伝えると、具体性のある内容になります。
今あるものを守るだけでなく、より良い社会のために新しい価値を生み出す視点を持つことが、これからの国家公務員に求められているのです。
多様な立場の人々と協働できるコミュニケーション力のある人
国家公務員の仕事は一人で完結するものではありません。むしろ、関係省庁や地方自治体、民間企業、さらには市民やNPOなど、さまざまな立場の人々と協力しながら物事を進めることがほとんどです。
そのため、相手の立場を尊重しながら、適切に意思疎通ができるコミュニケーション力が非常に重要になります。
特に、政策の企画や実行には、多様な利害関係者との調整が欠かせません。
こうした場面では、自分の考えをわかりやすく伝えるだけでなく、相手の意見に耳を傾け、共通の目標に向かって建設的に協働する力が問われます。
志望動機では、グループ活動やアルバイトなどで、チームで成果を出した経験や相手の意見を尊重しながら対話を重ねた経験などを交えて、自分のコミュニケーションスタイルを具体的に伝えると良いでしょう。
公務員というと堅いイメージを持たれがちですが、実際の現場では人と人とのつながりが仕事の基盤になります。
多様な価値観を受け入れ、相互理解を深めながら働ける方に向いている職種です。
【国家公務員の志望動機】志望動機を書く前に準備しておくこと
国家公務員の志望動機を書くにあたっては、単に安定しているからや社会貢献がしたいからといった表面的な理由だけでは説得力に欠けてしまいます。
自分自身の価値観や経験、将来のビジョンと国家公務員という仕事をしっかり結びつけて言語化することが必要です。
そのためには、事前の準備が非常に重要です。
自己分析や就活の軸の明確化、省庁ごとの業務理解、説明会やインターンを通じた実体験の取得など、段階的に取り組んでいくことで、より深みのある志望動機が完成します。
ここでは、志望動機を書く前に押さえておきたい5つの準備ポイントをご紹介します。
それぞれを丁寧に進めていくことで、自分らしい、かつ相手に響く志望動機に近づけるはずです。
自己分析を深める
まず取り組みたいのは、自分自身の理解を深める自己分析です。
これまでの経験や大切にしてきた価値観、将来どのように社会と関わっていきたいかを振り返り、なぜ国家公務員を志望するのかを明確にしていきましょう。
特に意識したいのは、なぜ国家に関わりたいのかという点です。
たとえば、地域でのボランティア経験を通じて制度の限界に疑問を感じた、留学中に国際協力に興味を持ったなど、自分の実体験から動機を掘り下げることが重要です。
自己分析が深まると、単なる憧れやイメージではなく、自分の過去と国家公務員という職業がどうつながっているのかが見えてきます。
その上で、どの職種・どの省庁で何を実現したいのかという具体的な方向性を考えていくと、志望動機に厚みが出てきます。
就活の軸を明確にする
国家公務員の仕事に限らず、どんな仕事を選ぶ上でも自分の就活の軸を明確にしておくことは欠かせません。
就活の軸とは、仕事選びの際に大切にしたい価値観や判断基準のことです。
たとえば、人の役に立ちたい、安定した環境で働きたい、長期的に専門性を高めたいチームで大きなプロジェクトを動かしたいなど、人によって重視するポイントはさまざまです。
この軸を明確にしたうえで、なぜ民間企業ではなく国家公務員なのか、なぜ他の公的機関ではなく中央省庁なのかといった問いに答えられるようになると、志望動機に一貫性と納得感が生まれます。
就活の軸を洗い出す際には、自己分析で得た情報や、過去の意思決定の傾向を振り返ることがヒントになります。
軸を明確にしておくことで、将来的なミスマッチも防ぎやすくなります。
人事院のサイトで希望する省庁の仕事内容を押さえる
志望動機を作成する際には、希望する省庁の業務内容や求める人物像をしっかり理解しておくことが大切です。
そのための情報源として最も基本になるのが人事院の公式サイトです。
人事院のサイトでは、各省庁がどのような政策分野を担当しているのか、具体的な仕事内容や職種ごとの役割、さらには試験制度や選考の流れなどが詳しく紹介されています。
志望する省庁が行っている政策や事業が、自分の興味や関心とどう結びつくのかを確認することができます。
また、パンフレットや職員インタビューなども掲載されているため、現場のリアルな声を知る手がかりにもなります。
こうした公式情報をきちんと押さえておくことで、なぜこの省庁を選んだのかという問いに具体的に答えることができ、説得力のある志望動機に仕上がります。
国家公務員の説明会やインターンに参加する
国家公務員の仕事に対する理解を深めるためには、実際に現場で働く職員の声を聞いたり、業務を体験することが非常に有効です。
その手段として活用したいのが、各省庁が実施している説明会やインターンシップです。
説明会では、職員から直接仕事内容や働く上でのやりがい・課題などを聞くことができるため、ネットや資料だけでは得られない情報に触れることができます。
また、質疑応答の時間を通じて自分の疑問を解消したり、省庁ごとの雰囲気を感じ取ることもできるでしょう。
さらに、インターンに参加した経験があれば、それ自体を志望動機に盛り込むことも可能です。
実際に体験したことから自分に合っていると感じたこの業務にやりがいを感じたなどと具体的に伝えることで、動機にリアリティが加わります。
政策情報を調べる
最後に取り組みたいのが、関心のある省庁が現在どのような政策に力を入れているのかを調べることです。
政策は日々変化しており、社会課題に対する取り組みの最前線を知ることで、志望動機の具体性が格段に高まります。
たとえば、環境省であれば脱炭素社会の実現、厚生労働省であれば少子化対策や働き方改革、外務省であれば国際協力の強化など、それぞれに重点政策があります。
自分が興味を持っているテーマとリンクする政策を見つけ、それに対して自分はどう関わりたいかを言語化することで、意欲と理解の深さをアピールできます。
また、白書や政策資料を読むことに慣れておくと、面接時の質疑にもスムーズに対応できるようになります。
単なる省庁のイメージではなく、現実の行政課題に目を向けることが、信頼される志望動機づくりには欠かせません。
【国家公務員の志望動機】国家公務員の志望動機で書くべきポイント3選
国家公務員の志望動機を書く際には、国家に貢献したい安定した仕事に就きたいといった漠然とした表現だけでは、他の志望者との差別化が難しくなります。
多くの学生が似たような志望理由を書く中で、自分だけの経験や視点をどう盛り込むかが大切なポイントです。説得力のある志望動機を書くには、まず自分は何ができるのか、そしてなぜ国家公務員なのかなぜその省庁なのかを明確にすることが基本です。
これら3つの視点をしっかり押さえることで、読み手に伝わる具体性と納得感のある内容に仕上がります。
ここでは、国家公務員の志望動機に盛り込むべき3つの重要ポイントをわかりやすく解説します。構成を考えるうえでも非常に役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。
どのような能力を活かして国家に貢献ができるかを盛り込む
志望動機の中で特に重視されるのが、あなた自身がどんな強みを持ち、それをどう国家公務員の仕事に活かせるのかという視点です。
この部分が明確に伝わることで、選考官にこの人が入省したら、どのような形で活躍してくれるのかというイメージを持ってもらいやすくなります。
たとえば、大学で培った論理的思考力を政策立案に活かしたい、留学経験を通じて得た国際感覚を外交分野で活かしたいなど、自分の過去の経験と国家公務員の職務をつなぐことが重要です。
抽象的な表現だけで終わらず、できる限り具体的なエピソードを交えることで、説得力が増します。
また、成果だけでなく、どのような姿勢で物事に取り組んできたかやどんな課題を乗り越えてきたかなど、過程にも触れると、人間味のある文章になります。
強みと業務内容の接点を意識しながら、自分だけの貢献のかたちを描いていきましょう。
民間や地方公務員ではなく国家公務員でないとできないことを入れる
国家公務員の志望動機を考えるうえで、もう一つ大切なのが、なぜ国家公務員なのかという問いに明確に答えることです。
これは、民間企業や地方公務員との違いを理解した上で、国家というフィールドだからこそ挑戦したいと感じた理由を伝えるパートになります。
たとえば、国全体に影響を与える政策に携わりたい、スケールの大きい仕事を通じて社会課題の根本解決に貢献したいといった視点は、国家公務員ならではの魅力と言えます。
また、国際機関との連携や法律・制度の設計といった業務も、国家レベルでないと経験できない部分です。
このように、国家公務員ならではのフィールドで何を実現したいのかを具体的に述べることで、なぜ他ではなく国家公務員なのかという理由に納得感が生まれます。
す. 単に大きな仕事がしたいだけでなく、その背景にある思いや体験も合わせて伝えるようにしましょう。
なぜその省庁でなくてはならないのかを盛り込む
最後に欠かせないのが、なぜその省庁を志望するのかという点です。
国家公務員の試験に合格した後、希望する省庁ごとに採用面接が行われるため、この部分の説得力が合否を大きく左右します。
それぞれの省庁には独自のミッションや重点政策があり、たとえば外務省であれば外交・国際関係、厚生労働省であれば医療や福祉、環境省であれば脱炭素・自然保護など、特色がはっきりしています。
まずは、その省庁がどのような課題に取り組んでいるのかを調べ、自分の関心や経験とどうつながるかを考えてみましょう。
さらに、この政策に共感したこの分野で自分の力を活かしたいといった想いを、自分の言葉で表現することが大切です。
表面的な理由やイメージではなく、なぜこの省庁でなければならないのかという問いに、自分自身が納得できる答えを持っているかがカギになります。
【国家公務員の志望動機】志望動機に書かない方がよい内容
国家公務員の志望動機を書くうえで大切なのは、自分自身の言葉でその職種・省庁にしかない理由を伝えることです。
しかし中には、よかれと思って書いた内容が、実は評価を下げてしまう原因になっている場合もあります。
特に注意したいのは、どの企業や組織でも通用するような汎用的な内容や、表面的な情報を並べただけの志望動機です。
これではなぜ国家公務員なのかなぜその省庁なのかという本質的な問いに答えていることにならず、印象に残らない結果になってしまいます。
ここでは、国家公務員の志望動機で避けた方がよい内容を3つに絞ってご紹介します。
志望動機をブラッシュアップする際のチェックポイントとして、ぜひご活用ください。
どの企業や組織でも通じる内容
志望動機を書く際によく見られるのが、社会に貢献したい自分を成長させたいといった抽象的な表現をそのまま使ってしまう場合です。
これらの言葉自体が悪いわけではありませんが、それだけでは国家公務員を志望する理由にはなりません。
実際、社会貢献や成長は多くの企業や組織でも得られる要素であり、それだけではなぜ民間企業ではなく国家公務員なのかという問いに十分に答えられていないと判断されてしまいます。
評価される志望動機にするためには、社会貢献したいという思いを、自分の経験や関心に紐づけて具体化することが必要です。
たとえば、災害支援のボランティアで、制度や仕組みの必要性を感じたため、行政の立場から支えたいといったように、自分自身のエピソードを交えて理由を深掘りしていきましょう。
その人にしか書けない志望動機を目指すことが、他の応募者との差別化につながります。
その省庁の強みや特徴を並べるだけ
省庁のパンフレットやホームページを参考にすることは、志望動機を作る上で大切なステップです。
しかし、そこで得た情報をそのまま書いてしまうと、調べただけ借りてきた言葉という印象を与えかねません。
たとえば、〇〇省は〇〇政策に力を入れており、国際的な取り組みも盛んですといった文だけでは、受け手にはあなた自身の考えや意欲が見えてきません。
大切なのは、そうした省庁の特徴を自分の価値観や経験とどうつなげるかという視点です。
志望動機は、私は〇〇という経験から、△△という社会課題に関心を持ちました。
その中でも、〇〇省の取り組みに共感し、自分もその一員として携わりたいと感じましたといったように、個人のストーリーを交えて表現することが求められます。
強みを紹介するだけでなく、共感し関わりたいと思った理由を言葉にすることが、説得力のある志望動機への第一歩です。
給与や福利厚生をメインで伝える
国家公務員の仕事には安定性や手厚い福利厚生といった魅力があるのは事実です。
しかし、それを志望動機の中心に据えてしまうと、やりがいよりも安定を重視している受け身の姿勢と受け取られかねません。
もちろん、長く働きたいライフステージに合わせた働き方ができることに魅力を感じたといった補足的な要素としてなら問題ありませんが、それを主な志望理由としてしまうと評価が下がってしまう可能性があります。
選考官が見ているのは、この人が本気で行政の仕事に関わりたいと思っているか社会課題に対して主体的に取り組む意欲があるかという点です。
そのため、志望動機では、仕事の内容や政策との接点、自分の将来ビジョンを中心に据えて書くことが大切です。
安定しているからという理由に終始してしまわないよう、あくまで動機の補足にとどめ、本質的な思いや目的をしっかり伝えるよう心がけましょう。
【国家公務員の志望動機】志望動機の面接での伝え方
国家公務員の選考では、筆記試験に加えて各省庁ごとの面接が重要な評価ポイントとなります。
とくに志望動機は、人物面を判断するうえでの大きな材料となるため、しっかりと準備しておく必要があります。
面接では、書類に書かれた志望動機をもとに、さらに深掘りされた質問がされることが多く、なぜ国家公務員なのかなぜその省庁なのか将来的に何を目指しているのかといった点について、具体的かつ一貫性のある回答が求められます。
また、面接は時間が限られているため、内容の正確さだけでなく、伝え方にも工夫が必要です。どれだけよい動機があっても、相手に伝わらなければ評価にはつながりません。
ここでは、志望動機を面接で効果的に伝えるためのポイントを2つの観点からご紹介します。
面接官が志望動機で知りたいこと
面接で志望動機を聞かれる際、面接官が見ているのは単なる熱意ややる気ではありません。
彼らが本当に知りたいのは、あなたはどんな目的意識を持って国家公務員を目指しているのか、なぜその省庁を選んだのか入省後にどのように働き、貢献していくつもりなのかという、将来に向けたビジョンや考えの一貫性です。
つまり、なぜ国家公務員なのかなぜこの省庁なのか入省後にどうなりたいのかの3点を、自分の経験や価値観と絡めながら説明できるかどうかが評価されます。
例えば、大学での研究を通じて〇〇という課題に関心を持ち、それに取り組んでいる〇〇省の政策に共感したため志望しましたというように、自分の歩みと政策の方向性をつなげて話せると説得力が高まります。
また、突発的な思いつきや漠然とした憧れではなく、現実的な理解に基づいた動機であることも重要です。
説明会やインターンで得た情報、自分で調べた政策の知識などを踏まえて、自分の言葉で語ることを意識しましょう。
端的に表現できるような言い方を考えておく
面接は限られた時間の中で自分をアピールする場です。志望動機を伝える際も、冗長にならず、聞き手にとってわかりやすい表現を意識することが重要です。
特に冒頭での第一印象が大切になるため、最初の1〜2文でこの人は何を軸に志望しているのかが伝わるよう準備しておきましょう。
そのためには、あらかじめ志望動機の要約版を作っておくのがおすすめです。
たとえば、〇〇という経験から〇〇に関心を持ち、〇〇省の〇〇政策に共感し、そこで自分の〇〇という力を活かしたいと考えていますといった形で、志望理由・省庁の特徴・自分の強みを簡潔につなげて表現する練習をしておくと、応用が効きます。
また、面接では想定外の質問が飛んでくることもありますが、要点を抑えたフレーズを持っておくことで、落ち着いて答えることができます。
事前に何度も声に出して練習し、自分の言葉として自然に話せるようにしておくことが、本番での自信につながります。
加えて、表情や話し方も含めた伝え方全体が印象に影響します。
内容と同じくらい、伝え方にも気を配って準備していきましょう。
【国家公務員の志望動機】志望動機のおすすめ構成
志望動機は、ただ思いや熱意を語るだけでなく、論理的な構成で順序立てて伝えることが大切です。
特に国家公務員の面接では、なぜ国家なのかなぜその省庁なのかといった深い問いに対して、一貫性のある説明が求められます。
そこでおすすめしたいのが、結論→原体験→民間との違い→省庁の理由→再結論という流れです。この構成は、読み手・聞き手の理解を助けるだけでなく、あなた自身の思考の深さや動機の本気度を自然に伝えることができます。
各パートをしっかりと作り込むことで、誰でも書ける志望動機から一歩抜け出し、自分にしか書けない志望動機へと仕上げることができます。
ここでは、その5つの構成要素について詳しく解説していきます。
結論(その省庁を通して成し遂げたいこと・想い)
志望動機の冒頭では、まず自分がこの省庁を通して何を成し遂げたいのかという結論を簡潔に述べましょう。最初にビジョンや熱意を提示することで、面接官や採用担当者に強い印象を与えることができます。
たとえば、誰もが安心して子育てできる社会を実現したい、持続可能なエネルギー政策を推進したいといったように、自分の関心や価値観とリンクする形で伝えるのが効果的です。
ここでは具体性と主体性がカギになります。
ポイントは、〇〇省に入りたいではなく、「〇〇という社会課題に取り組みたい。そのために〇〇省で働きたい」といった構造にすることです。
目的と手段の順序を間違えずに伝えることで、志望の本気度や目的意識がより明確になります。
冒頭の数文が相手に与える印象を大きく左右します。
ぜひ自分の言葉で、端的かつ熱意のこもった一文を考えてみましょう。
そう考えるようになった原体験
次に、その志望の背景にある原体験や課題意識を述べることで、なぜその想いに至ったのかを納得感を持って伝えます。過去の経験や学びを具体的に語ることで、志望理由にリアリティと説得力が加わります。
たとえば、大学で環境問題を学ぶ中で、個人の努力では限界があることを痛感したとか、家族が子育てと介護に苦労する姿を見て、制度の重要性に関心を持ったといったように、あなた自身の感情や視点がにじみ出るエピソードが理想です。
ここで大切なのは、ただ出来事を説明するのではなく、その出来事を通じて何を感じ、何を考えたかをきちんと言語化することです。
考えたこと、悩んだこと、その先に芽生えた想いがあるからこそ、志望動機に深みが生まれます。
なぜ民間企業ではなく国家公務員なのか
次に、民間企業や地方公務員などではなく、なぜ国家公務員なのかという点を明確にしておくことが重要です。国家公務員という選択肢でなければならない理由が語られているかどうかは、面接官が特に注目するポイントのひとつです。
国家公務員の特徴として、全国的な規模での政策立案・実行に携われること、制度の根幹に関われること、長期的・広域的な視点で社会課題に取り組めることが挙げられます。
これらの点が、自分のビジョンや関心とどう重なるのかをしっかりと語りましょう。
たとえば、社会保障制度を全国レベルで整備するには、国家レベルでの視点が必要だと感じたといったように、国家公務員だからこそ実現できる点を意識して言葉にすると効果的です。
漠然とした安定しているからといった理由ではなく、だから国家公務員しかないと感じた根拠を自分の言葉で伝えるようにしましょう。
なぜその省庁か
ここでは、数ある省庁の中でも、なぜその省庁を選んだのかを明確に述べます。
これは、採用担当者が最も重視する部分のひとつであり、しっかり調べているか省庁の方向性を理解しているかが問われるパートです。
省庁ごとに政策課題や重点分野は異なるため、自分の関心や経験と省庁の取り組みがどのように重なるのかを具体的に語る必要があります。
たとえば、厚生労働省の子育て支援政策に感銘を受け、自分もその分野で制度づくりに携わりたいと思ったといったように、自分の視点を交えて説明するのがポイントです。
また、省庁の説明会やインターンでの気づき、現場の職員から聞いた話なども盛り込めると、よりリアリティが増します。
共感、理解、貢献したいという三つの要素を軸に、なぜその省庁を選んだのかを伝えましょう。
結論(入省後にどうしていきたいか)
最後に、入省後にどのような形で貢献していきたいか、そして将来的にどんな職員を目指しているのかを語りましょう。
これにより、この人を採用すれば、こういう未来が描けるというイメージを持ってもらうことができます。
たとえば、まずは現場で制度運用の実態を学びながら、将来的には政策立案にも関わりたいといったように、段階的なキャリアビジョンを描くと、現実味があり評価されやすいです。
また、社会の変化に応じて柔軟に制度を見直せる職員を目指したいなど、理想像を言葉にするのも良いでしょう。
このパートでは、自己実現ではなくどう社会に貢献していきたいかに重きを置くことが大切です。
あなたの熱意や覚悟を締めくくりとしてしっかり伝えられるようにしましょう。
【国家公務員の志望動機】国家公務員の志望動機の例文14選
国家公務員を目指すにあたって、志望動機の書き方がわからない、どこまで具体的に書けばいいのか悩んでいるという声は多く聞かれます。
特に国家公務員は民間企業とは異なる評価ポイントがあり、抽象的な表現では伝わりにくいこともあります。
そのため、志望動機を書く際はなぜ国家公務員なのかなぜその職種・省庁なのかを自分の経験や価値観と結びつけて明確にすることが大切です。自分の言葉で想いを語ることが前提となりますが、書き方に悩んだときには例文を参考にするのも効果的です。
ここでは、国家総合職・国家一般職・デジタル庁・文部科学省・国土交通省の5つの例文をご紹介します。それぞれ異なる関心や背景をもとに構成しているので、自分の状況に近いものを参考にしてみてください。
国家総合職の例文
私は、政策立案という形で社会全体にインパクトを与える仕事に携わり、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。
特に、経済の安定と成長を支える制度設計に関心があり、国家総合職という立場で長期的かつ多角的な視点から政策に取り組みたいという思いを強く抱いています。
大学では経済政策を中心に学び、特に財政制度と所得再分配に関するゼミに所属していました。
その中で、経済格差や少子高齢化といった複雑な課題に対し、制度的なアプローチが必要であることを実感しました。
また、ゼミで行った模擬政策提言の発表を通じて、多面的に物事を捉える視点や、他者の意見を取り入れながらより良い解決策を導く力を身につけました。
民間企業では特定の分野や業務に限られることが多いですが、国家総合職であれば、広範な分野を横断的に学び、制度そのものを設計・改革する立場で社会に貢献できます。
そのスケール感と責任の重さに惹かれました。
将来的には、社会保障や労働政策の分野で、誰もが安心して暮らせる社会基盤の構築に貢献したいと考えています。
自らの専門性と現場の声を結びつけ、課題に応じた柔軟な政策を立案できる職員を目指します。
木下恵利

社会課題に対する問題意識と、国家総合職という職務への適性・関心が論理的かつ具体的に示されています。大学での学びやゼミ活動の経験が志望動機と直結しており、納得感のあるストーリーになっています。
特に、「制度設計」「スケール感」「責任の重さ」に触れた表現が国家総合職ならではの魅力を的確に捉えており、志望の本気度と将来像が明確です。
国家一般職の例文
私は、地域に根差した行政の現場で、住民一人ひとりの暮らしを支える仕事に携わりたいと考え、国家一般職を志望しました。
行政サービスの現場で実際に人々の声を受け止め、その声を政策に反映していく仕事に強いやりがいを感じています。
大学時代、市役所でのインターンシップに参加した際、市民の相談窓口で業務補助を行う中で、行政が果たしている役割の大きさを実感しました。
たとえば、子育て世帯の相談に対応する中で、丁寧に話を聞いてもらえて安心したという声を聞いたことが強く印象に残っています。
その経験から、一人の職員の対応が、住民の安心感や信頼感につながるという責任を感じるようになりました。
国家一般職では、各省庁や出先機関を通じて、地域課題に対応した施策を実行できる立場であることに魅力を感じています。
特に地域に密着した業務を行う中で、目の前の課題に対して自分が直接的に関わり、着実に社会を支えていくことができる点に大きな価値を感じます。
入省後は、行政の現場を支える立場として、正確かつ丁寧な事務処理を徹底しながら、国と地域をつなぐ役割を果たしていきたいです。
住民の安心を支える一員として、信頼される職員を目指します。
小玉 彩華

地域住民への貢献意識と、行政現場での実体験をもとにした志望動機が一貫しており、国家一般職への理解と適性がよく伝わります。特に「一人の職員の対応が信頼につながる」という気づきがリアルで、志望動機に説得力を与えています。
また、インターン経験を通じて「丁寧さ・正確さ」への意識を持っている点も、公務員として評価される要素です。
デジタル庁の例文
私は、行政のデジタル化を推進することで、すべての人が安心して行政サービスを利用できる社会の実現に貢献したいと考え、デジタル庁を志望しました。
誰一人取り残さない社会づくりのためには、テクノロジーの力で制度やサービスの使いやすさを根本から見直す必要があると感じています。
大学では情報工学を専攻し、ユーザーインターフェース設計やプログラミングに関する知識を習得しました。
特に、地域高齢者向けのデジタル講習を手伝った経験から、単に技術を導入するだけでなく、利用者の視点に立った設計の重要性を痛感しました。
デジタル庁では、国民目線のサービスデザインを重視した政策が進められており、その理念に深く共感しています。
単なるIT導入にとどまらず、行政全体の業務改革に踏み込む姿勢に魅力を感じ、自分もその一員として貢献したいと強く思いました。
入庁後は、利用者のニーズを的確に捉えながら、行政サービスのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、誰にとってもわかりやすく、使いやすい行政の仕組みづくりに取り組んでいきたいです。
木下恵利

デジタル庁の理念と自身の経験・専門性を結びつけた志望動機で、非常に納得感があります。
特に「高齢者向け講習を通じた気づき」や「国民目線のサービス設計」など、現場視点を持ったDX推進への姿勢が強く伝わり、技術者としての志だけでなく社会貢献意識も高く評価される内容です。
文部科学省の例文
私は、すべての子どもが等しく学べる社会を実現したいという思いから、文部科学省を志望しました。
教育の力は、一人ひとりの人生にとって大きな意味を持ち、社会全体の持続的な発展にも直結するものだと考えています。
大学時代、教育実習を経験した際、経済的な事情や家庭環境により、学びの機会に格差が生じている現状を目の当たりにしました。
中には、進路に不安を抱えながらも誰にも相談できないまま時間が過ぎていく生徒もおり、制度の限界や支援の不足を強く感じました。
文部科学省では、こうした教育格差の是正や、生涯学習社会の推進などに力を入れており、自分の問題意識と重なる政策が多く展開されています。
単なる現場支援だけでなく、制度の枠組みから整備する立場で関わりたいという思いが高まりました。
将来的には、教育政策を通じて、どのような家庭環境の子どもも夢に向かって学べる仕組みをつくりたいと考えています。
現場の声を丁寧にすくい上げ、社会の土台を支える教育を広げていける職員を目指します。
小玉 彩華

教育実習での実体験をもとにした「教育格差」への強い問題意識があり、文部科学省の政策との接点も明確に描かれている点が優れています。
現場と制度の両面を意識し、「制度の枠組みから整備したい」という視座の高さが志望動機に説得力を与えています。社会的意義と個人の経験がうまく融合した好例です。
国土交通省の例文
私は、災害に強く、誰もが安心して暮らせる国づくりに貢献したいという思いから、国土交通省を志望しました。
インフラ整備や都市計画、防災対策といった分野は、日常生活の安全を根底から支える重要な領域だと考えています。
大学では土木工学を専攻し、構造力学や都市インフラ設計を学びました。
また、東日本大震災の被災地でボランティア活動に参加した際、復旧が進んでもなお不安を抱えながら暮らす住民の声を聞き、インフラが持つ安心を届ける力の大きさを実感しました。
国土交通省は、国全体の基盤整備を担う省庁として、災害対応や防災まちづくりを含む幅広い領域に関与しており、学んできた知識を最大限に活かせる場だと感じています。
また、現場主義を掲げ、地域の実情に即した政策を重視している点にも強く共感しました。
入省後は、防災インフラの企画・整備に携わり、人命と暮らしを守る制度づくりを推進したいです。
将来的には、災害に強い持続可能な都市計画を実現するための制度設計にも挑戦していきたいと考えています。
木下恵利

土木工学の専門性と、震災ボランティアの実体験が結びついており、国土交通省の業務への適性と志が明確に伝わる構成です。
「安心を届けるインフラの力」や「現場主義への共感」といったフレーズが、省の理念と深くリンクしており、熱意と理解の深さが光る優れた志望動機です。
農林水産省の例文
私は、国内の食と農業の持続可能性を高める政策に携わりたいと考え、農林水産省を志望します。
大学では環境経済学を学び、農業従事者の高齢化や輸入依存の問題について研究を進める中で、制度や仕組みから支える重要性を実感しました。
中でも、食料安全保障や農村振興といった分野での取り組みは、民間企業ではなく国家全体を見据える農林水産省だからこそ実現できると感じています。
将来的には、地域ごとの農業課題に即した政策立案に携わり、現場と行政の橋渡し役として信頼される存在を目指します。
日本の食と農を守る基盤づくりに貢献していきたいです。
総務省の例文
誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献したいと考え、総務省を志望します。
地方で育った私は、人口減少や高齢化によって公共サービスが制限される現実を目の当たりにしました。
この経験から、地域間格差の是正や地方活性化に強く関心を持つようになりました。
民間企業では特定地域や利益に限定されますが、国家公務員であれば全国の課題に横断的に関与できると考えました。
中でも総務省は、地方行政やICT政策を通じて日本全体の基盤を支える役割を担っており、広範な視点から地域社会を支援できる点に魅力を感じました。
入省後は、地域ごとの特性を踏まえた制度設計に携わり、持続可能な社会の実現に寄与したいです。
財務省の例文
持続可能な財政を通じて、将来世代が安心して暮らせる日本を築きたいと考え、財務省を志望します。大学で財政政策を学ぶ中で、国の予算配分が社会構造に大きな影響を与えることに気づきました。
民間企業では特定事業の経済合理性に基づく判断に留まりますが、国家公務員であれば国全体の利益を見据えた財政運営に関与できます。
中でも財務省は、予算編成や税制設計、国際金融などを通じて国の方向性を決定づける責任ある立場にあり、他省庁と連携しながら政策を形にできる点に魅力を感じました。
入省後は、経済成長と財政健全化の両立に取り組み、信頼される国家の基盤を支えていきたいです。
農林水産省の例文
農業・漁業を次世代につなぐ持続可能な仕組みをつくりたいと考え、農林水産省を志望します。
実家の近くにある農村地域で、高齢化や担い手不足に悩む姿を見てきました。
そうした現実から、食料供給の安定性や地方経済の持続性に関心を抱きました。
民間企業では個別のサプライチェーンやサービス提供にとどまりますが、国家公務員であれば制度面から産業全体にアプローチできると考えました。
農林水産省は、生産から消費に至るまでの幅広い政策を担い、一次産業の振興と環境保全の両立を進めている点に魅力を感じました。
入省後は、現場の声を反映した制度設計に取り組み、持続可能な地域社会の形成に貢献したいです。
経済産業省の例文
イノベーションを通じて、日本経済の再成長を支える政策を推進したいと考え、経済産業省を志望します。
大学で中小企業の経営を学ぶ中で、日本の多くの企業が潜在力を持ちながらも制度や支援が十分でないことを知りました。
民間では一企業の成長支援にとどまりますが、国家公務員であれば制度・予算を通じて広範な産業支援が可能です。
中でも経産省は、産業政策やエネルギー政策、スタートアップ支援など多様な分野をリードし、日本経済の構造転換を促す役割を担っています。
入省後は、現場と政策の橋渡し役となり、成長と持続性を両立する経済社会の実現に尽力したいです。
環境省の例文
将来世代に豊かな自然を残すため、環境政策を推進したいと考え、環境省を志望します。
小学生のころから自然体験活動に参加し、自然の大切さや気候変動の影響を学んだことが原体験です。
民間企業のCSR活動では影響範囲に限界がありますが、国家公務員であれば法律や制度面から広く社会全体を変える力を持てると感じました。
環境省は、気候変動、生物多様性、資源循環などあらゆる環境課題に取り組み、国内外でリーダーシップを発揮している点に魅力を感じます。
入省後は、科学的根拠に基づく環境政策を通じて持続可能な社会の実現に尽力したいです。
警察庁の例文
安心して暮らせる社会の維持に貢献したいという思いから、警察庁を志望します。中学生の頃に近所で事件が起こり、不安を感じた経験をきっかけに、治安の重要性を意識するようになりました。
民間では防犯対策の一端しか担えませんが、国家公務員として制度・仕組みから治安維持に携わることで、より根本的な対策が可能だと考えました。
警察庁は、サイバー犯罪対策や広域捜査の指導、災害時の初動体制構築など、全国の治安維持に中枢から関わる点に魅力を感じました。
入庁後は、技術革新に即した犯罪対策や、国民の信頼に応える治安体制の構築に貢献したいです。
国税庁の例文
私は、租税正義の実現を通じて社会全体の公正と信頼を支える仕事に魅力を感じ、国税庁を志望します。
大学では法律学を専攻し、税法のゼミで所得税法や相続税法の仕組みを学ぶ中で、国の財源を支える税務行政の重要性を強く意識するようになりました。
民間では経験できない、法的根拠に基づいた調査や執行を通じて国民生活を支える点に責任とやりがいを感じています。
特に、国税専門官として納税者との信頼関係を築きながら、公平な課税の実現に向けて真摯に対応していきたいと考えています。
総務省のインターン志望動機例文
地域の課題解決を制度面から支える行政の役割を学びたいと考え、総務省のインターンシップを志望します。
私は、地方出身であることから、人口減少や高齢化により公共サービスが縮小される現状を身近に見てきました。大学では地方行政や政策立案について学び、自治体単位の努力だけでは限界があることを知り、国の制度設計の重要性を強く感じるようになりました。
インターンシップでは、地方自治体との連携やデジタル化支援など、総務省が担う幅広い業務の現場に触れ、行政の意思決定のプロセスを具体的に学びたいと考えています。また、地域の持続可能性を支えるために、どのような視点で制度が作られているのかを理解し、将来は公共政策に関わる仕事に活かしていきたいです。
【国家公務員の志望動機】よくあるNGポイント
最後に志望動機を作る際によくあるNGポイントを紹介していきます。
志望動機を作る際は、ぜひ以下のポイントに気をつけて作成してください。
「成長したい」だけで終わる
「成長したい」という意欲だけを述べる志望動機は、漠然としすぎており、どの企業にも通用してしまいます。
企業は、何を通じてどう成長したいのか、そのために自社を選んだ理由を知りたいと考えているため、具体的な内容が伴わないと評価されにくくなります。
自己PRになってしまっている
志望動機の中で「自分は○○が得意です」「責任感があります」といった自己PRばかりが目立ってしまうと、「なぜその企業を志望しているのか」が伝わらず、志望動機としては不十分です。
自分の強みを活かして企業でどんな貢献がしたいのかまで書くことで、志望理由として成立します。
抽象的で具体性がない
「人の役に立ちたい」「社会に貢献したい」といった抽象的な表現だけでは、応募者の価値観や行動が見えてきません。
どのような経験からそう思ったのか、具体的なエピソードや背景を添えることで、説得力のある志望動機になります。
業界研究・企業研究が浅い
企業や業界についての理解が浅いまま志望動機を書くと、どの企業にも使い回せるような内容になってしまい、熱意が伝わりません。
事業内容や理念、他社との違いなどを把握し、それを踏まえて自分の思いを語ることが大切です。
志望理由が待遇・知名度・イメージだけ
「福利厚生が良さそう」「知名度が高いから」といった理由だけでは、企業への共感や業務への興味が伝わらず、志望動機としては弱くなります。
企業が何を目指しているのか、その姿勢にどう共感したのかなど、より内面的な理由を示す必要があります。
受け身な印象がある
「学ばせてほしい」「経験を積ませてもらいたい」といった受け身な言葉ばかりだと、主体性が感じられず、積極性に欠ける印象を与えてしまいます。
インターンや仕事を通じて自分から何をしたいのか、どう貢献したいのかという視点を持つことが求められます。
自分の目的と企業の提供内容が噛み合っていない
「海外で働きたい」という志望があるのに、国内事業中心の企業を志望しているような場合、自分の目的と企業の方向性にズレが生じてしまいます。
企業の業務内容や育成方針と、自分のやりたいことが合致していることを丁寧に示すことが重要です。
テンプレ文章の丸写し
よくある例文やネットに載っているテンプレートをそのまま使用すると、どの応募者とも似たような内容になってしまい、オリジナリティが伝わりません。
自分の経験や考えを反映させたオリジナルの文章で、自分だけの志望動機を作ることが評価につながります。
熱意が空回りする
「どうしても御社に行きたいです」「絶対に働きたいです」といった強い表現ばかりが並ぶと、気持ちは伝わっても、なぜそう思うのかという根拠が薄く、内容が伴っていないように見えてしまいます。
熱意は、しっかりと調べた上での理解や、納得感のある動機に裏打ちされることで伝わるものです。
【国家公務員の志望動機】よくあるQ&A
はい、それぞれ役割と求められる視点が違います。たとえば、総合職は“政策の企画・立案”を担い、国家の方向性に関わります。一方で一般職は“制度を実際に運用する現場”の担い手で、国民と行政の橋渡しの役割が強いです。志望動機では、『なぜその立場で社会に関わりたいのか』を明確にすることで説得力が増します。
“安定しているから”だけでは弱いですが、切り口次第でプラスになります。たとえば『安定した環境で、長期的な視点で社会課題に取り組みたい』といった形にすれば、個人の志望理由が“公務員という職業観”と結びついて、納得感が出ます。大事なのは“なぜ安定性が必要なのか”まで掘り下げることです。
もちろん使ってOKです。重要なのは“公務員として求められる資質”とどうつながるかです。たとえば『アルバイトで地域住民の声を聞く大切さを学び、国レベルで制度を整えたいと考えた』など、自分の経験から『国の仕組みに関心を持った』流れを作れば十分に有効な志望動機になります。
“自分だからこその視点”を入れるのが鍵です。過去の経験からどんな課題意識を持ち、それをどう国家公務員として解決したいかを語りましょう。たとえば『地方出身として、地方と都市の格差に疑問を持ち、それを是正する政策に関わりたい』というように、“主語が自分”であることが差別化につながります。
結論→理由→将来へのつながり、この3ステップで構成すると、自然にまとまりのある志望動機になります。『国家一般職を志望するのは、○○な社会課題に取り組みたいからです。学生時代の△△な経験からその重要性を実感しました。将来的には□□という形で貢献していきたいです。』という流れを意識してみましょう。
結論から言えば、“公務員一本に絞るかどうかは人それぞれ”ですが、“民間も併願する”ことには大きなメリットがあります。なぜなら、面接経験や自己分析が深まり、公務員試験にもプラスになるからです。特に筆記試験に自信がない人や、官庁訪問での選考に不安がある人は、保険として民間を受けておくことで精神的な余裕が生まれます。選択肢を持った状態で挑むことで、かえって公務員試験にも全力を注ぎやすくなるんです。
結論、業界の平均に比べると、やや激務よりとされているでしょう。国家公務員は仕事量が多い割に、その分の給与が反映されにくいところがあります。
しかし最近では、国家公務員の給与が大手企業並になる動きが現れており、昔ほどブラックさは無くなってきているでしょう。
今後も待遇の改善は進んでいくと考えられるので、そこまで深く心配する必要はありません。
ソース:読売新聞「中央省庁の国家公務員給与、大幅引き上げへ…民間企業の給与水準「1000人以上」の大企業並に」https://www.yomiuri.co.jp/national/20250725-OYT1T50181/
まとめ
国家公務員を目指すうえで、志望動機は自分の思いや価値観を伝える大切な要素です。
ただ安定しているからといった理由だけではなく、なぜ国家公務員なのかなぜその職種・省庁なのかを明確にし、自分の経験や課題意識としっかり結びつけて表現することが求められます。
本記事で紹介したように、事前準備や自己分析を丁寧に行い、伝え方の工夫を意識することで、より説得力のある志望動機に仕上がります。
例文を参考にしながら、自分自身の言葉で伝えることを大切にしてください。
不安に感じることもあるかもしれませんが、真摯に向き合えば必ずあなたらしい志望動機が見つかります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート





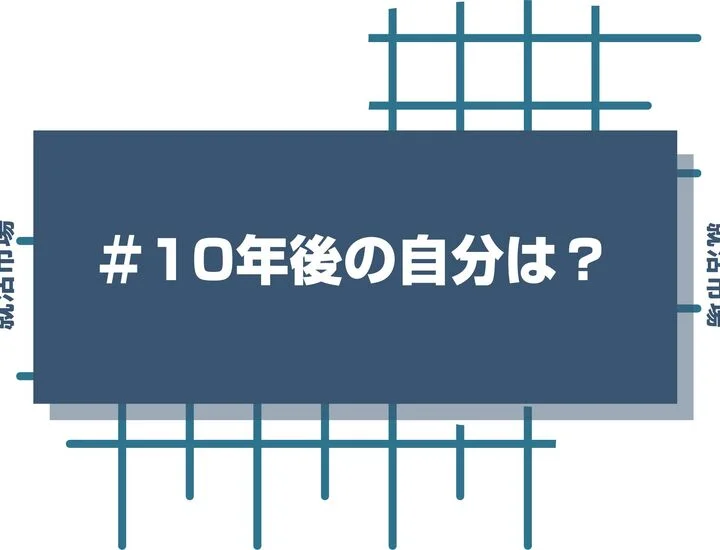






柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
ここからは、国家公務員の主な職種について詳しくご紹介していきます。それぞれの特徴を理解し、自分にとっての適職や志望動機のヒントを見つけていきましょう。