ガクチカで深掘りの質問に心配になっている人は多いのではないでしょうか?
面接ではいくら準備をしても想定通りに進むことはなかなか難しいものです。
本記事では就活生の「深掘り質問の対策をしたい」「人事が質問する理由を知りたい」といった悩みを解説していきます。
- 人事がガクチカを深掘りする理由
- よくある質問パターンと回答例
- 深掘り質問の対策と準備
- ガクチカで深掘り質問されたときの注意点
ガクチカの深掘り質問とは
面接において「深掘り質問」とは、応募者の経験やエピソードに対して、より詳細に掘り下げて尋ねる質問のことです。
この質問は、単に表面的な回答を超えて、応募者の考え方や行動の背景を明らかにするために行われます。
企業側は応募者の人柄やスキルだけでなく、困難な状況での判断力や行動力、そして成長意欲を見極める目的で深掘り質問を行います。
準備を怠ると答えに詰まってしまうため、事前にしっかりとエピソードを整理しておくことが重要です。
【ガクチカの深堀り質問】人事が深掘りをする理由
人事がガクチカを聞くだけで終わるのではなく、さらに深掘りして聞く理由はいくつかあります。
これから具体的に3つのポイントを紹介します。
人柄や思考傾向を知るため
企業は、応募者の人柄や価値観がどのように反映されているかを見たいと考えます。
例えば、困難な状況でどのように対処したのか、チームワークをどう捉えているのかが、深掘り質問を通じて浮き彫りにされます。
このような質問に対しては、自分の考え方や行動の動機を丁寧に説明することが重要です。
感情や態度を含めて話すことで、相手により自分らしさを伝えることができます。
企業とのマッチ度を確認するため
深掘り質問は、応募者が企業の文化や価値観に合っているかどうかを見極めるためにも行われます。
企業は、自社での成功を目指すために、どのような人物が組織に適しているのかを把握したいと考えています。
応募者が過去の経験でどのように考え、行動したかを詳細に掘り下げることで、企業の求めるスキルや価値観と一致しているかを確認できます。
論理的思考力を測るため
深掘り質問はまた、応募者の論理的な思考プロセスを評価するためにも用いられます。
なぜその行動を取ったのか、その行動がどのように結果に結びついたのか、こうした問いに対して一貫した答えが求められます。
自分の思考プロセスを整理し、順序立てて説明することで、論理的な対応力や問題解決能力をアピールすることができます。
【ガクチカの深堀り質問】高評価を得る答え方
ガクチカで深掘り質問されたときの答え方を解説します。
実際に聞かれた質問に対してどのように答えると好印象を与えることができるのか見ていきましょう。
結論から先に話す
面接官は、まず結果を知りたがることが多いので、質問に対しては結論を最初に述べるようにしましょう。
結論を先に伝えることで、その後の説明がより理解しやすくなります。
たとえば、「私はこのプロジェクトでチームをリードし、最終的に目標を達成しました」といった形で答え、続いてその背景やプロセスを補足すると、面接官に好印象を与えられます。
背景や状況を具体的に説明する
次に、エピソードの背景や状況を具体的に説明することが重要です。
どのような環境で、どんな課題に直面していたのかを詳細に話すことで、面接官が状況を理解しやすくなります。
抽象的な説明ではなく、具体的な事例やエピソードを交えて説明することで、自分の行動がより説得力を持つようになります。
自分なりの考えを焦点を絞って述べる
自分がどのように考え、どのように行動したのかを中心に答えると、面接官に自分らしさを伝えやすくなります。
考えが多岐にわたる場合でも、焦点を絞って伝えることで、要点が明確になり、面接官にインパクトを与えることができます。
特に、問題解決に取り組んだ際の工夫や発想を具体的に話すことで、あなたの独自性が強調されます。
数値を用いて成果を示す
面接での評価は、応募者の話の信憑性や具体性に基づいて行われることが多いため、できるだけ定量的なデータを示すことが重要です。
例えば、「売上を20%向上させました」「毎週3回のミーティングを行いました」など、成果や取り組みの数値を具体的に示すことで、面接官に対する説得力が増します。
特に成果を強調する際には、数値化することで評価がしやすくなります。
企業の求める人物像を意識する
面接官は、企業が求める人物像に合致しているかどうかを確認しながら話を聞いています。
そのため、事前に企業のビジョンや求めるスキルを理解し、それに合った回答を準備することが重要です。
例えば、リーダーシップを重視する企業であれば、チームリーダーとしての経験を強調し、協調性を求める企業であれば、チームワークに注力したエピソードを語ると効果的です。
【ガクチカの深掘り質問】面接で高評価を得たい学生さん必見!
深掘り質問への対策はもちろん!それだけでなく、「面接全体で高評価を得たい」と考えている学生さんも多いのではないでしょうか。
そんな学生さんにはこちらの記事もおすすめです!
面接における評価ポイントやガクチカの構成、注意点などの解説を幅広く掲載しています。
【ガクチカの深掘り質問】企業が注目するポイント
企業は学生時代にあなたが頑張ったことを通してどのような素質や原動力、経験があるのかを知りたいと考えています。
このポイントを理解して事前に面接官が聞きたいことを超えたられるように準備しておきましょう。
課題解決能力
企業が面接でガクチカを深掘りする際、特に注目するのが応募者の「課題解決能力」です。
どのような問題や困難に直面し、それをどう解決したかが重要な評価ポイントとなります。
例えば、困難な状況でどう冷静に対処したか、工夫を凝らして解決策を見つけたかを具体的に説明することで、あなたの実行力と問題解決力を企業にアピールできます。
チームワークの重要性
次に企業が重視するのは「チームワーク」です。
特にチームでのプロジェクトやグループ活動において、他のメンバーとの協力がどのように行われたかを見極めます。
あなたがリーダーシップを発揮したり、サポート役としてグループ全体を成功に導いたエピソードを具体的に話すことで、企業に対して協調性やコミュニケーション能力をアピールできます。
成長意欲
企業が求めるもう一つの重要な要素が「成長意欲」です。
ガクチカを通じて、どのようなスキルや知識を身につけ、自己成長を果たしたかを示すことが大切です。
例えば、最初はできなかったことが努力の結果できるようになったエピソードを伝えることで、学習意欲や向上心を強調することができます。
このような成長ストーリーを語ることで、企業に対してポテンシャルの高さをアピールできます。
【ガクチカの深堀り質問】回答の際の注意点
今までに述べた通り、回答するさいには色々なコツやポイントがありました。
しかし基本的なミスや相手に伝わりづらくなってしまう可能性もあるため、ポイントだけでなく注意点もおさえて完璧な事前の対策をしましょう。
専門用語を避ける
面接での回答には、できるだけ専門用語や業界用語を避けることが大切です。
面接官がその業界の専門家でない場合、専門用語が多すぎると話の内容が伝わりにくくなります。
分かりやすい言葉を使って、自分の経験を誰にでも理解してもらえるように工夫しましょう。
特に、異なる業種や業界に転職を希望する場合には、言葉選びに注意が必要です。
なぜそう考えたのかを丁寧に答える
深掘り質問に答える際には、単に「何をしたか」だけでなく、「なぜそのように考えたのか」を説明することが重要です。
自分の行動の背景や思考プロセスを丁寧に説明することで、面接官にあなたの価値観や判断力を伝えることができます。
自分の思考を整理し、順序立てて説明することで、より説得力のある回答ができます。
自分だけの功績にしない
チームでのプロジェクトに関する質問の場合、チーム全体の功績を自分一人の手柄として話すことは避けましょう。
チームでの役割や他のメンバーとの協力がどのように成果に繋がったのかを強調し、自分の貢献を適切に伝えることが大切です。
謙虚な姿勢を持ちながらも、自分が果たした役割をしっかりとアピールするバランスが重要です。
【ガクチカの深堀り質問】必要な対策と準備
次に実際に対策するときの方法や準備のやり方を解説していきます。
企業が見ているポイントや注意点を頭に入れたうえで本格的な対策についての理解を深めましょう。
エピソードの時系列を整理しておく
深掘り質問に備えるためには、自分が経験した出来事を時系列で整理しておくことが効果的です。
何がきっかけでその活動に取り組み、どのように進展し、最終的にどんな成果を得たのかを時系列で明確にしておくと、質問に対してスムーズに答えられるようになります。
また、複数のエピソードを準備しておくことで、様々な質問に対応できる柔軟性が生まれます。
「なぜ」「どのように」を繰り返し自問自答する
「なぜその行動を取ったのか?」「どのようにして問題を解決したのか?」といった質問に対して、自問自答を繰り返すことが重要です。
これを日常的に行うことで、面接時に自分の思考や行動を論理的に説明する力が養われます。
また、深掘り質問に対して即座に対応できるようになるため、面接の場でも落ち着いて答えられるようになります。
第三者に深掘りしてもらう
自分一人での準備に限界を感じたら、第三者に深掘りしてもらうことも有効です。
友人や家族、キャリアカウンセラーなどに協力してもらい、面接官のように質問をしてもらうことで、自分では気づかなかった部分や改善点が明らかになることがあります。
第三者の視点を取り入れることで、客観的に自分の経験を整理できるようになります。
面接経験を積む
実際の面接を経験することも重要です。
模擬面接を繰り返すことで、質問に答える際の流れや表現の仕方を改善できます。
特に緊張しがちな人は、実際の面接環境に慣れることで本番での落ち着きを保つことができます。
面接の経験を積むことで、自分に自信を持ち、自然に答えられるようになります。
【ガクチカの深掘り質問】面接練習のコツ
自分で対策する内容と実際の面接では想定通りに進む可能性はかなり低いです。
そのため、具体的に質問を当てるのは難しいですが、ある程度の範囲で準備しておくことはできます。
自己分析とフィードバックを行う
面接の準備として、自己分析を徹底的に行い、自分の強みや弱みを把握しておくことが大切です。
また、模擬面接や実際の面接後にフィードバックを受けることで、自分では気づかなかった改善点を知ることができます。
第三者の意見を取り入れながら、自分の面接スキルをブラッシュアップしていくことが、最終的な成功に繋がります。
事前準備を徹底する
面接の際に最も重要なのは、しっかりとした準備です。
企業の情報や業界の動向を事前に調査し、自分の経験がその企業にどう役立つかを考えておくことが必要です。
また、質問に対する答えを事前に用意し、繰り返し練習することで、本番でも自信を持って対応できるようになります。
実際の面接環境に慣れる
実際の面接の緊張感に慣れるためには、面接形式での練習が効果的です。
友人や家族に協力してもらい、模擬面接を行うことで、本番での緊張を和らげることができます。
また、実際の面接会場の雰囲気をシミュレーションしながら練習することで、当日の環境に驚かず、落ち着いて対応できるようになります。
【ガクチカの深掘り質問】頻出質問と回答まとめ21選
1.なぜその活動に取り組もうと思ったのですか?
私がカフェでの新マニュアル作成に力を入れたのは、非効率を放置したくないという、私の根源的な価値観に基づいています。
新人時代に、先輩によって教え方が違うことで、私自身が大きな戸惑いを感じたのがきっかけです。
このモヤモヤを放置せず、後輩には誰もがスムーズに働ける環境を作りたいという問題意識を解決するため、主体的に取り組みました。
単なる「興味」や「流れ」ではなく、あなたのパーソナリティが行動を起こした瞬間を鮮明に語りましょう。
その課題を他人事ではなく自分事として捉えた理由と、それを通じて得たいと考えていた具体的な成長を結びつけます。
2.その活動で最終的に何を目標にしていましたか?
目標は二段階で設定しました。
一つはチーム全体の効率化を図るため、新人OJT期間を平均2週間から1週間に短縮することという定量目標。
もう一つは、組織風土の改善として新人スタッフの半年後の定着率を10%向上させることです。
この二つを達成することで、根本的な人手不足の解消を目指しました。
目標は「頑張ったこと」ではなく「達成するべきゴール」として、数字と状態で明確にします。
その目標が、当時の状況においてどれだけ挑戦的だったかを伝えましょう。
3.その目標設定は妥当だと考えますか?
目標設定は妥当だったと考えています。
当初は3日短縮も検討しましたが、過去の離職データや、先輩スタッフが教育に割ける現実的な時間を分析しました。
その結果、教育の質を維持しつつ、最大限の効率化を図れるラインが1週間だと判断し、実現可能性と挑戦性を両立させました。
「なぜその目標にしたのか」というプロセスを語り、あなたの論理的思考力をアピールするチャンスです。
データや当時のリソース制約など、判断の根拠を具体的に示し、現実的な挑戦度を狙ったことを説明しましょう。
4.他に選択肢がある中で、なぜその取り組みを選んだのですか?
正直なところ、国際ボランティアなど、他にも力を入れられる活動はありました。
しかし私は、将来ビジネスの現場で通用する身近な課題を見つけ、関係者を巻き込みながら実務レベルで改善する力を最も身につけたいと考えていました。
このアルバイトでの組織改革は、まさにその仕事に直結する課題解決能力を鍛えるのに最適だと判断したからです。
比較した他の選択肢(例:部活動、別のアルバイト)を挙げた上で、その活動が、今の自分に必要な学びを最も得られると判断した理由を明確に伝えましょう。
あなたのキャリアや成長への明確な方向性をアピールします。
5.活動の中で最も困難だったことは何ですか?
最も困難だったのは、経験豊富なベテランスタッフからの理解と賛同を得ることでした。
私が作成したマニュアルは、彼らの長年の慣習と異なる部分があり、若手が何を言うかという抵抗感を強く感じました。
自分の経験不足が原因で、熱意だけでは組織は動かないと痛感した瞬間が、最も辛かったです。
単なる「大変だった事実」ではなく、「あなたがその時どんな壁にぶつかり、どう乗り越えたか」という内面的な葛藤を正直に伝えます。
困難に対するあなたの認識の深さを示すことが重要です。
6.課題に気づいたきっかけは何ですか?
マニュアルを配布して間もなく、ベテランスタッフが新人に「これは前のやり方でいいよ」とマニュアルを無視して指導している場面を目撃しました。
この時、問題はマニュアルの有無ではなく、マニュアルに対するスタッフ全員の信頼と納得感という、組織の意識レベルにあると気づき、アプローチを変えるきっかけになりました。
問題の表面的な現象ではなく、根本的な原因に気づいたプロセスを、具体的な出来事とあなたの鋭い観察力を結びつけて語ります。
7.困難を乗り越えるために具体的にどのような行動をとりましたか?
マニュアルを押し付けるのをやめ、『全員参加型』のアプローチに切り替えました。
まず、ベテランスタッフ一人ひとりに個別に話を聞き、マニュアルの不十分な点をヒアリングし、そのノウハウを反映した「ベテラン監修版」として改訂しました。
これにより、『自分たちの意見が反映されたもの』として、全スタッフがマニュアルを自分事として捉えるようになりました。
あなたの創意工夫が光る行動を、時系列で具体的に述べます。
失敗を恐れず「まずはやってみた」という実行力と、粘り強くPDCAサイクルを回した姿勢を強調しましょう。
8.行動をとる際、ほかの解決策は考えませんでしたか?
当初は店長命令で強制的に使用してもらう案も考えましたが、それではスタッフの不満が残り、形式的な運用に終わると判断しました。
時間をかけてでも全員の意見を取り入れ、納得感を生む方法が、組織文化として定着し、最も持続的な改善につながると確信したため、この対話によるアプローチを選びました。
比較検討した他の選択肢(A案、B案)を挙げた上で、採用した行動の優位性を論理的に説明します。
多角的な視点と冷静な判断力があることをアピールできます。
9.周囲の人(チームメンバー)をどのように巻き込みましたか?
特に役割の再定義を意識しました。
ベテランスタッフには、単なる指導役ではなく長年のノウハウを提供する共同編集者という役割と敬意を与えました。
また、新人の意見もマニュアルのレビュー担当として定期的に吸い上げ、全員が改善活動に参加している感覚を持てるように配慮しました。
相手の立場や心理を考慮し、協力することで相手にもメリットがあることを示して動機付けたプロセスを具体的に説明します。
あなたの協調性と影響力をアピールしましょう。
10.あなたのチーム内での役割、または立ち位置を教えてください。
私の役割は、まさに企画・調整役でした。
私が直接、指導方法を教えるというよりは、教育システムの企画立案を行い、意見が対立しやすいスタッフ間での利害調整と円滑な合意形成を担いました。
新人とベテランの間にある意識のズレを埋める通訳のような立ち位置を意識しました。
客観的かつ明確な役割(例:企画・調整役、データ分析担当、ムードメーカー)を述べ、その役割がチーム内でどのように機能したかを説明します。
自己認知の深さを示しましょう。
11.行動する中で、あなたのどのような強み(人柄)が活かされましたか?
私の粘り強さと傾聴力が活かされました。
特にベテランからの抵抗を受けた際、感情的にならず、なぜ彼らが抵抗するのかを深く知るために何度も対話を重ねました。
諦めずに相手の心を開く努力をし続けたことが、最終的に信頼を得る最大の要因になったと感じています。
あなたの強みと、それが具体的な行動や成果に結びついた理由をセットで説明します。
面接官が求める資質(粘り強さ、傾聴力など)を意識して選びましょう。
12.その行動に対して、周囲の反応はどのようでしたか?
店長からは、「最初は一人で突っ走るかと思ったが、最終的に全員を納得させた調整力に驚いた」という評価をいただきました。
この言葉で、企画力だけでなく、巻き込み力こそが成果に繋がると改めて認識し、自分の強みは人を動かす力にあると確信できました。
客観的な評価を取り入れ、多角的な視点で自己を捉えていることを示します。
フィードバックを受けたことで、自分自身の成長や変化があった点を述べましょう。
13.結果として目標は達成できましたか?
はい、目標を上回る形で達成できました。
OJT期間は目標通り1週間への短縮に成功し、さらに新人スタッフの半年間の定着率も目標を大きく超え85%に向上しました。
これは、マニュアルによって教育が均質化されたことに加え、組織全体の意識改革が連鎖的に起こった成果だと分析しています。
目標達成の有無を明確にし、定量的な成果を再確認します。
達成の要因を個人の努力とチームの貢献の両面から分析し、冷静な責任感を示しましょう。
14.その原因は何だと思いますか?
目標達成はしましたが、もし未達だった場合を考えると、原因は初期段階の合意形成の不足という私の見通しの甘さにあったと思います。
初めに一部だけで案を固めてしまい、後の協力体制を得るのに時間と労力を要しました。
目標達成には、計画の質だけでなく実行体制の構築と事前の根回しが不可欠だと痛感しました。
「他責」ではなく「自責」で原因を分析し、失敗から得た教訓を述べます。
冷静な分析力と、失敗を次に繋げる意欲をアピールしましょう。
15.その経験から得た最も大きな学びは何ですか?
最も大きな学びは、問題解決とは、テクニックではなく人間関係であるということです。
どれほど優れた施策も、それを実行する人々の納得感と意欲がなければ意味をなしません。
相手の立場や感情を尊重し、私たちで一緒にやる意味を共有することが、最も成果を生み出す鍵だと学びました。
具体的なスキルではなく、普遍的な教訓(例:リーダーシップの本質、課題解決の構造)を述べます。
その学びが今後の人生や仕事の軸になっていることを強調しましょう。
16.もう一度その活動をやり直せるとしたらどこを改善しますか?
改善点は、効果測定と改善サイクルをより頻繁に行うことです。
マニュアル導入後、次の定点観測まで期間が空いてしまいました。
やり直せるなら、導入後1ヶ月、3ヶ月といった短期的なレビュー会を設け、マニュアルを生きているドキュメントとして常に更新していく体制を整えます。
具体的な行動の改善点を挙げ、なぜその改善がより大きな成果を生むのかを論理的に説明し、継続的な改善意識を示します。
17.あなたの行動は結果にどれくらい影響したと思いますか?
直接的な結果(マニュアル作成と導入)への私の影響度は7割だと考えています。
私が主体となって企画・実行しなければ、この改善は実現しなかったでしょう。
しかし、残りの3割は、店長やベテランスタッフが指導者としての責任感を高め、熱心に新人を育成した成果だと認識しています。
成果はチーム全体で出したものだと考えています。
貢献度を客観的な根拠に基づき示し、チームへの感謝も忘れず、自己評価のバランスを示します。
18.その学びは、当社の仕事でどのように活かせると思いますか?
貴社の法人営業職においては、この関係構築力と課題解決力が活かせます。
顧客のニーズを深く傾聴し、ガクチカで培った相手の懸念を解消しながら合意形成を図る力を用いて、最適なソリューションを提供します。
お客様の潜在的な課題を発見し、組織的に解決に導くことで、貴社の売上に貢献します。
応募職種の具体的な業務内容と、ガクチカで得たスキルを具体的に結びつけます。
「入社後に早期に貢献できるイメージ」を明確に伝えましょう。
19.この経験は、ほかの活動にも活かされていますか?
はい、サークル活動でのイベント集客の際に活かされています。
以前は集客率が低い原因を広報不足と考えていましたが、この経験後、参加者の視点で分析し直すようになり、イベント内容そのものの改善に注力しました。
結果、集客率が20%向上しました。
ガクチカとは全く異なる分野での応用例を挙げ、汎用性のある能力であることをアピールします。
学びを「抽象化」し、他の場面で「具体化」したプロセスを説明します。
20.仕事は学生時代の活動とは違いますが、乗り越える自信はありますか?
仕事は学生時代の活動より専門性が高く、責任も重いことは承知しています。
しかし、ガクチカを通じて、私は未経験の課題に対し、原因を分析し、周囲の知見を取り込みながら粘り強く解決策を実行するプロセスを身につけました。
この自ら学び、成長し続ける姿勢こそが、環境が変わっても必ず活きる力であり、新しい壁を乗り越える上での自信です。
仕事の厳しさを理解していることを示した上で、ガクチカで培った「困難に立ち向かう姿勢」「学習意欲」が通用する根拠であることを強調します。
プロとしての覚悟を示しましょう。
21.その活動を通じて、働く上での価値観に変化はありましたか?
はい、大きく変化しました。
以前は与えられた役割を完璧にこなすことが重要だと考えていましたが、今では目の前の非効率や課題に対し、職務の範囲を超えて自ら改善提案を行い、周囲を巻き込んでいくことこそが、働く上で最も重要な価値観となりました。
この経験から、現状維持ではなく、常に組織に価値を生み出す改善に貢献できる社員になりたいと強く思っています。
活動前後の価値観の変化を明確に述べ、それが貴社の理念や社風と合致していることを示し、仕事への意義を見出していることを伝えます。
【ガクチカの深掘り質問】まとめ
深掘り質問は、応募者の経験や人柄をより深く理解するために行われます。
人事が重視するポイントを理解し、具体的かつ論理的に答えることが高評価を得るためのカギです。
また、面接に備えてしっかりと準備し、自己分析や模擬面接を通じて練習を重ねることが重要です。
あなたの経験や成果を効果的に伝え、企業に対してポテンシャルを最大限にアピールできるよう準備を整えましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)




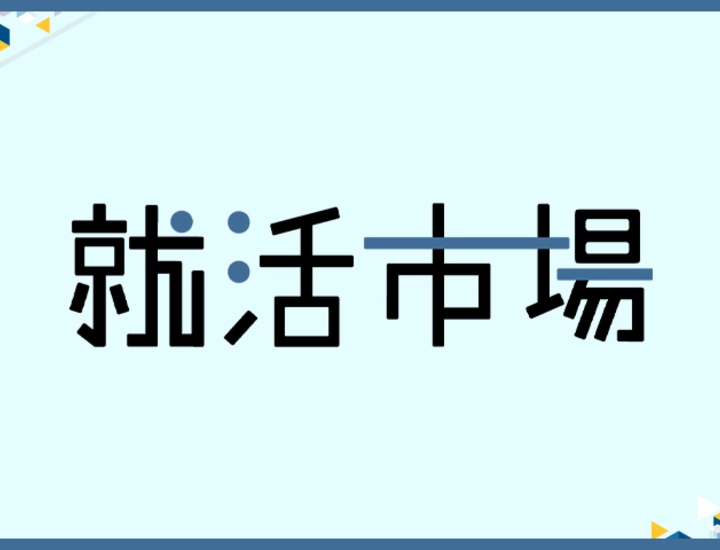
_720x550.webp)




