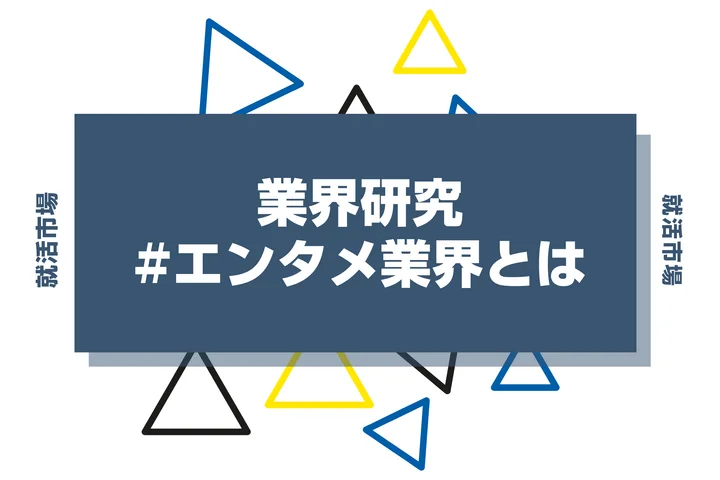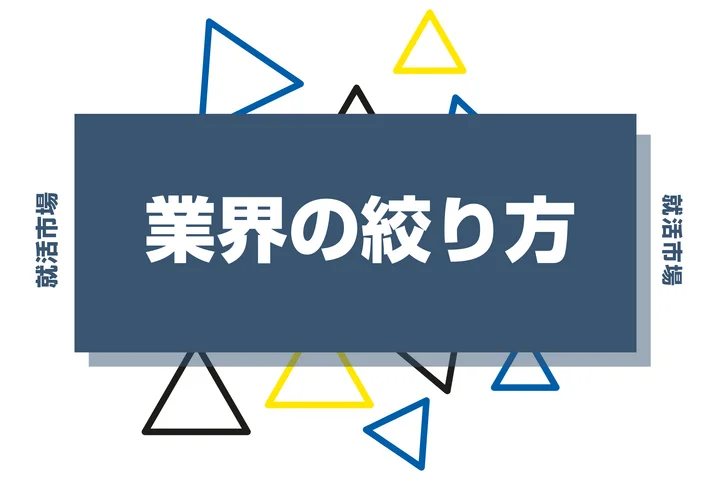- 業界を決めることの意味
- 業界の正しい選び方
- 業界が決まらない時にやること
27卒の就活では、特に業界の選び方が大切だと言われています。
就職活動において、業界を決めることは、就職活動を潤滑に進めるとても有効な方法のひとつです。
正しい選び方で業界を決めることで、企業選びがしやすくなり、就職活動の効率化にもつながります。
この記事では、業界を決めて就活がしたい!という方に向けて、業界の選び方から業界を決めることの重要性、業界を決めるコツまで徹底解説いたします!
就活、やるべきことが多すぎて、気づけば「どの業界を受ければいいのかすら決まっていない…」、「業界が絞りきれず、どの企業に申し込めばいいかわからない」なんてこと、ありませんか?
業界が決まっていない状態でESや面接に臨むのは、正直かなり危険です。
そこでおすすめしたいのが、就活市場の「AI業界診断ツール」です。
たった20問の質問に答えるだけで、あなたの性格タイプ(16タイプ)に基づいて向いている業界・向いていない業界が一目でわかります。(web完結)
そこでおすすめしたいのが、就活市場の「AI業界診断ツール」です。
たった20問の質問に答えるだけで、あなたの性格タイプ(16タイプ)に基づいて向いている業界・向いていない業界が一目でわかります。(web完結)
自分の軸が定まらずに不安な方、業界研究が手につかない方は、まずはこちらの診断から始めてみましょう。
目次[目次を全て表示する]
NEW!! 企業選びをしたい人は「企業研究データベース」を使おう
志望動機を作ったり、企業研究を行う際に一括の企業情報が必要な場合があります。
そこでおすすめなのが、 「企業研究データベース」を使うことです。
弊社が提供しているおすすめのツールを紹介します。
こちらのツールは業種・地域・規模感の3つの質問に答えるだけで、 あなたの希望に当てはまる企業を選び、企業研究を行うことができます。
完全無料で利用でき、1万社以上の企業情報が分かるので気になる方はぜひ利用してみてください。
【業界の選び方】就活は業界研究が肝になる
就活は業界研究が非常に重要です。
なぜならば、業界についてしっかりと知ることで業界を絞り込むことができるからです。
自分に向いている業界が何か知ることはもちろん、自分に向いていない業界を知ることも同様に重要であると言えます。
例えば、あなたが目指す業界が5つある場合と2つに絞り込めている場合とでは受ける企業を絞り込むこともできるため、より業界研究を深く行うことができ、ESや面接での受け答えのクオリティを高めることも可能です。
したがって、本記事を参考にして的確な業界選びを行ってください。
【業界の選び方】そもそも業界とは
就活において業界という単語をよく耳にしますが、意外と業界の意味を知らない学生も少なくありません。
業界とは、企業が扱う製品や商材の内容による分類であると考えるとわかりやすいです。
例えば、不動産業界は、土地や建物を取り扱う職種のことをいいます。
土地を開発するデベロッパーや、マンションの賃貸管理、売買仲介などすべて、不動産に直接関連する仕事は不動産業界と呼ばれます。
このように、商材や製品に関連した仕事を分類したものが業界と呼ばれます。
業界・業種・職種の違い
就活で自分に合う業界を選ぶ際は、まず、業界と業種の違いもチェックしておきましょう。
業界とは、共通の特徴やビジネスの性質を持つ企業・組織で、カテゴライズされたグループのことです。
通常の場合、業界は同じ目的や製品、サービスを展開する企業をまとめたカテゴリーとして扱われます。
例えば不動産関係のサービスを提供する企業は、包括的にまとめたグループとして、不動産業界と呼ばれることが特徴です。
一方で業種は、企業が提供するサービスや製品、もしくはその企業の具体的な事業をもとに分類されるカテゴリーになります。
そのためわかりやすくいうと、業種は「何を目的として活動しているか」という点がカテゴライズのポイントです。
また、業界は「産業」によって分類されますが、これに対して業種は「事業」で分類されることも大きな特徴です。
業界によって働き方や年収が違う
業界選びを考える上でまず重要なのは、業界ごとに働き方や年収が異なる点です。
同じ職種であっても業界によって扱う商材や営業の手法、サービスの提供方法が異なるため、業務内容や働き方にも大きな違いが生じます。
例えば、IT業界の営業職と製造業界の営業職を比較すると、IT業界の営業は新規のシステム導入やクラウドサービスの契約を取り付けることが多く、顧客とのコミュニケーションが中心になります。
一方で製造業の営業は製品の流通や製造プロセスの調整などが求められるため、製造現場や物流と密接に関わりながら働く場面が増えます。
また、業界ごとに年収も大きく異なるため、どのような企業が年収が高いのか、どのような企業が利益率が高いのかについても確認しておきましょう。
新卒でどの業界に入るかが社会人生活の鍵になる
確かに、現代においては転職は珍しいことではありません。
それでも、新卒でどの業界に入るかは社会人生活の基盤を築く上で非常に重要な要素です。
業界ごとに求められるスキルや知識が異なるため、経験の浅い段階での業界変更は不利になりがちです。
したがって、新卒での就職は自分のキャリアを専門的に深めるための基盤作りでもあるため、長期的な視点から選択することが望ましいとされています。
金融やコンサルティングなど待遇が良い業界では初任給が高く、スキルの習得やネットワークの構築が進みやすい環境が整っています。
一方、給与水準が低い業界に新卒で入社した場合、転職を繰り返しても収入面での成長が難しい場合もあります。
新卒時の業界選択は社会人生活全体の基盤を形成するため、目先の条件だけでなく、長期的な視点で将来を見据えた判断が求められます。
【業界の選び方】業界を決める重要性
業界を決める重要性としては、大きく以下の2つが挙げられます。
ここではこの3点について詳しく解説します。
企業選びがしやすくなる
業界を決めることで、その業界に属する受ける企業を絞り込むことができます。
そのため、企業研究にかかる時間や労力を削減することができます。
また、就職活動を進めていくにつれ、様々な企業の説明会に行くことになるため、業界への理解も深まります。
特に、第一志望の企業が大手で、選考が情報解禁後という方は、早めに業界を絞って、業界研究もかねて色々な企業の説明会や選考に参加してみましょう。
就職活動の効率化につながる
業界を決めることで、自己PRや志望動機などのES対策、面接対策もしやすくなります。
また、業界ごとに採用ニーズや選考基準が異なるため、業界を決めることで、より効果的な選考対策を行うことができるようになります。
就職活動において、受ける企業の業界の選考傾向を知ることはとても重要です。
どんな学生を欲している業界なのか、どんな受け答えが求められる業界なのか、という点の理解は、業界を絞ったほうが圧倒的に深められるでしょう。
ミスマッチを防げる
業界を決めることで、ミスマッチを防ぐ効果があります。
自分が向いている業界、興味のある業界に就職でき、強みが活かせるからです。
入社後に「想像していた業界と違った」とならないためにも業界選びは重要です。
業界研究を通じて、自分が志望する業界の特徴を理解しておきましょう。
同じ業務でも業界が違うだけで評価基準が異なります。
自分の強みが活かせる業界を選択しましょう。
業界を決めることで、その業界における就職活動はとても有利になります。
ですがその反面、他の業界のことを知らないまま就職活動を進めることになったり、軌道修正に時間がかかってしまったりするデメリットも存在します。
【業界の選び方】業界選びの大まかな3つの切り口
続いて、業界選びを行う際の大まかな3つの切り口についても紹介します。
以下の3つのポイントに着目して業界選びを行うことで、自分が向いている業界を選びやすくなることでしょう。
1.商材(何を扱うか)
扱う商材に注目することは自分がその業界でどのように貢献できるかを理解する上で大きな鍵となります。
商材は「有形」「無形」「お金」に分類され、それぞれが求めるスキルや価値提供の方法が異なります。
有形商材、つまり形ある商品を扱う製造業や小売業では品質管理や製品知識が重視され、消費者にとって信頼性や見た目の魅力が重要です。
一方、無形商材であるサービス業やIT、コンサルティング業界などでは目に見えない付加価値を提供するため、顧客との信頼関係構築やサービスの質の維持が成功の鍵を握ります。
顧客の要望を細かく汲み取り、柔軟な対応が求められるため、コミュニケーション力が強みとなる業界でもあります。
また、金融業界に代表される「お金」を扱う仕事では資金運用やリスク管理を通じて顧客の資産形成を支えたり、経済の発展に貢献したりする役割があります。
このように、商材のタイプによって仕事の内容や進め方が大きく異なるため、自分がどの分野でやりがいを感じ、最も力を発揮できるかを意識することで、充実したキャリアを築くための適切な業界選びが可能となるでしょう。
2.顧客(誰に売るか)
「顧客」に注目することも、業界選びにおいて重要な切り口です。
顧客は大きく「一般消費者(BtoC)」と「法人(BtoB)」に分かれ、それぞれ異なるアプローチが必要とされます。
BtoCでは消費者のニーズやトレンドを把握し、瞬時に反応するマーケティング力が求められます。
例えば、小売業や飲食業界では消費者が求める新しい商品をいかに早く市場に投入できるかが勝負になります。
そのため、消費者の好みに合わせた商品展開やサービスの改善が求められ、消費者の声に耳を傾ける姿勢が不可欠です。
一方、BtoBは企業間取引が中心であるため、信頼関係を長期間にわたり築くスキルが求められます。
製造業のサプライチェーン、ITソリューションの提供、コンサルティングといったBtoBの仕事では顧客の業務効率や利益向上に貢献するための提案力が大きな役割を果たします。
取引先の企業のビジネスモデルや目標を理解し、それに合わせたサービスを提供するため、的確な問題解決能力が必要です。
3.ビジネスモデル(どのように売るか)
「ビジネスモデル」つまり収益を上げる仕組みは業界の方向性や働き方を大きく左右する要素です。
ビジネスモデルは主に「作る」「売る」「動かす」「伝える」の4つに分類され、それぞれが異なる役割とスキルを要求します。
まず「作る」に当たる製造業や農業、建設業では製品やサービスを生み出すプロセスが仕事の中心です。
技術力や生産性の向上が競争力に直結し、製品開発や品質管理といった専門的な知識が求められます。
「売る」ことに重点を置く小売業やサービス業では消費者への販売が売上に直結するため、消費者のニーズを捉えたマーケティングや迅速なサービス提供が鍵となります。
「動かす」に分類される物流業や運輸業、インフラ業界は物資や人を安全かつ効率的に移動させる役割を担っています。
「伝える」に該当する広告業やメディア業界ではブランドイメージやメッセージを消費者に伝え、商品の認知度を高めることが主な役割です。
自分がどの過程に携わりたいか、またその過程でどう貢献できるかを考えることで、仕事への充実感が高まると同時に、業界選びの指針を持つことができます。
【業界の選び方】人気の業界5選を解説
就活において「どの業界を選ぶか」は、その後のキャリアに大きな影響を与えます。
特に、IT業界やコンサルティング業界、商社、金融業界、Web・インターネット業界は、多くの就活生から人気を集めています。
それぞれの業界には特徴があり、求められるスキルや働き方も異なります。
ここでは、これらの人気業界について詳しく解説し、自分に合った業界を見極めるためのポイントを紹介します。
業界選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
1.IT業界
IT業界は近年特に人気を獲得しています。
技術の進歩により、さまざまな場面でITの活用がされています。
さらに、文系や初心者でも学べるという点も人気の理由です。
進歩が著しく、需要も高いため受け口が多く、今勢いに乗っている印象が強いです。
また、リモートワークなどを積極的に採用している企業が多く、働く環境も良好な場合が多いです。
IT業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
- 社会のデジタル化に伴い需要が拡大し続けている成長産業
- エンジニア職だけでなく、営業や企画など幅広い職種がある
- 変化が速いため、常に学び続ける姿勢が求められる
2.コンサルティング業界
コンサルティング業界は企業や組織の課題を解決する仕事です。
企業は常にさまざまな問題を抱えています。
業績を向上させたい企業もあれば、人材不足に困っている企業もあります。
それらの問題を解決するためには論理性や課題解決力が求められます。
コンサルティング業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
- 企業の課題解決を支援するプロフェッショナル集団
- 論理的思考力やコミュニケーション力が重視される
- 多様な業界知識を得られる反面、業務は高負荷になりやすい
- 激務高収入の業界
3.商社
商社といっても、この言葉自体には幅広い意味があります。
そのため、商社と聞いてもあまりピンとこない人も少なくないでしょう。
簡単にいうと、商社は他の企業が自社商品やサービスをお客様に向けて提供する際に、お客様と結びつける役割を果たす存在です。
具体的には「総合商社」と「専門商社」の2種類がありますが、総合商社は幅広い分野で活動する商社に対し、専門商社は文字通り特定の分野において活動している商社になります。
いずれにしても、基本的なビジネスモデルはトレーディングや事業投資です。
つまり手数料によって利益を得たり、事業投資によって利益を得ることになるのが特徴だといえるでしょう。
もし商社を志望する場合は、以下の記事で商社対策のアドバイスをしているので、ぜひチェックしてみてください。
- モノやサービスを世界中から仕入れ・販売するビジネスの仲介役
- 総合職では語学力や交渉力、グローバル志向が求められる
- ダイナミックなビジネスができる一方、配属や転勤は多い傾向
- 激務高収入の業界
4.金融業界
金融業界は例えば銀行などです。
銀行内にも、営業や事務などの仕事がさまざまあります。
金融業界は絶対に受容がなくなることのない、インフラです。
そのため、働く上での安定性は非常に高いのです。
しかし、近年職種によってはAIに代替される業務について懸念があります。
金融系の企業については成長性や業績、職種などをよく精査することが重要です。
金融業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
- 銀行・証券・保険などを通じてお金の流れを支える社会基盤
- 数字への強さや信頼性、安定志向の人に向いている
- 業界再編やDXの進展により、変革期を迎えている
5.Web・インターネット業界
Web・インターネット業界はECサイト、検索エンジン、SNS、アプリといったインターネット上のサービスを中心に、開発、制作、マーケティングを行う企業が多く集まる業界です。
急速な技術進化とともに需要が高まり、企業は日々新しい機能やサービスを提供し競争力を強化しています。
特にSNSを活用したマーケティングやアプリ開発ではユーザーの行動データを分析し、パーソナライズされた情報を提供することで、より精密なターゲティングが可能となりました。
また、デジタルマーケティングやSEO対策、Web制作のスキルは業界全体で広く求められており、特にWebデザイナーやプログラマーといった専門職の需要は高まり続けています。
Web・インターネット業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
- SNSやEC、メディアなど人々の生活に直結したサービスを展開
- スピード感があり、若手でも裁量ある仕事を任されやすい
- 企画力やユーザー目線、最新技術への関心が重要となる
【業界の選び方】他にも注目の業界14選を解説
人気業界だけでなく、他にも多くの注目すべき業界があります。
メーカーや小売、マスコミ業界などは、私たちの生活に密接に関わる業界であり、安定性や将来性の観点からも魅力的です。
また、不動産・建設、インフラ、官公庁など社会の基盤を支える業界も重要な選択肢となります。
ここでは、こうした13の業界について、それぞれの特徴や魅力を解説します。
幅広い選択肢を知ることで、より自分に合った業界を見つけましょう。
1.メーカー業界
メーカー業界は製造業を行っている企業群のことを指し、製品の設計開発から始まり、工場での生産ラインでの製造加工を経て、市場に製品を供給するまでの一連のプロセスを担っている業界です。
自動車や家電、化学製品、食品などあらゆる製品がこの業界で生み出されています。
メーカー業界では技術の革新と製品管理が極めて重要です。
各企業は競争力を維持するために研究開発に多大な投資を行い、製品の性能やデザイン、コストパフォーマンスを向上させることに努めています。
また、サプライチェーンの効率化や環境への配慮もメーカー業界が取り組むべき課題です。
これらの努力により、高品質な製品が消費者に届けられ、社会の発展に寄与しています。
メーカー業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
2.小売業
小売業は皆さんご存知の通り、商品やサービスを消費者に直接提供する業態を指し、スーパーマーケットや百貨店、専門店などが挙げられます。
小売業の主な活動は商品を仕入れ、店舗やオンラインストアで販売することです。
消費者のニーズを的確に把握し、適切な商品を適正な価格で提供することが重要です。
また、競争優位性を保つために顧客サービスの質を高めることも求められます。
近年ではインターネット通販の拡大や消費者のライフスタイルの変化に対応するために、デジタル技術を用いた新しい販売手法も注目されています。
小売業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
3.マスコミ業界
マスコミ業界は大衆向けに情報を提供することを主な目的とする企業やメディアの集合体のことを指す言葉です。
テレビやラジオ、新聞、雑誌、インターネットメディア、ソーシャルメディアなどが含まれます。
マスコミ業界の役割はニュースやエンターテインメント、教育的なコンテンツを通じて社会に影響を与えることです。
情報の信頼性と速さが求められるため、ジャーナリズムの倫理観も重要な要素となります。
さらに、デジタル化の進展に伴い、インターネットやスマートフォンを利用した情報発信が増加しており、従来のメディアと新しいメディアが共存する時代となっています。
これにより、情報の取得方法が多様化し、視聴者や読者のニーズに応える柔軟性が求められているのです。
マスコミ業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
4.保険業界
保険業界とは、世の中のさまざまなトラブルに対する保険のサービスを取り扱う業界を指します。
厳密にいうと「生命保険会社」や「損害保険会社」さらに「保険代理店」の3つに分けることができ、それぞれ異なる役割があるのがポイントです。
例えば、生命保険会社の場合は、契約者から保険料をもらった上で、契約内容によって定められた保険金を渡します。
また、もらった保険料で資産運用をするのも仕事の1つになるでしょう。
そして、損害保険会社は事故や災害による損害査定を行い、そこから保険金を支払う手続きをするのが主な仕事です。
保険代理店は、上記2つの保険会社と契約をして、それぞれの保険会社の代わりに契約業務を代行する形になります。
人の集まる場所へ足を運び、その場で見込み客を集めて契約まで促すのが仕事です。
保険業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
5.人材業界
人材業界は主に、人材を欲する企業と就活をおこなう学生や再就職活動を行っている人のマッチングを行います。人手不足に困る企業は多くあります。
また、就活に難しさを感じる人も少なくありません。
それらを繋げることで、企業から報酬をもらう仕組みです。
営業やキャリアアドバイザーなど、職種はさまざまあります。
インセンティブ制をとっている企業も多いため、自分の実力が他よりも評価されやすい傾向にあります。
6.教育業界
教育業界は、人の成長を直接支援できる社会貢献性の高い業界です。
生徒が苦手を克服したり、目標を達成したりする瞬間に立ち会えるため、やりがいを実感しやすい職種になります。
近年ではEdTechと呼ばれるITと教育の融合が進み、新しい教育スタイルにも関われる点も魅力です。
EdTechとは、教育(Education)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた言葉です。
現在の教育業界は、教員数の長時間労働が慢性化しています。
そこでITを導入し、1人あたりの負担を軽減する取り組みが積極的に進められています。
教育業界は、生徒の成長に関わるため大きな責任が発生する仕事です。
しかし、教育業界でしか得られない達成感があります。
教育業界について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
7.不動産・建設業界
不動産・建設業界はデベロッパー、賃貸流通、仲介、管理業務などを行う分野で構成されており、ゼネコンやサブコンがその中心的な役割を担っています。
都市開発や再開発プロジェクト、住宅や商業施設の建設といった幅広い活動が含まれており、地域経済やインフラの発展に欠かせない存在です。
また、少子高齢化による住宅のニーズ変化やエコ志向の高まりにより、省エネルギー住宅やリノベーションの需要も高まっています。
さらに、不動産の管理・賃貸業務においてはAIやIoT技術の導入によるスマートビルディングの開発やデータ活用による効率的な資産管理が進められています。
不動産・建設業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
8.機械・電気業界
機械・電気業界は工作機械や建設機械、農業機械、産業用ロボットといった産業機械分野から自動車や船舶、航空機などの輸送機器分野まで幅広い範囲を含む、技術革新が求められる業界です。
機械・電気業界では高度な技術力をもとに安全性、効率性、環境性能を向上させることが常に重視されており、新しい製品や技術が開発されています。
特に近年は自動運転技術やAI、IoTの導入により機械の自動化や効率化が進んでおり、各メーカーは競って次世代製品の研究開発を行っています。
また、グローバル展開が進む中で品質管理や安全性の確保が重要となり、製品を世界中に輸出するための国際的な基準に対応することが必要です。
機械・電気業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
9.化学・素材業界
化学・素材業界は化学反応を駆使して製品を作り出すメーカーによって構成され、付加価値の高い製品の開発を中心とした成長が見込まれている業界の1つです。
製品の多様性が非常に広く、自動車、家電、医薬、建設、食品、農業など様々な分野で使用される素材を供給しており、その用途も年々拡大しています。
特に先端技術分野においては軽量化や耐久性、耐熱性など製品の特性を向上させる新素材の開発が重視されています。
環境負荷の低減を目指し、リサイクル素材などの開発が求められる化学メーカーは環境素材の開発や製造プロセスの見直しを進めています。
また、エネルギー効率の高い製品が求められることから、研究開発が盛んなこの業界はトレンドの「持続可能性」に着目しても、重要な役割を担っているとも言えるでしょう。
10.医療・医薬業界
医療・医薬業界は医薬品や医療機器の研究開発、効果検証、販売を主な業務とする業界です。
医療用医薬品や一般用医薬品の製造販売を行い、患者の治療と健康維持を支えています。
近年では手術ロボットや再生医療といった先進技術の導入も進み、革新的な医療サービスの提供が可能となっています。
医療・医薬業界は医薬品開発にかかる時間やコストが非常に大きく、また、臨床試験や安全性の確保が義務付けられているため、厳しい規制が設けられています。
これにより、業界全体の品質向上と信頼性の確保が徹底されているのが特徴です。
高齢化社会の進展とともに医薬品や医療機器の需要は増加しており、業界の成長が見込まれています。
医療・医薬業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
11.物流・運輸業界
物流・運輸業界は物資の輸送、保管、流通加工、情報管理など、サプライチェーンの中で欠かせない役割を担う業界です。
ECサイトなどオンラインで商品を購入できるインフラが普及してきたこともあり、物流需要は増加しており、特に迅速かつ効率的な配送サービスが求められています。
物資の保管や輸送を円滑に行うためには倉庫や運送車両を情報管理システムで整備することが不可欠であり、各企業は設備投資やITシステムの導入に力を入れています。
配送の効率化やコスト削減を目指す動きが活発であり、AIを活用したルート最適化やドローン、自動運転技術を取り入れた配送システムの開発もトレンドの1つです。
物流・運輸業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
12.旅行・エンタメ業界
旅行・エンタメ業界は旅行に関する交通手段や宿泊施設の手配、イベントや観光地の運営など、旅行者の体験を総合的にサポートする業界です。
特に観光立国を目指す日本では観光業が経済の一端を担う重要な分野とされています。
また、旅行者からの利益だけでなく、宿泊施設や観光地への送客を通じて地域の経済活性化にも貢献しています。
エンタメ業界ではライブイベント、映画、テーマパークなどの運営が含まれ、人々に楽しみ感動、エキサイティングな体験を提供できるため、大きなやりがいを感じられるのも魅力です。
コロナ後のインバウンド需要の回復とともに外国人観光客の増加も見込まれ、今後も業界の拡大が予想されています。
旅行・エンタメ業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
13.インフラ業界
インフラ業界はエネルギー、交通、運輸、通信、土木、建設といった生活基盤を支える分野で構成され、国民の生活や経済活動において必要不可欠な業界です。
インフラ業界は電気、ガス、水道の供給から公共交通機関、通信ネットワークの構築まで、日常生活に欠かせない基盤を提供しています。
特にインフラ設備は一度整うと長期にわたり安定的に運用されるため、業界全体としての安定性が高く、社会的意義が大きい業界です。
また、エネルギー業界では再生可能エネルギーの導入や電力自由化といった環境対応が求められ、業界全体での革新も見られます。
安定性と社会貢献性が高いことから、将来的なキャリア構築においても長期的な展望が持てる人気の分野であると言えるでしょう。
旅行・エンタメ業界についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
14.官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体は国や地方公共団体を指し、公共の安全と秩序を保つための行政業務を担当する重要な機関です。
官公庁の職員は国民の生活や経済を支える政策の立案や実行、規制の管理など、多岐にわたる業務を行っています。
例えば、厚生労働省や経済産業省、農林水産省など、それぞれの分野で専門知識を活かして政策を推進しています。
地方自治体の職員は地域の観光復興や教育、福祉サービスの提供など、地域のニーズに基づいた業務を担当し、住民の生活向上に貢献しており、国民のために働いているという強いやりがいを感じられるでしょう。
15.金融業界
金融業界は銀行や証券、保険などを通じて資金の流通を担い、経済を支える役割を果たしています。
安定性が高く、景気に左右されにくい側面もあるため、多くの学生にとって魅力的な進路といえます。
一方で近年はデジタル化やフィンテックの進展により、従来の業務内容が大きく変化しつつあります。
オンラインバンキングやキャッシュレス決済など、新しいサービスが次々に登場しているのも特徴です。
このため金融業界で活躍するには、従来の堅実さに加えて変化への対応力も必要です。
安定と革新の両立を意識しながら、自分がどう関わるかを考えることが求められます。
16.IT・情報通信業界
IT・情報通信業界はインターネットや通信、ソフトウェアなどを通じて社会の基盤を支える分野です。
リモートワークやオンライン教育の普及により、需要はますます高まっています。
また、AIやIoT、クラウドサービスといった技術革新が早いため、常に新しい知識を学び続ける姿勢が求められます。
文系学生であっても営業や企画、顧客折衝など多様な役割で活躍できるのが大きな魅力です。
さらに企業によっては研修制度が充実しており、未経験からでも専門スキルを身につけることが可能です。
成長性が高く、社会の変革をリードする業界として注目されています。
17.コンサルティング業界
コンサルティング業界は企業の課題解決や成長戦略を支援する専門性の高い分野です。
幅広い業種に関わるため、多様な知識や経験を積むことができます。
顧客企業の経営課題に対して分析を行い、最適な解決策を提案するため、論理的思考力や問題解決能力が重視されます。
また、プレゼンテーション力やコミュニケーション力も欠かせません。
厳しい労働環境とされる側面もありますが、その分成長スピードは早く、高い市場価値を得られる職種といえます。
挑戦的な環境で成長したい人に向いている業界として人気があります。
【業界の選び方】特徴別の業界ランキング
次は特徴別の業界ランキングを紹介します。
どの側面から見るかによって、業界のランキングは大きく変わるので、ぜひ参考にしてください。
ホワイト業界ランキング
| 順位 | 業界名 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | インフラ業界 | 安定した事業基盤と高い労働組合率、働き方改革が進んでいる |
| 2位 | 官公庁・公社・団体 | 残業が少なく、休暇制度や福利厚生が整っている |
| 3位 | メーカー業界(大手) | 業績が安定しており、福利厚生・ワークライフバランスも良好 |
| 4位 | 化学・素材業界 | 技術力で優位性があり、堅実な働き方ができる環境が多い |
| 5位 | 医療・医薬業界 | 社会貢献度が高く、専門職は無理のない働き方が可能 |
稼げる業界ランキング
| 順位 | 業界名 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 商社(総合商社) | 初任給・年収水準ともにトップクラス。海外案件や裁量も大きい |
| 2位 | コンサルティング業界 | 成果主義で若手でも高年収が狙える |
| 3位 | 金融業界(投資銀行・証券) | 成果報酬が大きく、30代で年収1000万円超も珍しくない |
| 4位 | 不動産・建設業界 | 歩合制で稼げる。高額物件を扱うほど収入が増える |
| 5位 | IT業界(外資・上流SIer) | スキル次第で年収が上がりやすく、専門職は高単価 |
成長業界ランキング
| 順位 | 業界名 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | IT業界 | DX・AI・クラウドなどの需要が拡大し続けている |
| 2位 | Web・インターネット業界 | SNS・EC・動画配信など新サービスが次々と誕生 |
| 3位 | 医療・医薬業界 | 高齢化・新興感染症対応で安定した成長が見込まれる |
| 4位 | インフラ業界 | 再生可能エネルギーやスマートグリッドで新展開 |
| 5位 | コンサルティング業界 | 企業の変革支援ニーズが高まり、多分野に展開中 |
転職・離職率が高い業界ランキング
| 順位 | 業界名 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 人材業界 | ノルマ・プレッシャーが強く、若手の離職が多い |
| 2位 | 小売業 | 長時間勤務や休日出勤が多く、待遇が低い傾向 |
| 3位 | 旅行・エンタメ業界 | 景気や社会情勢の影響を受けやすく安定しにくい |
| 4位 | 不動産・建設業界 | 実力主義が強く、営業ノルマが厳しい環境が多い |
| 5位 | マスコミ業界 | 納期プレッシャーや深夜作業などで離職リスク高め |
激務・残業が多い業界ランキング
| 順位 | 業界名 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | コンサルティング業界 | 案件ごとの納期がタイトで、長時間労働が常態化 |
| 2位 | 金融業界(投資銀行・証券) | 早朝出勤・成果主義で心身への負荷が大きい |
| 3位 | 総合商社 | 深夜会議・海外出張も多く、超長時間労働が日常 |
| 4位 | マスコミ・広告業界 | 不規則なスケジュール、突発対応が多く生活が乱れやすい |
| 5位 | 人材業界 | 営業ノルマ・対応業務量が多く、若手の離職率も高い |
【業界の選び方】業界を決めるための方法
業界を決めるための方法は、以下の5つが挙げられます。
どれか一つではなく色々試して、最終的に自分に最も合う業界を見つけましょう。
ここではこの5点を重点的に解説していきます。
1.自己分析
まずは、自分の興味や価値観、将来やりたいことを整理するために、自己分析を行いましょう。
自己分析をすることで、自分がどのような業界で働きたいのかを明確にすることができます。
自分がこれまでやってきたこと、今やっていることから、将来やりたいことを導き出し、それが叶う業界はどこかという視点で受ける業界を探していきましょう。
自己分析については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
2.業界研究
次に、興味のある業界について、詳しく調べましょう。
業界研究を行うことで、業界の特徴やトレンド、企業の規模や事業内容などを理解することができます。
イメージだけで「この業界が良さそう」などと考えていると、いざ説明会に参加したとき、最悪の場合、就職してから自分の理想とのギャップを感じ、離職に繋がってしまうことすらあります。
この業界研究は就職活動において最も大切なフェーズになるため、業界を絞る人も絞らない人も、受けたい業界の研究は徹底的に行うようにしましょう。
業界研究については以下の記事も参考にしてください。
3.合同説明会への参加
業界を決める上では、合同説明会に参加することをおすすめします。
特にマイナビやリクナビなどが主催する合同説明会は、多くの企業が一堂に会する場となります。
これにより、特定の業界に絞ることなく、幅広い業界や企業を一度に見学できるため、非常に効率的です。
また、複数の企業のブースを回り、説明してもらうことで自分の興味や関心がどの業界に向いているのかを具体的に把握することも可能です。
さらに、各企業の説明会では企業の理念や事業内容、職場環境についての具体的な情報が提供されることが多いため、企業選びの参考になること間違いありません。
合同説明会に参加することで、視野を広げ、自分に合った業界を見つける手助けになるでしょう。
4.インターンシップ
インターンシップに参加して、実際に業界や企業の仕事を体験してみるのもおすすめです。インターンシップに参加することで、業界や企業の雰囲気を肌で感じることができ、仕事内容や働き方などについて具体的なイメージを膨らませることができます。
また、人事の方やその業界で実際に働いている社員の方に話を聞くことができる機会もあり、業界理解を深めるのにも役立てることができます。
5.OB訪問
OB訪問は業界を決めるためのもう1つの重要な選択肢です。
過去にその企業や業界で働いていた卒業生や元社員の人に話を聞くことで、説明会では得られない詳細情報を得られます。
OB訪問では企業の見学やセミナー形式、個別面談など様々な方法で情報を収集することも可能です。
OBからは実際の業務内容や職場の雰囲気、キャリアパスなどリアルな体験に基づいたアドバイスを得られます。
OB訪問を通じて、企業や業界に関する具体的なイメージを持つことができ、自分がその業界で働くことを想像しやすくなります。
積極的に行い、自分の最適な業界を選ぶための貴重な情報源としましょう。
【業界の選び方】業界を決める際のポイント
業界を決める際は、以下のポイントを押さえましょう。
上記8点は、就職活動はもとより、実際にその業界で働くことになってから重要なポイントにもなってきます。
イメージで就活をしていると、実際に就業した際にギャップから早期離職につながるケースも多く、就職活動の時点からしっかりと上記を抑えて業界を決めていくことが大切になります。
どんな点を重視して業界を決めれば良いか、ここで解説します。
1.自分の興味や価値観
自分の興味や価値観に合った業界を選ぶことが大切です。
自分の興味や価値観に合っていない業界を選んでしまうと、仕事にやりがいを感じにくく、長続きしない可能性があります。
自分の興味や価値観については、先に解説した自己分析やインターンの参加経験などを元にして判断していくとよいでしょう。
2.将来やりたいこと
将来やりたいことを実現できる業界を選びましょう。
将来やりたいことが明確な場合は、その実現につながる業界を探しましょう。
将来やりたいことがまだ漠然としている場合は、業界研究やインターンシップを通して、さまざまな業界や企業を経験して、自分に合った業界を見つけましょう。
また、就職活動では選考の中で「将来のビジョン」を聞かれることも多いです。
将来やりたいことをしっかり持った上で、そこが志望理由の根拠の部分につながるととても良いですね。
5年後・10年後の自分を考えてみよう
5年後・10年後の自分の姿を想像することは重要です。
キャリア初期から将来を見据えた選択をすることで、仕事に対する一貫したモチベーションが得られ、成長し続けるための明確な指針となります。
例えば「10年後にマネジメントポジションに就きたい」「専門スキルを極めたい」など具体的なビジョンがあるなら、その目標を実現できる業界や企業を選ぶことが不可欠です。
成長著しいIT業界や医療分野では絶えず新たなスキルが求められ、専門性を磨きながらキャリアアップしやすい環境が整っています。
一方で、安定を重視し、長期的な安心感の中でキャリアを築きたい場合、公務員やインフラ関連業界といった安定性が強みのある業界が適しているかもしれません。
このように、5年後・10年後にどのような働き方や生活を送りたいかを明確にすることこそ、自分にとって最適な業界を見極めるための大きなヒントとなります。
3.仕事内容や働き方
仕事内容や働き方も重要なポイントです。
仕事内容や働き方が自分に合っていないと、仕事にストレスを感じやすくなります。
また、興味や価値観に合っていて、将来やりたいことを実現できる業界であったとしても、企業によって仕事内容や働き方は様々です。
業界研究やインターンシップを通して、実際に仕事内容や働き方を体験してみるとよいでしょう。
4.業界の将来性
業界の将来性も考慮しましょう。
業界の将来性が不安定な場合は、将来的に就職先がなくなってしまう可能性があります。
例えば、今現在AIに取って代わられるのでは?と言われる職業も多くあります。
全てがAIになることはもちろんありませんが、それでも、自分がやれると思っていた仕事が将来的にその業界から消えていくこともあるかもしれません。
業界研究を通して、業界の将来性や展望について調べておきましょう。
比較する時には興味を持った企業の共通点を抜き出してみよう
業界選びで迷った際には、興味を持った企業の共通点を整理することが有効です。
気になる企業の共通点を探ることで、自分が何に魅力を感じ、どんな価値観や仕事スタイルに惹かれているかが明確になります。
例えば、複数の企業に共通している特徴が「社員の成長を支える風土」や「新しい技術への挑戦を重視している」である場合、そういった特徴が強い業界に興味がある可能性が高いです。
また、選んだ企業が共にIT分野であれば、情報処理やデジタル技術への関心などが自分の軸になっていると考えられます。
このように、共通点を見つけ出すことで、自分にとっての譲れないポイントや、自分の価値観に合った業界をより具体的に絞り込むことができます。
5.複数の業界を比較する
1つの業界に最初から絞る必要はありません。
複数の業界を比較してみることで自分に合った業界を見つけることができます。
最初から1つに絞るのではなく、最初はある程度広い視野を持って興味のある業界以外も積極的に目を向けてみましょう。
自分の興味や価値観、将来やりたいこと、仕事内容や働き方、業界の将来性の4つのポイントを抑えることで、将来就業してから困らない業界選びをすることができます。
必ずどれか一つでもひっかかっていないか注意して受ける業界を決めるようにしていきましょう。
興味のある業界に近い業界を調べる
自分が興味を持っている業界だけでなく、関連する業界についてもリサーチすることが大切です。
例えば、IT業界に関心があるなら、医療や教育などIT技術を応用する場が増えている分野も視野に入れると、選択肢が広がります。
また、化学系の業界に興味がある場合、素材や医薬、エネルギー業界など、関連分野を調べてみると、異なる切り口から新たな可能性に気づくこともできます。
このように関連業界を探索することで、今まで見落としていた新しいキャリアパスが発見でき、新たな選択肢が生まれることも多いです。
異なる業界同士の視点を持つことは変化の激しい現代において柔軟なキャリア構築に役立つため、自分に最も合った業界を見極める貴重な視点となるでしょう。
6.自分ができることを元にして考える
業界を選ぶ際には自分の得意分野や既に身についているスキルを活かす視点も忘れてはなりません。
自分の「できること」を基に業界を考えることで、即戦力として貢献できる環境が見つかりやすくなり、自信を持ってキャリアをスタートさせることができます。
例えば、語学力が強みなら、貿易業界や観光業界、外資系企業など、外国語スキルを活かせる業界が選択肢に含まれます。
また、技術的なスキルや問題解決力が得意であれば、ITや製造業など、自分の能力を活かして成果を出しやすい環境が適しているかもしれません。
自分のスキルを活かすことで、入社後の成長もスムーズに進み、キャリアアップのチャンスにも恵まれやすくなります。
自分の「できること」を意識して業界を選ぶことで、就職後も早い段階で成果を出すことができ、仕事への満足度も高まります。
自己成長を感じながら働ける業界を見つけることは、QOLを高めるため、そして長期的なキャリア形成において重要です。
7.譲れないことから就活の軸を作る
業界選びにおいては自分の譲れない価値観や条件を明確にして、就活の軸を定めることが大切です。
自分が大切にする軸があれば、業界や企業を選ぶ際に優先順位が明確になり、迷わず判断できるようになります。
例えば、ワークライフバランスを重視するなら、残業が少なく、リモートワークが推奨されている業界が候補に挙がるでしょう。
また、自己成長や挑戦を重視するなら、急成長中のベンチャー企業や、技術革新が求められる業界が向いているかもしれません。
このように、自分の譲れない条件から軸を定めることで、効率良く業界や企業を絞り込むことができます。
軸を持つことで、様々な選択肢の中でもブレることなく自分に合った業界を選べる可能性が高まります。
自己の価値観に合致する業界を選ぶことで、将来的にも後悔の少ない選択ができるでしょう。
8.過去の経験から就活の軸を作る
業界選びの際には自分の過去の経験を振り返り、それをもとに就活の軸を作る方法もおすすめです。
過去にやりがいや達成感を感じた経験を基に業界や職種を絞り込むと、自分にとってのやりがいがどこにあるのかが明確になります。
例えば、学生時代にプロジェクトを成功に導いた経験があるなら、リーダーシップやチームワークを重視する業界が適しているかもしれません。
逆に、1つのことをじっくりと追求した経験があるなら、研究職や専門的な知識が必要とされる業界も視野に入ります。
過去の経験を振り返ることで、自分が最大限に力を発揮できた場面を理解し、それに合致する業界を選ぶことで、入社後も無理なく自己成長を実感できるでしょう。
自分の実体験を軸とすることで、将来にわたってモチベーションを維持しやすいキャリア選択が可能となり、充実した仕事人生を築く基盤になります。
以下の記事では就活の軸の例を120個と豊富に紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
9.扱う商材で選ぶ
業界を選ぶ際には、まずどのような商材を扱いたいかを考えることが有効です。
日用品や食品といった消耗品などの有形商材を扱うのか、あるいは保険やITサービスといった無形商材を扱うのかで、仕事内容やキャリアの方向性は大きく変わります。
有形商材の場合は商品の品質やデザインを重視した提案が中心となり、目に見える成果を実感しやすいのが特徴です。
一方で無形商材は顧客の課題解決やサポートを通じて価値を提供するため、コンサルティング要素が強くなります。
このように自分がどちらの商材に魅力を感じるかを基準にすれば、業界選びの軸を明確にできます。
10.ビジネス形態で選ぶ
業界を検討する際には、一般消費者向けのtoCビジネスと企業向けのtoBビジネスという視点も欠かせません。
toCは個人を相手にするため、商品のブランディングやマーケティング施策が重要になります。
短いサイクルで成果が見えるのが特徴で、消費者の反応をダイレクトに感じられるのも魅力です。
一方、toBは法人を相手にするため、長期的な関係構築や信頼性が重視されます。
契約単位が大きく、社会に与える影響も大きいため、責任感を持って仕事に取り組める点が特徴です。
自分がどのような顧客層を相手にしたいのかを明確にすることで、進むべき方向性が見えてきます。
【業界の選び方】業界の絞り方
100以上存在する業界の中から自分に合った進路を決めるのは簡単ではありません。
そのため消去法を使って選択肢を絞り込むことが効果的です。
やりたくないことを外したり、条件に優先順位をつけたりすることで、自分に合う業界を効率的に見つけられます。
業界の絞り方を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてみてください。
1.やりたくないことから考える
志望業界を選ぶときは、まず自分がやりたくないことを明確にするのも一つの方法です。
興味や関心から大きく外れる業界を除外していけば、自然と候補は絞られていきます。
例えば人前で話すことが苦手であれば営業中心の業界は避けるなど、自分の不得意分野を基準にして消去していくやり方です。
このようなプロセスを踏むことで、選択肢が整理され志望業界が見えやすくなります。
やりたいことが見つかっていない学生でも、やりたくないことを軸に考えれば方向性を定めやすくなります。
2.譲れない条件から優先順位をつける
もう一つの方法は、自分が就職にあたって譲れない条件を整理し、優先順位をつけることです。
勤務地、給与水準、働き方、福利厚生など、重要視する条件は人によって異なります。
条件を明確にして順位づけを行うことで、自分に合う業界や企業を効率的に探せるようになります。
例えばワークライフバランスを重視するなら残業時間が少ない業界、成長を重視するなら新しい分野に挑戦できる業界が候補になります。
優先順位を意識して業界を比較することで、納得感のある進路選択につながります。
【業界の選び方】業界を選ぶ時の注意点
- 業界を絞りすぎない
- 採用人数を確認する
- 2つ以上にまたがる企業に注意
これから就活を控えている人は、すでに業界選びを始めているかもしれません。
しかし、業界選びにはさまざまな注意点があります。
ここでは、就活初心者のために、何をどのように注意しなければいけないのかを3つに分けて紹介しましょう。
業界選びを始めている人はもちろん、これから取り組もうと考えている人も、ぜひ確認しておいてください。
業界を絞りすぎない
就活を始めた段階で志望業界を一つに絞り込みすぎるのは大きなリスクです。
なぜなら、その業界に集中して準備を進めても、後から志望を変更した際にすでに選考が終わっているケースがあるからです。
こうした状況では再び業界研究や選考準備を一からやり直さなければならず、就活全体のスケジュールに遅れが生じる可能性があります。
また一つの業界に依存すると、景気変動や業界特有のリスクに影響されやすくなるのもデメリットです。
そのため業界は複数を視野に入れて志望を進め、柔軟に軌道修正できる体制を整えておくことが大切です。
採用人数を確認
業界を選ぶ際には、各業界の採用人数の規模を確認することも重要です。
例えば金融業界やメーカー、IT業界は比較的大量採用が行われる傾向にあります。
採用人数が多ければエントリーの機会も増えるため、内定獲得のチャンスが広がるというメリットがあります。
一方でコンサルティングや出版など一部の業界は採用人数が少なく、競争倍率が高いケースが多いのが特徴です。
このような事情を理解せずに業界を選ぶと、思うように選考が進まず苦戦することもあります。
したがって業界を検討する際には、自分の興味だけでなく採用規模の現実も踏まえて判断することが欠かせません。
2つ以上にまたがる企業に注意
近年では、業界の区別がなくなりつつあるのをご存知でしょうか。
特にIT系の企業になってくると、さまざまな業界とのつながりを持つことが多くなるため、入社する場所によっては思いもよらない仕事をすることになります。
例えば、EC事業を展開しているようなところであれば、お客様とのやり取りはもちろんのこと、商品のピッキングや梱包作業などの仕事も、業務の一部として入ってくるようになるでしょう。
つまり、最初のイメージとは異なる結果を招く可能性があるのです。
だからこそ、どの企業で働くのかを考える際には、1つ1つの企業がどんな業界とつながりがあって、どのようなビジネス展開をしているのかを、きちんと調べておかなければいけません。
そうすれば、入社後にギャップを感じることもなくなるでしょう。
【業界の選び方】本当に選べない時には
どうしても業界を決められない場合は、第三者に相談するのがおすすめです。
第三者に相談することで、自分一人では見えてこなかった自分の長所や興味のある分野が見えてくることも多いです。
また、自分のことをよく知っている人とあまり知らない人の2人以上に相談してみるのがよいでしょう。
そうすることで、偏見のない意見も同時に得ることができるため、自分の将来の解像度がグッとあがります。
就活エージェントに頼るのもおすすめ
本記事では、就活エージェントに頼るのをおすすめします。
就活エージェントは、業界や企業に関する豊富な知識と経験を持ち、一人ひとりの学生の適性や希望に応じて、業界選びのサポートをしてくれます。
就活市場エージェントも、完全無料で業界に関する相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
オファー型採用を利用する
オファー型採用を利用するのも選択肢の1つです。
企業が興味を持った学生に対してオファーする採用形式であり、代表的なサイトとしてはOfferBoxなどがあります。
様々な業界からオファーが来るため、就活の可能性が広がるため、ぜひ利用してみましょう。
特に「OfferBox」は大手からベンチャーまで登録企業数はなんと17,982社以上であり、さらに自己分析ツールなども利用でき、自分の適性のある職種などについても診断してくれます。
累計100万人の診断結果に基づいた分析ができる非常に便利なツールであるため、ぜひ気になる方はこちらも利用してみてください。
【業界の選び方】まとめ
業界を決めることは、就職活動の第一歩です。
業界を決めることで、企業選びがしやすくなり、就職活動の効率化にもつながります。
業界を決める際は、自分の興味や価値観、将来やりたいこと、仕事内容や働き方、業界の将来性などを考慮して、慎重に決めるようにしましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート



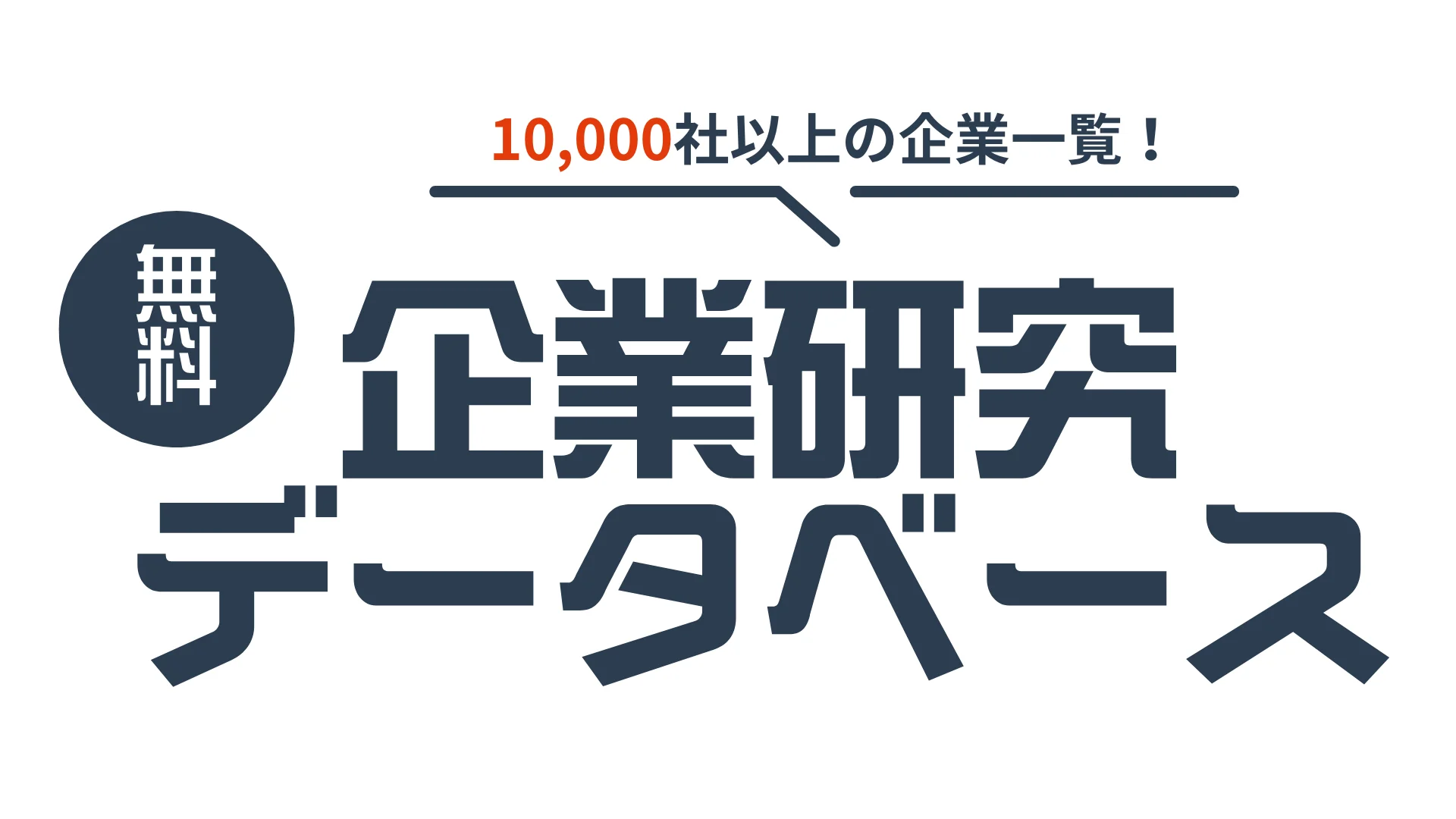




_720x480.webp)






_720x480.webp)