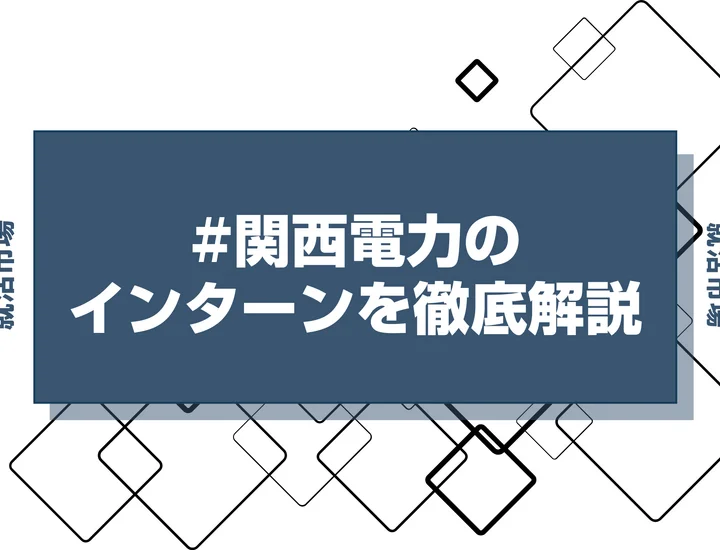今回は、就職活動を控える多くの学生さんから注目を集めている「長期インターン」について、その実態を詳しく解説していきます。
「周りの友達が始めたけど、自分もやるべき?」「そもそも長期インターンって何が得られるの?」そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、長期インターンに参加するメリット・デメリットから、どんな人に向いているのか、そして参加する前に確認すべきことまで、網羅的にご紹介します。
アルバイトとは一味違う、社会人としてのリアルな経験を積める長期インターン。
この記事を読めば、あなたが長期インターンに挑戦すべきかどうかが明確になり、就職活動に向けた次の一歩を踏み出すきっかけが見つかるはずです。
ぜひ最後まで読んで、あなたのキャリア選択の参考にしてくださいね。
目次[目次を全て表示する]
長期インターンに参加するメリット
長期インターンに参加することには、学生生活をより豊かにし、将来のキャリア形成に繋がる多くのメリットがあります。
単なる職業体験に留まらず、実践的なスキルを習得できる点は大きな魅力と言えるでしょう。
社員の一員として業務に携わることで、教科書や講義だけでは決して得られない、ビジネスの現場で通用する生きた知識と経験を身につけることができます。
また、年齢やバックグラウンドの異なる社会人と共に働く経験は、コミュニケーション能力や課題解決能力を養い、人としての視野を大きく広げてくれるはずです。
企業の内側から組織文化や業界の動向を肌で感じることで、入社後のミスマッチを防ぎ、より納得感のある企業選びが可能になります。
これらの経験は、就職活動においても他の学生と差別化できる強力なアピールポイントとなり、自信を持って選考に臨むための礎となるでしょう。
ここでは、長期インターンがもたらす具体的なメリットについて、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
ビジネススキルが身につく
長期インターンに参加する最大のメリットの一つは、実践的なビジネススキルが身につくことです。
アルバイト経験も貴重ですが、長期インターンではより社員に近い立場で業務に取り組むため、より専門的で応用範囲の広いスキルを習得できます。
例えば、企画書や報告書の作成を通じて、論理的思考力や分かりやすく伝えるための文章構成力が向上します。
また、会議での議事録作成やクライアントへのメール対応などを任されることもあり、社会人として必須のビジネスマナーやコミュニケーションスキルが自然と身につくでしょう。
さらに、データ分析やマーケティングリサーチといった専門的な業務に携わる機会があれば、ExcelやPowerPointなどのPCスキルはもちろん、より高度な専門知識を得ることも可能です。
これらのスキルは、特定の業界や職種に限らず、あらゆるビジネスシーンで求められるものばかりです。
学生のうちからこうした実践経験を積んでおくことで、入社後すぐに即戦力として活躍できる可能性が高まり、自身のキャリアにとって大きな財産となることは間違いありません。
人として成長ができる
長期インターンは、ビジネススキルだけでなく、人間的な成長を促す絶好の機会でもあります。
学生という立場から一歩踏み出し、企業の社員として責任ある業務を任される経験は、あなたを精神的に大きく成長させてくれるでしょう。
例えば、自分が担当した業務でミスをしてしまった場合、上司や先輩に報告し、その後の対応策を一緒に考え、実行に移す必要があります。
こうした経験は、決して楽なものではありませんが、失敗から学び、次に活かすという課題解決のプロセスを実践的に学ぶことができます。
また、社内には様々な経歴を持つ社員の方々がいます。
彼らとの日々のコミュニケーションや共同作業を通じて、多様な価値観に触れ、自分の視野が大きく広がるのを感じるはずです。
これまで出会ったことのないような大人たちと対等な立場で意見を交わす経験は、物事を多角的に捉える力や柔軟な思考力を養ってくれます。
困難な課題に挑戦し、それを乗り越えた時の達成感は、大きな自信となり、今後の人生を歩む上での強固な土台となるでしょう。
企業や業界にくわしくなる
企業のウェブサイトや説明会だけでは分からない、リアルな情報を得られることも長期インターンの大きなメリットです。
実際に企業の中に入って働くことで、その会社の雰囲気や文化、社員の方々の人柄などを肌で感じることができます。
「風通しの良い社風」と説明会で聞いていたけれど、実際にはどのようなコミュニケーションが取られているのか、といった具体的なイメージを掴むことができるでしょう。
また、日々の業務を通じて、その企業が属する業界全体の動向や課題、将来性についても深く理解することができます。
例えば、IT業界のインターンに参加すれば、最新技術のトレンドや市場の競争環境など、ニュースを読むだけでは得られない生きた情報を得られるはずです。
こうした内部からの視点は、企業研究や業界研究において非常に価値のある情報となり、自分が本当にその環境で働きたいのか、その業界でキャリアを築いていきたいのかを判断するための重要な材料となります。
入社後の「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぎ、心から納得できる企業選びを実現するために、長期インターンは非常に有効な手段と言えるでしょう。
就活で有利に働く場合がある
長期インターンでの経験は、就職活動において大きなアドバンテージとなる可能性があります。
多くの学生がアルバイトやサークル活動をアピールする中で、実務経験に基づいたエピソードは、採用担当者の目に留まりやすくなります。
特に、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」として、具体的な成果や学びを伴う長期インターンの経験を語ることができれば、他の学生と明確な差別化を図ることができるでしょう。
例えば、「チームで新規プロジェクトを立ち上げ、SNS運用を担当した結果、フォロワー数を3ヶ月で2倍にした」といった具体的なエピソードは、あなたの主体性や実行力を証明する強力な材料になります。
さらに、インターンでの働きぶりが評価されれば、特別選考ルートへの案内や、場合によっては早期内定に繋がるケースも少なくありません。
企業側としても、インターンを通じて人柄やスキルを深く理解した学生を採用することには大きなメリットがあるためです。
もちろん、有利になることだけが目的ではありませんが、結果として就職活動をスムーズに進められる可能性が高まるのは、長期インターンならではの魅力と言えるでしょう。
長期インターンに参加するデメリットはあるのか?
多くのメリットがある一方で、長期インターンに参加するにはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
良い面ばかりに目を向けるのではなく、大変な部分も理解した上で参加を決めなければ、後悔に繋がってしまうかもしれません。
最も大きな懸念点は、時間的な制約です。
大学の授業や課題、サークル活動、プライベートな時間など、学生生活は非常に多忙です。
そこに週に数日、まとまった時間のコミットメントが求められる長期インターンが入ってくると、学業との両立やプライベートの時間の確保が難しくなる可能性があります。
また、長期インターンはアルバイトとは異なり、社員と同様の責任感を求められる場面が多くなります。
任された仕事に対して成果を出すことが期待されるため、プレッシャーを感じることもあるでしょう。
安易な気持ちで始めてしまうと、精神的な負担が大きくなってしまうことも考えられます。
これらのデメリットを事前に理解し、自分のキャパシティやライフスタイルと照らし合わせ、本当に挑戦できるのかを冷静に判断することが重要です。
ここでは、長期インターンに参加する際に直面する可能性のあるデメリットについて、具体的に見ていきましょう。
時間的な制約が生まれることも多い
長期インターンに参加する上で、最も現実的なデメリットが時間的な制約です。
多くの長期インターンでは、週に2〜3日、1日あたり5時間以上といった、ある程度まとまった勤務時間を求められます。
そのため、大学の授業のスケジュールを調整したり、これまで参加していたサークル活動の頻度を減らしたりする必要が出てくるかもしれません。
特に、履修している授業が多い学年や、卒業研究で忙しい時期には、学業との両立が大きな課題となるでしょう。
また、友人と遊んだり、趣味に没頭したりするプライベートな時間も当然少なくなります。
これまでアルバイトに充てていた時間をインターンに使うことで、収入面での変化も考慮しなければなりません。
タイムマネジメントを徹底し、自分の中で何を優先するのかを明確にしておかなければ、学業がおろそかになったり、心身ともに疲弊してしまったりする可能性があります。
長期インターンを始める前には、自分の生活スタイルを見直し、無理なく続けられるかどうかを慎重に検討することが不可欠です。
責任を求められることがある
長期インターンは、単なる職業体験ではなく、企業の一員として業務に携わることを意味します。
そのため、アルバイト感覚でいると、求められる責任の重さに戸惑うことがあるかもしれません。
任された業務には納期があり、一定のクオリティが求められます。
自分の仕事の遅れやミスが、チーム全体や、場合によっては会社の利益に影響を与える可能性もゼロではありません。
例えば、クライアントに提出する資料の作成を任された場合、誤った情報を記載してしまえば、会社の信用を損なうことにもなりかねません。
このような社員と同様の責任感は、大きなプレッシャーとなることがあります。
もちろん、企業側も学生であることを理解しており、いきなり過度な責任を負わせることはありませんが、「お客様からお金をいただいて事業を行っている」というプロ意識を持つことは常に求められます。
指示されたことをこなすだけでなく、自ら考えて行動し、成果を出すという当事者意識が不可欠です。
この責任感を成長の機会と捉えられるかどうかが、長期インターンを充実させられるかどうかの分かれ道になるでしょう。
こんな人に長期インターンは向いている!
長期インターンは、誰にでもおすすめできるというわけではありません。
その経験を最大限に活かし、大きな成長に繋げられるのは、特定の意欲や目的を持った人です。
もしあなたが、現状に満足せず、学生のうちから何か新しいことに挑戦したい、自分を成長させたいと強く願っているなら、長期インターンは非常に良い選択肢となるでしょう。
例えば、「将来起業したい」「若いうちから市場価値の高いスキルを身につけたい」といった高い成長意欲を持つ人にとって、実践的なビジネスの現場は最高の学びの場となります。
また、就職活動を有利に進めたいという明確な目的がある人にも向いています。
他の学生と差がつくような圧倒的な経験を積み、自信を持って自己PRをしたいと考えているならば、長期インターンの経験は強力な武器になるはずです。
漠然と「何かやった方がいいのかな」と考えるのではなく、ビジネスの世界で通用する実践的なスキルを習得したいという具体的な目標がある人ほど、インターン先での学びは多く、充実した時間を過ごせるでしょう。
ここでは、長期インターンに特に向いている人の特徴を3つのタイプに分けてご紹介します。
成長意欲の高い人
「とにかく成長したい」「同世代の誰よりも早くビジネスの現場を経験したい」という強い成長意欲を持っている人は、長期インターンに非常に向いています。
長期インターンの現場では、常に新しい課題や困難な状況に直面します。
しかし、そうしたチャレンジングな環境を「成長のチャンス」と捉え、前向きに取り組める人にとっては、これ以上ない学びの場となるでしょう。
例えば、上司から「この新規事業のアイデア、君ならどうやって実現する?」といった難しい問いを投げかけられた時も、物怖じせずに自分の考えをぶつけ、積極的に行動できるような人です。
受け身で指示を待つのではなく、自ら仕事を見つけ出し、周囲を巻き込みながら課題解決に取り組める主体性が、成長の角度を大きく左右します。
また、失敗を恐れずに挑戦し、たとえうまくいかなくても、その経験から学びを得て次に活かそうとする姿勢も重要です。
現状の自分に満足せず、常に高みを目指し続けるハングリー精神を持つ人こそ、長期インターンを通じて飛躍的な成長を遂げることができるでしょう。
就活を有利に進めたい人
就職活動を有利に進め、希望する企業への内定を勝ち取りたいと考えている人にとって、長期インターンは非常に有効な戦略です。
面接の場で「学生時代に力を入れたことは何ですか?」と聞かれた際に、多くの学生がサークルやアルバイトの経験を話します。
その中で、実務経験に基づいた具体的なエピソードを語ることができれば、採用担当者に強い印象を残すことができます。
例えば、「営業のインターンシップで、テレアポの成功率を上げるためにトークスクリプトを改善し、アポイント獲得数を前月比150%にした」といった定量的な成果を伴う経験は、あなたの能力を客観的に証明する強力な武器となります。
また、長期インターンを通じて得たスキルや業界知識は、エントリーシートや面接での志望動機に深みと説得力をもたらします。
「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」という問いに対して、実体験に基づいた自分自身の言葉で語れるようになるため、他の学生との差別化を図ることができます。
単なる憧れではなく、リアルな企業理解に基づいた熱意を伝えることで、内定の可能性を大きく高めることができるでしょう。
ビジネススキルを身につけたいと思っている人
将来のキャリアを見据え、学生のうちから実践的なビジネススキルを身につけたいと考えている人にも、長期インターンは最適です。
大学の授業で得られる知識ももちろん重要ですが、それらをビジネスの現場でどのように活用するのかを学ぶ機会は多くありません。
長期インターンでは、社会人として働く上で必須となる基本的なスキルから、より専門的なスキルまで、幅広く習得することができます。
例えば、社内外の多くの人と関わる中で、相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝えるコミュニケーション能力が磨かれます。
また、複数のタスクを同時に進める中で、優先順位をつけて効率的に仕事を進めるタイムマネジメント能力も身につくでしょう。
さらに、マーケティングやプログラミング、デザインといった専門職のインターンに参加すれば、特定の分野における高度なスキルと実務経験を積むことができます。
これらのスキルは、就職活動でアピールできるだけでなく、社会人になってからのキャリアを築いていく上で、大きな財産となることは間違いありません。
こんな人には向いていない
長期インターンは多くのメリットがある一方で、誰もが参加すれば良いというものでもありません。
自分の性格や価値観、ライフスタイルによっては、長期インターンが負担になったり、期待したほどの成果が得られなかったりすることもあります。
ミスマッチを防ぐためにも、どのような人が向いていないのかを正直にお伝えします。
例えば、今は学業や研究に集中したい、あるいはサークル活動や趣味、友人との時間を何よりも大切にしたいと考えている人にとって、長期インターンによる時間的な制約は大きなストレスになる可能性があります。
プライベートな時間を充実させることが、自分にとっての最優先事項であるならば、無理にインターンを始める必要はないでしょう。
また、長期インターンの現場では、常に自分で考えて行動することが求められます。
指示されたことは完璧にこなせるけれど、自ら課題を見つけて行動するのは苦手という、受動的な性格の人にとっては、厳しい環境に感じられるかもしれません。
ここで挙げる特徴に当てはまるからといって、一概にダメというわけではありませんが、一度立ち止まって、本当に自分に合っているのかを考えてみることが大切です。
プライベートを優先したいと考えている人
もしあなたが、大学生活では友人との時間や趣味、サークル活動などを何よりも大切にしたいと考えているなら、長期インターンは慎重に検討すべきかもしれません。
長期インターンは、週に数日、ある程度の時間をコミットする必要があるため、必然的にプライベートな時間が少なくなります。
例えば、急な飲み会の誘いに参加できなくなったり、趣味に没頭する時間が取れなくなったりすることが増えるでしょう。
「今しかできない学生生活を思いっきり楽しみたい」という価値観を持っている場合、インターンによる時間的な制約が大きなストレスに感じられる可能性があります。
もちろん、タイムマネジメントを工夫することで両立は不可能ではありませんが、どちらも中途半端になってしまう恐れもあります。
自分のエネルギーをどこに注ぎたいのか、何を優先したいのかを自分自身に問いかけてみることが大切です。
もし、プライベートの充実が今の自分にとって最も重要なのであれば、無理に長期インターンを始めるのではなく、短期インターンに参加したり、就職活動が本格化してから集中して取り組んだりするという選択肢も考えられます。
何事においても受動的な性格の人
長期インターンの環境では、自ら考えて行動する「主体性」が強く求められます。
そのため、指示されたことはきちんとこなせるけれど、自分から積極的に仕事を探しに行ったり、改善提案をしたりするのが苦手な、いわゆる「指示待ち」タイプの人は、苦労する場面が多いかもしれません。
社員の方々は日々の業務で忙しく、手取り足取り丁寧に教えてくれる時間がないことも少なくありません。
そんな中で、「何かやることはありますか?」と常に受け身の姿勢でいると、成長の機会を逃してしまいます。
例えば、手が空いた時間に、ただ待っているのではなく、自ら「この業務について詳しく知りたいので、関連資料を読ませていただけませんか?」と提案できるかどうかが大きな違いを生みます。
長期インターンの目的は、単に作業をこなすことではなく、その経験を通じて学び、成長することです。
常に「なぜこの仕事をするのか」「もっと良くするためにはどうすればいいか」を考え、能動的に動ける人でなければ、貴重な時間を無駄にしてしまう可能性もあります。
もし自分に受動的な側面があると感じるなら、意識的に行動を変える覚悟を持って臨む必要があるでしょう。
長期インターンへ参加する前に確認しておきたいこと
長期インターンへの参加を決意する前に、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。
勢いだけで始めてしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔したり、途中で挫折してしまったりする原因になりかねません。
貴重な学生時代の時間を最大限に有効活用するためにも、事前の準備と自己分析は不可欠です。
まずは、「なぜ自分は長期インターンに参加したいのか」という目的を明確にすることが何よりも大切です。
目的意識がはっきりしていれば、インターン先選びの軸が定まり、参加後もモチベーションを維持しやすくなります。
次に、興味のあるインターン先について、徹底的に情報収集を行いましょう。
企業の公式サイトだけでなく、様々な角度からリアルな情報を集めることで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
そして、忘れてはならないのが、本分である学業との両立が可能かどうかを冷静に判断することです。
これらの準備をしっかりと行うことで、あなたは自信を持って長期インターンへの一歩を踏み出すことができるでしょう。
ここでは、参加前に必ず確認しておきたい3つのことについて、具体的に解説していきます。
参加する目的を明確にする
長期インターンを始める前に、まず「自分は何のために参加するのか」という目的を具体的に言語化してみましょう。
「周りがやっているから」「何となく就活に有利そうだから」といった漠然とした理由では、困難に直面した時に乗り越える力や、日々の業務から学びを得ようとする意欲が湧きにくくなります。
例えば、「Webマーケティングのスキルを身につけて、将来は事業会社のマーケターになりたい」「営業の実務経験を積んで、コミュニケーション能力に自信をつけたい」「ITベンチャーのスピード感の中で、新規事業の立ち上げを経験したい」など、できるだけ具体的に目的を設定することが重要です。
目的が明確であれば、数あるインターン先の中から自分に合った企業を選ぶ際のブレない軸になります。
また、面接の場でも、その目的を自分の言葉で熱意を持って伝えることができ、採用担当者に良い印象を与えることができるでしょう。
参加する目的意識の高さが、インターン期間中の学びの質を大きく左右します。
まずはノートやスマートフォンのメモ帳に、自分が長期インターンで得たいもの、達成したいことを書き出してみることから始めてみてください。
参加するインターン先についての情報を調べる
興味のあるインターン先が見つかったら、応募する前にその企業について徹底的にリサーチしましょう。
企業の公式ウェブサイトや採用ページを見るのはもちろんですが、それだけでは表面的な情報しか得られない可能性があります。
よりリアルな情報を得るためには、実際にその企業で働いている(または働いていた)人の声を参考にすることが非常に有効です。
例えば、企業の口コミサイトや、SNSで社名やインターンのプログラム名で検索してみると、社員や元インターン生の正直な感想が見つかることがあります。
どのような社風なのか、インターン生にはどのような業務が任されるのか、社員からのサポートは手厚いのか、といった具体的な情報を集めましょう。
また、可能であれば、その大学のキャリアセンターに相談して、過去にその企業のインターンに参加した先輩がいないか尋ねてみるのも良い方法です。
多角的な視点から情報を集め、自分が働く姿を具体的にイメージできるかどうかを確認することで、入社後の「思っていたのと違った」というミスマッチを最小限に抑えることができます。
学業に支障はないかよく考える
長期インターンへの熱意が高まるあまり、学生の本分である学業をおろそかにしてしまっては本末転倒です。
インターンを始める前には、必ず自分の履修状況や今後のスケジュールを確認し、学業に支障が出ないかを慎重に検討しましょう。
まず、自分の大学の卒業要件や、必修科目の単位がどのくらい残っているかを確認してください。
その上で、インターンにコミットできる時間が週に何時間、何曜日にあるのかを具体的に洗い出します。
特に、テスト期間やレポートの提出が重なる時期に、インターンの業務と両立できるかどうかは重要な判断ポイントです。
無理なスケジュールを組んでしまうと、どちらも中途半端になり、単位を落としてしまったり、インターン先で十分なパフォーマンスが発揮できなかったりする可能性があります。
少し余裕を持った計画を立てることが、長期的に両立させるためのコツです。
もし不安な点があれば、大学のキャリアセンターの職員や、信頼できるゼミの教授に相談してみるのも良いでしょう。
客観的なアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった問題点が見つかるかもしれません。
まとめ
今回は、長期インターンについて、メリット・デメリットから、向いている人の特徴、参加前に確認すべきことまで、幅広く解説してきました。
長期インターンは、実践的なビジネススキルを習得し、人として大きく成長できる貴重な機会です。
企業や業界への理解を深め、就職活動を有利に進めるための強力な武器にもなり得ます。
一方で、時間的な制約や責任が伴うことも事実であり、参加する目的を明確にし、学業との両立を慎重に考える必要があります。
この記事を読んで、自分が長期インターンに挑戦すべきかどうか、少しでもクリアになったでしょうか。
もし「挑戦してみたい」という気持ちが芽生えたなら、それはあなたの成長の第一歩です。
まずは自分の興味のある業界や企業をリサーチし、参加する目的を考えることから始めてみましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート