目次[目次を全て表示する]
5月から就活を始めるのは遅い?
就職活動は3月の広報解禁とともに本格化し、4月には多くの企業で選考が始まります。
そのため、5月から就活をスタートするのはやや遅いと感じる方が多いかもしれません。
ですが、「遅れたからもう無理だ」と決めつける必要はありません。
実際、厚生労働省の新規学卒者の採用に関する調査によると、約3割の企業が5月以降も新卒採用活動を継続しています。
また、通年採用を導入する企業も年々増えており、夏・秋採用での募集を行う企業も多く存在しています。
特に、中小企業やベンチャー企業、外資系、IT系企業では、5月以降が本格的な採用時期になることも少なくありません。
重要なのは、現在の自分の立ち位置を冷静に把握し、今から何をすべきかを明確にしたうえで、計画的に行動することです。
焦らず、着実にステップを踏めば、5月スタートでも納得のいく内定獲得は十分に可能です。
大学4年生:遅めだがまだ間に合う
5月から就職活動を始める大学4年生は、出遅れたと感じることもあるかもしれません。
実際、周囲の友人がすでに面接を受けていたり、内定をもらっていたりすると、焦る気持ちになるのも無理はありません。
しかし、就活は早ければ良いというものではありません。
自分に合った企業を見つけ、その企業にしっかりと準備して挑むことが何より大切です。
5月時点でも、企業の3割以上が採用活動を継続しているというデータもあります(厚生労働省調べ)。
また、夏採用・秋採用を実施する企業も多く、これからが本番という業界も少なくありません。
特に中小企業やベンチャー、外資系ではこの時期から選考が活発になります。
今から就活を始める際は、まず自己分析を丁寧に行い、志望業界や職種を明確にしましょう。
そのうえで、企業研究やエントリーシートの準備、面接練習など、やるべきことを一つずつ着実に進めていくことが大切です。
大学3年生:早めのスタートが就活成功の鍵
大学3年生で5月から就活を意識し始めている方は、非常に良いタイミングでスタートを切っていると言えます。
なぜなら、サマーインターンの募集がちょうど始まる時期であり、企業の情報を集めたり、自分の志向を整理したりするにはぴったりの時期だからです。
経団連の発表によると、多くの企業が6月〜8月にかけてサマーインターンの選考を行っており、5月はその準備期間にあたります。
この時期に情報収集やエントリーの準備を進めておけば、インターン参加を通して本選考に有利な立場を築くことも可能です。
ただし、「もう始めているから大丈夫」と安心してしまうのは禁物です。
むしろ、ここからの行動の質と量が、今後の就活を大きく左右します。
自己分析や業界研究、企業説明会への参加など、やるべきことは山積みです。

この時期から行動を始めた人ほど、志望業界の理解が深まり、自分に合った企業選びができるようになります。焦らず、しかし着実に準備を進めていけば、就活本番で自信を持って臨むことができます。就職活動は情報戦でもあります。早く動き始めたアドバンテージを活かし、自分に合った進路を見つけていきましょう。
【大学4年生の5月】最新の5月時点の26卒就活状況
5月時点では、多くの大学4年生がすでに就職活動を本格的に進めており、すでに内定を獲得している学生も多く見られます。
特に2026年卒の就活生においては、3月の広報解禁以降の動きが年々早まっている傾向があり、5月時点での内定率も高水準で推移しています。
その一方で、内定を得た学生が就活を継続している例も多く、自分に合った企業をじっくり見極めたいという姿勢が強まっていることが伺えます。
また、エントリー社数の平均値から見ても、就活生の多くが複数の企業を比較・検討している様子がうかがえます。
このような背景から、たとえ5月から就活を始めたとしても、まだ十分にチャンスがあるといえるでしょう。
今の自分の立ち位置をしっかりと把握し、状況に応じた準備と行動を進めていくことで、納得のいく結果を得ることは十分に可能です。
2026年春に卒業する就活生の内定率は76.2%
2025年5月時点で、2026年卒の大学4年生における内定率は76.2%に達しています。
これは前年同期(76.9%)とほぼ同水準で、就職活動の早期化が引き続き進んでいることがわかります。
多くの学生が3月の広報解禁と同時に積極的に動き出し、早期に選考を受けた結果といえるでしょう。
ただし、これはあくまで平均的な数値であり、すべての学生が同じ状況にあるわけではありません。

企業によって採用スケジュールは異なり、5月以降に本格的に採用活動を行う企業も少なくありません。したがって、まだ内定がないことに過度に焦る必要はありません。
3人に1人は内定を得ているが就活を続ける
注目すべきは、内定を獲得した学生のうち55.0%が引き続き就職活動を継続しているという点です。
これは、全体の約3人に1人が内定を得ていても納得のいく企業と出会うため、あるいは複数の内定を比較するために活動を続けていることを示しています。

この傾向は、自分に合った職場を慎重に選びたいという学生の姿勢の表れともいえるでしょう。ですから、今から就活を始める方も、まだチャンスは十分にあると前向きに捉えて行動することが大切です。
5月までの平均エントリー社数は23.4社
2026年卒の学生が5月までにエントリーした企業数の平均は23.4社とされています。
前年同期(23.9社)と比べやや減少傾向にはあるものの、依然として20社以上にエントリーしている学生が多い状況です。

就職活動においては幅広く企業を見ることがスタンダードになっているといえます。今から就活を始める方は、まずは興味のある業界・企業に積極的にエントリーし、情報収集を進めながら自分に合った選択肢を見つけていきましょう。
【大学4年生の5月】5月から就活を始める人がまずやるべきこと
就活が本格化する中で、「まだ何もしていない」「一度止めたけど再開したい」と感じている人も多いのではないでしょうか。
5月はまだ間に合う時期です。
自分の現状に応じて、今から何を始めるべきかを明確にして、一歩踏み出しましょう。
5月まで全く何もしてない場合
まず取り組むべきは自己分析です。
自分の価値観や得意分野、将来どう働きたいかを丁寧に見つめ直すことで、志望業界や企業選びの方向性が明確になります。
次に、業界研究や企業研究を始めましょう。
最初は興味のある分野からで構いません。
徐々に知識を深めることで、自分の希望に合った企業像が見えてきます。
その上で、エントリーシートの準備に取り掛かりましょう。
学生時代の経験や頑張ったことを整理し、志望動機と関連づけて言語化する練習が大切です。

オンラインや対面での企業説明会や合同企業説明会に参加することで、効率的に情報を得ることができます。最後に、面接対策にも早めに取り組んでおくと安心です。自己紹介や志望動機、学生時代に力を入れたことなど、基本的な質問にスムーズに答えられるように準備しておきましょう。
一度就活をしていたが休憩していた場合
再開する前に、まずは現在の就活市場の状況を確認することが大切です。
業界ごとの選考スケジュールや募集状況が変わっている可能性があるため、最新の情報を調べてみましょう。
そして、以前受けた選考を振り返り、うまくいかなかった点や手応えを感じた点を整理することで、自分の課題や強みに気づくことができます。
続いて、これまでに作成したエントリーシートや履歴書を見直し、今の自分に合った内容に更新しましょう。
就活の方向性が変わっている場合もあるため、志望業界や企業の見直しもおすすめです。
最後に、改めてなぜ働くのか、自分は何を大切にしたいのかといった軸を考えることで、モチベーションを再構築しやすくなります。
一度終わっていたが再就活をする場合
再就活を決意した背景を明確にすることが、選考を受ける際に非常に重要になります。
なぜ内定先を辞退したのか、あるいは就活を終えた後に再開する決断に至ったのか、自分なりの理由を整理しておきましょう。
それを踏まえ、今の自分がどんな企業に興味を持っているのかを見つめ直し、再度企業選びを行うことが必要です。
新たな視点で求人を探すことで、思いがけない良い出会いがあるかもしれません。

再びエントリーを始めるにあたっては、面接やエントリーシートの対策を丁寧に行い、ブランクが不安要素にならないように準備を重ねましょう。情報収集も継続的に行うことで、選考の機会を逃さずキャッチすることができます。迷いがあっても、再チャレンジを決意したその気持ちが、あなたの強みとなります。
【大学4年生の5月】順調に就活が進んでいる人が5月にやるべきこと
すでにエントリーや面接を重ね、就活が順調に進んでいる人にとっても、5月は今後の方針を整理したり、志望度を再確認したりする重要なタイミングです。
今の自分に合ったアクションを選び、納得のいく就活を続けましょう。
まだ内定がない場合
ここまで順調に選考に進んできたものの、まだ内定が出ていない場合は、自分の受けている企業との相性を改めて見直してみることが有効です。
通過率が高い企業の特徴を分析することで、今後の選考の方向性がより明確になります。
また、過去の面接経験を振り返り、うまく話せなかった部分や改善できそうな点に気づくことも重要です。
さらに、実際に働いている先輩やOB・OGとの交流を通じて、リアルな企業の姿を知ることができるのもこの時期ならではのメリットです。

自己PRや志望動機も、このタイミングで一度見直してみましょう。伝えたい内容がしっかり伝わるように、具体性や説得力を高める工夫が必要です。複数の選考が重なることも増えてくるため、スケジュール管理も忘れずに行いましょう。
内定は持っているが続ける場合
すでに内定を獲得していても、引き続き就活を継続する場合は、まず現内定先について冷静に分析してみることが大切です。
仕事内容や社風、待遇面など、自分の希望と照らし合わせて考えてみましょう。
その上で、比較対象となる企業を探してみると、新たな視点から企業選びができるようになります。
これまでの活動を通じて見えてきた就活軸をもう一度整理し、自分が本当に大切にしたい価値観を明確にすることも必要です。
選考準備も気を抜かず、常にベストな状態で臨めるようにしておくことで、新たな企業との出会いにも良い印象を与えることができます。
また、内定先とのやり取りや連絡は誠実に行うことが信頼関係を保つために大切です。
内定を持っていて終わろうか迷っている場合
内定を保有しているものの、就活を終えるべきか続けるべきか迷っているときは、まずその内定先についてより深く情報を集めてみましょう。
実際の職場の雰囲気や働き方など、イメージが明確になることで判断材料が増えます。
また、既に社会人として働いている先輩や信頼できる人に相談することで、新たな気づきを得られることもあります。
自分が今後どのような企業に応募する可能性があるかを洗い出してみると、就活を続けるべきかの判断もしやすくなります。

数年後の自分がどのように働いていたいかを想像してみると、今の選択がその未来につながるかを考えるきっかけになります。そして最後に、なぜ迷っているのかを自分の言葉で整理することで、心の中にあるモヤモヤの正体が見えてきます。
【大学4年生の5月】大学4年生5月の就活の注意点
大学4年生5月の就活の注意点は、以下の3つです。
- 面接対策をせずに面接に挑まない
- 持ち駒を切らさないようにする
内定を獲得するには、避けるべき行動が存在します。
何も考えずに行動していると、知らない間に内定獲得から遠ざかります。
順調に就活を進めている人や今から始める人も、本章の解説を参考にしてください。
無意識のうちに減点されないよう、きちんと対策しましょう。
面接対策をせずに面接に挑まない
面接対策をせずに面接に挑まないようにしてください。
就活は、対策していないとがバレると、評価が低くなるからです。
採用担当は、就活生の入社意欲や熱意を重要視しています。
その結果、対策していない=入社する意思がない、と判断されるでしょう。
5月になると面接の機会が増えます。
しかし、準備不足のまま挑むと本来の力を発揮できません。
面接対策は、過去の質問例を参考にしながら、自分の経験や志望動機を言語化しましょう。
また、面接の練習には模擬面接が効果的です。
企業の採用担当者や大学職員の方が、面接官を担当してくれます。
模擬面接後には、採用のプロからアドバイスがもらえるため、効率よく対策ができます。

面接では、短時間で自分の魅力や熱意を伝えることが求められます。そのため、事前の実践的な面接対策が結果を大きく左右する場面が多いのです。特に5月以降は選考が本格化し、面接機会も増えてくるため、模擬面接やフィードバックを活用することが、合格への近道になります。自分の言葉で語る経験や志望動機は、一朝一夕ではつくれません。今からでも遅くありませんので、地に足をつけた準備を積み重ねていきましょう。準備をしている姿勢そのものが、入社意欲の証として伝わるという点も意識しておくと良いですね。
持ち駒を切らさないようにする
持ち駒を切らさないことも重要です。
持ち駒とは、エントリーした後、選考結果を待っている企業数のことです。
つまり持ち駒が多い人は、たくさん応募していることになります。
時間が経つにつれて、選考結果の連絡が来るため、持ち駒は減少します。
内定が出るまでは、複数の企業を並行して受けましょう。
幅広い業界・企業にエントリーすることで、就活の焦りを減らせます。
「内定が獲得できない」「内定が獲得できなかったらどうしよう」と考える就活生は、どんどんエントリーしましょう。
ただし、自分の許容量には注意してください。
数が多すぎると管理できなくなり、本末転倒です。
自分にとって負担にならない企業数で、持ち駒を安定させましょう。
各選考の振り返りをする
5月は、選考が本格的に進んでいる人も多く、面接やESの経験が増えてくる重要なタイミングです。
選考が多くなる5月頃の時期に大切なのは、一つひとつの選考を「受けっぱなし」にせず、積極的に振り返りをすることです。
面接でどのような質問をされたか、自分はどのように答えたか、面接官の反応はどうだったかなどをしっかりとメモしておくことで、次回以降の選考に活かせるようになります。
また、うまくアピールできなかった箇所や自信を持って答えられた質問などを整理すれば、自分の課題や改善点が明確になります。
各選考の振り返りは、就活を通しての「自分の成長」を感じられる重要な機会でもあります。
選考結果に対して必要以上に一喜一憂するのではなく、経験を積み重ねながらそこから学んでいく姿勢が、内定獲得への近道になります。

この時期は、面接やエントリーシートを数多くこなすことになるため、つい1社1社が流れ作業になってしまうこともあります。ですが、選考ごとの振り返りこそが、就活力を高める最大のカギです。自分の伝え方や面接官の反応を記録することで、次の面接ではより洗練されたアピールができるようになります。失敗から学べる人は、短期間で驚くほど成長します。振り返りを積み重ねることで、自信と納得感をもって内定を迎えることができるはずです。自分の成長を感じながら、一歩ずつ前進していきましょう。
周りと比較しすぎない
5月になると、SNSなどで「内定報告」を目にする機会が増え、焦りを感じてしまう人も少なくありません。
大学でも「〇〇さんは△△会社から内定をもらったらしい」などの噂が頻繁に飛び交うようになるでしょう。
しかし、就活のペースや進め方は人それぞれです。
早く決まったからといって必ずしも優れているとはいえませんし、じっくり自分と向き合いながら、ぴったり合う企業を探している人もたくさんいます。
就活に集中するうえで大切なのは、他人と比較することではなく、自分の軸を見失わないことです。
「自分がどう働きたいか」「何にやりがいを感じるか」を重要視しながら、納得のいく就活を進めることが大事なポイントです。
なお、就活で必要以上に焦ることは、判断を鈍らせる原因にもなります。
周りとの比較は不要なので、まずは落ち着いて、やるべきことを確実にこなしていきましょう。

周囲の声やSNSでの内定報告に不安を感じる気持ちは、ごく自然なことです。でも、就職活動は「早ければ良い」「内定が多ければ正解」という単純なものではありません。むしろ、自分なりの基準で納得できる選択ができた人こそ、入社後の満足度や定着率が高い傾向にあります。情報があふれる時代だからこそ、他人の就活を軸のするのではなく「自分の価値観や将来像」を丁寧に見つめ直すことが就職活動成功への大きな一歩になるでしょう。
適度に休憩する
5月の就活では、適度に休憩することも重要です。
就活生にとって、就活に関連する活動は、エネルギーを大きく消耗するものです。
面接の緊張や結果待ちの不安、自己分析やES作成など、精神的にも体力的にも負担を感じるタイミングは多いでしょう。
そのような中でしっかりとモチベーションを保つには、意識的な休憩も欠かせません。
例えば1日だけ就活のことを一切考えない日を作ったり、好きなことに没頭する時間を取ったりするなど、リフレッシュの工夫をすることが重要です。
就活における適度な休憩は、集中力や判断力を回復させ、結果的に選考対策の質を高めてくれます。
心身の健康を大事にしながら、長期戦にもうまく耐えていけるようにすることが、5月以降の就活成功のカギになります。
【大学4年生の5月】5月に就活をする26卒が知っておくべき内定獲得のチャンス
5月以降の就活には、様々な内定獲得のチャンスが存在します。
- 夏採用・秋採用
- 通年採用
- 就活留年・浪人からの第二新卒就活
企業によって実施していない場合もありますが、採用枠としてこれらが設けられることも少なくない、ということを覚えておきましょう。
夏採用・秋採用
多くの企業が、5月〜10月にかけて「夏採用」「秋採用」として追加募集や選考を実施しています。
この時期は、就活を続けている学生の数が減るため、倍率が比較的下がり、じっくり見てもらえるチャンスでもあります。
- 夏・秋までの採用で必要な採用数を確保できなかった
- 内定辞退者が出て採用数が足りなくなった
- 新しいポジションができて採用枠が増えた
どの理由にしても、採用枠が残り少ない中で実施される採用活動であることは確かです。
企業側の目も厳しくなりがちなので、面接の質や志望動機の明確さが問われることを意識しましょう。
通年採用
IT業界や外資系企業を中心に、年中いつでも応募できる通年採用を導入する企業が増えています。
- 楽天
- ソフトバンク
- リクルート
- ファーストリテイリング(ユニクロ)
- サイバーエージェント
- メルカリ
- KDDI
この採用方式では、タイミングよりも本人のスキル・経験・ポテンシャルが重視されるため、自分の強みが明確な学生にとっては非常に有利です。
ポートフォリオ提出や課題選考などがあるケースも多いため、自己PRの質を高めておくことが鍵になります。
就活留年・浪人からの第二新卒就活
「どうしても納得できる内定が出なかった」ときは、あえて一度就職を見送り、再チャレンジする選択肢もあります。
就活留年・既卒として再挑戦する場合、重要なのは「なぜ就職しなかったのか?」「その期間に何をしていたのか?」を説明できることです。
また、第二新卒として入社1〜3年以内に転職する人も増えており、キャリアの柔軟性は高まっています。

納得できる就職先が見つからないとき、選択肢を広げて再挑戦することは決して後ろ向きではありません。重要なのは、その期間をどう過ごし、どのような意志を持って次の一歩に臨んでいるかです。就活留年や既卒でも、しっかりと目的意識があれば、企業側も前向きに評価してくれます。また、第二新卒という形で新たなキャリアを描く人も年々増加しており、今は多様なキャリアパスが認められる時代です。焦らず、自分の納得のいく選択を見つけることが、結果として良いキャリアのスタートにつながるはずです。
【大学4年生の5月】26卒が5月以降でも応募できる企業の例
5月を迎えた段階で、すでに多くの企業がエントリーを締め切っている状況ですが、それでもまだまだ応募可能な企業はたくさん存在します。
特に5月以降は、視野を少し広げることで、これまで気づかなかった優良企業との出会いが生まれるチャンスでもあります。
26卒が5月以降でも応募できる企業の例
- 大手企業のグループ会社
- 知名度が低いホワイト企業
- ベンチャー企業
- 二次募集をしている企業
これからご紹介するのは、26卒の皆さんが5月以降でもエントリーできる可能性の高い企業の例です。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った企業選びの参考にしてみてください。
焦らず、着実に未来を切り開いていくためにも、それぞれの特徴はしっかり理解しておきましょう。
大手企業のグループ会社
5月以降でも採用活動を続けている代表的な存在が、大手企業のグループ会社です。
親会社に比べると知名度は低めですが、経営基盤がしっかりしているため、倒産リスクも低く、安定した環境で働きたい方に特におすすめです。
大手企業のグループ会社の例
- 三井不動産レジデンシャル(親会社:三井不動産)
- ANAウィングス(親会社:ANAホールディングス)
- 日産車体(親会社:日産自動車)
- みずほリース(親会社:みずほフィナンシャルグループ)
- パナソニック コネクト(親会社:パナソニックホールディングス)
- NTTデータカスタマサービス(親会社:NTTデータ) など
大手グループの一員ということで、福利厚生や教育制度なども整っている場合が多く、待遇面も親会社に引けを取らないケースが少なくありません。
一方で、親会社と比較すると応募者数がやや少ないため、選考のハードルも若干下がる傾向にあります。
グループ会社ごとに特色が異なるため、自分の興味や得意分野にマッチした企業を探してみるとよいでしょう。
たとえば、メーカー系、金融系、IT系など、幅広い業種でチャンスがあります。
今からでも十分に間に合いますので、大手企業に憧れを持ちながらも、少し現実的な視点でグループ会社を調べてみると、新たな可能性が見えてくるかもしれません。
知名度が低いホワイト企業
世間的な知名度が高くないものの、働きやすさや待遇面に優れた「ホワイト企業」にも、5月以降に出会えるチャンスがあります。
特にBtoB(企業向けビジネス)を展開する企業は、一般消費者との接点が少ないため知名度が低くなりがちですが、実は隠れた優良企業が多いのです。
こうした企業は採用に苦戦することもあり、5月以降も新卒採用枠を開放していることが珍しくありません。
倍率も比較的低めであるため、しっかり準備をして臨めば十分に内定を獲得できるチャンスがあります。
また、BtoB企業は安定性が高く、腰を据えて長く働きたい方にも向いています。
知らなかった業界や企業に目を向けることで、自分でも想像していなかったような適性に気づくきっかけにもなるでしょう。
自分自身の希望条件を改めて整理し、「知名度に惑わされない就活」を意識することが、5月以降の成功の鍵となります。
ベンチャー企業
ベンチャー企業は、一般的な新卒採用スケジュールに縛られず、通年で採用活動を行っている場合が多いのが特徴です。
5月以降でも積極的に人材を募集している企業がたくさんありますので、今からの挑戦にも大きなチャンスが広がっています。
ベンチャー企業の魅力は、何といっても成長スピードの速さと、若手にも多くのチャンスが与えられる点です。
自分の力を試したい方や、裁量を持って働きたい方にとっては、非常にやりがいのある環境といえるでしょう。
もちろん、安定性や整った制度面では大手企業に劣る場合もありますが、それを補って余りある経験値や成長の機会が得られるのがベンチャー企業の良さです。
特に、これからのキャリアを自分自身で切り拓いていきたいという思いが強い方には、ベンチャー企業への挑戦をぜひ検討してみてください。
熱意とポテンシャルを評価してくれる企業が、きっと見つかるはずです。
二次募集をしている企業
5月以降には、一次募集を終えた企業が「二次募集」として追加採用を行うケースも多く見られます。
二次募集を行う企業の特徴
- 内定辞退者が出たため、追加募集を行う企業
- もともと採用活動を長期間行う計画の企業
- 採用ターゲットを絞り直している企業
- 新しい採用枠(事業拡張など)ができた企業
特に大手企業の中には、6月〜7月にかけて若干名の追加募集を行うことがあり、これを狙うのも一つの手です。
ただし、二次募集では、一次募集に比べて採用枠が少ない分、倍率が上がる傾向にあるため、より高いレベルの自己PRや志望動機が求められます。
自分のアピールポイントをさらに磨き、説得力のあるプレゼンテーションができるよう準備を重ねましょう。
また、中小企業や外資系、ベンチャー企業の中には、独自のタイミングで採用活動を行っているところも多いため、引き続き積極的に情報収集を続けることが大切です。
就活サイトだけでなく、企業のホームページやリクルーター経由の情報も活用し、アンテナを広く張っておきましょう。
チャンスは待つものではなく、自分から掴みに行くもの。
5月以降も、前向きな姿勢を忘れずに取り組んでいきましょう。
【大学4年生の5月】26卒が5月からでも内定を獲得するための方法
5月から本格的に就活をスタートする場合でも、正しい方法を押さえて行動すれば、十分に内定を獲得することが可能です。
26卒が5月からでも内定を獲得するための方法
- 企業説明会合同説明会に参加する
- 大学のキャリア支援を受ける
- 企業HPや公式SNSで情報収集する
- 就活エージェントを利用する
焦りや不安を感じるかもしれませんが、重要なのは「今できることに集中し、一歩ずつ確実に進めていくこと」です。
ここでは、26卒の皆さんが5月以降に内定を掴むために実践してほしい具体的な方法を4つご紹介します。
それぞれのアクションが、未来につながる大切な一歩になりますので、ぜひ参考にして積極的に行動してみてください。
企業説明会・合同説明会に参加する
5月以降も、各地で企業説明会や合同説明会が開催されています。
この機会を活かして、できるだけ多くの企業と直接接点を持つことをおすすめします。
企業説明会では、パンフレットやウェブサイトだけでは分からないリアルな情報を、社員の方から直接聞くことができます。
実際の仕事内容、職場の雰囲気、キャリアパスなど、具体的なイメージを持つことで、志望動機もより説得力のあるものになるでしょう。
また、合同説明会では一度に複数の企業の話を聞けるため、業界研究や企業比較にも非常に役立ちます。
「まだ業界や職種を絞りきれていない」という方にとっては、視野を広げる絶好のチャンスです。
参加する際には、事前に質問を準備しておくと、より深い情報を得ることができます。
積極的な姿勢を見せることで、企業側に好印象を与えることにもつながりますので、ぜひ前向きに活用しましょう。
大学のキャリア支援を受ける
大学に設置されているキャリア支援センターは、就活生にとって非常に心強いサポート機関です。
5月から本格的に動き出す方にとっても、ぜひ積極的に利用していただきたい存在です。
キャリアセンターでは、求人紹介、エントリーシートの添削、面接練習、キャリアカウンセリングなど、幅広い支援を受けることができます。
また、企業の中には、特定の大学にのみ求人情報を提供している場合もあり、こうした「学内限定求人」は非常に貴重なチャンスとなることがあります。
さらに、キャリア支援担当者は、過去の内定実績や業界ごとの傾向についても豊富な知識を持っているため、自分一人では気づかない選択肢を提案してくれることもあります。
「どこから手をつけていいか分からない」と感じる場合は、まずキャリアセンターに相談してみましょう。
一緒に就活戦略を立てることで、次に取るべき具体的な行動が明確になり、安心して進めることができるはずです。

大学のキャリア支援センターは、今からでも十分に活用できる頼もしいパートナーです。特に、動き出しが遅れたと感じている方にとっても、個別相談や添削指導を通じて短期間で力をつけることが可能です。「まずは話を聞きに行く」という小さな一歩が、思わぬチャンスに繋がることもあります。焦る必要はありません。一つ一つ着実に取り組むことが、確かな成長に繋がっていきますよ。
企業HPや公式SNSで情報収集する
就活を成功させるためには、最新の情報を素早くキャッチすることが欠かせません。
そのためには、企業の公式HPやSNSアカウントを積極的にチェックすることをおすすめします。
企業の採用ページでは、追加募集の情報や説明会の案内、採用スケジュールの変更などが随時更新されています。
また、企業が運用している公式SNSでは、社内イベントの様子や社員のインタビュー、最新プロジェクトの紹介など、公式サイトでは得られない「企業の今」を知ることができます。
リアルタイムで動いている情報をもとに行動することで、ライバルよりも一歩先にエントリーできる可能性も高まります。
さらに、就活に特化した情報を発信しているSNSアカウントや、業界で活躍している社会人のアカウントをフォローすることで、業界研究にも役立ちます。
日々のスキマ時間を有効活用し、情報感度を高めていきましょう。
就活エージェントを利用する
「一人での就活に不安を感じる」「効率的に内定を目指したい」という方におすすめなのが、就活エージェントの活用です。
エージェントでは、専任のアドバイザーが一人ひとりの性格や希望条件に合わせて企業を紹介してくれます。
紹介だけでなく、エントリーシートの添削や面接対策、スケジュール管理のサポートまで受けられるため、非常に心強い存在となります。
また、非公開求人に出会えるチャンスもあり、自力ではたどり着けない企業へのルートが開ける場合もあります。
エージェントを活用する際には、自分の希望や強みをしっかり伝えることがポイントです。
アドバイザーとの連携を密に取りながら、ミスマッチのない企業選びを進めていきましょう。
やみくもに応募を繰り返すよりも、プロの視点を取り入れた戦略的な就活を進めることで、効率的に内定獲得に近づくことができます。

就活エージェントの利用は、限られた時間の中で効率的に結果を出すための有効な手段です。特に、自己分析や企業選びに不安を感じている方にとって、第三者視点でのアドバイスは大きな助けになります。エージェントを賢く活用することで、思いがけない企業とのご縁が生まれることも少なくありません。「相談すること」自体が、次の一歩に繋がりますので、ぜひ前向きな気持ちで一度門を叩いてみてくださいね。
【大学3年生の5月】27卒が5月から就活をするのは遅い?
結論から申し上げると、大学3年生の5月から就活準備を始めるのは、決して遅くありません。
むしろ、多くの学生がこの時期から意識的に動き出しており、「早すぎるかも?」と不安になる必要もありません。
ただし、近年の就活は年々スピードが早くなっている傾向があり、のんびり構えていると周囲との差がついてしまう可能性もあります。
だからこそ、「5月は就活準備に取り組む絶好のタイミング」だと捉え、早めに行動を起こすことが大切です。
それでは、27卒の就活スケジュールや、今の時期にやっておきたいこと、企業の動きについて詳しく見ていきましょう。
27卒の一般的な就活スケジュール
27卒の就活は、26卒よりも半月〜1ヶ月ほど早く動き出すと予想されています。
これは、多くの企業が年々「早期選考」や「早期内定」を重視するようになってきているためです。
早期に優秀な学生を確保するため、サマーインターンの開始時期も年々早まっています。
一般的な流れとしては、
- 7月〜9月:サマーインターンに参加
- 10月頃〜:早期選考がスタート
- 1月頃〜:本選考開始(企業によっては12月から)
というスケジュールが想定されます。
つまり、今のうちからしっかり準備を進めておけば、サマーインターンにもスムーズに参加でき、その後の選考でも有利に立ち回ることができます。
5月からの準備が、夏以降の成功を左右すると言っても過言ではありません。
27卒の就活における5月の位置付け
27卒にとっての5月は、就活準備の土台を固める時期です。
この段階でやっておきたいのは以下のような内容です。
- 自己分析:自分の価値観や強みを明確にする
- 業界・企業研究:どんな企業があるのか、どんな働き方をしたいのかを知る
- 就活の軸決め:どんな基準で企業を選ぶか、自分なりの判断軸をつくる
今のうちにこれらをしっかり進めておくことで、サマーインターンの選考やES作成がスムーズに行えるようになります。
焦る必要はありませんが、「なんとなく後回しにしていたらあっという間に夏が来ていた」という状況は避けたいところです。
時間に余裕がある今だからこそ、丁寧に自分と向き合う時間を持つようにしましょう。

27卒の皆さんは、これまで以上に「早めの行動」がカギとなります。
5月時点で基礎を固められれば、サマーインターン選考も安心して臨めますし、秋以降の本格化に向けても大きなアドバンテージとなります。
一歩一歩着実に準備を進めながら、自分のペースを大切にすることも忘れずに取り組んでいきましょう。応援しています!
27卒の就活に向けた5月の企業の動き
企業側の動きとしては、5月時点ではまだ本選考や早期選考に向けた準備段階であることが多いです。
この時期は以下のような動きが見られます。
- 来年度(27卒)の採用計画を立てている
- サマーインターンの準備・設計を進めている
- 秋冬の採用イベントや説明会の企画を始めている
つまり、企業もまだ採用に向けての本格始動には至っていない場合が多いため、学生にとっては情報収集や準備を進めるチャンスでもあります。
また、一部の先進的な企業ではすでにサマーインターンの募集が始まっていたり、インターン選考の告知が行われている場合もあります。
企業のSNSや採用ページ、就活サイトをこまめにチェックしておくことが大切です。
【大学3年生の5月】大学3年生が5月にすべき就活
では、ここからは、大学3年生が5月にすべき就活の内容を紹介していきます。
近年は就活が早期化しているため、3年生の5月から準備に取り掛かる学生は決して珍しくありません。
そのため「そろそろ就活しなきゃ」と感じたら、以下をチェックし、やるべき準備をしっかりとこなしていきましょう。
大学3年生が5月にすべき就活の内容は、以下のとおりです。
- 外資系企業のES提出
- 就活対策
- サマーインターンの準備
特に、サマーインターンは就活のモチベーションを高めたり業界・企業研究を行ったりするうえで良い機会になるため、準備を欠かさないようにしましょう。
では、詳細を一つひとつまとめていきます。
外資系企業のES提出
外資系企業を目指す就活生は、ESを提出しましょう。
外資系企業は、日系企業と比較して、早い時期から選考が進むからです。
とくにコンサルや投資銀行、IT企業などは5月〜6月にESの締め切りを迎えます。
油断していると、エントリーできずに終わってしまう可能性があります。
そのため、できる限り早い段階でESを提出しましょう。
5月にはGWがあります。
長期休暇をうまく活用して、提出準備を整えましょう。
ただし、大学のキャリアセンターや就活エージェントは、休みに入るため注意してください。
相談事がある就活生は、GWに入る前に解決しておきましょう。
外資系企業を志望する就活生は、選考スケジュールに注意してください。
就活対策
ほかには、就活対策として、業界・企業について研究や分析を進めておくことが大切です。
まだ3年生の5月ではあるものの、今後はサマーインターンを経て、早ければ秋頃には一部の企業は早期選考をスタートさせることになります。
気がつけばほとんど何もしないまま3年生の秋になってしまった…というパターンも珍しくないため、時間があるうちに、業界・企業研究はしっかり進めておくべきといえます。
早いうちに研究を進めたうえで、自分がどの業界に合っているのかを把握しておけば、よりスムーズに業界・企業選びができます。
エントリーシートや面接などの選考対策にも時間を使いやすくなるため、5月頃からは、今後のために準備を徹底しておきましょう。
業界・企業研究を行っても自分がどの業界に向いているのかわからない、と悩んだときは、じっくり時間をかけて自己分析を行うことも大切です。
サマーインターンの準備
大学3年生が5月に行うべき就活の中でも、サマーインターンの準備は非常に重要なステップです。
多くの企業がサマーインターンの募集情報を5月頃から順次公開し始めるため、このタイミングでアンテナを張っておくことで、応募のチャンスを逃さずに済みます。
まずは、自分が気になる業界や企業のインターン情報を集め、「参加してみたい」と思える企業に目星をつけておきましょう。
興味のある企業をいくつかピックアップしておくと、選考が始まった際にスムーズに対応できます。
インターンのエントリーには、エントリーシートの提出や面接、適性検査などが求められることも多く、想像以上に準備に時間がかかる場合もあります。
そのため、5月の段階で余裕をもって情報収集を始め、必要な準備を少しずつ進めていくことが大切です。
また、サマーインターンは「就活を本格的に始めるきっかけ」にもなりやすく、実際の企業での体験を通じて業界理解を深めることができます。
参加した学生の中には、そのまま早期選考につながるケースもあるため、インターン参加は就活を有利に進めるうえでも非常に効果的です。
「まだ自分には早いかも…」と感じる方もいるかもしれませんが、まずは気軽に情報を見てみることから始めてみてください。
気になる企業が見つかれば、その情報をメモしたり、カレンダーに選考スケジュールを記録したりと、できることから少しずつ取り組んでいきましょう。
今の行動が、夏以降の就活に大きな差をつける第一歩になります。
焦らず、でも着実に準備を進めていくことが、サマーインターン参加、そしてその後の選考成功へとつながっていきます。

サマーインターンは、就活本番に向けた重要なスタートラインです。
情報収集と早めの準備が、後のチャンスを確実に広げるポイントになります。
「今の自分にできることから少しずつ」という意識を持つことで、着実に成長につながります。
最初の一歩を大切にしながら、焦らず自分のペースで進めていきましょう。応援しています!
【大学3年生の5月】27卒は5月からインターンに積極的にエントリーしよう
インターンシップは実際の仕事を体験できる貴重な機会です。
参加することで業界や企業に対する理解が深まり、自分に合う職場環境を見極めることができます。
また、社員との交流やフィードバックを通じて、自分の課題や強みに気づける点も大きなメリットです。
さらに、インターン経験は選考時のESや面接で説得力のあるエピソードとして活用できます。
特にサマーインターンは選考直結型も多いため、5月のうちから情報収集や準備を始めることが重要です。
就活が超早期化している27卒ではインターンシップに参加することが非常に重要です。時間を作り積極的に参加しましょう。
インターンに参加するメリット
インターンシップに参加することには様々なメリットがあります。
まず、企業の仕事内容や職場の雰囲気を実際に体験できます。
この体験は志望動機や自己PRの裏付けとなり、就活本番での説得力を高めてくれます。
次に、働くうえで大切にしたい価値観や、自分が活躍できる環境の条件にも気づけるようになります。
社員と直接コミュニケーションを取ることで、仕事への理解が深まり、自分の成長にもつながります。
一部の企業では、インターン参加者に早期選考の案内を出すケースもあるため、積極的に参加する価値があります。
また、インターンでは、他大学の就活生と関わることもできるので就活へのモチベーションを高めることができるでしょう。
サマーインターンの参加率
就活は年々早期化しているため、27卒では大学3年生のうち、およそ7割がサマーインターンに参加すると言われています。
就活の早期化が進むなかで、インターンへの参加は当たり前になりつつあります。
このため、参加しないと周りから出遅れた状況になってしまうと考えられます。
サマーインターンでは、企業側も学生を見極めており、評価次第では早期内定につながることもあります。
5月はその準備期間として、業界研究や企業分析、ES作成などに集中することが求められます。
本選考直結型がおすすめ
サマーインターンには、本選考直結型を採用する企業が増えています。
このタイプのインターンでは、参加中の評価によって早期選考や特別ルートに案内されることがあります。
通常の選考よりも早い段階で内定を獲得できるため、就活全体の負担を軽減することができます。
特に外資系企業や大手企業ではこの傾向が顕著で、効率よく就活を進めたい学生には最適な選択肢となります。
5月からインターン情報をチェックし、エントリーの準備を整えておくことが大切です。
ほとんどのインターンでは、参加するためにESを提出しなければなりません。
インターン選考の志望動機・自己PRの書き方について以下の記事で詳しく解説しているので是非参考にしてみてください。
【大学3年生の5月】サマーインターンのおすすめの探し方5選
サマーインターンは、就活の第一歩を踏み出すうえで非常に有効な機会です。
実際の職場を体験できるだけでなく、企業理解を深めたり、本選考への足がかりになったりと、多くのメリットがあります。
そのため、5月の段階で情報収集を始めることは、就活の成功に向けた重要な準備といえるでしょう。
とはいえ、どこから探せばよいのかわからないと感じている方も多いはずです。
そこでここでは、大学3年生がサマーインターンを見つけるためのおすすめの探し方を5つご紹介します。
それぞれの方法に特徴がありますので、自分に合ったやり方を見つけて、積極的に活用していきましょう。
企業HPを見る
気になる企業がある場合、まず確認したいのが公式ホームページの採用情報や新卒採用ページです。
多くの企業が、インターンシップ情報を自社サイトでいち早く発信しています。
特に大手企業では、サマーインターンの詳細やエントリー期間、選考方法などが分かりやすくまとめられていることが多いため、情報の正確性という点でも安心できます。
また、企業HPでは事業内容や社風、求める人物像なども詳しく紹介されているため、応募前に企業理解を深めるのにも役立ちます。
志望動機を考える際のヒントにもなりますので、こまめにチェックするようにしましょう。

企業HPは待つのではなく見に行く姿勢が大切です。気になる業界の企業をリストアップしておくと、効率よく情報収集が進みます。
企業の公式SNSをみる
近年では、多くの企業が公式のSNSアカウントを活用して、採用やインターンに関する情報を発信しています。
特にTwitter(現X)やInstagram、YouTubeなどでは、インターン募集のお知らせだけでなく、実際に働いている社員の声や職場の雰囲気が伝わる投稿が多く見られます。
SNSならではの企業の素顔を知ることができる点は、企業HPにはない魅力のひとつです。
オフィスの様子や社員のイベントの様子など、社風を知るヒントが多く詰まっています。
また、フォローしておくことで最新情報をリアルタイムでキャッチできるのも大きなメリットです。
サマーインターンの募集開始や説明会の告知などもタイムリーに受け取れるため、情報に乗り遅れることがありません。
SNSを使った企業研究は、今後の志望動機づくりにもつながるので、気になる企業があれば積極的にチェックしておきましょう。
Webサイトを活用する
就活サイトやインターン専門のポータルサイトも、インターン情報を探すうえで非常に便利なツールです。
代表的なものとしてはマイナビ、リクナビ、あさがくナビなどがあり、各企業のインターン情報が豊富に掲載されています。
検索機能が充実しているため、業界別・職種別・開催地域・実施時期など、自分の希望条件に合わせて効率よく探すことができます。
また、エントリーの管理やスケジュールの確認なども一括で行えるため、複数の企業に応募する際にも便利です。

さらに、インターン参加者の体験談や企業担当者のインタビュー記事なども掲載されており、企業選びの参考になる情報が盛りだくさんです。まずは複数のサイトに登録し、希望条件を登録しておくことで、最新のインターン情報をメールで受け取ることもできます。情報収集の主軸として、積極的に活用しましょう。
大学のキャリアセンターで探す
大学のキャリアセンター(就職課)は、企業と学生をつなぐ大切なサポート機関です。
実は、一般には出回っていない大学限定のインターンシップ情報や、企業から大学宛に届いた非公開の募集情報が紹介されることもあります。
また、キャリアアドバイザーに相談することで、自分の希望や適性に合った企業やプログラムを提案してもらえるケースもあります。

履歴書やエントリーシートの添削、面接練習などのサポートも受けられるため、就活準備を総合的に進めるうえでも大変心強い存在です。「インターンって何から始めればいいかわからない…」という方は、まずキャリアセンターを訪れてみるのがおすすめです。大学独自のネットワークを活かして、自分に合ったインターンを見つけていきましょう。
先輩・知人に紹介してもらう
実際にインターンに参加した経験のある先輩や、就職活動を終えた知人からの情報は、とても貴重です。
パンフレットやWebサイトには載っていないリアルな体験談や本音の感想を聞くことで、その企業やインターンの実態がぐっと身近に感じられるようになります。
たとえば、「社員の人柄がよかった」「業務が想像以上に本格的だった」「参加後に早期選考へ案内された」など、実際に参加した人だからこそ分かるポイントがあります。
紹介や推薦でインターンに参加できる場合もあるため、チャンスを広げる意味でも周囲に声をかけてみましょう。

ゼミの先輩やサークルの仲間、アルバイト先の社員など、少し視野を広げるだけで、思わぬご縁につながることもあります。ちょっと聞いてみるだけでもOKなので、ぜひ積極的に行動してみてください。
【大学3年生の5月】5月から就活を始める27卒学生が意識すべきこと
大学3年生の5月は、就活に向けて少しずつ意識が芽生え始める時期です。
しかし、焦って手当たり次第に動き出すのではなく、今の自分にとって何が必要なのかを見極めながら、バランスよく行動することが大切です。
ここでは、5月から就活を始める27卒の学生が、特に意識しておきたいポイントを3つに分けて解説します。
就活に時間を使いすぎない
5月の段階では、エントリーを開始しているサマーインターンの数も限られており、公開されている企業情報もまだまだ少ないのが実情です。
そのため、就活に時間をかけすぎても「やったことに対して成果が出ない」と感じやすく、モチベーションが下がってしまうこともあります。
この時期は、就活一本に集中しすぎるのではなく、学業やアルバイト、サークル活動などとバランスよく時間を使うことが大切です。
特に大学生活での経験は、自己PRやガクチカのネタにもつながるため、無理に就活だけに集中する必要はありません。
「情報収集の習慣をつける」くらいの感覚で、無理なく始めていくことがポイントです。
サマーインターンが全てではない
「サマーインターンに参加しないと、いい企業に行けないのでは?」と不安に感じる方も多いかもしれません。
しかし、サマーインターンが就活のすべてではありません。
実際、サマーインターンに参加できなかったとしても、大手企業を含め秋以降にも多数のインターンが開催されます。
また、企業によっては冬や春のインターンを本選考につなげるケースもあります。
サマーインターンは、企業を知ったり、就活の雰囲気に慣れるための第一歩。
落ちてしまっても、その経験は次に必ず活きてきます。
今は一つひとつの経験を積み重ねていくことが大切です。
「インターンに参加すること」ではなく、「自分に合った企業を見つけること」が最終目標であることを忘れず、広い視野で取り組んでいきましょう。
早期に内定を獲得しても入社は大学卒業後の4月
最近では、早期選考や早期内定といった言葉をよく耳にするようになりました。
確かに、早く内定を得ることで安心感は得られますが、内定を早く取ったからといって、早く社会人になれるわけではありません。
どれだけ早く内定をもらっても、入社は基本的に大学卒業後の翌年4月。
つまり、周囲より少し早くゴールに近づいたように感じるかもしれませんが、最終的なスタート地点はみな同じです。
そのため、「早く内定を取らなければ」と焦るのではなく、自分が納得のいく企業と出会うことを大切にしてほしいと思います。
就活はマイペースで進めて良いものです。
5月の時点では、情報収集や自己分析を通じて、自分自身をよく知るところからスタートするのがちょうどよいタイミングです。

就活のスタートダッシュに不安を感じる方も多いですが、5月時点では「焦らず土台をつくる」意識が何より大切です。
サマーインターンも、あくまで経験の一つ。最終的な目標は、自分に合った企業と出会うことだということを、忘れずにいてください。
今できる小さな準備の積み重ねが、未来の自信に変わります。自分のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。
5月の就活に関するよくある質問
5月から就活を始めた場合でも、大手企業から内定をもらうことは可能です。
ただし、大手企業の選考は3月から始まり、5月を迎える頃にはエントリー自体が締め切られている場合も多いです。
スケジュール的に一部の企業は手遅れになってしまうため、大手を目指したい場合は、5月からでもエントリーできる大手企業を見つけると良いでしょう。
また、タイミングが良ければ、採用枠が空いたことによって二次募集がかかるケースもあります。
一般的には、10月までに内定を得られなければ、かなり状況は厳しくなります。
5月の時点で内定ゼロでも、春採用も含めれば夏採用・秋採用とまだチャンスはいくつか残されていますが、10月まで来ると残るチャンスは冬採用のみです。
企業によっては卒業ギリギリのタイミングまで採用活動を行っている場合もありますが、時期が遅くなるほど、募集人数が少なくなることで倍率も上がっていきます。
そのため、5月から就活を始める場合・5月の時点で内定ゼロの場合は、遅くとも10月までをめどに行動を起こす必要があります。
まとめ
4年生の5月は、多くの企業で選考が本格化するタイミングです。
そのため、面接などの予定が入りやすく、しっかりとスケジュール管理を行いながら動く必要があります。
選考と対策の同時並行が必要になるため、効率的かつ計画的な動きが必要不可欠です。
また、5月から就活を始める場合は一般的なペースと比べて遅れているため、より一層効率的な対策が重要といえます。
必要に応じて就活エージェントなどの支援サービスを活用しながら、対策を強化し、遅れを取り戻しましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート









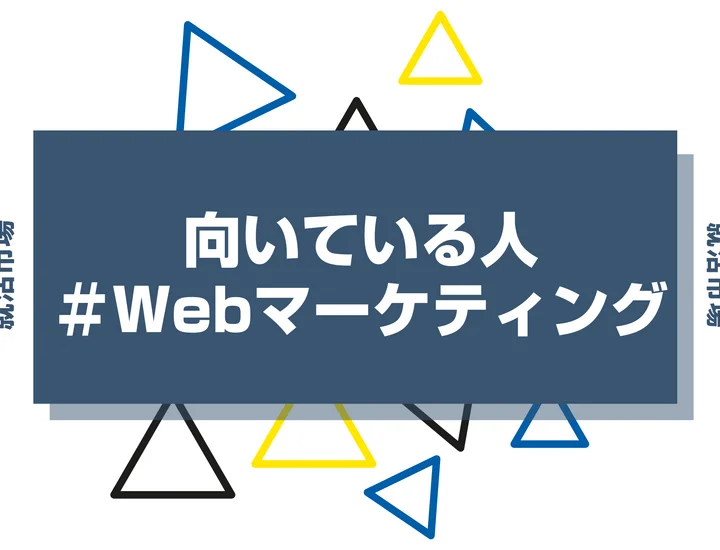








柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
「もう遅い」と思い込むのではなく、「今からでもまだ間に合う」という前向きな気持ちで取り組めば、必ず道は開けてきます。大切なのは、今日から本気で動き出すことです。