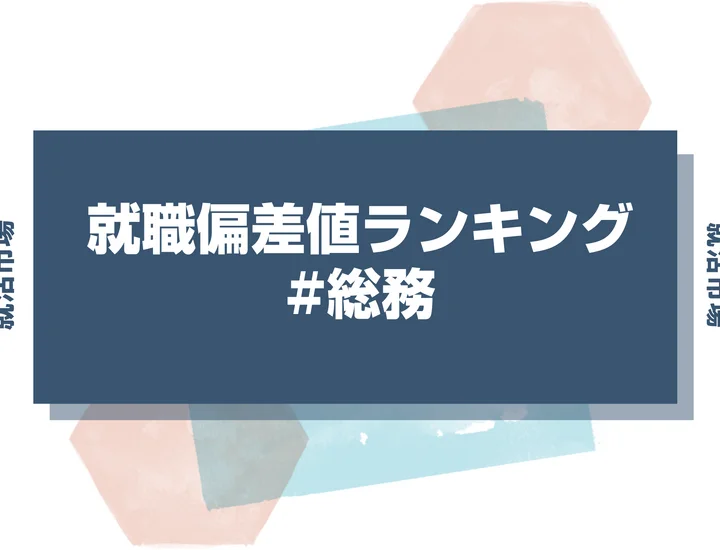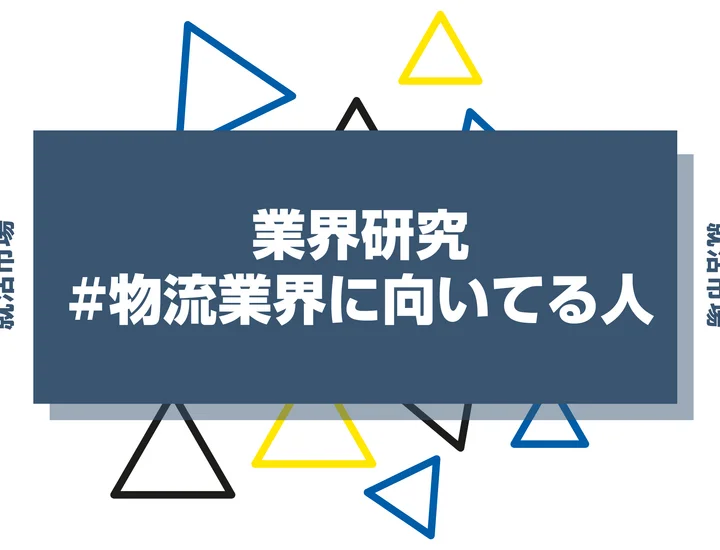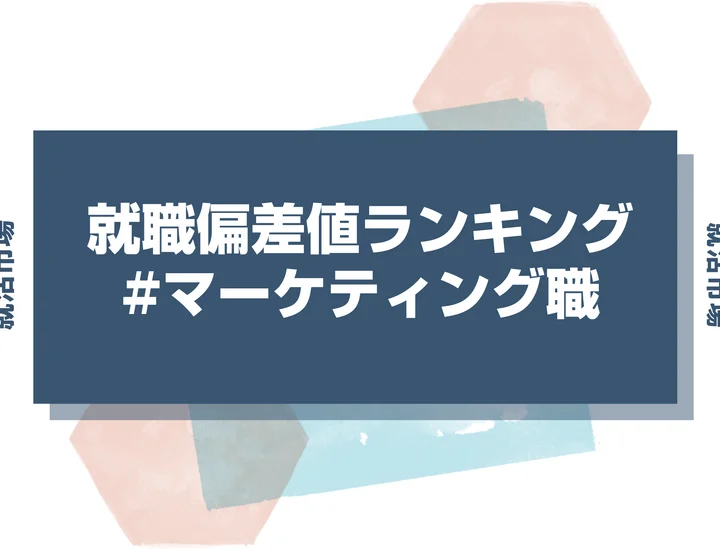いろんな仕事がある中で、コンサルタントとして働いてみたい方は少なくないと思います。
知的な専門職というイメージがあり、これからの不確かな時代を生きていく上で魅力的な職業として見られるようになり、最近注目されるようになっています。
学生の就職先ランキングでも上位にコンサルティング会社が見られるようになっていますし、転職先としてコンサルタント業に携わることを希望する人も年々増加しています。
人気が高まっているコンサルタントですが、どのような人が向いているのか紹介していきます。
【コンサルに向いている人】コンサルタントとは
英語の「consult」が語源で、相談する・助言を求める意味を持ち、専門知識を持ち顧客の支援を行います。
コンサルタントとは、どんな仕事なのでしょうか。
一言で言いますと、顧客の課題を明らかにし、改善の実現をサポートする仕事です。
通常、コンサルタント業務は、企業や自治体向けに、一定のテーマについて有償で実施するものを指します。
企業も自治体も、自らの活動内容について絶対の自信を持っているわけではなく、常に改善を模索しています。
また、新しい制度や時代の要請に対応するために進むべき方向性や体制改革などについてのアドバイスを求めています。
そうした顧客ニーズに応える仕事がコンサルタントの仕事です。
コンサルティングの目的
コンサルティングの目的は、クライアントが抱える問題の解決と企業価値の向上です。
担当する業界のプロとして経験や知識を活かし、クライアントの成長に貢献します。
たとえば、集客に苦戦している場合、集客率をアップさせるための方法をアドバイスします。
SNSの活用やWeb広告など、クライアントの事業戦略やターゲット層に合わせて、アドバイス内容を変化させることが重要です。
ほかにも、コンサルティングを通じて、財務状況や組織体制などの支援も実施します。
コンサルティングは、ノウハウがない企業に対して、さまざまな角度からサポートするため、幅広い知識と経験が必要です。
そのため、クライアントが属する業界や社会情勢など、日々勉強することが求められます。
【コンサルに向いている人】コンサルタントの仕事内容
コンサルタントの仕事内容は、大きく以下の2つに分けられます。
- 現状分析と今後の課題の抽出
- 課題の解決方策の提示、改善に向けたサポート
コンサルタントは、現状分析から改善に向けたサポートまで、幅広く対応します。
そのため、さまざまな知識と経験が必要です。
また、クライアントごとに課題は異なるため、クライアントにあった改善方法を企画・提案します。
以降の文章では、それぞれの仕事内容について詳しく解説します。
コンサルタントの基本業務になるため、きちんと理解しておきましょう。
まず一つ目は、調査を通じた現状分析と今後の課題の抽出です。
顧客の現状と問題点を明らかにするために、まず顧客の実態調査を行います。
顧客が企業であれば、事業現場の状況、商品やサービスの内容、業績・財務内容、人事や組織体制などを調査します。
いわば、人・物・金といった企業の基本要素を調査し、同業他社や業界動向も踏まえながら調査します。
顧客が市町村や地方公共団体の場合も、基本的には同様の調査手法をとります。
市民アンケートや関係者ヒアリング、あるいは海外先進事例調査などといった手法も取り混ぜながら、予算具合に応じて各種調査を進めていくことになります。
調査については、データの客観性を重視します。
すなわち、ある事象の時系列で見たデータ推移や、構成比の変化など実態把握に必要なデータを的確に収集・分析することが必要になります。
以上の各種調査を通じて、現状がどういう状態か、このままでいくとどうなるか、将来どんなことが問題となるかなどを明らかにしていきます。
そして2つ目は、課題の解決方策の提示、改善に向けたサポートです。
調査の結果導き出された現状の問題点を踏まえ、課題解決の方策を示すと同時に、その実施に向けたサポートを行うことになります。
課題解決方策は、項目ごとに、時系列で示されるのが一般的です。
ここで求められるのは、納得感と実効性のある課題解決方法の提示となります。
顧客は、問題を明らかにするだけではなく、その解決による改善の実現を求めています。
そのため、顧客に問題点を理解してもらった上で、できるだけ明確にポイントを絞って、具体的な解決方法を提示することが求められます。
大きな調査になりますと、上記2つの調査内容を社内の他部署や別の専門会社を用いて分業することも珍しくありません。
例えばアンケートを専門に手掛ける調査会社も存在します。
調査・分析を経て明らかになった課題に対して、コンサルタントはその解決に向けた方策をクライアントに提示します。
ここで重視されるのは、業界全体の構造的な知見と、特定分野における専門性を組み合わせた実効性のある提案です。
業界の流れや将来の動向を理解した上で、クライアント特有の事情に配慮した内容を構築することが、成果につながるカギとなります。
【コンサルに向いている人】コンサルタントの分類
コンサルタントに向いている人の特徴をチェックする際は、あわせて、コンサルタントの分類も理解しておきましょう。
一口にコンサルタントと言っても、その種類はさまざまであり、専門分野や活躍の場は異なります。
主な分類は以下の通りです。
- 戦略コンサルタント
- 総合系コンサルタント
- 人事・組織コンサルタント
- ITコンサルタント
- リスク管理コンサルタント
コンサルタントを目指す際は、自分の強みも考慮したうえでキャリアプランを立て、具体的にどのようなコンサルタントになりたいのかをイメージしましょう。
では、以下から分類を一つずつ解説していきます。
戦略コンサルタント
戦略コンサルタントはコンサルティング業界の中でも最も知名度が高く、企業の経営戦略を支援することを主な業務としています。
企業の事業方針や経営改善に対して全体的な視点から指導やアドバイスを提供し、特に経営層や上級管理職に向けて提案を行います。
戦略コンサルタントの業務はデータ分析や市場調査を基に、企業が持続的な競争優位を確立できるような戦略を立案することに焦点を置いています。
例えば、競争環境の分析を通じて、新規事業の立ち上げ方針や市場参入戦略を提示したり、コスト削減のための効率化プランを提供することなどが代表的です。
戦略コンサルタントには論理的思考力が特に求められ、複雑な課題を整理し、クライアントにとって最適な解決策を提案する能力が重視されます。
したがって、分析力と共に、経営者視点での判断力も必要とされ、ビジネスの最前線で活躍するためのスキルと知識が要求される職種です。
総合系コンサルタント
総合系コンサルタントは企業の経営改革や業務プロセスの改善、IT導入支援など、幅広い分野においてクライアントの課題解決をサポートする役割を担っています。
戦略コンサルタントとは異なり、戦略の立案からその実行支援まで幅広く対応することが特徴です。
例えば、業務効率化のためのプロセス改善や、ITシステムの導入支援、財務戦略の見直し、人事制度の改革など、クライアントの多岐にわたるニーズに応えることが仕事です。
クライアントの現場に密着して支援を行うことが多く、実際の業務に深く関わりながら変革を推進する姿勢が求められます。
総合系コンサルタントには幅広い分野の知識や、複数の専門分野を統合して課題を解決するスキルが必要とされます。
また、常に新しい知識を学び続ける姿勢や、好奇心旺盛で柔軟な対応力も重要です。
クライアントとの信頼関係を築き、長期的な視点で支援することが、総合系コンサルタントの大きな役割となります。
人事・組織コンサルタント
次は人事・組織コンサルタントです。
社員が最適な環境で能力を発揮するための処遇制度の構築や、企業が持つ人的資源の最適な配置を行います。
人事制度に関する法律的な知識も求められますので、このジャンルのコンサルタントとしては、社会保険労務士の資格を持つ人がよく活躍しています。
それから、財務・税務コンサルタントです。
これは、会社の資金運営、税務対策に関するコンサルタントですが、税金関係の専門知識が不可欠なことから、税理士の有資格者がこのコンサルタントを担っているケースが数多くあります。
以上は従来からあるスタンダードはコンサルタントです。
このほかにも、時代の要請に合わせて活躍している主なコンサルタントを以下に紹介します。
ITコンサルタント
まずはITコンサルタントです。
これは、進展する情報化社会に適合するために求められているコンサルタントです。
具体的には、経理関係の勘定処理システム化、社内外の情報ネットワークの構築などに関するコンサルタントです。
このコンサルタント業務に引き続いて、本格的なシステム構築プロジェクトへつなげるケースも多いです。
そのため、コンサルタント業務と、それに引き続くシステム導入業務を複数の系列会社などが連携して継続実施することがよくあります。
SAPコンサルタントやPMOコンサルタントも含まれます。
リスク管理コンサルタント
最近増えているのがリスク管理コンサルタントです。
近年、自然災害による被害が増加していますが、自然災害に限らず、企業のリスク管理の在り方について、課題抽出と解決方策を提示するコンサルタントです。
地震・火災といった災害リスクから、社員の健康管理上のリスク、情報漏洩リスク、そのほかのさまざまなリスクに備えるためのコンサルタントです。
このコンサルタント業務では、業務終了後、実際の保険契約につなげるケースが多く見られます。
そのため、保険関係の企業グループが協働して手掛けているケースがよくあります。
シンクタンクコンサルタント
シンクタンクコンサルタントは、政策提言や戦略立案、社会課題の調査・分析を通じて、政府機関や自治体、企業、非営利団体などに対して専門的な知見を提供する職種です。
学術的な知識と現場感覚のバランスを取りながら、公共政策や産業戦略の策定を支援することが主な役割となります。
シンクタンクと呼ばれる機関には、経済や福祉、環境、地域開発など特定の領域に特化したものも多く、それぞれの分野で高度な知識や分析スキルが求められます。
例えば、人口減少地域の活性化策を考える場合、地域経済の構造把握、住民ニーズの調査、行政制度の理解など、幅広い視点からのアプローチが必要となります。
このような業務に携わるためには、客観的なデータに基づいた分析力が不可欠です。
数値的根拠をもとに仮説を立て、論理的に検証し、クライアントが意思決定を行うための材料を提示することが求められます。
時には政府の政策決定に影響を与えるような提言を行うこともあり、社会的な影響力の大きな仕事といえるでしょう。
事業再生コンサルタント
事業再生コンサルタントは、経営が悪化した企業の再建を支援するプロフェッショナルです。
業績不振の原因を見極め、資金繰りの改善、コスト構造の見直し、事業の選択と集中など、再生に向けた具体的な計画を策定し、実行までをサポートします。
単なるアドバイザーにとどまらず、再建プロジェクトの中核を担う存在です。
クライアントとなる企業は、業界の変化や経営判断の失敗、人材不足などさまざまな要因で困難な状況に陥っています。
そのため、コンサルタントは幅広い視野と知識を活かして、財務分析、人材マネジメント、マーケティング戦略など多岐にわたる分野からアプローチする必要があります。
たとえば、収益が減少している企業に対しては、販売チャネルの再構築や、コストの見直し、新規事業の立ち上げ支援などが求められます。
以上、コンサルタントのジャンル分けについて見てきました。
このほかにも、顧客の要望の種類に応じて、特化したマイナーなものまで含めると、実に多様なジャンルが存在しています。
コンサルタントの活躍の場は、顧客が抱える問題の数だけ存在するといってもいいでしょう。
【コンサルに向いている人】コンサルタントに向いている人の特徴11選
それでは、コンサルタントに向いている人の特徴を具体的に見ていきます。
多くの職業同様、仕事に対して真面目に真摯に取り組むのは当然としても、コンサルタントならではの素養や必要とされる資質は確かにあります。
ここでは、向いてる人の特徴11点を紹介します。
- 好奇心旺盛な人
- 体力がある
- 論理的思考力がある
- 言語化できる
- コミュニケーション能力がある
- 向上心が高い
- 勉強が好き
- 臨機応変に対応できる
- 結果にこだわる
- 推進力が高い
- 傾聴力が高い
1.好奇心旺盛な人
好奇心旺盛な性格も、重要な要素の1つです。
コンサルタントの仕事は多岐にわたる業界や企業の課題に取り組むものであり、常に新しい情報や知識を吸収する必要があるからです。
クライアントごとに異なる業界やビジネスモデルに適応しなければならないため、未知の分野にも積極的に興味を持ち、深く学ぶ姿勢が求められます。
好奇心旺盛な人は新しい知識を楽しみながら学ぶことができるため、幅広い視点で問題を捉え、最適な解決策を見つけ出す力を備えています。
また、現場ではクライアントごとに異なる複雑な課題に柔軟に対応する必要があります。
新しい挑戦に対して前向きに取り組み、常に「もっと知りたい」「より良い解決策を見つけたい」という探究心を持つ人こそ、次々と現れる課題に対して迅速に適応し、質の高いサポートができるでしょう。
2.体力がある
まず、基本的はことですが、体力が必要です。
コンサルタントというと、インテリのイメージがあるかもしれませんが、綿密な調査の実施と分析、顧客との膝を付け合わせての協議、明確で説得力のある解決方策の提示とその実現に向けたサポート実施といった、実にハードな業務です。
請け負っている業務の数や勤務環境にもよりますが、時には夜遅くまで調査分析や課題検討に時間を割くことも珍しくはありません。
こうした難関を通過していくためには、それ相応の体力とタフさが必要になります。
コンサルタントを行う顧客先にもよりますが、大きな現場をいくつも抱えているメーカーの実地調査や、膨大で複雑な実務データを抱えている事業者の分析作業は物理的にもハードです。
単にオフィスでパソコン相手にレポートをまとめられれば良いという楽なものではありません。
コンサルタントには、実態調査をやり切る体力が、まず持って必要不可欠です。
さらに、関係者との打ち合わせも時間と体力を必要とします。
コンサルタント業務は顧客と緊密な連携を必要とします。
都度、顧客先へ出向いて、打ち合わせを重ねることが求められますので、そういった面でも、フットワークの軽さ、基本的体力の有無が問われます。
3.論理的思考能力がある
コンサルタントの調査において求められることは、検証可能な客観性のある結果です。
単なる印象や推測では顧客を納得させることはできません。
各種の実態調査を踏まえ、なぜそういう結論が導き出されるのか、明解に示せなければなりません。
そのためには、論理的思考が不可欠となります。
コンサルタント業務においては、筋道の通った理論展開ができる能力が求められます。
それがなければ、適切な解決策を示すこともできず、顧客に満足のいく成果を約束できません。
論理的思考の巧拙が、コンサルタントの成否を決めるといっても過言ではありません。
それぐらい重要な素養といえます。
4.言語化できる
コンサルタントの仕事は、顧客の抱えている課題に対しての解決方法を提案し、実現に向けてのサポートを行うことです。
課題解決に向けての方策を顧客に正しく伝えたうえで、それに対して十分な納得を得られなければ、実現に向けてのサポートが効率良くできなくなってしまいます。
どんなに良い解決方法を導き出せたとしても、自分の考えをわかりやすく言語化し、正しく顧客に説明する力がないと、コンサルタントの仕事はうまくいかないのです。
5.コミュニケーション能力がある
コンサルタントの相手は、個人事業者であれ、企業であれ、結局のところ最後は人次第となります。
個人の事業者についてはもちろんですが、企業であれば、コンサルタントを依頼してきた部署の担当の方々や、その上司、さらには経営層にコンサルタント内容について、納得してもらわなければなりません。
そのためには、適切なコミュニケーション能力が必要となります。
独りよがりの押し付けや、説得力のないプレゼンテーションをしていても、顧客の信頼は得られず、納得してもらえません。
6.向上心が高い
コンサルタントに向いている人は、向上心が高く、自分自身を積極的に成長させたいという意思が強い人です。
そのような成長に対して貪欲な姿勢を持っていれば、新しい課題や環境に対してもすぐに適応でき、柔軟に対応していけるでしょう。
そのような適応と柔軟な行動が本人の対応力を高めたり知見を深めたりするため、向上心が高い人は、スピーディーに成長できるといえます。
コンサルタントは、クライアントによってさまざまなケースの課題に向き合わなければならず、新しい考え方や視点を求められる場面も少なくありません。
クライアントの課題を解決に導くプロフェッショナルとしての責任を担っています。
そのため、自らの知識やスキルを常に高め続ける姿勢が欠かせません。
特に、AI・データサイエンス・サステナビリティ・DX(デジタルトランスフォーメーション)といった分野は、今後ますます多くのクライアント企業にとって重要なテーマとなっていくでしょう。
7.勉強が好き
コンサルタントに向いている人は、勉強が好きな人、新しい知識を取り入れることに貪欲な人です。
さまざまな情報や知識に興味を示したうえで、素早く吸収できれば、課題の分析や戦略の策定に大きく役立つでしょう。
コンサルティング業務では、業界の動向やビジネストレンドを積極的に把握する必要があり、その知見が深いほど活躍のポテンシャルは高いといえます。
反対に勉強が嫌いな人や、新しい知識を取り入れるうえで偏見や先入観などがいつも邪魔してしまう人などは、スムーズにコンサルティング業務に取り組めない可能性があります。
コンサルティング業務ではまさにインプットとアウトプットの繰り返しであるため、勉強好きな人ほど早いスピードで成長し、成果につなげていけると考えられます。
8.臨機応変に対応できる
コンサルタントは臨機応変に対応できる人が適しています。
クライアントの課題や市場の状況が常に変化するからです。
たとえば、過去に通用した解決策であっても、時代の変化によって最適解ではなくなる可能性があります。
そのため、コンサルトには柔軟な思考と臨機応変な対応力が必要不可欠です。
ほかにも、状況の変化を瞬時に察知し、迅速に戦略を変更できる能力も求められます。
1つの方法に強いこだわりを持ってしまうと、クライアントの成果につながらないかもしれません。
仕事にプライドを持つことは大切ですが、柔軟に変化させることも重要です。
臨機応変に対応することに自信がない就活生は、普段の生活から多様な視点を持つように意識してください。
9.結果にこだわる
コンサルタントに向いている人は、結果にこだわり、クライアントに対してしっかりと成果を提供できる人です。
コンサルティング業務は、クライアントに対して課題解決などの成果を提供できなければ信頼獲得につながらず、成果や実績こそがものを言う業界です。
そのため、会社自体も成果主義の考え方が浸透しているケースが多いといえます。
結果にこだわる人は、どのような状況でも目標達成に向けてひたむきに努力できるため、そのような粘り強さや諦めない精神が実際に成果につながっているのでしょう。
そもそもコンサルは、企業の課題解決という重要な役割を担うため、大きな責任が伴います。
結果にこだわる強い意思を持っていなければ、そのような責任重大な仕事は受けられないでしょう。
10.推進力が高い
推進力とは目標に向かって自ら行動を起こし、周囲を巻き込みながら物事を前に進める力を指します。
コンサルティングの現場では、クライアントの合意形成が遅れる場面や社内調整が停滞する場面が頻繁に発生します。
その際に重要なのは単に指示を待つのではなく、課題を細分化して短期的な成果を積み上げることで信頼を築く能力です。
具体的にはタスクの優先順位を明確にし、関係者に対して定期的な進捗報告と次アクションを提示することでプロジェクトを前に進めます。
また、困難な局面でも代替案を複数示しつつ実行へ移す姿勢が評価されます。
このような場面で率先して動き、他者を巻き込める力があると、短期的な成果と長期的な信頼を同時に得られます。
11.傾聴力が高い
傾聴力はクライアントやチームの話を丁寧に聞き、ニーズや課題を正確に理解する力を指します。
コンサルタントは表面的な要望だけでなく、背景にある真の課題を読み解く必要があるため、注意深く整理して問い直す技術が求められます。
具体的には相手の発言を要約して確認したり、矛盾点や前提を丁寧に掘り下げることで、本質的な問題を明確化します。
また、傾聴は単なる聞き役ではなく、得た情報を基に仮説を立て、最適な提案につなげるための出発点となります。
プロジェクト成功のためには関係者の利害や感情も踏まえた調整が必要であり、その際に相手の言葉に寄り添える能力が信頼を構築します。
その意味で相手の意図を正確に汲み取り、適切な提案に結びつけられる力がある人はコンサルタントに非常に向いています。
【コンサルに向いている人】コンサルタントに向いていない人の特徴9選
次に、コンサルタントに向いていない人の特徴について見てみましょう。
以下のような特徴がある人の場合、残念ながらコンサルタントを目指すことには、ハンデがあると言わざるを得ません。
明らかに当てはまる場合は、その特徴を改善するように努力するか、それがどうしても無理ならば、コンサルタントを目指さず、より適切な仕事を考えたほうが賢明かもしれませんので、参考にしてください。
- ストレスに弱い人
- 頭を使うのが苦手
- 人と話すのが苦手
- 安定を求める
- 自己中心的
- 臨機応変な対応が苦手
- 思考がネガティブ
- ルーティーンワークが好きな人
- 変化への耐性が弱い
1.ストレスに弱い人
ストレスに弱い人は、コンサルには向いていません。コンサルは依頼ごとに期間が定まっている職種です。
期間内に仕事を終えるために、1日の業務量が多くなる時期があるでしょう。常に忙しいとは限りませんが、激務がストレスに感じる人にはつらい仕事です。
さらに、コンサルはお客様と直接やり取りします。お客様次第では、急な仕事が舞い込んだり、前提が覆ったりするでしょう。
他にも、成果が求められる仕事でもあるため、大きなプレッシャーがかかります。
1つひとつは小さなストレスでも積み重なることで、大きなストレスに変化するでしょう。
コンサルは、ストレス耐性がない人には向かない職種です。
2.頭を使うのが苦手
課題を抽出し、解決策を考え出すには、現状分析力と、課題解決能力、すなわちソリューション能力を発揮することが必要となります。
顧客のために、調査結果をにらみながら、あれこれと頭を使って、問題の本質と課題解決策を考えることこそ、コンサルタントの役割です。
そもそも業務本来の性質そのものからいって、コンサルタントは頭を使うことを大いに求められますが、それが苦手ということになりますと、コンサルタントであることは難しいということになります。
頭の使いどころこそが、コンサルタントの売りの部分であり、価値といえます。
逆の言い方をすれば、頭を使うことが好きならば、コンサルタントに向いているともいえます。
3.人と話すのが苦手
コンサルタントは、パソコンに向かってデータ分析やレポート作成だけをしていれば務まるものではありません。
コンサルタント業務の中でも特に重要なことは、顧客との信頼関係構築です。
そしてそれには、コミュニケーション能力が必要となります。
調査の進め方や、中途報告については、逐次顧客の理解を得ながら丁寧に進めていくことが必要です。
ネット社会が進んでメールでのやり取りが増えてはいますが、やはり重要なことは、顔を突き合わせて、じっくり話し合わなければなりません。
人と話すのが苦手というのは、その重要なコミュニケーションを取る上での障害となってしまいます。
加えて、コンサルタント業務は、テーマにもよりますが、調査の過程で人と接することが少なくありません。
良い調査を行う上でも他者とのコミュニケーション能力は重要です。
4.安定を求める
常に安定的な環境や働き方を求める人には、コンサルタントは向いていない可能性があります。
なぜならコンサルタントは、仕事の性質上、プロジェクトの内容や進行状況が大きく変動するからです。
毎日同じ業務に黙々と取り組めるわけではなく、イレギュラー対応も多いため、柔軟な対応力を求められるケースも少なくありません。
そのため、安定志向の人は、コンサルティング業務では大きなストレスを抱えてしまう恐れがあります。
コンサルタントとして円滑に業務に取り組むには、変化を恐れず、新しい提案やアプローチを積極的に試みる姿勢が重要になります。
自分自身がコンサル業界に適応できるか不安な場合は、変化に対して抵抗しないか、新しいチャレンジを前向きに受け入れられるかを考えてみましょう。
5.自己中心的
コンサルタントに向いていない人は、自己中心的な考え方が目立つ人です。
コンサル業務はチーム単位で動くケースが多く、常に周りの動きを考慮しながら、プロジェクトの進行状況をチェックしていく必要があるからです。
周りにいる人との協力が苦手であり、個人主義的なアプローチで仕事に集中してしまう人は、コンサルタントとしてチームを組んだ場合トラブルになる恐れがあります。
また、コンサルタントは当然、クライアントの動きに対しても柔軟に対応する必要があります。
自己中心的な人は、自分のやり方や考えを相手に押し付けがちなので、クライアントの状況に応じて動くことにはストレスを覚えるかもしれません。
そのため、自己中心的なふるまいを周りから注意された経験がある人などは、コンサルタントとしてチームメンバーと積極的に協力できるかどうかを十分にチェックしてみましょう。
6.臨機応変な対応が苦手
コンサルタントの仕事には、常に変化への対応が求められます。
その理由の一つは、プロジェクトのスケジュールや進行内容が事前の想定どおりに進むとは限らないからです。
クライアントの意向や状況が変わることもあれば、外部環境の変化によって計画を修正せざるを得ないこともあります。
そのような場面では、柔軟な思考と臨機応変な対応力が必要不可欠です。
たとえば、急に打ち合わせが入ったり、納品内容の修正が求められたりといった突発的な対応が日常的に発生します。
こうした場面に対して計画が崩れてしまったり、予想外に対応できないと戸惑ってしまうタイプの方には、コンサルの仕事はストレスが大きく感じられるかもしれません。
一方で、柔軟に対応できる方は何が起きてもチャンスに変えられると前向きに考えることができ、どんな状況でも冷静に対処することが可能です。
このような思考ができる方は、クライアントからの信頼も得やすく、プロジェクトの中で重要な役割を果たすことができます。
もしご自身が突発的な変更に弱いため予定が崩れると混乱してしまうと感じる場合は、日頃から柔軟な思考を意識してみると良いでしょう。
7.思考がネガティブ
コンサルタントの仕事は、複雑で前例のない課題を扱うことが多く、一筋縄ではいかないケースも少なくありません。
ときには困難な局面や壁にぶつかることもあります。
そうしたときに、自分には無理かもしれない失敗したらどうしようといったネガティブな思考に陥りやすい方は、気持ちの持ちようによってはモチベーションを保ちづらくなることがあります。
コンサルタントは、常に前向きな姿勢で解決策を模索し、クライアントの信頼を勝ち取っていく仕事です。
思考がネガティブだと、その前向きな姿勢や自信が伝わらず、説得力や影響力にも影を落としてしまう恐れがあります。
実際、チームで仕事をすることが多いため、周囲への影響も無視できません。
コンサルタントに必要なのは、どんな困難にもきっと乗り越えられると信じて取り組む姿勢です。
完璧である必要はありませんが、困難に直面してもあきらめず、ポジティブな視点を持ち直す力があれば、着実に成長していけます。
8.ルーティンワークが好きな人
コンサルタントの仕事は、決められた手順に従って同じ業務を繰り返すようなルーティンワークとは対照的です。
プロジェクトごとに扱うテーマや課題が異なり、常に新しい情報を調査・分析しながら提案内容を変化させる必要があります。
そのため、同じ作業を安定的にこなすよりも、変化を楽しみながら新しい方法を試す姿勢が求められます。
また、仮説を立てて検証を重ねるプロセスが多いため、失敗を恐れず挑戦できる人でないと継続が難しい仕事です。
このように日々異なる課題に柔軟に対応する環境を楽しめない人は、コンサルタントとして成果を出すのが難しい傾向にあります。
9.変化への耐性が弱い
コンサルティング業界では、クライアントの要望や市場環境が短期間で変わることが日常です。
したがって、変化への耐性が弱く柔軟に対応できない人は、業務のスピード感についていくことが難しくなります。
特にプロジェクトの進行中には、仮説の修正や資料の方向転換などが頻繁に発生し、それに前向きに対応する姿勢が必要です。
また、複数の案件を同時に進めるケースも多く、優先順位を適切に判断して行動する能力が求められます。
一方で、変化をストレスと捉える人は精神的な負担が大きくなりやすく、長期的なキャリア形成が難しくなる傾向にあります。
そのため環境の変化を受け入れ、柔軟に軌道修正できる力が欠けている場合、コンサルタントにはあまり向いていません。
【コンサルに向いている人】コンサルタントに必要なスキル・能力
ここまで、コンサルタントのジャンルを大まかに説明してきましたが、ここではさらにコンサルタントの仕事をするうえで必要となるスキルや、能力にどのようなものがあるか見てみましょう。
ここであげるスキルや能力に自信のある人は、採用選考の際は積極的にアピールすると良いでしょう。
自己分析によって、その能力やスキルが自分の強みであることが裏付けられる具体的なエピソードを見つけておくと、志望動機や自己PRを考える際に役立ちます。
傾聴力
問題の解決方法を考えるためには、その問題の抱えている課題を見つけ出さなければなりません。
そして、顧客の課題を見つけ出すためには、顧客の悩みや意見を十分に聞き取ることが必要です。
そのため、コンサルタントには傾聴力が欠かせません。顧客の話す言葉へ丁寧に耳を傾けることで、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを発見できる場合もあります。
その結果として本当の課題を見つけ出し、押しつけではない顧客の望む形での解決方法の提案ができるのです。
視野の広さ
コンサルタントの仕事では、課題解決のために柔軟な発想力が求められます。
また、課題解決の方法を考える際には、その問題の抱える本質を明らかにしなければなりません。本質を見つけるためには、広い視点から問題を捉える必要があります。
問題点を明らかにしたり、解決方法を考えたりするときには、物事の一部分だけにこだわってしまうとうまくいきません。
コンサルタントは偏見をもたず、1つの考え方に固執せず、さまざまな角度から物事を見られる視野の広さが求められるのです。
問題分析力
問題の本質を見抜くための問題分析力がなければ、問題解決のための提案も見当違いのものになってしまいます。
丁寧な調査から物事を細分化し、構造を明らかにすることで、問題の原因が見えてきます。
解決すべき本当の問題がどこに潜んでいるのか、より内面的な分析ができる力は、コンサルタントの仕事にとっては欠かせない能力です。
常に物事を整理して構造化して考えられる人・原因と結果を正しく把握できる人は、問題分析力が備わっている人と言えるでしょう。
上昇志向
コンサルタントは、顧客の現状をより良くするためのサポートし、顧客の成長を促す仕事です。
そして顧客は、課題を解決し、成長することを望んでいます。つまり、顧客の成功が、コンサルタントとしての成功と言えるでしょう。
良い結果を出すためには、顧客の成長しようとする姿勢はもちろんですが、コンサルタント自身も成長しようとする姿勢が大切です。
自身も上昇志向をもって「顧客と共に成長しよう」という姿勢で臨めば、コンサルタントとしてより良い提案ができるのです。
ストレス耐性
どんな仕事にも、多かれ少なかれストレスの種はあるものですが、ことコンサルタントの仕事は、顧客の望む結果に導けるかどうかが自分の提案にかかってきます。
そのため責任が大きく、思うような結果が出ないときのストレスは、はかり知れないものがあるでしょう。
また、さまざまなタイプの顧客に合わせて対応しなければならないため、やりとりがうまく進まずストレスになる場合もあります。
ストレスを抱え込まずに、常に前向きに仕事に取り込めるストレス耐性は、コンサルタントの仕事には大切な能力です。
専門領域の深い知識
コンサルタントとして高い成果を出すためには、幅広い知識とスキルが必要ですが、特に重要なのが専門領域に対する深い理解です。
なぜなら、クライアントは自身の業界や組織が抱える課題について、現実的かつ具体的な解決策を求めており、それには業界特有の背景や商習慣、構造的な課題に対する理解が欠かせないからです。
仮に現時点で十分な知識がなかったとしても、学び続けようとする姿勢があれば、確実に力は身についていきます。
また、現場では情報量も膨大です。
プロジェクトを進めるうえで、大量の資料やデータから必要な情報を的確に選び、短時間で分析する力が求められます。
単に知識を持っているだけでなく、それを活かす判断力や情報精査力も、コンサルタントにとっては不可欠なスキルです。
専門知識があることで、クライアントからの信頼も得やすくなります。
この人に任せれば安心だと思ってもらえる存在になるには、知識と経験に裏打ちされたアドバイスが鍵を握ります。
【コンサルに向いている人】コンサルのやりがい
コンサルのやりがいは、以下の3つです。
- 難易度の高い仕事ができる
- 優秀な人材と共に仕事ができる
- 年収が高い
コンサルは激務である一方で、他の職種では経験できない業務や経験が多数存在します。上記の3点を重要視する就活生にとっては、非常に魅力を感じる職種です。以降の文章で詳しく解説しているので、コンサルに興味のある就活生は参考にしてください。
難易度の高い仕事ができる
コンサルのやりがい1つ目は、難易度の高い仕事ができることです。コンサルが相手するお客様は経営層になります。
一個人や一般のお客様ではないため、規模の大きい仕事になります。企業の経営戦略や経営課題の改善など重要な業務課題を任されるでしょう。
その結果、難易度の高い仕事に挑むことになります。「多額のお金が動く仕事がしたい」「企業の経営に携わる仕事がしたい」と考えている就活生にはぴったりです。
また難易度が高くなるほど、達成したときのやりがいも大きくなります。さらに、難易度の高い仕事に挑戦し続けることで、スキルも大幅に向上するでしょう。
重要度の高い仕事に就きながら、自分も成長できるコンサルは非常にやりがいがあります。
優秀な人材と共に仕事ができる
コンサルのやりがい2つ目は、優秀な人材と共に仕事ができることです。
コンサルは、誰でも入社できる業界ではありません。論理的思考力や豊富な知識、コミュニケーション能力とさまざまな要素が求められます。
高い壁を乗り越えた人が集まるコンサルは、優秀な人材が多く集まるでしょう。周りの優秀な社員と切磋琢磨することでさらに成長できます。
コンサルは「自分より優秀な人と働きたい」「競い合うライバルがほしい」と考えている就活生に向いているでしょう。
また、コンサル業界は自分の実力を試したい就活生も集まってくるため、よりレベルの高い選考を突破する必要があります。
その結果、同期に優秀な人が集まるため共に仕事ができるでしょう。
年収が高い
コンサルのやりがい3つ目は、年収が高いことです。コンサル業界の平均収入は1,429万円と言われています。
総合商社についで第2位の成績です。仕事のモチベーションに給与が関係する人には、コンサルが向いています。
成果が給与になってかえってくるためやりがいを感じるでしょう。
とくに若いうちからでもしっかり稼げるのが魅力です。ほとんどの企業は勤続年数が増えたり、役職に就いたりすることで給与が上がります。
しかし、コンサルは単価が高い業務のため、社員の給与も比例して高くなります。20代であっても400万円から600万円といった高水準の給与が狙えるでしょう。
【コンサルに向いている人】コンサルの厳しさ
コンサルの厳しさとして、以下の3つが挙げられます。
- 常に高いアウトプットが求められる
- 成果主義・競争の激しさ
- 長時間労働・納期プレッシャー
コンサルは、やりがいが大きい仕事である一方で、厳しいと感じる面もあります。
コンサルに就職したのち「思っていた職種と異なる」と後悔しないためにも、厳しさについて理解しておきましょう。
もし、自分の価値観と比較し、許容できる範囲であれば、コンサルに向いている可能性があります。
常に高いアウトプットが求められる
コンサルの厳しさの1つ目は、常に高いアウトプットが求められることです。
クライアントは、コンサルタントに相談すれば、抱えている課題が解決すると考えています。
また、コンサルタント=課題解決のプロと認識しているため、高いレベルの成果や提案を期待しています。
その結果、質の高い分析や提案資料を継続的に出し続けることにプレッシャーを感じるでしょう。
クライアントは1つひとつの成果物に対するチェックが厳しいため、細部までこだわらなければなりません。
プレッシャーがあることがモチベーションにある人であれば強みになります。
しかし、常に高品質な提案をネガティブに感じる人は、コンサルに合わない可能性があるので注意してください。
成果主義・競争の激しさ
コンサルの厳しさの2つ目は、成果主義・競争の激しさがあることです。
多くのコンサルティング会社では、成果によって評価が決まる文化があります。
たとえば、プロジェクトの成果やクライアントからの評価が昇進・給与に直結します。
自分が努力し、成果を出した分だけ待遇が良くなるため、働くモチベーションを得やすいです。
しかし、成果主義を採用していることで、社内ではコンサルタント同士の競争が常にあります。
同僚や先輩は頼もしい存在ですが、時としてライバルになることもあるでしょう。
競争関係を切磋琢磨できると捉えられる人は問題ありません。
一方で、競うこと自体に抵抗がある人は、コンサルの厳しさに直面するでしょう。
長時間労働・納期プレッシャー
コンサルの厳しさの3つ目は、長時間労働・納期プレッシャーです。
コンサルタントは、複数のプロジェクトを同時進行します。
それぞれの納期までに高品質なアウトプットが求められます。
そのため、タイミングによっては、長時間にわたる業務やタイトなスケジュールでの対応が必要です。
ワークライフバランスを就活の軸に置いている人にとっては、合わない価値観の可能性があります。
もちろん、常に長時間労働になるわけではありませんが、納期が近づくほど労働時間が長くなるでしょう。
労働時間が気になる人は、企業説明会や公式ホームページなどを確認し、業務実態を確認しておくことをおすすめします。
【コンサルに向いている人】最新版人気コンサル企業ランキング
東洋経済オンラインが2025年4月に発表したデータによると、就職人気ランキングのシンクタンク・調査・コンサルとして以下の企業がランクインしました。
- 大和総研
- アビームコンサルティング
- アクセンチュア
- 日本M&Aセンター
- 野村総合研究所
- 三菱総合研究所
- PwC Japanグループ
- デロイトトーマツコンサルティング
- 日本総合研究所
- KPMGコンサルティング
上記のランキングから現在、総合コンサルティング企業に人気が集まっていることがわかります。
ITや金融、経営などさまざまな分野に携われる点に魅力を感じていることが推察可能です。
ただし、人気が高い企業は就職難易度も高くなる傾向にあります。
きちんと自己分析した自己PRや業界・企業研究を重ねた志望動機などが重要です。
【コンサルに向いている人】コンサルタントの有名企業と特徴
コンサルタントに向いている人の特徴を調べる際は、コンサル業界の基礎知識として、コンサルタントの有名企業もチェックしておきましょう。
主な有名企業は、以下が挙げられます。
- ボストン コンサルティング グループ
- マッキンゼー・アンド・カンパニー
- アクセンチュア
- 大和証券
- 野村証券
いずれも代表的な外資系コンサル企業のため、関わったことはなくても、名前だけなら聞いたことがあるという人は多いでしょう。
特徴をよく理解したうえで、エントリーすべきかを検討してみてください。
なお、コンサルティング業界の就職偏差値については、以下の記事をチェックしておきましょう。
ボストン コンサルティング グループ
ボストン コンサルティング グループは、戦略コンサル企業の大手として、クライアント企業の成長戦略や市場進出をサポートしています。
これらのビジネス戦略において強みを持ち、実際に数多くの支援実績があることが特徴です。
コンサルティングを行う際は、イノベーションやデジタル化に関する取り組みを強化しており、経営層との密接な関わりを持ちながら一つひとつの仕事を進めていきます。
採用人数は30人であり、入社難易度は高いとされています。
あくまで参考の一つではありますが、就職偏差値のランキングにおいても、ボストン コンサルティング グループは上位にランクインしていることが特徴です。
就職にあたっては、外資系コンサルだからこそグローバルな視点を持つことや、柔軟な考え方で戦略策定につなげていけることなどが求められます。
マッキンゼー・アンド・カンパニー
マッキンゼー・アンド・カンパニーは、世界的に高い知名度を誇る戦略コンサルティングファームです。
特に企業の経営戦略や改革に強みを持っており、大規模な改革を支援し、企業の大幅な成長につなげてきた実績を持ちます。
マッキンゼー・アンド・カンパニー自体がトップクラスの外資系企業だからこそ、コンサルを行う際は、ほかの業界のトップクラスのクライアントを相手にするケースが多々あります。
そのため、背負う責任は重大であり、より大きな仕事を動かすことに対して責任感とやりがいを感じられることが重要なポイントです。
また、分析力や問題解決力が求められるのは言うまでもなく、入社難易度が高いからこそ総合力がより上であるに越したことはないでしょう。
傾向としてかなりの難関大学の学生を積極的に採用しており、採用人数は45人となっています。
アクセンチュア
アクセンチュアは、ITコンサルティングを中心に、テクノロジーやデジタル分野において協力な支援を提供している大手コンサル企業です。
戦略の立案からシステムインテグレーション、アウトソーシングまで幅広く支援サービスを展開しており、DXやクラウド技術、AIの分野に強いことが特徴です。
大手外資系企業として世界55か国に39万人もの優秀な社員を抱えており、日本法人だけでも5,000人以上の大所帯を誇るため、大規模なコンサルティングファームとしても有名です。
ほかの大手コンサル会社と同様に、難関大学からの採用が多いのは間違いありませんが、合計95大学893人と、裾野を広げた採用を行っています。
そのため、入社難易度は確かに高いとはいえ、トップクラスの難関大生でなければ受からないというわけではありません。
大和証券
大和証券は、日本の大手証券会社です。
主に株式や債券、投資信託など多岐にわたる金融商品を提供しています。
とくに個人投資家向けのサービスに強みがあります。
たとえば、お客様の投資スタイルによって、取引コースを選択することが可能です。
投資について相談しながら進める「ダイワ・コンサルティング」コースとインターネット上で進める「ダイワ・ダイレクト」コースなどです。
また、インターネットによるセミナーや店舗での講演会など、個人向けのサポートが充実しています。
ほかにも、グローバル展開もしており、海外市場でも一定のシェアを獲得しています。
また、海外拠点にはニューヨークやロンドン、シンガポール支店があり、今後のシェアが拡大していくでしょう。
野村証券
野村證券は、大和証券と並ぶ日本最大手の証券会社の1つです。
国内外で広範な投資銀行業務を展開し、企業のM&Aや資金調達支援を行う投資銀行業務に強みがあります。
とくに法人向けサービス(機関投資家向け)では、リーディングカンパニーとして、日本国内のみならず、アジアや米国など海外市場でも活躍しています。
アメリカでの大口取引では日本を超える割合です。
ほかにも、富裕層向けの新規顧客開拓に力を入れています。
今までにない価値創造を目的とし、多様なニーズに応える開発を実施しています。
また、富裕層向けを強化するにあたって、事務処理の電子化や人材確保に努めるつもりです。
今後も成長するために、環境はどんどん変化していくでしょう。
【コンサルに向いている人】コンサルの就活対策
コンサルに就職するために必要な対策は、以下の4つです。
- 自己分析
- 業界・企業研究
- 志望動機
- 面接対策
- OBOG訪問
コンサル業界は、就活生から人気の高い業界の1つです。そのため、事前準備は欠かせません。志望する業界で仕事するためにも、本章で解説する対策をしっかりとしておきましょう。
自己分析
まずは、自己分析しましょう。
コンサル業界を志望する理由や自分の性格を把握するために必要です。曖昧なままでは、自己PRや志望動機の作成に影響します。
就活を始めたらまず自己分析から開始しましょう。自己分析のやり方がわからない就活生は、専用ツールがおすすめです。
いくつかの質問に回答するだけでAIが、自分の性格や強みを教えてくれます。
効率よく就活対策したい就活生は、積極的に利用しましょう。
業界・企業研究
次は、業界・企業研究に取り組みます。業界・企業研究が不足すると不採用になる確率が高くなるでしょう。
採用担当者から「入社意欲が低い」と判断されるからです。そのため、業界・企業研究ノートをそれぞれ作成しましょう。
ノートにまとめることで情報が整理でき、見返すのが簡単になります。以下の記事でおすすめの業界・企業研究テンプレートを無料で配布しています。テンプレートをうまく活用して、就活にかかる時間を節約しましょう。
志望動機
コンサルタントを目指すうえで就活対策を強化するなら、志望動機をより明確なものにすることは欠かせないでしょう。
人気の高い業界だからこそ、志望動機は、企業の理念などを踏まえて具体的な内容を伝える必要があります。
どのような業界・企業にも当てはまるような内容では、熱意や積極的な関心が伝わりません。
対して、企業理念や事業内容などに触れていれば、事前にたくさんの企業研究を重ねていることがわかります。
企業理解度が高ければ、熱意・入社意欲は自然と伝わるため、説得力のあるアピールにつながります。
「なぜコンサル業界なのか」「なぜその企業でなければならないのか」を突き詰め、納得感のあるアピールを行いましょう。
なお、コンサル業界の志望動機の書き方については、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
面接対策
そして、面接対策も欠かせません。面接は、直接採用担当者に自分の入社意欲や強みをアピールできるチャンスです。
あらかじめ質問への回答を用意し、焦らずに答えられるように準備しておきましょう。とくに自己PRや志望動機、学生時代に力を入れたことの3つは頻出の質問です。質問される前提で回答を用意してください。
また、コンサルはケース面接も実施されます。ケース面接とは、課題が出され一定時間考えたのちに自分の考えを発表する面接です。
一般的な面接と異なり、慣れが必要になります。さらに、練習相手も必要になるため、就職エージェントの力を借りた対策がおすすめです。就活のプロがコンサル業界に入るために必要な知識を共有してくれるでしょう。
OBOG訪問
最後は、OBOG訪問も視野に入れておきましょう。OBOG訪問することで職場の雰囲気を肌で感じたり、社員の声を直接聞いたりできます。
公式ホームページや就活情報サイトからでは手に入らない情報のため貴重です。他にも入社意欲がアピールできる効果もあります。
ただし、相手は忙しい中で対応してくれるでしょう。
失礼のないように振る舞うことが大切です。集合時間より早めに到着したり、質問をあらかじめ用意したりして時間を無駄にしないように努めましょう。
OBOG訪問は人脈が必要です。部活の先輩や大学のキャリアセンターなどに事情を説明し、仲介役になってもらいましょう。
コンサルは選考スケジュールが早い!
コンサル業界の選考スケジュールは早いことが特徴です。大学3年生の夏から冬にかけて選考がスタートします。
大学4年生になる頃には、採用が終了しているため注意してください。コンサル業界への就職が不安な就活生は、ジョブコミットがおすすめです。
すべての就活サポートが無料で受けられます。さらに、エージェントが専属で就活をサポートしてくれるため、コンサル業界に特化した対策が可能です。就活のプロの力を借りて、効率よく就活対策してください。
よくあるQ&A
コンサル業界を目指すうえで、就活生の皆さんが気になるのが実際のところどうなの?という素朴な疑問ではないでしょうか。
ネットや説明会で得られる情報も多い一方で、断片的だったり、ケースによって答えが異なったりするものも少なくありません。
ここでは、コンサルティング業界を目指す就活生からよく寄せられる質問について、わかりやすくお答えしていきます。
企業研究や面接対策のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
コンサルティングファームとは、企業や行政、NPOなどのクライアントに対して、課題解決や意思決定を支援するコンサルティングサービスを提供する会社を指します。
ファームの種類は多岐にわたり、それぞれの特徴を理解することが、志望企業を選ぶ上でも非常に重要です。
代表的な分類としては、外資系と日系、戦略系総合系IT系FAS系(財務アドバイザリー)シンクタンク系などがあり、それぞれで業務領域や働き方も大きく異なります。
たとえば、戦略系は企業の中長期的な成長戦略の立案を得意とし、総合系は業務改善やIT導入支援などを幅広く手がけています。
自分の興味や得意分野がどのファームにマッチするのかを理解することが、志望動機を深める第一歩となるでしょう。
新卒でコンサルタントを目指すにあたって、特定の資格が必須というわけではありません。
ただし、資格があると知識の裏付けとして評価されやすくなる場合があります。
代表的な資格としては、MBA(経営学修士)や中小企業診断士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、ITストラテジストなどが挙げられます。
これらの資格を持っていなくても問題はありませんが、資格取得に向けて勉強していることをアピールするだけでも、学習意欲や専門性への関心が伝わります。
とくにIT系やFAS系のファームでは、専門的なスキルがあると早期に活躍しやすいため、将来的に資格取得を視野に入れるのもおすすめです。
コンサルタントの年収は、他業界と比べても比較的高水準にあります。
新卒で入社した場合、20代のうちから500万円前後の年収を得られることが一般的です。
さらに経験を積み、30〜40代でマネージャーやシニアマネージャーに昇進すると、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
さらに、役員クラスやパートナーに到達すれば、年収2,000〜3,000万円に達することもあります。
ただし、責任やプレッシャーも大きく、成果主義が徹底されている企業も多いため、自身のキャリアビジョンと照らし合わせながら判断することが大切です。
コンサルタントに対して、やめとけと言われることがあるのも事実です。
よく挙げられる理由としては、以下のようなものがあります。
- 最終的な意思決定はクライアントが行うため、提案が採用されないこともある
- 実働ではなく提案業務が中心のため、ビジネスの基礎スキルが身につきにくいと感じる人もいる
- プレッシャーや期待値が大きく、常に高い成果を求められる環境に疲れてしまう
こうした側面は確かに存在しますが、それと同時に、高い成長機会とキャリアの幅広さを得られるのも事実です。
やめとけという意見があるからこそ、自分自身の価値観や目指す姿を明確にしておくことが大切です。
コンサルティング業界は、今後も成長が期待される分野のひとつです。
企業や自治体が多様な課題に直面する中、外部の専門家による支援のニーズは高まり続けています。
特に近年では、AIやDX推進を支援するテクノロジー系コンサルや、サステナビリティ人的資本経営などを扱う分野にも注目が集まっています。
また、経験を積んだ後は、事業会社への転職や起業・独立といった選択肢も豊富です。
多様なキャリアパスを描ける点でも、将来性は非常に高い業界と言えるでしょう。
【コンサルに向いている人】まとめ
以上、見てきました通り、コンサルタントには、客観的に検証可能な形で論理的に現状分析を行い、その結果を顧客に納得させ、適切な解決方策を顧客が実行できるようサポートする能力が必要となります。
大変高い能力が求められる専門職の一つであるといえますが、やる気と一定の能力・素養がある人であればチャレンジする価値がある仕事です。
関心がある人は、関連の情報を収集し、ぜひコンサルタントを目指していただきたいと思います。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)