はじめに
普通の面接では平均どのくらい時間がかかるのか気になる人は多いのではないでしょうか。
面接の平均所要時間がわからないと、面接準備をどの程度したら良いのかわからず不安になりますし、その後の予定も組みにくくなってしまいます。
また、平均よりも面接が長すぎた、もしくは短すぎた場合は、合格か不合格か非常に心配になってしまうのではないでしょうか。
本記事では、面接の平均時間と、平均時間と比べ面接の時間が長すぎた場合や短すぎた場合に考えられることを詳しく解説し、面接で気をつけるべきポイントも紹介しています。
この記事を読むと、面接時間に悩まされることがなくなり、面接を受けている際に平均時間なんてものを気にすることなく、面接に集中することができるようになります。
ぜひこの記事を読んで、面接で時間に振り回されず、あなたの実力を存分に発揮できるようになってください。
面接の平均時間は

就活の平均面接時間は、当然企業によって大きく異なります。
大企業で多くの学生の面接を行う場合には一次面接が集団面接である可能性もあるでしょう。
個人面接も15分ほどで終わることも珍しくありません。
一方で、中小企業の二次選考などにおいて、1時間ほど時間をとって面接を行うこともあります。
新卒の採用予定人数によって面接を行う学生の数も異なるので当然と言えます。
また、学生の返答が長ければその分面接時間も延びるでしょう。
それでも、平均としてはおそらく30分ほどでしょう。
30分の間にだいたい6問から8問の質問ができるため、自己PR、志望動機などの質問に加えて、その企業が聞きたいことを学生から聞き出すには十分な時間です。
もちろん、話が盛り上がったり学生の返答が長かったりする場合、また逆質問をいくつかした場合などに45分から1時間かかることがあっても不思議ではありません。
面接の長さは合否に関係ない

就活生にとって、面接の長さや質問数は気になるところですが、面接は長いことを想定して準備しておくことが賢明といえます。
面接時間の長さが合否に関係あるとは限らないため、心配しすぎずに自分の熱意を面接で伝えることが重要です。
面接の種類との平均時間は?

面接によっては面接時間が長いと感じることもあります。
なぜ面接時間が長くなるのかというと、それは、面接の合否に対して的確な判断を下せていないからです。
面接時間が長くなると、悪い評価がつくと判断する人もおられますが、面接時間の長さによっては、よい評価も含めて判断に迷っている証なのです。
一次面接
一次面接は、面接に長い時間をかけることが少ないです。
マニュアル的に対応しているので短くなるケース、もしくは、二次面接に重きを置く傾向にあるため、このような対応が好ましいと判断している企業もあります。
1人にかける時間が少ない
一次面接の時間は、長くても10分を少し超える程度と思ったほうがよいでしょう。
一次面接には顔合わせの要素が多く、主に能力、人柄などを審査していることが多いです。
そのため、質問を掘り下げてくることが少ないため、一次面接で何度も質問されるということは、面接官に好意を持たれているケースが予想されます。
グループ面接を実施する企業が多い
グループ面接は、面接時間を削減するためのものではありません。
受け答えに対して素早い対応を求められることの多いグループ面接では、ムダな質問を省いて、対応力のある人を見極められます。
そのため、実施されていると思ったほうがよいでしょう。
二次面接
一次面接とは違い、二次面接の面接時間は応募者数によって変動することが多いです。
応募人数が多いと面接時間が短くなり、逆に、応募人数が少ないと時間をかけて面接してくれることが多くあります。
これは、面接官の数による影響もあるため、面接官の人数が少ない企業では、数分で面接終了になるケースも少なくありません。
個別面接での対応が多い
二次面接の時間に余裕がある企業では、個別面接による対応を取ることが多いです。
一次面接で聞き出せなかったことを質問されるケース、もしくは、個人の要望などを1つずつチェックするといった対応が行われます。
平均30分~1時間程度が多い
二次面接の時点で、一次面接の時より入念な審査をすることが多いため、一次面接の倍以上の時間をかけて面接してくれることが多いです。
面接時間の平均では、30分程度で終了することが多いでしょう。
企業によっては、家族構成、家族と仲はよいのかといった、面接官の意思で独特な面接に発展するケースも少なくありません。
そのため、二次面接にかけられる時間が60分以上のケースもあるのです。
面接官の質問意図を読み解くポイント
面接官は表面的な回答を求めているわけではありません。
質問からあなたの経験や仕事の意欲、志望動機などを見極めています。
また、自社が求める人物像にマッチした人材かもチェックしています。
質問から面接官が見ているポイントを見抜き、「なぜ?」「どうやって?」といった深掘りの意図を予測してください。
質問のキーワードから求められる内容を連想し、意図に合致するよう答えましょう。
深い自己分析が面接時間を有効に使うカギ
深い自己分析は、あなたの核となる価値観と行動原理を明確にします。
自己理解を深めることで、質問の意図に対して最適なエピソードを瞬時に選択することが可能です。
結果、質問の回答に一貫性と高い説得力が生まれます。
面接官が知りたい情報を先回りして提供することで、限られた時間であっても質の高い面接になります。
面接時間はあなたの強みや魅力をアピールする貴重な機会です。
チャンスを逃さないためにも自己分析は徹底してください。
最終面接
最終となっているため、一次面接、二次面接よりも内容が濃い面接と勘違いされることがよくあります。
ですが実際は、最終面接として役員や社長クラスが、面接内容を確認するだけの傾向にあります。
平均1時間程度の面接時間
最終面接では、今まで行われた質問などを役員クラス以上がチェックします。
ほかにも、志望動機の確認、就職に対する意思の在り方、就職後にどのような貢献をしたいのかといった、事細かい意思疎通も行われることが多いです。
そのため、30分以内といった短時間で終わるケースは、少ないと理解しておいたほうがよいでしょう。
企業の感度が高い学生は時間が長いことが多い
最終面接も二次面接と同じで、好感触の相手に対してはその雰囲気を表に出してきます。
そのため、企業から気に入られている人物ほど、何気ない日常会話に時間をあてることが多く、このような時は、少しリラックスして対応できると、面接に対して余裕のある人物と判断されるでしょう。
リクルーターがついていると5分で内定を獲得できることもある
リクルーターとの面談を、リクルーター面談と言います。
面接とは別物と思ってしまいますが、リクルーターと呼ばれるスタッフを通じての面接となります。
そのため、面談のほうで高評価をもらえる人であれば、評価を軸にした短時間の面接が可能となるのです。
短い最終面接で内定が出た理由とは?
短い最終面接で内定が出た場合、以下の3つの理由が考えられます。
過去の選考で完璧な評価を得ていた
最終面接が入社意思の確認のみだった
質問に対する回答の質が圧倒的に高かった
面接時間が短い=悪いというわけではありません。
面接時間ではなく、質に注目してください。
最終面接は、入社意欲を確認し、早期に退職しないか確認する作業がほとんどです。
つまり、1時間以上の時間をかける想定がされていません。
さらに、面接官の想定をはるかに超えた場合も短い時間で面接が終わります。
聞きたい質問が10個あったとします。
あなたの回答が複数の質問に該当する内容だった場合、面接の時間が短縮されるでしょう。
役員面接で聞かれる「逆質問」の重要性
役員面接で聞かれる逆質問は、あなたの入社意欲を直接伝えるチャンスです。
入社前に聞いておきたい内容を確認しつつ、アピールにつなげてください。
たとえば、経営戦略や事業ビジョン、企業文化が挙げられます。
質問例
「御社の資料を拝見し、〇〇事業の今後の成長に期待しております。
その一方で、社長が現在、最も優先度高く解決すべきだと考えている経営課題は何でしょうか?」
「御社の社員の方々が、働き続ける理由や最も大切にしている価値観は、経営層の視点から見てどんな点だとお考えでしょうか?」
逆質問をいくつも投げかけるのは避けましょう。
ほかの就活生がいる場合、迷惑がかかるからです。
選考を通じて「この疑問は解消したい」と感じる優先度の高い質問を厳選してください。
面接の長さは内定に影響ある?

一般的に、人の印象は初めの5分ほどで決まると言われており、人事担当者が就活生を見極めるために必要な時間も長くはありません。
ただし、5分で面接を終わらせるのは学生に失礼という気遣いや、一通りの質問は聞いてみて評価シートを記入するというルールがある場合もあるため、最低でも15分か20分は面接をするケースが多いでしょう。
一方で、面接時間が長いほど合格の可能性が高いというわけでもありません。
単純に学生の話が長すぎる場合には、必ずしも高評価を得られるとは言えないでしょう。
また、学生の返答に矛盾があった場合などに、面接官が質問を変えて別の角度から聞き直すこともあります。
そのため、評価が中ぐらいで次の選考に進めるべきか判断しかねている場合に、面接時間が長くなる可能性もあります。
面接時間が長いと企業からの評価が高い?
採用面接を受けていると、思いのほかその時間が長くなるケースがあります。
戸惑ったり不安に感じたりすることもありますが、その理由を把握しておけば安心して対応できるでしょう。
面接が長くなる主な理由としては、学生に魅力を感じている、そもそも確保している時間が長い、学生の人となりを把握するのに時間がかかるといったものが挙げられます。
良い理由、どちらでもない理由、悪い理由が考えられますので、それぞれの原因をチェックしてみてください。
学生が魅力的
学生の回答を発端にして会話が盛り上がる場合やより深く質問される場合、面接担当者が学生に魅力を感じていて面接時間が長くなっていると考えられます。
これは、応募してきた学生が魅力的であるため、企業にとって有益な人材であるかどうかをもっと知りたいという心理によるものです。
具体的には、学生が持っているスキルに興味があるケースやハッキリとした自信のある受け答えに将来性を感じているケースがあります。
こうした場合には、良い印象を残しやすいため、次のステップへ進む手応えを感じるかもしれません。
もともと設けている時間が長い
企業側が1人あたりの面接時間を長く設定しているために、面接が長時間になる場合もあります。
これは、応募者が比較的少ない中小企業などに多く見られる特徴です。
学生一人ひとりに時間をかけて面接する方針であったり、面接回数が少ない代わりに一回あたりの面接時間を長く設定していたりするケースもあるでしょう。
会話が盛り上がったという手応えが少ない割に面接時間が長ければ、応募者全員一律で面接時間が長い可能性があります。
具体的な面接内容としては、用意されている質問の数が多い、細かな部分まで質問されるといったケースが該当するでしょう。
面接官が話し好き
面接官が話し好きだった場合も、面接時間が長くなります。
企業のことを説明する以外に、面接官が世間話などを話していた場合はこちらのケースが考えられます。
この場合は、基本的に応募者全員一律で面接時間が長い可能性が高いです。
学生の特徴が掴めない
面接担当者が学生の特徴をうまく把握しきれず、結果的に面接に時間がかかるケースもあります。
これは、学生が質問に対してスムーズに回答していない場合に多くなるケースです。
同じようなことを何度も繰り返し聞かれたり、面接担当者が悩むような素振りを見せたりしたら、求められている回答ができていない可能性があります。
自分の考えが伝わりにくいと、面接が長引くだけでなく、コミュニケーション能力が低いと評価されるかもしれません。
落ち着いて、自分の熱意や意志を伝えてみてください。
面接が短く終わったら不合格?
面接時間があまりにも短いと手応えを感じられず不安になることもあるでしょう。
しかし、面接時間の短さは、必ずしも悪い兆候ではありません。
面接時間が短く終わるケースには、良い理由も悪い理由もあるものです。
具体的には、面接する学生の人数が多く1人あたりの時間が短い、学生の話し方が上手でありスムーズに進んだ、すでに内定が決まっていてもう聞くことがない、学生に魅力を感じていないといった理由が挙げられます。
それぞれの内容をチェックして、安心して面接を受けましょう。
面接人数が多い
面接する人数が多いため、1人あたりの面接時間が短くなるケースもあります。
これは、応募人数が多い人気企業に多く見られる特徴で、大人数を効率良くさばくためにもやむを得ない事情と言えるでしょう。
具体的には、たくさんの学生が待機している場合や質問内容がベーシックなものに絞られている場合に、全員一律で面接時間が短い可能性があります。
こういったケースでは、経験やスキルといった部分は事前のESでチェックして、面接では人柄や印象を見るだけであることも多いでしょう。
学生の話し方が上手
学生の話し方が上手であり、予定していた時間が余るケースもあります。
面接に慣れていなかったり話し方が下手だったりすると、1つの質問にかかる時間は長くなってしまうでしょう。
しかし、スムーズな受け答えができれば、1つの質問に必要な時間は短くなります。
また、何度も質問しなければ学生の特徴が掴めないといった事態になりにくいため、質問の数も少なくなるでしょう。
時間は短くても会話のキャッチボールがうまくできていて面接担当者が納得した様子であれば、短時間でも手応えを得られるはずです。
すでに内定が決まっている
面接の前にすでに内定が決まっている場合、面接には長い時間をかけないケースもあります。
特に最終面接まで進んだ場合には、面接の場では短時間でお互いの意思確認のみを行う企業も多く、大きなミスをしない限り内定が出るでしょう。
一次面接であっても、ESなどで高いスキルや経験をアピールできた場合には、魅力ある人材として次のステップに進むことが確定していることも珍しくありません。
ESなどをしっかり作り込めていれば、面接の時間が短くても戸惑う必要はないでしょう。
学生に興味が湧かない
残念ながら、その学生に対する興味がないために、面接時間が短くなるケースもあります。
第一印象が悪い場合、面接担当者は学生に対する興味がなくなるため、面接の内容にかかわらず不採用となるでしょう。
そのため、短時間で切り上げられてしまうこともあるのです。
連絡なしに遅刻した・入室時のマナー違反・敬語が使えないといった基本的な社会人としてのマナーが守れていないと、魅力ある人材とは判断されないため、面接する価値がないと判断されてしまうでしょう。
面接ではマナーを厳守し、まず自分に興味を持ってもらうよう心がけてください。
面接時間の長さで合否はわからない
面接が思ったよりも短く終わってしまう場合にはどのようなケースが考えられるでしょうか。
そもそも面接を担当している方が仕事でバタバタしているせいでそれぞれの就活生に対して時間を取ることができないということも考えられます。
他にも、すでに合否が決まっている場合なども面接が短く終わることがあります。
例えば、あらかじめ提出を求められたESなどの書類を見た段階ですでに採用や通過が決まっていたりする場合には、認識の違いなどがないかどうかを見るだけなので面接の時間は短くなります。
またこの逆もあり、事前にすでに不採用が決まっていたり、面接の最初の方であなたの合否が決まっていたりする場合にも面接の時間は短くなります。
短く終わる場合にも合格している可能性はあるため、できるだけ自信を持って面接に望むようにしましょう。
【番外編】面接には何分前に到着していればいい?

面接中の時間について詳しく解説してきましたが、面接には実際に何分前に到着していればいいのでしょうか?
遅刻はもちろんできないというのは前提ですが、あまりに早く到着してもかえって企業に迷惑になってしまいます。
ここでは、そんな面接での疑問について詳しく解説していきます。
しっかりとして準備をして内定獲得、選考突破を目指しましょう。
ビルには10分前には到着しておく
多くの場合、大きなビルの中に入っている企業がほとんどです。
そのため、時間ちょうどにビルについても会社に着くまで時間がかかってしまいます。
そうならないように、オフィスが入っているビルには10分前や15分前には到着しておくようにしましょう。
また、駅についてからビルまで意外と距離があるということもあるため、事前にマップでどのくらい時間がかかるのかチェックした上で早めの行動を心がけましょう。
受付を済ませるのは5分前まで
ビルに早めについてからはトイレを済ませておくなどして、実際の受付には5分前や10分前には到着するようにしましょう。
これは、あまり早すぎても企業に迷惑がかかってしまうこと、ギリギリに到着しても企業にマイナスイメージを持たれてしまう可能性があるということがあるため、できるだけ5分から10分前を目安に受付を済ませられるようにしましょう。
遅刻しそうな場合は事前連絡を
あまり考えたくないですが、もしも遅刻しそうになってしまった場合には事前の連絡を心がけましょう。
この時、マイナスイメージを持たれないようにするためには到着時間を少し余裕を持って伝えるようにしましょう。
そうすることで普通に向かっても少し急いだのかなという印象を与えることもできますし、何かあっても間に合うようになります。
ただ、この時に気をつけて欲しいのは、30分以上遅れないようにしてください。
基本的に社会人はカレンダーを使って1日の予定を管理しています。
あなたの面接の時間の後にも予定が詰まっているかもしれません。
基本的に来客であるあなたの都合を優先してくれるとは思いますが、そうしたリスケの手間がマイナスイメージにつながることもあるため、こうした視点を持つことで他の就活生とも差別化できるようになります。
面接に遅れるときの対処法
面接に遅れることがわかった時点ですぐに採用担当者へ「電話」で連絡してください。
メールは避け、あなたの言葉で真摯な姿勢を見せることが重要です。
また、メールは採用担当者が見ない可能性があるので注意が必要です。
電話では、誠意ある謝罪の言葉を伝えてください。
言い訳はせずに遅刻する旨と具体的な到着予定時刻を簡潔に報告します。
面接開始の時間ギリギリの連絡は避けましょう。
到着後も面接官に会った際、あらためて遅刻のお詫びを直接伝え、気持ちを切り替えて面接に臨んでください。
具体的な手順は以下の通りです。
- 遅刻が確定する
- 電話で採用担当者に遅刻の旨を伝える
- 謝罪の言葉を述べつつ、到着予想時間を伝える
- 到着後、採用担当者にあらためて謝罪する
できる限り早期に対応し、採用担当者に迷惑をかけないようにしましょう。
面接の時間を有効に使うための心構えと対策

簡単な対策では、面接時に必要となるものをチェックしておきます。
そのほかにも、髪型、服装を整えるようにすると効果的です。
さらに、面接時間、アクセスマップの再確認を行っておくと、ミスが少なく精神的にも楽な面接になるでしょう。
自己分析や企業研究をしっかりしておく
面接では必ず自己PRと志望動機を聞かれます。
しっかりと自分をアピールできるように自己分析をしておくこと、そして志望動機を明確に答えられるように企業研究をしておくことが大切です。
企業研究をすることで、その企業が求めている人材も分かるようになります。
そこに関連付けた自身の強みをアピールすることができるようになれば、それは合格への第一歩となるでしょう。
本番同様の空気感の中で面接練習をする
面接練習をすることは非常に大切ですが、行っている環境が本番同様でないのであれば、実践で全く役に立ちません。
本番さながらの空気感で、緊張感を持って練習に臨むことで、本番で緊張しながらでも自身の力を発揮できるようになります。
面接練習をなんとなくで行わず、意味のあるものにすることが非常に大切です。
話す内容はすべて書き出しておく
日常会話にも言えることですが、たどたどしい会話よりも、スムーズなコミュニケーションのほうが楽な会話になります。
面接の場合は、あらかじめ話す内容をおさえていることによって、自信のある人物を演出できます。
また、話す内容を事前に書き出しておくと、いざという時の確認も楽になることが多いです。
結論から話す
話をコンパクトにまとめるコツは、自分の言いたいことをはっきりさせることです。
なので、長々と会話をしても自分の考えは伝わりづらいと、そのように考える癖を身につけましょう。
面接官の質問に対して的確に返答する
面接官の質問といっても、それほどパターンは多くありません。
志望動機、今までの経験、学業で打ち込んだもの、部活動、行事で記憶に残っていることなどをよく聞いてきます。
その他では、資格、趣味、将来的にやりたいことも聞かれるので、こちらの回答を用意していると、気持ちよい質疑応答ができるようになるでしょう。
表情は明るく見せることを意識する
常に笑っているような対応ではなく、入室時、退室時、質問の受け答えをする時は笑顔を意識したほうがよいです。
暗い表情のままでは、表情の暗さの理由を聞かれるなどして、面接時間が長くなることもあります。
余裕がある場合は、面接官の顔を見て話すようにすると、歯切れのよいコミュニケーションができる人物として評価されることが多いです。
面接官が「この学生は採用したい!」と感じる5つの特徴
面接官が「この学生は採用したい!」と感じるのは、以下の5つに当てはまる人です。
- 主体性がある
- 建設的なコミュニケーションが取れる
- 学習意欲があり知的好奇心が旺盛である
- 高いストレス耐性と柔軟性を持っている
- 企業のビジョンと合致する熱意と志望動機がある
面接官は、自ら考え行動し、責任感を持ってやり遂げる人材を探しています。
任せた仕事を最後まで取り組んでほしいからです。
また、職場環境に満足することなく、新しいスキルを身につけたいと考える人材を高く評価します。
ほかにも、コミュニケーション能力や高いストレス耐性も有効です。
長期間にわたって成果を出すために必要な要素を満たしていることの証拠になります。
当てはまる数が多いほど、評価は高くなるので面接では積極的にアピールしてください。
自己紹介と自己PR、履歴書とESの違いを理解する
自己紹介と自己PR、履歴書とESはそれぞれ役割が違います。
間違ったまま覚えてしまうと、面接官の意図に反した回答になります。
以下で解説する内容を理解し、適切に使用してください。
自己紹介と自己PRの違い
| 名称 | 違い |
|
自己紹介 |
面接の冒頭で行う、場を和ませるための基本的な挨拶。時間は30秒〜1分程度で簡潔さが大切。 |
|
自己PR |
面接の本題。 自分という商品を売り込むプレゼンテーション。応募職種に活きる具体的な強みと根拠となるエピソードを語る。 |
履歴書とESの違い
| 名称 | 違い |
|
履歴書 |
氏名、学歴、資格、志望動機など、公的な事実情報を記載する書類。公的な記録として扱われる。 |
| ES |
企業が独自に設定したテーマに対し、人物像や適性を詳細に評価するための書類 |
面接対策アプリやサービスの活用方法
就活を効果的に進めるには外部のサポートを活用することが効果的です。
「就活対策の時間がない」「効率よく準備を進めたい」など考えた就活生は、ぜひ参考にしてください。
| 名称 | 活用方法 |
|
生成AI |
AIに〇〇会社の採用担当者という役割を与え、志望企業の質問を生成してもらう。 また、あなたの回答を入力し、より説得力のある伝え方を提案してもらう。 |
|
スマートフォン |
模擬面接や練習中の自分の回答を録画・録音し、時間配分や話し方を客観的にチェックする |
|
就活エージェント |
エージェントに志望企業のES・履歴書を添削してもらう企業ごとの模擬面接を依頼する |
|
大学のキャリアセンター |
面接マナーや服装、質問への練習相手になってもらう |
【番外編】特別な面接時間のケース
面接は対面だけではありません。
オンラインやケース、GDも立派な選考です。
企業によっては採用している可能性があるので、本章で紹介するケースも対策しておきましょう。
もし、該当した場合に慌てることなく対応できるからです。
オンライン面接
オンライン面接は、対面とは異なる非言語情報が大切です。
技術面とコミュニケーション面の双方に注意しながら参加してください。
オンライン面接をスムーズに突破したい就活生は、以下の表にある注意点を覚えておくと便利です。
| 項目 |
注意点 |
|
通信環境 |
有線接続を推奨。不安定なWi-Fiは避け、事前に接続をテストする |
|
照明・背景 |
顔色が明るく見えるよう正面から光を当てる。生活感のないシンプルな壁を背景にする。 企業イメージに合ったバーチャル背景もあり。 |
|
カメラ位置 |
カメラを目線の高さに合わせる。目線が下がりすぎないようにPCの高さを調整する。 |
| カンペ |
カンペは使ってOK。ただし、目線を落とさずに済むよう、カメラの近くにメモを貼る。 |
ケース面接
ケース面接は、特定のお題に対して、論理的思考力と課題解決能力を測る選考形式です。
主にコンサルティング企業で出題される傾向にあります。
また、ケース面接ではお題の正解ではなくプロセスが大切です。
どのようにして回答を導き出したのか、言語化できるように練習してください。
ケース例①:〇〇社の売上を2倍にするには?
ケース例②:通勤ラッシュはどうすればなくなりますか?
ケース面接を突破するには、以下の4つを意識してください。
|
項目 |
意識するポイント |
|
課題の定義と明確化 |
質問の背景や条件を確認し、何を解くべきかを明確にする |
|
フレームワークの言語化 |
課題を解くにあたってどういった過程を辿ったか説明する |
|
仮説設定と検証 |
効果が高いと思われる仮説を立て、根拠を提示する |
|
結論と提言 |
結論は簡潔に提示する。実現性とデメリットについても触れ、多角的な視点をアピールする |
GD(グループディスカッション)
GDは、複数人での議論を通じて、あなたの集団内での振る舞いやチームへの貢献度を測る選考形式です。
GDの時間は30分〜1時間が一般的です。
企業によって設定時間が異なるため、開始時に確認してください。
GDの流れは以下の通りです。
| 段階 |
目安時間 |
目的 |
|
テーマ理解 |
5分〜10分 |
議題を整理し、理解する |
| 討論 |
20分〜40分 |
メンバーと意見を交換する 論点の深掘りし、結論の導く |
|
発表 |
5〜10分 |
最終結論の発表 |
面接官はGDの成果よりもあなたの貢献具合に注目しています。
他の意見をきちんと聞いたり、話がそれた際に軌道修正したりする様子を観察しています。
議論が白熱すると面接官の存在を忘れがちです。
しかし、審査されていることを自覚し、チームに貢献できることがないか考えてください。
在職中に転職活動をする場合の面接スケジュールのポイント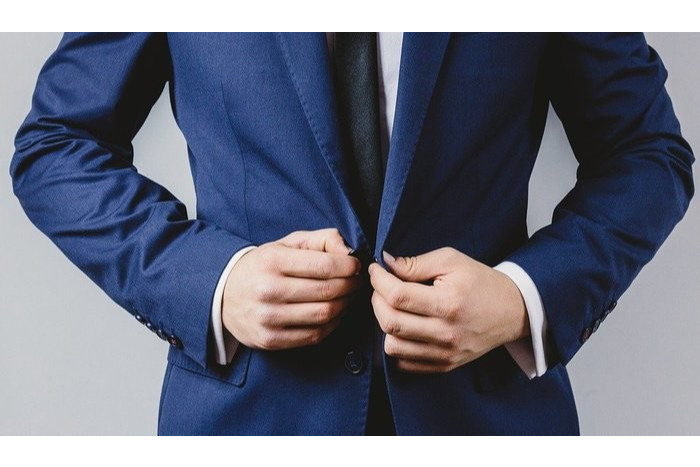
在職中に転職活動する場合は、自分で面接日程を調整しなければいけません。
その時に気をつけたいポイントが、以下に記載している3点です。
次の項目で1つずつ解説していきます。
- 面接希望日を指定する場合には複数用意する
- 基本的に面接時間の変更は避けるようにする
- 面接時間帯を考える
面接希望日を指定する場合には複数用意する
面接応募者が面接希望日を指定する場合は、希望日を複数用意すると良いでしょう。
採用担当者も普段は通常業務を行っており、忙しいことがほとんどです。担当者に配慮して、なるべく多くの日程を提示するようにしましょう。
基本的に面接時間の変更は避けるようにする
面接時間の変更をしたからといって不合格にはなりません。
しかし、時間変更を依頼したときのこちらの対応によっては一気に合格から遠ざかる場合があります。
直前に連絡をした場合や、2回以上時間変更を依頼した場合は、スケジュール管理能力がないとみなされ、ほとんどの場合不合格となるでしょう。
面接の日は有給制度をするなどして、なるべく時間変更をしないように心がけましょう。
面接時間帯を考える
面接の時間帯も気をつけたいところです。
おすすめは、一般的な定時内の10時から12時です。
朝であれば面接官の疲労が溜まっておらず、集中力が高い状態で面接を行ってもらえます。
しかし、在職中の転職活動では、仕事を休むことができず日中に面接を受けられない場合もあるでしょう。
その場合は、終業後の夕方以降に面接を受けられないか確認してみましょう。
終業後の18時から19時の間で面接をしてくれる企業も多くあります。
その場合は、面接官以外の社員さんが少なくなっていることも多いため、日中よりも落ち着いた状況で面接を受けられるのが利点です。
転職活動中の場合は、面接の時間を企業に相談することが可能です。
しかし、こちらはあくまでも面接をしていただくという立場です。
面接の時間帯を一方的に指定するようなことはないようにしましょう。
まとめ
この記事では面接の平均時間から注意するべきポイントについて解説してきました。
面接はあなたの強みや魅力を直接伝える貴重な機会です。
事前準備を怠らず、あなたを採用するべき理由を伝えてください。
ただし、面接時間が長い=良い、短い=悪いとは限りません。
5分で面接が終わっても内定がもらえることもあります。
時間を気にするよりも、あなたの良いところを見せることに注力してください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート




_720x550.webp)
_720x550.webp)





