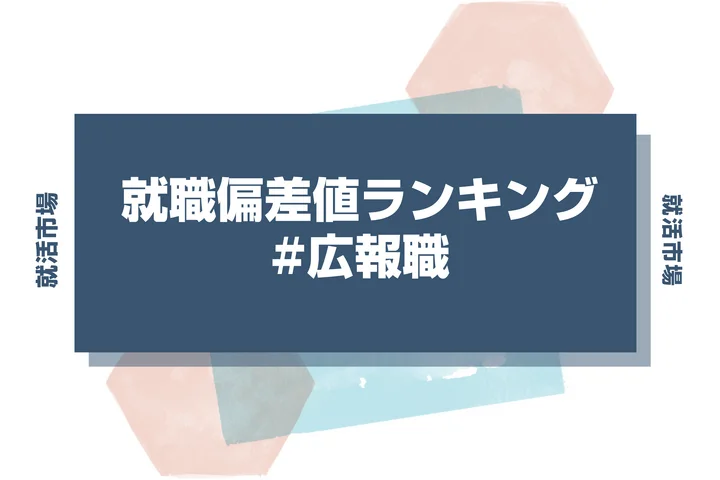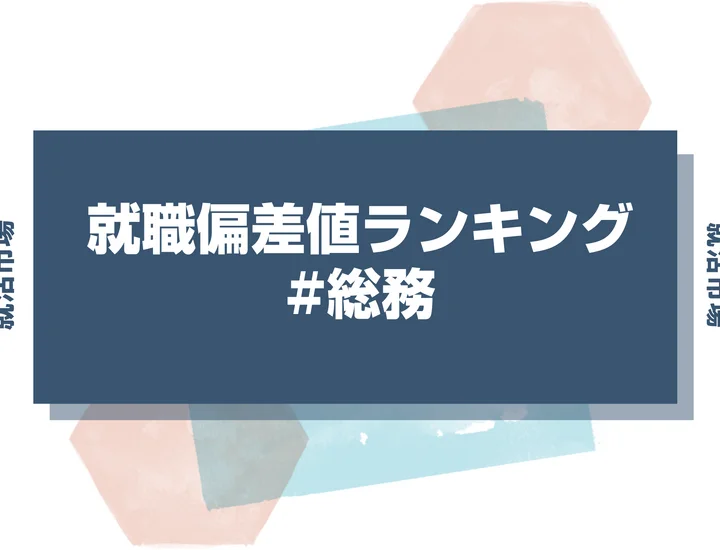目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
広報の就職偏差値ランキング
広報職の就職偏差値は、企業の規模、業界、そして広報業務の専門性の深さによって大きく変動します。
広報は企業イメージやブランド価値を対外的に発信する、いわば「企業の顔」を担う重要なポジションです。
そのため、特に高い偏差値の企業では、論理的な思考力や高い言語化能力、そして危機管理能力といった多角的なスキルが求められます。
このセクションでは、広報職の採用難易度を偏差値別に分類し、それぞれの特徴や求められる資質について詳しく解説していきます。
皆さんが志望する企業がどのランクに位置するのか、またそのランクの企業に入るためにどのような対策が必要なのかを把握するための導入として、ぜひ参考にしてください。
【広報】SSランク(就職偏差値75以上)
- 上場企業・外資企業のコーポレート広報で、企業のレピュテーションを担う
- メディア対応・記者会見・危機管理広報など高度な実務が中心
- 経営層と連携する場面が多く、事業理解と情報整理の能力が必須
- 英語力やストーリーテリング力など、専門スキルの要求水準が非常に高い
【80】外資系テック企業のコーポレートPR
【78】プライム上場企業の広報・IR部門
【75】大手総合商社・大手メーカーの広報部
SSランクは企業のイメージを左右する重要領域を担うため、メディア対応の経験や情報発信力など高度な専門性が求められる。
特に外資企業では英語でのプレスリリース作成や海外拠点との連携が発生するため、語学力が必須となる。
また上場企業ではIR(投資家向け広報)と連携するケースも多く、財務知識が要求される。
責任の大きさはあるが、キャリアとしての希少性と市場価値は非常に高いゾーンである。
【広報】Sランク(就職偏差値70〜74)
広報の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、広報の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ広報の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手企業やメガベンチャーの広報で、ブランド発信・SNS運用・メディア対応を担当
- プレスリリース作成やメディア向けイベントの企画が中心
- 経営理念やサービス価値を言語化するスキルが求められる
- 応募者が多く人気が高いため、倍率も上がりやすい
【74】大手IT企業の広報戦略チーム
【72】大手メーカーのブランドコミュニケーション部
【70】メガベンチャーのPRチーム
Sランクは企業のブランド価値を高める役割を担い、文章力・企画力・SNS運用力など多面的なスキルが評価される。
新卒でもプレスリリース作成やメディア対応を任されることがあり、スキルアップが早い環境が多い。
一方で、企業イメージ形成に関わるため、細かな情報管理やリスク対応の意識が必要である。
成長環境とブランド力の両方を重視する学生に人気の高いゾーンといえる。
【広報】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 中堅企業やITベンチャーの広報担当で、実務を幅広く経験できる
- SNS運用・ニュースリリース・社内広報など業務範囲が広い
- 広報とマーケティングが近い組織も多く、連携して働くことが多い
- 裁量が大きく、自ら企画を提案し実行できる環境がある
【69】ITベンチャーのPR担当
【67】中堅メーカーの広報・宣伝担当
【65】スタートアップのコーポレートPR
Aランクは広報の実務を幅広く任されるため、文章力や企画力を中心に総合的なPRスキルを磨ける点が魅力である。
少人数チームも多く、プレスリリースからSNS運用、イベント企画まで担当するケースもある。
企業によってブランドの知名度が異なるため、広報として工夫が求められる場面が多い。
自ら手を動かしながら広報スキルを積みたい学生に適したゾーンといえる。
【広報】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 中小企業やローカル企業の広報で、事務作業と運用が中心
- SNSの投稿管理、社内報作成、プレスリリース補助などサポート業務が多い
- 専門性よりもコミュニケーション力と事務処理能力が求められる
- 広報経験の入口として挑戦しやすい
【64】中小企業の広報アシスタント
【62】ローカル企業のSNS運用担当
【60】地域医療機関・学校法人の広報事務
Bランクは広報のサポート業務が中心で、まずは現場で実務になじみたい学生が挑戦しやすいゾーンである。
フォト撮影、SNS投稿、イベント補助など運用業務が多く、地道な作業が求められる場面も多い。
企画よりも実務寄りの経験が増えるが、広報の基本フローを理解するには十分な環境である。
将来的に広報の専門性を高めたい学生にとって、入口として志望しやすい領域といえる。
【広報】Cランク(就職偏差値55〜59)
- 広報未経験歓迎のポジションで、事務的な業務が中心
- SNS投稿管理やデータ整理など、比較的ライトな業務が多い
- クリエイティブというより事務・運用寄りの職務内容
- 企業規模が小さいほど兼務も発生しやすい
【59】広報事務(SNS投稿補助)
【57】コンテンツ管理スタッフ
【55】バックオフィス兼広報補助
Cランクは広報領域に触れつつも、実務は事務作業が多いため専門性は高くないが経験を積む入口としては有効である。
投稿管理や簡単な原稿作成など、細かい作業の積み重ねが中心となる。
小規模組織では他部門と兼任するケースがあり、広報業務の幅は限られやすい。
まずは広報の職種に触れたい学生が選びやすいゾーンである。
【広報】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 資料整理・データ入力など、広報よりも一般事務に近い業務が中心
- 広報の専門的なスキルを求められないポジションが多い
- 情報発信よりも庶務業務が中心となる
- キャリアアップには追加の学習や経験が必要
【54】広報庶務・資料作成担当
【52】小規模企業のバックオフィスアシスタント
【50】コンテンツ整理担当(非専門職)
Dランクは広報の中でも事務寄りの業務が中心で、専門性を求められないため未経験から入りやすい層である。
資料作成やデータ整備が多く、メディア対応や企画業務に触れる機会は少ない。
一方で、バックオフィス領域として安定した働き方がしやすい点は利点である。
広報の周辺業務を経験しながら、徐々に専門領域へ広げたい学生に適したゾーンといえる。
広報の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
広報職の就職偏差値は、企業が属する業界によって顕著な傾向が見られます。
これは、各業界が持つ社会的な影響力の大きさ、事業の注目度、そして広報活動に求められる専門性の種類が異なるためです。
たとえば、社会への影響が大きく、常にメディアの注目を集めるような業界では、広報の採用競争率が高まり、結果として偏差値が高くなる傾向にあります。
逆に、ニッチな業界やBtoBビジネスが中心の企業では、一般の知名度が低いため偏差値は落ち着きがちですが、その分、業界特有の専門知識や関係構築スキルが重視されます。
ここでは、広報職を志望する学生が、どの業界でどのような能力が求められ、どれくらいの競争率が予想されるのかを具体的に把握できるよう、主要な業界別の広報職の傾向を解説します。
自身の興味や強みがどの業界の広報とマッチするかを考える参考にしてください。
大手総合商社・外資系企業:最高峰のSS・Sランク
総合商社や外資系の広報職は、広報職の中でも最高峰のSSランクやSランクに位置することが多いです。
これは、事業のグローバル性や、企業のレピュテーション(評判)が事業そのものに直結するリスクの高さが関係しています。
総合商社は資源、インフラ、金融など多岐にわたる事業を展開しており、広報には複雑な事業内容を簡潔に説明する能力に加え、海外支社や投資家(IR)との連携も求められるため、高い語学力や財務知識が必須となります。
また、外資系企業は本社の方針やグローバルのプレスリリースを国内市場に合わせてローカライズする能力、そして極めて高い危機管理能力が要求されるため、採用ハードルが非常に高くなっています。
これらの企業を志望する場合、学生時代から高い専門性や、グローバルな視点を持って活動した実績が強く求められます。
大手IT・メガベンチャー:人気集中型のS・Aランク
大手IT企業や成長著しいメガベンチャーの広報職は、SランクからAランクに集中しており、新卒・中途を問わず非常に人気が高く、応募倍率が上がりやすいのが特徴です。
これらの業界は、新しいサービスやテクノロジーのリリースが頻繁に行われるため、広報にはスピード感と企画力が求められます。
特に、SNSやオウンドメディアを活用したデジタル広報に強みを持つ必要があり、データ分析に基づいた効果測定や、クリエイティブなコンテンツ作成スキルが重視されます。
企業カルチャーがオープンなことも多く、社員の個性やビジョンを積極的に発信することが求められるため、企業の理念やサービス価値に深く共感し、それを熱意を持って語れる人材が内定を掴む傾向にあります。
大手メーカー・金融:安定性と信頼重視のA・Bランク
日本の大手メーカーやメガバンクなどの金融機関の広報は、AランクやBランクの企業が多く、安定性や信頼性が重視される傾向が強いです。
メーカーの場合は、製品のプレスリリースや技術広報が主な業務となり、専門性の高い情報を分かりやすく伝える文章力や正確性が求められます。
一方、金融機関では、法令順守や顧客の資産に関わるため、厳格な情報管理とコンプライアンス意識が広報活動の根幹となります。
ITやベンチャーほど華やかさは強調されませんが、企業としての歴史や社会的な信頼性を守り、育てるという、広報の本質的な役割を深く経験できる環境です。
そのため、地道な努力を厭わず、長期的な視点でブランドを守りたいと考える学生に適しています。
中小企業・ローカル企業:挑戦しやすいB・Cランク
中小企業や地域に根ざしたローカル企業の広報職は、BランクやCランクに位置することが多く、広報未経験の学生でも比較的挑戦しやすい領域です。
これらの企業では、広報部門が独立しておらず、総務や人事と兼務するケースも珍しくありません。
業務範囲が広く、プレスリリース作成からSNS運用、社内報の作成、さらにはイベント企画や事務作業まで、幅広い業務を一人で担当することが多いため、高いマルチタスク能力と自主的に行動できる意欲が求められます。
知名度が低い分、広報の力で企業を成長させるやりがいが大きく、裁量権を持って広報活動を一から作り上げたいという学生にとっては、大きな成長機会を得られる魅力的な環境といえます。
広報の就職偏差値が高い理由
広報職の就職偏差値が高い背景には、広報という仕事が持つ企業の経営戦略における重要性と、その職務を遂行するために必要なスキルの希少性が深く関わっています。
広報は単なる情報発信ではなく、企業のブランドイメージを形成し、メディアや社会との良好な関係を構築することで、事業の成長を根底から支える役割を担っています。
特に、SNSの普及や情報過多の現代社会において、企業が発信する情報の「質」と「信頼性」は企業の存続を左右するほど重要になっており、そのプロフェッショナルである広報職のニーズは高まる一方です。
ここでは、広報職がなぜ高い競争率と偏差値を持つに至ったのか、具体的な理由を掘り下げて解説していきます。
企業のブランドイメージ・レピュテーションを左右する重要性
広報職の就職偏差値が高い最大の理由の一つは、その業務が企業のブランドイメージやレピュテーション(評判)を直接的に左右するという極めて重要な役割を担っているからです。
広報は、良いニュースだけでなく、不祥事や製品トラブルなどの「危機管理広報」においても、迅速かつ適切な情報発信を通じて、企業への信頼を最低限に抑える防波堤の役割を果たします。
特に上場企業や大手企業では、情報一つで株価や世論が大きく変動するため、経営層直下で、企業全体の戦略的視点を持って広報活動を行う必要があります。
このように、企業の「価値」そのものに直結する仕事であるため、採用側も優秀な人材を厳選せざるを得ず、結果的に採用難易度が高くなっています。
高い言語化能力とコミュニケーションスキルが必須
広報職は、企業の事業内容やビジョンといった抽象的な概念を、プレスリリースやメディア対応を通じて分かりやすく、かつ魅力的な言葉で社会に伝える高い「言語化能力」が必須となります。
ただ情報を発信するだけでなく、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかという戦略的なストーリーテリングのスキルが求められます。
また、メディア関係者、投資家、消費者など、多様なステークホルダーと信頼関係を築くための高度なコミュニケーションスキルも不可欠です。
論理的思考力に基づいて複雑な情報を整理し、それを相手に合わせて最適な形で伝える能力は一朝一夕には身につかず、この専門性が高い偏差値の背景にあると言えます。
メディア・SNSの進化による需要の増加と多様化
インターネットとSNSの爆発的な普及により、企業と社会との接点は飛躍的に増加し、広報に求められるスキルも大きく多様化しました。
かつてはマスメディア対応が中心でしたが、現在はTwitterやInstagram、YouTubeといった各種SNSの運用、オウンドメディアの記事作成、インフルエンサーとの連携など、デジタル広報の知識と実践力が不可欠です。
このデジタルシフトにより、広報職には従来のメディアリレーションに加え、デジタルマーケティングの知見やデータ分析能力も求められるようになりました。
このように、求められる専門領域が拡大し、複合的なスキルを持つ人材の市場価値が高まった結果、広報職の採用競争が激化し、偏差値が押し上げられています。
採用枠が少なく、他職種からの異動が少ない希少性の高さ
広報部門は、営業やマーケティング部門と比べて、そもそも採用人数が非常に少ないという構造的な問題も、就職偏差値が高い理由の一つです。
多くの企業では、広報部門は数人〜数十人程度の少数精鋭で運営されており、新卒採用枠も極めて限られています。
また、広報は専門性の高い職種であり、他部門から簡単に異動できるわけでもありません。
そのため、広報職を志望する学生の数に対して、門戸が狭い状態が続いています。
この「希少性の高さ」が、結果として選考倍率を押し上げ、高偏差値につながっています。
この限られた枠を勝ち取るためには、入社意欲だけでなく、学生時代から広報に活かせる具体的なスキルや経験を積んでいることが重要になります。
広報の高偏差値企業に内定するための対策
広報の高偏差値企業に内定を勝ち取るためには、一般的な就職活動の対策だけでは不十分です。
SS・Sランクといったハイレベルな企業群は、学生に「広報パーソンとしての素質と将来性」を強く求めます。
具体的には、企業のブランドを深く理解する洞察力、危機的な状況にも対応できる冷静さ、そして何よりも情報を戦略的に操る高い言語化能力が問われます。
これらの企業は、「なぜ広報でなければならないのか」という職種への深い理解と情熱、そしてそれを裏付ける具体的な行動実績を重視しています。
ここでは、難関企業の広報職を目指す皆さんが、他の応募者と差別化し、内定を掴むための具体的な対策を解説します。
企業・ブランドへの深い洞察力をES・面接で示す
高偏差値の広報企業は、自社のブランドや事業に対する表面的な理解ではなく、「深い洞察力」を求めています。
単に「御社の製品が好きです」というレベルではなく、「御社のAという事業は、社会のBという課題に対して、Cという広報戦略で臨むべきだ」といった、戦略的な視点を含めて語れるように準備しましょう。
具体的には、志望企業の過去のプレスリリースやメディア報道、SNSでの反応などを徹底的に分析し、「企業の現状の広報の強みと課題」を自分なりに言語化することが重要です。
面接では、「もし今、御社で〇〇という危機が発生したら、どのように対応しますか?」といった、即座の判断力と論理性を試す質問が来ることも想定し、具体的なシミュレーションをしておきましょう。
プレスリリース作成・SNS運用など実践的なアウトプット経験
広報職の選考では、文章力や情報編集能力といった実践的なスキルが重要視されます。
高偏差値企業への対策としては、実際にプレスリリースを作成してみるなど、具体的なアウトプット経験を積むことが非常に有効です。
たとえば、自身が所属するサークルやアルバイト先での活動をニュースとして捉え、「どのような見出しで、どのような内容を盛り込めば、メディアやターゲット層に響くか」を考え、プレスリリースの形式で作成してみるのです。
また、SNSの個人アカウントを単なる私的な利用にとどめず、「特定のテーマを持った情報発信」として戦略的に運用し、フォロワーの反応やエンゲージメントを分析した経験をアピールすることも、デジタル広報の素養を示す上で大きな差別化要因になります。
多様なステークホルダーとのコミュニケーション実績を具体化する
広報の仕事は、メディア関係者、投資家、顧客、社員など、多様なステークホルダーと信頼関係を築くことにあります。
この能力をアピールするためには、学生時代の活動において、「立場の異なる人々とどのように信頼関係を構築し、目標を達成したか」という具体的なエピソードを準備する必要があります。
たとえば、「サークル内の意見対立を、双方の主張を第三者の視点からまとめ直し、共通の目標に言語化することで解決に導いた」といった経験は、利害調整力や言語化能力の証拠となります。
面接では、抽象的な表現ではなく、「〇〇の行動により、関係者の〇〇というネガティブな反応を、〇〇というポジティブな結果に変えた」というように、行動と結果を数値や具体例で示すことを意識しましょう。
語学力・財務知識など専門性の高い学習実績を積む
SSランクやSランクの外資系、大手総合商社の広報職を目指す場合、語学力やIR(投資家向け広報)に関わる財務知識など、専門性の高い学習実績は必須の対策となります。
特にグローバル展開をしている企業では、海外拠点や外国メディアとのコミュニケーション、英文プレスリリースの作成が発生するため、ビジネスレベルの英語力(TOEIC L&R 800点以上など)は大きなアドバンテージとなります。
また、上場企業の広報はIR部門と連携することが多いため、日商簿記3級程度の会計知識を身につけておくと、企業の財務状況を理解し、投資家向けのメッセージ作成に活かすことができるため、他の学生に差をつけることができます。
専門スキルは、広報職としての将来性とキャリアの幅を示す重要な要素となるのです。
広報の就職偏差値に関するよくある質問
広報職の就職偏差値について理解が深まるにつれて、「では、具体的に自分の場合はどうすればいいのだろう?」といった疑問が湧いてくるかもしれません。
広報という職種は、営業や事務といった他の職種に比べて、新卒採用の枠が少なく、業務内容も多岐にわたるため、就活生の間でも情報が錯綜しがちです。
特に、未経験から広報を目指す際のステップや、大学での専攻が不利にならないか、といったキャリアに関する悩みは尽きません。
このセクションでは、広報職を志望する学生から頻繁に寄せられる疑問について、就活アドバイザーとしての視点から具体的かつ実践的な回答を提供します。
皆さんの不安を解消し、自信を持って選考に臨むためのヒントとして活用してください。
Q. 地方大学出身でも高偏差値の広報企業に内定できますか?
A. はい、出身大学の所在地や偏差値は、高偏差値の広報企業への内定を直接的に左右する要因ではありません。
大手企業が本当に見ているのは、「広報パーソンとしてのポテンシャルと熱意」です。
採用において重視されるのは、あなたが学生時代にどのような「情報発信」や「対外コミュニケーション」に関わる活動に取り組み、どのような成果を出したかという点です。
例えば、大学の広報誌編集やSNS運用代行、地域イベントのPRボランティアなど、地域に根ざした活動でも、それを戦略的に実行し、具体的な結果を伴っていれば高く評価されます。
大切なのは、地方にいながらも、いかに主体的に広報的な視点を持って行動したかを明確に語れることです。
Q. 広報は文系職種のイメージですが、理系出身でも有利になりますか?
A. 理系出身であることは、むしろ強力な差別化要因となり、有利に働くケースが増えています。
特に、IT、メーカー、製薬といった専門性の高い技術や製品を扱う企業の広報では、理系的な思考力や知識が非常に重宝されます。
理系学生は、複雑な技術情報を論理的に整理し、それを簡潔に分かりやすい言葉に落とし込む「構造的な言語化能力」に優れている傾向があります。
面接では、「専門知識を一般の人にも理解できるよう、どのように伝えてきたか」といった具体的なエピソードを通じて、その能力をアピールしましょう。
あなたの専門性が、企業技術の「翻訳者」として広報活動に貢献できることを示すことが重要です。
Q. 広報職を目指すために取得すべきおすすめの資格はありますか?
A. 広報職の内定に直結する必須資格というものはありませんが、「広報のプロ意識と基礎知識」を示す上で、いくつかの資格は有効です。
特におすすめなのは、「PRプランナー資格認定制度」です。
これは、広報・PRに関する体系的な知識を学んだ証となり、職種への真剣な取り組み姿勢をアピールできます。
また、前述の通り、上場企業を志望する場合は、「日商簿記検定」を取得しておくと、IR広報や企業の財務状況を理解する上で役立ちます。
資格そのものよりも、資格取得を通じて学んだ知識を、広報業務でどう活かしたいかを具体的に語れることが、選考突破の鍵となります。
Q. 広報は新卒で入るのが難しいと聞きますが、あえて挑戦するメリットは何ですか?
A. 広報職は確かに採用難易度が高い職種ですが、新卒で挑戦し内定を勝ち取ることには、非常に大きなメリットがあります。
最大のメリットは、「経営視点とブランド戦略を若いうちから身につけられること」です。
広報は経営層と近い位置で働くことが多く、企業のトップの思考や事業全体を見る視点を間近で学ぶことができます。
また、高い専門性を持つため、一度スキルを身につければ、市場価値の高いキャリアを築きやすく、転職市場でも常に求められる人材になれます。
難易度が高いからこそ、新卒で広報経験を積むことは、あなたの社会人としての成長スピードを圧倒的に加速させるための最高のスタートラインとなるのです。
まとめ
本記事では、新卒の皆さんが広報職の就職偏差値ランキングを理解し、その上で高偏差値企業の内定を勝ち取るための具体的な対策について詳しく解説してきました。
広報職は、企業の「顔」としてブランドイメージとレピュテーションを担う、極めて重要でやりがいのある仕事です。
その分、高い論理的思考力、言語化能力、そして多様なステークホルダーと関わるコミュニケーション能力が求められます。
広報職の就職偏差値は高いですが、それは決して超えられない壁ではありません。
企業への深い洞察力を持ち、プレスリリース作成やSNS運用などの実践的なアウトプット経験を積み重ねることで、他の志望者と一線を画すことができます。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート