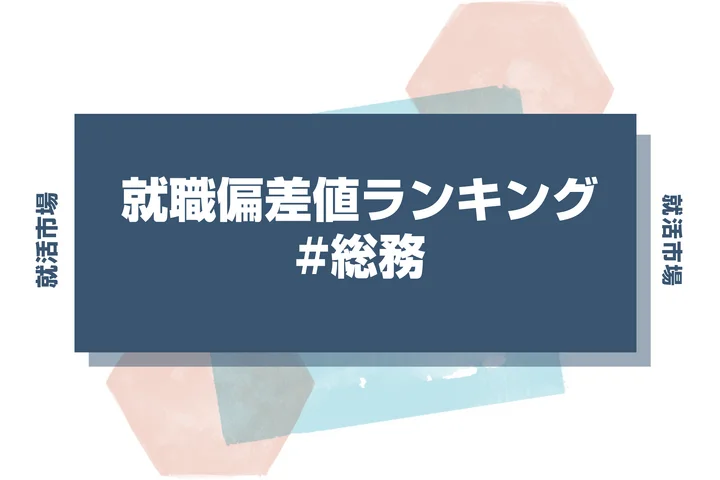目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
総務の就職偏差値ランキング
この記事を読んでいるあなたは、「総務」という職種に興味を持ちつつも、具体的にどのような企業が難易度が高いのか、そして自分にはどのレベルの企業が合っているのかを知りたいのではないでしょうか。
総務は「縁の下の力持ち」と表現されるように、企業運営を円滑に進める上で欠かせないバックオフィスの要です。
しかし、その業務範囲は非常に広く、企業規模や業界によって求められるスキルや採用難易度が大きく異なります。
一般的に、企業規模が大きく、かつ上場している大手企業の総務職は非常に高い偏差値を示す傾向にあります。
これは、関わる業務が「株主総会の運営」「コンプライアンス統括」「大規模なファシリティマネジメント」など、専門性が高く、かつ企業の根幹に関わる重要なものが多いためです。
逆に、中小企業やベンチャー企業では、総務だけでなく人事や経理など他のバックオフィス業務も兼任する「ゼネラリスト」としてのスキルが求められ、総合的な難易度で言えば高偏差値大手とは異なります。
ここでは、総務職の就職偏差値をランク別に分け、それぞれの特徴と目指すべき企業の傾向について詳しく解説していきます。
あなたの目指す総務像と照らし合わせながら、最適な目標設定に役立ててください。
ランキングはあくまで目安として、あなたが本当にやりたい業務内容を重視して企業選びを進めることが大切です。
【総務】SSランク(就職偏差値75以上)
- 上場企業の株主総会運営やコンプライアンス統括など高度な業務を担当
- 経営層との距離が近く、判断スピードと正確性が求められる
- グループ全体のガバナンス体制整備を担うケースが多い
- 難易度が高く、総務経験者でも狭き門となる希少ポジション
【80】トヨタ自動車(本社総務)
【78】三菱商事(コーポレート統括)
【75】ソニーグループ(ガバナンス強化部門)
SSランクは株主総会運営やコンプライアンス体制の構築など、企業の根幹に関わる高度な総務業務を担当する。
企業規模が大きいため扱う範囲も複雑で、法務・財務・経営企画との連携も求められる。
ミスが許されない業務が多く、専門知識と高い調整能力が必須となる。
責任は大きいが、企業価値を支える中枢として経験価値は非常に高い。
【総務】Sランク(就職偏差値70〜74)
総務の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、総務の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ総務の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手企業の本社で社内制度構築・規程管理・リスクマネジメント等を担当
- 会社全体の運営管理に関わるため視野の広さが求められる
- 法務・労務・情報システムとの連携が多く、統合力が必要
- 教育体制が充実し、専門性を高めやすい環境が整っている
【74】NTTグループ(総務企画)
【72】三井住友銀行(総務部門)
【70】パナソニック(規程管理・リスク統括)
Sランクは企業運営の中枢を支えるポジションで、制度設計やリスク管理など専門性を高められる環境が魅力である。
規模が大きいため担当領域は細分化され、専門スキルを深めやすい。
社内外との調整も多く、ビジネススキル全般が鍛えられる。
安定した企業で長くキャリアを積みたい学生に人気が高い。
【総務】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 中堅企業で総務全般(設備管理・規程整備・社内イベントなど)を担当
- 幅広い業務に関わるためゼネラリストとして成長しやすい
- 社内の相談窓口としてコミュニケーションが重要な役割を果たす
- 業務改善の裁量が大きく、提案力が評価されやすい
【69】中堅メーカー(総務総合職)
【67】IT企業(ファシリティ管理・制度整備)
【65】医療法人の総務部(運営管理)
Aランクは幅広い総務業務を経験できるため、ゼネラリストとして力をつけたい学生に向いている。
施設管理から社内制度改善まで担当範囲が広く、実務を通して総務の基礎を学びやすい。
中堅企業は業務の変化も大きいが、改善提案を行いやすいメリットがある。
実務経験を積みながら総務としてキャリアの軸をつくることができる。
【総務】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 備品管理・来客対応・安全管理など日常運営業務が中心
- 未経験でも挑戦しやすく、基本的な総務スキルを身につけられる
- 小規模企業の場合はバックオフィス全体をサポートすることもある
- 正確性と気配りが評価につながりやすい領域
【64】中小企業(総務アシスタント)
【62】ベンチャー企業のバックオフィス
【60】事務系総務(未経験可)
Bランクは日常運営業務が中心で、初めて総務に挑戦する学生でも入りやすい層である。
備品管理や安全管理など、企業運営に欠かせない基礎業務を経験できる。
職場によっては人事・労務・経理の補助も兼務することがある。
総務の基礎を身につけながらキャリアの方向性を探したい学生に適している。
【総務】Cランク(就職偏差値55〜59)
- 書類整理・郵便対応・電話受付など補助的な業務が中心
- 事務未経験者でも採用されやすい
- 専門性よりも丁寧な対応やサポート力が重視される
- 総務職としての基礎に触れたい学生に向いている
【59】総務事務(補助メイン)
【57】バックオフィス事務
【55】電話・来客対応中心のオフィスサポート
Cランクは事務サポート業務が中心で、専門性が必要なく働きやすい。
総務の基礎に触れながらも負荷が少ないため、事務職デビューに適している。
幅広いサポート業務を担当するためマルチタスク力が鍛えられる。
将来的に総務としてキャリアを広げたい場合は経験を積みながら上位を目指すことも可能である。
【総務】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 簡単な事務作業・清掃管理・受付案内など業務負荷が低い
- 専門知識を必要とせず、採用ハードルは低め
- ルーティン業務が多く安定した働き方が可能
- キャリアアップや専門性強化は限定的となる
【54】オフィス受付
【52】庶務スタッフ
【50】簡易事務(総務補助)
Dランクはルーティンが中心で総務の専門スキルは求められないが、安定して働きやすい職場が多い。
事務経験が浅い学生でも挑戦しやすい環境である。
一方で、総務スキルを大きく伸ばすには物足りない可能性がある。
働きやすさ重視で、まずは事務スキルをつけたい学生に適した領域である。
総務の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
総務職はどの業界にも存在する「普遍的な職種」ですが、その難易度や求められる役割は業界の特性によって大きく異なってきます。
例えば、金融業界やインフラ業界といった規制が厳しく公共性の高い業界の総務は、コンプライアンスやリスク管理の重要性が増し、その分採用のハードルが高くなる傾向にあります。
一方で、ITやベンチャー業界では、急速な成長に伴う組織改編や新たな制度設計が頻繁に発生するため、柔軟性やスピード感、そして制度をイチから作り上げる企画力が求められます。
単に「総務」として一括りにするのではなく、志望業界の特性を理解することで、あなたが持つ強みが活かせる企業を見つけやすくなります。
ここでは、特に就職偏差値の傾向が顕著に現れる主要な業界について、総務職の特徴と求められる資質を具体的に解説していきます。
業界ごとの違いを把握することは、志望動機や自己PRを具体的にする上で非常に重要なステップです。
財閥系・大手金融・インフラ系企業の総務
財閥系や大手金融機関、社会インフラを支える企業の総務職は、一般的に最上位の就職偏差値を示すことが多く、その理由は「ガバナンスとリスク管理の重要性」にあります。
これらの業界は、社会に対する影響力が非常に大きく、不祥事やシステムトラブル一つが社会問題に発展するリスクを常に抱えています。
そのため、総務部門は、株主総会の円滑な運営、法務・コンプライアンス体制の厳格な構築、そして大規模な社内規程の整備といった、企業の土台を守る高度な業務を担当します。
新卒に求められるのは、正確性に極めて優れ、論理的な思考力を持ち、重い責任を担う覚悟があることです。
教育体制は手厚い一方で、求められるプレッシャーや専門性は高いため、狭き門となります。
「日本経済を支える安定した環境で、企業の根幹に関わる重要な仕事がしたい」という学生にとっては、非常に魅力的な選択肢です。
大手メーカー・総合商社の総務
大手メーカーや総合商社の総務職も高い偏差値帯に位置しますが、前述の金融・インフラ系とはやや傾向が異なります。
メーカーの場合、大規模な工場や研究施設のファシリティ管理、海外拠点を含めたグループ会社間の規程統一など、物理的な資産管理やグローバルな調整能力が求められるのが特徴です。
一方、総合商社は、国内外の様々な事業投資やプロジェクトに関わるため、多岐にわたる契約やリスクの調整、そしてフットワークの軽さが求められます。
新卒には、スケールの大きなプロジェクトを支える調整力や、部門を超えたコミュニケーション能力が重視されます。
特に海外事業が多い企業では、国際的な法規制や慣習を理解する姿勢も重要です。
「ダイナミックな事業展開をバックオフィスから支えたい」「グローバルな環境で専門性を磨きたい」と考える学生に適しています。
IT・Web・ベンチャー企業の総務
IT企業や急成長中のベンチャー企業の総務は、他の伝統的な大手企業と比較すると、平均的な就職偏差値はばらつきが大きいものの、「柔軟性とスピード感」が最も重視される傾向にあります。
組織の拡大や事業の変化が非常に速いため、総務部門は固定的なルーティン業務よりも、新しいオフィス環境の設計、評価制度や就業規則の迅速な改訂、M&Aに伴う統合業務など、変化に対応するための企画・設計業務が中心となります。
新卒であっても、積極的に業務改善の提案や、新しい制度の導入を任される裁量が大きいことが魅力です。
求められるのは、前例にとらわれず、自ら課題を発見し、解決策を実行に移せる主体性です。
「成長企業と共に自分も成長したい」「自分の提案で会社をより良くしたい」という意欲的な学生に最適な環境と言えるでしょう。
医療・福祉・教育系法人の総務
医療法人や学校法人といった非営利組織の総務は、一般企業とは異なる特有の難しさがあります。
就職偏差値は比較的安定した中間層に位置することが多いですが、法令遵守(コンプライアンス)が非常に重要です。
病院運営や学校運営には特有の法令や監督官庁の指導が存在し、それらに則った施設管理や人事労務管理が求められます。
また、営利を目的としないため、利用者や地域社会への貢献という視点が常に業務に付随します。
新卒に求められるのは、専門的な知識を学ぶ意欲と、組織の理念に共感し、地道な業務にも真摯に取り組む姿勢です。
「人の生活や教育に貢献できる仕事がしたい」「安定した環境で社会的な意義を感じたい」という学生にとって、やりがいのある選択肢となります。
総務の就職偏差値が高い理由
総務職は一見すると「事務作業」が中心と思われがちですが、高偏差値企業における総務は、企業の「守り」と「土台」を担う、極めて戦略的かつ専門性の高いポジションであるため、採用難易度が高くなっています。
多くの就活生が営業や企画といった「攻め」の職種に目を向けがちな中で、総務の重要性を理解し、その役割を担える人材は限られています。
特に、大手企業になるほど、総務が扱うリスクの規模や、関わる法律・規制の複雑さが増すため、新卒採用においても高い資質が求められるのです。
ここでは、なぜ総務職、特に高偏差値企業の総務の難易度が高いのか、その具体的な理由を掘り下げていきましょう。
これらの理由を知ることで、あなたが総務職を志望する際に、どのようなポイントをアピールすべきかが明確になります。
経営層と現場をつなぐ「調整力・企画力」が求められる
高偏差値企業の総務は、単なる事務処理係ではなく、経営戦略を実行するための「企画部門」としての側面を持っています。
例えば、新しい働き方(テレワークなど)を導入する際、総務は単に備品を手配するだけでなく、経営層の意向を踏まえつつ、現場の意見を聞き、法的な問題やセキュリティ対策をクリアするための複雑な制度設計を行います。
この過程で、経営陣を納得させる論理的な企画書作成能力と、全社員を巻き込む高いコミュニケーション能力・調整力が必須となります。
つまり、「会社の未来を制度から設計する能力」が求められるため、その採用ハードルは自然と高くなるのです。
「企業ガバナンス」と「コンプライアンス」の要である
特にSS・Sランクの大手企業では、総務は企業ガバナンス(企業統治)とコンプライアンス(法令遵守)の最前線に立ちます。
具体的には、株主総会の運営を通じて資本市場との信頼関係を維持したり、社内規程を整備して従業員の不正を防いだりする役割を担います。
これらの業務は、企業の信用や存続そのものに関わるため、ミスは絶対に許されません。
求められるのは、高い倫理観と、法務や財務会計に関する専門知識をスピーディに習得できる学習意欲です。
このような専門性と責任の重さから、採用選考では学生の地頭の良さや真面目さ、安定性が厳しくチェックされるため、偏差値が高くなります。
企業の顔となる「ホスピタリティと危機管理能力」
総務職は、来客対応、電話対応、社内イベントの企画など、社外や社内の人々と接する機会が非常に多く、「企業の顔」として見られます。
そのため、ただ丁寧なだけでなく、相手のニーズを先読みして行動できる高いホスピタリティ(もてなしの心)が必須です。
また、地震や火災といった緊急事態が発生した際には、全社員の安全を確保するための危機管理マニュアルを策定し、実行する冷静な判断力とリーダーシップも求められます。
「平時の円滑な運営能力」と「有事の際のリスク対応能力」という両極端のスキルセットが求められる点も、総務職の難易度を高めている大きな要因です。
専門分野が多岐にわたり「ゼネラリスト的専門性」が必須
総務の仕事は、「庶務」「ファシリティマネジメント(設備管理)」「法務・コンプライアンス」「社内広報」「契約管理」など、多岐にわたります。
高偏差値企業では、これらの分野で高い専門性を求められつつも、部門を超えて連携し、全体最適を図る「ゼネラリスト的な視点」も同時に要求されます。
例えば、新しいオフィスの契約(法務)と、内装設計(ファシリティ)、そして引っ越しに伴う社内への周知(広報)をすべてリードする必要があります。
幅広い知識と経験を統合し、プロジェクトを完遂する能力を持つ人材は非常に希少であるため、必然的に就職偏差値は高水準となるのです。
総務の高偏差値企業に内定するための対策
総務の高偏差値企業に内定するためには、「なんとなく事務がやりたい」という曖昧な志望動機では太刀打ちできません。
求められるのは、「企業の土台を支えるプロフェッショナルになる」という強い意志と、それを裏付ける具体的な資質や経験です。
高偏差値の総務職は、採用人数が少ない上に、学歴や地頭の良い学生からの応募が集中するため、競争率が非常に高くなります。
そのため、一般的な選考対策に加えて、総務職ならではの視点を取り入れた戦略的な準備が必要です。
ここでは、総務の高偏差値企業の内定を勝ち取るために、今すぐ取り組むべき具体的な対策を4つのステップでご紹介します。
「総務の専門性」を理解した上で志望動機を構築する
まずは、あなたが志望する企業が位置する偏差値帯の総務が、具体的にどのような業務を担っているかを深く理解しましょう。
SS・Sランクであれば、「株主総会運営」「法務・コンプライアンス」「大規模な危機管理」といった、企業の根幹に関わる業務が中心です。
あなたの志望動機は、「なぜ、その企業の顔となる総務として働きたいのか」「数ある職種の中で、なぜ縁の下の力持ちである総務を通して企業に貢献したいのか」という点に、「企業の安定性や社会的信用を土台から支えたい」という強い想いを込める必要があります。
単なる事務処理能力ではなく、「会社の未来設計に貢献したい」という視点を盛り込むことで、採用担当者に響く志望動機となります。
「縁の下の力持ち」経験をロジカルにアピールする
総務職では、地道な業務を通じて組織をサポートし、大きな成果に貢献した経験が強く評価されます。
サークル活動やアルバイトなどで、「目立たないけれど、組織全体の効率や雰囲気を劇的に改善した」という経験を具体的にアピールしましょう。
例えば、「イベントの集客状況を分析し、受付フローを改善することで、参加者の待ち時間を50%短縮した」といった具合です。
この際、単なる「頑張った話」ではなく、「課題発見→論理的な解決策の立案→実行→成果」というプロセスを明確にし、あなたの「調整力」「正確性」「ホスピタリティ」がどのように活かされたのかを論理的に説明することが重要です。
法務・財務・労務の基礎知識を意識的に学習する
高偏差値の総務職は、入社後に法務や財務会計の知識をスピーディに習得することが求められます。
選考の段階でこれらの専門知識を持っている必要はありませんが、「学習意欲」と「問題解決能力の片鱗」を示すことが内定につながります。
例えば、面接で「総務として最も重要だと思うことは?」と聞かれた際に、「社内制度を構築する上で、労働基準法や個人情報保護法といった関連法規を理解することが不可欠だと考え、現在、〇〇という資格の勉強を通じて基礎を学んでいます」のように回答できると、プロフェッショナルとしての自覚をアピールできます。
日頃からニュースを見て、企業の不祥事や法改正に関する総務の役割について考える習慣をつけましょう。
OB・OG訪問で「仕事のリアルな責任」を体感する
総務職は、部署によって業務内容が大きく異なるため、OB・OG訪問は必須の対策です。
実際に働く社員から、普段の業務でどのようなリスクに直面し、どのような判断を下しているのか、仕事の「リアルな責任の重さ」を聞き出しましょう。
例えば、「株主総会の準備で最も神経を使う点は何か」「社内規程を改定する際、各部門の利害をどのように調整したか」といった具体的な質問をすることで、入社後のイメージを具体化できます。
この訪問を通じて得た「総務のプロとしての視点」を選考の受け答えに反映させることで、他の学生とは一線を画す、深みのある志望者として評価されるでしょう。
総務の就職偏差値に関するよくある質問
就職偏差値ランキングを見て、総務職への興味を深めた一方で、「本当に自分に合っているのか」「キャリアの将来性はどうなのか」といった疑問が湧いてきたのではないでしょうか。
総務職は、企業によって業務の幅が広すぎるがゆえに、抱える疑問も多岐にわたります。
特に、バックオフィスである総務は、営業や企画職に比べて、具体的なキャリアパスが見えにくいと感じるかもしれません。
ここでは、就活生が総務の就職偏差値に関して抱きがちな、代表的な質問をQ&A形式で解説します。
これらの疑問を解消し、あなたの総務職への理解を深めることで、選考に自信を持って臨めるようになるはずです。
Q1. 総務職は「専門性がない」ため、転職が難しいですか?
A. 高偏差値企業での総務経験は、むしろ「高度な専門性」として評価され、転職に有利に働くケースが多いです。
「専門性がない」と言われるのは、C・Dランクのルーティン業務中心の総務を指すことが多く、SS・Sランク企業で経験する「ガバナンス構築」「大規模ファシリティマネジメント」「法務・労務との高度な連携」といった業務は、他社でも通用する市場価値の高いスキルです。
特に、大手企業でのコンプライアンス体制構築経験などは、企業規模を問わず求められるため、同業他社やベンチャー企業の管理部門責任者(CFO/COO候補)といったキャリアパスも開けます。
大切なのは、「備品管理」だけでなく「なぜその備品が必要なのか」という経営視点を常に持ち、経験を言語化することです。
Q2. 文系学生が多いイメージですが、理系でも総務は目指せますか?
A. 理系学生も総務職を十分に目指せますし、むしろ「論理的な思考力」が評価される場面が増えています。
総務の仕事は、社内制度設計や、コスト分析、ファシリティ管理など、データに基づいた論理的な意思決定を必要とすることが多々あります。
理系で培った「仮説構築・検証能力」や、実験データなどを扱う「正確性・緻密さ」は、社内規程の不備や契約書のミスが許されない総務の業務で大きな強みとなります。
面接では、「研究で培った問題解決のプロセスを、社内ルールの最適化に活かしたい」といったように、理系的なアプローチで総務職への意欲を具体的にアピールしましょう。
Q3. 高偏差値企業の総務は激務ではないですか?
A. SS・Sランクの総務は責任が重いため、平時でも繁忙期でも「精神的なプレッシャー」はありますが、激務かどうかは時期や部門によって異なります。
例えば、株主総会前の時期や、大規模な社内制度改定のプロジェクト中は、残業が増える傾向にあります。
しかし、労働環境やコンプライアンスを最も厳格に管理する部署が総務自身であるため、他の職種と比較して「過度な長時間労働」は抑制されていることが多いです。
大切なのは、激務かどうかよりも、「企業の信用を守る」という責任の重さに耐えうるプロ意識があるかです。
業務効率化や働き方改革を推進するのも総務の役割であるため、自部署の働き方にも配慮がなされています。
Q4. B・Cランクの総務からでもキャリアアップは可能ですか?
A. はい、「経験を積んで専門性を深める」ことで、十分なキャリアアップが可能です。
B・Cランクの企業で総務を経験することは、「総務の基礎」である備品管理、庶務、契約書作成の補助といった実務を幅広く経験できるという大きなメリットがあります。
これらの経験は、次にAランク以上の中堅企業へ転職する際に、「即戦力としての実務能力」として評価されます。
キャリアアップの鍵は、日常業務をこなすだけでなく、「簿記や社会保険労務士などの資格取得」を通じて専門知識を身につけ、「なぜこの業務を行うのか」という上位の視点を常に意識することです。
基礎を固めた後、法務や労務などの専門領域に特化することで、より高偏差値の企業への道が開けます。
まとめ
本記事では、新卒就活生に向けて、総務職の就職偏差値ランキングから業界別の傾向、そして高偏差値企業への内定対策までを詳しく解説しました。
総務職は、企業運営の根幹を支える「縁の下の力持ち」であり、特にSS・Sランクの大手企業では、経営層と現場をつなぐ高度な企画力と、コンプライアンスを統括する専門性が求められます。
単なる事務職ではなく、企業の信用と成長を担うプロフェッショナルな職種として、その採用難易度は決して低くありません。
あなたが総務職を目指すのであれば、まずは志望する企業がどの偏差値帯にあり、どのような「総務の顔」を持っているのかを理解することが第一歩です。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート