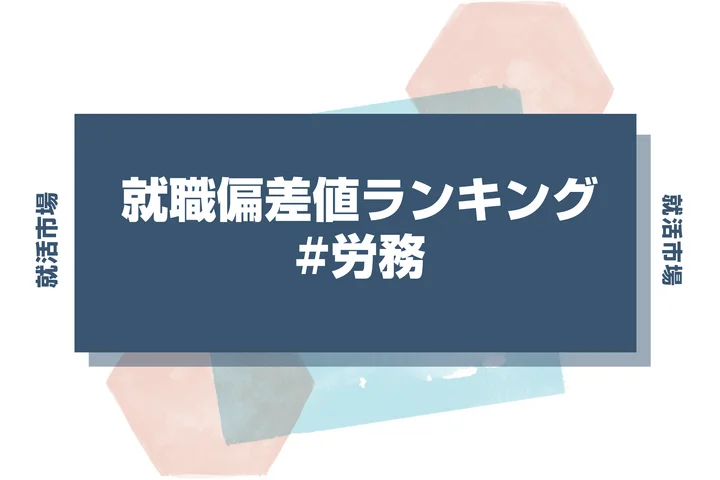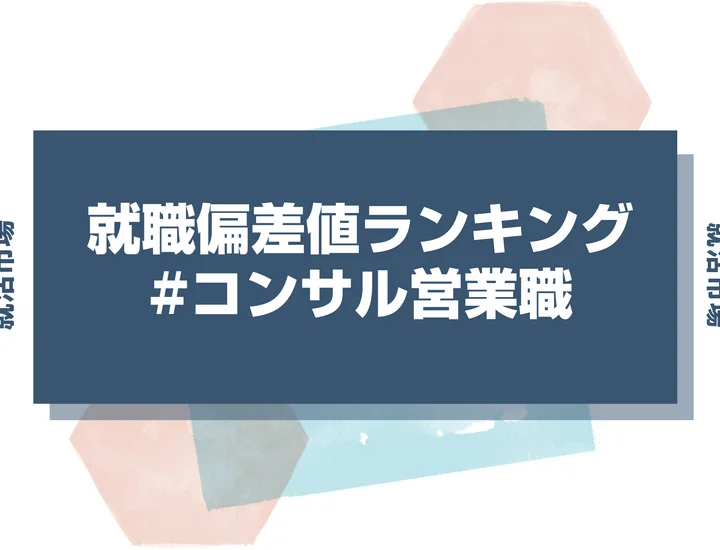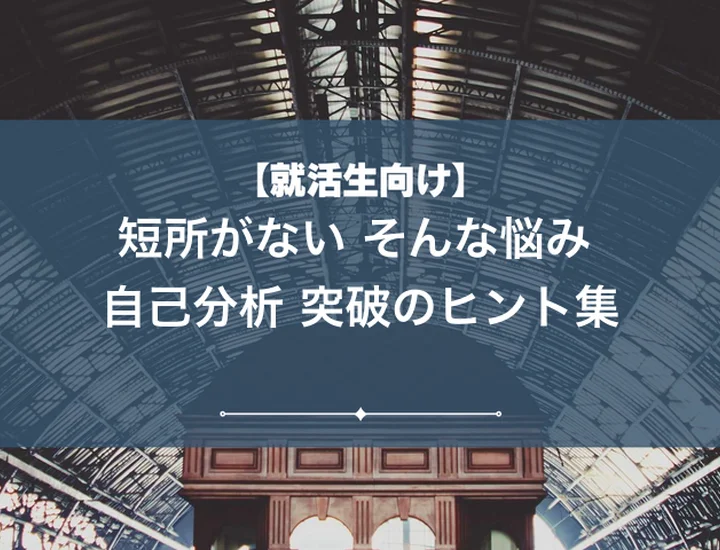目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
労務の就職偏差値ランキング
人事の中でも専門性が高く、新卒から目指す学生も多い労務職。
この労務職の就職偏差値は、企業の規模と担当する業務の専門性によって大きく特徴が分かれます。
大前提として、労務は法律の知識に基づいて従業員の働き方や組織の制度を設計・管理する役割を担うため、正確性と専門性の高さが求められる職種です。
特に、上場企業や大手の労務部門は、その企業規模の大きさから労働法規への対応や人事制度の企画・運用が非常に複雑化し、必然的に採用難易度が上がります。
これが高偏差値企業群を形成する大きな要因です。
具体的には、SSランクは高度な法務知識と全社的な制度設計能力が求められる超難関の専門職、Sランクは労務管理の中核を担う専門性の高いポジション、そしてB〜Dランクは労務の基礎的な業務やサポートからスタートできる門戸が広いポジションと分類できます。
企業の知名度だけでなく、業務の深さと幅が偏差値に反映されているため、ランキングを見る際は「どのレベルの労務スキルを身につけたいか」という視点を持つことが重要です。
【労務】SSランク(就職偏差値75以上)
- 上場企業の労務部門で、労働法対応・働き方改革・全社制度の設計を担う
- 人事制度や就業規則、労使交渉など高度な法務知識が必要
- 従業員数が多く複雑な労務問題が発生しやすい
- 経験者採用が多く、新卒で入るのは極めて難しい
【80】大手メーカー(上場企業の労務部)
【78】大手IT・通信(人事労務企画)
【75】大手金融グループ(労務統括)
SSランクは法務と人事の中間に位置する高度専門職で、労働法の深い知識と制度設計力が求められる。
従業員数が数千名規模になるため、複雑な労務課題への対応力が必要となる。
正確性・専門性・リスク管理能力が重視され、新卒枠はごくわずかである。
将来労務スペシャリストとしてキャリア形成したい学生に人気の領域である。
【労務】Sランク(就職偏差値70〜74)
労務の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、労務の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ労務の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手企業の人事部で、社会保険・勤怠管理・給与計算の中核業務を担当
- 法改正対応や働き方制度の運用など高度な専門性が要求される
- 社内調整や従業員対応が多く、コミュニケーション力も重視される
- 教育体制が整っており、専門職として成長しやすい
【74】大手インフラ(人事労務)
【72】大手製造業(労務管理)
【70】大手サービス業(人事制度運用)
Sランクは大企業で労務管理の中核を担い、専門性と正確性が高く評価される領域である。
労基法・社保法を理解した上で制度を運用するため、法的視点が不可欠となる。
従業員からの問い合わせ対応も多いため、説明力や調整力が必要である。
労務分野で専門スキルを高めたい学生に向いている。
【労務】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 中堅企業で労務全般を担当し、幅広い専門スキルが身につく
- 勤怠・給与・社保・安全衛生など複数領域を経験できる
- 法令対応も求められ、実践的な労務知識が身に付く
- 業務範囲が広いため、自走できる人材が評価されやすい
【69】中堅メーカー(労務総務)
【67】IT企業(勤怠・給与担当)
【65】物流・サービス業(社保・安全衛生)
Aランクは労務実務の幅が広く、経験を積むほど市場価値が高まる成長型の環境が特徴である。
給与計算や社保手続きなど正確さが求められるが、実務経験が積みやすい。
労務と総務を兼任するケースも多く、実務で鍛えられる環境が多い。
専門性を身につけながらキャリアアップしたい学生に向いている。
【労務】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 中小企業で労務・総務・経理などバックオフィスを兼任することが多い
- 入退社手続き、給与データの入力、勤怠チェックが中心
- 専門性よりも正確性とコミュニケーションが重視される
- 未経験でも挑戦しやすい採用枠が多い
【64】中小企業の人事労務
【62】スタートアップ(バックオフィス兼任)
【60】サービス企業(勤怠・給与サポート)
Bランクはバックオフィス全体に関わり、労務の基礎を実務で学べる点が魅力である。
未経験でも挑戦しやすく、まずは労務の入口として経験を積める。
企業規模が小さいほど業務範囲が広がるため柔軟性が求められる。
実務を通して専門性を育てたい学生に向いている。
【労務】Cランク(就職偏差値55〜59)
- 労務アシスタントとして書類作成やデータ入力が中心
- 勤怠集計や社保書類の準備など補助業務を担当
- 専門知識は不要で、未経験から挑戦しやすい
- 正確な事務処理能力が評価されるポジション
【59】労務アシスタント(大手グループ)
【57】中小企業の労務事務
【55】スタートアップの人事サポート
Cランクは補助業務中心のため負荷は高くなく、未経験から労務を学ぶスタート地点として最適である。
給与計算や勤怠管理の流れを実務で理解できる。
正確性とルール遵守が求められるため、几帳面な人が活躍しやすい。
まずは労務に触れたい学生に向いたポジションである。
【労務】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 書類提出・データ整理・ファイリングなど事務中心の職務
- 専門知識は不要で、新卒や未経験者が採用されやすい
- 責任範囲は狭く、サポート業務が中心
- キャリアアップには追加の勉強が必要となる
【54】労務事務補助
【52】バックオフィスサポート
【50】書類管理・入力中心の事務スタッフ
Dランクは補助業務が中心で、専門的な労務スキルを求めない働きやすいポジションである。
給与計算や勤怠管理は担当しないことが多くプレッシャーは少ない。
キャリアアップには簿記や社労士知識などの追加学習が必要となる。
まずはバックオフィスを経験したい学生に向いている。
労務の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
労務職は、業種に関わらずすべての企業で必要不可欠な機能ですが、その就職偏差値の傾向は業界によって明確な違いが見られます。
これは、業界の特性、企業規模、そして労働環境の複雑さが、労務が扱うリスクや専門性のレベルに直結するためです。
例えば、金融やメーカーのような伝統的な大企業は、歴史が長く従業員数が多いため、複雑な人事制度や労使関係が存在し、高度な専門性が求められます。
一方で、ITやスタートアップのような成長産業は、新しい働き方を推進するため、法改正や柔軟な制度設計への対応力が重視されます。
このように、業界特有の事情を理解することで、あなたが目指す労務像に合った企業を見つけやすくなります。
ランキングで高い偏差値を示す企業群には、その業界を代表する大手が多く含まれており、新卒の採用枠は非常に狭き門となりますが、得られる専門知識やキャリアの可能性は非常に大きいと言えるでしょう。
大手金融・メーカー・インフラ系の傾向
大手金融、伝統的なメーカー、そしてインフラ系の企業は、労務の就職偏差値が非常に高い水準にあります。
これらの企業は歴史が長く、労働組合が存在するケースも多く、就業規則や人事制度が複雑で多岐にわたります。
そのため、労務部門には高度な労働法規に関する知識と、労使間の交渉や調整を円滑に進めるコミュニケーション能力が求められます。
特に、数万人規模の従業員を抱える企業では、給与計算や社会保険手続きだけでも莫大な業務量となり、法改正への対応も全社に大きな影響を与えるため、ミスが許されない正確性が最重要視されます。
新卒採用においても、企業への理解度の深さや、論理的思考力、そして安定して業務を遂行できる誠実さが評価されやすく、倍率も非常に高くなる傾向にあります。
大手IT・通信・サービス業の傾向
IT・通信業界や大手サービス業の労務職も、近年非常に高い人気と偏差値を誇っています。
これらの業界は、フレックスタイム制度、リモートワーク、副業解禁など、新しい働き方を積極的に導入する傾向が強く、その制度設計と運用を担う労務職の役割が非常に重要になります。
特に、技術の進展や市場の変化が速いため、柔軟で迅速な対応能力が求められます。
従来の労務知識に加え、新しい労働環境におけるリスクマネジメント能力や、従業員のエンゲージメントを高めるための制度提案力が評価されるポイントです。
労務の専門知識を持ちつつ、変化を恐れず新しい制度を導入・運用できる企画力や実行力を持つ学生が求められるため、単に法律に詳しいだけでなく、企業文化を理解し、事業成長に貢献できる視点を持つことが重要です。
中小・ベンチャー企業(成長企業)の傾向
中小企業や急成長中のベンチャー企業における労務職は、偏差値の幅が広くなりますが、実務の幅広さが特徴です。
大手企業のように分業制が進んでいないことが多く、労務・総務・人事の業務を兼任するケースが一般的です。
給与計算、社会保険手続きはもちろん、オフィス管理や備品発注など、バックオフィス全般を担うことも少なくありません。
この環境は、短期間で幅広い労務実務を経験できるという大きなメリットがあります。
専門的な深い知識よりも、まずは正確な事務処理能力と、目の前の課題を解決する自走力が重視されます。
将来的に社会保険労務士などの専門資格を目指す学生にとっては、実務経験を積みやすい環境であり、企業とともに成長したいという意欲を持つ学生に向いていると言えます。
医療・福祉・教育分野の傾向
医療・福祉、そして教育分野の労務職は、その事業の公共性から安定志向の学生に人気があり、一定の偏差値があります。
これらの業界は、労働時間が不規則であったり、専門職の雇用管理が必要であったりと、業界特有の労務課題を抱えていることが特徴です。
特に、シフト制勤務や複雑な勤務形態への対応が必須となるため、勤怠管理や給与計算の正確性が非常に重要になります。
また、法改正の影響を直接受けやすいため、最新の法令に常にアンテナを張り、組織を動かす法令遵守の意識が強く求められます。
この分野の労務を目指す場合は、業界特有の労働環境を理解し、従業員が安心して働ける環境を整備することに強い使命感を持てるかが評価のポイントとなります。
労務の就職偏差値が高い理由
労務職の就職偏差値が高い背景には、その職務の重要性と求められるスキルセットの特殊性があります。
新卒の就職活動において、単なる一般事務職とは一線を画す専門性の高いポジションとして認識されており、人気と難易度が年々上昇しています。
労務は企業の「人」に関わる根幹の業務であり、そのミスや判断の誤りが企業の信用や経営に直結するリスクを孕んでいます。
この重大な責任を新卒に任せるにあたり、企業は高いレベルの資質を求めるため、結果として就職偏差値が高くなるのです。
特に、大企業になるほど、労務問題が与える影響範囲は広大になるため、専門知識とリスクヘッジ能力の両方が必要不可欠となります。
労働法規の専門知識が必要不可欠なため
労務の就職偏差値が高い最大の理由は、労働基準法や社会保険関連法規など、専門的な法令知識が必須となる点にあります。
労務は、単に書類を作成するだけでなく、法改正に応じて就業規則や人事制度を改定し、従業員の働く環境を適法かつ公正に保つ責任があります。
特に、近年は「働き方改革」関連法の施行や、ハラスメント対策の強化など、労働法規の改正が頻繁に行われており、常に最新の知識にアップデートしていく必要があります。
この高度で継続的な学習意欲と、法令を正しく解釈し実務に落とし込む応用力は、一朝一夕で身につくものではないため、選考では入社後の成長ポテンシャルや、専門分野への興味関心の強さが重視されます。
企業のコンプライアンス(法令遵守)に直結するため
労務は企業のコンプライアンス(法令遵守)の要であり、企業の信用や経営の安定性に直結する重要な職務です。
給与の未払い、不適切な労働時間管理、ハラスメント対応の不備などは、企業の信頼を失墜させ、多額の損害賠償や行政指導につながる可能性があります。
高偏差値企業ほど、世間からの注目度が高く、一つの労務リスクが与える影響は計り知れません。
そのため、採用では高い倫理観と、リスクを予見し未然に防ぐ能力が求められます。
単に知識があるだけでなく、「なぜこのルールがあるのか」「この判断が会社にどのような影響を与えるか」を深く考えられる責任感と判断力を持つ学生が評価されるため、選考の難易度が高くなっています。
社内の多様な関係者との調整力が求められるため
労務職は、経営層、人事部門、各現場の部署長、そして一般の従業員といった社内の多様なステークホルダーと関わりを持ちます。
例えば、新しい人事制度を導入する際や、勤怠ルールの変更を行う際には、経営層の意向、現場の業務実態、そして従業員の感情など、様々な要素を考慮した調整が必要です。
特に、従業員にとって不利益になる変更を伝える場合や、労使間の意見対立を調整する場面では、高いコミュニケーション能力と公平性を保つ姿勢が求められます。
利害関係の異なる人々の意見を聞き、法律に基づきながらも納得感のある落としどころを見つけ出す高い折衝能力が評価されるため、単純な事務処理能力だけでは内定を獲得することは難しいと言えます。
企業の規模が大きく、専門性と業務量が多いため
一般的に、企業の規模が大きくなるほど、労務職の専門性が高まり、業務量が膨大になります。
数千人、数万人規模の従業員を抱える大企業では、一人ひとりの給与計算や社会保険手続きが複雑化するだけでなく、部門ごとに異なる労働時間制度や、海外赴任者の労務管理など、多岐にわたる専門的な業務が発生します。
また、分業が進んでいるため、自分が担当する分野(例:給与計算専任、社会保険専任)においては極めて深い知識が求められます。
この高い専門性と、正確性が求められる膨大な業務量に対応できる処理能力と粘り強さが新卒に期待されるため、高偏差値企業への就職は難関となります。
労務の高偏差値企業に内定するための対策
労務の高偏差値企業に内定するためには、単なる企業の人気に流されるのではなく、専門職としての適性を戦略的にアピールする必要があります。
労務職が求めるのは、正確性、専門性、そして高い倫理観を持った人材です。
そのため、ES(エントリーシート)や面接では、これらを裏付ける具体的な行動や経験を論理的に伝えることが内定への鍵となります。
特に、高偏差値企業は新卒の採用枠が非常に少ないため、周りの就活生との差別化を図り、入社への強い意欲を専門的な視点から示すことが重要です。
今からできる対策を一つひとつ実行し、あなたのポテンシャルを最大限に引き出す準備をしましょう。
労働法や社会保険に関する知識を身につける
高偏差値の労務職に内定するためには、「労務に対する熱意」を具体的な知識で示すことが最も重要です。
学生時代から労働基準法や社会保険の基礎知識を自主的に学習し、その知識を選考でアピールしましょう。
例えば、社会保険労務士試験の勉強を始める、簿記検定を取得して給与計算の基礎となる会計知識を身につけるなどが有効です。
面接で「なぜ労務を志望するのか」と聞かれた際に、「法律に基づいて従業員の働く権利を守ることに使命を感じている」「最近の法改正(例:同一労働同一賃金)について自分なりに調べている」といった具体的な回答ができるだけで、他の学生との専門性の差を明確に示すことができます。
正確な事務処理能力と地道な努力をアピールする
労務職は、給与計算や勤怠管理など、一切のミスが許されない正確な事務処理能力が求められます。
そのため、ESや面接では、あなたが「正確性」と「地道な努力」を重視し、それを実現できる人物であることを具体的にアピールしてください。
「大学のサークルで経理を担当し、1円のミスもなく予算管理をやり遂げた」「アルバイトでレジ締めを任され、毎日ダブルチェックの仕組みを自分で作って徹底していた」といった、ミスを防ぐための工夫や粘り強く一つのことに取り組んだ経験を伝えるのが効果的です。
特に、几帳面さやルールを厳守する姿勢は、この職種で非常に高く評価されるポイントです。
企業特有の労務課題に対する解決策を提示する
内定を勝ち取るためには、企業への深い理解を示し、「入社後に貢献できるイメージ」を持たせることが不可欠です。
まずは志望企業が属する業界の特有の労働課題を徹底的にリサーチしましょう。
例えば、IT企業であれば「エンジニアの長時間労働対策」、メーカーであれば「製造現場の変形労働時間制の運用」などです。
その上で、「貴社のAという課題に対し、私は大学で学んだBという視点から、Cのような制度設計のアイデアを持っています」というように、課題に対する自分なりの具体的な解決策を選考で提案してみてください。
これにより、単なる志望ではなく、専門職としての視点を持っていることを証明でき、高い評価を得ることができます。
誠実性と高い倫理観をエピソードで伝える
労務職は、従業員の機密情報(給与、病歴など)を扱い、公平な判断を下す必要があるため、誠実性と高い倫理観が必須です。
面接では、この人柄の部分を深く見られます。
「友人の秘密を絶対に守り通した経験」「ルールが不明確な状況で、敢えてルールに則って行動した経験」など、あなたが倫理的に正しい行動を選んだエピソードを具体的に伝えてください。
信頼できる人物であること、そして公私を混同せず、プロフェッショナルとして職務を遂行できることが伝われば、高偏差値企業が求める最も重要な要素の一つをクリアしたことになります。
労務の就職偏差値に関するよくある質問
労務職は、学生にとっては業務内容がイメージしにくい部分も多く、就職活動において多くの疑問が生じやすい職種です。
特に高偏差値企業を目指す学生からは、「資格は必須か」「法学部以外でも目指せるのか」といった質問が頻繁に寄せられます。
これらの疑問を解消することは、志望動機を固め、選考対策を具体化する上で非常に重要です。
ここでは、労務の就職偏差値やキャリアに関する、新卒就活生が抱きやすい疑問について、専門的な視点から具体的かつ実践的な回答を提供します。
疑問を解消し、不安なく就職活動を進めていきましょう。
労務職に就くために社会保険労務士などの資格は必須ですか?
結論から言うと、新卒の就職活動において社会保険労務士(社労士)などの資格は必須ではありませんが、持っていると強力なアピール材料になります。
高偏差値企業が新卒に求めているのは、資格そのものよりも「専門分野への強い関心」と「継続的な学習意欲」です。
もし社労士の資格を持っていなくても、「資格取得に向けて勉強中であること」や、「大学で労働法ゼミに所属している」といった具体的な学習実績を伝えられれば、十分に高い評価につながります。
「資格は入社後、実務経験を積みながら取得したい」というキャリアプランを明確に伝えることで、学習意欲と計画性をアピールすることが、内定獲得の鍵となります。
法学部出身でなくても労務職を目指せますか?
法学部出身でなくても、問題なく労務職を目指せます。
実際、経済学部、経営学部、さらには文学部など、様々なバックグラウンドを持つ人が労務職として活躍しています。
もちろん、法学部で労働法を学んでいることは有利に働きますが、企業が労務職に求めているのは、「法律の知識」だけでなく、「論理的思考力」「正確な処理能力」「高いコミュニケーション能力」です。
例えば、経済学部出身であれば「定量的なデータ分析能力」、文学部出身であれば「高度な文章作成能力や傾聴力」など、自分の学部の特性を労務業務にどう活かせるかを明確に説明できれば、十分に戦えます。
入社後の学習意欲を伝え、多様な視点から労務課題に取り組める人材であることをアピールしましょう。
労務職のキャリアパスはどのように描けますか?
労務職は、非常に明確で専門性の高いキャリアパスを描くことができます。
キャリアの出発点として、勤怠管理や給与計算などの実務を経験し、その後は大きく2つの方向性があります。
一つは、「労務スペシャリスト」として、労働法や社会保険の深い知識を武器に、高度な制度設計や労使交渉を担う専門家としてキャリアを積む道です。
もう一つは、労務の知識を活かしつつ、採用や育成なども含めた「人事のジェネラリスト・マネージャー」として、人事部門全体を統括する管理職を目指す道です。
高偏差値企業では、将来的に経営層に近いポジションで、企業の働き方を根幹から変える「戦略人事」の役割を担うことも可能です。
キャリアパスを具体的に面接で語ることで、長期的なキャリア志向をアピールできます。
労務職は激務になりやすいのでしょうか?
一般的に、労務職は繁忙期と閑散期の差が大きい職種です。
特に、年末調整、社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新といった法定期限のある手続きがある時期は、業務量が大幅に増加し、一時的に残業が増える傾向があります。
しかし、これはどの企業の労務職でも共通する特性であり、高偏差値の大手企業ほど、コンプライアンス意識が高く、従業員の労働時間管理が厳格なため、極端な激務は避けられる傾向にあります。
むしろ、中小企業やスタートアップで労務を一人で担当している場合の方が、業務範囲の広さから恒常的に業務過多になりやすいケースが見られます。
面接で「繁忙期の業務の乗り越え方」について具体的に質問し、企業側の残業対策を確認してみると良いでしょう。
まとめ
労務職の就職偏差値は、企業の規模、業界特性、そして求められる専門知識のレベルによって明確に分かれており、高偏差値企業ほど労働法規の深い知識と、高いコンプライアンス意識が要求されます。
SSランクやSランクの企業は、企業の根幹を支える高度専門職としての採用であり、新卒で内定を得るためには、社会保険労務士の勉強などの具体的な学習実績と、正確性を証明する経験を戦略的にアピールする必要があります。
法学部出身でなくても、論理的思考力や誠実性といった汎用的なスキルを労務にどう活かすかを明確に伝え、企業特有の課題に対する自分なりの解決策を提示することが、他の就活生との差別化につながります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート