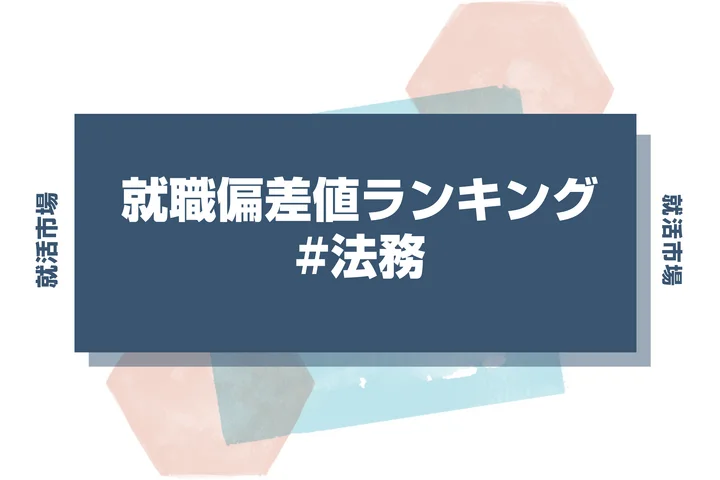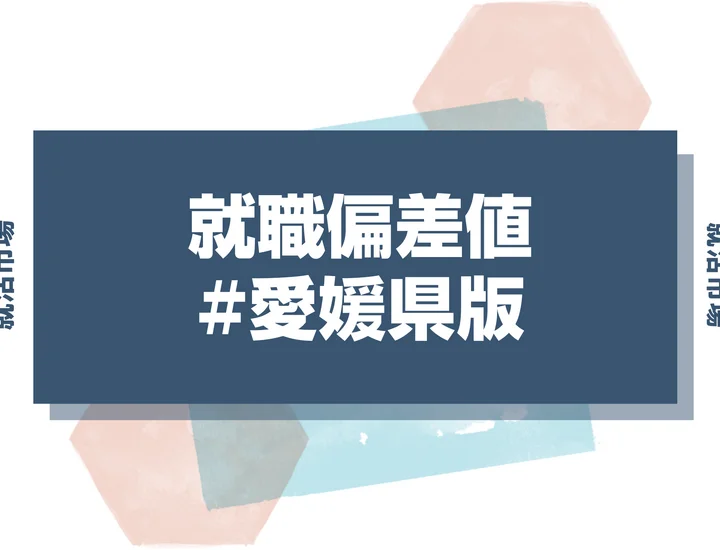目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
法務の就職偏差値ランキング
企業の法務部門は、その企業の法的リスク管理やコンプライアンス体制を担う、極めて重要な役割を果たしています。
このため、一般的に法務職の就職偏差値は、専門性の高さと企業の規模に強く関連しているのが特徴です。
特に大手企業や国際的な事業を展開する企業では、高度な法律知識や英語力、そして複雑な事案を論理的に処理する能力が求められるため、採用難易度が非常に高くなります。
ランキング上位になるほど、契約書レビューや国際法務、M&Aといった企業の根幹に関わる業務に深く携わることになり、新卒で採用される学生には、即戦力となる高いポテンシャルや、入社後の学習意欲が期待されます。
逆に偏差値が下がるにつれて、業務は契約書のひな形管理や法務事務といったサポート的な役割が中心となりますが、これらも法務キャリアの基礎を築く上で欠かせない貴重な経験となります。
就職偏差値ランキングは、あなたが目指すべき法務キャリアのレベルと、必要なスキルセットを把握する上で非常に有効な羅針盤となるでしょう。
【法務】SSランク(就職偏差値75以上)
- 上場企業・外資企業の法務部で、高度な契約管理や国際法務を担当
- M&A、組織再編、ガバナンス構築など専門性が非常に高い
- 英語力・契約レビュー力・論理思考が必須で難易度が高い
- 事業部からの相談が絶えず、スピードと正確性が求められる
【80】外資系テック企業(国際法務)
【78】大手総合商社の法務部
【75】プライム上場企業の法務・ガバナンス部門
SSランクは企業の重要な意思決定に深く関わるため、契約法務だけでなくガバナンスやM&Aまで幅広く担当する点が特徴である。
複雑な契約書の作成・レビューが多く、法的リスクを最小化するための分析力が求められる。
また外資企業では英語契約の対応が必須となり、スキルのハードルは非常に高い。
専門性と責任が大きい分、キャリア価値は極めて高く、法務のエリート層が目指すゾーンとなる。
トップレベルの法務スキルを身につけ、企業経営をリーガル面から支えたいという強い意欲を持つ学生にとって、最難関の挑戦となるでしょう。
【法務】Sランク(就職偏差値70〜74)
法務の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、法務の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ法務の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手企業の法務部で、契約レビューやコンプライアンス業務を担当
- 契約書管理・知財・内部統制など幅広い分野を経験できる
- 研修体制が整っており、新卒でも成長しやすい
- 部門として成熟しており、専門家のもとで法務スキルを磨ける
【74】大手メーカーの法務部
【72】大手IT・通信企業の法務領域
【70】大手金融機関のコンプライアンス部
Sランクは契約法務を中心に専門性を高めながら、企業に必要な幅広いリーガル領域を学べる環境が整っている。
業務は専門的だが、チーム体制が確立されているため新卒でも挑戦しやすい。
また内部統制や個人情報保護など、ガバナンス全体に触れられる機会も多い。
安定した環境で法務として確かな基盤を築きたい学生に適したゾーンである。
大手企業ならではの充実した研修制度と、専門家からの指導を受けられるため、新卒から法務のプロフェッショナルを目指すには最適な環境と言えます。
高い専門性を着実に身につけたいと考える学生が、このランクの企業を志望する傾向にあります。
【法務】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 中堅企業の法務部門で、契約書作成・法務相談が中心
- 法令調査や社内規程の整備など、実務中心の業務が多い
- 上場準備企業では内部統制やガバナンス構築にも携われる
- 専門性と働きやすさのバランスが良い
【69】中堅メーカーの契約法務
【67】上場準備中ベンチャーの法務担当
【65】IT企業の法務・規程管理チーム
Aランクは中堅規模の企業で、契約・規程管理・リーガルチェックなど実務を主体に法務スキルを磨ける点が特徴である。
配属後すぐ実務に触れる機会が多く、成長スピードは速い。
担当領域は広くなるが、その分スキルの幅も広がるため若手のキャリア形成に適している。
安定しつつ専門性を高めたい学生に選ばれやすいゾーンとなる。
裁量の大きな環境で、自ら主体的に法務業務を推進したい学生にとって、Aランクは非常に魅力的な選択肢です。
特に上場準備中のベンチャー企業などでは、企業の成長フェーズを法務面から支えるという貴重な経験を得ることができます。
【法務】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 小規模企業の法務担当として、契約書のひな形管理や事務作業が中心
- 法的判断よりも運用管理や書類整備がメインになる
- 専門性は低いが、法務の入口として経験を積める
- 社内ルールや規程作成のサポートを担当することが多い
【64】中小企業の法務アシスタント
【62】法律関連書類の管理担当
【60】バックオフィス兼任の法務サポート
Bランクは契約書の管理や行政手続きなど、法務の基礎業務に触れながら専門領域へ進む準備をするゾーンである。
小規模企業では法務専任が少なく、バックオフィス業務と兼務するケースも多い。
専門的な契約レビューは少ないが、実務経験の最初の一歩としては十分な環境である。
まずは法務領域に触れたい学生にとって、現実的で挑戦しやすい選択肢となる。
法務業務の全体像を把握し、基礎的な実務スキルを習得するには適した環境であり、ここでの経験を土台として、将来的なキャリアアップを目指すことが可能です。
【法務】Cランク(就職偏差値55〜59)
- 事務要素が強く、書類整理やデータ管理が中心
- 契約レビューなど専門業務に関わる機会は少なめ
- 企業の法務部門に属しながら、補助的な役割を担う
- 細かい作業や正確性が求められるポジションが多い
【59】契約書管理担当・法務事務
【57】法務関連のデータ入力・書類管理
【55】人事・総務と兼任する法務アシスタント
Cランクは契約書の管理やデータ登録など事務作業が中心で、法務部門のサポート役として経験を積むゾーンである。
専門領域に触れる機会は多くないが、法務のフローや社内規程の運用を理解しやすい。
法律知識よりも正確な作業やコミュニケーションが求められる場面が多い。
事務職から法務に関わる経験を積みたい学生が選びやすい層である。
高い専門性はまだないが、法務業務の近くで働き、知識を吸収したいと考える学生にとっては、第一歩として有効な選択肢となります。
このポジションでは、法務業務における正確性とスピードといった基礎的なビジネススキルを磨くことができます。
【法務】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 法務未経験可の事務ポジションが中心で、サポート業務がメイン
- 法律知識はほぼ不要で、資料作成や庶務作業が中心
- 法務の専門家と連携する場面は少ない
- キャリアアップには積極的な学習が必要
【54】法務庶務・資料作成担当
【52】バックオフィスアシスタント
【50】小企業の事務兼法務サポート
Dランクは専門性よりも事務スキルが中心で、法務領域への入口として位置づけられる。
資料作成や庶務対応が主な業務となり、法的判断や契約レビューに関わることはほとんどない。
一方で、法務に興味がある場合は徐々に業務を広げる余地もある。
まずはバックオフィス領域からキャリアを積みたい学生に選ばれやすいゾーンである。
未経験から法務部門の雰囲気や文化に触れたい学生にとって、Dランクは最もハードルの低い選択肢です。
しかし、将来的に専門性を高めるには、入社後の自主的な法律学習が必須となります。
法務の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
法務職の就職偏差値は、企業規模だけでなく、その企業が属する業界の特性によっても大きく変動します。
なぜなら、業界ごとに適用される法令や抱えるリスク、そして法務部門に求められる専門分野が異なるためです。
例えば、海外展開が活発な業界や、常に新しい技術や規制に直面する業界では、国際法務や知財法、M&Aなどの高度で専門的な知識が求められ、結果として偏差値が高くなる傾向にあります。
逆に、比較的法規制が安定している業界や、事業内容が国内中心の企業では、コンプライアンスや契約管理といった基礎的な法務が中心となり、専門性の高さよりも安定性が重視される傾向が見られます。
このセクションでは、就職偏差値ランキングを分析し、業界別に法務職に求められる具体的なスキルや採用の傾向を解説します。
あなたが興味を持つ業界の法務部門が、どのような特徴を持ち、どのような人材を求めているのかを理解することで、より具体的な就職活動の戦略を立てられるはずです。
金融・保険業界はコンプライアンスへの意識と難易度が高い
金融・保険業界の法務部門は、一般的に就職偏差値が高い傾向にあります。
これは、金融商品取引法や銀行法、保険業法など、厳格かつ専門的な法規制に常に準拠する必要があるためです。
この業界では、一つ一つの取引やサービス提供において、膨大な法規制をクリアしているかを厳しくチェックする「コンプライアンス」が法務の主要な業務となります。
また、顧客情報の取り扱いに関する個人情報保護法への対応も重要です。
そのため、高い専門知識に加え、組織全体の法的なリスクを察知し、未然に防ぐための厳格な論理的思考力が求められます。
新卒採用においても、法律のバックグラウンドはもちろんのこと、高い倫理観と責任感が強く問われるのが特徴です。
大手金融機関の法務やコンプライアンス部門は、SSランクやSランクに位置づけられることが多く、採用難易度は非常に高いと言えます。
IT・通信業界は知財法務や新技術への対応が重要
IT・通信業界における法務職も、近年特に就職偏差値が上昇している分野です。
この業界の特徴は、技術の進化が速く、それに伴い新たな法的な課題が次々と発生する点にあります。
例えば、データ保護、AIの利用、プラットフォームの運営に関する規制、そしてサイバーセキュリティ関連法など、常に新しい法律やガイドラインに対応する必要があります。
特に、自社の技術やサービスを守る知的財産権(知財)法務の重要性が非常に高く、特許や著作権に関する専門知識を持つ人材の需要が高まっています。
また、海外展開が盛んな企業が多いため、国際的な契約法務や現地の法規制に対応できる語学力も求められます。
これらの専門性の高さから、大手IT企業の法務部門はSランク以上に位置することが多く、知的好奇心が旺盛で、新しい法律分野を主体的に学べる学生が歓迎される傾向にあります。
総合商社・メーカーは国際契約とM&A法務が中心
総合商社やグローバル展開している大手メーカーの法務部門は、その事業の性質上、国際法務が中心となり、非常に高い就職偏差値を誇ります。
彼らの法務部門は、海外企業との大規模な契約交渉や、国境をまたいだM&A(企業の合併・買収)といった、企業の将来を左右する重要な案件をリーガル面からサポートします。
特に総合商社では、多岐にわたる事業分野の全てに対応できる幅広い知識と、各国の法律を踏まえたリスクヘッジ能力が必須です。
メーカーでは、国際的なサプライチェーンにおける契約や、製品の安全に関するPL法(製造物責任法)への対応も重要となります。
そのため、ビジネスレベル以上の高い英語力と、国際的な商慣習を理解する能力が採用の鍵となります。
これらの業務の専門性と企業の社会的な影響力の大きさから、SSランクやSランクのトップ層に位置づけられています。
ベンチャー・スタートアップ企業は幅広い裁量が特徴
ベンチャーやスタートアップ企業の法務部門は、一般的には大手企業に比べて偏差値はAランクやBランクに位置することが多いですが、その業務内容は非常に幅広いという特徴があります。
特に、上場を目指す「上場準備中」の企業では、内部統制の構築やガバナンス体制の整備といった、企業全体を形作る重要な法務に携わることになります。
大手のように細分化された部署がなく、契約書作成から労務管理、新規事業のリーガルチェックまで、法務に関するあらゆる業務を少人数で担当するため、若いうちから幅広い実務経験を積むことができます。
この環境では、高度な専門知識よりも、スピード感を持って様々な法的な課題に対応できる柔軟性や、経営層に近い位置で働きたいという意欲が重視されます。
法務の就職偏差値が高い理由
法務職の就職偏差値が他の職種と比較して高い傾向にあるのは、いくつかの明確な理由が存在します。
一つは、業務の性質上、企業の「法的リスク」という、経営の根幹に関わる重要な責任を負っている点です。
一度の法的ミスが企業の存続に関わるほどの損害につながる可能性があるため、採用において極めて慎重にならざるを得ません。
また、法務部門で求められる知識は、一般的なビジネススキルだけでなく、専門的な法律知識や論理的思考力が不可欠であり、これらのスキルを持つ人材は市場でも希少性が高いのです。
さらに、企業のガバナンス強化やグローバル展開の加速により、法務の重要性は年々増しており、質の高い法務人材の需要が供給を上回っていることも、偏差値が高止まりする大きな要因となっています。
ここでは、法務職の採用難易度を押し上げている具体的な理由を深掘りして解説します。
企業の法的リスクを担うため専門性が必須
法務職の就職偏差値が高い最大の理由の一つは、その業務が企業の法的リスクの最前線を担うからです。
契約書の不備やコンプライアンス違反は、企業に巨額の損害賠償や社会的信用の失墜をもたらす可能性があります。
そのため、法務部門には、高い法律知識と、複雑な状況下で最善の法的判断を下す能力が不可欠です。
この専門性は、法学部出身者やロースクール修了者に限定されるわけではありませんが、採用側は入社後のキャッチアップの速さや、すでに持っている専門知識の深度を厳しくチェックします。
特に、国際法務やM&A法務といった高度な分野では、高度な専門知識の有無が、企業の事業展開そのものに直結するため、採用難易度は必然的に高くなります。
法務人材の需要増加と採用枠の少なさ
企業のグローバル化と法規制の強化により、法務人材の需要は年々増加しています。
しかし、その一方で、法務部門の新卒採用枠は、営業や企画職など他の職種に比べて非常に少ないのが現状です。
多くの企業では、法務部門は即戦力となる中途採用をメインとしており、新卒の採用は少数精鋭で行う傾向があります。
これは、法務業務が企業の秘密情報や経営判断に深く関わるため、入社後の育成に時間とコストがかかることも一因です。
結果として、少ない採用枠に対して、法務職を志望する優秀な学生が集中するため、倍率が高くなり、就職偏差値を押し上げる要因となっています。
狭き門を突破するためには、他の学生にはない突出した強みを示す必要があります。
法律知識だけでなく高い論理的思考力が要求される
法務職は、単に法律を知っているだけでなく、それを具体的なビジネスの状況に適用し、最適な解決策を導き出す「論理的思考力」が極めて重要です。
例えば、新しい事業を立ち上げる際、法務は「法律に違反していないか」だけでなく、「このやり方で法的なリスクを最小限にしつつ、ビジネスの利益を最大化できるか」という視点から判断を下す必要があります。
これは、法律の条文を暗記するだけでは不可能です。
多様な情報を整理し、複雑な問題を構造化して分析する能力、そしてそれを分かりやすく他部署に説明し、説得するコミュニケーション能力も不可欠です。
このような高度なスキルセットは一朝一夕には身につかないため、選考では学業成績だけでなく、学生時代に取り組んだ課題解決の経験などが重視されます。
法務の高偏差値企業に内定するための対策
法務の高偏差値企業に内定するためには、一般的な就職活動対策に加え、法務職ならではの専門的なアプローチが求められます。
単に「法律が好き」という意欲だけでは、厳しい選考を突破することはできません。
企業が法務職に求めるのは、即戦力となり得る専門的な知識と、それをビジネスの現場で活用できる論理的思考力、そして責任感です。
そのため、選考においては、あなたがどれだけ法務という仕事の本質を理解し、入社後に企業にどのような価値を提供できるのかを具体的に示す必要があります。
ここでは、SSランクやSランクといった高偏差値企業への内定を勝ち取るために、今すぐ取り組むべき具体的な対策を解説します。
法律の専門知識を深掘りし、面接で応用力を示す
高偏差値企業の法務部門では、採用段階から法律の専門知識がある程度備わっていることが期待されます。
具体的には、会社法や民法、知的財産法など、志望企業の業界で特に重要となる法律分野を重点的に学習することをおすすめします。
ただし、単に知識を暗記するだけでなく、具体的なビジネス上の事例に照らして、その法律がどのように適用され、どのようなリスクがあるのかを説明できる「応用力」を示すことが重要です。
面接では、「あなたが考える、〇〇業界における最新の法的リスクは何ですか?」といった、専門性と論理的思考力を問う質問がされる可能性があります。
これに対し、具体的な法令名や判例を挙げつつ、自分の意見を明確に論理的に伝えられるように準備しましょう。
企業法務への熱意と適性を裏付ける行動をする
法務職への熱意を示すためには、「なぜその企業の法務部門でなければならないのか」という理由を明確にすることが必須です。
単に「大手だから」「安定しているから」といった理由ではなく、その企業の事業内容や業界特有の法的課題を深く理解し、「その課題に対して、自分がどのように貢献したいのか」という具体的なビジョンを語ることが求められます。
具体的には、企業のIR情報やニュースリリースを読み込み、特に法務が関わりそうな新規事業やM&Aの動向を分析することが有効です。
また、企業法務のインターンシップに参加したり、弁護士事務所や企業法務に携わるOB・OG訪問を積極的に行ったりして、実務のリアルな情報を得ておくことで、志望動機に説得力を持たせることができます。
論理的思考力と問題解決能力をアピールする
法務の仕事は、曖昧な状況から法的論点を抽出し、筋道を立てて解決策を提示するプロセスそのものです。
したがって、選考においては、あなたの論理的思考力と問題解決能力を証明するエピソードを準備しておく必要があります。
これは、法律の勉強に限らず、ゼミでの研究活動、サークルでの組織運営、アルバイトでのクレーム対応など、どのような経験でも構いません。
「どのような問題に直面し、その問題をどのように分析し、どのような手順で解決に至ったのか」を、「結論→根拠→具体例」の順で明確に説明できるようにしておきましょう。
特に、多様な意見を持つ人を法的な観点から説得し、合意形成を図った経験などは、法務職の適性を強くアピールできるでしょう。
法務の就職偏差値に関するよくある質問
就職活動を進める中で、法務職の就職偏差値やキャリアパスに関して様々な疑問を持つのは自然なことです。
法務職は専門性が高いがゆえに、他の職種に比べて情報が少なく、不安に感じる学生も多いでしょう。
特に「法律を専攻していないと不利なのか?」「偏差値の高い企業と低い企業で仕事内容はどのように違うのか?」といった疑問は、多くの就活生から寄せられます。
このセクションでは、法務職の就職偏差値にまつわる、就活生が抱きやすい疑問について、Webライターとして活躍する就活アドバイザーの視点から具体的かつ実践的な回答を提供します。
これらの質問と回答を通じて、法務職への理解を深め、あなたの就職活動に対する自信を深めてください。
法学部やロースクール出身でないと不利ですか?
法務職の採用において、法学部やロースクール出身であることが有利に働くことは間違いありませんが、必須条件ではありません。
近年、ビジネス環境の複雑化に伴い、企業が求める法務人材のスキルセットも多様化しており、経済学や国際学、情報科学など、他の専攻を持つ学生も積極的に採用されています。
特にIT・テック企業などでは、技術的な知見を持つ理系出身の法務人材のニーズが高まっています。
重要なのは、入社までにどれだけ法務の基礎知識を自主的に学習し、その知識をビジネスで活かせる論理的思考力を持っているかです。
面接では、「なぜ法務職を志望したのか」「法務の知識をどのようにキャッチアップしていくのか」という質問に対し、明確で説得力のある回答を用意しておくことが重要です。
資格は就職偏差値の高い企業の内定に必須ですか?
弁護士資格や司法書士、行政書士などの法律系資格は、法務職の選考においてアピール材料にはなりますが、新卒採用においては必須ではありません。
特にSSランクやSランクの大手企業では、資格よりも、学生時代の成果、ポテンシャル、企業への適性を重視する傾向があります。
彼らは、入社後の充実した研修体制を通じて、社員に専門知識を習得させる自信を持っています。
ただし、資格の勉強を通じて得られた法律的な論理的思考力や学習意欲は高く評価されます。
もし資格取得に向けて勉強しているのであれば、そのプロセスを通じて何を学んだのか、どのように思考力が鍛えられたのかを具体的に伝えることが、資格自体を持つこと以上に重要となるでしょう。
偏差値の低い法務職を選ぶメリットは何ですか?
就職偏差値がBランク以下の法務職を選ぶことには、高い偏差値の企業にはない独自のメリットがあります。
まず、採用倍率が比較的低いため、法務職へのキャリアの「入口」として挑戦しやすい点が挙げられます。
特に小規模な企業やベンチャー企業では、法務専任の社員が少ないため、若いうちから契約書作成や社内規程の整備など、法務業務の全体像を把握することができます。
大手企業では一部の業務しか担当できないことが多いのに対し、裁量が大きく、幅広い経験を積むことで、将来的なキャリアアップのための「土台」を短期間で築くことが可能です。
まずは実務経験を積み、その後のキャリアで専門性を高めていきたいというキャリア戦略を持つ学生にとっては、有効な選択肢となります。
まとめ
本記事では、法務職の就職偏差値ランキングをSSランクからDランクまで詳細に解説し、そのランキングから読み取れる業界別の傾向、そして高偏差値企業に内定するための具体的な対策について解説しました。
法務職の就職偏差値が高いのは、企業の法的リスクを担うという業務の専門性と重要性、そして少ない採用枠に対して優秀な学生が集中するという需給バランスに起因します。
法務職を目指すあなたにとって、就職偏差値は志望企業の採用難易度や求められる専門性を測る上での一つの重要な参考指標となりますが、あくまで一つの目安に過ぎません。
大切なのは、あなたがどのような法務キャリアを築きたいのか、そしてそのために今からどのような知識とスキルを身につけていくのかという具体的な行動です。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート