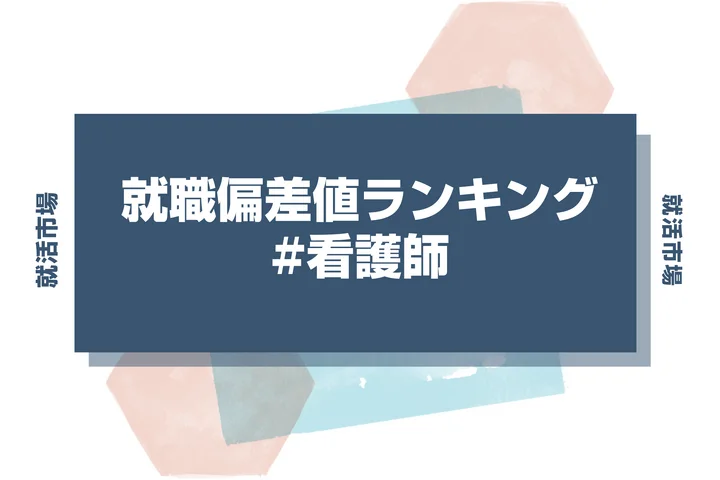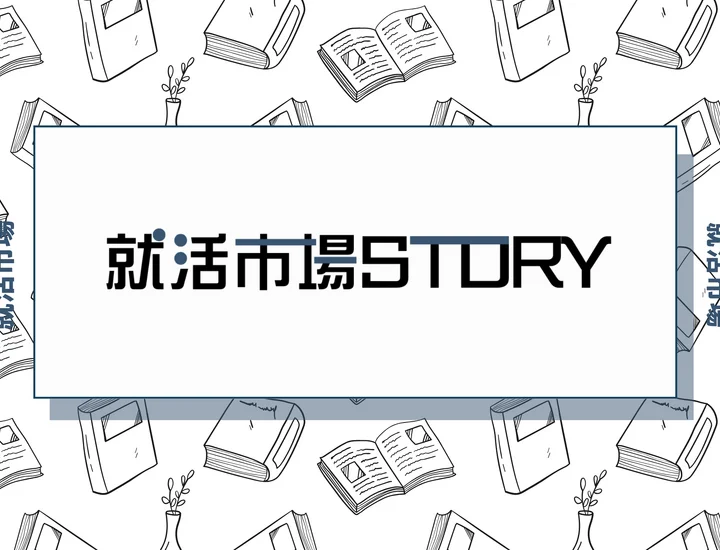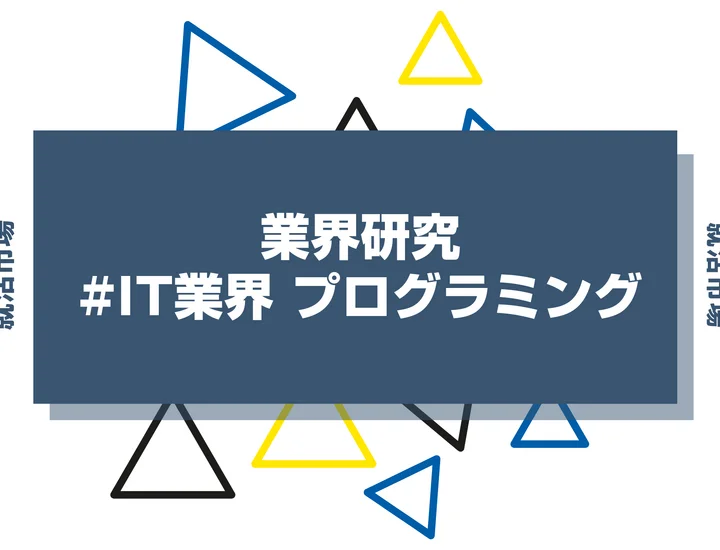目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
看護師の就職偏差値ランキング
看護師の就職偏差値は、一般的な事業会社の偏差値とは算出の基準や意味合いが少し異なります。
このランキングでは、病院や施設などの「就職先・職場」の採用難易度、専門性の高さ、そして労働環境の負荷と給与のバランスを総合的に評価しているのが大きな特徴です。
特に、高度な医療を提供する特定機能病院や大学病院、三次救急病院は、求められるスキルレベルと業務の忙しさから、必然的に偏差値が高くなる傾向にあります。
これに対し、回復期や慢性期、クリニックなどは、専門性や業務負荷が抑えられる分、偏差値は低くなる傾向がありますが、ワークライフバランスを重視する学生からの人気は非常に高いです。
看護学生の皆さんが、自身の目指す看護の形やキャリアプランに合わせて、最適な就職先を見つけるための具体的なロードマップとして、この偏差値ランキングを役立ててください。
ただし、偏差値はあくまで参考情報であり、自分自身の価値観や適性を最優先に考えることが何よりも大切です。
【看護師】SSランク(就職偏差値75以上)
- 高度急性期・特定機能病院での業務が中心
- 救命救急・ICU・手術室など高度医療の現場を担当
- 忙しさが非常に高く、高度な判断力とスピードが求められる
- 最先端医療を学べる反面、離職率も高く覚悟が必要
【80】国立病院機構(高度医療センター)
【78】大学病院(救命救急・集中治療)
【75】大手医療グループの三次救急病院
SSランクは三次救急やICUなど最も専門性と負荷が高い領域で、看護師としての総合力が強く求められる。
重症患者が多く、一瞬の判断が生死に直結する場面も多い。
その分、臨床スキルの習得が早くキャリア価値が高い。
高負荷の現場で成長したい学生に向いているが、強い精神力も必要となる。
【看護師】Sランク(就職偏差値70〜74)
看護師の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、看護師の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ看護師の就職偏差値をチェックしましょう!
- 急性期病院で、多様な疾患・治療に触れながらスキルを磨ける
- 配属先が多く、希望分野のキャリア形成がしやすい
- 研修制度が充実し、教育体制が整った法人が多い
- 夜勤が多く業務負荷は高いが、やりがいも大きい
【74】大手民間急性期病院
【72】地域の中核病院(急性期)
【70】公立・市立病院(急性期中心)
Sランクは急性期医療の中心で働く層で、症例の幅が広く看護技術を短期間で大きく伸ばすことができる。
教育体制が整っているため、基礎から専門分野まで段階的に学べる。
配属先によっては救急や手術室を経験でき、キャリアの幅が広がる。
忙しさはあるが、看護師として成長したい学生に人気が高い。
【看護師】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 回復期・地域包括ケア病棟など、患者と向き合える環境が多い
- 急性期より負担が軽く、患者との時間を大切にできる
- 生活支援やリハビリ補助など多様な看護に関わる
- ワークライフバランスが整いやすく、離職率が低い
【69】回復期リハビリテーション病院
【67】地域包括ケア病棟を持つ病院
【65】慢性期病院(安定したケア中心)
Aランクは急性期と比べ負荷が低く、患者の回復過程に寄り添いながら働けるため、精神的なやりがいを感じやすい。
生活面の支援が業務に含まれ、看護技術だけでなくコミュニケーション力も必要になる。
シフトや夜勤も急性期ほど厳しくなく働きやすさが高い。
バランスの取れたキャリアを築きたい学生に適している。
【看護師】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 療養型病院・高齢者医療での長期ケアが中心
- 医療処置は少なめで、患者の生活支援が多い
- 夜勤の負担が少なく、安定した勤務が可能
- 働きやすさ重視の学生に人気がある
【64】療養型病院(慢性期・長期ケア)
【62】介護医療院
【60】高齢者医療センター
Bランクは医療行為より生活支援の比重が高く、患者との関わりを丁寧に持ちたい学生に向いている。
急性期ほど忙しくないため、働きながらスキルを落ち着いて学ぶことができる。
精神的負荷も少なく、長期的に働き続けやすい環境が多い。
まずは安定した現場で看護に向き合いたい場合に最適である。
【看護師】Cランク(就職偏差値55〜59)
- クリニックや外来中心で医療行為が少なめ
- 日勤のみで働けるため生活リズムが整う
- 患者とのコミュニケーションが多く接客要素もある
- 専門スキルよりも気配りや調整力が求められる
【59】総合クリニック(外来)
【57】美容クリニック(施術補助)
【55】小児科・内科クリニック
Cランクは日勤中心で働きやすく、ワークライフバランスを優先したい学生に人気である。
医療行為が少ない分、患者対応やコミュニケーション力が重要になる。
クリニックは少人数体制のため、多様な業務を幅広く担当することもある。
看護師資格を活かしつつ安定した働き方を目指す人に向いている。
【看護師】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 健診センターや訪問看護補助など専門性が低い業務
- 医療行為はほぼなく、サポート要素が中心
- スキルよりも丁寧なコミュニケーションが重視される
- 未経験から挑戦しやすいがキャリアアップは限定的
【54】健診センター(採血・案内)
【52】訪問看護補助
【50】企業内看護師(健康管理中心)
Dランクは医療行為がほぼなく、看護スキルよりも安全管理やコミュニケーションが中心となる。
働きやすさは高いが、専門性を高めたい場合は物足りなさがある。
安定と負担の低さを求める学生に向いているが、キャリア形成は限定的である。
看護を軸にしつつ柔らかい働き方をしたい層に適した領域である。
看護師の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
先の看護師の就職偏差値ランキングを分析すると、働く環境や業務内容によって、明確な傾向が浮かび上がってきます。
病院や施設をランク付けしているこの偏差値は、単なる「入りやすさ・難しさ」だけでなく、「そこで働く看護師に求められるスキルや経験値」「労働環境の専門性や負荷」を反映していると言えます。
特に、三次救急を担う高度急性期病院がトップランクに位置し、回復期、慢性期、外来・健診と、医療行為の難易度や緊急性が下がるにつれて偏差値も低くなる傾向が顕著です。
これは、就職活動における競争率の高さだけでなく、看護師としてのキャリアの初期段階で得られる経験の幅と深さを示す指標にもなっているのです。
偏差値が高い=良い、低い=悪いと一概に判断するのではなく、皆さんが将来どのような看護師になりたいか、どのような働き方をしたいかという自己分析の結果と照らし合わせて、各業界の傾向を理解することが重要です。
高偏差値層:高度急性期・特定機能病院の傾向
SS~Sランクに位置する高度急性期病院や大学病院は、最先端の医療と複雑な症例に触れられる機会が圧倒的に多く、新卒から看護師としての専門的スキルを極限まで高めたい学生に人気が集中します。
これらの病院は、充実した研修制度や専門看護師・認定看護師の資格取得支援が整っているため、自己成長意欲の高い学生にとっては非常に魅力的な環境です。
しかし、救命救急やICU(集中治療室)など、生命に関わる緊急性の高い現場が多く、高いプレッシャーと長時間労働を伴うことも事実です。
採用では、単に成績が良いだけでなく、タフな精神力と倫理観、チーム医療における協調性が重視されます。
入職後も高いプロ意識を持ち続け、学び続ける姿勢が求められるのが、この高偏差値層の大きな特徴と言えるでしょう。
中間偏差値層:一般急性期・回復期リハビリテーション病院の傾向
S~Aランクに該当する一般的な急性期病院や回復期リハビリテーション病院は、看護師として多様な経験とワークライフバランスのバランスを取りたい学生が多く集まる層です。
急性期病院では、幅広い疾患の看護を経験することで基礎的な看護技術を確固たるものにでき、回復期では患者様の生活に寄り添い、リハビリテーションや生活支援を通じた深い関わりを持つことができます。
この層の病院は、高偏差値層と比べて業務負荷が少し落ち着き、離職率も比較的低い傾向にあります。
特に回復期は、患者様の回復を間近で見られるという精神的なやりがいが大きく、急性期での経験を経て、より患者様と向き合う看護を追求したい学生にも人気が高いです。
地域の中核病院としての役割も大きく、安定した経営基盤を持つ法人が多いのも特徴です。
低偏差値層:慢性期・外来・専門クリニックの傾向
B~Dランクに見られる慢性期病院、療養型病院、クリニック、健診センターなどは、医療行為の緊急性が低く、生活リズムを安定させたい学生にとって魅力的です。
これらの職場は、夜勤や残業が少ない、あるいは日勤のみの求人が多く、プライベートの時間を確保しやすいため、ライフステージの変化を見据えた看護師や、子育て中の看護師にも選ばれやすい傾向があります。
業務の中心は、長期的なケア、生活支援、健康管理などであり、高度な専門スキルよりも丁寧なコミュニケーション力や気配りが重視されます。
キャリアアップの機会は高偏差値病院に比べて限定的かもしれませんが、安定した環境で長く働き続けたいという価値観を持つ学生にとっては、最適な選択肢となるでしょう。
「看護師資格を活かしつつ、負担を抑えて働きたい」というニーズに応える業界と言えます。
看護師の就職偏差値が高い理由
看護師の就職偏差値が高い病院・施設は、その多くが特定の魅力的な要素を持っているため、新卒学生からの応募が集中し、結果として採用難易度が上がっています。
単に「給料が高い」という理由だけでなく、その後のキャリア形成に直結する「学びの質」や「経験の希少性」が大きく関わっているのです。
特に、命に関わる高度な医療が提供される現場では、看護師一人ひとりのスキルが患者様の予後に直接影響するため、採用側の基準も非常に厳しくなります。
また、大規模な病院ほど、福利厚生や研修制度が充実している傾向があり、長期的なキャリアを見据えた学生にとって非常に有利な選択肢となります。
このように、高い偏差値は、「競争率の高さ」と「提供される成長環境の質の高さ」という二つの側面から説明できます。
専門性の高い経験とスキルを積める
就職偏差値が高い病院は、三次救急や特定機能病院など、高度な医療を提供する施設が中心です。
ここでは、多様かつ複雑な重症例に日々触れることができるため、一般的な病院よりも圧倒的なスピードで臨床スキルと専門知識を磨くことができます。
例えば、SSランクの病院でICU経験を積めば、集中ケア認定看護師などの高度な資格を目指しやすくなり、その後の転職市場においても極めて高い評価を得られます。
新卒の段階で「質の高いファーストキャリア」を築きたいと考える学生にとって、これらの病院は、自己投資として非常に価値が高いため、競争率が跳ね上がり、結果的に偏差値が高くなります。
得られる経験の「希少性」が、偏差値の高さを決定づける大きな要因の一つです。
充実した教育体制と安定した福利厚生
高偏差値の病院、特に大学病院や国立病院機構などの大規模な医療法人は、新卒向けの研修制度が非常に充実しています。
集合研修やOJT(On-the-Job Training)が体系的に組まれており、新人が現場でつまずかないよう、教育専門の部署やプリセプター制度がしっかりと機能しています。
これは、専門性の高い医療現場であるからこそ、基礎を確実に固めさせる責任があるからです。
また、給与水準が高い、寮などの福利厚生が整っている、労働組合があり労働環境が守られているなど、物質的な安定性も学生からの人気を集める理由です。
安心して働きながら成長できる環境が整備されていることが、安定志向の学生にとって大きな魅力となり、結果として応募者数を増やしています。
看護師としての市場価値を高めやすい
偏差値が高い病院での勤務経験は、将来のキャリアパスを大きく広げることにつながります。
たとえば、大学病院での高度急性期経験は、その後の認定看護師や専門看護師へのキャリアチェンジはもちろん、行政や教育機関、民間企業(医療機器メーカーなど)への転職においても、「即戦力としての高度なスキルと知見」を持っている証明になります。
病院のブランド力自体が、その後のキャリアの「パスポート」としての役割を果たすため、将来的に様々な働き方を模索したい学生は、まず高偏差値の病院で実績を作ろうとします。
高い市場価値を意識する学生が多いため、結果的に採用競争が激化し、偏差値が上昇するメカニズムとなっているのです。
看護師の高偏差値企業に内定するための対策
高偏差値の病院への内定を勝ち取るためには、一般的な就職活動対策に加え、看護学生特有の対策と「熱意」のアピールが不可欠です。
これらの病院は、学生の看護観や倫理観、そしてタフな現場で働き続ける覚悟を厳しく見極めます。
単に「有名だから」「給料が良いから」という理由では内定は遠のいてしまいます。
重要なのは、その病院でなければならない具体的な理由と、入職後にどのように貢献し、成長していきたいかという明確なビジョンです。
具体的には、インターンシップや病院説明会への積極的な参加を通じて、現場の雰囲気を肌で感じ、自身の適性を確かめ、それを説得力のある志望動機へと昇華させることが求められます。
徹底した病院研究と明確な志望動機を作成する
高偏差値の病院は、救命救急、移植医療、がん専門医療など、それぞれ得意とする分野や力を入れている医療が異なります。
対策の第一歩は、その病院の「強み」と「自分が目指す看護」がどこで結びつくのかを具体的に特定することです。
例えば、「貴院の○○センターで行われている先進的な治療に携わり、専門性の高い看護を提供したい」というように、具体的な部署や取り組みに言及した志望動機を作成しましょう。
さらに、「なぜ他の急性期病院ではなく、貴院なのか」という問いに明確に答えられるよう、その病院の理念や地域における役割、具体的な部署の特徴まで深く掘り下げておくことが、面接官に本気度を伝える鍵になります。
看護観と倫理観に基づいた自己PRを構築する
高偏差値病院の採用面接では、あなたの看護師としての根本的な考え方、すなわち「看護観」が深く問われます。
単なる「患者様に優しくしたい」ではなく、「チーム医療においてどのような役割を担いたいか」「命の危機に瀕した患者様に対してどのような倫理的判断を下すか」など、具体的な事例に基づいた質問がされます。
自己PRでは、学生時代の実習経験やアルバイトで、困難な状況に直面した際の行動、倫理的なジレンマにどう向き合ったかを具体的に伝えましょう。
「患者様の不安を傾聴することで、治療への主体的な参加を促しました」といったように、あなたの行動が患者様の予後にどのような影響を与えたかをセットで語れるように準備しておくことが重要です。
インターンシップ・病院説明会に積極的に参加する
高偏差値病院の多くは、学生に対し、複数回のインターンシップ参加を推奨しています。
これは、学生に職場の現実を理解してもらうと共に、病院側が学生の熱意と適性を測る重要な機会だからです。
インターンシップや病院説明会に参加した際には、積極的に質問をし、現場の看護師とコミュニケーションを取ることで、「入職後のイメージ」を具体化しましょう。
その場で得たリアルな情報を志望動機や面接での回答に盛り込むことで、「貴院で働くことへの強い意欲と、現場を理解している冷静さ」を示すことができます。
単なる参加ではなく、内定への重要なプロセスとして捉え、臨む姿勢が大切です。
論理的な思考力とタフさをアピールする
高度な医療現場では、緊急時の冷静な判断力と、多忙な中でも感情的にならずに業務を遂行するタフな精神力が不可欠です。
面接では、「実習で最も困難だった経験と、それをどう乗り越えたか」「チームメンバーと意見が対立した際にどう対応したか」といった、あなたの問題解決能力とレジリエンス(精神的回復力)を問う質問が頻出します。
これらの質問には、「状況→問題点→あなたの行動→結果→学んだこと」という流れで論理的かつ簡潔に答える練習をしておきましょう。
厳しい環境で働く覚悟と、それを支える論理的な思考力こそが、高偏差値病院の内定を勝ち取るために求められる資質です。
看護師の就職偏差値に関するよくある質問
就職偏差値は、看護学生の皆さんにとって非常に気になる指標ですが、誤解や不安を招く情報も少なくありません。
このセクションでは、就職偏差値に関するよくある疑問に、就職アドバイザーとして具体的かつ実践的な視点からお答えしていきます。
偏差値はあくまで一つの参考情報であり、あなたのキャリアを決定づけるものではないということを理解した上で、自身の就職活動に役立ててください。
特に、偏差値と離職率、そしてキャリアパスの関係については、多くの学生が疑問に持つポイントですので、しっかりと確認しておきましょう。
就職偏差値が低い病院は、本当に「悪い」病院ですか?
全くそんなことはありません。
就職偏差値は、主に「学生からの人気・応募の殺到度」と「求められる専門性の高さ・業務負荷」によって決まる傾向があり、「病院の質」や「働きやすさ」を直接的に示す指標ではないからです。
例えば、偏差値が低めのC・Dランクのクリニックや療養型病院は、日勤のみで残業が少なく、ワークライフバランスが非常に取りやすいという大きなメリットがあります。
急性期のような高度な医療行為は少なくても、患者様一人ひとりと深く向き合える、精神的なやりがいの大きい看護が実践できます。
大切なのは、あなたの「看護観」と「求める働き方」にその病院が合っているかどうかです。
「偏差値が低い=自分にとって良い」という視点を持つことが、後悔のない就職を実現する鍵です。
偏差値が高い病院は、やはり離職率も高いのでしょうか?
高い傾向にあることは否定できません。
SSランクやSランクの病院は、救命救急やICUなど精神的・肉体的に非常に負荷の高い部署が多く、新卒が経験するプレッシャーや忙しさは相当なものです。
高度な専門性を追求できる反面、その環境に耐えられずに離職する新人も一定数いるのが現状です。
しかし、これらの病院は離職率の高さを問題視し、新人教育やメンタルヘルスサポートに特に力を入れているケースも多く見られます。
重要なのは、その病院の離職率そのものよりも、「離職後のキャリアパス」や「病院が離職率を下げるためにどのような対策をしているか」をチェックすることです。
病院説明会やインターンで、新人の定着率やサポート体制について積極的に質問してみましょう。
偏差値の低い病院に就職した場合、その後のキャリアアップは難しいですか?
いいえ、そんなことはありません。
キャリアアップに最も重要なのは、「あなたがそこで何を学び、どのようなスキルを身につけたか」という実績と経験の質です。
例えば、Bランクの療養型病院で、終末期ケアや認知症ケアの分野で深く専門性を磨いたとします。
これは、訪問看護や地域包括ケアなど、今後の医療ニーズが高まる分野で非常に価値のあるキャリアとなります。
また、クリニックでの経験も、患者対応や地域連携のスキルとして、企業内看護師など異業種への転職に有利に働くことがあります。
偏差値はスタート地点を示しているだけで、その後の努力と選択でキャリアはいくらでも広げられます。
入職後も学び続ける意欲を持ち、資格取得などに励むことが大切です。
自分の偏差値に見合った病院を選んだ方が良いですか?
自分の偏差値に縛られず、行きたい病院を選ぶべきです。
看護師の就職偏差値は、一般企業のそれと違い、「入試」のような明確な学力基準があるわけではありません。
あなたの看護観、熱意、そして倫理観が、その病院の求める人材像と合致すれば、内定は十分可能です。
特に、偏差値が70以上の超難関病院を目指す場合でも、諦める必要はありません。
大切なのは、「挑戦する」という強い意志と、それに見合う徹底的な対策です。
逆に、自分の偏差値が高いからといって安易に高偏差値の病院を選んでしまうと、ミスマッチを起こし、早期離職につながる危険性もあります。
「偏差値は参考情報の一つ」として活用し、「自分にとっての最良の選択」を追求してください。
まとめ
この記事では、看護師の就職偏差値ランキングを深く掘り下げ、各ランクの病院の特徴や、高偏差値病院に内定するための具体的な対策について解説しました。
就職偏差値は、あなたの「キャリアの方向性」を決めるための地図のようなものです。
どこに向かうべきか、その道筋を知る上で非常に役立ちますが、最終的な目的地(あなたの目指す看護師像)を決めるのは、あなた自身の価値観と意志に他なりません。
この記事で得た情報を活用し、後悔のない最高のファーストキャリアを掴み取ってください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート