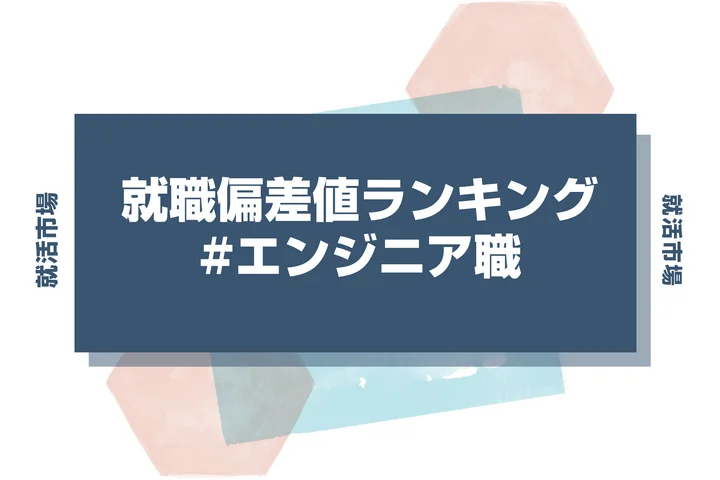目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
エンジニア職の就職偏差値ランキング
エンジニア職は、技術革新のスピードが速く、企業によって求められるスキルレベルが大きく異なるため、就職偏差値も非常に幅広くなります。
SSランクのような超難関企業は、世界トップレベルの技術力と専門性を要求しますが、D・Eランクのように未経験者でもIT業界のキャリアをスタートできる企業も多く存在するのが特徴です。
このランキングは、技術力の高さやプロダクトの規模、そして企業人気を総合的に反映した結果となっており、上位ランクになるほど採用選考における技術審査の比重が高くなる傾向があります。
そのため、皆さんが目指す企業のランクを知ることは、必要な対策や学習計画を立てる上で非常に重要です。
このランキングを参考に、自身のスキルレベルと照らし合わせながら目標設定を行ってみましょう。
【エンジニア職】SSランク(就職偏差値78以上)
- 世界規模のサービスや巨大プロダクトの開発に携わる
- 高度なアルゴリズム・セキュリティ・スケーラビリティ設計が必須
- 開発スピード・技術選定・プロダクト改善力が高いレベルで求められる
- 選考はコーディングテスト、ホワイトボードテストなど技術審査が中心
【80】Google(Software Engineer) Meta(Backend/Frontend Engineer)
【79】Amazon Web Services(AWS Engineer)
【78】LINEヤフー(バックエンドエンジニア) メルカリ(SRE/ServerSide)
SSランクのエンジニア職は、技術難度が極めて高く世界基準のスキルが求められる層です。
特にアルゴリズム能力や計算量への理解、スケールを意識したアーキテクチャ設計が重要になります。
コーディングテストは高難度で、基礎力と応用力の両方が評価されます。
プロダクトに対するオーナーシップが強く、設計から改善まで一気通貫で任される環境が特徴です。
【エンジニア職】Sランク(就職偏差値75〜77)
エンジニア職の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、エンジニア職の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐエンジニア職の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手IT企業や上場テック企業で高度な開発に携わる
- フロント・バックエンド・インフラなど専門領域で高水準の技術が必要
- 技術選定・プロダクト改善など裁量の大きい開発を担当する
- 選考では実装力だけでなく、ロジック思考・要件理解も重視される
【77】楽天(アプリ/サーバーサイド)
【76】サイバーエージェント(エンジニア) リクルート(ITエンジニア)
【75】DeNA(アプリ/ゲームエンジニア)
Sランクは技術水準が高く、プロダクトの中核を担うポジションに若手から挑戦できる層です。
大規模プロダクトの運用経験が積めるため、技術者として価値の高いキャリアが形成されます。
コードの品質やレビュー文化が強いため、開発者としての基礎が徹底的に鍛えられます。
主体的に学び、改善提案を積極的に行う姿勢が評価されやすい環境です。
【エンジニア職】Aランク(就職偏差値70〜74)
- 大手企業の情報システム部門や中堅IT企業で開発経験を積める
- アプリ開発・Web開発・社内システムなど領域が幅広い
- 研修制度やOJTが充実しており、未経験でも成長しやすい
- 設計・実装・テストをバランスよく経験できる環境が多い
【74】大手メーカー(社内SE)
【72】中堅IT企業(アプリエンジニア)
【70】SIer(プログラマー/SE)
Aランクは基礎の土台づくりに適しており、プログラミングの実務スキルを体系的に学べる層です。
研修が整っている企業も多いため、未経験の学生でも安心して成長できる点が特徴です。
また要件定義や設計へのステップアップがしやすく、キャリアの選択肢が広がります。
長期的にエンジニアとしてのキャリアを築きたい学生に向いています。
【エンジニア職】Bランク(偏差値65〜69)
- 中小IT企業やWeb制作会社で実務経験を積みやすい
- 実装中心のポジションが多く、手を動かす量が多い
- 開発スピードや対応力が重視されやすい環境
- 若手でも裁量を持って実務経験を積みやすい
【69】中堅Web制作会社(フロントエンド)
【67】中小IT企業(バックエンド/アプリ)
【65】SES企業(開発プロジェクト参画)
Bランクはプロジェクト参加の機会が多く、エンジニアとして実務経験を積みたい学生に適した層です。
案件数が多いため、短期間でスキルの幅を広げられる点が大きな魅力です。
ただし研修環境は企業によって差があるため、自己学習の姿勢が非常に重要です。
経験を積むことでAランク・Sランクへのキャリアアップも十分可能です。
【エンジニア職】Cランク(偏差値60〜64)
- IT未経験者でも挑戦しやすい企業が多い
- サポート業務やテスター業務からスタートするケースが多い
- プログラミングよりも運用・保守が中心の業務が多め
- IT領域に触れながらキャリアの入口を作れる
【64】テスト企業(QAエンジニア)
【62】運用・監視企業(システムオペレーター)
【60】ITサポート企業(ヘルプデスク)
CランクはIT業界の入口として挑戦しやすく、基礎的な業務を経験しながら成長できる層です。
IT知識が浅くても採用されやすいため、ここからスキルを伸ばすことで開発職への転向も可能です。
ただしコードを書く機会は少なめで、自主学習がキャリアアップに必須となります。
将来的にエンジニアを目指す場合は、経験を積みながらポートフォリオを作ることが重要です。
【エンジニア職】Dランク(偏差値55〜59)
- 完全未経験でも採用されやすく、IT基礎から学べる環境が多い
- テスター、ヘルプデスク、事務サポートなど業務は幅広い
- 研修の質は企業によって大きく異なる
- 配属により成長スピードが大きく変わる
【59】地方IT企業(ITサポート)
【57】中小テスト企業(QA補助)
【55】SES企業(初級エンジニア)
Dランクはエンジニア経験ゼロからでも挑戦できる企業が多く、業界の理解を深めながら働きたい学生に向いています。
まずは運用やテストなど基礎的な業務からスタートし、スキルを身につけていく形が一般的です。
配属先によってスキル習得の速度が異なるため、自主的な学習が成長の鍵になります。
キャリア形成の土台を作るという意味で、エンジニアの入口として有効なランクです。
【エンジニア職】Eランク(偏差値50〜54)
- 未経験歓迎で、ITサポートや事務職に近い業務が中心
- 専門スキルは不要で、パソコン操作や事務処理ができれば採用されやすい
- IT業界に触れる機会が多く、キャリアの入口として機能する
- 成長意欲があれば、後から開発職への転向も可能
【54】ITサポート企業(事務+サポート)
【52】一般企業の社内ヘルプデスク
【50】中小IT企業(初歩的な運用補助)
EランクはIT業界に興味はあるものの、専門スキルがまだ十分でない学生に向いている層です。
仕事内容は事務に近いものが中心ですが、IT環境に触れられるためキャリア選択のきっかけになります。
IT業界を理解したい学生にとって、最初のキャリアとして取り組みやすい領域です。
実務を続けながら独学で学べば、開発職へのステップアップも十分狙えます。
エンジニア職の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
エンジニア職の就職偏差値は、企業の属する業界や事業モデルによって明確な傾向が見られます。
SS〜Sランクには、自社サービスをグローバルに展開するメガベンチャーやWeb系企業が多くランクインしています。
これらの企業は、革新的な技術を高速で取り入れ、大規模なトラフィックを扱うため、極めて高い技術力が求められるのが特徴です。
一方、Aランクには、大手企業の情報システム部門や歴史ある大手SIer(システムインテグレーター)が多く、安定した基盤の中で要件定義やプロジェクト管理といった上流工程の経験を積める魅力があります。
このように、業界によって求められるスキルセットやキャリアパスが異なるため、ランキングを見る際には単なる数値だけでなく、「その企業がどのような事業を行い、エンジニアに何を期待しているか」という視点を持つことが大切です。
あなたの将来像と照らし合わせ、どの分野に進むのが最適かを見極めるヒントにしてください。
Web系自社開発企業は技術力と成長速度が重視される
Google、Meta、LINEヤフー、メルカリなどのWeb系自社開発企業がSS・Sランクに集中しているのは、技術の進化速度が非常に速く、常に最先端の技術を実務で使いこなす能力が求められるためです。
これらの企業は、自社プロダクトの成長に直接的に貢献できるエンジニアを求めており、選考ではコーディングテストや技術面接を通じて、ロジック思考力、アルゴリズムの知識、そして高速な実装力が厳しく評価されます。
企業文化として、若手であっても裁量が大きく、新しい技術へのキャッチアップや改善提案を主体的に行う姿勢が重要視される傾向があります。
そのため、高偏差値企業への内定を目指すには、大学での研究や個人開発を通じて、高い技術力と問題解決能力を証明できるポートフォリオを構築することが不可欠です。
SIerや社内SEはプロジェクト管理能力やビジネス理解が鍵
SIer(システムインテグレーター)や大手メーカーの社内SEといったA・Bランクに多く見られる企業群では、Web系企業とは異なり、技術力に加えてプロジェクトマネジメントや顧客の業務理解が重視されます。
これらの企業は、顧客の課題解決や社内システムの安定運用が主要なミッションであるため、要件定義能力、コミュニケーション能力、そしてセキュリティやインフラに関する幅広い知識が求められます。
特にSIerでは、複数の企業や技術を組み合わせたシステム構築を行うため、体系的な知識と調整能力が重要です。
技術の深さだけでなく、ビジネス視点でのシステム設計や、チームでの開発経験をアピールすることが、これらの企業での内定獲得に直結します。
受託開発・SES企業は実務経験を積みやすいキャリアの入口
C・Dランクに多く位置する受託開発企業やSES(システムエンジニアリングサービス)企業は、IT未経験者にとって実務経験を積むキャリアの入口として機能しています。
これらの企業では、開発プロジェクトの現場に早期から参加する機会が多く、プログラミングスキルや業務フローを実践を通じて学ぶことができます。
企業によっては研修制度が充実している場合もありますが、基本的には現場で「手を動かす」ことで成長していくスタイルです。
技術力の高い企業へのキャリアアップを目指す学生にとって、まずはこれらの企業で確かな実務経験とポートフォリオの材料を得ることが、次なるステップへの有効な戦略となります。
ただし、配属されるプロジェクトによって経験の幅が大きく変わるため、企業選びの際には教育体制やプロジェクトの多様性をしっかり確認しましょう。
エンジニア職の就職偏差値が高い理由
エンジニア職の就職偏差値が高い企業群、特にSSランクやSランクの企業は、その採用難易度の高さから就活生の間で非常に注目されています。
その背景には、企業が提供する「圧倒的な成長機会」と「高い報酬・待遇」という2つの大きな魅力があります。
世界トップレベルの技術を持つ企業は、優秀なエンジニアを惹きつけるため、選考基準を非常に高く設定せざるを得ません。
結果として、競争率が上がり、就職偏差値も高くなります。
しかし、これは単なる人気の指標ではなく、求められる専門性の高さを反映したものでもあります。
なぜこれらの企業の偏差値が高いのかを理解することは、あなたがエンジニアとしてどのようなキャリアを築きたいのかを考える上で重要な視点を与えてくれるでしょう。
突出した技術力とプロダクトの社会的な影響力
SS・Sランクに位置する企業は、Googleの検索エンジンやメルカリのフリマアプリのように、数千万から数十億というユーザーを抱える大規模なプロダクトを開発・運用しています。
この規模のサービスを支えるためには、高度なアルゴリズム、スケーラビリティに優れたアーキテクチャ設計、そして極めて高いセキュリティレベルが必須となり、世界トップクラスの技術力を持つエンジニアが求められます。
こうした環境で働くことは、自身の技術が社会に与える影響を肌で感じられる、突出した成長機会を意味します。
学生からすれば、世界に通用する技術に触れられる機会は非常に魅力的であり、結果として多くの優秀な人材が殺到し、選考の難易度が高まる一因となっています。
市場価値の高いスキル習得とキャリアパスの豊富さ
高偏差値の企業は、最新の技術動向に常にアンテナを張り、業務を通じてエンジニアに市場価値の高いスキルを習得させる環境が整っています。
例えば、クラウド技術、ビッグデータ処理、機械学習など、今後のIT業界で不可欠となる技術を実務で深く経験できることは、その後のキャリア形成において非常に大きな財産となります。
また、これらの企業で数年経験を積むことで、フリーランスとして独立したり、別のスタートアップでCTO(最高技術責任者)を目指したりと、キャリアの選択肢が格段に広がることも魅力です。
高いレベルでスキルを磨ける環境は、将来的な自分の市場価値を高めたいと考える優秀な学生にとって、最も魅力的な要素の一つなのです。
圧倒的に優遇された給与水準と福利厚生
就職偏差値の高い企業の多くは、その高い技術力を確保するために、新卒であっても他の業界と比較して圧倒的に高い給与水準を設定しています。
これは、エンジニアの採用競争が激化する中で、優秀な人材を獲得し、定着させるための戦略です。
年収が高いだけでなく、充実した福利厚生や自由度の高い働き方(リモートワーク、フレックスタイムなど)を提供しているケースも多く、ワークライフバランスの面でも優位性があります。
学生からすれば、高い技術を身につけながら経済的な安定も得られるこれらの企業は非常に魅力的であり、結果として志望者が集中し、採用倍率が非常に高くなります。
少数精鋭の採用と厳格な技術選考プロセス
SS・Sランク企業では、採用人数を絞り、少数精鋭で組織を構成する傾向があります。
これは、高いパフォーマンスを維持し、迅速な意思決定を可能にするためです。
そのため、新卒採用においても、高い技術力だけでなく、企業文化への適合性や自走力など、非常に厳格な基準で選考が行われます。
特に、コーディングテストや技術面接では、アルゴリズムの正確性、計算量の最適化、そして実装における設計思想などが深く問われます。
この厳格な技術選考プロセスこそが、これらの企業の就職偏差値を押し上げている最大の理由の一つであり、生半可な準備では内定を獲得できないことを示しています。
エンジニア職の高偏差値企業に内定するための対策
就職偏差値の高いエンジニア職の企業への内定は、単に知識があるだけでは難しく、戦略的な対策と早期からの行動が必須です。
特にSS・Sランクのような企業は、技術力、論理的思考力、そしてプロダクトに対する情熱の全てにおいて高い水準を求めてきます。
一般的な就活対策に加えて、エンジニアならではの選考プロセスに対応するための準備が欠かせません。
このセクションでは、皆さんが目標とする企業の内定を勝ち取るために、具体的に何をすべきか、実践的な対策を解説していきます。
まずは自分の現在のスキルレベルを正確に把握し、目標達成までのロードマップを明確に描くことからスタートしましょう。
基礎的なプログラミングスキルとアルゴリズムへの深い理解
高偏差値企業の選考では、まず間違いなくコーディングテストが実施されます。
このテストを突破するためには、特定の言語の文法を知っているだけでは不十分で、データ構造やアルゴリズムに関する深い理解と実践的な実装力が必要です。
具体的には、競技プログラミングのプラットフォーム(AtCoderやLeetCodeなど)を活用し、二分探索、動的計画法、グラフ探索といった基本的なアルゴリズムを時間内に正確に実装できるように訓練することが重要です。
この基礎力が、面接での技術的な議論や、入社後の複雑な問題解決の土台となります。
毎日少しずつでも良いので、継続的にコーディング問題を解く習慣をつけましょう。
実務レベルのポートフォリオとアウトプットの質を追求する
SS・Sランク企業では、学業での成績以上に、「何を創ったか」「どのように貢献したか」という具体的なアウトプットが評価されます。
内定を獲得するためには、企業の事業内容や技術スタックに合わせた、実務レベルで通用するポートフォリオの作成が必須です。
単なる動くWebサイトではなく、解決したい課題設定の明確さ、使用技術の選定理由、そして実装における工夫点を論理的に説明できるように準備しましょう。
GitHubでソースコードを公開し、コミット履歴やコードレビューの経験などを通じて、開発プロセスへの真摯な姿勢を示すことが非常に重要です。
早期からの長期インターンシップへの参加
高偏差値企業の多くは、サマーインターンや長期インターンシップを新卒採用の重要な選考ルートとして位置づけています。
特に長期インターンは、企業の現場で社員と同じ業務に携わることで、実務レベルでの技術力やチームでの働き方を深く理解する絶好の機会です。
インターンに参加し、そこで成果を出すことは、選考で最も強力なアピール材料となります。
また、インターンを通じて企業の文化や社員との相性を確認できるため、入社後のミスマッチを防ぐ意味でも非常に有益です。
大学1〜2年生の比較的早い時期から、興味のある企業のインターンシップ情報をチェックし、積極的に応募してみましょう。
企業の文化やプロダクトに対するオーナーシップを示す
エンジニアの採用選考では、技術力と同じくらい、企業が手掛けるプロダクトやサービスへの強い興味、そしてそれを改善したいという情熱、すなわちオーナーシップが重視されます。
面接では、「なぜ競合他社ではなく、この企業のプロダクトを選んだのか」を明確に答えられる必要があります。
例えば、「〇〇という機能について、自分ならAという技術を使ってBのように改善できると考えます」といった具体的な提案をすることで、技術力だけでなく、事業に対する貢献意欲を示すことができます。
企業の技術ブログや登壇資料を読み込み、独自の視点を持って臨むことが、内定を勝ち取るための大きな鍵になります。
エンジニア職の就職偏差値に関するよくある質問
就職偏差値ランキングを参考に企業選びを進める中で、多くの学生さんから同様の疑問が寄せられます。
特にエンジニア職においては、技術的な要素が絡むため、「どのランクの企業を目指すべきか」「未経験でも本当に高偏差値企業に内定できるのか」といった不安を抱えることは自然なことです。
ここでは、皆さんが抱きがちな就職偏差値に関する疑問について、就活アドバイザーとしての経験を踏まえて、具体的かつ実践的な回答を提供します。
偏差値はあくまで参考指標の一つであり、あなたのキャリアを決定づけるものではないということを念頭に置きながら、自身の進路を考える参考にしてください。
Q1. 未経験から高偏差値(Sランク以上)のエンジニアを目指せますか?
A. 目指すことは可能ですが、非常に厳しく、徹底した対策が必要です。
SS・Sランクの企業は、新卒であっても即戦力に近い、あるいは高い技術ポテンシャルを求めています。
そのため、大学での専門的な研究経験がない場合でも、独学でプログラミングスキルを習得し、質の高いポートフォリオを作成することが最低条件となります。
具体的には、Webアプリのフルスタック開発、競プロで上位成績を収める、OSS(オープンソースソフトウェア)に貢献するなどの明確な実績が必要です。
単に「興味がある」というレベルでは不十分です。
まず、B〜Aランクの企業で実務経験を積み、転職でステップアップするという戦略的なキャリアプランも現実的かつ有効な選択肢となります。
Q2. 就職偏差値が低い企業=「ブラック企業」ですか?
A. 必ずしもそうではありません。
就職偏差値は、企業の「人気」や「採用難易度」を示すものであり、「働きやすさ」や「企業の安定性」を直接示す指標ではないからです。
特にC〜Eランクに位置する企業の中には、研修制度が充実しており、未経験者が安心してITスキルを学べる優良企業も多く存在します。
また、地方の優良企業や専門性の高いニッチな分野の企業は、一般知名度が低いために偏差値が低く算出されがちですが、非常に高い技術力と安定した収益基盤を持っていることが多々あります。
企業を評価する際は、企業の評判、離職率、平均残業時間、そして提供される研修内容などを多角的に調査し、あなた自身の価値観に合うかどうかを基準に判断することが重要です。
Q3. 高偏差値企業への内定後に企業とのミスマッチを防ぐには?
A. 長期インターンシップへの参加と、社員との綿密なOB/OG訪問が最も有効な対策です。
高偏差値企業の内定を獲得しても、実際に働く環境や文化が自分に合わなければ、早期離職につながるリスクがあります。
これを防ぐため、選考期間中に可能な限り長期インターンに参加し、現場の雰囲気や具体的な業務内容を体験してください。
また、OB/OG訪問では、採用担当者ではない現場の若手社員や直属の上司になる可能性のある方と話し、「残業の実態」「チームのコミュニケーション頻度」「技術選定の自由度」など、企業のHPには載っていないリアルな情報を引き出すよう努めましょう。
自分のキャリアの希望を具体的に伝え、入社後のイメージを明確に共有することがミスマッチを防ぐ鍵となります。
Q4. 就職偏差値を参考にするときの注意点はありますか?
A. 就職偏差値はあくまで「参考指標の一つ」として捉え、盲信しないことが重要です。
偏差値は学生の「人気投票」に近い側面があるため、あなたの目指すキャリアや専門分野とは関係なく、単に知名度が高い大手企業が高ランクになる傾向があります。
例えば、特定の分野に特化した優良なBtoB企業は、一般知名度が低いため偏差値が低くなりがちですが、非常に高い技術力と安定した収益基盤を持っていることが多々あります。
あなたの興味のある技術や、将来的にどのようなエンジニアになりたいかという自身の軸を最優先にし、偏差値はその軸に沿った企業を探すための大まかなスクリーニングツールとして活用するのが最も賢明な方法です。
まとめ
本記事では、エンジニア職の就職偏差値ランキングを通じて、各ランクの企業の特徴、業界別の傾向、そして高偏差値企業への内定を勝ち取るための具体的な対策を詳しく解説しました。
SS〜Sランクの企業は、世界に通用する高度な技術力と、プロダクトへの深いオーナーシップを求めており、内定には早期からのアルゴリズム学習や質の高いポートフォリオ作成が不可欠です。
一方で、D〜Eランクの企業も、未経験からIT業界に飛び込むキャリアの入口として非常に有効です。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート