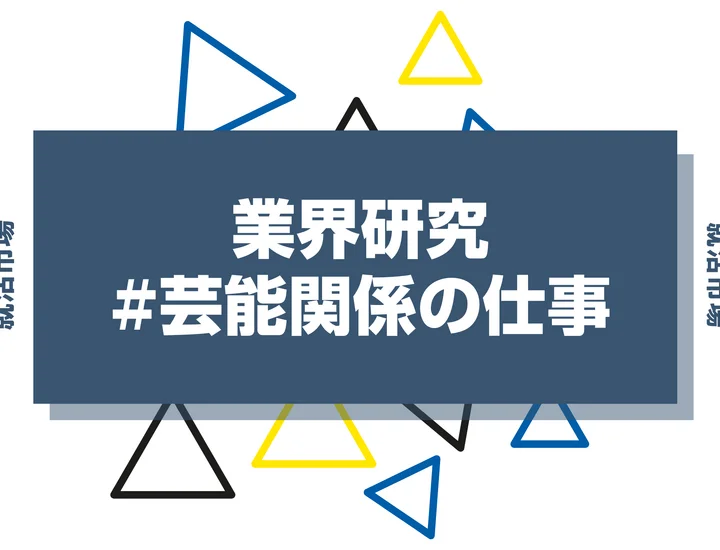就職活動を進める中で、「官公庁」という選択肢が気になっている方も多いのではないでしょうか。
「公務員」という言葉は知っていても、具体的に「なんの会社なの?」と聞かれると、民間企業との違いを説明するのは難しいかもしれません。
この記事では、官公庁とはそもそも何なのか、どんな仕事があり、どのような人が求められているのか、そして内定を掴むために何が必要なのかを、就活生の皆さんの目線で徹底的に解説していきます。
官公庁への就職は、民間企業とは異なる準備が必要です。
この記事を読んで、あなたのキャリア選択の一つとして、官公庁を深く理解するきっかけにしてくださいね。
目次[目次を全て表示する]
【官公庁はなんの会社】官公庁はどんな会社なのか
「官公庁」と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちますか?霞が関の立派な建物や、市役所の窓口を思い浮かべるかもしれませんね。
まず大前提として、官公庁は「会社」ではありません。
会社(企業)が利益を追求することを目的としているのに対し、官公庁は国や地方公共団体(都道府県、市町村など)の行政機関として、利益ではなく「公共の利益」のために活動する組織です。
つまり、国民や住民が安全で豊かな生活を送るためのルール作りや、教育、福祉、インフラ整備といった社会全体の基盤となるサービスを提供することが仕事です。
国全体の運営を担う「国の機関(省庁など)」と、地域に密着したサービスを提供する「地方公共団体(役所など)」の総称、それが官公庁だと理解しておきましょう。
【官公庁はなんの会社】官公庁の仕事内容
官公庁の仕事内容は、私たちが想像する以上に幅広く、多岐にわたります。
その根底にあるのは、先ほどお話しした「公共の利益のために働く」という共通のミッションです。
民間企業のように特定の製品やサービスを売って利益を上げるのではなく、国や地域の仕組みそのものを作ったり、守ったり、改善したりするのが主な役割と言えるでしょう。
例えば、新しい法律の案を考えたり、道路や学校を作ったり、社会保障制度を運営したり、海外との交渉を行ったりと、そのフィールドは非常に広大です。
大きく分けると、国全体に関わる仕事をする「国家公務員」と、地域住民の生活に直結する仕事をする「地方公務員」に分類されますが、どちらも社会の土台を支えるという重責を担っています。
ここでは、具体的にどのような仕事があるのか、いくつかの側面に分けて詳しく見ていきましょう。
国民生活の基盤を支える「国家公務員」
国家公務員は、国の行政機関、つまり「省庁」などで働く職員を指します。
財務省、外務省、経済産業省、文部科学省など、テレビのニュースでもよく耳にする組織ですね。
彼らの仕事は、まさに国全体の運営に関わるスケールの大きなものです。
例えば、国の予算を編成したり、外交政策を立案・実行したり、エネルギー政策を考えたり、教育制度を設計したりします。
国の未来を左右するような重要な政策決定に携わることが多く、強い責任感と高い専門性が求められます。
また、国の出先機関(例えば、税務署やハローワーク、法務局など)で、国民と直接接しながら法律の執行やサービスの提供を行う業務もあります。
国家公務員は、採用区分によって「キャリア」と「ノンキャリア」と呼ばれる区分があることも特徴ですが、いずれにせよ日本という国を動かすダイナミックな仕事に関われるのが大きな魅力と言えるでしょう。
地域住民の暮らしに密着する「地方公務員」
地方公務員は、都道府県庁や市役所、区役所、町役場など、それぞれの地方公共団体で働く職員です。
国家公務員が国全体を見るのに対し、地方公務員はその地域に住む人々の生活に直接関わる、より身近な仕事を担当します。
例えば、戸籍や住民票の管理、子育て支援、高齢者福祉、公立学校の運営、道路や公園の整備、地域の観光振興、防災対策など、私たちの暮らしに欠かせないサービスばかりです。
数年ごとに部署を異動(ジョブローテーション)することが多く、福祉、教育、土木、税務など、非常に幅広い分野の業務を経験できるのが特徴です。
地域住民の声に耳を傾け、その地域の課題解決に直接貢献できることは、地方公務員ならではの大きなやりがいと言えます。
自分が生まれ育った町や、愛着のある地域のために働きたいという人にとって、非常に魅力的な選択肢です。
専門知識を活かす「専門職(技術職・心理職など)」
官公庁の仕事は、法律や経済の知識が中心となる「行政職(事務職)」だけではありません。
特定の分野における高度な専門知識や技術を活かして活躍する「専門職」の職員も数多く在籍しています。
例えば「技術職」には、土木、建築、機械、電気・電子、化学、農学といった理系のバックグラウンドを持つ人が多く、公共事業の計画・設計・監督(道路、橋、ダム、上下水道の整備など)や、環境保全、農業振興などに携わります。
「心理職」であれば、児童相談所や福祉施設で人々の心のケアにあたったり、「福祉職」であれば、生活に困窮する方への支援を行ったりします。
他にも、税務の専門家である「国税専門官」、労働基準法などに基づき企業を監督する「労働基準監督官」など、その種類は様々です。
自分の専門性を公共のために直接役立てたいと考える人にとって、官公庁の専門職は非常にやりがいのあるキャリアパスとなるでしょう。
民間企業とは異なる「公務員」ならではの働き方
官公庁で働く「公務員」の働き方は、民間企業と比べていくつかの特徴があります。
最も大きな違いは、利益追求を目的としないため、ノルマや売上目標に追われることが基本的にない点です。
もちろん、税金を原資としているため、コスト意識や効率性は常に求められますが、あくまでも「公共の福祉の増進」が最大のミッションです。
また、法律や条例に基づいて仕事を進めることが非常に多く、手続きや前例を重んじる傾向があります。
これは、公平性・公正性を担保するために不可欠な要素です。
景気の変動によって経営が左右されたり、解雇されたりするリスクが極めて低いことも、民間企業との大きな違いでしょう。
一方で、数年ごとの部署異動や、場合によっては転勤(特に国家公務員)も多く、様々な環境への適応力が求められる側面もあります。
良くも悪くも「安定」していると言われるゆえんを理解することが大切です。
【官公庁はなんの会社】官公庁が選ばれる理由と競合比較
多くの就活生が、民間企業と並行して官公庁を志望します。
なぜ官公庁は就職先として選ばれ続けるのでしょうか。
その背景には、民間企業にはない公務員ならではの魅力と、社会的な役割の大きさが関係しています。
もちろん、仕事である以上、大変なことや厳しい側面もありますが、それを上回るほどの安定性や社会貢献の実感が、多くの学生を惹きつける要因となっているようです。
また、就職活動においては、インフラ業界や金融業界など、「社会基盤を支える」という点で共通する民間企業が競合として比較されることも少なくありません。
ここでは、官公庁が選ばれる具体的な理由と、民間企業と比較した際のメリット・デメリットについて掘り下げていきます。
自分が仕事に何を求めるのかを考えながら、比較検討してみてください。
圧倒的な「安定性」と「社会的信用」
官公庁が選ばれる最大の理由の一つは、やはりその「安定性」です。
公務員は国や地方公共団体に雇用されており、その身分は法律によって手厚く保障されています。
民間企業のように、業績不振によるリストラ(解雇)や倒産のリスクが基本的にありません。
また、給与や昇進も年功序列の要素が強く、景気の波に大きく左右されることなく、長期的なキャリアプランやライフプランを立てやすいのが特徴です。
退職金や年金といった制度もしっかりと整備されています。
さらに、「公務員」という職業は社会的な信用が非常に高いため、ローンを組む際やクレジットカードの審査など、生活の様々な面で有利に働くことが多いのも事実です。
将来の生活設計を見据えたときに、この「安定」と「信用」は何物にも代えがたい魅力として映るようです。
「公共への貢献」という明確なやりがい
官公庁の仕事は、そのすべてが「公共の利益」、つまり社会全体や地域住民のために行われます。
自分の仕事が、特定の誰かや一企業の利益のためではなく、不特定多数の人々の生活を支え、より良い社会づくりに直接つながっているという実感は、公務員ならではの大きなやりがいです。
民間企業でも社会貢献を掲げる企業は多いですが、官公庁の仕事は、その貢献のスケールが国や地域全体に及ぶという点で異なります。
例えば、災害が発生した際の復旧支援、子どもたちが安全に学べる学校環境の整備、安心して暮らせるための治安維持など、社会に不可欠な役割を担っているという誇りが、日々の業務のモチベーションにつながります。
営利を目的としないからこそ、純粋に「人の役に立ちたい」「社会を良くしたい」という想いを実現しやすい環境だと言えるでしょう。
民間企業(特にインフラ・金融)との違い
官公庁、特に「社会基盤を支える」という点では、電力・ガス・鉄道といったインフラ企業や、経済の血液とも言われる金融機関(特にメガバンクや政府系金融機関)がよく比較対象に挙がります。
これらの民間企業も公共性は高いですが、決定的な違いは「利益追求」が組織の目的であるか否かです。
インフラ企業や金融機関も、安定したサービス提供という社会的使命を負いつつ、株主のために利益を最大化する必要があります。
一方、官公庁は利益を目的とせず、採算が取れない分野であっても、公共の必要性があればサービスを提供します。
また、官公庁は法律に基づいた「権力」の行使(許認可、徴税、取り締まりなど)を伴う場合がありますが、民間企業にはそれがありません。
より直接的かつ広範な「公共性」を追求したいか、民間企業のスピード感やサービス競争の中で社会貢献したいかが、選択の分かれ目になるでしょう。
ワークライフバランスと福利厚生の実態
公務員は「定時で帰れる」「休みが取りやすい」といったイメージを持つ人も多いかもしれません。
確かに、カレンダー通りの休日(土日祝休み)が基本で、年次有給休暇に加えて、夏季休暇や病気休暇、育児・介護休暇などの各種休暇制度が法律で手厚く定められており、取得しやすい環境が整っています。
育児休業の取得率も民間企業に比べて高い傾向にあり、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい職場と言えるでしょう。
ただし、部署や時期によっては、国会対応、予算編成期、災害対応、選挙期間中などは、連日深夜までの残業や休日出勤が続くことも珍しくありません。
特に霞が関の中央省庁などは激務であることで知られています。
「公務員=楽」というイメージは必ずしも正しくなく、職場によって実態は大きく異なることを理解しておく必要があります。
【官公庁はなんの会社】官公庁の求める人物像
官公庁は、民間企業とは異なる役割を担うため、求められる人材の資質も自ずと変わってきます。
利益を追求するのではなく、国や地域全体、あるいは住民全体の奉仕者として働くことが求められるため、個人の能力の高さ以上に、その倫理観や公共心といった内面的な要素が重視される傾向にあります。
もちろん、政策を立案したり、複雑な行政課題を解決したりするための論理的思考力や実行力も不可欠です。
しかし、それらの能力は「全体の利益」のために使われるべき、というのが基本的なスタンスです。
法律やルールを遵守し、公平・公正に職務を遂行できる誠実さは、すべての公務員に共通して求められる大前提と言えるでしょう。
ここでは、官公庁がどのような人物を求めているのか、具体的な要素に分解して解説します。
高い「倫理観」と「責任感」
公務員は、国民や住民から預かった「税金」を使って仕事をし、時には国民の権利や自由に関わるような「公権力」を行使することもあります。
そのため、一般の職業以上に高い倫理観、道徳観が求められます。
「全体の奉仕者」として、私利私欲を捨て、常に公平・中立な立場で職務を遂行しなければなりません。
特定の個人や団体を優遇したり、不正や不祥事を起こしたりすることは、行政全体の信頼を失墜させる行為として厳しく戒められます。
また、自分の仕事が社会に与える影響の大きさを自覚し、最後まで粘り強く任務をやり遂げる強い「責任感」も不可欠です。
地道で目立たない仕事であっても、それが社会基盤を支えているという自覚を持ち、誠実に取り組める人が求められています。
「全体の利益」を考え行動できる奉仕精神
官公庁の仕事は、常に「公共の利益」を最優先に考えなければなりません。
民間企業であれば自社の利益や顧客の満足を追求しますが、官公庁は、社会全体の多様な利害関係者のバランスを取りながら、最も多くの人々にとって最善となる道を探る必要があります。
時には、一部の人々からは反対されたり、批判されたりするような政策決定をしなければならない場面もあります。
そうした状況でも、感情的にならず、あくまでも「全体の利益」という大局的な視点に立って物事を判断し、行動できる資質が求められます。
「誰かのために役立ちたい」という純粋な「奉仕精神」や、社会貢献への強い意欲は、公務員として働く上での原動力となるでしょう。
面接などでは、自己PRや学生時代の経験を通じて、こうした視点を持っているかを問われることが多いです。
多様な立場の人と連携する「調整能力」
行政の仕事は、一人の力で完結することはほとんどありません。
省庁内・役所内の他部署はもちろんのこと、他の省庁や自治体、民間企業、NPO、そして何より国民や住民といった、非常に多くの関係者と連携・調整しながら進めていく必要があります。
それぞれの立場や利害が異なるため、意見が対立することも日常茶飯事です。
そうした中で、相手の意見を尊重しつつも、粘り強く交渉・説得し、最終的な合意形成を図っていく「調整能力」は、公務員にとって極めて重要なスキルです。
多様な価値観を受け入れ、円滑な人間関係を築けるコミュニケーション能力や、物事を客観的に分析し、論理的に説明する力も、この調整能力の土台となります。
派手なリーダーシップよりも、周りと協力しながら着実に物事を前に進められる力が重視される傾向にあります。
前例にとらわれない「課題解決意欲」
公務員というと「前例踏襲」や「お堅い」といったイメージがあるかもしれませんが、現代の行政が直面している課題は、少子高齢化、デジタル化への対応、環境問題、地域コミュニティの希薄化など、過去のやり方だけでは解決できない複雑なものばかりです。
そのため、既存の枠組みや前例にとらわれることなく、新しい視点や発想で課題解決に挑戦しようとする意欲も強く求められています。
もちろん、法律や公平性を無視した独りよがりな変革は許されませんが、現状を分析し、より良い行政サービスを提供するために何ができるかを主体的に考え、行動できる人材は高く評価されます。
「ルールを守る」ことと「現状維持」はイコールではありません。
決められたルールの中で、いかに工夫し、改善していけるかを考える姿勢が重要です。
【官公庁はなんの会社】官公庁に向いてる・向いていない人
ここまで官公庁の仕事内容や特徴を見てきましたが、皆さんは自分に合っていると感じたでしょうか。
官公庁の仕事は、民間企業とは大きく異なる特性を持っているため、残念ながら「すべての人に向いている」とは言えません。
「安定」や「社会貢献」といった魅力的な側面に惹かれる一方で、その働き方や組織文化が自分の価値観や志向と合わなければ、入庁後にミスマッチを感じてしまう可能性もあります。
就職活動は、単に内定を得ることがゴールではなく、自分らしく活き活きと働ける場所を見つけることが大切です。
ここでは、官公庁の仕事に「向いている人」と「向いていない人」の具体的な特徴を、就活アドバイザーの視点から率直にお伝えします。
自分自身の性格やキャリアプランと照らし合わせながら、自己分析の材料にしてください。
向いている人:社会貢献意欲が高く、地道な努力が苦にならない人
まず、官公庁に強く向いているのは、「誰かの役に立ちたい」「社会を良くしたい」という純粋な社会貢献意欲が高い人です。
官公庁の仕事は、その成果が直接的な利益や報酬として返ってくるわけではありません。
しかし、自分の仕事が国や地域の基盤を支え、多くの人々の生活に貢献しているという実感こそが、最大のモチベーションとなります。
また、行政の仕事は、法律や膨大な資料の読み込み、関係各所との地道な調整、正確性を求められる事務作業など、華やかさとは裏腹に、コツコツとした地道な努力の積み重ねである場合がほとんどです。
目先の成果や評価に一喜一憂せず、長期的な視点で物事に取り組み、縁の下の力持ちとして社会を支えることに喜びを感じられる人は、公務員としての適性が高いと言えるでしょう。
向いている人:ルールや秩序を重んじ、安定した環境で働きたい人
官公庁は、法律や条例といった「ルール」に基づいて運営される組織です。
そのため、決められた手順やルールをしっかりと守り、公平・公正に物事を進めることが得意な人に向いています。
独創的なアイデアを次々と出すことよりも、既存の枠組みの中でいかに正確かつ効率的に業務を遂行できるかが評価される場面も多いです。
また、組織の秩序や上下関係を重んじる文化も比較的強く残っています。
こうした環境を「堅苦しい」と感じるか、「規律が保たれていて働きやすい」と感じるかは人それぞれです。
さらに、雇用の安定性や、景気に左右されない給与体系、充実した福利厚生といった環境面を重視する人にとっても、官公庁は非常に魅力的な職場です。
安定した生活基盤の上で、長期的にキャリアを築いていきたいと考える人には最適な選択肢の一つです。
向いていない人:成果が給与に直結する環境を望む人
官公庁(公務員)の給与は、個人の業績や成果が直接的に反映される「成果主義」ではなく、年齢や勤続年数に応じて上昇していく「年功序列」の体系が基本です。
もちろん、勤務評価による多少の差は生じますが、民間企業のように「大きな成果を出したからボーナスが倍になる」といったことはありません。
そのため、自分の頑張りや成果が、目に見える形(特に給与)でスピーディーに評価されることを強く望む人にとっては、物足りなさを感じる環境かもしれません。
若いうちからバリバリ働いて高収入を得たい、実力次第でどんどん昇進したいという志向が強い人は、インセンティブ制度が充実している民間企業、特に外資系企業やベンチャー企業のほうが向いている可能性が高いです。
向いていない人:スピーディーな意思決定や大きな変革を主導したい人
官公庁の仕事は、公平性や正確性を担保するため、多くの手続きや関係者との調整を必要とします。
一つの物事を決定するにも、多くの決裁(ハンコ)や会議を経る必要があり、意思決定のスピードは民間企業に比べて遅くなる傾向があります。
また、法律や前例を重んじるため、新しい取り組みや大きな変革を実現するには、かなりの時間と労力がかかります。
「トップダウンで素早く物事を進めたい」「既存のやり方を抜本的に変えたい」という強い変革志向を持つ人にとっては、手続きの多さや組織の硬直性を「もどかしい」と感じる場面が多いかもしれません。
もちろん、公務員の中にも改革マインドを持って活躍している人はいますが、民間企業、特にベンチャー企業のようなスピード感で物事を動かすのは難しい環境であることは理解しておく必要があります。
【官公庁はなんの会社】官公庁に受かるために必要な準備
官公庁への就職を目指す場合、民間企業の就職活動とは異なる、特有の準備が必要になります。
その最大の違いは、原則として「公務員試験」に合格しなければならない点です。
民間企業の選考が主にエントリーシート(ES)や複数回の面接で行われるのに対し、官公庁は、まず筆記試験(教養試験・専門試験)という大きなハードルを越える必要があります。
この試験対策には膨大な時間がかかるため、どれだけ早い時期から計画的に準備を始められるかが合否を大きく左右します。
また、筆記試験を突破した後には、民間企業の面接とは少し毛色の違う「官庁訪問」や「人物試験(面接)」が待っています。
ここでは、官公庁に受かるために不可欠な準備について、具体的なステップを解説していきます。
最難関:「公務員試験(筆記)」の徹底対策
官公庁の内定を勝ち取るための最初の、そして最大の関門が「公務員試験(筆記)」です。
国家公務員(総合職・一般職)、地方公務員(上級・中級など)といった目指す区分によって出題科目は異なりますが、多くの場合、中学から大学レベルまでの幅広い知識を問う「教養試験」(数的処理、文章理解、社会科学、自然科学など)と、大学の専門レベルの知識を問う「専門試験」(憲法、民法、行政法、経済学など)が課されます。
これらの試験範囲は非常に広大で、付け焼き刃の勉強では到底太刀打ちできません。
多くの受験生は、大学3年生の春頃から、公務員試験予備校に通ったり、専門のテキストを使ったりして、1年以上の時間をかけて計画的に対策を進めます。
どの試験区分を受験するのかを早期に決定し、膨大な試験範囲をカバーするための学習スケジュールを立てることが何よりも重要です。
なぜ民間ではないのか:「官庁訪問・面接」対策
筆記試験に合格すると、次はいよいよ面接試験です。
国家公務員の場合は「官庁訪問」と呼ばれる、志望する省庁を実際に訪問して職員と面談を繰り返すプロセスが、地方公務員の場合は「人物試験」として複数回の面接が行われるのが一般的です。
ここで問われるのは、学力ではなく、あなたの人柄や志望動機です。
特に「なぜ民間企業ではなく、公務員(官公庁)なのか」「なぜ他の省庁・自治体ではなく、ここなのか」という問いに対して、明確かつ説得力のある答えを準備しておく必要があります。
「安定しているから」といった理由だけでは、公共のために尽くす覚悟があるとは見なされません。
自己分析と、志望する官公庁の政策や課題に関する「徹底した研究」に基づき、自分の言葉で「ここで何を成し遂げたいのか」を熱意を持って語れるように準備しましょう。
情報収集の要:「説明会」や「インターンシップ」の活用
筆記試験の勉強に追われがちですが、官公庁も民間企業と同様に、業務内容や職場の雰囲気を知るための説明会やインターンシップ(国家公務員では「霞が関OPENゼミ」など)を実施しています。
これらは、パンフレットやウェブサイトだけでは得られない「生の情報」に触れる絶好の機会です。
実際に働く職員の方から仕事のやりがいや苦労話を聞くことで、自分がその官公庁で働くイメージを具体的に持つことができますし、面接で話す志望動機の説得力も格段に増します。
また、インターンシップなどに参加することで、職員の方に顔を覚えてもらえたり、同じ志を持つ仲間と出会えたりするメリットもあります。
筆記試験の勉強と並行して、こうした情報収集の機会にも積極的に参加し、志望先への理解を深めていくことが、最終的な合格につながる重要な鍵となります。
併願は可能?:民間企業との就活スケジュールの両立
「官公庁が第一志望だけど、民間企業も受けておきたい」と考える就活生は非常に多いです。
結論から言えば、官公庁と民間企業の併願は可能ですが、相当な覚悟と計画性が必要です。
公務員試験の勉強は、大学3年生から本格化することが多いですが、民間企業の就職活動(インターンシップや早期選考)も同じ時期に活発になります。
筆記試験の勉強時間を確保しながら、民間企業のES作成、Webテスト対策、面接練習もこなすのは、時間的にも精神的にもかなりの負担となります。
どちらも中途半端になってしまうリスクを避けるためにも、自分の中で優先順位を明確にすることが重要です。
例えば「公務員試験の勉強を最優先にしつつ、民間は業界を絞って受ける」「大学3年の夏までは民間のインターンに集中し、秋から公務員試験の勉強に切り替える」など、自分なりの戦略を立てて臨む必要があります。
【官公庁はなんの会社】官公庁の志望動機の書き方
官公庁の選考、特に面接試験において最も重視されるのが「志望動機」です。
筆記試験で高い点数を取っていても、志望動機が曖昧だったり、熱意が感じられなかったりすると、内定を得ることは難しいでしょう。
面接官は、数ある職業の中から「なぜ公務員を選んだのか」、そして「なぜ他の自治体や省庁ではなく、ウチ(志望先)なのか」という点を厳しくチェックしています。
彼らが求めているのは、「安定してそうだから」といった受け身の理由ではなく、公共のために働きたいという強い意志と、その官公庁の課題を理解した上での具体的な貢献意欲です。
自分の経験と志望先の業務を結びつけ、説得力のあるストーリーとして語れるかどうかが勝負の分かれ目となります。
ここでは、面接官の心に響く志望動機を作成するための重要なポイントを解説します。
根幹:「なぜ公務員なのか」を明確にする
志望動機を組み立てる上で、全ての土台となるのが「なぜ民間企業ではなく、公務員(官公庁)なのか」という問いへの答えです。
この部分が曖昧だと、その後の話がどれだけ立派でも「それって民間企業でもできるよね?」と一蹴されてしまいます。
ポイントは、「利益追求」を目的としない公務員の仕事の特性と、自分の価値観を結びつけることです。
例えば、「特定の顧客のためでなく、社会全体や立場の弱い人も含めた全ての人々の生活を支える仕事がしたい」「営利を目的としないからこそ、公平・中立な立場で長期的な課題解決に取り組みたい」といった視点が考えられます。
自分の過去の経験(ボランティア活動、サークル活動、アルバイトなど)を振り返り、「社会貢献」や「公共性」にやりがいを感じた具体的なエピソードを交えながら、公務員の仕事に惹かれた理由を論理的に説明できるようにしましょう。
具体性:「なぜその省庁・自治体なのか」を深掘りする
「公務員になりたい」という理由だけでは不十分です。
「なぜ数ある官公庁の中から、〇〇省(あるいは〇〇市)を志望するのか」という点を具体的に説明できなければなりません。
そのためには、徹底した「志望先研究」が不可欠です。
その省庁や自治体が現在どのような政策に力を入れているのか、どのような課題を抱えているのか、他の官公庁と比べてどのような特徴があるのかを、公式ウェブサイト、広報誌、報道、説明会などで徹底的に調べ上げましょう。
その上で、「〇〇市が推進している子育て支援策に共感し、自分もその一員として貢献したい」「〇〇省が取り組む〇〇という課題に対し、大学で学んだ〇〇の知識を活かしたい」というように、その組織でなければならない理由を明確に述べることが重要です。
漠然とした「地元だから」といった理由だけでは、熱意は伝わりません。
貢献:「入庁後にどのように貢献したいか」を伝える
志望動機は、単なる「憧れ」や「希望」を語る場ではありません。
面接官が知りたいのは、「あなたが組織に入って、具体的に何をしてくれるのか」ということです。
つまり、入庁後にどのように活躍し、その官公庁(ひいては国民・住民)に貢献できるかを具体的に提示する必要があります。
ここでは、自己PRとも重なる部分ですが、自分の強みや学生時代に培った経験・スキルを、志望先の業務内容と結びつけてアピールしましょう。
例えば、「サークル活動で培った調整能力を活かし、多様な関係者と連携しながらプロジェクトを進めたい」「留学経験で得た語学力と異文化理解力を、国際交流の分野で活かしたい」といった形です。
自分の能力が、その官公庁が直面する課題の解決にどう役立つのかを論理的に説明することで、「この学生を採用したい」と思わせる説得力のある志望動機が完成します。
避けるべきNG例とブラッシュアップのコツ
官公庁の志望動機として避けるべきNG例の代表格は、「安定しているから」「福利厚生が充実しているから」「親に勧められたから」といった、自分の待遇面や他者からの影響を前面に出した理由です。
「全体の奉仕者」としての自覚が疑われてしまいます。
また、「社会貢献がしたい」という理由も、それ自体は悪くありませんが、あまりに抽象的すぎます。
「なぜ民間ではなく公務員なのか」「具体的にどのような社会貢献がしたいのか」まで深掘りしなければ、熱意は伝わりません。
志望動機をブラッシュアップするコツは、「過去(経験)」「現在(価値観・強み)」「未来(入庁後の貢献)」の3点を一貫したストーリーでつなげることです。
大学のキャリアセンターや、予備校の講師、OB・OGなど、第三者に何度も読んでもらい、客観的なフィードバックをもらうことも非常に有効です。
【官公庁はなんの会社】官公庁についてよくある質問
ここまで官公庁の全体像について詳しく解説してきましたが、就活生の皆さんからは、まだまだ細かい疑問や不安の声が寄せられます。
特に、民間企業とは異なる公務員特有の制度や働き方については、なかなかイメージが湧きにくい部分も多いようですね。
例えば、「異動や転勤はどれくらいあるのか?」「学歴は選考に影響するのか?」といったリアルな疑問は、キャリアプランを考える上で非常に重要です。
こうした疑問を一つひとつ解消しておくことが、入庁後のミスマッチを防ぎ、自信を持って選考に臨むための鍵となります。
ここでは、就活生の皆さんから特によく寄せられる質問をピックアップし、就活アドバイザーの視点から分かりやすく、かつ率直にお答えしていきます。
Q. 部署異動(ジョブローテーション)は多いですか?
はい、官公庁(公務員)は部署異動が非常に多いのが特徴です。
特に、行政職(事務職)で採用された場合、一般的に2〜3年程度の間隔で異なる部署へ異動することが多いです。
これは、特定の部署に長くいることによる癒着を防ぎ、公平性を保つと同時に、職員に幅広い業務知識と多様な視点を身につけさせ、将来の幹部候補生を育成する(ゼネラリストを育てる)という目的があります。
例えば、市役所であれば、税務課から福祉課へ、次は企画課へといった形で、全く異なる分野の仕事を経験します。
様々な仕事に挑戦できることをメリットと捉えるか、専門性が身につきにくいことをデメリットと捉えるかは、人によって分かれる点でしょう。
ただし、技術職や心理職などの「専門職」として採用された場合は、その専門分野内での異動が基本となります。
Q. 転勤の範囲と頻度はどれくらいですか?
転勤の有無や範囲は、「国家公務員」か「地方公務員」か、またその中でもどの職種かで大きく異なります。
まず、都道府県庁や市町村役場などの「地方公務員」は、原則として採用された自治体のエリア内での異動が基本です。
例えば、東京都庁に採用されれば東京都内、横浜市役所なら横浜市内での異動となり、引っ越しを伴うような転勤は(本庁と出先機関が離れている場合を除き)ほとんどありません。
一方、「国家公務員」は、転勤が非常に多い職種と言えます。
特に「総合職(キャリア)」や、国税専門官、労働基準監督官などの専門官、地方(出先機関)への異動がある「一般職」は、数年おきに霞が関(本省)と全国各地のブロック機関・出先機関を行き来する、あるいは海外の大使館へ赴任するなど、全国転勤、場合によっては海外転勤が伴います。
Q. 学部・学科による有利不利はありますか?
公務員試験の「受験資格」としては、一部の専門職(技術職など)を除き、年齢要件さえ満たしていれば、学部・学科による制限は一切ありません。
法学部や経済学部以外の、文学部、教育学部、理工学部など、どのような学部の出身者でも平等に受験でき、合格している実績も多数あります。
ただし、試験科目という点では、専門試験で法律系科目(憲法、民法、行政法)や経済系科目(ミクロ経済、マクロ経済)が課される試験区分(国家公務員や地方上級の行政職など)が多いため、これらの科目を大学で学んでいる法学部や経済学部の学生が、勉強を進める上で有利であることは事実です。
しかし、それ以外の学部の学生も、予備校の活用や独学でこれらの科目を習得し、合格を掴んでいます。
面接においても、学部学科で有利不利がつくことはありません。
Q. 「ノンキャリア」と「キャリア」の違いとは何ですか?
この区分は、主に「国家公務員」において用いられる採用試験の区分(通称)です。
一般的に「キャリア」と呼ばれるのは、「国家公務員総合職試験」に合格して採用された職員のことを指します。
彼らは、将来の幹部候補生(局長、事務次官など)として採用され、入省(庁)当初から重要な政策立案などに携わり、非常に早いスピードで昇進していきます。
全国転勤や海外赴任も多く、激務であることでも知られています。
一方、「ノンキャリア」と呼ばれるのは、主に「国家公務員一般職試験(大卒程度)」に合格して採用された職員です。
彼らは、主に各省庁の本省や地方の出先機関で、政策の実行や事務処理といった中核的な実務を担います。
キャリアに比べると昇進のスピードは緩やかで、転勤の範囲も限定的(採用されたブロック内など)であることが多いです。
まとめ
皆さん、お疲れ様でした。
「官公庁はなんの会社なのか」という疑問から始まり、その仕事内容、魅力、求められる人物像、そして選考対策まで、詳しく解説してきました。
官公庁は「会社」ではなく、利益のためではなく「公共の利益」のために存在する組織であること、そしてその仕事は、国や地域の基盤を支える非常に幅広く、責任あるものであることがお分かりいただけたかと思います。
「安定」という魅力だけでなく、「社会貢献」という確かなやりがい、そして「全体の奉仕者」としての高い倫理観が求められる、それが官公庁で働くということです。
民間企業とは異なる公務員試験という大きなハードルはありますが、計画的に準備を進め、「なぜ自分は公務員として働きたいのか」という軸をしっかり持つことができれば、道は必ず開けます。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート