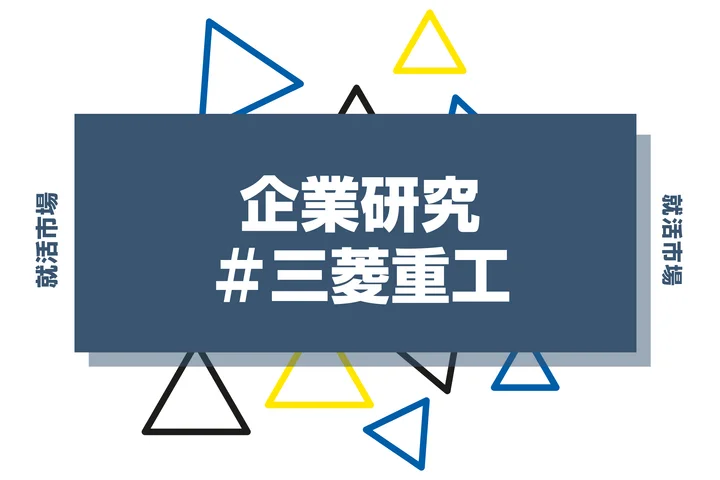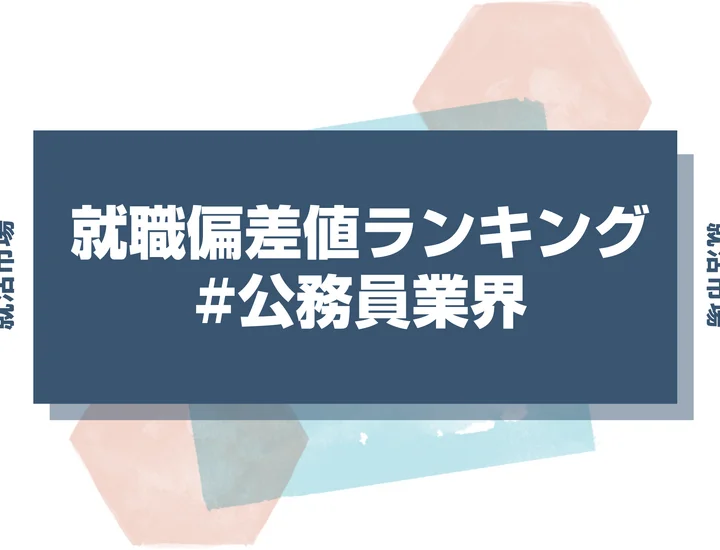日本を代表する総合重工業メーカーであり、その規模の大きさや事業の幅広さから、多くの就活生が憧れる企業の一つです。
しかし、「名前は知っているけれど、具体的に“なんの会社”なのか、どんな仕事をしているのかはよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、三菱重工がどのような会社で、どのような人材を求めているのか、そして内定を勝ち取るためにはどうすればよいのかを、徹底的に解説していきます。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工はどんな会社なのか
三菱重工、正式には三菱重工業株式会社は、その名の通り「重工業」を担う、日本を代表する総合メーカーです。
ひと言で「重工業」と言っても、その領域は非常に幅広く、まさに「陸・海・空、そして宇宙まで」が事業フィールドです。
具体的には、私たちの生活に欠かせない電力(火力・原子力・再生可能エネルギー)を生み出す発電プラタントや、環境を守るためのCO2回収技術といった「エナジー」分野。
社会インフラを支える製鉄機械や環境設備などの「プラント・インフラ」分野。
物流を支えるフォークリフトやエンジン、快適な空間を作るエアコンなどの「物流・冷熱・ドライブシステム」分野。
そして、民間航空機やロケット、防衛機器などを手掛ける「航空・防衛・宇宙」分野。
これら4つのセグメントを柱に、世界中の人々の暮らしと産業の発展を根底から支えています。
まさに、社会の基盤そのものを作っている会社だと言えるでしょう。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工の仕事内容
三菱重工と聞くと、巨大な工場で機械を組み立てる姿を想像するかもしれませんが、その仕事内容は非常に多岐にわたります。
これだけ大規模で幅広い事業を展開しているため、社内には多様なプロフェッショナルが存在し、それぞれの役割を果たしています。
大きく分けると、新しい技術を生み出したり製品の形を決めたりする「技術系」の職種と、それらの技術や製品をビジネスとして動かし、会社全体を支える「事務系」の職種があります。
例えば、技術系には最先端の研究を行う研究開発職や、製品の青写真を描く設計職があり、事務系には国内外の顧客と交渉する営業職や、プロジェクトに必要な資材を世界中から集める資材調達職などがあります。
三菱重工の仕事は、これら多様な職種が複雑に連携し合うことで、一つの巨大なプロジェクトを動かしていくのが特徴です。
ここでは、その代表的な仕事内容を4つピックアップして、具体的にどのような業務を行っているのかを詳しく見ていきましょう。
技術系:研究開発
研究開発職は、三菱重工の未来を創る仕事です。
数年後、あるいは数十年後を見据え、社会が必要とするであろう革新的な技術や製品の「種」を生み出す役割を担います。
例えば、より効率的な発電方法、CO2を排出しないエネルギーシステム、次世代の航空宇宙技術など、地球規模の課題解決に直結するテーマに取り組みます。
この職種では、専門分野に関する深い知識はもちろん、既成概念にとらわれない発想力や、失敗を恐れずに試行錯誤を繰り返す粘り強さが求められます。
日々の業務は、実験やシミュレーション、データ分析が中心となりますが、時には国内外の大学や研究機関と共同でプロジェクトを進めることもあります。
すぐに成果が出ないことも多いですが、自分の研究が世界初の技術として実用化され、社会を大きく変える瞬間に立ち会える可能性がある、非常にやりがいのある仕事です。
最先端の知見に触れながら、まだ誰も見たことのない未来を自らの手で切り拓きたいという情熱を持つ人にとって、魅力的なフィールドと言えるでしょう。
技術系:設計
設計職は、研究開発で生まれた技術の「種」を、具体的な「製品」という形にする仕事です。
顧客の要望や社会のニーズに基づき、安全性、コスト、性能、デザインなど、あらゆる要素を考慮しながら、製品の仕様や構造を決定し、図面(現在は主に3D CADデータ)を作成します。
三菱重工が手掛ける製品は、発電タービンやロケット、船舶など、非常に大規模で複雑なものが多いため、設計の仕事も細かく分かれています。
例えば、製品全体の基本構想を練る「基本設計」、個々の部品レベルまで詳細を詰める「詳細設計」、そしてプロジェクト全体を技術面から管理する「プロジェクト設計」などがあります。
この仕事には、工学的な知識だけでなく、関連する法規の理解、コスト意識、そして他部門(製造、営業、資材調達など)と円滑に連携するためのコミュニケーション能力が不可欠です。
自分が設計したものが、巨大な機械やインフラとして形になり、世界中で人々の生活を支える。
そのスケールの大きな「ものづくり」に、構想段階から深く関わることができるのが、設計職の最大の醍醐味です。
事務系:営業
事務系職種の代表格である営業は、三菱重工の技術力と製品を、世界中の顧客に届け、ビジネスを創出する最前線の仕事です。
三菱重工の営業は、単に「モノを売る」だけではありません。
特に、発電プラントや航空機、防衛システムといった大規模プロジェクトの場合、顧客が抱える課題を深く理解し、自社の技術やリソースを組み合わせて最適なソリューションを提案するところから始まります。
契約交渉、プロジェクト全体の進捗管理、そして納入後のアフターサービスまで、技術部門や法務、経理部門など社内の多くの関係者を巻き込みながら、プロジェクトリーダーとして全体を牽引する役割を担います。
国内だけでなく海外の政府や大手企業が顧客となることも多く、グローバルな舞台で活躍するチャンスが豊富にあります。
この仕事には、高いコミュニケーション能力や交渉力はもちろん、複雑なプロジェクトをまとめ上げる調整力、そして異文化を理解し受け入れる柔軟性(求める人物像の「Balanced」にも通じます)が求められます。
自分の手で数千億円規模のビジネスを動かし、社会インフラの構築に直接貢献できる、ダイナミックな仕事です。
事務系:資材調達
資材調達は、三菱重工が「ものづくり」を行う上で欠かせない、非常に重要な仕事です。
製品を製造するために必要な原材料、部品、設備などを、世界中のサプライヤーから「最適な品質」「最適なコスト」「最適な納期」で調達する役割を担います。
三菱重工が手掛ける製品は、時に数百万点もの部品で構成されるため、調達の仕事はプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。
この職種では、国内外のサプライヤーとの価格交渉や納期調整はもちろん、新規サプライヤーの開拓も行います。
また、最近では、環境負荷や人権問題に配慮した「サステナブルな調達」も重視されています。
単に安く買うだけでなく、長期的な視点で信頼できるパートナーを選定し、強固なサプライチェーンを構築することが求められます。
この仕事には、交渉力やコスト感覚、そしてグローバルな市場動向を読む力が必要です。
技術部門と密に連携し、製品に関する知識を深めながら、会社の「ものづくり」を根幹から支える。
縁の下の力持ち的な存在ですが、ビジネス全体に大きな影響を与えることができる、専門性の高い仕事です。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工選ばれる理由と競合比較
数あるメーカーの中でも、なぜ三菱重工は多くの就活生から選ばれるのでしょうか。
その理由は、一言で言えば「圧倒的なスケール感」と「社会貢献性の高さ」にあります。
三菱重工は、日本の重工業界においてトップクラスの売上高と事業規模を誇り、手掛ける製品の多くが社会インフラやエネルギー、防衛といった国の根幹を支えるものです。
これは、他の企業ではなかなか経験できない、ダイナミックな仕事に挑戦できる環境があることを意味します。
また、競合他社と比較しても、その総合力や技術の幅広さは際立っています。
もちろん、川崎重工業やIHI(旧:石川島播磨重工業)といった強力なライバルも存在し、それぞれに得意分野や強みがあります。
企業研究を進める上では、これらの競合と比べることで、三菱重工ならではの魅力や立ち位置がより明確になるはずです。
ここでは、三菱重工が選ばれる具体的な理由と、代表的な競合他社との違いについて掘り下げていきます。
圧倒的な事業規模と技術力
三菱重工が選ばれる最大の理由は、その「圧倒的な事業規模と技術力」にあります。
売上高は4兆円を超え、連結従業員数は約8万人(2024年3月期)と、競合他社と比べてもその規模は群を抜いています。
この規模の大きさがもたらすのは、まず手掛けるプロジェクトのスケールの大きさです。
例えば、国全体の電力を支える巨大な発電プラントの建設や、国家プロジェクトであるロケットの開発・打ち上げなど、文字通り社会を動かすような仕事に携わるチャンスがあります。
また、三菱重工は500以上もの製品・技術を保有しており、その「技術の幅広さと深さ」も大きな強みです。
一つの会社にいながら、陸・海・空・宇宙の最先端技術に触れられる環境は、技術者を目指す学生にとって非常に魅力的でしょう。
このように、他社では経験できないダイナミックな「ものづくり」に関わり、自らの手で社会インフラを構築したいという強い意欲を持つ学生にとって、三菱重工は最高の舞台と言えます。
社会インフラを支える貢献性の高さ
「社会インフラを支える貢献性の高さ」も、三菱重工が強く支持される理由の一つです。
私たちが毎日当たり前に使っている電気。
その多くは、三菱重工が手掛けた発電設備によって生み出されています。
また、人々やモノの移動を支える航空機や船舶、国の安全を守る防衛機器、さらには地球環境を守るためのCO2回収技術まで、その事業のほとんどが人々の生活や社会の基盤と密接に結びついています。
就職活動において、「社会の役に立ちたい」「大きなインパクトを与えられる仕事がしたい」と考える学生は多いですが、三菱重工の仕事は、その思いを最もダイレクトに実現できるフィールドの一つです。
目先の利益だけでなく、長期的な視点で社会全体の発展に貢献するという、強い使命感を持って働くことができる。
この「社会貢献性」の実感こそが、多くの就活生を惹きつける大きな魅力となっています。
自分の仕事が、今この瞬間も世界のどこかで誰かの生活を支えているという誇りを感じられるのは、三菱重工ならではのやりがいでしょう。
競合比較:川崎重工業
三菱重工を理解する上で欠かせないのが、競合他社との比較です。
代表的なライバルとして、まずは「川崎重工業(川崎重工)」が挙げられます。
川崎重工も、航空宇宙、鉄道車両、船舶、エネルギー、モーターサイクル(バイク)など、非常に幅広い事業を手掛ける総合重工業メーカーです。
特に、「Ninja」ブランドで知られるモーターサイクル事業は一般消費者にも馴染みが深く、三菱重工にはない特徴的な事業ポートフォリオを持っています。
また、鉄道車両の分野でも高い技術力とシェアを誇ります。
社風に関しては、OpenWorkなどの口コミサイトでは、三菱重工が「堅実」「組織的」と評されるのに対し、川崎重工は「風通しが良い」「若手にも裁量がある」といった声が比較的見られる傾向があります。
ただし、これらはあくまで個人の感想であり、部署や事業所によって大きく異なる点には注意が必要です。
事業規模や利益性といった総合力では三菱重工が上回る側面が多いですが、川崎重工には独自の強みと魅力があり、どちらが自分に合っているかを慎重に見極める必要があります。
競合比較:IHI
もう一つの主要な競合として、「IHI(旧:石川島播磨重工業)」も重要です。
IHIは、資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、そして航空・宇宙・防衛の4分野を柱としています。
特に強みを持つのが、航空機のジェットエンジンの分野です。
日本の民間航空機用ジェットエンジンの生産シェアの大部分を担っており、この領域では世界的なプレーヤーの一角を占めています。
また、橋梁などのインフラ分野や、自動車のターボチャージャー(過給機)など、特定の分野で高い技術力とシェアを持つ製品が多いのが特徴です。
財務面では、売上規模は三菱重工、川崎重工に次ぐ位置づけですが、在庫管理の効率性など、コスト面での強みも見られます。
三菱重工が「陸・海・空・宇宙」のあらゆる領域で圧倒的な総合力を持つ「デパートメントストア」だとすれば、IHIは特定の技術分野で深く強みを発揮する「専門店」のような側面があると言えるかもしれません。
自分がどの技術分野に興味があり、どのような働き方をしたいのかを考える上で、IHIとの比較は非常に有益でしょう。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工の求める人物像
これほどまでに大規模で、社会的に重要な役割を担う三菱重工では、一体どのような人材が求められているのでしょうか。
三菱重工グループは、採用サイトなどで「求める人物像」として、3つのキーワードを明確に掲げています。
それは「Active(アクティブ)」「Balanced(バランスド)」「Creative(クリエイティブ)」です。
これは単なるスローガンではなく、三菱重工がグローバルな舞台で直面する複雑な課題を乗り越え、未来を切り拓いていくために、社員一人ひとりに期待する資質を示しています。
例えば、前例のない大規模プロジェクトを推進するには、困難に直面しても前向きにやり遂げる「Active」な姿勢が必要です。
また、世界中の多様なステークホルダー(顧客、パートナー、社内関係者)と協働するには、互いの価値観を尊重する「Balanced」な感覚が欠かせません。
そして、常に変化する顧客のニーズに応え、新しい価値を生み出し続けるためには、柔軟な発想で挑戦する「Creative」な思考が求められます。
ここでは、これら3つのキーワードが具体的にどのような能力を指しているのか、そして、それらを補完する重要な資質について詳しく解説していきます。
Active:主体的に行動し、最後までやり遂げる力
一つ目のキーワードは「Active(アクティブ)」です。
これは、単に活発であるという意味ではありません。
三菱重工が求める「Active」とは、困難な状況に直面しても決して諦めず、自ら高い目標を掲げ、周囲を巻き込みながら、最後まで責任を持ってやり遂げる力を指します。
三菱重工の仕事は、数年がかりの大規模プロジェクトや、世界初の技術開発など、一筋縄ではいかないものばかりです。
想定外のトラブルやプレッシャーは日常茶飯事です。
そうした中で、他人任せにせず、当事者意識を持って「自分ならどうするか」を常に考え、前向きに行動できる人材が求められています。
学生時代の経験で言えば、例えば部活動やサークル、アルバートなどで、困難な課題に対して自ら率先して動き、周囲と協力して解決に導いた経験などが、この「Active」な資質を示すエピソードになるでしょう。
面接では、その時の状況、あなたの考え、具体的な行動、そして結果を論理的に説明することが重要です。
Balanced:多様な価値観を尊重し、協働できる力
二つ目のキーワードは「Balanced(バランスド)」です。
これは、多様な文化や価値観を持つ人々と円滑にコミュニケーションをとり、互いの考えを尊重しながら一つのチームとして成果を出していく力を意味します。
三菱重工のビジネスは非常にグローバルであり、世界中の顧客やパートナー、そして多国籍なメンバーと協働する機会が日常的にあります。
また、社内においても、技術系、事務系といった職種の違い、あるいは世代や経験の違いなど、多様なバックグラウンドを持つ人々が連携してプロジェクトを進めています。
こうした環境では、自分の意見を主張するだけでなく、相手の立場や考えを理解し、柔軟に物事を調整していく「バランス感覚」が不可欠です。
異なる意見の対立を乗り越え、議論を通じてより良い結論を導き出した経験や、異文化交流の経験などは、この「Balanced」な資質をアピールする上で有効です。
単なる「協調性」ではなく、多様性の中で最適解を見出そうとする姿勢が問われています。
Creative:柔軟な発想で、新しい価値を創造する力
三つ目のキーワードは「Creative(クリエイティブ)」です。
これは、アーティストのような独創性のみを指すのではありません。
三菱重工が求める「Creative」とは、従来のやり方や常識にとらわれず、柔軟な発想で物事を多角的に捉え、顧客や社会の新たなニーズに応える新しい価値を生み出す力を指します。
技術革新のスピードが速く、社会課題が複雑化する現代において、過去の成功体験に安住していては企業は成長できません。
常に問題意識を持ち、「もっと良い方法はないか」「本当にこれで顧客は満足しているか」と自問自答し、新しいアイデアを積極的に提案・実行できる人材が必要です。
例えば、サークル活動の運営方法を根本から見直して成果を上げた経験や、アルバート先で非効率な業務プロセスを改善した経験なども、この「Creative」な思考を示す具体例となります。
重要なのは、変化を恐れずに自ら考え、行動を起こす「主体的な創造性」です。
顧客志向と現場対応力
上記の3つのキーワードに加えて、三菱重工グループ(特に顧客との接点が多い事業会社)では、「顧客志向性」と「現場対応力」も重視される傾向にあります(5.1参照)。
「顧客志向性」とは、常に「お客様が本当に求めているものは何か」「お客様のために何ができるか」を第一に考える姿勢です。
三菱重工の製品はBtoB(企業間取引)が中心ですが、その先には必ず社会や一般の人々がいます。
その最終的な価値を意識できるかが重要です。
「現場対応力」とは、文字通り「現場」で起こる様々な問題に柔軟かつ的確に対応する力です。
三菱重工の「現場」は、工場の製造ラインかもしれませんし、海外のプラント建設地かもしれません。
机上の空論ではなく、現実の状況(ヒト・モノ・カネ)を踏まえて最適解を導き出し、物事を前に進めるタフさが求められます。
これら2つの力は、「Active」「Balanced」「Creative」という3つの資質を、実際のビジネスシーンで発揮するための土台となると言えるでしょう。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工に向いてる・向いていない人
三菱重工が日本を代表する優良企業であることは間違いありませんが、だからといって「すべての人にとって最高の職場」とは限りません。
企業の文化や仕事の進め方には独自の特徴があり、それが自分に合うか合わないかは、入社後の満足度やパフォーマンスに大きく影響します。
例えば、三菱重工の魅力である「プロジェクトの規模の大きさ」は、裏を返せば「個人の裁量が小さく、意思決定に時間がかかる」と感じる人もいるかもしれません。
また、「社会インフラを支える」という安定感や使命感は、一方で「既存の枠組みが強く、新しいことをスピーディーに進めにくい」と感じる可能性もあります。
自分自身の価値観やキャリアプランと、三菱重工という企業が持つ特徴を照らし合わせ、ミスマッチがないかを冷静に判断することが非常に重要です。
ここでは、どのようなタイプの人が三菱重工で活躍しやすいのか、また、逆にどのような人が「向いていない」と感じやすいのか、その特徴を具体的に解説していきます。
向いている人:大規模プロジェクトで社会貢献したい人
まず、三菱重工に非常向いているのは、「大規模なプロジェクトを通じて社会に貢献したい」という強い意志を持つ人です。
前述の通り、三菱重工の仕事は、発電所、ロケット、航空機、防衛システムなど、その多くが国のインフラや安全保障に直結しています。
一つのプロジェクトが数年がかり、関わる人数も数百人から数千人規模になることも珍しくありません。
個人の成果がすぐに見える仕事よりも、大きなチームの一員として、社会に不可欠な「大きなもの」を創り上げ、支えていくことにやりがいを感じる人にとって、三菱重工は最高の環境です。
自分の仕事が、目に見える形で長期間にわたって社会の役に立つ。
その実感と誇りをモチベーションに変えられる人は、困難なプロジェクトも乗り越えて活躍できるでしょう。
逆に、自分の手掛けたものがすぐに市場に出て、消費者の反応がダイレクトに返ってくるような仕事をしたい人には、少し物足りなさを感じるかもしれません。
向いている人:最先端のものづくりと技術に挑戦したい人
「最先端のものづくりと技術に挑戦したい」という探究心旺盛な人も、三菱重工に向いています。
三菱重工は、その長い歴史の中で常に日本の「ものづくり」をリードし、数々の「日本初」「世界初」の技術を生み出してきました。
現在も、脱炭素社会の実現に向けたCO2回収技術や次世代エネルギー、宇宙開発など、人類規模の課題解決に向けた最先端の研究開発に莫大なリソースを投じています。
技術系の学生であれば、自分が大学で学んだ専門知識を活かし、さらに高めていける環境が整っています。
また、事務系の職種であっても、こうした最先端の技術をビジネスとして世界に広めていくダイナミズムに関わることができます。
技術に対するリスペクトがあり、新しい知識を学ぶことに貪欲で、それを社会実装することに情熱を注げる人。
そうした知的好奇心と挑戦意欲を持つ人は、三菱重工で大きな成長とやりがいを見つけられるはずです。
向いていない人:安定志向が強く、変化を好まない人
意外に思われるかもしれませんが、「安定志向が強すぎ、変化を好まない」人は、現在の三菱重工には向いていない可能性があります。
確かに、三菱重工は巨大な企業グループであり、経営基盤は非常に安定しています。
しかし、その事業領域であるエネルギー、インフラ、航空宇宙といった分野は、今まさに世界的な大変革の渦中にあります。
例えば、脱炭素化の波はエネルギー事業のあり方を根本から変えようとしていますし、航空分野も新たな技術革新が求められています。
このような環境下で、三菱重工は「Active」「Creative」な人材を求め、自ら変革を起こしていくことを社員に期待しています。
したがって、「一度入社すれば安泰」「言われたことだけをこなしていれば良い」という受け身の姿勢では、活躍することは難しいでしょう。
むしろ、安定した基盤の上で、自ら新しい課題に挑戦し、変化を楽しめるような人でなければ、ミスマッチを感じてしまうかもしれません。
向いていない人:個人プレーでスピーディーに成果を出したい人
「個人の裁量で、スピーディーに成果を出したい」という志向が強い人も、三菱重工の仕事の進め方にギャップを感じる可能性があります。
三菱重工が手掛けるプロジェクトは、その規模の大きさゆえに、関わるステークホルダー(関係者)が非常に多いのが特徴です。
社内の他部門はもちろん、顧客、パートナー企業、官公庁など、様々な人々と合意形成を図りながら仕事を進めていく必要があります。
これは、求める人物像の「Balanced」が重視される理由でもあります。
そのため、個人のひらめきで物事をトップダウンで進めたり、短期間で結果を出したりすることは難しい場面が多いです。
一つひとつのプロセスを丁寧に踏み、粘り強く調整を重ねていくことが求められます。
スタートアップ企業のように、若いうちから大きな裁量権を持ってスピーディーに事業を動かしたい、というタイプの人にとっては、組織の大きさや意思決定のプロセスが「堅苦しい」「遅い」と感じられるかもしれません。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工に受かるために必要な準備
三菱重工は、その知名度と安定性、仕事のスケールの大きさから、毎年非常に多くの優秀な学生が応募する、就職難易度の高い企業の一つです。
内定を勝ち取るためには、付け焼き刃の対策ではなく、綿密な準備と戦略が不可欠になります。
特に重要なのは、「なぜ他の重工業メーカーではなく、三菱重工でなければならないのか」を、自分自身の言葉で明確に語れるようにすることです。
そのためには、徹底した企業研究はもちろん、自己分析を深めて、三菱重工の求める人物像と自分の強みがどう合致するのかを論理的に説明できる必要があります。
また、選考プロセス自体は、エントリーシート(ES)、Webテスト(SPI)、複数回の面接という比較的オーソドックスなものですが、それぞれの段階で三菱重工独自の特徴があり、それに応じた対策が求められます。
ここでは、三菱重工の選考を突破するために、具体的にどのような準備をすべきか、4つの重要なポイントに絞って解説します。
徹底した企業研究と「なぜ三菱重工か」の明確化
内定獲得に向けた最も重要な準備は、「徹底した企業研究」です。
特に、前述した川崎重工やIHIといった競合他社と、三菱重工を徹底的に比較分析してください。
それぞれの強み、弱み、事業ポートフォリオの違い、最近のニュース(どの分野に注力しているかなど)を調べ上げます。
その上で、「なぜ自分は、川崎重工でもIHIでもなく、三菱重工を志望するのか」を、具体的な理由を持って説明できるようにしなければなりません。
例えば、「航空機に携わりたい」というだけでは、「それは川崎重工でもIHIでもできるのでは?」と必ず聞かれます。
そうではなく、「数ある航空機メーカーの中でも、防衛から宇宙、民間機まで最も幅広く手掛け、特に国の安全保障という領域に強く惹かれたから」といった、三菱重工ならではの魅力と自分の志向を結びつけることが重要です。
この「なぜ三菱重工か」という問いに対する答えの深さが、志望度の高さを測る最大の指標となります。
SPI(Webテスト)の徹底対策
選考の初期段階で実施されるSPI(Webテスト)は、多くの学生が通過する最初の関門ですが、ここで油断してはいけません。
三菱重工のSPIのボーダーラインは、一般的に「7割程度」と言われており、決して低くはありません(6.1参照)。
人気企業であるがゆえに、ここで一定数の応募者を絞り込む必要があるためです。
対策としては、市販のSPI対策問題集を最低でも1冊は完璧に解ききることが基本です。
特に非言語(数学)は、問題のパターンがある程度決まっているため、繰り返し練習すれば確実に点数を上げられます。
重要なのは、時間を計りながら解くことです。
SPIは時間との勝負でもあります。
1問あたりにかけられる時間を体で覚え、苦手分野を特定して集中的に克服しましょう。
性格検査については、正直に答えるのが基本ですが、求める人物像(Active, Balanced, Creative)を意識しすぎず、一貫性のある回答を心がけることが大切です。
深掘りを前提としたエントリーシート(ES)対策
三菱重工のESは、設問自体は「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」や「自己PR」など標準的なものが多いですが、その内容は面接で深く掘り下げられることを前提に作成する必要があります。
例えば、「タイトル付き自己PR」や「困難だった経験を3段階で説明する」といった、少し工夫を凝らした設問が出されることもあります(6.1参照)。
これは、単なる事実の羅列ではなく、あなたがその経験から何を学び、どのような強みを発揮したのかを、簡潔かつ論理的に伝える能力を見ているためです。
ガクチカや自己PRを書く際は、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」のSTAR法を意識し、特に「行動(Action)」の部分で、自分がどう考えて動いたのか、そのプロセスを具体的に記述しましょう。
このESが、後の面接でのあなたへの質問の「台本」となります。
面接官が「この部分をもっと詳しく聞きたい」と思うような、魅力的な内容に仕上げることが重要です。
面接:希望事業への理解と一貫性
三菱重工の面接は、通常3回程度行われます。
特に二次面接以降は、技術系であれば専門分野、事務系であれば希望する事業領域について、具体的な理解度が問われるようになります(6.1参照)。
「エナジー分野を希望します」と言うだけでは不十分です。
「エナジー分野の中でも、なぜガスタービンなのか、それともCO2回収技術なのか」「その事業が今直面している課題は何だと思うか」といった、深い質問に答えられるよう準備しておく必要があります。
そのためにも、企業研究の段階で、自分がどのセグメントで何をしたいのかを明確にしておくことが不可欠です。
また、最終面接では、ESから面接全体を通しての「一貫性」が厳しくチェックされます。
ESでアピールした強みと、ガクチカでの行動、そして志望動機がすべて一つの線で繋がっているか。
そして、それが三菱重工の求める人物像(Active, Balanced, Creative)と合致しているか。
この一貫したストーリーを、自信を持って自分の言葉で語れるかどうかが、内定への最後の鍵となります。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工の志望動機の書き方
三菱重工の選考において、志望動機は合否を分ける最も重要な要素の一つです。
なぜなら、先に述べた通り、競合他社も似たような事業を手掛けている中で、「なぜ三菱重工でなければならないのか」を説得力を持って伝えられなければ、面接官に「他の会社でも良いのでは?」と思われてしまうからです。
単に「社会インフラを支えたい」や「最先端の技術に触れたい」といった抽象的な理由だけでは不十分です。
重要なのは、①三菱重工のどの部分に魅力を感じているのか(事業内容、技術力、企業風土など)を具体的に示し、②それが自分のどのような経験や価値観と結びついているのかを明らかにし、③その結果として入社後に何を成し遂げたいのかを明確に語ることです。
この3つの要素が論理的に繋がった志望動機こそが、面接官の心を動かします。
ここでは、三菱重工に響く志望動機を構築するための、4つの具体的なステップと書き方のポイントを解説します。
「なぜ重工業界か」を明確にする
志望動機を作成する最初のステップは、「なぜ自分は、数ある業界の中で、特に重工業界に興味を持ったのか」を明確にすることです。
例えば、自動車メーカーや電機メーカーではなく、なぜ発電プラントや航空宇宙といった、より大規模で、社会の基盤となる「ものづくり」に惹かれるのか。
その原体験を振り返ってみましょう。
それは、幼少期に見たロケットの打ち上げかもしれませんし、大学での研究を通じてエネルギー問題の重要性に気づいたことかもしれません。
「日本の技術力で世界に貢献したい」「目に見える形で人々の生活を長期間支える仕事がしたい」といった、あなたが重工業界に感じる「ロマン」や「使命感」を、まずは自分の言葉で整理することがスタートラインです。
この「業界への志望理由」がしっかりしていないと、その後の「企業への志望理由」も説得力を欠いてしまいます。
「なぜ三菱重工か」を競合比較で差別化する
次に、重工業界の中でも「なぜ三菱重工なのか」を、競合他社(川崎重工、IHIなど)との比較を通じて明確にします。
これは選考対策の核となる部分です。
例えば、同じ「航空宇宙」分野に興味がある場合でも、三菱重工は防衛分野やロケット(H-IIA/B, H3)といった国家プロジェクトに深く関わっている点が強みです。
もし、その「国の安全保障や宇宙開発への貢献」という側面に強く惹かれるのであれば、それは川崎重工やIHIにはない、三菱重工を志望する強力な理由になります。
また、「エネルギー」分野であれば、三菱重工が世界トップクラスのシェアを持つガスタービン技術や、先進的なCO2回収技術に焦点を当て、「脱炭素社会の実現という大きな課題に、最も影響力のある立場で挑戦したいから」と具体化することができます。
このように、他社にはない三菱重工独自の強みと、自分のやりたいことを結びつけることが不可欠です。
求める人物像と自身の経験を結びつける
志望動機には、あなたが三菱重工の求める人物像(Active, Balanced, Creative)に合致する人材であることも、具体的に盛り込む必要があります。
ただ「私はActiveです」と言うのではなく、学生時代の経験(ガクチカ)を引用しながら、その資質をどう発揮したのかを証明します。
例えば、「大学の研究で前例のない課題に直面した際、自ら計画を立て、周囲の研究室も巻き込みながら(Active, Balanced)、粘り強く試行錯誤を繰り返して(Active)、新しい解決策を導き出した(Creative)経験がある。
この強みは、貴社の困難なプロジェクトを推進する上で必ず活かせると考えている」といった形です。
このように、自分の過去の行動事実と、三菱重工が求める資質をリンクさせることで、志望動機に説得力と具体性を持たせることができます。
あなたの強みが、入社後にどう貢献できるのかを明確に示しましょう。
入社後に実現したいことを具体的に示す
最後に、志望動機の締めくくりとして、「三菱重工に入社したら、何を成し遂げたいのか」という将来のビジョンを具体的に示します。
これは、あなたの入社意欲の高さと、キャリアプランの明確さを伝える上で非常に重要です。
ただし、あまりに壮大すぎたり、現実離れしていたりする内容は逆効果です。
まずは、自分が希望する事業分野で、どのような仕事に挑戦したいかを述べましょう。
例えば、「エナジーセグメントにおいて、まずはガスタービンの設計(あるいは営業)として経験を積み、将来的には、私が大学で学んだ〇〇の知見も活かしながら、水素ガスタービンのような次世代エネルギーソリューションの普及に貢献したい」といった形です。
このように、地に足のついた具体的な目標を語ることで、面接官はあなたが自社で活躍する姿をイメージしやすくなります。
「この学生と一緒に働きたい」と思わせることがゴールです。
【三菱重工はなんの会社】三菱重工についてよくある質問
ここまで三菱重工の事業内容や選考対策について詳しく解説してきましたが、就活生の皆さんからは、ほかにも様々な質問をいただきます。
特に多いのが、「実際、年収はどのくらいもらえるの?」「社風はやっぱり堅いの?」「福利厚生は充実してる?」「学歴フィルターって本当にあるの?」といった、リアルな働き方や待遇に関する疑問です。
これらは、入社後のミスマッチを防ぎ、長く働き続ける上で非常に重要な情報ですよね。
確かに、三菱重工は歴史ある大企業であり、世間一般のイメージもあるかと思います。
しかし、実際のところはどうなのか、最新の情報を知りたいという方も多いでしょう。
ここでは、就活生の皆さんが特に気になる、三菱重工に関する「よくある質問」4つに、就活アドバイザーの視点から具体的にお答えしていきます。
年収はどのくらいですか?
年収に関しては、就活生が最も気にするポイントの一つでしょう。
三菱重工の平均年収は、有価証券報告書や口コミサイトなどを見ると、一般的に850万円〜900万円程度(※平均年齢40歳前後)とされており、日本の製造業全体で見てもトップクラスの高い水準にあります。
ただし、これは全社員の平均値です。
新卒入社の場合、初任給は他の大手メーカーと同水準ですが、その後の昇給カーブが異なります。
口コミなどによれば、若手のうちは残業代にもよりますが、昇給は比較的緩やかで、同期との差も出にくい傾向にあるようです。
しかし、30代中盤頃から主任クラスになると昇給幅が大きくなり、そこから管理職へとステップアップしていくにつれて、他社との年収差が顕著になってくると言われています(8.1参照)。
安定した給与体系と、成果や役職に応じた昇給が期待できる、非常に恵まれた環境であることは間違いないでしょう。
社風や働きやすさはどうですか?
社風については、「歴史ある大企業だから、堅くて上下関係が厳しいのでは?」とイメージする方もいるかもしれません。
実際、手掛ける製品が社会インフラや防衛といったミスの許されない分野であるため、仕事に対する真面目さや堅実さ、プロセスを重視する文化は根付いています。
しかし、選考時の面接官の雰囲気が「温かい」「穏やか」であったという声も多く(3.1)、理不尽な体育会系というわけではありません。
むしろ、大規模なプロジェクトを動かすために、関係各所との「調整」や「協調」を重んじる「Balanced」な社風とも言えます。
働きやすさに関しては、大企業ならではの制度が充実しています。
フレックスタイム制(勤務地による)の導入や、有給休暇の取得も推進されています。
競合他社との比較では、「風通しの良さは川崎重工の方がある」といった意見も見られますが(4.1)、三菱重工も働き方改革には積極的に取り組んでいます。
福利厚生は充実していますか?
福利厚生の充実度は、三菱重工の大きな魅力の一つです。
日本の大企業の中でもトップレベルと言えるでしょう。
まず、独身寮や社宅が完備されており、若手社員は非常に安価な家賃で生活することができます。
これは可処分所得に直結するため、大きなメリットです。
また、住宅購入時の財形貯蓄制度や社員持株会など、資産形成をサポートする制度も整っています。
特に注目すべきは、育児と仕事の両立支援です。
育児休業は子どもが最長3歳になるまで取得可能で、復職率は100%というデータもあります(3.2)。
男性社員の育休取得も増えています。
その他、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)などもあり、社員が安心して長く働き続けられるための基盤が、あらゆる面で手厚く整備されていると言えます。
この福利厚生の手厚さが、三菱重工の安定性や社員を大切にする姿勢の表れとも言えるでしょう。
採用大学や学歴フィルターはありますか?
「三菱重工は高学歴でないと入れないのでは?」という不安を持つ学生も多いですが、結論から言うと、明確な「学歴フィルター」はないと考えられます。
採用実績を見ると、旧帝大(東大、京大、阪大、東北大など)や早慶といった、いわゆる難関大学の出身者が多いことは事実です(6.1参照)。
これは、技術系の専門職などでは高度な専門知識が求められるため、結果としてそれらの大学からの採用が多くなっている側面があります。
しかし、採用実績校には全国の国公立大学や私立大学、地方大学の名前も多数含まれています。
重要なのは、大学名そのものよりも、あなたが学生時代に何を学び、どのような経験をし、三菱重工が求める人物像(Active, Balanced, Creative)にどれだけ合致しているかです。
SPIで必要な点数をクリアし、ESと面接で自分の強みと熱意をしっかりと伝えられれば、出身大学に関わらず内定のチャンスは十分にあります。
まとめ
今回は、日本を代表する総合重工業メーカー「三菱重工」について、「なんの会社」なのか、その具体的な仕事内容から、求める人物像、そして内定を勝ち取るための選考対策まで、詳しく解説してきました。
三菱重工は、「陸・海・空・宇宙」の幅広い領域で、エネルギー、インフラ、防衛といった社会の根幹を支える、非常にスケールの大きな仕事をしている会社です。
その選考を突破するためには、「なぜ競合ではなく三菱重工なのか」を徹底的に突き詰め、あなたの経験と求める人物像(Active, Balanced, Creative)を一貫したストーリーとして語ることが不可欠です。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート