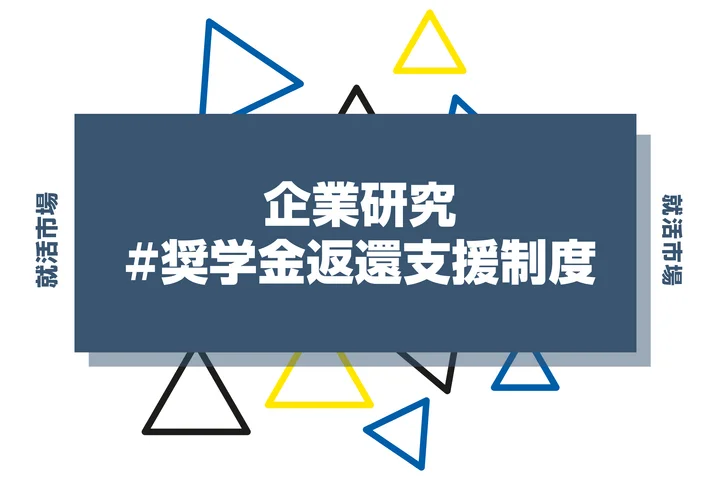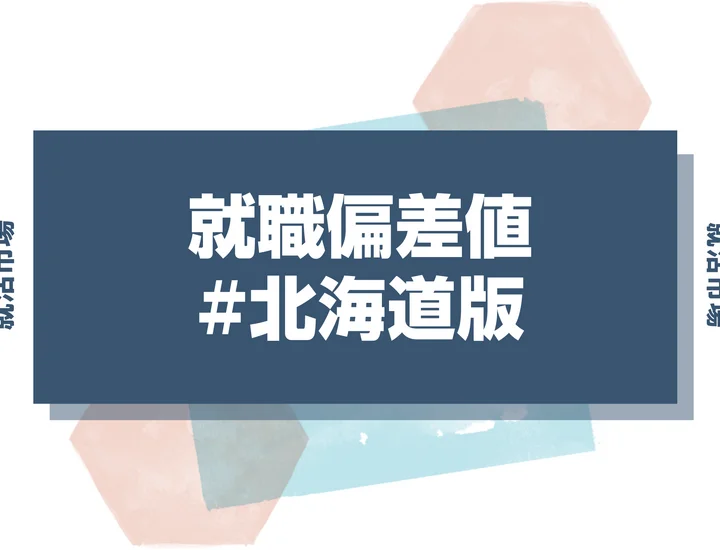はじめに
奨学金を利用して大学生活を送る学生にとって、社会人になってから始まる返済は大きな負担になります。
特に物価上昇や生活費の増加も重なり、不安を感じている人も多いでしょう。
その中で注目されているのが奨学金返還支援制度です。
近年は大企業を中心に導入が進んでおり、若手人材の確保や定着につながる福利厚生として位置付けられています。
本記事では大企業の奨学金返還支援制度をテーマに、その仕組みや導入状況、活用の方法を詳しく解説していきます。
【奨学金返還支援制度 大企業】制度の基本理解
奨学金返還支援制度は、企業が従業員に代わって返済を行う、もしくは補助を行う仕組みです。
制度の理解は就活で企業を見極める際の重要なポイントになります。
この章では制度の仕組み、対象となる奨学金の種類、税制や課税面での注意点を整理し、就活生が正しく判断できるよう解説します。
制度の仕組みと種類を理解する
奨学金返還支援制度には大きく分けて二つのタイプがあります。
一つは企業が直接日本学生支援機構へ返済を行う代理返還制度、もう一つは企業が社員に手当を支給する補助型です。
代理返還は確実に負担を減らせる仕組みであり、社員の口座からの引き落としが不要になる点が特徴です。
一方、補助型は給与に上乗せされるため、見かけ上は返済支援を受けながらも所得に含まれるため課税対象となります。
どちらの制度も若手社員の経済的負担を軽減する目的で導入されていますが、その内容は企業ごとに異なります。
そのため、就活生は求人票や説明会で詳細を確認することが欠かせません。
対象となる奨学金と返還方法の違い
奨学金には一種と二種が存在します。
一種は無利子ですが、審査には厳しい条件があります。
一方で二種は利子がある代わりに一種よりも審査の条件は緩くなります。
また、変換方法の違いも理解しておきましょう。
企業が奨学金返済を支援する場合、新制度の代理返還と旧制度の補助返還があるからです。
| 返還方法 | 制度内容 |
| 代理返還 | 企業が従業員の奨学金を直接返還する |
| 補助返還 | 企業は従業員に対して奨学金の手当を支給する |
2021年4月から企業が従業員の奨学金を直接返還することが可能になりました。
結果、従業員の返還漏れや返還手続きの手間がなくなります。
直接返還するには一定の条件をクリアする必要があるため、志望企業がどちらを採用しているのか確認してください。
参考:企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度 | 独立行政法人日本学生支援機構
税制や課税上の注意点
奨学金の代理返還と補助型では税法上に違いがあります。
同じ制度だと認識すると手元に残るお金の違いで損した気分になるので注意してください。
| 返還方法 | 税法上の違い |
| 代理返還 | 給与とは別の扱い 給与所得はそのままであるため支払う税金は増えない |
| 補助返還 | 給与所得に換算される 社会保険料が増加するため手元に残る金額が減少する |
計算例
*月15,000円を返還する場合
*社会保険料15%、所得税・住民税を5%として計算
代理返還
月給:20万円
支給額:0円
手取り額:161,500円
補助返還
月給:20万円
支給額:15,000円
手取り額:158,612円
代理返還と補助返還では毎月2,888円の差があります。
年間に直すと34,656円となり、大きな違いがあることを理解しておきましょう。
【奨学金返還支援制度 大企業】導入が進む背景
大企業で奨学金返還支援制度の導入が進む背景には複数の要因があります。
人材確保や離職防止といった経営上の課題に加え、社会的責任を果たす取り組みとしての意義も強調されています。
さらに国や自治体による後押しが進んでいることも制度普及を後押ししています。
この章では、企業が制度導入を決める理由を三つの観点から整理し、理解すべき背景を明らかにします。
人材確保と離職防止の観点
多くの大企業が奨学金返還支援制度を導入する最大の理由は人材確保と定着にあります。
若手社員の経済的負担を軽減することで、入社後の生活を安定させ、離職率を下げる効果が期待できます。
特に近年は人手不足の業界も多く、企業は魅力的な福利厚生を用意して優秀な学生を採用しようとしています。
制度があること自体が採用広報のアピールポイントになり、学生から選ばれる企業になるための差別化要素となっています。
就活生にとっても、この制度がある企業は安心感を持って働ける環境を提供していると言えます。
安定したキャリア形成を求める学生にとって制度導入は大きな魅力となるのです。
社会的責任やCSRとしての位置付け
奨学金返還支援制度は単なる福利厚生ではなく、企業が果たすべき社会的責任の一部と位置付けられています。
学生の経済的負担を軽減する取り組みは、教育機会の公平性を支えるものであり、社会的意義が高いと評価されています。
特に大企業は株主や顧客からの信頼を得るためにCSR活動を重視しており、その一環として制度を導入するケースが増えています。
社会全体に対して価値を提供する姿勢は、企業ブランドの向上にもつながります。
就活生にとっては、社会貢献を重視する企業文化を見極める視点としても参考になるでしょう。
制度の有無は企業がどのような理念を持っているかを示す指標にもなります。
政策的な後押しと今後の広がり
奨学金の支援制度が広まる背景には国や自治体の後押しもあります。
内閣官房が令和6年に公表した「地方公共団体における奨学金返還支援取組状況について」によると、奨学金返還支援の取組を実施している地方公共団体数は増加傾向にあります。
令和元年では32府県349市区町村でした。
しかし、令和6年には47都道府県816市区町村にまで増加しています。
支援金額も年々上昇し、利用人数も増加しています。
今後は、奨学金の返済が滞る社会問題の解決や従業員の定着率向上を目的とし、返還制度を採用する企業は増加していくでしょう。
奨学金の返済を心配している就活生にとって、働きやすい環境が整備されつつあることを覚えておくことで、就活が安心して継続できます。
参考:地方公共団体における奨学金返還支援取組状況について|内閣官房
【奨学金返還支援制度 大企業】導入企業の事例
奨学金返還支援制度はすでに多くの大企業で導入が進んでいます。
制度の形は企業ごとに異なり、支援金を節目に支給するものから毎月補助を行うものまでさまざまです。
ここでは具体的な導入企業の事例を取り上げ、就活生が企業研究をする際に参考になるよう整理します。
業界の違いや支援方法の特色を把握することで、自分に合った企業選びにつなげることができます。
建設業界
建設業界のうち、積極的に奨学金支援を実施している企業は以下の3社です。
独立行政法人日本学生支援機構が公開している企業数は400社を超えるため、一部の紹介となります。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| イガリ建設株式会社 | 上限3万円 | 上限288万円まで | 既卒3年以内 期間は最長8年間 |
| 東陽工業株式会社 | 上限1万円 | 上限60万円まで | 試用期間終了後 |
| 株式会社冨士土木 | 上限2万円 | 上限400万円まで | 満40歳まで |
建設業界は、入職者数の減少と高齢化によって人手不足が慢性化しています。
新卒かつ若い人材を受け入れるためにも奨学金返還の支援に力を入れています。
建設は、国家の基盤を支える大切な業界です。
技術者を育成し、後世に技術を伝えるためにも、多くの企業が奨学金の返還を支援しています。
金融業界・保険業界
金融業界・保険業界のうち、積極的に奨学金支援を実施している企業は以下の3社です。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 姫路信用金庫 | 1年目〜:7,000円 6年目以降:1万円 | 上限162万円 | 特記なし |
| KOYO証券株式会社 | 社内規定による | 上限90万円 | 特記なし |
| 有限会社 シンプルプラン | 2万円 | 上限240万円 | 正社員 選考を突破した人 |
金融業界・保険業界は、高度な金融知識、リスク分析能力、法務・税務の専門知識を持つ人材を求めています。
優秀な人材を早期に確保するためにも奨学金返還支援を実施しました。
たとえば、理系の大学院に進学した就活生が該当します。
学費が高額になりやすいため、企業が返還を支援することで採用を有利に進めています。
製造業界
製造業界のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
150社以上あるため一部の紹介になります。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 王子製鉄株式会社 | 上限15,000円 | 上限200万円 | 自分で返還している 返還上限15年 |
| 株式会社OA研究所 | 上限2万円 | 上限192万円 | 入社から8年以内 |
| 樫山工業株式会社 | 上限3万 | 上限180万円 | 正社員or嘱託社員 |
製造業界は、全産業と比較して技能労働者(職人)や技術者(現場監督など)の高齢化が顕著です。
2025年問題(団塊の世代の引退)に直面しており、技術やノウハウの伝承が急務となっています。
奨学金の返還を支援することで業界のイメージアップを図っています。
卸売業・小売業
卸売業・小売業のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 株式会社ベルク | 最大15,000円 | 最大180万円 | 新入社員を対象 最大10年 |
| 日産東京販売 株式会社 | 2万円 | 最大240万円 | 整備学校を卒業した新卒者のみ |
| 株式会社 カネスエ商事 | 上限15,000円 | 上限180万円 | 入社10年未満かつ 満35歳未満 |
小売業は土日祝日の勤務、卸売業では深夜・早朝のシフト制が一般的です。
しかし、不規則な勤務が若者のライフスタイルと合わず、早期離職の原因になっています。
そこで、奨学金を支援する仕組みを作ることで離職防止に努めています。
不動産業界
不動産業界のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 三光ソフラン 株式会社 | 2万円 | 上限240万円 | 期間:最長10年 |
| 大東建託株式会社 | 10万円/年 | 最大5年で50万円 | 入社5年目まで |
| エスリード賃貸 株式会社 | 1万円 | 上限60万円 | 特記なし |
不動産業界は、宅地建物取引士(宅建士)などの専門資格を持つ人材は引く手あまたです。そこで、経済的な支援は採用における強力な差別要因になります。
不動産業界は成果主義や長時間労働のイメージから、新卒の初期離職率が高い傾向です。
奨学金支援は、若手社員の経済的な不安を解消し、仕事に集中できる環境を提供することで、定着率の向上を目指しています。
サービス業界
サービス業界のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
サービス業界は該当する企業数が100を超えるため一部を抜粋しています。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| ALSOK株式会社 | 最大18,000円 | 最大1,080,000円 | 入社5年以内の社員 |
| 日章警備保障 株式会社 | 20,000円 | 上限240万円 | 特記なし |
| 株式会社 小田急ビルサービス | 最大12万/年 | 最大60万円 | 勤続1年以上6年未満 |
サービス業界は不規則な勤務形態になりがちです。
土日に出勤したり、深夜に勤務したりもあります。
ワークライフバランスを支援するためにも企業は奨学金の一部を返還し始めました。
医療・福祉業界
医療・福祉業界のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
医療・福祉業界は高齢化に伴い、需要が増加しています。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 医療法人社団永生会 | 返還額と同額 | 上限300万円 | 正社員のみ |
| 株式会社 ユニスマイル | 上限5万円 | 上限240万円 | 社内規定あり |
| ねごろ歯科医院 | 上限3万円 | 上限36万円 | 正社員のみ |
医療系の専門職(看護師や薬剤師、医師など)になるための教育は、一般の学部に比べて学費が高額です。
そこで、奨学金を支援することで経済負担を軽減する狙いがあります。
地方の医療機関や過疎地域の病院では、都市部へ流出する人材を食い止め、地域医療の担い手を確保する意味もあります。
情報通信業界
情報通信業界のうち、奨学金返還を支援している企業は以下の3社です。
インターネットの普及に伴い、企業数が増加しています。
新しい業界ではありますが、積極的に支援する仕組みがあります。
| 企業名 | 返還支援額 | 返還支援総額 | 返還条件 |
| 京葉システム 株式会社 | 上限1万円 | 上限36万円 | 特記なし |
| 東海テレビ放送 株式会社 | 上限2万円 | 総額200万円まで | 期間:最大10年 満35歳まで |
| 株式会社中国新聞社 | 12万円/年 | 最大36万円 | 入社3年目かつ 満30歳まで |
5GやIoT、AIなどの登場により、情報通信業界は社会インフラとして不可欠です。
急速なデジタル化を支えるためにシステムエンジニア(SE)やプログラマー、ネットワークエンジニアなどの需要が増しています。
しかし、需要に対して人材が不足しており、採用が喫緊の課題です。
奨学金の返還を支援することで、将来的に企業の中核を担う人材を集めています。
【奨学金返還支援制度 大企業】制度を活用するメリット
奨学金返還支援制度を導入している大企業で働くことには、経済的な安心感だけでなくキャリア形成における強みもあります。
返済負担の軽減により生活が安定すること、将来設計に前向きになれること、さらに他の福利厚生と比較しても魅力的な制度であることが挙げられます。
ここでは制度を活用する三つのメリットを整理し、就活生が企業研究を行う際に注目すべき観点を示します。
返済負担の軽減と生活による安定
奨学金返還支援制度の最大のメリットは、返済負担の軽減によって生活の安定が得られる点です。
毎月数万円に及ぶ返済額が補助されることで、家計に余裕が生まれます。
これにより貯蓄や趣味、自己投資に資金を回すことが可能となり、社会人としての生活に安心感を持てます。
経済的な不安が少ない環境は仕事への集中力を高め、結果的にパフォーマンスの向上にもつながります。
就活生にとっても、社会人生活のスタートをスムーズにする重要な要素といえます。
安心した生活基盤を築けることは制度活用の大きな魅力です。
キャリア形成における安心感
奨学金返還支援制度があることで、キャリア形成における安心感も得られます。
返済への不安が減ることで、新しい挑戦やスキル習得に意欲的になれるからです。
経済的な制約が少なくなることで、長期的なキャリアプランを描く余裕が生まれます。
また、制度を提供する企業は社員の成長を支援する姿勢を持っていることが多く、教育研修やキャリア開発の制度とあわせて利用できる場合もあります。
就活生にとっては、働きながら将来の可能性を広げるための大きな後押しとなるでしょう。
挑戦を後押しする環境が整う点は就職先選びの判断材料となります。
企業選びに迷った際の判断材料になる
奨学金の返還支援制度があることで、企業選びに迷った際の判断材料になります。
企業を比較することで、働きやすい環境かどうか決断しやすくなるからです。
たとえば、毎月2万円を支援してくれる企業があったとします。
1年間で24万円です。
つまり、支援制度がない企業と比較して年間24万円の差が生まれます。
24万円があれば趣味や自己投資に利用することが可能です。
不動産業界なら資格を取得することで、給与をアップさせられます。
さらに、情報通信業界なら最新技術に触れたり、勉強したりする機会があるでしょう。
同じ業界や業種の場合、比較する材料が少ないと決断するのが困難です。
そこで、奨学金の返還制度を調べておくことで、入社に迷った際の判断材料になります。
【奨学金返還支援制度 大企業】利用時の注意点
奨学金返還支援制度は魅力的な福利厚生ですが、利用する際には注意すべき点があります。
支援を受ける条件や勤続年数の制約、離職や転職時の扱い、さらには制度の有無だけで企業を判断しない姿勢が大切です。
この章では制度利用に伴う三つの注意点を整理し、就活生が失敗なく制度を活用するための視点を提供します。
勤続年数や条件に伴う制約
奨学金返還支援制度は勤続年数や雇用形態などに条件が設けられている場合が多いです。
例えば入社から数年間勤務した社員のみ対象とするケースや、正社員に限定している企業もあります。
このような条件を満たさなければ支援を受けられないため、就職前に詳細を確認する必要があります。
また、一部の企業では支援額に上限があり、全額が補助されるわけではありません。
就活生は支援制度の有無だけでなく、利用可能となるタイミングや条件を理解しておくことが重要です。
利用条件の明確化を事前に把握することが失敗を避けるポイントです。
離職時や転職時の制度の扱い
奨学金返還支援制度は勤続を前提として設計されているため、離職や転職の際に注意が必要です。
企業によっては一定期間内に退職すると支援を受けた分を返還しなければならないケースもあります。
また、転職先では同様の制度が導入されていない可能性も高く、結果的に返済負担が再び重くなることも考えられます。
キャリアの選択肢を広げるうえでは、制度だけに依存しない姿勢が求められます。
就活生にとっては、制度を利用しつつも将来のキャリアプランを柔軟に描くことが大切です。
退職時のリスクを理解しておくことで安心して制度を活用できます。
制度の有無だけで企業を判断しない視点
奨学金返還支援制度は魅力的ですが、制度の有無だけで企業を選ぶのはリスクがあります。
企業文化や仕事内容、成長環境、その他の福利厚生なども総合的に判断材料にする必要があります。
制度があるからといって必ずしも自分に合った働き方ができるわけではありません。
また、奨学金以外の支援制度やキャリア形成の仕組みが充実している企業も数多く存在します。
就活生は奨学金返還支援制度を一つの指標としつつ、全体的な環境を見極めて選択することが重要です。
総合的な企業研究を行うことが後悔しない就活につながります。
【奨学金返還支援制度 大企業】就活での活かし方
奨学金返還支援制度を理解するだけでなく、就活にどう活かすかを考えることが重要です。
制度が導入されているかを確認する方法、志望動機に組み込む工夫、そして他のキャリア要素とのバランスを取る姿勢が就活生には求められます。
ここでは就活で役立つ三つの視点を整理し、実際の行動につなげるポイントを紹介します。
企業説明会や面接で確認すべき質問
奨学金返還支援制度を就活で意識するなら、企業説明会や面接の場で積極的に質問することが重要です。
例えば「支援対象となる奨学金の種類」「利用開始時期」「勤続年数の条件」「代理返還か補助型か」といった具体的な点を確認しましょう。
これらを事前に理解することで、制度の実態を把握しやすくなります。
また、説明会で質問する姿勢は企業への関心を示すことにもつながります。
就活生にとって、疑問を解消しながら選択肢を広げる行動は大きな意味を持ちます。
積極的な質問姿勢は制度理解と自己アピールの両方に役立ちます。
志望動機に制度を盛り込む工夫
奨学金返還支援制度は志望動機に取り入れることも可能です。
ただし、制度そのものを目的にするのではなく、企業の姿勢や価値観と結び付けて表現することが大切です。
例えば「社員の成長を支援する制度に魅力を感じた」「経済的な安心が挑戦を後押しすると考えた」といった形で言及すると自然です。
制度を通じて企業の魅力を理解していることを示せば、志望度の高さを伝えられます。
就活生にとっては、他の就活生との差別化にもつながる表現方法です。
制度を価値観と結び付ける工夫が評価につながります。
制度とキャリア要素のバランスを取る方法
奨学金返還支援制度は魅力的ですが、それだけで企業を決めるのはリスクがあります。
キャリア形成に必要なスキル習得の機会や、働きやすさを左右する勤務制度、他の福利厚生も含めて総合的に判断することが大切です。
制度を一つの軸としつつも、仕事内容や将来の成長可能性を加味して選択する姿勢が求められます。
また、将来的に転職やキャリアチェンジを考える際も、制度だけに依存しない考え方が必要です。
就活生は、自分のライフプランと制度の相性を見極めて判断することが賢明です。
バランスの取れた視点を持つことで後悔のない選択が可能になります。
【奨学金返還支援制度 大企業】他に注目すべき福利厚生
奨学金返還支援制度は魅力的ですが、大企業ではそれ以外にも学生にとって価値のある福利厚生が数多く用意されています。
住宅手当や家賃補助、柔軟な働き方を支える制度、さらには出産育児に関連するサポートなどは、将来の生活設計に直結する重要な要素です。
この章では、奨学金以外の福利厚生に焦点を当て、就活生が企業研究を進めるうえで見ておくべきポイントを紹介します。
住宅手当や家賃補助の充実度
大企業では住宅手当や家賃補助を福利厚生として導入しているケースが多いです。
特に都市部で一人暮らしをする場合、家賃は大きな負担となるため、この制度の有無は生活に直結します。
住宅手当があることで、給与から家賃を差し引いた可処分所得が増え、安心して生活できます。
また、社宅や寮を提供している企業もあり、金銭的な支援だけでなく生活環境の安定にもつながります。
就活生にとっては、奨学金返済の支援と同じくらい重要な判断材料になります。
生活基盤を支える制度として住宅関連の福利厚生は注目すべきです。
リモートワークやフレックス制度
柔軟な働き方を可能にするリモートワークやフレックス制度も、大企業で導入が広がっています。
これらの制度は時間や場所にとらわれず働けるため、ワークライフバランスの改善に直結します。
特に今の世代は働き方に多様性を求める傾向があり、こうした制度の有無は企業選びの重要な軸となります。
業界によって導入状況に差はありますが、近年はITや金融だけでなくメーカーやインフラでも取り入れられるようになってきました。
奨学金返済支援と組み合わせることで、経済面と生活面の両立が図れます。
柔軟な働き方の実現は長期的なキャリア形成にもプラスです。
出産育児支援やキャリア形成サポート
出産や育児を支える制度は、大企業ならではの強みの一つです。
産前産後休暇や育児休業の取得推進に加え、時短勤務や保育費補助なども充実しています。
また、社員のスキルアップを後押しする教育研修制度や資格取得支援も、キャリア形成に直結する福利厚生です。
こうした制度が整っている企業は、ライフステージの変化に対応しながら働き続けやすい環境を提供しています。
就活生にとっても将来を見据えた安心感を得られるポイントになります。
長期的に働ける仕組みを備えているかどうかは必ず確認しておきましょう。
まとめ
奨学金返還支援制度は、就活生にとって経済的な不安を軽減し、安心してキャリアを築くための大きな助けとなります。
制度の仕組みや導入背景を理解し、具体的な企業事例やメリット、注意点を把握することで、就活における判断材料を増やすことができます。
また、奨学金以外の福利厚生にも注目し、総合的に企業を比較検討することが重要です。
制度の有無だけにとらわれず、自分のキャリア設計やライフプランと結び付けて考えることで、後悔のない企業選びが可能になります。
就活生は、奨学金返還支援制度を一つの指標としながらも、幅広い視点を持って未来を見据えることが大切です。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート