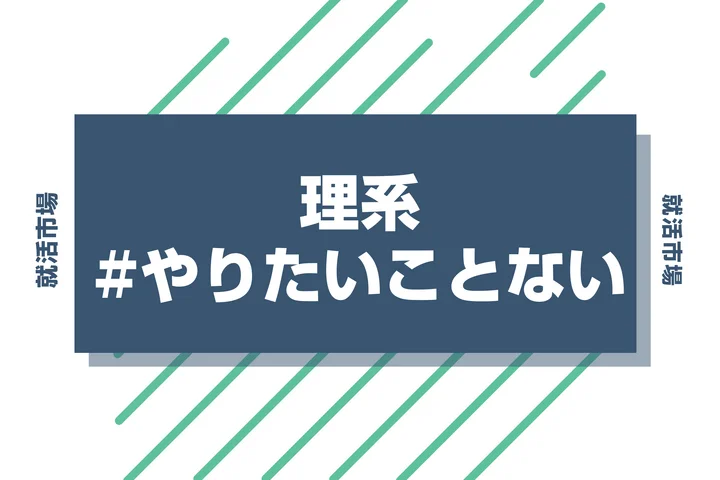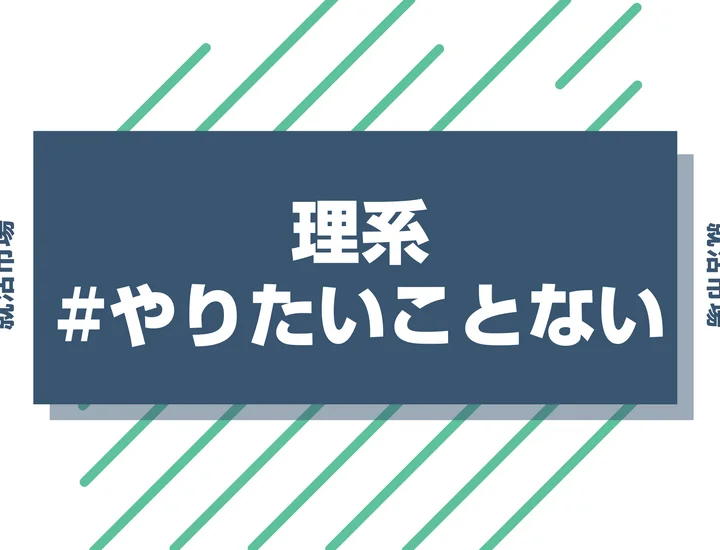目次[目次を全て表示する]
はじめに
理系学生の皆さん、就職活動を前にして、自分にはやりたいことがないと悩んでいませんか。
専門的な知識を学んできたからこそ、その分野で活躍しなければならないというプレッシャーを感じ、周りの友人たちが明確な目標に向かって進んでいる姿を見ると、一層焦りを感じてしまうかもしれません。
しかし、やりたいことが今すぐに見つからないからといって、自分を責める必要は全くありません。
この記事では、なぜやりたいことが見つからないのか、その原因を探りながら、自分らしいキャリアを見つけるための具体的なヒントを、自己分析から大学生活の活用法、今すぐできる行動まで、幅広くご紹介します。
焦らず、自分のペースで将来を考える一歩を踏み出しましょう。
なぜ「やりたいこと」が見つからないのか
理系学生がやりたいことないと感じるのは、決して珍しいことではありません。
多くの場合、やりたいことという言葉をあまりにも壮大に捉えすぎているか、あるいは自分と向き合う時間が不足していることが原因です。
就職活動では、やりたいことを明確に語ることが求められる場面が多く、それが見つからない自分はダメだと感じてしまうかもしれません。
しかし、大切なのは完璧な答えを最初から用意することではありません。
この記事を通じて、まずはそのプレッシャーから自分を解放し、小さな興味や関心から視野を広げていく方法を探っていきましょう。
「やりたいこと」がなくても焦らなくていい
就職活動が本格化してくると、周りの友人たちが次々とインターンシップに参加したり、志望業界を熱心に語ったりする姿が目に入り、やりたいことがない自分に強い焦りを感じてしまうかもしれません。
しかし、その焦りは一旦横に置いて、深呼吸してみましょう。
そもそも、学生のうちに人生を捧げたいと思えるほど明確なやりたいことを見つけている人の方が少ないのです。
多くの社会人は、実際に働き始めてから、様々な経験を積む中で、徐々に自分のやりたいことや目指す方向性を見つけていきます。
ですから、現時点で明確な目標がないからといって、悲観的になる必要は全くありません。
大切なのは、周りと比べて焦ることではなく、自分の心と向き合い、小さな興味や関心の種を見つけることです。
今は、視野を広げるための準備期間だと捉え、これから紹介する方法を参考に、じっくりと自分自身を探求する時間に使ってみてください。
「やりたいこと」=「人生の目標」ではない
やりたいことない、と悩む理系学生の多くは、やりたいことを人生を懸けるほどの壮大な目標でなければならない、と思い込んでいる傾向があります。
例えば、世界を変えるような発明をしたい、ノーベル賞級の研究を成し遂げたい、といった大きな目標ばかりを想像してしまうと、現実とのギャップに苦しみ、何も見つけられなくなってしまいます。
しかし、仕事におけるやりたいこととは、もっと身近で、日々の業務の中に存在するものです。
例えば、自分が設計したものが製品として世に出ることが嬉しい、チームで協力して難しい課題を乗り越えることに達成感を感じる、自分の専門知識を活かして顧客の問題を解決するのが楽しい、といったことも立派なやりたいことです。
壮大な目標を掲げるのではなく、まずは自分が仕事を通じてどのような状態でありたいか、何に喜びや充実感を感じるのか、という視点で考えてみましょう。
そうすることで、やりたいことのハードルが下がり、自分なりの答えが見つけやすくなるはずです。
「やりたいこと」と「好きなこと」の違い
やりたいことが見つからない原因の一つに、やりたいことと好きなことを混同しているケースが挙げられます。
この二つは似ているようで、実は大きな違いがあります。
好きなこととは、主に自分が楽しむための、消費者としての視点に立った活動を指します。
例えば、ゲームをプレイすること、音楽を聴くこと、スポーツを観戦することなどがこれにあたります。
これらは受動的な活動であり、趣味や娯楽として生活を豊かにしてくれます。
一方で、仕事におけるやりたいこととは、自分のスキルや知識を使って誰かに価値を提供し、その対価として報酬を得る、生産者としての活動を指します。
ゲームが好きだからといって、ゲームを開発する仕事がやりたいこととは限りません。
好きなことを仕事にする道もありますが、それが必ずしも幸せに繋がるとは限らないのです。
まずは、自分が好きなことと、仕事として取り組みたいことを分けて考えることで、キャリアの選択肢をより客観的に見つめ直すことができます。
「好き」と「得意」は別物
自己分析を進める上で、好きという感情と、得意という能力を区別して考えることは非常に重要です。
好きという感情は、物事に取り組む上でのモチベーション、つまりエンジンのような役割を果たします。
自分が心から好きだと感じることには、自然とエネルギーを注ぐことができます。
一方で、得意なこととは、他人よりも少ない労力で、高い成果を出すことができる能力を指します。
理系学生であれば、論理的に物事を考えること、数値を扱うこと、地道な実験を繰り返すことなどが得意な分野かもしれません。
この好きと得意は、必ずしも一致するわけではありません。
好きだけれども、なかなか上達しないこともあれば、あまり好きではないけれど、なぜか人よりもうまくできてしまうこともあります。
やりたいことを見つけるためには、この両方の視点から自分を見つめることが大切です。
好きと得意が重なる領域に、あなたにとって理想的な仕事のヒントが隠されている可能性が高いのです。
自分だけの「好き」を見つける自己分析
やりたいことないと感じている理系学生にとって、自己分析は自分自身の内なる声に耳を傾けるための重要なプロセスです。
自己分析と聞くと、難しく堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
これは、自分という人間を理解し、どのようなことに喜びを感じ、何に価値を置くのかを明らかにする作業です。
特に、これまで学業や研究に没頭してきた理系学生は、自分の内面と向き合う機会が少なかったかもしれません。
この章では、自分だけの好きを見つけるための、具体的な自己分析の方法を紹介します。
まずは過去の経験を丁寧に振り返ることから始めてみましょう。
過去の経験を振り返る
自己分析の第一歩は、自分自身の歴史を紐解くことです。
難しく考える必要はありません。
まずは、小学校、中学校、高校、大学と、これまでの人生で起きた出来事や、その時々に感じた感情を時系列で書き出してみましょう。
楽しかったこと、夢中になったこと、逆に辛かったこと、悔しかったことなど、印象に残っているエピソードを思い出してみてください。
特に、なぜそれに心を動かされたのか、その背景にある自分の価値観を探ることが重要です。
理系学生であれば、科学に興味を持ったきっかけの出来事、初めて実験が成功した時の感動、あるいは研究で行き詰まった時の苦悩など、専門分野にまつわる経験を深掘りすることで、自分の興味の源泉や、仕事に求めるものがより明確に見えてくるはずです。
時間を忘れて熱中できることを見つける
あなたが時間を忘れるほど夢中になれるものは何でしょうか。
それは、必ずしも研究や勉強である必要はありません。
趣味のプログラミング、サークルでの楽器演奏、アルバイトでのチーム作業など、どんなことでも構いません。
大切なのは、その活動の何があなたをそこまで惹きつけるのかを深く考えることです。
例えば、プログラミングに熱中している場合、単にコードを書く作業そのものが好きなのか、それとも自分のアイデアが形になる創造的なプロセスが好きなのか、あるいは複雑なエラーを解決した時の達成感が好きなのか。
その理由を突き詰めていくと、あなたの仕事選びの軸となる価値観が見えてきます。
創造性を発揮したい、課題解決に貢献したい、達成感を味わいたいといった、あなた自身の仕事に対する欲求がそこに隠されています。
この熱中できることの要因分析こそが、やりたいことを見つけるための最も純粋なコンパスとなるのです。
苦手なことから見えてくる「やりたくないこと」
やりたいことが明確に見つからない時は、視点を変えて、自分がやりたくないこと、苦手なことをリストアップしてみるのも非常に有効な手段です。
これまで生きてきた中で、どうしても好きになれなかったこと、苦痛を感じたこと、できるだけ避けて通りたいと思ったことは何でしょうか。
例えば、大勢の前で発表することが極度に苦手、毎日同じことの繰り返しである単調な作業は耐えられない、人とコミュニケーションを取らずに進める仕事は避けたい、など、些細なことでも構いません。
これらのやりたくないことを明確にすることで、自分が仕事や職場環境に求めるものが、消去法によって浮かび上がってきます。
これは、単に選択肢を絞り込むだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、自分らしく働ける環境を見つける上で極めて重要な自己分析のアプローチです。
やりたいこと探しで行き詰まったら、まずはやりたくないことのリスト作成から始めてみましょう。
漠然とした「好き」を言語化するヒント
多くの学生が、ものづくりが好き、人の役に立ちたい、社会に貢献したいといった漠然とした好きや願望を持っています。
これらは素晴らしい動機ですが、就職活動で自分の言葉として伝えるには、より具体的に言語化する必要があります。
そのために有効なのが、なぜ、を繰り返す自己分析の手法です。
例えば、ものづくりが好き、という気持ちに対して、なぜ好きなのか?と問いかけます。
それは、自分のアイデアが形になるのが嬉しいからかもしれません。
では、なぜ形になるのが嬉しいのか?それは、課題を解決するプロセスに達成感を感じるから、といった具合に深掘りしていきます。
このなぜの繰り返しによって、漠然としていた感情が、具体的なエピソードや価値観と結びつきます。
友人や家族に自分の好きなことについて話してみるのも良い方法です。
他人に説明する過程で、自分の考えが整理されたり、客観的なフィードバックをもらえたりすることで、自分でも気づかなかった新たな視点が得られることもあります。
大学の学びから「やりたいこと」のヒントを見つける
理系学生である皆さんにとって、大学での学びは専門知識を深めるだけでなく、自分自身の興味や関心を探る絶好の機会です。
日々の講義や実験、研究活動の中にこそ、将来やりたいことを見つけるためのヒントが数多く隠されています。
もしかしたら、今は単位取得のためにこなしているだけ、と感じているかもしれません。
しかし、その一つ一つの学びが社会とどのようにつながっているのかを意識するだけで、世界は大きく広がります。
この章では、最も身近な環境である大学での学びを最大限に活用し、自身のキャリアへとつなげていくための具体的な視点を紹介します。
なぜその学部・学科を選んだのかを再確認する
少し時間を遡って、大学受験の頃を思い出してみてください。
数ある学部・学科の中から、なぜ今の場所を選んだのでしょうか。
その選択の裏には、高校生だったあなたの純粋な興味や、将来への漠然とした憧れがあったはずです。
例えば、最先端の技術に触れたい、環境問題の解決に貢献したい、あるいは特定の科学者のようになりたい、といった動機があったかもしれません。
その時の気持ちを改めて掘り起こしてみることで、あなたが本当に大切にしている価値観や興味の原点が見えてきます。
大学生活を送る中で、入学前のイメージとの間にギャップを感じたとしても、そのギャップ自体が重要な自己分析の材料になります。
理論よりも手を動かす方が好きだと気づいたなら、研究職よりも開発職や生産技術職の方が向いているかもしれません。
初心に立ち返ることは、進むべき道に迷った時の羅針盤となり、キャリアの方向性を再設定する大きなきっかけを与えてくれます。
眼の前の講義や研究テーマとの接点を探す
今はまだやりたいことがないと感じているなら、まずは目の前にある講義や研究に真剣に取り組んでみましょう。
たとえ興味が持てないと感じる科目であっても、その学問が現実社会でどのような技術に応用され、人々の生活を支えているのかを調べてみると、意外な面白さや重要性に気づくことがあります。
例えば、退屈に感じる数学の講義も、最先端のAI技術や金融工学の基礎となっていることを知れば、見方が変わるかもしれません。
自身の研究テーマについても同様です。
その研究が将来、どのような社会課題の解決に貢献できる可能性があるのか、大きな視点で捉え直してみてください。
受け身の姿勢で知識を吸収するだけでなく、社会との接点を探すという能動的な学びの姿勢を持つことが重要です。
その探求の過程で、ほんの少しでも心が動く部分、もっと知りたいと感じる分野が見つかれば、それがあなたのやりたいことに繋がる貴重な芽となるでしょう。
他の理系分野や文系分野の講義も受けてみる
自分の専門分野の枠に閉じこもらず、意識的に視野を広げることは、新たな興味の扉を開く鍵となります。
多くの大学では、自分の所属する学部や学科以外の講義を履修できる制度が整っています。
この制度を最大限に活用し、これまで触れることのなかった他の理系分野や、さらには文系分野の講義にも積極的に参加してみることをお勧めします。
例えば、情報工学を専攻する学生が生命科学の講義を受けることで、バイオインフォマティクスという新たな領域に興味を持つかもしれません。
また、機械工学を学ぶ学生が経済学の基礎を学ぶことで、技術的な視点だけでなく、ビジネスの視点からも製品開発を考えられるようになります。
一見すると無関係に見える分野の知識が組み合わさることで、あなただけのユニークな視点や強みが生まれる可能性があります。
食わず嫌いをせずに、少しでも面白そうだと感じた講義には、ぜひ一度足を運んでみてください。
その小さな一歩が、予期せぬやりたいこととの出会いを引き寄せるかもしれません。
学内イベントや課外活動に参加する
大学のキャンパスは、学問の場であると同時に、多様な人々と出会い、様々な経験を積むことができる貴重なプラットフォームです。
キャリアセンターが主催する業界研究セミナーや企業説明会、あるいは著名な研究者を招いた講演会など、学内で開催されるイベントには積極的に顔を出してみましょう。
社会の第一線で活躍する人々の話は、自分の専門知識が実社会でどのように活かされているのかを具体的にイメージする助けとなります。
また、サークル活動やボランティア、学園祭の実行委員といった課外活動も、自己を成長させる絶好の機会です。
チームで一つの目標に向かって努力した経験や、困難な課題を乗り越えるために試行錯誤した経験は、教室で学ぶだけでは得られないあなたの強みや価値観を教えてくれます。
こうした活動を通じて、自分はどのような役割を担う時にやりがいを感じるのか、どのような仲間といる時に力を発揮できるのかを知ることは、やりたいことを見つけるための重要な手がかりとなるはずです。
理系学生が今すぐできる「やりたいこと」探し
自己分析を深め、大学での学びをキャリアの視点から見つめ直したら、次は外の世界に目を向けて実際に行動を起こすステップです。
頭の中で考えているだけでは、得られる情報や気づきには限界があります。
理系学生という自身の立場を活かしながら、社会との接点を持ち、リアルな情報を集めることが、やりたいことを見つけるための近道となります。
ここでは、机の前から一歩踏み出して、今すぐにでも始められる具体的なアクションを紹介します。
行動することでしか見えてこない景色が、きっとあなたの視野を大きく広げてくれるはずです。
教授や研究室の先輩に話を聞いてみる
最も身近にいる社会人、それは大学の教授や研究室の先輩たちです。
彼らは、あなたの専門分野のプロフェッショナルであると同時に、多くの卒業生を社会に送り出してきたキャリアの先輩でもあります。
特に教授は、学術的な知識だけでなく、産業界とのつながりや業界全体の動向についても深い知見を持っていることが少なくありません。
研究に関する相談だけでなく、キャリアパスについてのアドバイスを求めてみるのも良いでしょう。
また、年齢が近く、少し前まで同じ学生だった研究室の先輩たちの話は、非常に参考になります。
就職活動をどのように進めたのか、なぜその企業を選んだのか、研究室での経験が仕事でどのように活きているのかといったリアルな体験談は、あなたが自身のキャリアを考える上で具体的なイメージを与えてくれます。
研究の合間やゼミの後など、気軽に話せる機会を見つけて、積極的にコミュニケーションを取ってみることをお勧めします。
OB・OG訪問でリアルな仕事の話を聞く
企業のウェブサイトや採用パンフレットに書かれている情報は、あくまで企業が発信する公式な情報です。
仕事の本当の姿を知るためには、実際にその企業で働いている先輩、すなわちOB・OGに話を聞くことが非常に効果的です。
大学のキャリアセンターや研究室の教授の紹介、あるいはOB・OG訪問専門のサービスなどを活用して、興味のある企業で働く先輩にアポイントを取ってみましょう。
仕事の具体的な内容はもちろん、一日のスケジュール、仕事のやりがいや大変な点、職場の雰囲気、そして理系の専門性がどのように活かされているのかなど、インターネットだけでは決して得られない生きた情報を得ることができます。
複数の先輩に話を聞くことで、同じ企業や業界でも、職種や部署によって働き方が大きく異なることにも気づくでしょう。
こうしたリアルな情報に触れることで、仕事に対する漠然としたイメージが具体的になり、自分が本当にやりたいことは何かを判断する上での貴重な材料となります。
興味のある業界・企業について調べてみる
やりたいことがないと感じている状態でも、テレビCMでよく見る、あるいは自分の研究分野と少し関係がありそう、といった程度のぼんやりとした興味を持つ業界や企業はいくつかあるのではないでしょうか。
まずはそこから情報収集を始めてみましょう。
企業の公式ウェブサイトを訪れ、どのような製品やサービスを提供しているのか、どのような事業部門があるのかを眺めてみるだけでも、新たな発見があります。
特に、企業のIR情報、つまり投資家向けの情報ページには、事業の現状や将来の戦略が詳しく書かれており、その企業が社会でどのような役割を果たそうとしているのかを深く理解するのに役立ちます。
また、業界全体の動向を掴むためには、業界地図のような書籍を読んでみるのも良いでしょう。
最初は点でしかなかった企業や業界の知識が、調べていくうちに線でつながり、自分なりの興味の方向性が見えてくることがあります。
この地道な情報収集が、やりたいこととの思わぬ出会いにつながるのです。
実践的なスキル(プログラミングなど)を学んでみる
新しいスキルを習得するプロセスは、それ自体が自己分析の機会となり、やりたいことを見つけるきっかけになることがあります。
特にプログラミングは、現代のあらゆる産業で必要とされており、理系学生が持つ論理的思考力との親和性も高いため、学んでおいて損のないスキルです。
オンラインの学習プラットフォームなどを利用すれば、自分のペースで手軽に学習を始めることができます。
簡単なウェブサイトやアプリケーションを自分で作ってみるという経験は、ものづくりの楽しさや、課題を解決する達成感を直接的に味わうことができるでしょう。
その過程で、自分がどのような作業に没頭できるのか、チームでの開発と個人での開発のどちらが好きなのか、といった自己理解も深まります。
たとえプログラマーを本気で目指さないとしても、プログラミングの基礎知識は、将来どのような職種に就いたとしても必ず役立ちます。
何か一つでも自信を持ってできるスキルがあることは、就職活動を進める上での大きな心の支えにもなるはずです。
インターンシップに参加してみる
百聞は一見にしかず、ということわざの通り、実際に仕事を体験してみることは、やりたいことを見つける上で最も効果的な方法と言えるでしょう。
インターンシップに参加すれば、企業のオフィスという環境に身を置き、社員の方々と一緒に働くことで、仕事の具体的な内容や職場の雰囲気を肌で感じることができます。
自分が持っていた仕事に対する華やかなイメージと、地道な作業の連続である現実とのギャップに気づくこともあるかもしれません。
理系学生を対象とした技術系のインターンシップでは、大学の研究室とは異なる、企業の製品開発の現場に触れることができます。
そこで自分の専門知識が通用する部分と、まだまだ足りない部分を実感することは、大きな成長の機会となるでしょう。
もし参加したインターンシップの仕事が自分には合わないと感じたとしても、それは決して無駄な経験ではありません。
むしろ、自分がやりたくないことが明確になったという大きな収穫です。
まずは短期のプログラムからでも良いので、勇気を出して参加してみることを強くお勧めします。
将来のキャリアを見据えた研究室選びのポイント
多くの理系学生にとって、研究室選びは大学生活における最大の選択の一つです。
どの研究室に所属するかは、残りの学生生活の質を左右するだけでなく、その後の就職活動や将来のキャリアパスにも大きな影響を与えます。
単に興味のある研究テーマというだけで選ぶのではなく、自分がどのような環境で成長したいのか、そしてどのような未来を描きたいのかという、長期的な視点を持って臨むことが重要です。
この章では、将来のキャリア形成という観点から、後悔しない研究室選びのための具体的なポイントを解説します。
研究テーマと自分の興味の接点を探す
研究室選びの最も基本的な出発点は、もちろんその研究室が扱うテーマと、あなた自身の興味が合致していることです。
しかし、まだやりたいことが明確でない段階では、どのテーマに心から惹かれるのか判断が難しいかもしれません。
そのような場合は、まず、これまでの大学の講義や実験の中で、少しでも面白いと感じた分野、あるいはもっと知りたいと思ったキーワードを洗い出してみましょう。
そして、各研究室のウェブサイトをじっくりと読み込み、公開されている研究論文の概要に目を通してみてください。
最先端の研究内容を完全に理解する必要はありません。
大切なのは、その研究が最終的にどのような社会課題の解決を目指しているのか、どのような未来を創り出そうとしているのかを想像してみることです。
あなたの漠然とした興味や問題意識が、具体的な研究テーマと結びついた時、それがあなたにとってのやりたいことに変わる可能性があります。
研究室の雰囲気や働き方をどう調べるか
研究生活は、一日の多くの時間を研究室で過ごすことになります。
そのため、研究内容そのものと同じくらい、研究室の雰囲気や文化、いわゆる働き方が自分に合っているかどうかは非常に重要な要素です。
例えば、毎日決まった時間に研究室にいなければならないコアタイムの有無、ゼミやミーティングの頻度と形式、教授や先輩とのコミュニケーションの取りやすさなど、事前に確認しておくべき点は数多くあります。
これらの情報を得る最も確実な方法は、研究室訪問や説明会に積極的に参加し、そこに所属する先輩たちから直接話を聞くことです。
ウェブサイトや資料だけでは決して分からない、研究室のリアルな日常や人間関係を知ることができます。
自分がどのような環境であれば最も能力を発揮でき、ストレスなく研究に打ち込めるのかを自己分析し、それに合った研究室を選ぶことが、充実した研究生活を送るための鍵となります。
卒業後の進路や就職先をチェックする
将来のキャリアを具体的に考える上で、その研究室を卒業した先輩たちが、どのような企業や業界に就職しているのかを調べることは、極めて重要な情報収集です。
多くの研究室では、公式ウェブサイトなどに過去の卒業生の主な就職先リストを掲載しています。
このリストを確認することで、その研究室で培われる専門性やスキルが、産業界でどのように評価され、どのような分野で求められているのかを客観的に把握することができます。
もしあなたが特定の企業や業界に興味を持っているのであれば、その研究室から多くの先輩が就職しているかどうかは、重要な判断材料となるでしょう。
また、企業によっては特定分野の研究室に対して推薦応募枠を設けている場合もあります。
教授や先輩たちが築き上げてきた企業とのコネクションは、あなたの就職活動を有利に進める上で大きな助けとなる可能性があります。
研究室選びは、未来への投資であるという視点を忘れないでください。
まとめ
理系学生の皆さんが、やりたいことがないと悩むのは、真剣に自分の将来と向き合っている証拠です。
決して特別なことではなく、多くの人が通る道なので、焦りや不安を感じすぎる必要はありません。
大切なのは、完璧な答えを急いで見つけることではなく、自分自身を深く理解し、少しずつ行動を起こしていくことです。
まずは、過去の経験を振り返る自己分析を通じて、自分の小さな好きや得意、そしてやりたくないことを見つけることから始めてみてください。
そして、大学での日々の学びや研究の中に、社会との接点や興味の種を探してみましょう。
さらに、インターンシップやOB・OG訪問などを通じて、実際に社会に触れることで、あなたのキャリアイメージはより具体的になっていくはずです。
この記事で紹介した様々なヒントが、皆さんが自分らしい道を見つけるための一助となれば幸いです。
あなたのこれからのキャリアが、充実した実りあるものになることを心から応援しています。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート