はじめに
「AIによって仕事はなくなるの?」
「AIに奪われない仕事に就きたい」
AIの登場によって、労働環境は変わりつつあります。
そのため、就活に不安を覚える就活生がいても不思議ではありません。
この記事では、AIによって今後消える仕事と残る仕事の特徴について詳しく解説します。
就活は、将来を見据えたうえで選択することが重要です。
この記事を最後まで読むことで、AIが仕事にどのような影響を及ぼすのか理解できます。
【AIによってなくなる仕事】定義とその背景
- ルーティン作業が中心の職種
- 判断基準が明確な職種
- コミュニケーションが少ない職種
AIは、同じ作業の繰り返しや明確なルールのある作業が得意です。
そのため、AIの登場・発達によって特定の業務が不要になる可能性があります。
就活ではどの職種が、AIに置き換わる対象になりやすいか理解しておくことが重要です。
もし、AIに代替される職種を選んでしまうと、業務が縮小しキャリアアップが難しくなるでしょう。
本章では、具体的にどういった業務がなくなるのか解説します。
企業・職種を選ぶ際の参考にしてください。
ルーティン作業が中心の職種
毎日同じ作業を繰り返す仕事は、AIが最も得意とする分野です。
AIは大量のデータを高速かつ正確に処理できるからです。
たとえば、経理事務はAIによって効率化されます。
請求書のデータ入力や仕訳作業、支払い処理、給与計算などの定型業務があるからです。
経理にAIを利用することで、人的ミスが削減され、処理速度が飛躍的に向上し、担当者はより戦略的な業務に時間を割けます。
もちろん、想定外のトラブルや例外の対応は人間がしなければなりません。
つまり、全ての業務がAIに置き換わる可能性は低いです。
しかし、AIの導入がルーティン作業に大きな影響を与えることも理解しておきましょう。
判断基準が明確な職種
AIは基準にもとづいた判断が得意です。
AIは、今までのデータや過去の履歴を参考にするため、即時の判断ができます。
そこで、マニュアルや手順をAIに学習させることで、条件に沿った判断がくだせます。
たとえば、コールセンターの顧客対応や製造業における品質管理などです。
人間は長時間の作業を続けると、疲労により集中力が低下します。
集中力が失われた状態では、生産性も大きく落ちるでしょう。
しかし、AIは24時間365日、休みなく稼働し続けることが可能です。
その結果、AIは連続的な対応が必要な業務でも安定したパフォーマンスが発揮できます。
コミュニケーションが少ない職種
コミュニケーションが少ない職種は、AIに置き換わるでしょう。
会話による複雑な対応をAIがこなす必要がないからです。
AIは、判断基準が曖昧だったり、複雑な背景を理解するのが苦手です。
そのため、人間との会話は、まだまだ精度が足りません。
しかし、コールセンターの自動音声対応やプログラミングなど、会話がない業務の場合、AIの強みが活かせます。
つまり、わざわざ人間に仕事をさせる必要性がなくなることで、仕事がAIに代替されるでしょう。
他にも、Webライターやデータ入力なども同様にAIが得意とする分野の仕事です。
自分が志望する職種がAIの登場によって、どう影響を受けるのか調べておきましょう。
【AIによってなくなる仕事】代表的な職種一覧
- 一般事務・データ入力
- テレアポ・カスタマーサポート
- 工場作業員・検品業務
- レジ打ち・受付業務
- 銀行窓口・簡易な金融業務
- 運転代行・配送ドライバー
- 通訳・翻訳の一部業務
- 記事作成・文章生成の定型業務
- 監視カメラのモニタリング業務
- 不動産査定や価格予測業務
- 会計・経理の仕訳入力業務
- 法律文書のレビュー業務
続いて、AIによってなくなる代表的な職種を12個紹介します。
AIの登場で、多くの業務が効率化しました。
一方でAIに仕事が奪われている職種もあります。
本章では、AIの影響を強く受ける職種について解説しています。
自分が志望する職種が含まれている就活生は、AIの存在を認識したうえで就活するようにしてください。
AIが自分の仕事を奪う可能性を無視した就活は、入社後に後悔する可能性があります。
一般事務・データ入力
一般事務やデータ入力の仕事は、AIによる自動化が進んでいる分野の1つです。
一般事務・データ入力の多くは同じ作業の繰り返しが多いからです。
たとえば、経理部門での請求書処理では、AIの画像認識技術を利用できます。
請求書の画像をAIに読み取らせることで日付や金額、取引先などの情報を自動で読み取ることが可能です。
また、取得した情報は会計システムに直接入力することも可能です。
他にも、顧客からの問い合わせメールの内容をAIが分析し、定型的な返信を自動で生成できるようになりました。
ルーティン作業は、人間が手作業で行うと時間がかかり、入力ミスも発生しやすいです。
しかし、AIは膨大な量のデータを高速かつ正確に処理できるため、業務効率が劇的に向上します。
その結果、一般事務やデータ入力のような業務は、人間の仕事からAIの仕事に置き換わるでしょう。
テレアポ・カスタマーサポート
テレアポ・カスタマーサポートの業務は、AI化が進んでいます。
AIの機能が向上したことで、AIチャットボットや音声AIとしての活用が可能になりました。
そこで、人間ではなくAIに顧客対応させるケースが増えています。
顧客からのよくある質問や定型的な問い合わせに対しては、AIが過去のデータやマニュアルを学習し、自動で最適な回答を提示します。
その結果、24時間365日の顧客対応が可能となり、顧客満足度の向上につながっています。また、複雑な問い合わせやクレーム対応など、AIでは対応しきれないと判断された場合、人間が対応する仕組みも構築されています。
つまり、テレアポ業務の大部分をAIが負担し、人間が担当する部分が狭くなっています。
テレアポ・カスタマーサポートで働くには、AIにできない業務をこなす必要があることを覚えておきましょう。
工場作業員・検品業務
工場作業員・検品業務もAIに置き換わるでしょう。
製造業の工場では、ロボットやAIの導入により、生産ラインにおける組み立て、運搬、検品といった作業が自動化されているからです。
すでにロボットによる作業は普及していましたが、近年はAIの登場により人手が必要な作業がよりなくなりました。
たとえば、精密な組み立て作業は産業用ロボットが担当します。
さらに、人間が担当するには危険な作業や重労働もロボットが代替します。
また、製品の品質検査では、画像認識AIがカメラで製品をスキャンし、人間では見落としがちな微細な傷や欠陥を高速かつ高精度で検出します。
従来は人の目で確認していた作業が、AIに変わっていることを理解しましょう。
レジ打ち・受付業務
レジ打ちや受付業務は、セルフレジや無人受付システムの普及により、大幅に自動化が進んでいる分野です。
店舗スタッフが担当した作業をAIに任せることで、人手不足の解消に役立っています。
たとえば、スーパーやコンビニでは、顧客自身が商品のバーコードをスキャンして決済を行うセルフレジが一般的になりつつあります。
その結果、店舗はレジ担当の従業員を減らし、接客や商品陳列といったAIではできない業務に人員を配置することが可能になりました。
また、ホテルや病院などでは、AIを搭載した無人受付システムが導入されています。
来訪者のチェックインや予約確認、案内などを自動化することで、スムーズな案内が可能になりました。
銀行窓口・簡易な金融業務
銀行窓口の業務は、単純な入出金や振込といった定型的な取引の必要性が減少しています。
ATMやネットバンキング、スマートフォンアプリが普及したからです。
また、金融業務ではAIが顧客の取引履歴や金融データを分析し、顧客1人ひとりに最適な金融商品の提案が可能になっています。
AIに金融商品の提案を任せることで、銀行員は顧客の資産運用や相続に関する相談といった、より専門的で複雑な業務に専念できるようになりました。
つまり、銀行は単なる取引の場から、顧客のニーズに合わせてコンサルティングする場へと変化しています。
銀行員を目指す就活生は、銀行員に必要なスキルが変わっていることを覚えておきましょう。
運転代行・配送ドライバー
自動運転技術が進化することで、将来的に運転代行や配送ドライバーの仕事を大きく変える可能性があります。
物を運ぶには人手が必要です。
しかし、自動運転トラックやドローンによる配送が実現すれば、配送業における大部分の仕事がなくなるでしょう。
現在、配送業は人手不足や燃料費の高騰により、厳しい環境にいます。
現状の物流を維持するためにも自動化の採用が急がれています。
とくに、高速道路での長距離輸送は、定型的な運転ルートが多いため、自動化の可能性が高いとされています。
つまり、ドライバーは運転そのものから解放され、荷物の積み下ろしや顧客対応、車両のメンテナンスといった、運転以外の業務にシフトしていくことになるでしょう。
通訳・翻訳の一部業務
通訳・翻訳の一部業務はAIの登場によりなくなる可能性があります。
AI翻訳ツールを利用した方が、簡単かつ迅速に効果が得られるからです。
たとえば、簡単な日常会話や定型的なビジネス文書の翻訳は、Google翻訳といったツールが非常に高い精度でこなせるようになりました。
つまり通訳・翻訳を専門とする仕事のうち、基礎的な業務がAIに置き換わる可能性が高まっていることを意味します。
将来は、通訳や翻訳で躍したい就活生は、単に言語を変換するスキルだけではなく、その背景にある文化や社会的な文脈を理解しなければなりません。
また、相手の感情やニュアンスまで汲み取って伝える高度なコミュニケーション能力も重要です。
さらに、特定の専門分野(医療、法律、ITなど)の知識を活かした翻訳スキルを磨くことが重要になります。
記事作成・文章生成の定型業務
ChatGPTに代表される生成AIの登場は、ライターや編集者を目指す就活生にとって、大きな変化をもたらしています。
ニュース速報や決算報告書、商品の説明文など、テンプレートにもとづいた定型的な文章は、AIが短時間で大量に生成できるようになりました。
その結果、単純な情報伝達を目的としたライティング業務は、AIに任せられることが増えていくでしょう。
文字を扱う分野でキャリアを築くためには、AIには生み出せない「独自の視点」や「深い洞察力」が必要です。
そして、読者の心に響く文章力を磨くことも欠かせません、
ライターを目指す場合、AIをツールとして活用し、効率的に情報収集や下書きを済ませつつ、人間ならではの創造性や感性を伸ばしましょう。
監視カメラのモニタリング業務
警備員や監視員の仕事も、AIの進化によって大きく変わろうとしています。
映像認識AIは、監視カメラの映像をリアルタイムで分析し、不審者の侵入や異常な行動、置き忘れられた荷物などを自動で検知することが可能です。
その結果、人間が長時間にわたってモニター前に座り、同じ画面を凝視し続ける必要がなくなります。
警備や監視の仕事に就くなら、AIが検知した情報をもとに、いかに迅速かつ冷静に対応するかといった状況判断能力が重要です。
他にも、緊急時に冷静に行動できる危機管理能力も身につけましょう。
ただし、AIはあくまで監視の補助です。
最終的な判断や対応は人間が行うため、AIと連携して業務を遂行するスキルが重要です。
不動産査定や価格予測業務
不動産査定や価格予測といった仕事もAIの得意分野です。
AIは、過去の取引データや物件情報、さらには周辺の商業施設や人口動態などのデータを分析し、人間よりも高速かつ正確に不動産価格を判断できます。
その結果、不動産会社の査定業務の多くが自動化され、人間が行っていた初期段階の価格判断はAIに任せることになるでしょう。
不動産業界に興味のある就活生は、単に価格を出すだけでなく、顧客のライフプランや将来のビジョンに寄り添った提案力が必要です。
つまり、物件の魅力を最大限に引き出すコンサルティング能力が求められる時代になります。
AIの進化により不動産業界は、より顧客対応に特化したスキルを磨くことが重要になるでしょう。
会計・経理の仕訳入力業務
会計や経理担当者の仕事の中でも、レシートや請求書の情報をシステムに入力するといった定型的な仕訳作業は、AIによって自動化が急速に進んでいます。
AIはルールに沿った仕分け作業が得意です。
そのため、AIに入力業務を任せることで、過去の経理情報をもとに、ミスなく仕分けてくれるでしょう。
たとえば、従来の経理は領収書を見ながら日付や金額をパソコンに打ち込んでいました。
しかし、AIを使った自動仕訳にすることで、手作業による入力ミスが減り、作業効率が大幅に向上します。
会計や経理職を希望する就活生は、単に数字を処理するだけでは不十分です。
AIが分析したデータを読み解き、企業の経営状態を把握する能力やより戦略的な視点から経営陣にアドバイスする能力が求められます。
法律文書のレビュー業務
法律事務所での契約書や法的文書のレビュー業務もAI化が進んでいます。
AIに、過去の法的文書を学習させることで、契約書の矛盾点やリスクの高い条項を効率的に洗い出すことが可能です。
AIを業務に加えることで、弁護士は初期段階の確認作業をAIに任せ、より複雑な訴訟対応や顧客との交渉、そして法的な戦略立案に集中できるようになります。
法律に関係する職種を目指すなら、AIをツールとして使いこなし、高度な法的知識と論理的な思考力が必要です。
事務所に在中し、弁護士から依頼された仕事を漫然とこなすだけでは、AIに仕事が奪われる可能性があります。
今後は、AIがサポートできない角度から弁護士をサポートする必要があるでしょう。
【AIによってなくなる仕事】共通点
AIによってなくなる仕事の共通点は、以下の3つです。
- 再現性の高い業務内容
- 判断が単一で済む業務
- スキルの汎用性が低い業務
AIは便利なツールですが、全ての仕事にとって変わるわけではありません。
そこで、AIに代替されやすい仕事の共通点を理解しておくことで、入社後に仕事が減る可能性が少なくなります。
さらに、働き始めたのちも、本章で解説する内容を参考にすることで、AIに負けない活躍ができるでしょう。
再現性の高い業務内容
再現性の高い業務内容は、AIによってなくなる可能性が高いです。
誰がやっても同じ結果になる、マニュアル化しやすい作業は、AIにより自動化しやすいからです。
たとえば、データ入力や整理、商品の検品といった業務は、特定のルールに従って正確に繰り返すことが求められます。
AIは、ルーティン化した作業を人間よりもはるかに高速かつ正確に、そして24時間休みなく実行することが可能です。
つまり、これまで人間が担っていた単純作業の多くがAIに置き換わり、人はより創造性や柔軟な思考が求められる仕事へとシフトしていくことになります。
仕事内容を調べていくうえで、誰でもできる作業や想像性が少ない場合は、AIに置き換わるリスクを頭に入れておきましょう。
判断が単一で済む業務
判断が単一で済む業務もAIが得意とする範囲のため、仕事はなくなるでしょう。
AIは明確なルールや一定の基準にもとづいて判断するため、迷うことがありません。
たとえば、銀行の融資審査や保険の査定では、申込者の信用情報や過去のデータといった客観的な情報をもとに、融資の可否や保険金額を判断します。
審査のような「〇〇の場合はA、そうでない場合はB」といった業務は、AIが膨大なデータを分析することで、人間よりも迅速かつ公平に判断することが可能です。
就活では、AIには真似できない複雑な状況判断や顧客の感情に寄り添うといった、人間ならではのスキルをアピールすることが重要になります。
スキルの汎用性が低い業務
スキルの汎用性が低い業務は、AIに仕事が取られる可能性があります。
わざわざ人間に仕事として依頼する必要がないからです。
たとえば、工場の製造ラインでの部品の組み立てや単純な伝票整理といった業務は、その作業に関係するスキルしか身につきません。
しかし、AIやロボットは、上記の作業を人間よりも効率的にこなすことが可能です。
そのため、AIに仕事を取られたくない就活生は、特定の技術や知識に固執しないでください。
転職先でも活躍できる、問題解決能力やコミュニケーション能力、新しいことを学ぶ柔軟性などを優先して身につけましょう。
複数の分野で応用できる汎用性の高いスキルを身につけることが、キャリアの選択肢が広げられます。
【AIによっても残る仕事】今後も必要とされる職種
- 創造性が求められる仕事
- 高度な対人スキルが必要な仕事
- 経営・戦略を担う上流職種
- 教育・カウンセリング関連職種
- 医療・看護・福祉関連職種
多くの仕事がAIに代替される一方で、今後も必要とされる職種があります。
本章では、AIに置き換えることが困難であり、今後も安定した仕事が見込める職種を5つ解説します。
本章で紹介する内容を覚えておくことで、就活で迷った際の判断材料になるでしょう。
また、AIに仕事が奪われたくないと危機感を持っている就活生もぜひ参考にしてください。
創造性が求められる仕事
創造性が求められる仕事はなくなりません。
AIは、ゼロから価値を生み出す仕事が苦手だからです。
たとえば、新しい企画やデザイン、アートなどが挙げられます。
AIは過去のデータを分析し、最適解を導き出すことが得意です。
しかし、まったく新しいアイデアやコンセプトを生み出すことは苦手です。
そのため、マーケティング戦略の立案者やデザイナー、アーティストなど、ユニークな発想が求められる職種は、今後も人間が主役となります。
ただし、AIを使わないわけではありません。
情報収集や作業効率化のツールとしてAIは存在します。
あくまで仕事の中心にAIがいないことを覚えておきましょう。
高度な対人スキルが必要な仕事
高度な対人スキルが必要な仕事は需要が増していくでしょう。
相手の感情に寄り添ったり、場の空気を読んだりすることは、AIにはできないからです。
たとえば、営業職やコンサルタント、ウェディングプランナーなどは、顧客との信頼関係を築くことが成功の鍵となります。
AIはマニュアル通りの対応はできても、相手の表情や声のトーンから心の機微を読み取り、臨機応変に対応することは困難です。
そこで、就活ではコミュニケーションや協調性といった、信頼関係を築くスキルをアピールしましょう。
AIの得意分野から距離を取ることで、面接官に自分を採用するメリットを伝えられます。
経営・戦略を担う上流職種
経営・戦略を担う上流職種は人間にしかできません。
最終判断をくだすのは、どこまでAIが進化しても人間だからです。
AIは膨大なデータを分析することで未来予測ができます。
しかし、最終的な経営判断をくだすには、長年の経験や直感、そしてリスクを恐れない決断力が必要です。
また、企業のビジョンを掲げたり、従業員を鼓舞したりすることもAIは担えません。
CEOやCFOといった経営層、M&A戦略を策定するコンサルタントなどは、今後も生き残れる職種になるでしょう。
もちろん、どの職種でもAIは便利なツールとして活用します。
AIと差別化するには、人間はリスクが負える点であることを覚えておきましょう。
教育・カウンセリング関連職種
人に寄り添う、教育やカウンセリングの分野もAIに代替されにくい領域です。
個々の生徒やクライアントの個性や感情に寄り添い、成長をサポートする仕事は、人間にしかできません。
AIは、学習データにもとづいて最適なカリキュラムを提案することが可能です。
しかし、生徒の「なぜ?」という疑問に深く向き合ったり、落ち込んでいる人の気持ちに寄り添ったりするのは苦手です。
そこで、教師やカウンセラーとして、1人ひとりの個性を見抜き、心に寄り添うことで、AIでは提供できない質の高い支援ができます。
教育やカウンセリングは、AIとの役割分担がしやすい職種です。
人と関わるのが好きな就活生にとっては、安心して就職できるでしょう。
医療・看護・福祉関連職種
医療・看護・福祉といった人の命や生活に関わる仕事は、今後も人が中心です。
AIは、病気の診断や治療法の提案をサポートできます。
しかし、患者さんの体調変化を細やかに観察し、不安な気持ちに寄り添うケアは、人の手と心が必要です。
また、介護の現場でも同様です。
利用者の日々の生活を支える身体介助や心の交流は、AIには代替できません。
もちろん、医療現場にもAIは浸透しています。
診断を考えるにあたって医師をサポートする存在です。
一方、現在のAIでは、人間ならではの温かさや思いやり、気遣いの再現はできません。
そのため、今後もAIによって作業効率がアップする程度に留まるでしょう。
【AIによってなくなる仕事】就活戦略
- 将来性のある業界を選ぶ
- 業務範囲が広い職種を選ぶ
- 長期的なスキルが身につく職場を選ぶ
AIの存在を理解し、うまく立ち回るには就活であっても戦略を立てる必要があります。
むしろ、就活の段階から戦略を練っておくことで、5年10年先のキャリアパスを豊かにしてくれるでしょう。
本章では、就活生が取るべき就活戦略を3つ紹介します。
できそうな戦略から取り組んでもらってかまいません。
ただし、できる限り3つを掛け合わせるようにしてください。
戦略を多く立てることで、状況の変化にも柔軟に対応できるからです。
将来性のある業界を選ぶ
AI時代を生き抜くためには、テクノロジーと共に成長する業界を選ぶことが重要です。
現在の生活においてAIの存在は欠かせないからです。
たとえば、AIそのものを開発するIT業界はもちろん、医療や環境、教育といったAIが社会課題の解決に活用される分野では、今後も人の活躍が見込まれます。
上記の業界では、AIを使いこなす能力に加え、専門的な知識や倫理観、そして新しい価値を創造する力が求められるからです。
もし、市場規模が縮小している業界を選んでしまうと、人件費の削減と称してAIが導入されるでしょう。
その結果、AIに仕事を奪われる可能性があります。
そこで、業界研究を通じて、自分が希望する業界に将来性があるかチェックしましょう。
業界研究のやり方については、こちらの記事をご覧ください。
業務範囲が広い職種を選ぶ
業務範囲が広い職種を選ぶこともAI対策の1つです。
AIは、ルーティン化した作業が得意です。
そのため、特定の作業しか行わない職種はAIに置き換わる可能性が高くなります。
反対に企画立案から予算管理、対人対応など、幅広い業務をこなす職種は代替されにくいです。
具体的には、プロジェクトマネージャーや現場監督などです。
データ分析やタスク管理にAIは欠かせません。
しかし、チームメンバーとのコミュニケーションやクライアントとの交渉といった人間にしかできない業務が存在します。
そこで、定型業務をAIに任せることで、より複雑で高度な業務に集中できるため、AI時代でも人材価値を高められるでしょう。
長期的なスキルが身につく職場を選ぶ
今後は、経験とスキルが長期的に蓄積される職場を選ぶことが重要です。
AIの登場により、時代が変化するスピードが速くなるからです。
たとえば、単調な作業を繰り返すだけの仕事ではなく、新しいプロジェクトに挑戦できたり、専門的な研修を受けられたりする環境です。
「問題解決能力」「新しい技術を学ぶ柔軟性」といった汎用性の高いスキルは、今後どのような技術革新が起きても活かせる力になります。
また、一朝一夕では身につかないため、早い段階から少しずつ訓練する必要があります。
そこで、就活生は、企業の研修制度やキャリアパスについて具体的に質問し、自分の成長をサポートしてくれる職場か確認しましょう。
従業員を教育するつもりがない企業は、AIに置き換わる仕事の可能性があります。
【AIによってなくなる仕事】なくなる仕事に対する誤解
- すべての単純作業がなくなるわけではない
- 全ての業務がすぐにAI化されるわけではない
- AIが苦手な領域も存在する
AIの登場によって、一部の仕事はなくなり始めています。
しかし、就活生の中にはAIの存在を誤解している人がいます。
AIは全ての業界・業種にとって変わる存在ではありません。
そこで、本章ではAIに対して不安になる必要がないことを解説します。
「AI=自分の仕事を奪う敵」と感じている人は、最後まで読んでいただくことで、冷静に対応できるでしょう。
全ての単純作業がなくなるわけではない
AIが全ての単純作業をなくすという考えは誤解です。
確かにAIはルーティン作業を得意とします。
AIを導入するコストや安全性、倫理的な側面から、人の手で作業する方が効率的な場面があるからです。
たとえば、飲食店の簡単な配膳作業や高齢者の見守りなど、人の温かさや細やかな配慮が求められる作業は、AIが完全に代替するのは難しいでしょう。
AIはあくまでツールです。
人がより高度な仕事に集中するためのサポート役と捉えてください。
そのため、人が担当する単純作業を補助する道具として、AIが導入されるでしょう。
AIが今すぐ単純作業の全てに取って変わるわけではないので、就活生のみなさんは安心してください。
全ての業務がすぐにAI化されるわけではない
AI技術が進化しても、すべての業務がすぐに置き換わるわけではありません。
技術の普及には、システムの開発期間や法整備、そして社会全体の理解と浸透するまでに時間がかかります。
つまり、AIへの代替は今日や明日にでも完了する話ではありません。
AIの普及は段階的に進みます。
就活では「AIに仕事が奪われる」と悲観的に考えるのではなく、自分の仕事がどうAIと共存していくかを考えることが重要です。
まずは、業務にAIを導入するコストやメリット、デメリットを理解してください。
次に、自分の強みをどう活かすかを考えることで、AI時代を生き抜くキャリアプランが見つかります。
AIが苦手な領域も存在する
AIは万能なツールではありません。
苦手な領域が存在するので安心してください。
たとえば、柔軟な思考や曖昧な情報への対応は、依然として人の力が求められる領域です。とくに、顧客の感情を読み取ってニーズを深く理解したり、前例のない問題に対してクリエイティブな解決策を考案したりすることは、AIには困難です。
そこで就活では、論理的思考力やコミュニケーション能力といった、AIが苦手とする人間ならではのスキルをアピールすることが重要です。
AIを知識のデータベースとして活用し、人間がより高度な判断や創造的な仕事に専念できるようにすることで、AIを使いこなす側になれます。
【AIによってなくなる仕事】見極めるリサーチ方法
- 業界・企業のDX動向を確認する
- OB訪問で業務の実態を聞く
- 志望企業の技術投資方針を分析する
就活するにあたって、自分が志望する業界・業種がAIによってなくなるのか気になる就活生は多いでしょう。
AIに仕事が奪われるかどうかを見極めるには、情報収集が重要です。
そこで、本章では就活対策として効果的なリサーチ方法を3つ紹介します。
漠然とAIの存在が不安な就活生は、ぜひ本章の解説を最後まで読んでください。
自分の不安を解消する方法を知っておくことで、適切な対策が可能です。
業界・企業のDX動向を確認する
まずは、志望する業界・企業のDX動向を確認しましょう。
リサーチするにあたって、どれだけデジタル化が進んでいるかを確認することは、AI導入の可能性を判断するのに重要です。
AIが気になる就活生は、企業の公式ホームページやIR情報、ニュースリリースなどをチェックしてください。
「DX」「AI活用」「業務効率化」といったキーワードを検索してみましょう。
検索する数が多いほど、デジタル化が進んでいる業界・企業です。
つまり、AIによる自動化が進む可能性が高いといえます。
逆に、いまだに紙の書類が多く、手作業が中心となっている場合は、DXが遅れている可能性があります。
OB訪問で業務の実態を聞く
OB訪問で業務の実態を聞くのは、AIをリサーチするのに有効な手段です。
直接会って話を聞くことで、就活サイトや口コミだけでは分からない「現場のリアルな声」を聞くことが可能です。
業務にどの程度AIを活用しているのかを質問することで、AIに代替されるリスクを予想できます。
質問できる時間になれば「現在どのような業務がAIに置き換わっていますか?」「5年後、10年後、〇〇の仕事はどう変化していくと思いますか?」といった質問を投げかけてみましょう。
調べてもわからない疑問は積極的に質問してください。
不安や悩み、心配を解消することで、企業の将来的なビジョンや自分の仕事がどう変化していくかを具体的にイメージするきっかけになります。
志望企業の技術投資方針を分析する
志望度の高い企業の場合、技術投資の方針を分析しましょう。
AIを判断するには、企業が発表しているデータをもとに、AIやテクノロジーにどれだけ投資する計画なのか分析することが重要です。
企業の決算資料には、将来の成長戦略や技術投資の方針が記載されていることがあります。「AI関連事業に〇〇円投資する」といった具体的な数値があれば、AI活用への優先度が高いと判断できます。
また、情報を分析することで、志望企業がAIを脅威と捉えているのか、それとも成長の機会と捉えているのかを知ることが可能です。
読み慣れない言葉や数字が多く出てくるため、最初は苦戦するかもしれません。
しかし、AIをリサーチするには欠かせない情報になるため、ぜひ活用してください。
【AIによってなくなる仕事】避けるために意識したいスキル
- デジタルリテラシーの向上
- 論理的思考と課題解決力
- コミュニケーションとチーム力
- 状況に応じた柔軟な対応力
- 自己学習を継続する姿勢
社会で活躍するには、AIが苦手な分野に加えて、対応できないジャンルのスキルを極める必要があります。
そこで、本章では就活と並行しながら身につけるべきスキルについて解説します。
就活に学業、部活やアルバイトと忙しい人は多いでしょう。
しかし、就活は人生を大きく左右するイベントの1つです。
納得のいく就活にするためにも、本章の解説を頭に入れておきましょう。
今からでも意識しておくことで、自己PRを考える際に役立ちます。
デジタルリテラシーの向上
AIが普及する現代では、基本的なITスキルやデジタルツールの理解は必須です。
これからの社会ではAIをツールとして使うだけでなく、仕組みを理解し、業務にどう活用できるかを考えられる人材が求められます。
たとえば、ExcelやGoogleスプレッドシートの関数を使いこなしたり、データ分析ツールを操作したりする能力は、AIを使いこなすために必要不可欠です。
デジタルリテラシーを高めることで、AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使いこなして仕事の幅を広げられるようになります。
また、AIを正しく使うには生成した情報に誤りがないか、人の目で確かめなければなりません。
そのため、デジタルリテラシーを身につけておく必要があります。
論理的思考と課題解決力
AIを使いこなすには、論理的思考と課題解決力を鍛えてください。
AIは膨大なデータを処理し、パターンを見つけ出すことが得意です。
しかし、複雑な背景を考慮したり、物事を決断したりするには、人間の力が必要です。
また、不確定な未来を予想する想像力は、依然として人間の強みになります。
そこで、論理的思考力があれば、AIが提示したデータや情報を鵜呑みにせず、なぜそのような結果になったのかを深く考察できます。
就活では、学生時代の経験を話す際に「なぜそうなったのか」「どうすれば解決できるか」といった視点で話すことで、課題解決能力をアピールできます。
論理的思考は、面接でも活躍する力なので、身につけて損はありません。
コミュニケーションとチーム力
AIがどれだけ進化しても、人と人とが信頼関係を築き、協力しながら目標に向かっていく力は、企業の発展には必要不可欠です。
チーム内でのコミュニケーションや顧客や取引先との交渉は、相手の感情や場の空気を読み取る必要があります。
そのため、AIが完全に代替するのは難しい領域です。
そこで、チームで協力して成果を出した経験や多様な人と関わった経験は、AI時代において自分の価値を高める重要なスキルとなります。
ただし、部活やアルバイトの経験を列挙するだけでは不十分です。
自分が信頼関係を構築するにあたって工夫した点や苦労した点をエピソードとして盛り込みましょう。
内容に具体性が生まれ、説得力のある発言になります。
状況に応じた柔軟な対応力
AIはルールにもとづいた処理が得意です。
しかし、予期せぬトラブルや変化の多い環境において、柔軟に判断し、対応するのは困難です。
つまり、臨機応変に対応できるのは人間ならではの強みです。
たとえば、顧客からのクレーム対応や災害時の緊急対応など、前例のない状況では、マニュアルにない判断が求められます。
想定外の状況でも、臨機応変に対応するのは、AIが苦手とする領域です。
就活では、アルバイトやサークル活動での経験を通じて、予測不能な事態にどう対応したかを具体的に話すことで、柔軟性をアピールできます。
つまり、AIでは代替できない人材だと、面接官に伝えることが可能です。
自己学習を継続する姿勢
就職後は、新しい技術や情報が次々と生まれるため、常に学び続け、自分自身をアップデートしていく姿勢が重要です。
一度身につけたスキルに満足せず、積極的に新しい知識を習得していく人材は、どんな変化にも柔軟に対応できます。
つまり、企業にとって、採用する価値の高い人材となります。
就活では、学生時代にどのようなことに興味を持ち、どうやって学んだかを具体的に話してください。
面接官に入社後の姿を期待させつつ、自己学習意欲をアピールできます。
もし、学習を継続した経験がない就活生は、今日から何か勉強を始めてください。
現在進行形であると正直に伝えることで、上記と同じような効果が得られます。
まとめ
現在は、AIの登場により、仕事を奪われる可能性がある時代です。
だからこそ、人間にしかできない力を伸ばすことが大切です。
給与や福利厚生に目がいく気持ちは理解できますが、将来を見据えたキャリア設計も忘れてはなりません。
納得のいく就活にするためにも、AIについてきちんと理解しておきましょう。
AIを使う側になることで、AIに怯える必要がなくなります。
AIに不安を抱く就活生は、この記事の解説を参考にしてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

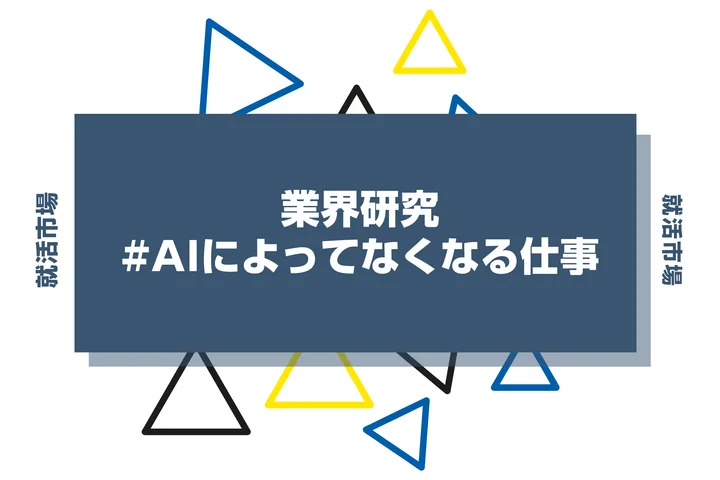


_720x550.webp)






