【短所のいい例】人事が短所を聞く理由
面接で短所を質問されると、多くの学生は「欠点を正直に話して評価が下がるのでは」と不安を感じます。
しかし、人事の意図は減点ではなく、あなたの自己理解の深さや課題への取り組み姿勢、そして社風との相性を見極めることにあります。
短所は、伝え方と補足の仕方次第で強みに変えることも可能です。
本記事では、人事が短所を聞く3つの理由を詳しく解説します。
自己理解の深さを測るため
人事が短所を聞く大きな理由の一つは、応募者が自分をどれだけ客観的に理解しているかを知るためです。
自己理解が深い人は、自分の行動パターンや感情の傾向を整理し、改善の糸口を見つける力を持っています。
これは入社後の成長スピードにも直結します。
逆に、自己理解が浅いと、回答が集中力がない、緊張しやすいといった一般的な表現に終始し、説得力に欠けます。
具体的なエピソードや背景が伴わないと、人事は自分をあまり振り返っていないと判断します。
短所を伝える際は、どのような場面で現れるのか、なぜそうなったのかを具体的に述べることが重要です。
たとえば行動が早すぎて周囲とのペースが合わないという短所なら、新しい課題に取り組む際に先走って資料を作成してしまい、後で方向性を修正することがあったなど、事例とともに説明します。
さらに、その経験を通じて何を学び、どう改善しようとしているかを添えることで、単なる欠点ではなく成長意欲を示す材料になります。
自己理解の深さは、正直さと分析力、そして成長可能性の証明になるのです。
課題への向き合い方を見るため
短所の質問は、単なる弱点探しではなく、その課題にどう向き合ってきたかを評価するための場です。
企業は、完全無欠な人材よりも、課題を認識し、それを改善する努力を継続できる人を求めています。
実際、仕事を進める上では失敗や改善点が必ず生まれます。
そのときに、諦めるのではなく改善策を考え、実行できる姿勢が重要です。
短所を答える際は、課題を認識 → 改善のための行動 → 成果や変化という流れで伝えると効果的です。
例えば優先順位をつけるのが苦手という短所を挙げた場合、タスクを同時進行しようとして全体の進捗が遅れることがあったと具体例を示し、その後、優先度を付けるためのToDoリストを毎朝作成するようにした結果、納期を守れるようになったと改善の過程を説明します。
この流れを守れば、短所はむしろ前向きな印象を与えます。
ポイントは、改善策が実際に効果を上げた事例を入れることです。
努力していますで終わらせず、その努力でこう変わったという成果まで伝えると、課題への向き合い方が具体的に伝わります。
人事はこのプロセスを通して、入社後の成長力や問題解決力を見極めています。
社風と合うか見極めるため
短所は、応募者がその会社の文化や価値観に合うかを見極める材料にもなります。
どんなに能力が高くても、社風とミスマッチがあると早期離職や職場の不和につながりやすいため、企業は慎重に判断します。
例えば、スピード感を重視する企業では慎重すぎて行動が遅れるタイプは適応に時間がかかる可能性があります。
一方で、正確性を重視する企業では、その慎重さが強みとして評価されることもあります。
このため、短所を答える際は、応募企業の社風や業務内容を理解したうえで伝えることが大切です。
事前に企業研究を行い、自分の短所が業務にどう影響するかを考え、ネガティブになりすぎない表現にする必要があります。
例えば集中すると周りが見えなくなるという短所も、細部までこだわる性格と捉えながら、改善策として作業の合間に周囲の状況を確認する習慣をつけていると付け加えれば、協調性への配慮も伝えられます。
人事は短所の回答から、この人と一緒に働きたいか、職場で力を発揮できるかを判断します。
したがって、短所は自己分析だけでなく企業分析と組み合わせて準備することが、面接での好印象につながるのです。
【短所のいい例】短所は内容を極めることが鍵?
面接やESで短所を伝える際、大切なのは欠点を並べることではなく、その内容を深く掘り下げることです。
表面的な表現だけでは、自己理解の浅さや準備不足と判断される可能性があります。
人事は短所からあなたの自己分析力や改善意欲、そして人柄を読み取っています。
短所を的確に伝えるためには、自分の行動パターンや経験と紐づけて具体化し、改善の取り組みまでを語ることが重要です。
【短所のいい例】25選|定番な短所
短所を見つけるには、まず自分の性格や行動傾向を整理することが大切です。
以下は、就活でよく挙げられる短所の定番例25個です。
ただし、このまま答えるのではなく、必ず具体的な経験や改善策を添えて伝えるようにしましょう。
優柔不断
優柔不断な性格から、複数の選択肢があると時間をかけすぎてしまうことがあります。
特に学生時代のグループ活動では、全員の意見を聞きすぎて決定が遅れた経験があります。
しかし、この性格は裏を返せば慎重さにもつながります。
改善のため、意思決定の期限をあらかじめ設け、必要な情報を優先的に集めてから判断する習慣を取り入れました。
その結果、判断スピードが向上し、チーム活動でもスムーズに方向性を決められるようになりました。
心配性
心配性で、物事に取り掛かる前にリスクや問題点を考えすぎてしまうことがあります。
大学のイベント運営では、想定外のトラブルを恐れて準備が過剰になった経験があります。
ただ、この性格は危機管理能力としても生かせます。
改善のため、懸念点を紙に書き出し、重要度ごとに分類して必要以上に不安を抱え込まないようにしました。
これにより、必要な備えを確保しつつ、行動のスピードも維持できるようになりました。
マイペース
自分のペースで動くことが多く、周囲の進行速度と合わないことがありました。
ゼミの共同研究では、他メンバーの進捗を気にせず作業を進め、調整に手間取ったことがあります。
しかし、この特性は焦らず物事を進められる強みでもあります。
改善として、定期的に進捗共有の場を設け、全体の流れを確認する習慣を身につけました。
結果として、チーム全体の動きと調和しながら、自分のペースも維持できるようになりました。
緊張しやすい
人前に立つと緊張しやすく、頭が真っ白になることがありました。
大学のプレゼンでは、重要な場面で言葉が詰まり、伝えたい内容を十分に話せなかった経験があります。
ただ、事前準備を丁寧に行う習慣はこの性格から生まれました。
改善のため、発表の練習回数を増やし、想定質問への回答も準備しました。
その結果、緊張は残るものの、落ち着いて話せる場面が増え、プレゼンの成功率も向上しました。
完璧主義
細部にこだわりすぎて作業時間が長くなる傾向があります。
学園祭の企画書作成では、細かな表現やレイアウトに時間をかけすぎ、提出がぎりぎりになった経験があります。
しかし、正確性や品質を追求できる強みもあります。
改善策として、まず全体を仕上げてから細部を調整する手順を採用しました。
これにより、納期を守りつつ、品質の高い成果物を作れるようになりました。
人見知り
初対面では距離を置きがちで、打ち解けるまで時間がかかります。
アルバイト先でも、最初は同僚と必要最低限の会話しかできませんでした。
しかし、相手の話をよく聞く姿勢は信頼構築につながります。
改善として、挨拶や簡単な質問から会話を広げることを心がけました。
結果、打ち解けるスピードが上がり、チームワークも向上しました。
頑固
自分の考えを曲げにくく、議論が長引くことがあります。
ゼミ討論では、自分の案に固執して柔軟性を欠いた経験があります。
ただ、信念を持って意見を貫ける強みもあります。
改善のため、まず相手の意見を最後まで聞き、メリットを理解する姿勢を取り入れました。
その結果、より建設的な議論ができるようになりました。
負けず嫌い
勝ち負けにこだわりすぎ、感情的になることがあります。
スポーツサークルで試合に負けた際、必要以上に悔しさを引きずった経験があります。
ただ、この性格は向上心の源でもあります。
改善として、結果より過程や成長に目を向けるよう意識しました。
これにより、冷静さを保ちながらモチベーションを維持できるようになりました。
考えすぎる
物事を深く考えすぎて判断が遅れることがあります。
企画案作成では、あらゆるパターンを検討しすぎて締切直前になったことがあります。
しかし、分析力としては強みです。
改善として、検討時間をあらかじめ設定し、期限内に結論を出すルールを作りました。
その結果、判断のスピードと質のバランスが取れるようになりました。
飽きっぽい
新しいことに興味を持つ反面、長く続けるのが苦手な傾向があります。
資格勉強でも、途中で別の分野に手を出してしまいました。
ただ、好奇心旺盛で幅広い知識を得られる強みもあります。
改善策として、短期目標を設定し、小さな達成感を積み重ねる方法を取りました。
結果、継続力が高まり、最後までやり遂げられるようになりました。
計画性がない
その場の流れで動くことが多く、準備不足になることがあります。
サークルのイベント準備では、直前に慌てて作業することになりました。
ただ、柔軟に対応できる強みもあります。
改善として、ToDoリストを作り、期限を逆算して行動する習慣を取り入れました。
その結果、余裕を持って作業を終えられるようになり、全体の質も向上しました。
楽観的
良くも悪くも「なんとかなる」と考えすぎて、リスクを軽視してしまうことがあります。
旅行計画で事前調査を怠り、当日困った経験があります。
しかし、前向きな姿勢は周囲を安心させる強みです。
改善として、行動前に最低限の準備項目を確認するルールを作りました。
これにより、ポジティブさを保ちながらもトラブルを減らせました。
諦めが悪い
一度決めたことを最後までやり抜こうとしすぎ、非効率になることがあります。
研究テーマで成果が出ない方法に固執し、時間を無駄にした経験があります。
ただ、粘り強さは目標達成に役立ちます。
改善として、定期的に進捗を評価し、必要なら方向転換するよう心がけました。
その結果、努力の効果を最大化できるようになりました。
こだわりが強い
自分なりのやり方に固執し、他人の方法を受け入れにくいことがあります。
アルバイトで業務手順を独自に変え、注意された経験があります。
しかし、品質向上への意識は強みです。
改善のため、まずは既存ルールを尊重し、改善案は相談してから実行するようにしました。
その結果、協調性を保ちながら提案力も生かせるようになりました。
集中しすぎる
一度作業に没頭すると時間を忘れ、他の業務が滞ることがあります。
課題作成で細部に集中しすぎ、他の科目の提出が遅れました。
ただ、高い集中力は成果の質を高めます。
改善として、作業ごとにタイマーを設定し、一定時間で区切る方法を取りました。
これにより、全体のバランスを保ちながら集中力を生かせるようになりました。
流されやすい
周囲の意見に合わせすぎて、自分の意見を出せないことがあります。
グループ決定で多数派に従い、後から後悔した経験があります。
ただ、柔軟に対応できる長所でもあります。
改善として、まず自分の考えをまとめてから会議に臨むようにしました。
その結果、自分の意見を適切なタイミングで発信できるようになりました。
真面目すぎる
責任感が強く、規則やルールを守ることを優先しすぎることがあります。
アルバイトで臨機応変な対応が求められた際、融通が利かずに困った経験があります。
ただ、信頼されやすい性格でもあります。
改善として、状況に応じて優先順位を見直す練習をしました。
これにより、真面目さを保ちつつ柔軟に対応できるようになりました。
めんどくさがり
面倒だと感じる作業を後回しにしがちで、期限が迫ってから慌てることがあります。
掃除や整理整頓でこの傾向が強く出ます。
ただ、効率的な方法を探す習慣があるのは強みです。
改善として、小さな作業はすぐ終わらせる「2分ルール」を導入しました。
結果、後回しの癖が減り、生活や作業がスムーズになりました。
忘れっぽい
予定や細かい作業を忘れてしまうことがあります。
友人との約束をダブルブッキングした経験があります。
しかし、気持ちの切り替えが早いという強みもあります。
改善として、スマホや手帳で予定を一元管理し、リマインダーを活用しました。
その結果、スケジュールミスが減り、信頼性が向上しました。
八方美人
誰にでも良い顔をしようとして、自分の意見がぼやけることがあります。
サークルの意見調整で、全員に配慮しすぎて結論が出なかった経験があります。
ただ、対人関係の円滑さは強みです。
改善として、譲れないポイントを事前に決めてから話し合いに臨むようにしました。
その結果、バランスを保ちながらも芯を持った発言ができるようになりました。
おせっかい
人のことに首を突っ込みすぎて、相手に負担をかけてしまうことがあります。
友人の課題を手伝いすぎて、自分の時間がなくなった経験があります。
しかし、周囲を助けたい気持ちは長所です。
改善として、相手の希望を確認してから手を差し伸べるようにしました。
その結果、適切な距離感でサポートできるようになりました。
ネガティブ
悪い結果を想像しすぎて、行動が慎重になりすぎることがあります。
新しい活動への参加をためらった経験があります。
ただ、リスク回避能力は強みです。
改善として、行動前に「最悪のケースとその対策」を整理し、不安を軽減しました。
結果、行動範囲が広がり、新しい経験を得られるようになりました。
抱え込みやすい
仕事や課題を一人で抱え込み、負担が大きくなることがあります。
ゼミの資料作成を全部自分で引き受け、体調を崩した経験があります。
しかし、責任感の強さは評価されます。
改善として、タスクを分担し、早めに相談する習慣を取り入れました。
その結果、チーム全体の効率も向上しました。
集中力がない
気が散りやすく、作業が長続きしないことがあります。
試験勉強中にスマホを触ってしまうことが多々ありました。
ただ、切り替えが早く多様な業務に対応できる強みもあります。
改善として、作業を短時間の区切りに分けるポモドーロ・テクニックを活用しました。
これにより集中時間が安定し、成果が上がりました。
責任感が強い
責任感が強すぎて、自分を追い込みすぎることがあります。
アルバイトで他人のミスまで引き受け、過労気味になった経験があります。
しかし、信頼される資質は大きな長所です。
改善として、役割分担を明確にし、自分の責任範囲を意識しました。
結果、負担を減らしつつ成果を維持できるようになりました。
【短所のいい例】評価される短所の特徴3つ
面接で短所を聞かれたとき、ただ弱点を並べるだけでは評価は上がりません。
評価される短所とは、長所と表裏一体であり、努力で改善可能で、自己認識と具体的な対策が伴っているものです。
本稿では、その三つの特徴を詳しく掘り下げ、実際に使える表現例と伝え方のコツを紹介します。
準備の仕方から面接での話し方まで、実務に直結する実践的なアドバイスを提供します。
これらを押さえれば、短所を語る場面が逆にあなたの成長意欲を示すチャンスになります。
長所と紙一重であること
面接で評価されやすい短所は、実は長所と紙一重の関係にあります。
たとえば「頑固」という短所は、自分の考えや信念をしっかり持ち、それを貫く強さとも言えます。
この性格は場合によっては周囲と意見が衝突することもありますが、仕事においてはブレない判断力や責任感の高さとして評価されることが多いです。
また「心配性」は細かいところまで気を配る慎重さの裏返しで、ミスの防止やリスク管理に役立つこともあります。
このように短所の裏にはプラス面が隠れているため、単に欠点として伝えるのではなく、長所としての側面も説明することが大切です。
一方で、「遅刻が多い」や「約束を守らない」など、信頼性に直結し改善が難しいものは評価が下がる可能性があります。
短所を伝える際は、その性質を理解したうえで、長所にもなる面を伝え、バランスよく説明することが面接で評価されるポイントです。
改善可能な範囲であること
評価される短所は、本人の努力によって改善できる範囲であることが重要です。
面接官は完璧な人を求めているのではなく、課題を自覚し、それに向き合って成長しようとする姿勢を重視しています。
たとえば「緊張しやすい」「優柔不断」といった性格的な特徴は、経験を積んだり工夫をしたりすることで徐々に克服できます。
しかし、業務に支障をきたす致命的な短所は、たとえ改善したい気持ちがあってもマイナス評価につながることが多いです。
そのため、短所を話す際は「現時点での課題であるが、具体的な改善策に取り組んでいる」という内容をセットで伝えることが効果的です。
こうした説明により、面接官に「自己成長できる人材」としての印象を与えやすくなります。
自己認識と対策がセットであること
短所を伝える際は、単に「こういう欠点があります」と述べるだけでなく、自己認識と具体的な対策をセットで話すことが大切です。
たとえば「集中しすぎて全体の状況を見落とすことがあるため、タイマーを使って時間管理を行っています」と説明すれば、課題の自覚と対策が一体となっていることが伝わります。
面接官は短所そのものよりも、課題に気づき、改善に向けて行動しているかどうかを重視しています。
自己分析がしっかりできていて、改善意欲があることを示せれば、マイナス面があっても評価につながる可能性が高いです。
したがって、短所の説明は「気づき」から「具体的な行動」まで一貫して話すことが、採用評価のポイントとなります。
【短所のいい例】丁寧で信頼感のある印象にする伝え方
私の短所は慎重すぎる点です。
慎重であるがゆえに、決断に時間がかかってしまうことがあります。
しかし、この性格はミスを防ぎ、周囲から信頼を得るうえで大きな役割を果たしています。
大学のゼミ活動で、グループの計画を進める際に、細部まで確認を怠らず、リスクを洗い出して慎重に進めた結果、大きなトラブルを未然に防ぐことができました。
そのため、時間はかかりますが、最終的に安心して任せてもらえる信頼感につながっています。
今後は、効率性も意識しつつ、この慎重さを活かして丁寧な仕事を続けていきたいと考えています。
P(結論)
結論部分は、まず自分の短所を端的に述べることが重要です。
面接官は具体的な話を聞く前に、どんな短所かを把握したいためです。
たとえば「私の短所は慎重すぎるところです」と簡潔に伝えます。
この時、ネガティブな印象を与えすぎないよう、「慎重すぎる」といった言葉を選ぶと良いでしょう。
また、結論の後に続く理由やエピソードでしっかり補足することを意識してください。
結論を明確にしておくことで、話の流れが整理され、聞き手に理解されやすくなります。
短所を最初に示すことで、自己理解があることを示し、その後の説明に説得力を持たせる効果もあります。
R(理由)
理由のパートでは、結論で述べた短所が具体的にどのような性質を持ち、どのような影響を及ぼすかを説明します。
ここで重要なのは、単に「短所です」と言うだけでなく、なぜその短所が課題として現れるのか、具体的な理由を明確に伝えることです。
例えば「慎重すぎるために、意思決定に時間がかかり、業務が遅れることがある」といったように、自分の行動や性格が仕事にどう関わるのかを示すことで、面接官は短所の内容をより深く理解できます。
加えて、この説明によって自己分析の深さや課題認識の高さをアピールできます。
理由を伝える際は、できるだけ客観的な視点を取り入れ、感情的にならず冷静に話すことが望ましいです。
また、課題として認識しているだけでなく、その短所が仕事やチームの成果にどのような影響を及ぼすかを考えられることも評価されます。
理由部分は、自己理解のレベルを示す重要なパートです。
E(エピソード)
エピソードは、短所を裏付ける具体的な体験や出来事を話す部分です。
面接官は抽象的な話だけでなく、実際にどのような場面でその短所が現れたのかを知りたいと考えています。
例えば「大学のゼミ活動で、グループの計画を進める際に細部まで入念に確認し、リスクを洗い出してトラブルを未然に防いだ」という具体例を示すことで、話に説得力が生まれます。
また、この段階で短所がどのように良い方向に働いたかを一緒に伝えると効果的です。
たとえば「時間はかかりましたが、結果的にメンバーからの信頼を得ることができた」といったポジティブな側面を含めることで、短所が単なる欠点でなく成長や成果に繋がる力であることを印象付けられます。
エピソードは話の具体性とリアリティを高める役割があり、面接官の記憶に残りやすくするために重要です。
話す際はわかりやすく簡潔にまとめ、聞き手がイメージしやすいように配慮しましょう。
P(結論)
最後の結論は、話の締めくくりとして非常に重要です。
ここでは、冒頭の短所を踏まえつつ、それをどのように克服・改善し、どのように仕事に活かしていくかを具体的に伝えます。
たとえば「慎重すぎる点は意識して効率も考えながら仕事に取り組み、丁寧かつ信頼される仕事を続けていきたい」という表現が適切です。
このパートでは、短所を単なる欠点として終わらせず、前向きな成長意欲や問題解決能力を示すことがポイントです。
また、具体的な改善策や工夫を述べることで、面接官に自発的に課題に向き合う姿勢を印象付けられます。
結論の締めくくりが強ければ、話全体がまとまり、聞き手に好印象を与えられます。
自己分析から課題認識、行動、成長の流れをわかりやすく伝えられることが、短所の伝え方で最も評価される部分です。
【短所のいい例】25選|短所の例文集
短所は単なる弱点ではなく、適切に伝えることで自己成長の意欲や人柄の魅力を示すチャンスになります。
本記事では就活や面接でよく挙げられる25の短所を厳選し、それぞれの特徴や伝え方のポイント、具体的な例文を解説します。
単にネガティブに捉えられないよう、長所とのバランスや改善努力を伝えるコツも盛り込みました。
初めて短所を整理する方にも参考になる内容です。
優柔不断
私の短所は、物事を決めるまでに時間がかかってしまう優柔不断なところです。
たとえば、チームでプロジェクトを進める際、複数の選択肢があると、どれも捨てがたく、どの選択肢を選べば最善の結果につながるかを深く考えすぎてしまいます。
その結果、決定が遅れてしまい、チームメンバーに迷惑をかけてしまった経験があります。
この短所を改善するために、現在は、選択肢を3つに絞り、それぞれのメリットとデメリットを書き出すことを習慣づけています。
そして、最終的には「この選択肢を選んだらどうなるか」という未来を具体的に想像することで、納得して決断できるよう努めています。
この取り組みを通じて、最近では、以前よりも迅速に決断を下せるようになってきました。
優柔不断な性格をネガティブなまま伝えるのではなく、「深く物事を考えることができる」という長所につなげることが重要です。
例文では、物事を決めるのに時間がかかるという事実を認めた上で、その背景に「最善の結果を求めている」という前向きな意図があることを示しています。
また、具体的な改善策として「選択肢を絞って分析する」という行動を提示することで、問題意識を持って主体的に改善に取り組んでいる姿勢をアピールしています。
心配性
私の短所は、心配性なところです。
新しい仕事やプロジェクトを任されると、成功するかどうか、ミスをしてしまうのではないか、とついあれこれと考えてしまいます。
たとえば、重要なプレゼンテーションを控えている時は、資料の細かな部分まで何度も見直し、想定される質問に対する回答も網羅的に用意しようとします。
その結果、準備に時間がかかりすぎてしまうことがありました。
しかし、この心配性な性格は、リスクを事前に洗い出すことや、万全の準備をすることに繋がるという側面もあります。
現在は、心配な点をリストアップし、優先順位をつけて対策を講じることで、効率的に準備を進める工夫をしています。
このやり方によって、不安を解消しつつ、計画的かつ確実に業務を進められるようになりました。
心配性な性格は、リスク管理能力や慎重さとしてポジティブに捉えることができます。
例文では、「ミスを恐れる」という側面を率直に認めつつ、それが「万全の準備」という行動につながっていることを示しています。
また、「心配な点をリストアップして優先順位をつける」という具体的な改善策を提示することで、ただ心配するだけでなく、それを業務に活かす工夫をしている点をアピールしています。
マイペース
私の短所は、周囲の状況に左右されず、自分のペースで物事を進めてしまうマイペースなところです。
チームで一つの目標に向かって作業を進める際、つい自分の担当分に集中しすぎてしまい、チーム全体の進捗状況を把握できていないことがありました。
その結果、チーム全体の足並みが乱れてしまう原因を作ってしまったこともあります。
この短所を改善するため、現在は、こまめな報連相(報告・連絡・相談)を心がけるようにしています。
具体的には、作業を始める前に、チームのメンバーに進捗状況を確認し、自分の担当分が終わった際もすぐに共有するようにしています。
また、チャットツールなどを活用し、リアルタイムでチームの状況を確認することで、自分のペースとチームのペースを同期させる工夫をしています。
マイペースな性格は、集中力や自律性の高さとしてポジティブに言い換えられます。
例文では、マイペースが原因でチームの足並みを乱してしまったという反省を述べつつ、具体的な改善策として「こまめな報連相」と「チャットツールの活用」を提示しています。
これにより、自身の短所を自覚し、チームワークを重視して行動している姿勢を効果的に伝えています。
緊張しやすい
私の短所は、人前で話すことや、大勢の人の注目を集める場面で極度に緊張してしまうところです。
たとえば、重要な会議での発表や、顧客へのプレゼンテーションの際、頭が真っ白になってしまい、準備していた内容を十分に伝えきれないことがありました。
その結果、自分の能力を過小評価されてしまったのではないかと感じたこともあります。
しかし、この緊張しやすい性格は、事前の準備を徹底するという行動につながっています。
現在は、緊張を和らげるために、本番で話す内容を何度も声に出して練習したり、想定される質問と回答をまとめた資料を用意したりしています。
また、発表前には深呼吸をするなど、精神的なコントロールも意識的に行うことで、以前よりも落ち着いて発表に臨めるようになりました。
緊張しやすいという短所は、裏を返せば、真剣に物事に取り組む姿勢の表れです。
例文では、緊張で本来の力が発揮できないという課題を率直に述べつつ、それを克服するための具体的な準備や練習方法を提示しています。
これにより、「緊張しても、準備を怠らない真面目さ」や「課題解決に向けて努力する姿勢」をアピールすることができます。
完璧主義
私の短所は、完璧主義なところです。
仕事において、常に最高の成果を求めてしまうため、一つのタスクに時間をかけすぎてしまうことがあります。
たとえば、資料作成を任された際、細かなレイアウトや表現にこだわりすぎてしまい、締め切りギリギリまで作業を続けてしまうことがありました。
その結果、他のタスクがおろそかになってしまったり、チームメンバーの作業を待たせてしまったりしたことが反省点です。
この短所を改善するため、現在は、タスクに着手する前に「この作業のゴールはどこか」「どのレベルまで仕上げれば十分か」を明確に設定するようにしています。
そして、設定したゴールに到達した時点で、潔く次のタスクへ移ることを意識的に行うようにしました。
完璧主義は、質の高い仕事につながるという長所にもなり得ます。
例文では、完璧主義が原因で生じた「時間の浪費」や「チームへの迷惑」というマイナス面を正直に伝えつつ、それを改善するために「ゴールの明確化」という具体的な行動を提示しています。
これにより、自身の課題を客観的に分析し、効率性も意識できるようになった成長をアピールできます。
人見知り
私の短所は、初対面の人と話すのが苦手で、人見知りをしてしまうところです。
新しい環境に身を置くと、自分から積極的に話しかけることができず、打ち解けるまでに時間がかかってしまうことがあります。
そのため、チームの輪に入るのが遅れたり、他部署の人との連携が円滑にいかない時期がありました。
しかし、人見知りをする分、一度信頼関係を築いた相手とは、深くじっくりと向き合うことができます。
この短所を改善するため、現在は、まずは相手の話をじっくり聞く姿勢を心がけています。
共通の話題を見つけたら、そこから少しずつ質問をすることで、自然な形で会話を広げる練習をしています。
この取り組みによって、相手との信頼関係を丁寧に築けるようになりました。
人見知りという短所は、相手を深く知ろうとする誠実さや、聞き上手であるという長所と捉えることができます。
例文では、人見知りが原因でコミュニケーションが円滑にいかなかったという事実を認めつつ、「一度信頼関係を築いた相手とは深く向き合える」というプラスの側面を伝えています。
改善策として「聞き手に回る」というアプローチを提示することで、無理に社交的になろうとするのではなく、自身の強みを活かしてコミュニケーションを改善しようとしている姿勢を効果的に伝えています。
頑固
私の短所は、自分の意見や考えを曲げられない頑固なところです。
一度「これが正しい」と判断すると、他人の意見を聞き入れず、自分のやり方を通そうとしてしまうことがあります。
チームで新しいアイデアを出し合う際、自分の意見ばかり主張してしまい、議論を停滞させてしまった経験があります。
しかし、この頑固さは、一度決めたことを最後までやり抜く粘り強さにもつながると考えています。
この短所を改善するため、現在は、自分の意見を主張する前に、まず相手の意見を最後まで聞くことを意識しています。
そして、相手の意見の中に自分の考えにない視点や良い点がないかを探し、積極的に取り入れるように努力しています。
この取り組みによって、多角的な視点から物事を考えられるようになり、チームでの議論もより活発になりました。
頑固さは、意志の強さや信念の強さとして言い換えられます。
例文では、頑固さが原因でチームでの議論が停滞したという失敗を正直に認めつつ、それを「最後までやり抜く粘り強さ」という長所につなげています。
さらに、改善策として「まず相手の意見を聞く」という具体的な行動を提示することで、独りよがりにならず、周囲との協調性を大切にする姿勢をアピールしています。
負けず嫌い
私の短所は、負けず嫌いなところです。
仕事でライバルとなる人がいると、その人に負けたくないという気持ちが先行し、自分の成果を過度にアピールしたり、相手の成功を素直に喜べないことがありました。
過去には、チームメンバーと協力して一つの目標を達成するべき場面で、個人プレーに走ってしまい、チーム全体のパフォーマンスを下げてしまったこともあります。
しかし、この負けず嫌いな性格は、高い目標に向かって努力し続ける原動力にもなります。
この短所を改善するため、現在は「誰かと比べるのではなく、過去の自分を超える」という意識を持つようにしました。
また、チームの目標達成を第一に考え、メンバーの良い点を見つけて素直に褒めることで、協力的な関係を築く努力をしています。
負けず嫌いな性格は、向上心やハングリー精神としてポジティブに捉えられます。
例文では、負けず嫌いが原因でチームワークを阻害してしまったという反省を述べつつ、それを「向上心」や「自己成長」という前向きな力に変えようとしている姿勢を示しています。
具体的な改善策として「過去の自分を超える意識」と「チームメンバーを褒める」という行動を提示することで、個人主義から協調性へと意識をシフトさせている点をアピールしています。
考えすぎる
私の短所は、物事を深く考えすぎてしまい、行動に移すまでに時間がかかることです。
新しい仕事や課題を与えられると、あらゆる可能性やリスクを予測し、完璧な計画を立てようとします。
その結果、いつまでも「準備段階」から抜け出せず、実際の行動に移るのが遅れてしまうことがありました。
過去には、この考えすぎが原因で、せっかくのチャンスを逃してしまったこともあります。
しかし、この短所は、慎重さやリスク管理能力の高さとして捉えることもできます。
この短所を改善するため、現在は「まずはやってみる」ということを意識的に心がけています。
計画は8割ほどで完了させ、残りの2割は実践しながら調整していくようにすることで、より迅速にタスクに着手できるようになりました。
考えすぎるという短所は、慎重さや分析力、計画性として言い換えられます。
例文では、考えすぎが原因で行動が遅れるという事実を認めつつ、それを改善するために「まずはやってみる」という行動指針を提示しています。
これにより、「分析力」という強みを活かしつつ、「行動力」という弱点を克服しようとする成長意欲をアピールできます。
飽きっぽい
私の短所は、新しいことにはすぐ飛びつくのですが、一つのことを長く続けるのが苦手で飽きっぽいところです。
これまで、様々な趣味や習い事に挑戦してきましたが、ある程度のレベルに達すると、次の新しいことに興味が移ってしまい、最後までやり遂げたと言えるものが少ないのが課題です。
しかし、この飽きっぽい性格のおかげで、多岐にわたる分野に興味を持ち、幅広い知識や経験を得ることができたという側面もあります。
この短所を改善するため、現在は、新しいことを始める際に「なぜそれをやりたいのか」という目的を明確に設定し、達成すべき具体的な目標を立てるようにしています。
そして、目標を達成するまでは次のことに手を出さないというルールを自分に課すことで、粘り強く物事を続けられるよう努力しています。
飽きっぽい性格は、好奇心旺盛さや、多様な経験を積めるという長所として捉えられます。
例文では、飽きっぽいという短所を正直に認めつつ、それによって「幅広い知識や経験を得られた」というプラスの側面を伝えています。
改善策として「目的や目標設定」という具体的な行動を提示することで、衝動的な行動を抑え、計画的に物事を進めようとする姿勢をアピールできます。
計画性がない
私の短所は、計画性がないところです。
物事を始める前に、全体のスケジュールや段取りを立てることが苦手で、行き当たりばったりで行動してしまうことがあります。
その結果、締め切りが迫ってから慌てて作業に取りかかったり、タスクの漏れが発生したりして、周囲に迷惑をかけてしまった経験があります。
しかし、この計画性のなさは、突発的な事態にも柔軟に対応できるという一面もあります。
この短所を改善するため、現在は、大きなタスクを任された際、まず最初に全体像を把握し、そこから逆算してやるべきことを細分化するようにしています。
そして、各タスクに締め切りを設定し、進捗状況をこまめにチェックすることで、計画的に業務を進められるように努めています。
計画性がないという短所は、フットワークの軽さや、柔軟な対応力としてポジティブに言い換えられます。
例文では、計画性のなさによる失敗を反省しつつ、それを改善するために「タスクの細分化」や「逆算思考」という具体的な行動を提示しています。
これにより、自身の弱点を認識し、計画的に行動するための具体的な工夫をしている姿勢をアピールできます。
楽観的
私の短所は、物事を楽観的に捉えすぎてしまうところです。
困難な状況に直面しても「なんとかなるだろう」と考えがちで、事前のリスク管理や準備が甘くなってしまうことがあります。
チームで新しいプロジェクトを立ち上げた際、楽観的な見通しを立ててしまい、想定外の問題が発生したときに適切な対応が遅れてしまった経験があります。
しかし、この楽観的な性格は、どんな困難な状況でも前向きな姿勢を保ち、周囲を明るくする力にもなります。
この短所を改善するため、現在は、何かを始める前に、必ず「最悪の事態」を想定し、その場合の対処法を考えてから行動するようにしています。
この取り組みによって、楽観的な気持ちを保ちつつ、リスクも考慮した現実的な判断ができるようになりました。
楽観的な性格は、前向きさや、周囲を明るくする力としてポジティブに捉えられます。
例文では、楽観的すぎることが招いた失敗を正直に認めつつ、それを改善するために「最悪の事態を想定する」という具体的な対策を提示しています。
これにより、「前向きさ」という強みを活かしつつ、「リスク管理」という弱点を克服しようとしている成長意欲をアピールできます。
諦めが悪い
私の短所は、一度決めた目標や取り組んでいることに対して、諦めが悪いところです。
非効率なやり方だとわかっていても、「もう少し頑張ればうまくいくかもしれない」と考えて、無駄な努力を続けてしまうことがあります。
チームで進めているプロジェクトで、方向転換が必要な場面でも、これまでの努力を無駄にしたくないという気持ちから、なかなか新しいアイデアを受け入れられなかったことが反省点です。
しかし、この諦めの悪さは、困難な状況でも粘り強く物事に取り組めるという長所にもつながると考えています。
この短所を改善するため、現在は、定期的に客観的な視点から自分の行動を振り返る時間を持つようにしています。
そして、「このまま続けても効果が薄い」と判断した場合は、潔く方向転換することを意識しています。
諦めが悪いという短所は、粘り強さや、最後までやり遂げる力としてポジティブに言い換えられます。
例文では、諦めが悪いがゆえの非効率さや、方向転換の遅れを正直に認めつつ、それを改善するために「客観的な振り返り」という具体的な行動を提示しています。
これにより、自分の長所を活かしつつも、状況に応じて柔軟に対応できる能力も身につけようとしている姿勢をアピールできます。
こだわりが強い
私の短所は、仕事のやり方や成果物に対して、こだわりが強いところです。
自分なりの理想が高く、他の人が作ったものや、自分の意見と違うやり方に対して、納得できないと感じてしまうことがあります。
過去には、チームで一つの資料を作成する際、メンバーが作成した部分に、自分のこだわりを押し付けてしまい、雰囲気を悪くしてしまったことがあります。
しかし、このこだわりは、質の高いアウトプットを生み出すことにもつながります。
この短所を改善するため、現在は、まず相手の意図や考えをしっかりと聞くように努めています。
そして、自分の意見を伝える際は、「なぜそう思うのか」という理由を明確に説明し、客観的に納得してもらえるような伝え方を意識しています。
こだわりが強いという短所は、プロ意識の高さや、妥協しない姿勢としてポジティブに捉えられます。
例文では、こだわりが原因でチームの雰囲気を悪くしたという失敗を反省しつつ、それを改善するために「相手の意見を聞く」という協調的な姿勢と、「論理的な説明」というコミュニケーションの工夫を提示しています。
これにより、自分のこだわりを活かしつつ、周囲と円滑に協力できる能力も備えていることをアピールできます。
集中しすぎる
私の短所は、一つのことに集中しすぎてしまい、周囲が見えなくなってしまうところです。
タスクに取り組むと、周りの音が聞こえなくなるほど没頭してしまうため、他の人からの呼びかけに気づかなかったり、時間配分を誤ってしまったりすることがあります。
過去には、締め切りが近い別のタスクがあるにもかかわらず、目の前の作業に集中しすぎてしまい、納期を遅らせてしまったことが反省点です。
しかし、この集中力は、質の高いアウトプットを効率的に生み出すという長所でもあります。
この短所を改善するため、現在は、作業を始める前に、タスク全体のスケジュールを可視化し、タイマーを設定するようにしています。
これにより、集中する時間と、周囲の状況を確認する時間を区別できるようになりました。
集中しすぎるという短所は、高い集中力や、タスクを深く掘り下げる力としてポジティブに言い換えられます。
例文では、集中しすぎが原因で生じた問題(時間配分ミス、周囲への配慮不足)を率直に認めつつ、それを改善するために「スケジュールの可視化」や「タイマーの活用」という具体的な方法を提示しています。
これにより、自身の強みを活かしつつ、周囲への配慮もできるようになった成長をアピールできます。
流されやすい
私の短所は、周りの意見や雰囲気に流されやすいところです。
自分の中に確固たる意見や考えがあっても、周囲の意見が多勢を占めると、自分の意見を主張できなくなってしまうことがあります。
チームでのブレインストーミングの際、自分のアイデアを出すのをためらってしまい、結果的にチームの議論に貢献できなかったことが反省点です。
しかし、流されやすい性格は、人の意見を素直に受け入れられる柔軟さや、協調性の高さとして捉えることもできます。
この短所を改善するため、現在は、自分の意見を事前に整理し、なぜそう思うのかという理由を明確にしておくようにしています。
これにより、議論の場でも、自信を持って自分の意見を伝えられるようになりました。
流されやすいという短所は、柔軟性や協調性としてポジティブに言い換えられます。
例文では、流されやすさが原因で自分の意見を言えなかったという失敗を認めつつ、それを改善するために「事前の意見整理」という具体的な行動を提示しています。
これにより、協調性を保ちながらも、主体的に意見を発信できるよう成長している姿勢を効果的に伝えています。
真面目すぎる
私の短所は、何事にも真面目に取り組みすぎてしまうところです。
ルールやマニュアルを厳格に守ろうとしすぎるあまり、融通が利かなくなってしまうことがあります。
過去には、イレギュラーな事態が発生した際、マニュアルにない対応方法に戸惑い、迅速な判断ができなかったことが反省点です。
しかし、この真面目さは、責任感が強く、どんな仕事にも誠実に向き合えるという長所でもあります。
この短所を改善するため、現在は「ルールはあくまでも基準」と考えるようにしています。
そして、イレギュラーな事態に備え、事前に上司や先輩に相談する習慣をつけることで、柔軟な対応ができるように努めています。
真面目すぎるという短所は、責任感の強さや、誠実さとしてポジティブに言い換えられます。
例文では、真面目さが原因で柔軟な対応ができなかったという課題を認めつつ、それを改善するために「ルールは基準と考える」「事前の相談」という具体的な行動を提示しています。
これにより、真面目さという長所を活かしつつ、状況に応じて柔軟に対応できるバランス感覚を身につけようとしている姿勢をアピールできます。
めんどくさがり
私の短所は、めんどくさがりなところです。
特に、地道な作業や、時間がかかりそうな作業を後回しにしてしまう傾向があります。
過去には、資料の整理やデータの入力といったルーティンワークを怠った結果、必要な情報がすぐに見つからず、業務効率が低下してしまったことがありました。
しかし、このめんどくさがりな性格のおかげで、「どうすればこの作業を効率化できるか」を常に考えるようになりました。
この短所を改善するため、現在は、面倒な作業こそ、まず最初に着手するように意識しています。
また、マクロ機能やショートカットキーなど、業務を効率化できるツールを積極的に活用することで、面倒な作業をなるべく早く終わらせる工夫をしています。
めんどくさがりな性格は、効率化を考えるきっかけとして捉えることができます。
例文では、めんどくさがりが原因で生じた問題(作業の遅れ、業務効率の低下)を正直に認めつつ、それを改善するために「面倒な作業から先に着手する」という行動と、「効率化ツールの活用」という具体的な工夫を提示しています。
これにより、自身の短所をバネにして、生産性を高めようとしている成長意欲をアピールできます。
忘れっぽい
私の短所は、些細なことをすぐに忘れてしまうところです。
口頭で伝えられた伝言や、細かい作業指示をうっかり忘れてしまい、周囲に迷惑をかけてしまった経験があります。
過去には、お客様から受けた電話の内容をメモし忘れてしまい、後から確認するのに時間がかかってしまったこともありました。
しかし、忘れやすいからこそ、メモを取る習慣が身につき、情報整理の重要性を強く認識するようになりました。
この短所を改善するため、現在は、メモアプリやタスク管理ツールを積極的に活用し、言われたことややるべきことをその場で記録するように徹底しています。
また、重要な伝言は必ず復唱することで、聞き間違いや漏れがないかを確認する習慣も身につけました。
忘れっぽいという短所は、裏を返せば、記憶に頼らず、記録や情報整理の重要性を認識しているという強みにつながります。
例文では、忘れっぽさによる失敗を正直に認めつつ、それを改善するために「メモアプリの活用」「復唱」という具体的な行動を提示しています。
これにより、「忘れっぽい」という弱点を補うための工夫を自主的に行っている点をアピールできます。
八方美人
私の短所は、誰にでも良い顔をしてしまう八方美人なところです。
相手に嫌われたくないという気持ちが強く、自分の意見をはっきりと言えなかったり、頼まれたことを安請け合いしてしまったりすることがあります。
その結果、自分のキャパシティを超えてしまい、仕事が中途半端になったり、周囲からの信頼を損なってしまったことが反省点です。
しかし、八方美人な性格は、協調性が高く、誰とでも円滑な人間関係を築けるという長所でもあります。
この短所を改善するため、現在は、無理な依頼ははっきりと断る勇気を持つように心がけています。
また、自分の意見を伝える際は、相手を否定するのではなく、「私はこう思います」と、Iメッセージで伝えるように意識しています。
八方美人な性格は、協調性の高さや、良好な人間関係を築く力としてポジティブに捉えられます。
例文では、八方美人が原因で生じた問題(仕事の質低下、信頼損失)を正直に認めつつ、それを改善するために「断る勇気」や「Iメッセージでの意見伝達」という具体的な行動を提示しています。
これにより、協調性を保ちながらも、自己主張ができるようになった成長をアピールできます。
おせっかい
私の短所は、人の手助けをしたいという気持ちが強く、ついおせっかいを焼いてしまうところです。
チームメンバーが困っているように見えたら、すぐに声をかけて手伝おうとしてしまい、かえって相手のペースを乱してしまった経験があります。
また、自分の仕事に集中すべきタイミングで、他人の手伝いに時間を費やしてしまい、自分の業務が滞ってしまったこともありました。
しかし、このおせっかいな性格は、周囲の状況をよく見ており、困っている人にすぐに気づくことができるという長所にもつながります。
この短所を改善するため、現在は、相手が本当に助けを必要としているかを確認してから行動するようにしています。
具体的には、「何か手伝えることはありますか?」と一度尋ねてみて、相手の意思を尊重するように意識しています。
おせっかいな性格は、周囲への気配りや、困っている人を放っておけない優しさとしてポジティブに捉えられます。
例文では、おせっかいが原因で相手のペースを乱してしまったという反省を述べつつ、それを改善するために「相手の意思を確認する」という具体的な行動を提示しています。
これにより、周囲への配慮を怠らず、協調性を保ちながら貢献できる姿勢を効果的に伝えています。
ネガティブ
私の短所は、物事をネガティブに捉えやすいところです。
新しい仕事や課題に直面すると、成功するイメージよりも、失敗するイメージを先に思い浮かべてしまい、なかなか前向きに行動できないことがあります。
過去には、挑戦的なプロジェクトを任された際、不安が先行してしまい、本来の力を発揮できなかったことが反省点です。
しかし、このネガティブな性格は、物事のリスクを事前に予測し、慎重に行動できるという長所にもつながります。
この短所を改善するため、現在は、不安に感じたことをノートに書き出し、「どうすればその不安を解消できるか」という具体的な対策を考えるようにしています。
この取り組みによって、ネガティブな感情を「リスク管理」という行動に変換できるようになりました。
ネガティブな性格は、慎重さやリスク管理能力としてポジティブに捉えられます。
例文では、ネガティブさが原因で行動が鈍るという課題を認めつつ、それを改善するために「不安の可視化」と「対策を考える」という具体的な行動を提示しています。
これにより、「ただ不安がるだけ」ではなく、それを建設的な行動につなげている成長意欲をアピールできます。
抱え込みやすい
私の短所は、仕事や悩みを一人で抱え込みやすいところです。
人に弱みを見せたくないという気持ちや、自分の力で解決しなければいけないという責任感から、周囲に相談することが苦手でした。
その結果、業務が予定通りに進まなかったり、精神的に追い詰められてしまったりした経験があります。
しかし、この短所は、責任感が強く、最後まで自分の力でやり遂げようとする姿勢の裏返しでもあります。
この短所を改善するため、現在は、業務の進捗状況を定期的にチームメンバーに共有し、困ったことがあれば早めに相談することを心がけています。
また、困っていることを相談する際は、具体的な状況と、自分なりの解決策をいくつか用意した上で話すことで、より円滑なコミュニケーションを図れるように努めています。
抱え込みやすいという短所は、責任感の強さとしてポジティブに言い換えられます。
例文では、一人で抱え込んだ結果の失敗を正直に認めつつ、それを改善するために「定期的な共有」と「早めの相談」という具体的な行動を提示しています。
さらに、「解決策を用意してから相談する」という工夫を付け加えることで、単に助けを求めるだけでなく、主体的に問題解決に取り組む姿勢をアピールできます。
集中力がない
私の短所は、一つのことに集中力が続かないところです。
特に、長時間同じ作業を続けるのが苦手で、すぐに気が散ってしまい、作業効率が下がってしまうことがありました。
過去には、重要な書類作成の途中で集中力が途切れてしまい、細かいミスを見落としてしまったことが反省点です。
しかし、集中力がない代わりに、多様な情報にアンテナを張り巡らせることができるという側面もあります。
この短所を改善するため、現在は、集中力が途切れてしまう前に、意図的に休憩時間を挟むようにしています。
具体的には、タスクを25分間集中して行い、5分間休憩する「ポモドーロ・テクニック」を実践することで、短時間で高い集中力を維持できるようになりました。
集中力がないという短所は、広い視野を持つことや、多様な情報に気づく力としてポジティブに捉えられます。
例文では、集中力が続かないことによる失敗を認めつつ、それを改善するために「ポモドーロ・テクニック」という具体的な方法を提示しています。
これにより、自身の弱点を認識し、それを克服するための具体的な工夫をしている姿勢を効果的に伝えています。
責任感が強い
私の短所は、責任感が強すぎるところです。
チームで仕事を進める際、自分に与えられた役割だけでなく、チーム全体の責任まで背負い込んでしまうことがあります。
そのため、他のメンバーの業務にも深く関与してしまい、本来の自分の仕事に集中できなくなってしまうことがありました。
また、周囲の期待に応えようとしすぎるあまり、一人で抱え込んでしまい、精神的に追い詰められた経験もあります。
しかし、この責任感の強さは、どんな困難な状況でも最後までやり遂げようとする原動力にもなります。
この短所を改善するため、現在は、自分と他者の役割を明確にし、必要以上に他者の仕事に干渉しないように意識しています。
また、業務が逼迫している際は、上司や同僚に助けを求めることも大切だと考えるようになりました。
責任感が強いという短所は、一見すると長所ですが、過剰になると協調性を阻害したり、自己犠牲につながったりする可能性があります。
例文では、責任感の強さが原因で生じた問題(業務の集中力低下、自己犠牲)を正直に認めつつ、それを改善するために「役割の明確化」や「助けを求める勇気」という具体的な行動を提示しています。
これにより、責任感という強みを持ちつつ、周囲とのバランスも考慮できるようになった成長をアピールできます。
【短所のいい例】避けたいNG短所例
面接で短所を伝える際は、いくつか避けるべきNGパターンがあります。
まず、業務に支障をきたすレベルの短所は絶対に避けましょう。
「無断欠勤が多い」「納期を守れない」といった、社会人としての基本的な責任を欠く内容は、採用の対象外と見なされます。
次に、言い訳に聞こえる短所も危険です。
「仕事が多すぎて時間管理ができない」のように、問題を他者のせいにする態度は、責任感がないと判断されます。
最後に、自慢と捉えられる短所にも注意が必要です。
「完璧主義すぎて他人に任せられない」といった伝え方は、協調性の欠如を疑われる可能性があります。
短所を話す際は、謙虚な姿勢と改善への意欲を示すことが何より重要です。
業務に支障をきたすレベルの短所
業務に支障をきたす短所は、面接で避けるべきNG例です。
例えば、無断欠勤が多い、納期をいつも守れない、チームの指示に協調性なく従えないといった、社会人としての基本的な責任や常識を欠く内容は、企業にとって採用の対象外となる可能性が高いです。
これらの短所は、どんなに他のスキルが高くても、組織の一員として働く上で致命的な問題と見なされます。
また、嘘をついてしまう、顧客の悪口を言ってしまうといった倫理観に関わる短所も同様に避けるべきです。
面接はあくまでビジネスの場であるため、業務遂行能力や協調性を疑われるような短所は伝えないように注意しましょう。
言い訳に聞こえる短所
短所を伝える際、他責思考に聞こえるような言い方は避けるべきです。
時間管理が苦手なのは、仕事が多すぎるから、人見知りなのは、周りが話しかけてくれないからといった、自分の問題を外部環境のせいにするような表現は、責任感の欠如と判断されます。
企業は、自分の弱点を客観的に分析し、自ら改善しようと努力する人材を求めています。
言い訳に聞こえる短所は、問題解決能力が低いと受け取られかねません。
自分の短所を伝える際は、「〇〇という短所がありますが、現在は△△という方法で改善に努めています」と、自分の行動を起点とした改善策を具体的に述べることで、前向きな姿勢をアピールしましょう。
自慢と捉えられる短所
一見すると長所にも見える完璧主義、責任感が強いといった内容は、伝え方によっては自慢に聞こえてしまうことがあります。
例えば、完璧主義なので、他の人には任せられないといった表現は、協調性がない、チームワークを乱すといったネガティブな印象を与えかねません。
また、責任感が強すぎるので、一人で仕事を抱え込んでしまうという表現も、結果的に業務を停滞させる可能性を示唆することになり、リスクとして捉えられます。
これらの短所を伝える際は、それが原因で過去にどのような失敗をしたか、そして、その反省からどのように改善しようとしているかを具体的に述べることが重要です。
自分の短所によって、チームや周囲に迷惑をかけてしまったという謙虚な姿勢を示すことで、成長意欲を効果的にアピールしましょう。
【短所のいい例】まとめ
短所を伝える際は、単に弱点を述べるだけでなく、その短所が業務にどう影響し、どう改善しようとしているかという成長意欲をセットで伝えることが重要です。
企業は、完璧な人間ではなく、自分の弱みを客観的に分析し、課題解決のために努力できる人材を求めています。
そのため、短所を伝える際は、自己分析に基づいた具体的なエピソードと、それを克服するための行動を明確にすることが、採用担当者に良い印象を与えるカギとなります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート



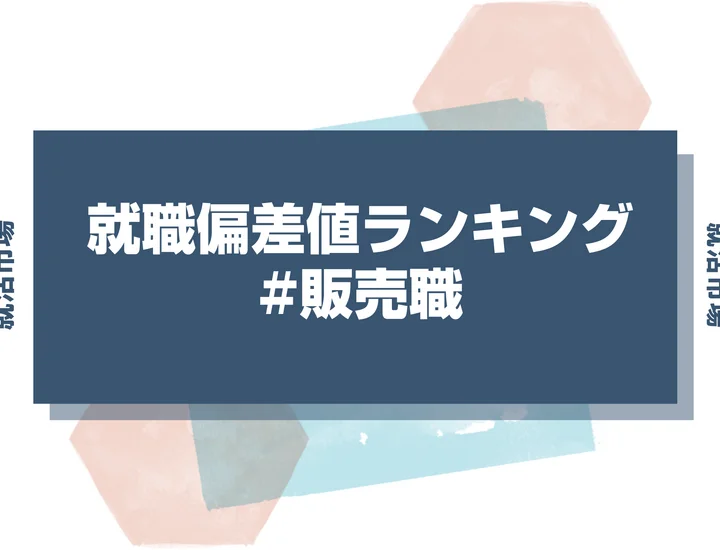

_720x550.webp)





