目次[目次を全て表示する]
はじめに
コロナ禍以降、リモートワークによる働き方が一般化しました。
そのため、新卒でも柔軟な働き方ができるリモートワークを求める傾向にあります。
しかし、すべての職種においてリモートワークができるわけではありません。
この記事では、新卒でも挑戦できるリモートワーク職種を詳しく解説します。
向いている人の特徴や注意点などを理解し、選考を効率よく突破しましょう。
また、リモートワークに適した職種も紹介するので、企業研究に役立ててください。
【リモートワーク 職種】リモートワークの働き方とは
本章では、リモートワークの基本的な知識、働き方について解説します。
リモートワークは、一般的な勤務形態と何が違うのか、どういった特徴があるのか理解しておくことが重要です。
また、どのようにしてリモートワークが導入されるようになったのか、背景も合わせて押さえておきましょう。
「なんとなく楽に仕事ができそう」と考えていると、面接官に浅い考えが見透かされてしまいます。
漠然とリモートワークに興味がある就活生は、参考にしてください。
リモートワークの定義と主な形態
リモートワークとは、会社に出社せず、離れた場所で働くことです。
Remote(遠隔の、離れた)とWork(仕事)を組み合わせた造語になります。
似た言葉にテレワークがありますが、基本的には同じ意味として扱われています。
また、リモートワークは、大きく3種類に分かれます。
| 名称 | 特徴 |
| 在宅勤務 | 業務のすべてを自宅で行う働き方 |
| モバイルワーク | 移動中の車内やカフェなどを勤務地とする働き方 |
| サテライトオフィス勤務 | 遠隔者用のオフィスを用意し、勤務する働き方 |
リモートワーク=在宅勤務だけではありません。
入社後にギャップを生まないためにも、リモートワークの種類と違いについて理解しておきましょう。
リモート勤務の広がりと導入背景
リモートワークの導入は、2020年を境に増加傾向にあります。
厚生労働省が発表した「令和6年通信利用動向調査ポイント」によると、2019年の導入割合は、20.2%でした。
しかし、2020年には47.5%と倍以上の数値となっています。
背景には、コロナの感染予防が考えられるでしょう。
コロナが落ち着いた現在では、社員の働き方改善や業務の効率化を高めることを目的とし、導入を継続している企業があります。
リモートワークを導入する背景が、時代と共に変化していることを理解しておきましょう。
将来、突然リモートワークがなくなることは考えにくいです。
しかし、現状の導入状況が維持されるかは不明です。
リモートワークを希望する就活生は、動向を注視しておきましょう。
参考:令和6年通信利用動向調査ポイント|厚生労働省
新卒就活におけるリモートワークの位置づけ
就活において、リモートワークの重要度が増しています。
リモートワークの有無によって、働き方に大きな違いが生まれるからです。
たとえば、仕事とプライベートの両立を希望する就活生にとって、リモートワークは欠かせない要素です。
通勤時間を趣味や資格の勉強に活かすことで、満足度の高い生活が送れます。
また、リモートでの企業説明会や一次面接、入社後の研修など、さまざまな機会でオンラインが利用され始めています。
リモートでの対応ができない場合、就活の効率が悪くなったり、選考を受けるのに余計な時間がかかったりするでしょう。
リモートワークを希望する就活生は、就活のうちから使いこなせるように、積極的に活用してください。
【リモートワーク 職種】制度の種類と働き方の違い
リモートワークは、すべての企業が同一の制度、種類を導入しているわけではありません。
仕組みや働き方は、企業の価値観や業務体制によって、異なります。
本章では、リモートワークの制度について詳しく解説します。
募集要項に記載のある「リモートワーク可」の言葉だけを信用してしまうと、入社後にギャップを感じる可能性があります。
自分の理想とするリモートワークを、志望企業が採用しているか確かめるための材料にしてください。
完全リモートと一部リモートの違い
リモートワークは、完全と一部の2パターンあります。
それぞれの違いは言葉の通りです。
完全リモートは、出社する必要がまったくありません。
企業全体で採用している場合と部署ごとに採用している場合があります。
さらに、完全リモートであるため、会社から離れた位置に住むことが可能です。
一方で、一部リモートは週に何日や月に何回など、一定回数は出社する必要があります。
完全リモートと比較して、通勤の必要があるため、居住地に限界があるでしょう。
リモートワークを採用している企業に就職する場合、事前にどちらのタイプを採用しているか確認してください。
完全リモートを希望する人が、一部リモートの企業に入社してしまうと、価値観にズレが生じます。
裁量労働やフレックス制度との関係
リモートワークは、裁量労働やフレックス制度と合わせて導入されています。
それぞれを組み合わせることで、より自由度の高い勤務を社員に提供できるからです。
裁量労働とは、労働時間ではなく成果で評価する仕組みです。
また、フレックス制度は始業・終業時間を社員が決める制度になります。
もちろん、リモートワークを導入することで、一定の働きやすさを享受することが可能です。
しかし、掛け合わせることで、社員満足度や生産性の向上も期待できます。
ただし、リモートワークを採用する企業が、両方を採用しているわけではありません。
企業によっては、裁量労働しか認めていない場合があります。
反対に、フレックス制度はあるが、裁量労働が用意されていない場合もあるでしょう。
新卒採用でもリモート制度は活用できるか
新卒採用でもリモートワークは可能です。
コロナ禍以降、企業はリモートワークを積極的に導入しているからです。
入社式や研修が終わったのち、リモートワークを用いた勤務になる企業があります。
ただし、新卒のリモートワークは注意が必要です。
仕事の進め方やビジネスマナー、社内の人間関係などがわからない状態で働く必要があります。
もちろん、企業も対策として資料や研修を用意しているでしょう。
しかし、先輩に対面で質問できない環境は、新卒にとってつらい可能性があります。
また、企業に対する帰属意識が薄くなるといったリスクも挙げられます。
リモートワークは、メリットとデメリットが存在することを理解し、就活の段階から自分に合っているか検討しましょう。
【リモートワーク 職種】求人が多い職種20選
続いて、リモートワークができる職種を紹介します。
リモートワークはすべての職種で採用されるわけではありません。
接客業やサービス業などでの採用は難しいでしょう。
そこで、リモートワークを希望する就活生は、どういった職種を選択することで、自分の理想が叶えられるのか把握してください。
リモートワークしやすい職種に応募することで、スムーズな就活が可能です。
IT・開発系で需要が高い職種
リモートワークは、IT・開発系の職種で採用される傾向にあります。
主にパソコンとインターネットがあれば、仕事が成立するからです。
実際の職種は、以下の表を参考にしてください。
| 職種 | 仕事内容 |
| QAエンジニア | 開発されたアプリやシステムの品質を確認 |
| Webディレクター | クライアントとの打ち合わせ、プロジェクトの管理 |
| インフラエンジニア | システム基盤の設計・構築・運用・保守を担当 |
| アプリ開発エンジニア | アプリの企画・設計・開発・運用・保守を担当 |
| バックエンドエンジニア | システムの開発・設計・導入・運用を担当 |
| フロントエンドエンジニア | ユーザーが直接目にする箇所を開発 例:ログイン画面、ホーム画面 |
プログラミングをはじめとし、インターネットに関係する職種はリモートワークを採用する傾向にあります。
マーケティング・運用系で注目の職種
マーケティングや情報を運用する職種もリモートワークが可能です。
マーケティングなどに興味のある就活生は、以下の表を参考にしてください。
| 職種 | 仕事内容 |
| SEO担当 | Googleなどの検索エンジンで上位表示させる改善を担当 |
| CRM担当 | 既存顧客との良好な関係を構築・維持する役割 |
| SNSマーケター | ソーシャルメディアを活用し、企業ブランドの認知度向上 |
| デジタル広告運用 | Googleなどに広告を出し、その後効果を測定 |
| コンテンツマーケター | メディアを通じて、潜在的顧客から顧客に育成 |
| データアナリスト補助 | 意思決定を支援するためのデータ収集、分析を担当 |
コミュニケーションツールやデータ分析に必要なツールが発達したことで、リモートワークが浸透しています。
事務・営業系でもリモートが進む職種
事務・営業系でもリモートワークが進んでいます。
主な職種は、以下の通りです。
| 職種 | 仕事内容 |
| 営業事務 | 営業担当者が営業に専念できるよう、事務的なサポート 例:書類作成、データ入力 |
| 営業企画 | 売上目標達成に向けて、営業戦略を企画・立案 |
| オンライン秘書 | 秘書業務や事務業務をリモートで行う 例:スケジュール管理、メール対応 |
| 採用アシスタント | 採用活動が円滑に進むよう、事部門をサポート 例:応募者対応、求人票の作成 |
| インサイドセールス | 電話やメールなどを活用した営業活動 |
| カスタマーサクセス | サービスを最大限に活用し、成功体験を得られるように支援 |
業務アプリやシステムの登場により、離れた場所からでも営業職をサポートできるようになりました。
【リモートワーク 職種】リモートワークが難しい職種7選
リモートワークが難しい職種についても解説します。
リモートワークは、新しい働き方として浸透している一方で、すべての職種で取り入れられているわけではありません。
自分が志望する職種とリモートワークができるかどうかは別の話です。
そのため、リモートワークと相性が悪い職種を理解しておきましょう。
自分の価値観と合わない企業に応募しないためにも、参考にしてください。
顧客と対面する接客・販売系の職種
顧客と対面する接客・販売系の職種は、リモートワークが困難です。
顧客と対面し、会話しながら接客する必要があります。
たとえば、アパレル販売員や百貨店スタッフ、飲食店ホールスタッフなどです。
ほかにも、コンビニ店員や美容師なども該当するでしょう。
接客業や販売職は、来店してくださった顧客に対して、サービスを提供します。
そのため、自分も同じ空間にいる必要があります。
もし、リモートワークを採用してしまうと、顧客が求めるサービスが提供できません。
また、顧客のなかには店員との会話を楽しみにしている人もいます。
リモートワークでは代替できない要素です。
今後も、接客・販売職系の職種はリモートワークになるのは難しいでしょう。
現場に出る必要がある医療・製造系の職種
現場に出る必要がある医療・製造系の職種も、リモートワークは難しいです。
医療・製造系の職種は、特定の設備や環境の下でないと、サービスが提供できません。
たとえば、足から血を流している患者がいたとします。
リモートでは、患者との距離があるため直接的な治療ができません。
もちろん、オンライン診療といった診察方法も浸透しています。
しかし、すべての診療が取って変わるわけではありません。
製造系も同様です。
機械化が進む一方で、最後は人間の目による確認が必要です。
作業を効率化しているとはいえ、基準に満たない製品が一定の割合で完成します。
品質や安全性を担保するには、リモートワークではなく、現場での確認作業が求められます。
教育・介護など人との接触が避けられない職種
教育・介護などの人との接触が避けられない職種も存在します。
人と人との関係性が重要であり、直接的な指導や支援が必要になるからです。
たとえば、保育士や介護福祉士、小中高校教員などが挙げられます。
職員の方々は、1人ひとりの様子を詳しく観察しながら、個別のサービスを提供します。
画一的なサービスを提供するわけではないので、リモートによる作業は難しいでしょう。
ただし、文部科学省はオンライン授業を一部認めています。
教員不足が問題となっているため、将来はオンライン形式の授業が増えるかもしれません。
一方で、介護は利用者の体に直接触れる仕事です。
利用者との信頼関係によるサービスの提供になるため、リモートになる可能性は低いでしょう。
参考:全日制・定時制課程の高等学校の遠隔授業|文部科学省
実習や訓練が重視される新人育成職種
実習や訓練が重視される職種もリモートワークは実施されません。
知識に加えて、実践的なスキルや現場での経験を学ぶ必要があるからです。
具体的には、自衛官や警察官、消防士などが挙げられます。
民間企業であれば、航空会社や鉄道会社も当てはまるでしょう。
業務や器具の使い方や安全手順など、実践を伴う指導は対面で行う方が効率的で理解度も高まります。
また、不明点があった場合、すぐに質問が可能です。
誤った方法による使用があった場合もその場での指導ができます。
とくに、人の命を守る仕事において採用されるのが特徴です。
将来的には、一部の項目がリモートに置き換わる可能性はあります。
しかし、完全リモートや在宅勤務のようにはならないでしょう。
チーム作業が必須の現場指揮系職種
チーム作業が必須の現場指揮系の職種もリモートワークに向いていません。
責任者として、自分の目で見たうえで判断、指示する必要があるからです。
具体的には、建設現場の監督やイベント運営スタッフなどが該当します。
現場で作業する職種は、進捗確認や資材の配置、作業員の安全確認などの管理が不可欠です。
もし、管理作業を怠ってしまうと納期に間に合わなかったり、チームの安全を脅かしたりするでしょう。
もちろん、すべての管理を1人で対応するわけではありません。
メンバー同士でチェックすることも重要です。
しかし、最後は責任者としての責任を果たす必要があります。
そのため、現場の指揮を取る職種はリモートワークにするのは困難です。
安全面や設備上の制約がある業種
安全面や設備上の制約がある業種もリモートワークにはならないでしょう。
厳格な安全基準のもと、現場での直接的な操作や監視が義務付けられているからです。
もし、事故が発生した場合、甚大な被害が出る可能性があるため、リモートワークは難しいでしょう。
たとえば、原子力発電所や精密機器工場作業員、危険物取扱業者などが当てはまります。
ほかには、電力・ガス施設の保守点検員や警備員などです。
安全面に配慮が必要な業務は、法律によって規制されています。
そのため、特定の業務は有資格者が特定の場所で従事しなければなりません。
つまり、指示された場所でしか勤務できないため、リモートワークとの相性が悪い仕事です。
クライアント対応に訪問が必須な業務
クライアント対応に訪問が必須な業務は、リモートワークに移行できません。
機器の設置場所の確認や不動産物件の内覧、工場のレイアウト確認など、現地での確認が必要になるからです。
具体的な職種としては、法人営業(訪問型)や不動産仲介営業、施工管理者などになります。
柔軟な働き方として、一部の業務をリモートワークにする企業もあります。
しかし、完全に移行することは難しく、残りの業務は現場に直接訪問しなければなりません。
とくに、高額な商品や複雑なサービスの場合、対面での丁寧な説明が必要です。
時間や手間がかかりますが、顧客に寄り添う姿勢を見せることで、信頼関係の構築に役立ちます。
【リモートワーク 職種】リモートワークのメリットとは
リモートワークのメリットは、以下の3つです。
通勤時間の削減と生産性の向上
自分のペースで働ける柔軟性
生活環境に合わせたキャリアの構築
リモートワークを希望する就活生は、メリットについて理解しておきましょう。
メリットを知らない状態の就活は、周囲と比較して不利に働きます。
メリットの全体像が把握できず、最大限の効果が得られないからです。
自分がどの部分に魅力を感じているのか、理解するきっかけにしてください。
通勤時間の削減と生産性の向上
リモートワークを採用することで、通勤時間の削減と生産性の向上が期待できます。
まず、通勤する必要がなくなることで、その分の時間を別のことに利用可能です。
たとえば、通勤に往復3時間かかったとします。
リモートワークを取り入れることで、本来は移動に費やしていた時間が、業務の準備や資格の勉強に当てられます。
プライベートを優先したい場合、趣味や家族の時間として利用することが可能です。
また、通勤による身体的・精神的な負担がなくなることも大きなメリットです。
満員電車でのストレスや移動による疲労が軽減され、仕事に集中できる時間が増えます。
結果として、心身ともに余裕が生まれ、業務への集中力が高まり、生産性の向上につながります。
自分のペースで働ける柔軟性
リモートワークは、自分のペースで働ける柔軟性にも期待できます。
リモートワークでは、働く場所をある程度自由に選択することが可能です。
子育てや介護などとの両立がしやすくなるでしょう。
また、集中しやすい環境を自分なりに用意することで、仕事を効率よく進められます。
たとえば、1人きりの方が集中できる場合、自宅での作業が効果的です。
さらに、裁量労働やフレックス制度が併用されている場合、働く時間帯も自由になります。
朝型の人なら、早朝から業務を開始し、日中に休憩を挟むといった働き方も可能です。
自分のペースでじっくりと業務に取り組むことで、質の高いアウトプットができます。
仕事の満足度やモチベーションの向上にもつながるでしょう。
生活環境に合わせたキャリアの構築
生活環境に合わせたキャリアの構築もリモートワークの魅力です。
リモートワークは、住む場所の選択肢を広げ、個人の生活環境に合わせたキャリアプランが形成できます。
たとえば、異動による引越しの必要がなくなります。
自分の好きな場所や街で暮らすことで、人生の満足度が高くなるでしょう。
また、自宅で仕事を続けられるため、家族都合によってキャリアを中断する必要がありません。
また、自然豊かな場所や物価の安い地域に移住するといった選択も現実的になります。
その結果、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。
働き方や住む場所に縛られないことで、より自分らしい生き方を追求しながら、長期的な視点でキャリアを築けます。
【リモートワーク 職種】リモートワークのデメリットとは
リモートワークのデメリットは、以下の3つです。
孤独感やチームとの一体感の欠如
自己管理が求められる働き方の難しさ
評価制度やキャリアアップの不透明さ
リモートワークは、新しい働き方として浸透しています。
しかし、リモートワークを採用することで、不都合も存在します。
メリットだけではなく、デメリットについても理解したうえで選択しましょう。
孤独感やチームとの一体感の欠如
リモートワークのデメリットに、孤独感やチームとの一体感の欠如が挙げられます。
リモートワークでは、オフィスで同僚と顔を合わせる機会が減るため、孤独を感じやすくなるからです。
また、会話が仕事の話ばかりでは息が詰まってしまいます。
たまには、世間話や雑談を交えることで、肩の力を抜いた状態での仕事が可能です。
そのため、雑談や偶発的なコミュニケーションが少なくなることで、チームの一員であるという意識が希薄になるでしょう。
その結果、仕事のモチベーション低下や精神的な負担が増す可能性があります。
さらに、一体感の欠如は、情報共有の遅れや連携ミスにもつながりかねません。
離れた位置で働くことで、孤独感が生まれることを覚えておきましょう。
自己管理が求められる働き方の難しさ
リモートワークは、自己管理が求められる働き方です。
リモートワークを活用することで、働く場所や時間を自由に決められます。
しかし、高度な自己管理能力が必要です。
従来はオフィスに出社することで、周囲の視線や上司の管理下にあるため、いい塩梅の緊張感があります。
一方で、リモートワークは仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい働き方です。
つい長時間労働になったり、逆に集中力が途切れて生産性が落ちたりします。
また、運動不足や食生活の乱れなど、健康面への影響も懸念されます。
自分を律して効率的に業務を進めるための規律と工夫が必要です。
リモートワークは、完全な自由ではないため勘違いしないようにしましょう。
評価制度やキャリアアップの不透明さ
リモートワークは、評価制度やキャリアアップの見通しが不透明になりやすいです。
リモートワーク環境下では、上司が部下の働きぶりを直接見れません。
そのため、評価制度の透明性が課題となることがあります。
たとえば、成果に加えて、プロセスも評価に含めるとします。
部下の努力を近くで見ていない上司は、判断が難しくなる可能性があります。
また、偶発的な交流や非公式な情報交換が減少することで、自分の業務が組織全体にどのように貢献しているのかが見えにくくなるでしょう。
その結果、キャリアアップの機会が不透明に感じられることもあります。
公正な評価とキャリアパスの提示は、リモートワークの満足度を維持する上で非常に重要です。
【リモートワーク 職種】営業職でも在宅は可能か
リモートワークは、営業職でも可能です。
以下の職種を選択することで、自宅にいながらの勤務ができます。
インサイドセールス
カスタマーサクセス
営業企画
リモートワークは、対面でのやり取りがある営業職には向いていません。
しかし、一部の営業職はリモートワークが可能です。
適切に選択することで、やりたい仕事と働き方を実現しましょう。
インサイドセールス
インサイドセールスはリモートワークが可能です。
インサイドセールスとは、顧客に直接訪問せず、電話やメール、Web会議ツールなどを活用しながら営業活動することです。
そのため、見込み顧客の開拓や商談、契約締結までの一連のプロセスが自宅で完結します。
子育てや介護などの都合がある人でも、出社する必要がないため、働きやすいでしょう。
また、一般的な営業とは異なり、移動時間が削減されるため、より多くの顧客にアプローチできる点が魅力です。
さらに、今までは遠隔地のため、営業できなかった地域にもアピールできます。
新規顧客の開拓や新しい販路が見つかるでしょう。
カスタマーサクセス
カスタマーサクセスもリモートワークできる職種の1つです。
カスタマーサクセスとは、顧客の成功体験を最大化させる仕事です。
顧客が製品やサービスを最大限に活用できるようサポートし、課題解決や満足度向上に努めます。
従来の販売方法は、製品を販売した瞬間に関係性が終わりました。
しかし、アフターサービスの充実が求められるようになった結果、カスタマーサクセスが設置されるようになりました。
カスタマーサービスは、顧客と対面で接客するわけではないため、高いコミュニケーション能力が必要です。
一方で、顧客とのコミュニケーションは、メールやチャットで行われるため、リモートワーク環境でも支障なく業務を遂行できます。
営業企画
営業企画もリモートワークが可能です。
営業企画は、営業戦略の立案から市場調査、競合分析、営業ツールの作成など、営業活動を裏側から支えます。
上記の業務は、個人の思考力や分析力、資料作成能力が求められることが多く、必ずしも対面での作業が必要ではありません。
以前の職場環境であれば、出社しないとパソコンやインターネットが使えませんでした。
しかし、現在は多くの社会人がパソコンを持つ時代です。
さらに、企業も備品として社員にパソコンを支給します。
そのため、出社する必要性が薄れています。
また、情報収集やチーム内での連携もオンラインツールを通じて効率的に連携することが可能です。
そのため、営業企画はリモートワークに適した職種といえます。
【リモートワーク 職種】向いている人
リモートワークに向いている人は、以下の3つに当てはまる人です。
自主的に動ける主体性がある人
コミュニケーションが得意な人
新しいツールや変化に柔軟な人
リモートワークには向き・不向きが存在します。
自分がリモートワークに向いている人材だと自覚することで、自信を持った状態で面接官にアピールできます。
リモートワークが自分に合った働き方か迷っている就活生は、ぜひ参考にしてください。
自主的に動ける主体性がある人
主体性がある人は、リモートワークに向いています。
リモートワークでは、オフィスのように上司や同僚が常に近くにいるわけではありません。そのため、自分でタスクを見つけ、計画し、実行できる主体性が非常に重要です。
指示を待つだけでなく、自ら課題を発見し、解決策を提案できる人は、リモート環境でも高いパフォーマンスを発揮できます。
また、リモートワーク中にも予期せぬミスやトラブルが発生するでしょう。
上司や同僚が近くにいないため、すぐに助けてもらえるとは限りません。
そこで、情報収集し、行動できる能力が不可欠です。
自己管理能力が高く、責任感を持って業務に取り組める人がリモートワークに向いているでしょう。
コミュニケーションが得意な人
コミュニケーションもリモートワークに欠かせない要素です。
リモートワークは、1人で作業するため、孤独を感じやすい働き方です。
そのため、オンラインだからこそ、意識的にコミュニケーションを取れる人が求められます。
チャットやビデオ通話など、非対面のツールを効果的に活用し、自分の意見を明確に伝えたり、相手の意図を正確に理解したりする能力は必須です。
たとえば、報連相をこまめに行い、チームメンバーや関係者と円滑な連携を図ることで、認識のズレが防げるでしょう。
さらに、プロジェクトをスムーズに進めることも可能です。
相手の状況を思いやり、文字だけでなく声のトーンや表情でも意図を伝えられる人は、リモートワークで強みを発揮します。
新しいツールや変化に柔軟な人
新しいツールや変化に柔軟なこともリモートワークには欠かせません。
リモートワークでは、さまざまなデジタルツールを活用します。
たとえば、Web会議システムやプロジェクト管理ツール、チャットツールなどです。
そのため、新しいテクノロジーへの抵抗がなく、積極的に使いこなせる柔軟性が求められます。
また、リモートワークはオフィスワークとは異なる働き方であり、時には予期せぬトラブルやルール変更なども起こるでしょう。
環境の変化にも戸惑うことなく、前向きに対応し、自ら学習して適応できる人は、ストレスなく業務を進めることが可能です。
さらに、柔軟な姿勢に加えて、常に改善意識を持ち、より良い働き方を模索できる姿勢も活躍できる要因になるでしょう。
【リモートワーク 職種】向いていない人
リモートワークに向いていない人は、以下の3つに該当する場合です。
指示がないと動けないタイプの人
オンラインでの対話が苦手な人
勤務管理や時間調整が難しい人
リモートワークは自由度が高い働き方です。
一方で、特定の特性を持つ人にとっては課題が生じるでしょう。
また、自分の価値観に合わない働き方を選択するのは、就活を後悔する原因になります。
誤った選択をしないためにも、本章の解説を参考にしてください。
指示がないと動けないタイプの人
指示がないと動けないタイプの人は、リモートワークに向いていません。
リモートワークは、上司や同僚と離れた環境で仕事に取り組みます。
そのため、自分で課題を見つけ、解決策を考え、行動する主体性が求められます。
もし、明確な指示がないと作業を開始できない人は、待機する時間が増え、生産性が落ちるでしょう。
ほかにも、次に何をすべきか判断に迷うタイプの人も、リモート環境で生産性を維持するのは難しいでしょう。
作業を進めるにあたって不明点があれば、自分から積極的に質問したり、情報を探しに行ったりする主体性がなければ、業務が滞りやすくなります。
周囲の状況を見ながら、次に取るべき行動を判断する人にとっては、適応が難しいかもしれません。
オンラインでの対話が苦手な人
オンラインでの対話が苦手な人もリモートワークは難しいでしょう。
リモートワークにおけるコミュニケーションは、基本的にオンラインツールです。
オンラインツールは、対面での会話に比べて、相手の表情やニュアンスが伝わりにくいという特性があります。
そのため、オンラインでの対話に抵抗がある、あるいは自分の意図を正確に伝えるのが苦手な人は、コミュニケーションエラーを起こしやすくなるでしょう。
また、対面での会話は、雑談から生まれる人間関係の構築や非公式な情報共有の機会があります。
しかし、オンラインではチームとの一体感を保つのが難しいと感じるでしょう。
そのため、リモートワークで活躍するには、積極的にオンラインツールを活用し、円滑なコミュニケーションを図るスキルが求められます。
勤務管理や時間調整が難しい人
リモートワークは、勤務管理や時間調整が重要です。
リモートワークでは、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、自己規律にもとづいた厳密な勤務管理や時間調整が不可欠です。
自分で労働時間を管理するのが苦手、休憩を適切に取れない、あるいは仕事とプライベートの切り替えが難しい人は、長時間労働になる可能性があります。
自宅という環境は、誘惑が多かったり、家族からの干渉があったりすることで、集中を維持するのが難しい場合もあります。
その結果、締め切りに遅れたり、連絡ミスが起こったりするでしょう。
自己管理能力が不足していると生産性が下がり、心身の健康を損なうリスクが高まります。明確なルーティン設定や意識的なオン・オフの切り替えが重要です。
【リモートワーク 職種】リモートワークに必要なスキル
リモートワークに必要なスキルは、以下の3つです。
タスクと時間を管理する自己マネジメント力
オンラインツールの基本操作スキル
非対面で成果を出すための文章力と報連相
リモートワークを始めるにあたって、必要なスキルについて理解しておきましょう。
就活の段階から意識して身につけることで、スムーズにリモートワークに参加できます。
現時点でスキルを持っていなくても問題ありません。
今から取得できるように行動してください。
タスクと時間を管理する自己マネジメント力
リモートワークには、自己マネジメント力が必要です。
リモートワークでは、自分でタスクを把握し、優先順位を決めます。
さらに、作業する時間も自分で決めなければなりません。
もちろん、上司や同僚に相談することは可能です。
しかし、直接的に監視してくれるわけではありません。
明確な指示がなくても、プロジェクトの全体像を把握し、今やるべきことを見極める能力が求められます。
また、集中力を維持するために、適切なタイミングで休憩を取るなど、自分の体調や精神状態を管理するセルフケアの側面も含まれます。
仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちなリモート環境だからこそ、計画的に業務を進め、メリハリをつけて働くための自己規律が不可欠となります。
オンラインツールの基本操作スキル
オンラインツールの基本操作スキルも重要です。
リモートワークは、業務を円滑に遂行するために、さまざまなオンラインツールが活用されます。
たとえば、Web会議システムならZoomやGoogle Meetなどがあります。
チャットツールは、SlackやMicrosoft Teamsなどです。
ほかにも、プロジェクトを管理するツールやデータをクラウド上に保存するツールの操作スキルも必須です。
これらのツールを使いこなすことで、チームメンバーとのコミュニケーションが円滑になります。
さらに、情報共有が簡単になり、共同作業がスムーズに進むでしょう。
ツールの操作に戸惑うことなく、積極的に活用していく姿勢が、リモートワークの生産性を大きく左右します。
非対面で成果を出すための文章力と報連相
リモートワークは文章力と報連相が求められます。
リモートワークでは、対面でのコミュニケーション機会が減少するからです。
そのため、文章による情報伝達の正確性と明瞭さが重要になります。
たとえば、チャットやメールで意図を正確に伝えたり、報告書や企画書を分かりやすくまとめたりするなどの高い文章力です。
また、状況をタイムリーに共有する報告・連絡・相談といった、報連相のスキルも重要です。
疑問点や問題が発生した際、曖昧にせず早めに周囲に共有することで、誤解を防ぎ、迅速な解決につながります。
非対面のコミュニケーションは、おろそかになりがちなので、意識して取り組むようにしましょう。
【リモートワーク 職種】リモートワークの注意点
リモートワークする際、以下の3点に注意してください。
コミュニケーション不足によるトラブル
情報セキュリティへの意識と対策
評価や人間関係での誤解が生じやすい点
リモートワークは、近年取り入れられた働き方です。
まだまだ改善の余地があります。
思わぬミスやトラブルを引き起こさないためにも、注意点について学びましょう。
コミュニケーション不足によるトラブル
リモートワークは、コミュニケーション不足によるトラブルに注意してください。
リモートワークでは、偶発的な雑談や非公式な情報共有の機会が減少します。
そのため、コミュニケーション不足が発生します。
その結果、業務の進捗状況が見えにくかったり、疑問点が瞬時に共有されなかったりするでしょう。
情報共有の遅れは、生産性の低下につながります。
たとえば、簡単な確認事項でもテキストベースでのやり取りになると時間がかります。
さらに、ニュアンスが伝わりにくいかもしれません。
上記のような問題を解決するためには、オンライン会議の定期的な実施、チャットツールの積極的な活用、意識的な声がけなど、意図的にコミュニケーションの機会を作ることが重要です。
情報セキュリティへの意識と対策
リモートワークは、情報セキュリティへの意識と対策が重要です。
オフィス外で業務するリモートワークは、企業の情報資産が自宅や外出先のネットワークに接続されるからです。
情報セキュリティへの対策をおろそかにすることで、個人のデバイスからの情報が漏洩するでしょう。
さらに、公共Wi-Fiの利用によるデータ傍受、紛失や盗難による機密情報の流出などのリスクも存在します。
そのため、社員1人ひとりが情報セキュリティに対する高い意識を持つことが大切です。
たとえば、強力なパスワード設定やデバイスの物理的な管理、不審なメールやサイトへの警戒といった具体的な対策を徹底しましょう。
リモートワークによって、企業のリスクにならないよう注意してください。
評価や人間関係での誤解が生じやすい点
リモートワークは、評価や人間関係での誤解が生じやすいので注意しましょう。
リモートワークは、上司が部下の働きぶりを直接見ることができません。
そのため、人事評価の透明性が課題になります。
成果だけでなく、プロセスや貢献度も評価される場合、自分がどのように判断されたのか確認しましょう。
評価に対する不公平感は、仕事のモチベーションを大きく低下させます。
また、対面での交流が少ないことで、人間関係における誤解が生じやすくなります。
テキストベースのコミュニケーションでは感情が伝わりにくく、意図しない解釈となるからです。
非公式なコミュニケーションを積極的に設けて、良好な人間関係を構築しましょう。
まとめ
この記事では、リモートワークができる職種を解説してきました。
リモートワークは、すべての職種に浸透するのは、難しいため注意してください。
また、自分がリモートワークに向いている人材かどうか、確かめたうえで企業にエントリーすることが重要です。
リモートワークに必要なスキルや価値観がない場合、つらい環境で働くことになります。
納得のいく就活にするためにも、リモートワークに適した人材か、この記事を読んで検討してください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

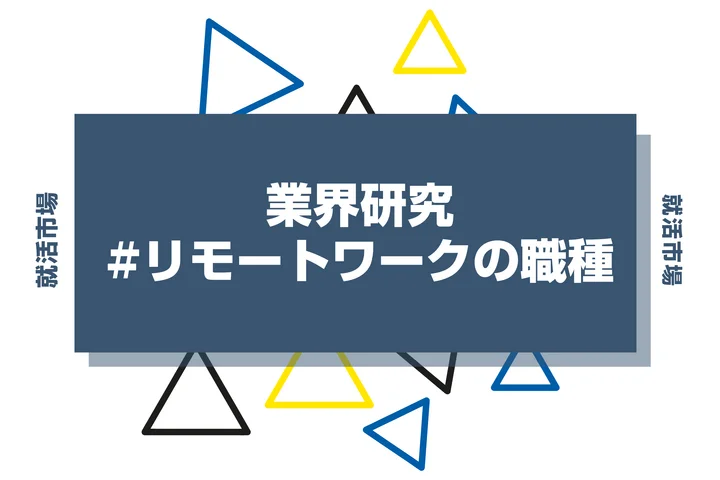

_720x550.webp)







