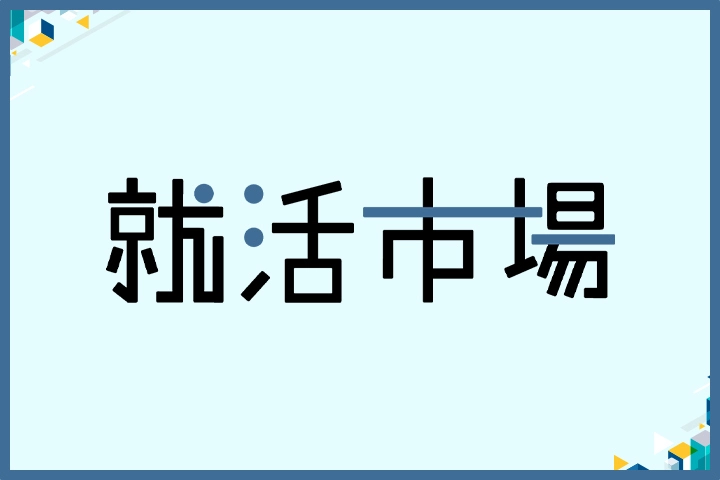目次[目次を全て表示する]
キーエンスのインターン選考・本選考ではガクチカが聞かれやすい
キーエンスの選考において、エントリーシート(ES)や面接で「学生時代に最も力を入れたこと」、通称「ガクチカ」は非常に重要な質問項目です。
なぜなら、キーエンスは候補者のポテンシャルや仕事への適性を見極める上で、皆さんがどのような状況で何に注力し、どのような成果を出したのか、その過程で何を学んだのかを知りたいと考えているからです。
特に、論理的思考力や課題解決能力、目標達成へのコミットメントといったキーエンスが求める人物像と合致する要素をガクチカから見出そうとしています。
効果的なガクチカを作成し、選考を突破するための具体的なポイントや例文をこの記事で徹底的に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
キーエンスがガクチカを聞く理由
キーエンスが選考でガクチカを重視するのには明確な理由があります。
単に皆さんの経験談を聞きたいわけではありません。
彼らが知りたいのは、その経験から皆さんが何を学び、どのように成長したのか、そしてそれがキーエンスで働く上でどのように活かされるのかという点です。
皆さんの過去の行動から、潜在的な能力や仕事への向き合い方、そして企業文化とのフィット感を見極めようとしているのです。
あなたの人柄が知りたいから
キーエンスはガクチカを通して、皆さんの「人柄」を深く理解しようとしています。
例えば、皆さんが困難に直面した際にどのように考え、行動したのか、チームの中でどのような役割を担い、周囲とどのように協働したのかといったエピソードからは、皆さんの価値観やコミュニケーションスタイル、リーダーシップの有無などが見えてきます。
単なる成功体験だけでなく、失敗から何を学び、次にどう活かしたのかというプロセスも重視されます。
人柄は企業文化への適応性や、入社後の活躍度を測る上で非常に重要な指標となるため、ガクチカを通じて皆さんの個性や魅力が伝わるように意識しましょう。
学生時代に力を入れたことを知りたいから
学生時代に力を入れたことを聞くことで、キーエンスは皆さんの「主体性」や「目標達成への意欲」を測ろうとしています。
どのような目標を設定し、それに対してどのような工夫や努力を重ねたのか、そしてどのような結果を出したのかを具体的に聞くことで、皆さんが仕事においても同様の姿勢で取り組めるかどうかを見極めます。
学業、アルバイト、サークル活動、ボランティアなど、どのような内容であっても構いませんが、皆さんが「なぜそれに力を入れたのか」「どのような壁にぶつかり、どう乗り越えたのか」「その経験から何を学び、どう成長したのか」という一連のストーリーが重要になります。
大切にしている価値観が知りたいから
ガクチカは、皆さんが「何を大切にしているか」という価値観を浮き彫りにする絶好の機会です。
例えば、チームワークを重視して行動した経験からは協調性が、困難な課題に粘り強く取り組んだ経験からは忍耐力や向上心がうかがえます。
キーエンスは成果にこだわる企業文化を持っているため、成果へのコミットメントや課題解決への意欲といった価値観を持つ学生を高く評価する傾向にあります。
皆さんのガクチカの背景にある動機や、行動の原動力となった思いを明確に伝えることで、皆さんの価値観とキーエンスの求める人物像との合致度をアピールできるでしょう。
キーエンスのガクチカで通過率を上げるためのポイント
キーエンスのガクチカで高い通過率を目指すには、ただ経験を羅列するだけでは不十分です。
彼らが知りたいのは、皆さんの行動の背景にある思考プロセスや、そこから得られた学び、そしてそれがどのように将来に繋がるのかという点です。
ここでは、キーエンスが評価するガクチカを作成するための具体的なポイントを解説していきます。
結論から具体的に述べることを意識する
ガクチカを作成する際は、まず結論から具体的に述べることを強く意識しましょう。
これは、エントリーシートでも面接でも共通の重要なポイントです。
最初に「私が学生時代に最も力を入れたことは〇〇です」と明確に述べることで、採用担当者は皆さんの話の全体像をすぐに理解できます。
その上で、具体的なエピソード、直面した課題、それに対する行動、結果、そしてそこから得られた学びを順序立てて説明することで、論理的で分かりやすいガクチカになります。
PREP法(Point, Reason, Example, Point)などを意識して、簡潔かつ説得力のある構成を心がけましょう。
成果を出すまでの過程を伝えることを意識する
キーエンスの選考では、「成果を出すまでの過程」が非常に重視されます。
単に「〇〇の成果を出しました」と述べるだけでなく、その成果を出すまでに「どのような目標を設定し」「どのような課題に直面し」「その課題に対してどのような分析を行い」「どのような工夫や改善策を実行し」「どのような試行錯誤があったのか」という具体的なプロセスを詳細に伝えることが重要です。
特に、課題解決に向けた皆さんの思考プロセスや、粘り強く取り組む姿勢を具体的に示すことで、入社後も困難な状況に対して主体的に行動できる人材であることをアピールできます。
その経験から何を学んだか伝えることを意識する
ガクチカで最も重要な要素の一つは、「その経験から何を学んだか」を明確に伝えることです。
単なる経験談で終わらせるのではなく、その経験を通じて皆さんがどのようなスキルを習得し、どのような価値観を培い、どのように人間的に成長できたのかを具体的に言語化しましょう。
そして、その学びがキーエンスで働く上でどのように活かされるのか、入社後にどのように貢献できるのかという視点まで繋げることで、皆さんの学びが企業にとって価値のあるものであることをアピールできます。
学びに加えて、今後の目標や意欲を示すことで、より強い印象を残せるでしょう。
キーエンスのガクチカで気をつけるべき注意点
キーエンスのガクチカで選考を通過するためには、いくつか注意すべき点があります。
せっかく素晴らしい経験をしていても、伝え方一つで評価が大きく変わってしまうこともあるからです。
ここでは、キーエンスのガクチカを作成・話す際に避けるべき落とし穴について詳しく解説します。
課題解決に向けて行動した内容が薄い
キーエンスの選考において、ガクチカで一番避けたいのは「課題解決に向けて行動した内容が薄い」ことです。
単に「頑張りました」「努力しました」といった精神論的な表現や、具体的な行動が見えない抽象的な内容では、採用担当者に皆さんの能力やポテンシャルが伝わりません。
どのような課題に対し、具体的に「何を」「どのように」「なぜ」行ったのかを詳細に描写することが重要です。
例えば、「売上を伸ばすために努力しました」ではなく、「顧客のニーズを分析し、ターゲット層に合わせた新商品の企画提案を行った結果、売上が〇〇%向上しました」といったように、皆さんの主体的な行動と具体的な成果を結びつけて説明するようにしましょう。
抽象的な表現が多い
ガクチカを作成する際に、抽象的な表現が多くなってしまうと、皆さんの個性が伝わりにくく、他の学生との差別化が難しくなります。
「コミュニケーション能力を高めました」「リーダーシップを発揮しました」といった表現だけでは、具体的なイメージが湧きません。
例えばコミュニケーション能力であれば、「チーム内の意見の対立を解消するために、個別のメンバーと丁寧に話し合い、共通認識を形成した」のように、具体的な行動や状況を描写することで、皆さんがどのようにコミュニケーション能力を発揮したのかが伝わります。
具体的なエピソードを盛り込み、五感に訴えかけるような表現を意識することで、より印象に残るガクチカになるでしょう。
失敗談から何も学んでいない
ガクチカでは、成功体験だけでなく失敗談を話すことも有効ですが、その際に「失敗から何も学んでいない」と受け取られるような内容は絶対に避けましょう。
失敗談を話す場合は、その失敗によって何が起こり、その原因をどのように分析し、次にどう活かしたのかという「反省」と「改善」のプロセスを明確に伝えることが重要です。
例えば、「企画が失敗しましたが、そこから何を学んだか」を具体的に述べることで、皆さんの成長意欲や課題解決能力をアピールできます。
失敗を糧に成長できる人材であることを示すことで、キーエンスが求める粘り強さや向上心があることを伝えられるでしょう。
キーエンスで選考を通過するためのガクチカ例文
キーエンスの選考を突破するためには、皆さんの経験がキーエンスの求める人物像に合致しているかを効果的にアピールできるガクチカを作成することが不可欠です。
ここでは、具体的な例文を参考にしながら、皆さんの強みを最大限に引き出すガクチカの作成方法について解説します。
例文1:成果へのコミットメントをアピールするガクチカ
私が学生時代に最も力を入れたことは、所属していたテニスサークルで新入生獲得イベントの企画・実行リーダーを務め、参加人数を前年比1.5倍に増やした経験です。
例年、新入生獲得に苦戦しており、参加人数が伸び悩んでいました。
私はこの課題に対し、まず過去のイベントの参加データとアンケート結果を徹底的に分析しました。
その結果、「イベント内容のマンネリ化」と「広報活動の不足」が主な原因だと特定しました。
そこで、新入生が飽きずに楽しめるよう、テニスの経験者・未経験者問わず参加できるゲーム形式の練習会を企画し、SNSを活用した積極的な広報活動を展開しました。
特に、サークルの日常風景やメンバーの魅力を伝える動画を制作し、毎週投稿することで、新入生がサークルの雰囲気を具体的にイメージできるように工夫しました。
また、参加者のモチベーション維持のため、イベント後のアンケートで改善点をすぐに反映するサイクルを確立しました。
結果として、イベントへの参加者は前年比1.5倍の150名を達成し、サークルへの入会者数も大幅に増加しました。
この経験から、目標達成のために現状を分析し、仮説を立て、具体的な施策を実行し、その効果を検証する「PDCAサイクル」を回す重要性を学びました。
これは、貴社で目標達成に向けて課題解決に取り組む際に必ず活かせると考えております。
このガクチカは、具体的な数字で成果を示し、その成果を出すまでの過程(課題分析、施策立案、実行、改善)を詳細に説明している点が評価できます。
キーエンスが重視する論理的思考力や課題解決能力、そして成果へのコミットメントが明確に伝わるでしょう。
例文2:課題解決能力をアピールするガクチカ
私が学生時代に最も力を入れたことは、アルバイト先のカフェで顧客満足度向上プロジェクトを立ち上げ、顧客アンケートの平均点を20%向上させた経験です。
当時、店舗の顧客アンケートの平均点が伸び悩み、特に「待ち時間」と「オーダーの正確性」に関する不満の声が多く聞かれました。
私はこの状況に対し、まずスタッフ全員で課題を共有するためのミーティングを定期的に開催し、顧客からのフィードバックを具体的な改善点に落とし込む作業を行いました。
次に、待ち時間短縮のためにオーダーシステムの改善を提案し、手書きでのオーダーをタブレット入力に切り替えました。
これにより、オーダーミスの減少と、キッチンへの情報伝達の迅速化を実現しました。
さらに、混雑時の対応として、事前に飲み物の用意を始める「先行準備」の導入や、お客様への声かけを徹底する「先手必勝」の接客マニュアルを策定しました。
これらの施策を導入した後も、定期的に顧客アンケートの結果を分析し、改善を重ねました。
その結果、顧客アンケートの平均点は当初の目標を上回る20%の向上を達成し、常連のお客様からは「最近、サービスが良くなったね」というお言葉をいただくことが増えました。
この経験を通じて、問題の本質を見極め、関係者を巻き込みながら具体的な解決策を実行する「課題解決能力」と、常に改善意識を持って業務に取り組む重要性を学びました。
このガクチカは、具体的な課題とその解決策、そして定量的な成果が明確に示されています。
特に、課題解決に向けた具体的な行動とその効果が具体的に記述されており、キーエンスが求める論理的思考力と実行力をアピールできます。
例文3:チームでの協働をアピールするガクチカ
私が学生時代に最も力を入れたことは、大学のゼミでチーム研究のリーダーを務め、全員で論文を完成させた経験です。
私たちのゼミでは、特定のテーマについてグループで研究し、最終的に論文を提出する課題がありました。
しかし、メンバー間で意見の相違や情報共有の不足があり、研究が滞ってしまう時期がありました。
私はリーダーとして、まず各メンバーの専門分野や得意なことをヒアリングし、それぞれの強みを活かせる役割分担を提案しました。
また、週に一度の定例ミーティングに加え、進捗が芳しくないメンバーには個別に時間を設けて相談に乗り、研究の方向性や課題解決のアドバイスを行いました。
特に、意見が対立した際には、それぞれの意見の背景にある考え方を丁寧に聞き出し、共通の目標達成に向けて建設的な議論ができるようファシリテーションに徹しました。
その結果、当初の計画より遅れはあったものの、最終的には全員が納得できる質の高い論文を完成させ、ゼミの発表会では最優秀賞をいただくことができました。
この経験を通じて、多様な意見を持つメンバーをまとめ上げ、共通の目標に向かって協力し合う「チームワークの重要性」と、個々の能力を最大限に引き出すための「リーダーシップ」を学びました。
このガクチカは、チームで目標を達成する過程での課題解決や、リーダーシップの発揮の仕方を具体的に示しています。
協調性や人を巻き込む力をアピールしたい場合に有効な例文です。
例文4:目標達成への執着をアピールするガクチカ
私が学生時代に最も力を入れたことは、大学の研究室で取り組んだ実験において、目標としていたデータ収集に成功したことです。
私が担当していた実験は、非常にデリケートな条件設定が必要で、少しの環境変化でも結果が大きく変動するという課題がありました。
当初は思うようなデータが得られず、何度も失敗を繰り返しました。
しかし、私はこの目標を達成することに強い執着心を持っていました。
そこで、失敗の原因を徹底的に究明するため、実験ノートに詳細な記録を残し、条件を一つずつ変えては結果を比較する地道な作業を繰り返しました。
また、教授や先輩にも積極的に相談し、彼らの経験や知識を吸収しようと努めました。
特に、深夜まで研究室に残り、わずかな変化も見逃さないよう、データの変動を詳細に観察し続けました。
時には心が折れそうになることもありましたが、「必ず成功させる」という強い意志を持って取り組み続けました。
その結果、試行錯誤の末に最適な実験条件を発見し、目標としていた精度の高いデータを収集することに成功しました。
この経験から、困難な目標に対しても決して諦めずに、粘り強く試行錯誤を繰り返す「目標達成への執着心」と「諦めない精神」を学びました。
これは、貴社の「高収益体質」を支える成果への追求姿勢に通ずるものがあると考えております。
このガクチカは、困難な状況下での目標達成への強い執着心と、諦めずに試行錯誤を繰り返す粘り強さをアピールしています。
キーエンスが求める成果主義や目標達成へのコミットメントと合致するでしょう。
例文5:主体的な行動力をアピールするガクチカ
私が学生時代に最も力を入れたことは、大学祭実行委員として、来場者アンケートで「最も印象に残った企画」に選ばれた地域連携企画をゼロから立ち上げた経験です。
例年、大学祭は学内イベントが中心で、地域住民の方々の参加が少ないという課題がありました。
私は、大学祭をより地域に開かれたものにしたいという思いから、地域住民の方々が楽しめる企画を提案しました。
しかし、前例がないため、最初は実行委員の中でも賛同を得るのが難しい状況でした。
そこで私は、地域の商店街やNPO法人に自ら足を運び、大学祭での連携企画の可能性について提案を行いました。
最初は門前払いされることもありましたが、何度も足を運び、地域の方々のニーズを丁寧にヒアリングすることで、徐々に協力者を増やしていきました。
最終的には、地元の特産品を販売するブースの出展や、地域の伝統芸能の披露など、地域の方々と共に作り上げる企画を実現することができました。
当日は多くの地域住民の方々にご来場いただき、アンケートでも高い評価を得ることができました。
この経験を通じて、前例がないことに対しても臆することなく、自ら行動を起こし、周囲を巻き込みながら目標を達成する「主体的な行動力」を学びました。
このガクチカは、自ら課題を見つけ、周囲を巻き込みながら新しいことに挑戦する主体性と実行力をアピールしています。
キーエンスで新規事業開発や新しいソリューション提案に貢献したいと考える学生に特に有効です。
キーエンスのガクチカに関するよくある質問
キーエンスのガクチカについて、就活生からよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
これらの疑問を解消し、より自信を持って選考に臨めるようにしましょう。
皆さんの疑問を解消し、選考突破に役立つ具体的なヒントを提供します。
ガクチカの経験はすごいものであるべきですか?
キーエンスのガクチカにおいて、必ずしも「すごい」経験である必要はありません。
重要なのは、皆さんがその経験から何を学び、どのように成長したか、そしてそれがキーエンスで働く上でどのように活かされるのかという点です。
アルバイト、サークル活動、学業、ボランティアなど、どのような内容であっても構いません。
例えば、地味な活動であっても、その中で皆さんがどのような目標を設定し、どのような課題に直面し、それをどう乗り越え、結果的に何を成し遂げたのかという「プロセス」が具体的に語られていれば、十分に評価の対象となります。
重要なのは、皆さんの主体性、課題解決能力、目標達成へのコミットメント、そしてそこから得られた学びを具体的にアピールすることです。
ガクチカの文字数はどれくらいが適切ですか?
キーエンスのエントリーシートにおけるガクチカの文字数については、指定がある場合はそれに従うのが絶対です。
特に指定がない場合や、面接で話すことを想定する際は、一般的にエントリーシートでは400字から600字程度、面接では1分から2分程度で話せるボリュームが適切とされています。
長すぎると要点がぼやけ、短すぎると内容が伝わりきらない可能性があります。
文字数や話す時間に合わせた情報の取捨選択が重要です。
具体的には、結論、課題、行動、結果、学びの5つの要素を盛り込みつつ、一番伝えたいメッセージが明確になるように調整しましょう。
面接では、話す内容を事前に整理し、簡潔かつ具体的に伝えられるように練習しておくことが大切です。
ガクチカで失敗談を話しても良いですか?
ガクチカで失敗談を話すことは、むしろ皆さんの成長性や課題解決能力をアピールする上で非常に有効な手段となり得ます。
しかし、ただ失敗した事実を述べるだけでは逆効果です。
重要なのは、その失敗から皆さんが何を学び、どのように改善し、次にどう活かしたのかという「反省」と「成長」のプロセスを具体的に伝えることです。
例えば、「〇〇の企画が失敗しましたが、その原因を分析し、〇〇という改善策を実行した結果、次は成功させることができました」といったように、失敗を単なるネガティブな経験で終わらせず、学びの機会として捉えている姿勢を示すことが大切です。
これにより、皆さんの粘り強さや向上心、そして困難な状況に直面した際の対応能力をアピールできるでしょう。
キーエンスのガクチカまとめ
キーエンスの選考において、ガクチカは皆さんの人柄、能力、そして企業文化への適応性を見極めるための重要な要素です。
単なる経験の羅列ではなく、皆さんがどのように課題に立ち向かい、どのように解決し、どのような成果を出したのかという「プロセス」と、そこから得られた「学び」を具体的に伝えることが重要です。
今回ご紹介したポイントや例文を参考に、皆さんの個性や強みが最大限に伝わるガクチカを作成し、キーエンスの選考突破を目指しましょう。
この記事が皆さんの就職活動の一助となれば幸いです。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート