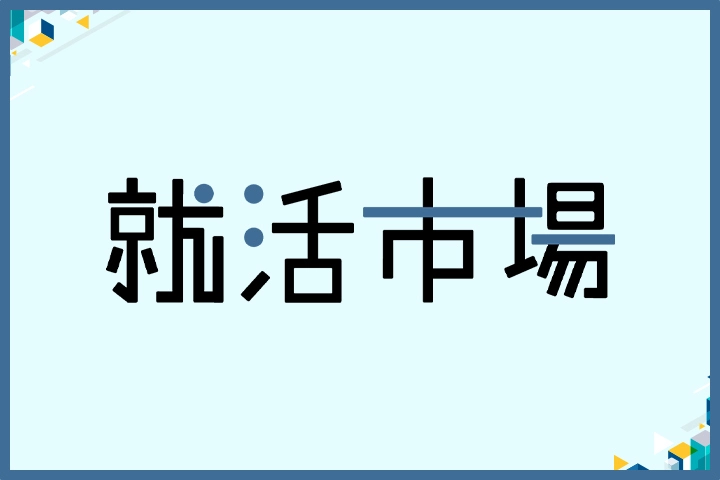目次[目次を全て表示する]
味の素のインターン選考・本選考ではガクチカが聞かれやすい
味の素の採用選考において、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」は非常に重要な評価項目の一つです。
インターンシップ選考はもちろんのこと、本選考においても、ガクチカに関する質問は頻繁に問われます。
味の素は、食品メーカーとして多様な事業を展開しており、社員一人ひとりの個性や主体性が事業成長に不可欠だと考えているからです。
そのため、皆さんが学生時代にどのような経験をし、そこから何を学び、どのように成長してきたのかを深く知ろうとします。
ガクチカは単なる活動内容の羅列ではなく、皆さんの個性や潜在能力、そして味の素という企業で活躍できるポテンシャルを示す絶好の機会です。
この記事では、味の素がなぜガクチカを重視するのか、そしてどのようにすれば選考を有利に進められるガクチカを作成できるのかについて、具体的なポイントと例文を交えながら徹底的に解説していきます。
味の素への入社を目指す皆さんは、ぜひこの記事を参考に、自身の経験を最大限にアピールできるガクチカを作成してください。
味の素がガクチカを聞く理由
味の素の採用選考において、ガクチカが繰り返し問われるのには明確な理由があります。
それは、皆さんの過去の経験から、入社後の活躍につながる可能性を見出そうとしているからです。
ガクチカは単なるエピソードではなく、皆さんの思考プロセスや行動特性、そして価値観を知るための重要な手がかりとなります。
味の素は、皆さんの個性や潜在能力を多角的に理解することで、企業文化へのフィット感や将来的な貢献度を測ろうとしているのです。
あなたの人柄が知りたいから
味の素は、ガクチカを通じて応募者の人柄や個性、潜在能力を深く理解しようとしています。
単にどんな活動をしたかだけでなく、その活動にどのように取り組んだのか、どんな困難に直面し、それをどう乗り越えたのかといったプロセスから、皆さんの内面的な特性や思考パターンを把握しようとしているのです。
例えば、チームで何かを成し遂げた経験があれば、協調性やリーダーシップの有無を見ますし、課題解決に主体的に取り組んだ経験からは、主体性や論理的思考力を評価します。
味の素が求めるのは、単に優秀な人材だけでなく、企業文化にフィットし、共に成長していける人材です。
そのため、ガクチカのエピソードから皆さんの持ち味や強み、そして仕事に対する姿勢や価値観を読み取り、入社後にどのような活躍をしてくれるのかを具体的にイメージしようとしているのです。
飾らない言葉で、皆さんのありのままの魅力が伝わるようなエピソードを選ぶことが重要です。
学生時代に力を入れたことを知りたいから
味の素がガクチカを聞くもう一つの大きな理由は、皆さんが学生時代に何に「力を入れた」のかを知ることで、その熱意や行動力、そして困難に直面した際の対応能力を測るためです。
ここでいう「力を入れたこと」とは、単に目覚ましい成果を出した経験だけを指すわけではありません。
むしろ、目標設定から計画、実行、そして振り返りといった一連のプロセスにおいて、皆さんがどのように考え、行動し、そしてそこから何を学んだのかという点に重きを置いています。
例えば、アルバイトでの顧客満足度向上への取り組みや、サークル活動でのイベント企画・運営など、規模の大小にかかわらず、皆さんが主体的に関わり、努力を重ねた経験が重要です。
味の素は、皆さんの「力を入れた」経験から、入社後も困難に臆することなく、目標達成に向けて粘り強く取り組める人材であるかを見極めようとしています。
具体的な行動と、それによって得られた学びや成長を明確に伝えることが重要です。
大切にしている価値観が知りたいから
味の素は、ガクチカを通じて皆さんがどんな価値観を大切にしているのかを知ろうとしています。
どのような経験を選び、その経験の中で何を重視し、どんな学びを得たのかという点から、皆さんの思考の軸や行動原理を読み取ろうとしているのです。
例えば、チームでの協調性を重視するエピソードであれば、味の素が大切にする「共創」の精神と合致するかどうかを見ますし、困難な課題に挑戦し、諦めずに解決策を探したエピソードであれば、粘り強さや成長意欲といった味の素が求める人材像と重なる部分があるかを確認します。
ガクチカは、皆さんの過去の経験を語るだけでなく、皆さんが「なぜそうしたのか」「何を大切にしたいのか」という内面的な部分を表現する場でもあります。
皆さんの個性や、仕事に対する価値観が、味の素の企業文化や事業内容とどのように結びつくのかを具体的に示すことで、入社後の活躍をより強くイメージさせることができます。
味の素のガクチカで通過率を上げるためのポイント
味の素のガクチカで選考通過率を上げるためには、単に素晴らしい経験を語るだけでなく、企業が何を求めているかを理解し、それに沿ったアピールをすることが重要です。
ここでは、味の素が求める人物像や企業文化を踏まえ、皆さんのガクチカをより魅力的に伝えるための具体的なポイントを解説していきます。
これらのポイントを意識することで、皆さんのガクチカはより一層、採用担当者の心に響くものとなるでしょう。
結論から具体的に述べる
味の素のガクチカで通過率を上げるためには、まず結論から具体的に述べることを徹底してください。
採用担当者は多くのESや面接に触れるため、最初に結論が明確に示されていないと、皆さんの伝えたいことが伝わりにくくなってしまいます。
例えば、「私は〇〇の経験を通して、〇〇という目標を達成しました」といった形で、最初にガクチカの核となる部分を提示しましょう。
その上で、具体的なエピソードを肉付けしていくことで、相手は皆さんの話をスムーズに理解できます。
例えば、「私が学生時代に最も力を入れたのは、〇〇サークルでの新規イベント企画です。
この活動を通して、参加者数を前年比150%に増加させるという目標を達成しました。
」のように、まず活動内容と達成目標を明示することで、その後の説明が非常に分かりやすくなります。
結論を明確にすることで、論理的思考力や要約力があるという印象も与えられます。
味の素の求める人物像と合致させる
味の素のガクチカで選考通過率を上げるためには、味の素が求める人物像と皆さんのガクチカを合致させることが不可欠です。
味の素は、「食」と「健康」の分野で社会に貢献することを目指しており、チャレンジ精神、主体性、協調性、そして多様性を尊重する姿勢を重視しています。
皆さんのガクチカを語る際には、これらの要素がどのように含まれているかを意識してエピソードを選び、具体的に説明しましょう。
例えば、チームで目標達成のために困難を乗り越えた経験であれば、協調性や粘り強さをアピールできますし、自ら課題を見つけて解決策を実行した経験であれば、主体性や課題解決能力を示すことができます。
単に経験を羅列するだけでなく、その経験から得られた学びや成長が、味の素の企業理念や求める人物像とどのようにリンクするのかを明確に伝えることで、採用担当者に「この学生は当社で活躍できる」というイメージを持ってもらうことができるでしょう。
成果だけでなくプロセスも重視する
味の素のガクチカでは、単に素晴らしい成果を上げたことだけをアピールするのではなく、その成果に至るまでのプロセスを具体的に説明することが非常に重要です。
なぜなら、味の素は結果だけでなく、皆さんがどのような思考を巡らせ、どのような行動を取り、どのような困難に直面し、それをどう乗り越えたのかという過程から、皆さんの本質的な能力やポテンシャルを見極めようとしているからです。
例えば、「〇〇のイベントで集客目標を達成しました」だけでなく、「集客が伸び悩んだ際に、どのような原因分析を行い、どのような改善策を考案し、どのように実行したのか」といった具体的な行動と、そこでの思考プロセスを詳細に語ることで、皆さんの課題解決能力や主体性、粘り強さといった強みがより明確に伝わります。
失敗から何を学び、次にどう活かしたのかという点も伝えることで、学び続ける姿勢や成長意欲もアピールできるでしょう。
味の素のガクチカで気をつけるべき注意点
味の素のガクチカを作成する上で、いくつか注意すべき点があります。
これらの点を見落としてしまうと、せっかくの素晴らしい経験も十分に伝わらなかったり、意図しないマイナスイメージを与えてしまったりする可能性があります。
ここでは、皆さんのガクチカが最大限に魅力的に伝わるよう、注意すべきポイントを具体的に解説していきます。
これらの点を意識することで、より完成度の高いガクチカを作成し、選考通過に近づくことができるでしょう。
企業理念や事業内容とミスマッチがないか
味の素のガクチカを準備する際、最も重要な注意点の一つは、皆さんの経験が味の素の企業理念や事業内容とミスマッチを起こしていないかを事前に確認することです。
味の素は「食」と「健康」を通じて、社会課題の解決に貢献することを目指しており、「アミノ酸のはたらきで、持続可能な社会の実現に貢献する」というパーパスを掲げています。
皆さんのガクチカのエピソードが、この企業の方向性や価値観と大きくかけ離れている場合、採用担当者は入社後の皆さんの活躍イメージを描きにくくなります。
例えば、IT系の専門知識を深くアピールするばかりで、人々の生活や健康への貢献といった視点が抜けていたり、チームでの協調性よりも個人の成果ばかりを強調しすぎたりすると、味の素が求める人材像とのズレが生じる可能性があります。
ガクチカを語る際には、自身の経験が味の素の事業や企業文化とどのように関連し、貢献できるのかを意識して、メッセージを調整することが重要です。
成果が抽象的になっていないか
味の素のガクチカにおいて、成果が抽象的になっていないかは特に注意すべき点です。
「頑張りました」「成長できました」といった曖昧な表現だけでは、皆さんの具体的な貢献度や能力が伝わりません。
採用担当者は、皆さんがどのような目標を設定し、それに対してどのような具体的な行動を取り、結果としてどのような数値的、あるいは客観的に測れる成果を出したのかを知りたいと考えています。
例えば、「アルバイトで売上を伸ばしました」ではなく、「新商品の提案を積極的に行い、担当期間で〇〇%の売上向上に貢献しました」といったように、具体的な数字や客観的な事実を盛り込むことで、説得力が増します。
もし具体的な数字がなくても、「顧客からの感謝の声が〇件寄せられた」「チーム内の課題を〇〇に改善した」といった、定性的な成果であっても、具体的なエピソードを交えて説明することで、皆さんの努力や貢献度が伝わりやすくなります。
成果を具体的な言葉で表現することで、皆さんの実力や貢献意欲をより明確にアピールできます。
専門用語や難しい言葉を使いすぎていないか
味の素のガクチカを説明する際、専門用語や難しい言葉を使いすぎていないかにも注意が必要です。
皆さんが専門分野で素晴らしい経験を積んでいたとしても、採用担当者全員がその分野に精通しているとは限りません。
例えば、研究内容を説明する際に、特定の学術用語や略語を多用してしまうと、聞いている側はその内容を十分に理解できず、皆さんの魅力が伝わりにくくなってしまいます。
大切なのは、誰が聞いても理解できるような、平易な言葉で説明することです。
もし専門用語を使わざるを得ない場合は、必ずその場で簡単な説明を加えるか、言い換え表現を用いるようにしましょう。
例えるなら、小学生にもわかるように説明するくらいの気持ちで臨むと良いでしょう。
自分の言葉で、分かりやすく、具体的に伝えることで、皆さんのコミュニケーション能力や説明能力も同時にアピールできます。
相手への配慮が伝わる話し方は、非常に好印象を与えます。
味の素で選考を通過するためのガクチカ例文
味の素の選考を突破するためのガクチカは、単に華やかな経験を語るだけでなく、味の素が求める人物像や価値観と合致していることを示す必要があります。
ここでは、具体的なガクチカの例文をいくつかご紹介し、それぞれの例文がどのように味の素の選考において有効であるかを解説していきます。
これらの例文を参考に、皆さんの個性や強みを最大限に引き出すガクチカを作成してください。
ガクチカ例文1:リーダーシップをアピール
私が学生時代に最も力を入れたことは、大学祭実行委員会での企画リーダー経験です。
例年参加者数が伸び悩んでいたフード企画において、私は参加者のニーズを徹底的に分析し、これまでにない体験型の企画を立案しました。
具体的には、SNSでのアンケート調査を複数回実施し、学生が求める「映え」と「手軽さ」を両立させた「オリジナルドリンク開発体験ブース」を提案。
企画書作成から予算交渉、資材調達、当日の運営まで、リーダーとして全体を統括しました。
当初は予算や人員の確保に難航しましたが、他部署との綿密な連携や、メンバーのモチベーション維持に努め、最終的には目標を大きく上回る2,000人以上の来場者数を達成し、大学祭の集客に大きく貢献しました。
この経験から、困難な状況でも目標達成に向けて粘り強く取り組むリーダーシップと、周囲を巻き込みながら課題を解決する能力を身につけることができました。
解説:この例文は、リーダーシップと課題解決能力を効果的にアピールしています。
具体的な目標(来場者数2,000人以上)と、それを達成するためのプロセス(ニーズ分析、企画立案、交渉、統括)が明確に述べられており、困難に直面した際の対応力や、周囲を巻き込む力が伝わります。
味の素が求める主体性や協調性にも繋がる内容です。
ガクチカ例文2:協調性をアピール
私が学生時代に力を入れたことは、所属するテニスサークルでの新入生歓迎イベントの企画・運営です。
例年、新入生の入会率が低迷していたため、私は「新入生が本当に楽しめる企画」を目標に掲げ、メンバー全員でアイデアを出し合う機会を設けました。
特に、新入生の不安を解消するため、上級生が個別に相談に乗る「メンター制度」を導入することを提案し、メンバーを説得して実行に移しました。
企画会議では、意見が対立することもありましたが、私は積極的に議論に参加し、それぞれの意見を尊重しながら、全員が納得できる落としどころを見つける努力をしました。
その結果、新入生から「先輩との距離が近く、安心して参加できた」という声が多く寄せられ、例年よりも20%多い新入生が入会する実績を上げることができました。
この経験を通じて、チームで目標を共有し、協力しながら課題を解決していくことの重要性を学びました。
解説:この例文では、協調性と課題解決への貢献が具体的に示されています。
新入生歓迎イベントという身近な題材を通じて、チームで意見を調整し、目標達成に向けて協力する姿勢が伝わります。
味の素が重視する「共創」の精神にも通じる内容であり、周囲との協調性を重視する人物像をアピールできます。
ガクチカ例文3:目標達成への執着心をアピール
私が学生時代に最も注力したのは、大学での研究活動です。
特に、〇〇に関する論文執筆においては、既存のデータだけでは十分な結論を導き出せないという壁にぶつかりました。
私はこの状況を打開するため、研究室の教授や先輩に積極的に相談し、新たな実験方法を自ら考案しました。
実験は予想以上に困難で、失敗を繰り返しましたが、諦めることなく試行錯誤を続け、休日も返上してデータ収集と分析に没頭しました。
時には、徹夜で実験を行うこともありました。
その結果、これまで誰も発見できなかった新たな知見を得ることに成功し、最終的には国内学会での発表と、学術雑誌への論文掲載を果たすことができました。
この経験を通じて、困難な課題に対しても粘り強く取り組み、目標達成のために努力を惜しまない執着心を培うことができました。
解説:この例文は、目標達成への強い執着心と粘り強さをアピールしています。
研究という具体的な活動を通して、困難に直面した際の行動力、試行錯誤を繰り返す姿勢、そして最終的な成果が明確に示されています。
味の素の研究職や開発職を目指す学生にとっては特に響く内容であり、主体性と課題解決能力も同時にアピールできています。
ガクチカ例文4:傾聴力・顧客志向をアピール
私が学生時代に力を入れたのは、カフェでのアルバイトにおける顧客満足度向上への取り組みです。
当店では常連客が少なく、リピート率の低さが課題でした。
私はこの状況を改善するため、お客様との会話の中で積極的にニーズをヒアリングし、「お客様が本当に求めているサービスは何か」を深く考えるようになりました。
具体的には、お客様が注文に迷っている際に、おすすめのメニューや組み合わせを提案するだけでなく、お客様の好みや気分に合わせたカスタマイズを提案するなど、一人ひとりに寄り添った接客を心がけました。
また、常連客の方々の好みやライフスタイルを把握し、次回来店時にさりげなくお声がけをするなど、細やかな気配りも実践しました。
その結果、「このカフェに来るのが楽しみになった」という声をいただくようになり、私の接客指名が増え、リピート率も以前より向上しました。
この経験から、相手のニーズを深く理解し、それに応えることの重要性を学びました。
解説:この例文は、傾聴力と顧客志向を効果的にアピールしています。
カフェのアルバイトという身近な経験を通して、顧客のニーズを深く理解し、具体的な行動で満足度向上に貢献したプロセスが明確に示されています。
味の素が「生活者視点」を重視する企業であることから、非常に高く評価される内容であり、コミュニケーション能力や課題解決能力も同時にアピールできています。
ガクチカ例文5:多様性を受け入れる姿勢をアピール
私が学生時代に最も力を入れたのは、国際交流イベントの企画運営です。
大学には様々な国籍の学生が在籍していましたが、異なる文化背景を持つ学生同士の交流機会が少ないと感じていました。
そこで私は、互いの文化を理解し、尊重し合うことを目的とした「多文化交流カフェ」の企画を提案しました。
企画を進める中で、文化や価値観の違いからメンバー間で意見の衝突もありましたが、私はそれぞれの意見の背景にある考えを丁寧に聞き出し、共通の目標に向かって建設的な議論を進めるよう努めました。
例えば、食事の習慣の違いを考慮し、各国からの持ち寄り料理に加え、全員が楽しめるような工夫を凝らしました。
結果として、イベントには100名以上の学生が参加し、「国籍を超えて友達ができた」という喜びの声が多く寄せられました。
この経験を通じて、多様な価値観を受け入れ、異なる背景を持つ人々との協働を通じて新たな価値を創造することの重要性を深く学びました。
解説:この例文は、多様性を受け入れる姿勢と、異文化理解における協調性をアピールしています。
国際交流イベントという具体的な活動を通して、異なる価値観を持つ人々とのコミュニケーションにおける課題解決能力や、共創の精神が伝わります。
グローバルに事業を展開する味の素にとって、非常に魅力的な人材像をアピールできる内容です。
味の素のガクチカに関するよくある質問
味の素のガクチカについて、就活生からよく寄せられる質問にお答えします。
ガクチカ作成で迷った時や、より深く味の素の求める人物像を理解したい時に、ぜひ参考にしてください。
これらの質問と回答を通じて、皆さんのガクチカをさらに磨き上げ、自信を持って選考に臨めるようサポートします。
ガクチカが複数ある場合、どれを選べば良いですか?
ガクチカが複数ある場合、味の素の企業理念や求める人物像に最も合致するエピソードを選ぶことが重要です。
味の素は、食と健康を通じて社会に貢献するというパーパスを掲げ、「共創」や「多様性の尊重」、「チャレンジ精神」といった価値観を重視しています。
例えば、チームで困難な課題を乗り越えた経験や、自ら課題を見つけて解決策を実行した経験、異なる文化背景を持つ人々と協力して何かを成し遂げた経験などは、味の素が求める人物像と親和性が高いと言えるでしょう。
単に「すごい」経験であるかどうかに囚われず、その経験から何を学び、どのように成長し、その学びが味の素で働く上でどのように活かせるのかを具体的に説明できるエピソードを選びましょう。
一番華やかな経験である必要はなく、皆さんの内面的な成長や、味の素での活躍に繋がるポテンシャルが最も伝わるエピソードを選ぶことが大切です。
ガクチカに失敗談を盛り込んでも良いですか?
ガクチカに失敗談を盛り込むことは、むしろプラスに働くことが多いです。
味の素は、皆さんの「完璧さ」を求めているのではなく、困難に直面した際にどのように考え、どのように行動し、そしてそこから何を学び、どう次へ活かそうとしているのかというプロセスに注目しています。
失敗談を語ることで、皆さんの人間性や、挫折から立ち直るレジリエンス、そして学び続ける姿勢をアピールできます。
ただし、失敗談を語る際には、単に失敗した事実を述べるだけでなく、以下の点を明確に伝えることが重要です。
一つ目は、「どのような失敗だったのか」を具体的に。
二つ目は、「なぜその失敗が起こったのか」を自己分析する姿勢。
そして三つ目は、「その失敗から何を学び、次にどう活かそうとしているのか」というポジティブな展望です。
失敗を恐れずに挑戦し、そこから学びを得て成長できる人物であることを示すことで、採用担当者に深い印象を与えることができるでしょう。
ガクチカの深掘り質問にどう答えるべきですか?
味の素の選考においてガクチカの深掘り質問は頻繁に行われます。
これに効果的に答えるためには、事前に自分のガクチカを多角的に分析し、どのような質問が来ても答えられるように準備しておくことが不可欠です。
例えば、「なぜその活動を選んだのか」「最も困難だったことは何か、そしてどう乗り越えたのか」「その経験から何を学んだか」「その学びを味の素でどう活かしたいか」といった質問は頻出です。
これらに対して、具体的なエピソードを交えながら、論理的に説明できるようにしておきましょう。
特に重要なのは、「なぜ」という問いに対して、自分の思考プロセスや動機を深掘りして説明することです。
例えば、「なぜその目標を立てたのか」「なぜその行動をとったのか」といった問いには、皆さんの価値観や行動原理が表れます。
また、もし想定外の質問が来たとしても、焦らずに「少し考えさせてください」と断ってから、冷静に自分の考えをまとめる時間をもらうことも有効です。
自己分析を徹底し、自分の言葉で自信を持って語れるように準備しましょう。
味の素のガクチカまとめ
味の素の選考におけるガクチカは、皆さんの個性、潜在能力、そして味の素で活躍できるポテンシャルを示す上で非常に重要な役割を果たします。
単に素晴らしい経験を語るだけでなく、なぜその経験を選んだのか、その中で何を考え、どのように行動し、そこから何を学んだのかというプロセスを具体的に伝えることが重要です。
味の素の企業理念や求める人物像を深く理解し、自身のガクチカがどのようにそれらと合致するのかを明確にアピールすることで、選考通過の可能性は大きく高まります。
この記事で解説したポイントと例文を参考に、皆さんの魅力が最大限に伝わるガクチカを完成させ、味の素の内定を掴み取りましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート