就職活動の時期は、大学生活の中でも特に忙しく、精神的にも負担が大きい時期と言われています。
しかし、就活の忙しさは常に一定ではなく、時期によって波があるため、月によって就活スケジュールの組み方を変えていかなければなりません。
本記事では、就活が忙しくなる時期ごとの特徴や、忙しさの背景、さらに忙しさを乗り切るためのポイントまで詳しく解説していきます。
これから就活を迎える方も、すでに動き始めている方も、スムーズな就職活動を進めるための参考にしてみてください。
【就活が忙しい時期】最も忙しいのは大学3年の3月!
就活市場では、就活生を対象にした「就活で最も忙しかった時期はいつか」という調査を行いました。
その結果では、大学3年の3月が最も忙しかったと回答した割合が最も多くなりました。

大学3年生の3月は、就職活動が本格化する時期として、多くの学生にとって最も忙しい時期となります。
この時期には、企業の採用情報が一斉に解禁され、会社説明会やエントリー受付が始まります。
これに伴い、履歴書やエントリーシートの作成、筆記試験や面接対策など、やるべきことが一気に増加します。
実際に、就活生の多くがこの時期に複数の企業説明会に参加し、エントリーシートを提出しています。
また「大学3年の3月が最も忙しかった」と回答した就活生に対して、その時期にどんな就活をしていたか訪ねたところ、1人あたり約10社の会社説明会に参加し、約8社にエントリーシートを提出していたことがわかりました。
このように、同時に複数社の選考を進めなければならない3月は就活生にとって非常に多忙な時期であり、計画的なスケジュール管理が求められます。
就活が忙しい時期はどれくらいアルバイトに入ってた?
就活が本格化する3月には、アルバイトのシフト調整が必要になる場合があります。
実際、来月の就活の忙しさがどれくらいになるかを知ってシフトの提出量を調整したい、という方も少なくないのではないでしょうか。
就活市場の調査結果は、以下の通りになりました。

多くの企業が平日に説明会や面接を実施するため、平日のスケジュールを空けておくことが重要です。
先輩就活生の中には、アルバイトを土日に限定し、平日は就活に専念するようにシフトを調整することにより、企業からの急な連絡や面接の予定にも柔軟に対応できるようにした、という方もいました。
アルバイトと就活の両立は可能ですが、就活が最優先となる時期には、アルバイトの時間を見直すことも検討してみるのがおすすめです。
【就活が忙しい時期】就活の基本的なスケジュール
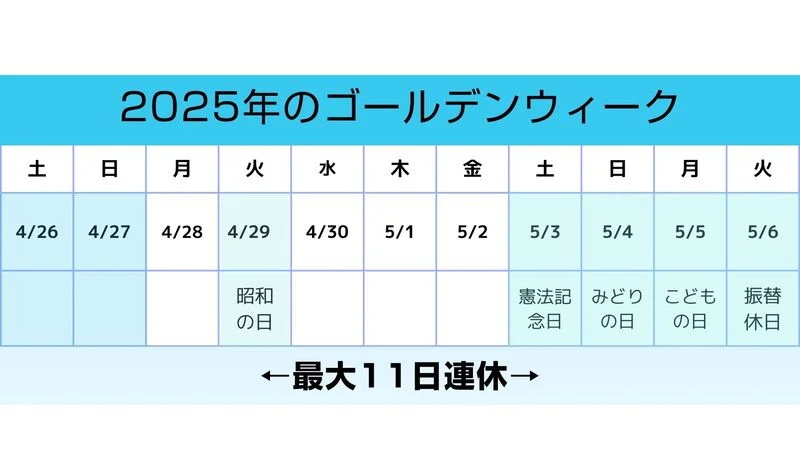
就職活動のスケジュールは、一般的に以下のような流れで進行します。
- 大学3年生の6月頃:インターンシップの募集が始まり、企業研究や自己分析を進める
- 大学3年生の夏〜冬:サマーインターンやウィンターインターンに参加し、実際の業務を体験する
- 大学3年生の3月:企業の採用情報が解禁され、エントリー受付や会社説明会が本格的に始まる
- 大学4年生の6月:採用選考が解禁され、面接やグループディスカッションなどが行われる。
- 大学4年生の10月:内定が出始め、就職活動の終盤を迎える
このスケジュールはあくまで一般的なものであり、企業によっては早期に採用活動を開始する場合もあります。
26卒の就活は、25卒の就活スケジュールに比べて忙しい時期が半月〜1ヶ月前倒しになっていると言われています。
就活の早期化に伴って、就活の忙しさも変化してきていると言えるでしょう。
早めに情報収集を行い、自分の志望する企業のスケジュールを把握しておくことが大切です。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!3年4月〜5月の忙しさ
大学3年生の4月から5月にかけては、就活準備が本格化する時期です。
- 就活準備が始まり、やることが見えずに焦る時期
- インターン選考と学業の両立が大変
多くの学生が自己分析やエントリーシートの作成、企業研究などに取り組み始めます。
ここでは、就活が忙しかった時期にどんなことをしていたのかのアンケートを取りましたので、その結果を元に、大学3年生の4月から5月はどんな忙しさがあったのかを解説していきます。
就活準備が始まり、やることが見えずに焦る時期
この時期は、初めての就活に戸惑い、「何をしたらいいかわからない」と感じる学生も少なくありません。
自己分析やエントリーシートの作成、企業研究など、やるべきことが多く、精神的にもプレッシャーを感じやすい時期だったことがアンケート結果からわかりました。
しかし、焦らず一つ一つ取り組むことで、自分の強みや志望する業界・企業が明確になっていきます。
周囲の友人や先輩、キャリアセンターの相談員などに相談しながら進めていくと、安心して就活を進めることができるため、1人で進めようとするのではなく、早め早めに誰かに相談していきましょう。
インターン選考と学業の両立が大変
4月から5月にかけては、サマーインターンの選考が始まる時期でもあります。
エントリーシートの提出や面接など、インターンの選考に時間を取られることが多くなり、なかなか忙しかったようでした。
一方で、学業も本格化する時期であり、授業や課題との両立が求められます。
スケジュール管理を徹底し、優先順位をつけて取り組むことが重要です。
無理をせず、自分のペースで進めていくことが、就活と学業の両立の鍵となるため、スケジュール管理の方法を自分なりに確立させて、無理なく余裕をもった就活スケジュールを組み込んでいきましょう。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!3年6月〜9月の忙しさ
大学3年生の6月から9月にかけては、サマーインターンシップの選考・参加が本格化し、就活の実感が強くなってくる時期です。
- サマーインターンの準備と参加でスケジュールが埋まる
- インターン中に自己分析の甘さを痛感
早期選考へとつながるインターンも多く、志望業界が明確な学生にとっては重要なステップとなります。
一方で、「まだ準備が整っていない」と感じながらも、スケジュールに追われて参加していたという声も少なくありません。
この時期は、就活と学業のバランスを取りながら、インターン準備・参加・振り返りと、複数のタスクを同時並行で進めなければならず、多くの学生にとって多忙さを感じる期間です。
初めての企業との接点が増える中で、社会人との関わり方やビジネスマナーにも触れ、自分の就活の方向性を見直すきっかけになる方も多いようでした。
サマーインターンの準備と参加でスケジュールが埋まる
6月から8月にかけては、サマーインターンの選考や参加がピークを迎えます。
エントリーシートの提出、Webテスト、面接など、複数社に応募する学生にとっては日々の予定がスケジュール帳で埋め尽くされるような時期です。
「就活が本格化してきた」「本気で向き合うタイミングだと感じた」といった声も多く、実際に企業と接することで自分の進路に対する意識が一段と高まる時期だったという回答が見受けられました。
一方で、体力的にも精神的にも疲れを感じる学生も見受けられ、特に複数社を並行して受けている場合は、時間管理や優先順位のつけ方が重要になってきます。
周囲と比較せず、自分のペースで取り組む意識が大切です。
インターン中に自己分析の甘さを痛感
実際にインターンに参加してみると、「思っていた業務と違った」「想像よりも合わなかった」という感想を持つ学生も少なくありません。
この経験を通じて、自分の価値観や適性について改めて考え直すことができたという声が多数寄せられました。
インターンに参加して実際の業務や社風を経験し、自分に合っているか、もしくは合っていないかを判断することは、就活におけるとても大切な判断軸の一つです。
また、参加前の自己分析が不十分だったことに気づき、「もっと準備しておけばよかった」と後悔するケースもあります。
そのため、インターン終了後の振り返りは非常に重要です。
経験を言語化し、自己PRや志望動機にどう活かすかを整理することで、今後の選考対策にもつながるため。インターンは就活のリハーサルとして捉え、次につなげていきましょう。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!3年10月〜2月の忙しさ
10月から翌年2月にかけては、秋冬インターンの選考・参加や本選考に向けた準備が本格化し、就活における「山場」となる時期です。
- 秋冬インターンの準備と面接が重なった
- 本選考を見据えて焦りを感じ始めた
企業によっては年内に選考を実施するところもあり、早めに動いていた学生との間で差がつき始めるタイミングでもあります。
そのため、周囲の進捗と比べて不安や焦りを感じやすくなる時期でもあるのです。
この時期は、ESや面接対策の精度を高めることが求められます。
また、インターン経験を振り返りながら、志望業界や職種をさらに明確にしていくことが求められるため、情報収集や自己分析に改めて力を入れる必要があります。
学業や卒業論文との両立も重なるため、心身ともに忙しさを感じやすい時期ですが、ここを乗り越えることで自信をもって本選考に臨めるようになるため、ぜひ力を入れて就活に取り組んでみてください。
秋冬インターンの準備と面接が重なった
10月以降は秋冬インターンの選考や実施が本格化します。
特に外資系企業や一部のベンチャー企業では、インターンが実質的な本選考の一部となっている場合もあり、学生側も真剣度が高まる時期です。
加えて、エントリーシートの締切や面接日程が重なることも多く、スケジュールのやりくりが大きな負担になります。
さらに、大学の授業やゼミ活動、期末試験など学業との両立も難しくなってくる時期です。
優先順位をしっかりつけながら、限られた時間をどう使うかが問われます。
インターンの経験を無駄にしないためにも、選考での気づきや学びをその都度振り返って記録しておくことが、後の自己PRに生きてくるでしょう。
本選考を見据えて焦りを感じ始めた
年末が近づくにつれ、一部の企業が早期に本選考を開始することで、周囲との進捗に差を感じ始める学生も増えてきます。
「あの子はもう内定をもらった」「自分はまだ準備不足かも」と、焦りや不安を感じる声が多く聞かれるようになるのがこの時期だといえるでしょう。
しかし、本選考のピークは3月以降であり、焦りすぎず、今できる準備に集中することが何より大切です。
自己分析や業界研究を丁寧に行い、志望理由やエピソードを深掘りすることが、後の選考での自信につながります。
また、焦りを感じたときこそ、キャリアセンターやOB・OG訪問など、外部の力を借りて視野を広げることも有効です。
本選考が近いからといって極端に焦るのではなく、焦らず、自分のペースで一歩ずつ進めていきましょう。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!3年3月〜4年5月の忙しさ
大学3年生の3月から大学4年生の5月にかけては、本選考が本格化する就活の最繁忙期です。
- 3年3月は圧倒的に忙しい!選考が一気に始まる
- 4年4月・5月は内定の有無で心境が分かれる
企業の採用情報が一斉に公開され、エントリー受付・ES提出・面接が立て続けに行われることで、学生にとって毎日が就活で埋まるような時期になります。
この時期は、数十社単位で応募する学生も多く、選考が重なることでスケジュール管理が非常に重要になってきます。
一方で、4年生に入ると、徐々に内定が出始める学生と、まだ結果が出ていない学生とで心境の差が生まれるタイミングでもあります。
具体的にどのような忙しさがあるのか、順番に解説していきます。
3年3月は圧倒的に忙しい!選考が一気に始まる
就活が本格スタートする3月は、多くの企業が一斉に選考を開始するため、学生の予定は一気に埋まっていきます。
エントリーシートの締切が重なったり、1日に複数の面接が入るなど、スケジュール調整だけでも大変な時期です。
「毎日が選考で休む暇がなかった」「何社受けたか覚えていないほど」といった声も多く聞かれ、まさに就活のピークといえるでしょう。
緊張の連続の中でも、自分の軸を持って判断することが、納得のいく結果につながります。
この時期をどう乗り切るかが、就活の成否を左右すると言っても過言ではありません。
4年4月・5月は内定の有無で心境が分かれる
4月・5月になると、内定が出始める学生が増え、少しずつ就活の終わりが見えてくる時期です。
すでに内定を得た学生にとっては、気持ちに余裕が生まれ、卒業研究や大学生活に集中できるようになります。
一方で、まだ結果が出ていない学生にとっては、「周りは終わっているのに、自分は…」という焦りや不安が大きくなりがちです。
このような心の揺れは誰にでも起こり得ることなので、必要以上に自分を責めず、自分のペースを大切にしましょう。
就活は早さだけでなく、自分に合った企業に出会うまで粘り強く向き合うことが大切です。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!4年6月〜9月の忙しさ
4年生の6月から9月にかけては、就活全体としては終盤に差し掛かる時期ですが、まだまだ多くの企業が採用活動を継続しています。
- 最終選考や追加募集が狙い目だった
- 焦りつつも諦めずに活動した人が結果を出した
特にこの時期は、内定辞退者への対応として「追加募集」や「最終選考」が行われることも多く、最後のチャンスを狙って活動を続ける学生は少なくありません。
また、就活を続けていることに対する焦りやプレッシャーが大きくなる時期でもありますが、ここで「もう少しだけ頑張ってみよう」と踏み出した学生が結果を出しているという実例もあります。
自分にとって納得のいく就職先に出会うための粘り強さが光るタイミングともいえるでしょう。
最終選考や追加募集が狙い目だった
6月以降、多くの企業が一次採用を終える中で、内定辞退や採用人数の調整に伴って追加募集を行うケースが見られます。
このような情報は目立ちにくい一方で、チャンスが眠っている時期でもあります。
実際に、「諦めずに応募した企業で最終選考に進めた」「このタイミングで運命の会社に出会えた」という声も少なくありません。
周囲が就活を終え始める中、自分もそろそろ終わりにしようかと感じることもあるかもしれません。
しかし、情報をこまめにチェックし、少しの勇気を持って行動を起こすことで、思わぬ出会いや成果につながる可能性が広がります。
焦りつつも諦めずに活動した人が結果を出した
6月から9月にかけての時期は、「周囲が次々と内定をもらっている中で、自分だけが遅れているように感じた」という声も多く聞かれます。
しかし、そこで立ち止まらず、最後まで粘り強く行動した学生こそが、最終的に納得のいく結果を手にしているのが事実です。
「正直、諦めかけていたけれど、あと一歩踏み出したことで内定をもらえた」というように、この時期の就活は粘りと行動が成功の鍵となります。
気持ちを切り替え、自分の強みを見直して再挑戦する姿勢が、企業側にも好印象を与えるのです。
【就活が忙しい時期】みんなに聞いた!4年10月以降の忙しさ
大学4年生の10月以降は、就活の一般的なピークが過ぎた後の時期ではありますが、すべての学生にとって「終わり」ではありません。
- 一部企業の通年採用や第2新卒枠を狙った
- やり直し就活・再挑戦で動き出す人も
一部の企業では通年採用や追加募集が行われており、粘り強く行動を続ける学生にとっては最後のチャンスが眠っている期間でもあります。
また、この時期には、すでに一度就活を終えた学生が「やり直し」を決意し、再度動き出すケースも見られます(再就活)。
周囲が落ち着いていく中での就活は孤独を感じやすくなりますが、自分が納得のいく道を選ぶためにもう一度チャレンジする姿勢は、十分に価値のある選択です。
この時期の就活は「自分のために行動できるかどうか」が問われるタイミングとなるので、自分のペースを大切に、焦らず、着実に歩んでいきましょう。
一部企業の通年採用を狙った
10月以降も採用活動を続ける企業は少なくありません。
特に中小企業やベンチャー、地方企業などでは、通年採用を行っていることがあります。
この時期まで活動を続けている学生にとっては、競争が比較的緩やかになっている分、丁寧にアプローチすることで内定につながる可能性があります。
「最後まであきらめずに行動したことが内定につながった」「この時期だからこそ、じっくり話を聞いてもらえた」というような、粘り強さが実を結んだという体験談もありました。
情報収集を欠かさず、自分に合った企業を見つけていくことが重要です。
やり直し就活・再挑戦で動き出す人も
一度内定を承諾したものの、「本当にここでいいのだろうか」と違和感を抱き、再び就職活動を始める学生もいます。
この決断には大きな勇気が必要であり、周囲が就活を終えている中での再スタートは孤独やプレッシャーと向き合う覚悟も必要です。
しかし、自分が納得できる選択をすることは、将来への後悔を減らすうえでも非常に大切です。
やり直しの就活では、自分の価値観や働きたい環境を改めて見直す良い機会になります。
「最初よりも自分のことを深く理解できた」という声も多く、再挑戦は決してマイナスなものではありません。
【就活が忙しい時期】就活の忙しさが変わる理由5選
就活の忙しさは、時期や企業の動きによるものだけでなく、「個人の状況」や「生活スタイル」によっても大きく変わってきます。
同じ大学3年生でも、ある人は比較的余裕を持って行動できていたのに、別の人は常に時間に追われていた、といったような差が生まれる背景には、いくつかの共通した理由があります。
- 大学の授業の単位取得
- 部活動やサークルの予定
- アルバイトや長期インターンとの両立
- 就活エントリー前の準備
- 一度に受ける企業数の増加選考対策
ここでは、学生の皆さんが実際に感じた「忙しさの原因」を5つに分けてご紹介します。
自分の状況と照らし合わせながら、どこに工夫の余地があるのかを見つけるヒントになれば幸いです。
大学の授業の単位取得
就活の忙しさに影響を与える一つの要因が、授業の履修状況です。
これまでに必要単位をしっかり取っている学生は、3年後期以降の授業が少なくなるため、比較的就活の時間を確保しやすくなります。
一方、卒業単位がまだ多く残っている場合は、週5日しっかり授業があることもあり、就活と学業の両立が難しくなってしまいます。
できるだけ早めに単位を取っておくことで、後の就活期間をゆとりあるものにできるでしょう。
部活動やサークルの予定
部活動やサークルに積極的に参加している学生にとっては、活動時間とのバランスも忙しさを左右するポイントになります。
特に、幹部やリーダーなどの役職についている場合、就活との両立は非常に難しくなる傾向があります。
スケジュールが固定されている活動は、就活の面接日程や企業説明会と重なってしまうこともあり、調整が必要です。
事前に自分の優先順位を明確にし、無理のない両立方法を模索することが大切です。
アルバイトや長期インターンとの両立
アルバイトや長期インターンを行っている学生も多く、これらのスケジュールが就活の忙しさに直結することがあります。
特に生活費や交通費のためにアルバイトを減らせない場合、選考日程との調整が難しくなってしまうことも。
また、インターン先での業務が忙しい時期と就活が重なることで、心身の疲労が蓄積するケースもあります。
可能な範囲でシフトや働き方を調整し、「今は就活を優先する」と割り切ることも選択肢の一つです。
就活エントリー前の準備
就活が忙しく感じられる背景には、準備不足もあります。
エントリー開始前の段階で、自己分析や企業研究、エントリーシートのひな型作成などを行っておくことで、本番の負担を軽減できます。
また、スーツや靴、カバンなどの物理的な準備にも時間がかかるため、早めに揃えておくと安心です。
事前準備がしっかりできていれば、選考が始まってからも余裕を持って対応できます。
一度に受ける企業数の増加選考対策
就活が本格化する3月以降は、一度に複数の企業を受ける学生がほとんどです。
それに伴って、エントリーシートの作成、面接練習、Webテストの対策など、やるべきことが一気に増加します。
企業ごとに求められる内容が異なるため、それぞれに合わせた準備が必要となり、時間と労力がかかります。
このような時期は、優先順位を明確にし、計画的に進めることが重要です。
無理のないスケジュール管理が、精神的な安定にもつながります。
【就活が忙しい時期】忙しさを乗り切るためのポイント
就職活動の時期は、学生生活の中でも特に多忙な期間となります。
授業、アルバイト、部活動などと並行して行う必要があるため、時間の使い方や準備の進め方次第で、就活の負担感は大きく変わってきます。
ここでは、多くの先輩たちが実践していた「忙しさを乗り切るためのポイント」を4つご紹介します。
- できるだけフル単で単位を取得しておく
- 大学3年生までに就活の準備を済ませる
- 余裕を持った就活スケジュールを組む
- 適度にリラックスタイムを取る
事前の準備と、計画的なスケジュール管理を意識することで、心身の余裕を保ちつつ納得のいく就職活動につなげることができます。
焦らず、無理なく、自分らしい就活を進めていくための参考にしてみてください。
できるだけフル単で単位を取得しておく
就活時期に授業が少ないと、面接や説明会への参加、自己分析や企業研究に十分な時間を確保することができます。
そのため、大学2年生までに可能な限り「フル単」を目指し、必要な単位を前倒しで取得しておくのがおすすめです。
もちろん大学や学部によって履修のしやすさは異なりますが、将来の自分が余裕を持って就活に集中できるよう、早めに計画を立てて授業に取り組むことは大きな助けとなります。
就活のピークを迎える3年後期〜4年前期に自由な時間を確保するために、今できる準備をしておきましょう。
大学3年生までに就活の準備を済ませる
スーツやバッグ、靴、証明写真など、就活に必要なモノの準備は、大学3年生に入る前までに済ませておくと安心です。
いざ就活が始まってからバタバタと準備をすると、肝心な企業研究や自己分析にかける時間が取れなくなってしまうこともあります。
また、自己PRやガクチカといったエントリーシートの基本項目についても、早めに書き始めておくことで、本番の提出がスムーズになります。
3年生になる前に基本的な準備を整えておけば、選考対策に集中できる余裕が生まれます。
余裕を持った就活スケジュールを組む
就活が忙しいと感じる一因には、予定が過密すぎるスケジュールがあります。
企業説明会や面接が重なってしまうと、移動や準備に追われ、心に余裕がなくなってしまいがちです。
そのため、エントリーする企業数や選考日程は、あらかじめ計画を立てて無理のない範囲に収めることが大切です。
時間に余裕があることで、面接対策にじっくり取り組めたり、体調管理や気分転換の時間を確保できたりと、結果的にパフォーマンスの向上にもつながります。
適度にリラックスタイムを取る
就活期間中は、気づかないうちに心身ともに緊張状態が続いてしまうことがあります。
そんなときこそ、意識的に「リラックスタイム」を設けることが大切です。
たとえば、友人との食事や趣味の時間、好きな音楽を聴くひとときなど、日常の中にほっとできる時間を作ってみましょう。
適度な休息を取ることで気持ちが切り替わり、次の選考にも集中して臨めるようになります。
頑張りすぎず、自分を労わる時間を大切にしながら、長丁場の就活を乗り切っていきましょう。
【就活が忙しい時期】忙しい時期に効率よく進めるためのポイント7選
就職活動が本格化する時期は、授業や卒論、アルバイトなどとの両立に追われ、どうしても忙しくなってしまうものです。
限られた時間の中で満足のいく活動を進めるためには、効率を意識した取り組みが欠かせません。
特に、事前の情報収集やサポートツールの活用によって、就活をスムーズに進める工夫が重要になってきます。
- インターンに参加する
- 早めに業界研究や企業研究をする
- OB・OG訪問をする
- 大学のキャリアセンターを利用する
- 就活エージェントを利用する
- 逆求人サイトやアプリを利用する
- 就活イベントに参加する
焦りや不安を感じやすいこの時期だからこそ、自分に合った方法で無理なく進めることが、心にも体にも優しい就活スタイルにつながります。
ここでは、忙しい時期でも効率よく就活を進めるための具体的なポイントを7つご紹介します。
取り入れやすいものからぜひ実践して、あなたらしいペースで一歩ずつ前進していきましょう。
1. インターンに参加する
効率良く就活を進めたい方には、インターンシップへの参加をおすすめします。
インターンシップに参加することで、企業の雰囲気や仕事の実態を肌で感じることができ、業界研究や企業研究がぐっと深まります。
短期インターンでも、実際に社員の方と接する機会があったり、仕事体験ができたりと、ネットやパンフレットだけでは得られないリアルな情報を得ることができます。
また、企業によっては、インターンの参加者に対して早期選考の案内がある場合もあり、通常よりも一歩リードして就活を進められるチャンスが広がります。
さらに、自分に合った仕事や働き方を見極めるためにも、インターンは大きな役割を果たします。
実際に体験してみることで、想像と現実のギャップに気づいたり、逆に「ここで働きたい」と強く感じることもあるでしょう。
忙しい中でも、夏休みや春休みといったまとまった時間を活用してインターンに参加しておくと、後の本選考が格段にスムーズになります。
2. 早めに業界研究や企業研究をする
忙しい就活期間をスムーズに進めるためには、業界研究や企業研究を早めに始めることが重要です。
早い段階で情報を集めておくことで、自分に合った業界や企業を見極めやすくなり、選考時の迷いや焦りを減らすことができます。
特に、興味のある業界だけでなく、幅広い業界に目を向けることを意識しましょう。
最初はあまり興味がなかった業界でも、調べてみると意外な魅力に気づくことも少なくありません。
選択肢を広げておくことは、就活が思うように進まなかった場合の切り替えにも役立ちます。
具体的には、業界ごとの特徴や動向、企業の理念や事業内容、働き方などを調べていきましょう。

情報源としては、企業の公式サイトや就活サイト、業界地図、ニュース記事などを活用するのがおすすめです。
また、志望業界や企業がある程度固まったら、選考対策も早めにスタートできます。
エントリーシートや面接で求められるポイントを把握し、事前に準備を進めておけば、忙しい時期にも余裕を持って対応できるでしょう。
3. OB・OG訪問をする
効率よくリアルな情報を得るために、OB・OG訪問を積極的に行うことも大切です。
実際にその企業で働く先輩方から直接話を聞くことで、Webサイトや説明会だけではわからない、より具体的な仕事の内容や職場の雰囲気を知ることができます。
たとえば、実際の一日の業務スケジュール、働いてみて感じたギャップ、キャリアパスの例など、現場ならではのリアルな声は、就活の視野を大きく広げてくれるでしょう。
志望動機や自己PRを考える際にも、OB・OG訪問で得た体験談を盛り込むと、説得力が増します。
訪問の際は、あらかじめ質問を用意しておくと、時間を有効に使えます。
また、訪問後は必ずお礼の連絡をするなど、社会人としてのマナーを意識することも忘れずに。
こうした細かな対応が、良い印象につながることもあります。
最近では、大学のキャリアセンターや専用のマッチングサービスを通じてOB・OG訪問をサポートしてもらえる場合もありますので、積極的に利用してみてください。
4. 大学のキャリアセンターを利用する
忙しい中でも効率的に就活を進めたいなら、大学のキャリアセンターを活用するのがおすすめです。
キャリアセンターには、大学生向けに特化した求人情報が届いていたり、学部学科ごとの傾向を踏まえたアドバイスを受けられたりと、非常に役立つ情報が集まっています。
たとえば、過去に同じ学部の先輩がどのような企業に内定しているか、どんな就活の進め方をしていたかなど、実績に基づくデータをもとにした相談が可能です。
また、エントリーシート添削や面接練習、自己分析サポートなど、プロによるきめ細やかな支援も受けられます。

就活の進め方に悩んでいるときや、自分に合う企業選びに迷ったときには、一人で抱え込まずキャリアセンターに相談してみましょう。
無料で利用できるサービスがほとんどなので、使わない手はありません。
特に、就活初期の段階からキャリアセンターをうまく活用することで、忙しい時期の負担を減らし、より自分に合った道を選びやすくなります。
5. 就活エージェントを利用する
さらに効率的に就活を進めたい方には、就活エージェントの利用もおすすめです。
エージェントは、就活生一人ひとりに専任のアドバイザーがつき、求人紹介から選考対策まで幅広いサポートを行ってくれます。
特に、自己分析に自信がない、志望企業がまだ絞れていないといった場合でも、プロの視点で適切なアドバイスを受けられるため、就活の軸を定める手助けとなるでしょう。
エントリーシートや履歴書の添削、模擬面接の実施など、具体的な対策もスピーディーに進めることができます。
また、非公開求人と呼ばれる、一般には出回っていない特別な求人情報を紹介してもらえることもあり、チャンスの幅が広がります。
自分一人で探しているだけでは出会えなかった企業とのご縁が生まれるかもしれません。
就活エージェントは複数登録して比較することも可能なので、自分に合ったエージェントを見つけて、積極的に活用していきましょう。
6. 逆求人サイトやアプリを利用する
スカウト型の逆求人サイトやアプリを利用するのも、忙しい就活生にとって大きな味方になります。
逆求人サイトでは、自分のプロフィールを登録しておくだけで、企業側からオファーをもらうことができ、受け身でもチャンスを得られる仕組みになっています。
この方法の良いところは、自分が知らなかった企業や業界から声がかかる可能性があることです。
自分ではなかなか見つけられなかった魅力的な企業と出会えるきっかけにもなります。
また、スカウトを受けた企業とは、通常よりもカジュアルな面談形式で話ができるケースが多く、選考のプレッシャーを感じずに企業理解を深められるメリットもあります。

逆求人サイトを利用する際には、プロフィールを丁寧に記入し、自分の強みや志向を明確に伝えることがポイントです。
質の高いスカウトを受けるためにも、しっかりと準備をしておきましょう。
7. 就活イベントに参加する
最後にご紹介するのは、就活イベントへの参加です。
特に、選考直結型のイベントは、短期間で効率的に企業との接点を持つことができるため、多忙な就活生にとって非常に有効です。
こうしたイベントでは、企業説明と選考が一度に行われることが多く、気になった企業にはそのままエントリーできる場合もあります。
通常の説明会よりも、企業との距離が近く感じられ、相互理解を深めやすいのも魅力のひとつです。
また、同じように就活に励む仲間と出会える場でもあり、情報交換や刺激を受けるきっかけにもなります。
就活は孤独を感じがちな活動ですが、こうした場に足を運ぶことで、モチベーションを高めることもできるでしょう。

事前予約制のものが多いので、気になるイベントは早めに申し込んでおくことが大切です。
無理のない範囲で積極的に活用し、充実した就活を目指していきましょう。
【就活が忙しい時期】選考で忙しい時期には選考管理シートの利用がおすすめ
就活が本格化してくると、複数の企業の選考が同時並行で進むようになります。
エントリーシートの締切、Webテスト、面接日程などが重なると、スケジュールの管理がとても大変になります。
「この企業の締切、明日だった…」といったミスを防ぐためにも、選考の進捗状況をひと目で把握できる選考管理シートの活用がおすすめです。
選考管理シートは、企業名やエントリー日、提出物の締切、面接日時、進捗状況などを一覧でまとめることができるツールです。
エクセルやGoogleスプレッドシートで自作する学生も多く、自分が今どの企業の何次選考にいるのかを整理しておくことで、就活の全体像が見えやすくなります。
また、可視化することで「この企業は進んでないから優先して対策しよう」といった戦略的な行動もしやすくなります。
特に、就活を始めたばかりで情報の整理が苦手な方や、タスクが多くて混乱しやすい方には非常に心強いツールです。
効率的に就活を進めたい方は、ぜひ自分に合った管理方法を見つけて活用してみてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
















柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
インターンは選考の一部と考える企業も増えているため、早い段階で経験を積んでおくことで、今後の選択肢が広がるはずです。
自分に合うインターンを見つけるためには、大学のキャリアセンターやインターン情報サイトをこまめにチェックすることも大切です。
興味を持った企業には積極的にエントリーして、経験を重ねていきましょう。