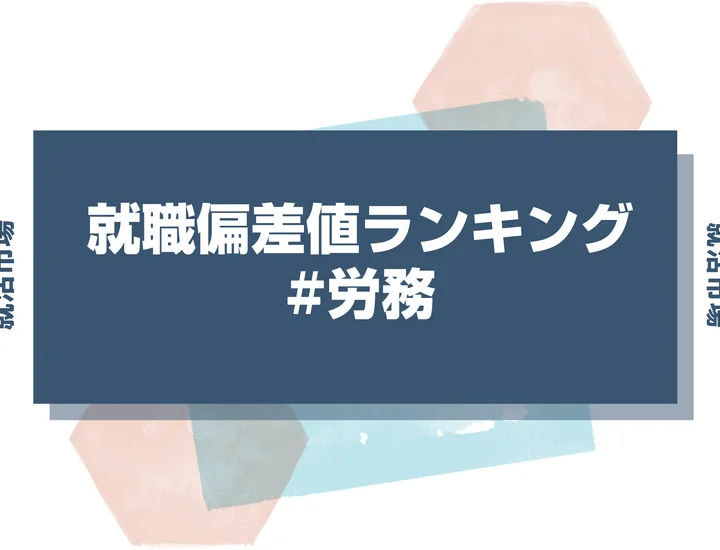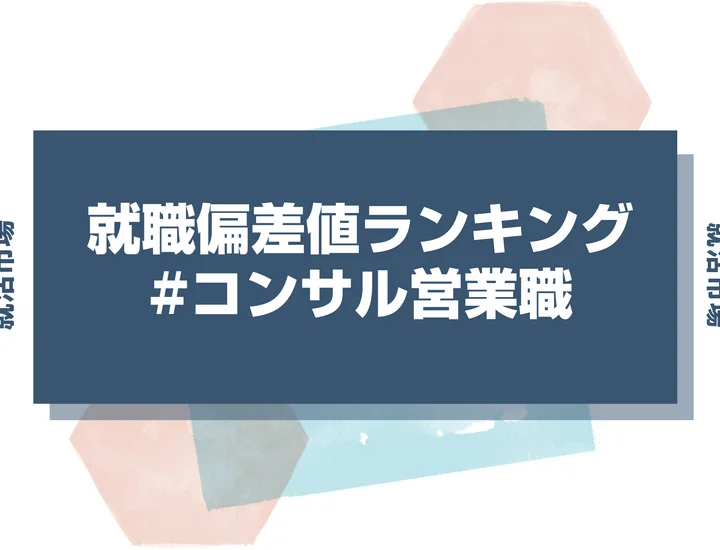「就活が本格化してきたけど、バイトはどうしよう…」「お金は必要だけど、就活と両立できるか不安…」そんな悩みを抱えている就活生は多いのではないでしょうか。
就職活動には、スーツ代や交通費など、何かと出費がかさむものです。
しかし、学業や企業研究、面接対策などに追われる中で、アルバイトの時間を確保するのは簡単なことではありません。
だからといって、安易に「就活に集中するためにバイトは辞めるべき」と決めてしまうのは、少し早いかもしれません。
実は、アルバイトの経験は、金銭的なメリットだけでなく、就活そのものにプラスに働く側面もたくさんあるのです。
この記事では、就活中のアルバイトの必要性から、両立させるための具体的なポイント、さらには就活に有利になる可能性のあるアルバイトまで、皆さんの疑問や不安を解消するための情報を網羅的に解説していきます。
この記事を読めば、自分にとって最適な「就活とバイトの付き合い方」が見つかるはずです。
ぜひ最後まで読んで、後悔のない選択をするための参考にしてください。
就活中にバイトは必要?
結論から言うと、就活中にアルバイトが「絶対に必要」というわけではありません。
ご実家からの支援が十分に受けられたり、これまでの貯蓄で活動費用をまかなえたりする人もいるでしょう。
最も大切なのは、言うまでもなく納得のいく企業から内定を獲得することです。
そのため、アルバイトが原因で企業説明会に参加できなかったり、面接対策がおろそかになったりしては本末転倒です。
しかし、就職活動には想像以上にお金がかかるのも事実です。
全国の就活生の平均的な活動費用は、10万円を超えるとも言われています。
特に地方から都市部へ何度も足を運ぶ学生にとっては、交通費や宿泊費が大きな負担となるでしょう。
金銭的な不安を抱えながら就活を進めることは、精神的な焦りにも繋がります。
そういった意味で、計画的にアルバイトを続けることは、経済的な安心材料となるだけでなく、精神的な安定にも繋がると言えるのです。
次の章で、具体的にどのような費用がかかるのかを詳しく見ていきましょう。
それらを踏まえた上で、自分にアルバイトが必要かどうかを判断することが大切です。
就活中に必要な費用
就職活動には、どれくらいの費用がかかるか具体的にイメージできていますか?「なんとなくお金がかかりそう」という漠然とした不安を抱えている方も多いかもしれません。
実は、就活にかかる費用は決して少なくなく、計画的に準備しておかないと、活動そのものに支障をきたす可能性もあります。
全国の就活生を対象とした調査では、平均して10万円から15万円程度の費用がかかると言われています。
特に、地方の学生が都心で就活を行う場合は、交通費や宿泊費が加わるため、さらに高額になる傾向があります。
ここでは、具体的にどのようなことにお金がかかるのか、主な内訳を5つに分けて詳しく解説していきます。
あらかじめ必要な費用を把握しておくことで、計画的な資金準備が可能になります。
また、「これだけかかるなら、やはりバイトで補おう」といった判断基準にもなるはずです。
自分の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
スーツと靴代
就活費用の内訳として、まず最初に思い浮かぶのがスーツと靴代ではないでしょうか。
リクルートスーツは、就活生の第一印象を左右する重要なアイテムです。
一式揃えるとなると、決して安い買い物ではありません。
一般的に、スーツ本体の価格相場は2万円から5万円程度です。
もちろん、ブランドや素材にこだわればそれ以上の価格になりますが、就活で着用する分にはこの価格帯のもので十分でしょう。
また、スーツだけでなく、革靴も必要になります。
靴の相場は5,000円から1万5,000円程度を見ておくと安心です。
スーツは夏用と冬用で2着用意したり、連日の面接に備えてシャツを複数枚購入したりすると、さらに費用がかさみます。
最近では、比較的安価で品質の良いスーツを販売している専門店も増えているので、複数の店舗を比較検討するのがおすすめです。
入学式などで購入したスーツがまだ着られる場合は、それを利用することで費用を大きく抑えることができます。
まずはクローゼットの中身を確認してみることから始めましょう。
小物代
スーツと靴を揃えたら、次は小物類の準備が必要です。
こうした細かなアイテムは一つひとつの単価は高くないものの、積み重なると意外な出費になります。
例えば、男性であればネクタイ、女性であればストッキングは複数用意しておく必要があります。
ネクタイは1本2,000円から5,000円程度、ストッキングは数枚セットで1,000円程度のものが多いでしょう。
また、男女共通で必要になるのが、A4サイズの書類が入る就活用のバッグです。
これも5,000円から1万円程度が相場となります。
その他にも、ベルトや腕時計、企業から指定があった場合に必要な証明写真の撮影代なども考慮しなければなりません。
特に証明写真は、後から焼き増しすることも考えると、最初にデータ付きのプランで撮影しておくのが賢明です。
これらの小物を一から全て揃えるとなると、合計で2万円から3万円程度の出費は覚悟しておいた方が良いでしょう。
フリマアプリなどを活用して中古品を探したり、先輩から譲ってもらったりするなど、工夫次第で費用を抑えることも可能です。
履歴書・送料
最近ではWebエントリーが主流になりつつありますが、依然として履歴書やエントリーシートの郵送を求める企業も少なくありません。
特に、老舗の企業や特定の業界では、手書きの書類を重視する傾向が見られます。
履歴書用紙は、大学指定のものであれば大学の生協などで、市販のものであれば文房具店やコンビニで手軽に購入できます。
価格は1セット数百円程度ですが、何十社と応募することを考えると、複数セット購入しておく必要があります。
また、郵送する際には、書類を折らずに入れられる角形A4号の封筒と、切手代も必要です。
普通郵便であれば140円程度ですが、簡易書留など追跡可能な方法で送る場合は、さらに料金が加算されます。
一社あたりの費用は数百円と少額ですが、応募する企業数が増えれば増えるほど、その合計金額は無視できないものになります。
特に、書き損じを考慮すると、履歴書や封筒は多めに用意しておく必要があるため、予想以上に出費がかさむ可能性があります。
エントリーする企業の応募方法を事前に確認し、どれくらいの費用がかかりそうか、あらかじめ見積もっておくと良いでしょう。
交通費
就活費用の中で、最も大きな割合を占める可能性があるのが交通費です。
特に、地方に住んでいて都心部の企業を複数受ける学生にとっては、深刻な問題と言えるでしょう。
説明会や面接のたびに新幹線や飛行機を利用するとなると、一度の上京で数万円の費用がかかってしまいます。
連泊すれば宿泊費も必要になり、その負担は計り知れません。
都市部に住んでいる学生であっても、複数の企業を回るためには電車やバスの利用が必須です。
1回の移動は数百円でも、就活期間全体で考えると、数万円単位の出費になることも珍しくありません。
最近ではオンラインでの説明会や面接も増えていますが、最終面接は対面で行う企業が依然として多いのが実情です。
そのため、ある程度の交通費は必ずかかると考えておくべきでしょう。
航空会社の学割プランや、高速バスの早期予約割引などを積極的に活用することで、少しでも費用を抑える工夫が求められます。
自分の志望する企業がどの地域に多いのかを把握し、交通費がどれくらいかかりそうか、早めにシミュレーションしておくことが重要です。
飲食費
見落としがちですが、意外とかさんでくるのが飲食費です。
朝早くから家を出て、説明会や面接をハシゴしていると、昼食を外で済ませる機会が必然的に増えます。
1回の食事が1,000円程度だとしても、それが週に何日も続けば、1ヶ月で1万円以上の出費になることもあります。
また、説明会と次の面接の間に時間が空いてしまった場合、カフェで時間を潰しながらエントリーシートを書いたり、企業研究をしたりすることも多いでしょう。
カフェ代も1回500円程度ですが、これも積み重なれば大きな金額になります。
就活中は、慣れない環境での緊張や移動の疲れから、普段よりもエネルギーを消費しがちです。
空腹や疲労は集中力の低下を招き、万全の状態で面接に臨めなくなる可能性もあります。
そのため、飲食費を切り詰めることはあまりおすすめできません。
しかし、毎回外食に頼るのではなく、水筒や軽食を持参するなどの小さな工夫で、日々の出費をコントロールすることは可能です。
こうした地道な節約が、結果的に就活全体の費用を抑えることに繋がります。
就活とバイトを両立させる利点
就活中のアルバイトと聞くと、「大変そう」「時間がなくなる」といったマイナスのイメージを持つ人が多いかもしれません。
確かに、スケジュール管理が難しくなったり、体力的にきつくなったりする側面はあります。
しかし、見方を変えれば、就活とアルバイトを両立させることには、金銭面以外にも多くの利点が存在するのです。
むしろ、計画的に両立させることで、就職活動そのものを有利に進められる可能性すらあります。
例えば、就活漬けの日々から少し離れることで気分転換になったり、アルバイトで得た経験が自己PRの強力な武器になったりすることもあります。
ここでは、そんな就活とバイトを両立させる4つの利点について、具体的に解説していきます。
これらの利点を理解すれば、「ただお金を稼ぐため」という考えから、「就活を成功させるため」という前向きな目的意識を持ってアルバイトに取り組めるようになるでしょう。
単なる負担ではなく、自分を成長させるための機会としてアルバイトを捉え直すきっかけにしてください。
就活の息抜きになる
就職活動は、精神的にも肉体的にも大きなプレッシャーがかかります。
連日のように企業説明会に参加し、エントリーシートを作成し、面接対策に追われる日々が続くと、知らず知らずのうちにストレスが溜まってしまうものです。
そんな時、アルバイトが良い息抜きになることがあります。
就活のことを一旦忘れ、アルバイト先の仕事に集中したり、同僚と他愛もない話をしたりする時間は、凝り固まった頭と心をリフレッシュさせてくれるでしょう。
就活中は、どうしても自分の評価や将来のことばかりを考えがちですが、アルバイトを通じて社会と繋がり、誰かの役に立っているという実感を得ることは、自己肯定感を高める上でも非常に効果的です。
また、アルバイトで体を動かすことで、運動不足の解消にも繋がります。
就活モードから意識的に離れる時間を作ることで、新たな視点で自己分析ができたり、面接の受け答えを冷静に振り返ったりする余裕が生まれることもあります。
適度な息抜きは、長期戦である就職活動を乗り切るために不可欠な要素なのです。
就活の出費を補える
前の章でも詳しく解説した通り、就職活動にはスーツ代や交通費、飲食費など、様々な費用がかかります。
特に、一人暮らしの学生や、地方から都市部で就活を行う学生にとって、その金銭的な負担は決して軽いものではありません。
「お金が足りないかもしれない」という不安は、精神的な焦りを生み、企業選びや面接でのパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。
アルバイトを続ける最大の利点は、やはりこの経済的な不安を解消できることでしょう。
定期的な収入があることで、金銭的な心配をせずに就職活動に集中することができます。
例えば、急な面接で遠方に行かなければならなくなった場合でも、ためらうことなく交通手段を手配できるでしょう。
また、説明会の合間にカフェで情報収集したり、就活仲間と情報交換を兼ねて食事に行ったりと、自己投資や人脈作りのためにお金を使う余裕も生まれます。
経済的な基盤が安定していることは、精神的な安定に直結し、結果として就職活動全体に良い影響を与えてくれるのです。
社会のマナーが身につく
アルバイトは、学生でありながら社会に出て働く貴重な経験です。
特に、接客業やオフィスワークなどのアルバイトでは、お客様や取引先といった目上の方と接する機会が多くあります。
その中で、正しい敬語の使い方や電話応対の仕方、来客対応のマナーなどを実践的に学ぶことができます。
これらのスキルは、付け焼き刃で身につくものではなく、日々の業務を通じて自然と体に染み付いていくものです。
就職活動の面接では、入室時の挨拶から言葉遣い、立ち居振る舞いまで、学生のビジネスマナーが厳しくチェックされます。
アルバイト経験を通じて社会人としての基礎的なマナーが身についていれば、面接官に「しっかりとした学生だ」という好印象を与えることができるでしょう。
教科書でマナーを学ぶのと、実際に現場で経験するのとでは、その定着度に大きな差が生まれます。
電話でのアポイントメント取得や、OB・OG訪問の際のやり取りなど、面接以外の場面でもアルバイトで培った経験は必ず活きてきます。
お金を稼ぎながら、社会人としての土台を作れるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
バイト経験を就活でアピールできる
多くの学生が自己PRや「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」の題材としてアルバイト経験を挙げるように、その経験は就活における強力なアピールポイントになります。
ただし、単に「コンビニでアルバイトをしていました」と伝えるだけでは、面接官の心には響きません。
重要なのは、そのアルバイト経験を通じて何を学び、どのようなスキルを身につけ、それを入社後にどう活かせるかを具体的に語ることです。
例えば、「アルバイトリーダーとして、新人教育のマニュアルを改善し、全体の業務効率を10%向上させました」といったように、具体的な課題、自分なりの工夫、そしてその結果を数字などを用いて示すことで、あなたの主体性や課題解決能力を効果的にアピールできます。
アルバイトという身近な題材だからこそ、あなたの人柄や価値観を伝えやすいという側面もあります。
どのような目的意識を持って仕事に取り組み、困難な状況にどう向き合ったのかを自分の言葉で語ることで、他の学生との差別化を図ることができるでしょう。
お金を稼ぐだけでなく、自己PRのネタを作るという視点でアルバイトに取り組むことで、その経験はより価値のあるものになります。
就活とバイトを両立させるポイント
就活とアルバイトを両立させることには多くの利点がありますが、一方で、何も考えずに続けていると、就活がおろそかになってしまう危険性もはらんでいます。
企業の選考スケジュールは待ってくれません。
急な面接の連絡が入ったり、エントリーシートの締切が迫っていたりする中で、「バイトのシフトが入っていて対応できない」という事態は絶対に避けなければなりません。
両立を成功させるためには、行き当たりばったりではなく、戦略的に考えて行動することが不可欠です。
ここでは、就活を最優先に進めながら、アルバイトのメリットを最大限に享受するための5つの具体的なポイントを解説します。
これらのポイントを意識するかどうかで、両立のしやすさが大きく変わってきます。
これから紹介する内容を参考に、自分なりのルールを決めて、賢くスケジュールを管理していきましょう。
シフトを入れすぎない
就活とアルバイトを両立させる上で、最も基本的かつ重要なポイントが「シフトを入れすぎない」ことです。
お金を稼ぎたいという気持ちが強いと、ついつい多くのシフトを申請してしまいがちですが、それは得策ではありません。
就職活動は、いつ、どこで、どんな予定が入るか予測が難しいものです。
急に一次面接の案内が来たり、魅力的な企業の追加募集が始まったりすることは日常茶飯事です。
そんな時に、「来週はバイトのシフトがびっしり入っていて動けない」という状況になってしまっては、みすみすチャンスを逃すことになりかねません。
大切なのは、就活のスケジュールに柔軟に対応できるだけの「余白」を常に意識しておくことです。
収入は少し減ってしまうかもしれませんが、「週に2日まで」「1日4時間まで」といったように、自分の中で上限を決め、無理のない範囲で働くことを徹底しましょう。
あらかじめ勤務先に就活中であることを伝え、急なシフト変更にも対応してもらえるよう相談しておくことも大切です。
スケジュール管理を徹底する
就活とアルバイトを両立させるには、徹底したスケジュール管理が不可欠です。
企業の選考スケジュール、エントリーシートの締切、大学の授業、そしてアルバイトのシフトなど、管理すべき項目は多岐にわたります。
これらを頭の中だけで整理しようとすると、必ずどこかでダブルブッキングや締切忘れといったミスが発生します。
そこでおすすめしたいのが、手帳やスマートフォンのカレンダーアプリを活用することです。
全ての予定を一元管理し、週単位、月単位でスケジュールを可視化することで、自分のキャパシティを客観的に把握することができます。
予定が決まったらすぐに書き込む習慣をつけましょう。
特に、エントリーシートの作成や企業研究といった「タスク」も、具体的な時間を設けてスケジュールに組み込んでしまうのがポイントです。
例えば、「火曜の10時から12時はA社のES作成」というように具体的に決めることで、計画的に準備を進めることができます。
こうした地道な管理が、結果的に心と時間の余裕を生み出すのです。
短期・単発バイトをする
もし現在のアルバイト先が、シフトの融通が利きにくい長期契約のものである場合、思い切って短期や単発のアルバイトに切り替えるのも非常に有効な手段です。
長期のアルバイトは、安定した収入が見込める一方で、「急に休むと迷惑がかかる」「自分が辞めると人手不足になる」といった責任感から、就活の予定を優先しづらくなることがあります。
その点、短期・単発のアルバイトであれば、自分の都合の良い日時だけを選んで働くことができます。
例えば、イベントスタッフや試験監督、軽作業の補助など、1日単位で完結する仕事は数多く存在します。
これらの仕事は、専門的なスキルを必要としない場合が多く、気軽に応募できるのも魅力です。
就活の予定が入っていない週末だけ、あるいは選考が落ち着いた時期に集中的に働くといった、柔軟な働き方が可能になります。
精神的な負担も少なく、必要な時に必要な分だけ稼ぐことができるため、就活中の学生にとっては非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。
平日を避けてバイトをする
多くの企業の会社説明会や面接は、カレンダー通りの平日に実施されます。
そのため、アルバイトのシフトを平日の日中に入れてしまうと、選考に参加する機会を大きく制限してしまうことになりかねません。
そこでおすすめしたいのが、アルバイトはなるべく土日祝日や、平日の夜の時間帯に集中させるという方法です。
平日の日中は「就活のための時間」として完全に空けておくことで、企業からの急な連絡にも慌てず対応することができます。
もちろん、業界や職種によっては土日に選考を行う企業もありますが、全体的に見れば平日に集中しているのが実情です。
自分の志望する業界の選考スケジュールをあらかじめリサーチし、どの時間帯を空けておくべきか戦略を立てることが重要です。
この方法であれば、生活のリズムも作りやすく、平日は就活、土日はアルバイトといったように、オンとオフの切り替えがしやすくなるというメリットもあります。
バイトよりも就活を優先する
両立を考える上で、絶対に忘れてはならない大原則は「常に就活を最優先する」という意識です。
アルバイトはあくまで学生生活の一部であり、あなたの本分は納得のいく形で社会への第一歩を踏み出すことです。
もし、アルバイトのシフトと第一志望の企業の最終面接が重なってしまったら、迷わず面接を優先すべきです。
そのためにも、アルバイトを始める前、あるいは就活が本格化する前に、店長や責任者の方に「就職活動を優先させていただきたい」という旨を正直に伝え、理解を得ておくことが非常に重要です。
事前に相談しておくことで、急なシフトの変更や欠勤にも快く対応してくれる可能性が高まります。
誠意をもって事情を説明すれば、多くの職場ではあなたの将来を応援してくれるはずです。
この前提が共有できていないと、罪悪感から就活の予定を言い出しにくくなり、結果的に自分の首を絞めることになってしまいます。
就活とアルバイト、どちらが自分にとっての「本業」なのかを常に心に留めておきましょう。
就活に有利なバイト
どうせアルバイトをするのであれば、ただお金を稼ぐだけでなく、就職活動そのものにプラスになる経験を積みたいと考えるのは自然なことです。
アルバイトの選び方一つで、得られるスキルや知識、そして自己PRで語れるエピソードの質は大きく変わってきます。
もちろん、どんなアルバイトであっても、真剣に取り組めば学びはありますが、より就活との関連性が高い仕事を選ぶことで、効率的に自分を成長させることができます。
ここでは、就活に有利に働く可能性のあるアルバイトを3つのタイプに分けてご紹介します。
これらのアルバイトは、社会人として求められる基礎的な能力を養えたり、業界理解を深めたりする絶好の機会となります。
これからアルバイトを探すという方はもちろん、現在のアルバイト経験を振り返り、就活でどうアピールできるかを考える上でのヒントにもなるはずです。
教育体制が整っていることで有名な企業のバイト
就活に有利なアルバイトの一つとして、教育体制が充実していることで知られる企業のアルバイトが挙げられます。
例えば、大手カフェチェーンやファミリーレストラン、一部の小売店などでは、新人研修のプログラムが非常に体系化されています。
入社後すぐに行われる座学研修から、OJT(On-the-Job Training)での実践的な指導まで、しっかりとしたマニュアルに基づいて行われるため、社会人として必要な基礎を効率的に学ぶことができます。
正しい言葉遣いや接客マナー、クレーム対応の方法といったスキルは、業界を問わずどんな仕事でも役立ちます。
こうした企業で働くことで、自然と高いレベルのビジネスマナーが身につくでしょう。
面接で「御社でアルバイトをしており、その中で培った〇〇というスキルは、貴社でも必ず活かせると考えております」と語れば、その言葉には強い説得力が生まれます。
しっかりとした教育を受けることで、自信を持って仕事に取り組めるようになり、それが就活での自己PRにも繋がっていくのです。
自主性を促すことで有名な企業のバイト
教育体制が整っている企業とは対照的に、あえてマニュアルが少なく、個人の裁量や自主性が重んじられる環境で働くことも、非常に価値のある経験となります。
例えば、立ち上がったばかりのベンチャー企業でのインターンシップ兼アルバイトや、個人経営の飲食店などがこれにあたります。
こうした職場では、「指示待ち」の姿勢では仕事になりません。
自ら課題を見つけ、どうすれば改善できるかを考え、周りを巻き込みながら実行していく力が求められます。
「どうすればもっとお客様に喜んでもらえるか」「どうすれば業務が効率化できるか」といったことを常に考え、試行錯誤する経験は、あなたの課題解決能力や主体性を飛躍的に高めてくれるでしょう。
面接で「前例のない課題に対して、自ら〇〇を提案し、結果として売上を前年比120%に向上させました」といった具体的なエピソードを語ることができれば、他の学生と大きく差別化を図ることができます。
困難な状況を乗り越えた経験は、あなたを人間的に大きく成長させ、就活における何よりの強みとなります。
志望企業と同じ業界のバイト
もし既にある程度、志望する業界が固まっているのであれば、その業界内でアルバイトを経験することは非常に有益です。
例えば、アパレル業界を志望しているならアパレルショップの販売員、IT業界に興味があるならIT企業でのアシスタントやテスターなど、関連するアルバイトは探せば意外と見つかるものです。
業界内で働く最大のメリットは、その業界の「生の情報」に触れられることです。
企業のウェブサイトや説明会だけでは分からない、業界特有のビジネスモデルや慣習、やりがい、そして厳しさなどを肌で感じることができます。
この経験は、志望動機に圧倒的な具体性と説得力をもたらします。
「アルバイトとして働く中で、貴社の〇〇という理念が、単なるお題目ではなく、現場の隅々にまで浸透していることを実感し、ますます入社への意欲が高まりました」といった話は、他の誰にもできないあなただけの強力な武器になります。
また、社員の方と直接話す機会も増えるため、OB・OG訪問のような形で、キャリアパスや仕事内容について深く知ることができるかもしれません。
就活とバイトの両立を目指そう
ここまで、就職活動におけるアルバイトの必要性から、両立のメリット、具体的なポイント、そして就活に有利なアルバイトまで、幅広く解説してきました。
就活とアルバイトの両立は、決して簡単なことではありません。
しかし、計画的に、そして戦略的に取り組むことで、金銭的な不安を解消するだけでなく、人として成長し、就職活動を有利に進めるための大きな力とすることができます。
重要なのは、「なんとなく」アルバイトを続けるのではなく、自分なりの目的意識を持つことです。
「なぜ自分はバイトをするのか」「この経験を通じて何を得たいのか」を明確にすることで、日々の仕事への向き合い方も変わってくるはずです。
今回ご紹介したポイントを参考に、まずは自分の状況を整理し、無理のないスケジュールを立てることから始めてみてください。
アルバイト経験をあなたの強みに変え、自信を持って就職活動に臨んでください。
皆さんが納得のいく形で社会への一歩を踏み出せるよう、心から応援しています。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート