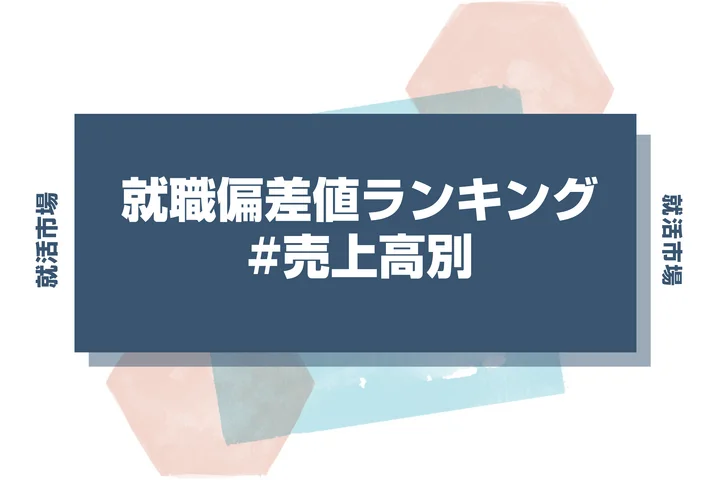目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
売上高別の就職偏差値ランキング
就職活動を進める中で、「この企業はどれくらいのレベルなんだろう?」「自分の実力で挑戦できるのだろうか?」といった疑問を持つことは自然なことです。
企業のブランド力や採用難易度を示す一つの指標として「就職偏差値」がありますが、今回は特に企業の売上高という客観的なスケールと就職偏差値を紐づけることで、企業群ごとの特徴をより立体的に捉えていきましょう。
売上高は企業の事業規模や市場における影響力を示す大きな要素であり、概して売上高が高い企業ほど、知名度や待遇、安定性が高くなる傾向にあり、それに伴い就職偏差値も高くなる傾向があります。
ただし、売上高だけが全てではなく、業界の特性や成長性、非上場企業などによっても偏差値は変動します。
このランキングを通じて、自分自身のキャリアの方向性や挑戦したい企業のレベル感を具体的にイメージするための参考にしてください。
単純な数値の比較ではなく、それぞれのランクに属する企業が持つ「強み」や「環境」を理解することが、より納得感のある企業選びにつながります。
【売上高別】SSランク(就職偏差値78以上)
- 売上高1兆円以上のグローバル企業やメガグループが中心
- 事業ポートフォリオが幅広く、配属先やキャリアパスの選択肢が多い
- 採用人数は多い一方で志望者も集中するため倍率が高くなりやすい
- ブランド力が高く、待遇面や教育制度が整備されていることが多い
【80】トヨタ自動車(売上高世界トップクラス)
【79】三菱商事・三井物産・伊藤忠商事(総合商社)
【78】NTTグループ・イオン・ソニーグループ(グローバル大手)
SSランクは売上高1兆円超の巨大企業が中心で、知名度と安定性の高さから就職人気・採用難易度ともにトップクラスとなる。
新卒での募集枠は多いものの、全国から優秀層が集まるため選考の競争は激しい。
配属先の幅が広く、将来のキャリアパスは多様だが、自らキャリアを描く主体性も必要になる。
ネームバリューや待遇だけでなく、事業内容や働き方まで理解したうえで志望理由を固めることが重要である。
【売上高別】Sランク(就職偏差値72〜77)
売上高別の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、売上高別の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ売上高別の就職偏差値をチェックしましょう!
- 売上高5,000億円〜1兆円クラスの大手企業が中心
- 業界内で存在感のあるポジションにあり、安定性と成長性のバランスが良い
- 募集職種が幅広く、専門職から総合職まで多様な働き方が選べる
- 選考ではポテンシャルだけでなく業界理解や企業理解の深さが問われる
【77】花王・資生堂(消費財メーカー)
【75】KDDI・ソフトバンク(通信大手)
【72】大手食品メーカー・大手インフラ企業
Sランクは業界内でトップクラスのポジションを持つ売上高5,000億円〜1兆円規模の企業が中心で、安定性と挑戦の両方を求める学生に人気が高い。
選考では企業ごとの価値観やビジネスモデルへの理解度が見られやすい。
業界研究を通して他社との違いを言語化できるかが志望理由の説得力につながる。
入社後は研修制度を活用しながら専門性とビジネススキルを両立して伸ばしていくことが期待される。
【売上高別】Aランク(就職偏差値66〜71)
- 売上高1,000億円〜5,000億円クラスの中堅〜大手企業が中心
- 事業ドメインが明確で、特定分野で強みを持つ企業が多い
- 経営との距離が近く、若手のうちから裁量の大きな仕事を任されやすい
- 企業によって成長ステージや社風の違いが大きく、見極めが重要になる
【71】専門メーカー(部材・素材・ニッチトップ企業など)
【69】中堅IT企業・SaaSベンダー
【66】地域密着の中堅小売・サービス企業
Aランクは売上高1,000億円〜5,000億円規模で、特定の市場や技術で強みを発揮する企業が多く、成長性とやりがいの両方を感じやすいゾーンである。
社内の組織規模は大手ほど巨大ではないため、部門を越えた連携の機会も多い。
若手の意見が反映されやすく、実力次第で早期にプロジェクトを任されることもある。
企業ごとの戦略や市場ポジションを理解し、自分のキャリアイメージと合うかを丁寧に見極める必要がある。
【売上高別】Bランク(就職偏差値60〜65)
- 売上高300億円〜1,000億円程度の中堅企業が中心
- 経営と現場の距離が近く、意思決定のスピードが速い傾向がある
- 一人ひとりの役割が広く、兼務で複数の業務を担当することも多い
- 成長意欲のある企業では、新規事業や組織づくりにも関わりやすい
【65】中堅メーカー・ITベンチャー
【63】地域で強い専門商社・物流企業
【60】業界ニッチ領域で安定した需要を持つ企業
Bランクは売上高300億円〜1,000億円規模の中堅企業が中心で、組織の中で自分の存在感を発揮しやすい環境が多い。
大手のような分業体制ではなく、幅広い業務を経験できる点が強みとなる。
一方で仕組みが整いきっていない企業もあり、自ら動ける主体性が必要となる。
安定と成長のバランスを取りながら、自分の力で組織を変えていきたい学生に向いている。
【売上高別】Cランク(就職偏差値55〜59)
- 売上高100億円〜300億円程度の中小〜準中堅企業が中心
- 地域密着型のビジネスモデルや特定顧客に強い会社が多い
- 制度や教育は発展途上なこともあり、自ら学ぶ姿勢が求められる
- 経営者との距離が近く、意思決定に関わる機会を得られるケースもある
【59】地域密着の小売・サービス企業
【57】専門性の高いBtoB中小メーカー
【55】老舗の地場企業・家業系企業
Cランクは売上高100億円〜300億円規模の中小企業が中心で、地域や特定市場に根ざしたビジネスを展開しているケースが多い。
社員数が比較的少ないため、若手でも責任あるポジションを任されやすい。
その一方で、大企業のような研修制度や福利厚生は限定的なこともある。
企業の成長フェーズや社風を見極め、自分がどのように貢献できるかを考えることが重要となる。
【売上高別】Dランク(就職偏差値50〜54)
- 売上高100億円未満の小規模企業・スタートアップが中心
- 少人数組織で、1人が担う業務範囲が非常に広い
- 経営基盤や事業モデルが成長途上の企業も多く、変化が激しい
- 大きな裁量と引き換えに、安定性や待遇面でのリスクもある
【54】創業数年のスタートアップ
【52】家族経営に近い小規模企業
【50】地域密着の零細企業
Dランクは売上高100億円未満の小規模企業が中心で、安定性よりもチャレンジ要素を重視する学生に向いたゾーンである。
少人数のため、入社直後から実務の最前線に立つことが多い。
一方で、事業リスクや待遇のばらつきは企業ごとに大きく異なる。
経営者の考え方やビジネスモデルをよく確認し、自分の価値観と合致しているか慎重に見極める必要がある。
売上高別の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
売上高別の就職偏差値ランキングを確認することで、企業規模と採用難易度の一般的な相関関係が見えてきました。
しかし、同じ売上規模の企業であっても、所属する業界によって採用の傾向や求められる能力は大きく異なります。
これは、業界特有のビジネスモデルや市場環境が、企業の採用戦略や学生からの人気度に直結するからです。
生活に密着したBtoCの業界は高い知名度から人気が集まりやすく、BtoBの専門的な業界は、知名度こそ低くても特定の専門性を持つ学生からの志望度が高くなる傾向があります。
ここでは、主要な業界を例にとり、売上高別の偏差値ランキングから読み取れる業界ごとの採用傾向について具体的に解説していきます。
自分の志望する業界が、このランキングのどのゾーンに位置し、どのような特性を持っているのかを理解することは、今後の選考対策において非常に重要です。
安定性と人気が集中する「インフラ・金融・総合商社」の傾向
電力、ガス、鉄道などのインフラ業界や、メガバンクを筆頭とする金融業界、そして総合商社は、その事業の公共性や社会インフラとしての役割、そして圧倒的な売上高と安定した収益基盤から、SS〜Sランクに集中する傾向があります。
これらの業界は、抜群の安定性と高い待遇水準が学生に非常に人気で、採用倍率は毎年非常に高くなります。
求められる人材像は、堅実性、高いコミュニケーション能力、そして特に総合商社ではグローバルな視野とタフネスさです。
選考では、入社後のキャリアプランの明確さや、組織の中で長期的に貢献する意欲が深く問われる傾向にあります。
技術力と成長性が偏差値に反映される「メーカー(製造業)」の傾向
メーカーは、自動車、電機、化学、食品など多岐にわたりますが、SS〜Aランクまで幅広く分布しています。
売上高1兆円を超えるSSランクのメーカーは、グローバル市場での競争力を持ち、高い技術力やブランド力が就職偏差値に反映されています。
一方、AランクやBランクには、特定分野で世界的なシェアを持つ「ニッチトップ」企業や、高い専門性を持つBtoB企業が多く存在します。
これらの企業は、知名度で劣る分、「技術力」「製品力」への深い理解と、その分野に対する強い探求心が選考で重視されます。
偏差値が高いメーカーを目指す場合、その企業の「何で世界と戦っているのか」という技術や製品の核を理解することが不可欠です。
スピードと専門性で偏差値が変動する「IT・Web業界」の傾向
IT・Web業界は、比較的若い企業やベンチャーが多く、売上高だけでは測れない成長性や将来性が偏差値に影響を与える特徴があります。
SS〜Sランクには、通信キャリアや老舗の大手IT企業が安定的に位置しますが、AランクやBランクには、急成長中のSaaSベンダーや独自性の高いWebサービス企業が多く入ってきます。
これらの企業の偏差値が高くなる背景には、デジタル化の波に乗った事業の将来性と、優秀なエンジニアや企画職を求める採用難易度の高さがあります。
選考では、変化への適応力、論理的思考力、そして職種によってはプログラミングスキルなどの専門性が非常に重要視される傾向があります。
売上高別の就職偏差値が◯い理由
一般的に、企業の売上高が高ければ高いほど、それに伴って就職偏差値も高くなる傾向が見られます。
これは、売上高という数値が企業の市場での地位や規模を端的に表す指標だからです。
しかし、なぜ売上高が高い企業は、学生からの人気を集め、結果として採用難易度が上がり、就職偏差値が高くなるのでしょうか。
その背景には、企業が持つ経済的な安定性、社会的な影響力、そして提供できるキャリアの質といった、学生にとって魅力的な複数の要因が絡み合っています。
ここでは、売上高が高い企業、つまり高偏差値の企業が学生に選ばれやすい具体的な理由について掘り下げていきましょう。
これらの理由を理解することで、単に「大手だから」という漠然とした理由ではなく、自分が本当に企業に求める価値は何なのかを再確認する機会にもなります。
抜群のネームバリューと高い安定性
売上高が高い企業、特にSSランクやSランクに位置する企業は、長年にわたり大規模なビジネスを展開しているため、世間に対するネームバリューが非常に高いです。
このブランド力は、学生自身の家族や友人からの評価につながるだけでなく、将来的な転職時にも有利に働くという安心感をもたらします。
さらに、高売上高の企業は、多角的な事業展開や強固なビジネス基盤を持っているため、不況時でも経営が揺らぎにくいという高い安定性を誇ります。
学生は、人生の大きな決断である就職において、「倒産のリスクが低い」「長期的に働き続けられる」という安定性を本能的に求めるため、結果として高偏差値企業に人気が集中するのです。
整備された教育制度と充実した福利厚生
売上高の高い大企業は、組織的な余裕があり、新卒の育成に対して多額の投資を行うことができます。
具体的には、体系立てられた研修制度や、部署を横断するローテーション制度など、新入社員を一人前のビジネスパーソンに育てるための環境が手厚く整備されている点も大きな魅力です。
また、給与水準が高いだけでなく、社宅制度、医療保険、独自の休暇制度など、福利厚生が非常に充実している傾向があります。
学生は、入社後のスキルアップの機会や、安心して生活できる待遇を重視するため、これらの「人への投資」が充実している企業に魅力を感じ、結果として就職偏差値が押し上げられます。
幅広いキャリアパスと大きな仕事のスケール
売上高が高い、事業規模の大きな企業では、国内に留まらず、海外も含めた非常に大きな市場を相手にビジネスを展開する機会があります。
新卒でも、数千億円規模のプロジェクトや、社会全体に影響を与えるような規模の大きな仕事に携わるチャンスがあり、これは「やりがい」や「自己成長」を重視する学生にとって大きな魅力となります。
さらに、企業内での部署や職種の数が多く、多様なキャリアパスが存在するため、例えば営業から企画、海外事業など、入社後に自身の適性や興味に合わせてキャリアを柔軟に変更できる可能性が高いことも人気の理由です。
優秀な人材が集まる環境と切磋琢磨できる仲間
高偏差値の企業には、全国から高い志を持った優秀な学生が集まってきます。
これは、入社後にレベルの高い同僚や先輩と共に働くことができる環境を意味します。
学生は、周囲から刺激を受けながら切磋琢磨し、自身の成長を加速させたいという思いを持っています。
また、優秀な人材の層が厚いことで、企業文化として高いプロ意識や倫理観が醸成されやすく、仕事の質やスピード感も高くなる傾向があります。
単なる安定だけでなく、「成長できる環境」そのものが、高偏差値企業の大きな魅力となっているのです。
売上高別の高偏差値企業に内定するための対策
売上高が高く、就職偏差値が高い企業は、その人気と採用倍率の高さから、内定を獲得するための競争が非常に激しくなります。
これらの企業は、採用プロセスにおいても学生の能力や適性、そして入社への熱意を非常に深く見極めようとします。
したがって、漠然とした対策ではなく、選考の各段階で求められるレベル感を理解し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。
高偏差値企業への内定は決して手の届かない夢ではありません。
ここで解説する具体的な対策を実践し、他の候補者との差別化を図り、あなたのポテンシャルを最大限にアピールできるように準備していきましょう。
徹底した企業・業界研究とビジネスモデルの理解
高偏差値企業は、「なぜ競合他社ではなく、うちの会社なのか」という志望動機を非常に重視します。
そのため、単に「安定している」「有名だから」といった理由では通用しません。
対策として、業界全体のトレンド、企業独自のビジネスモデル、主要な製品・サービスが市場でどのような位置づけにあるのかを具体的に言語化できるレベルまで研究しましょう。
企業のIR情報や中期経営計画を読み込み、「この企業が抱える課題」と「それに対する自分の貢献可能性」を結びつけることが、深い企業理解を示す鍵となります。
例えば、「貴社の〇〇事業は、△△という市場課題を解決していますが、私は大学での〇〇の経験を活かし、この課題をさらに深掘りする提案をしたい」といった具体的な視点が必要です。
経験の「深さ」を追求した自己分析
高偏差値企業では、学生時代に何を「したか」よりも、その経験から何を「学んだか」「どう行動し、どう成長したか」という経験の「深さ」が問われます。
自己分析を行う際は、単なるエピソードの羅列で終わらせず、例えばアルバイトやサークル活動における「最も難しかった課題」「それを解決するために取った具体的な行動」「そこから得た教訓」といった要素を明確にしてください。
特に、困難な状況下でのリーダーシップや協調性、論理的な問題解決能力を示すエピソードは、ビジネスシーンでの再現性が高いと評価されます。
自分の強みが、その企業のどのような文化や職種で活かせるのか、企業の求める人物像と結びつけて説明できるように準備をしましょう。
論理的思考力を鍛えるグループディスカッション対策
SSランクやSランクの企業では、選考の初期段階でグループディスカッション(GD)が実施されることが多く、論理的思考力、協調性、コミュニケーション能力が複合的に試されます。
対策として、日頃からニュースやビジネスに関するトピックに対し、「賛成か反対か」「その理由」を構造立てて考える習慣をつけましょう。
GDでは、発言量よりも「議論の方向性を定めたり、停滞した議論を前に進めたりする」質の高い発言が評価されます。
フレームワーク(3C分析やSWOT分析など)の練習を重ね、本番では傾聴と提案のバランスを取りながら、建設的に議論に参加する姿勢を見せることが内定への近道となります。
企業の文化や人に合わせた面接シミュレーション
高偏差値企業の内定を獲得するためには、企業の文化や風土への「フィット感」を示すことも重要です。
OB・OG訪問を通じて、企業で働く人々の雰囲気や、社員が持つ価値観を肌で感じ取りましょう。
面接では、その企業で働くイメージを具体的に持ち、あなたのパーソナリティが企業の文化にどう貢献できるかを伝えることが効果的です。
また、質問に対してただ答えるだけでなく、「結論ファースト」で簡潔に述べた上で、「なぜそう考えるのか」という理由付けや背景を論理的に説明できるように、模擬面接を繰り返し実施し、説得力のある話し方を身につけることが大切です。
売上高別の就職偏差値に関するよくある質問
就職偏差値は、企業の採用難易度を知るための便利な指標ですが、「本当にこの数値は信頼できるのか」「自分の志望企業がランキングにない場合はどうすればいいのか」など、多くの就活生が疑問を抱えるテーマでもあります。
特に企業の売上高と結びつけて考えることで、偏差値の持つ意味合いがよりクリアになりますが、それでも個別の疑問は尽きないでしょう。
ここでは、売上高別の就職偏差値ランキングに関連して、就活生から特によく聞かれる質問に対し、就活アドバイザーとしての視点から具体的にお答えしていきます。
これらの質問と回答を通じて、就職偏差値を「参考情報の一つ」として正しく活用し、あなたの就職活動をより確かなものにしてください。
就職偏差値が低い企業は、本当に「悪い会社」なのでしょうか?
結論から言えば、就職偏差値が低いことが、企業の「優劣」を決定づけるものではありません。
就職偏差値は、あくまで学生からの人気度や採用倍率を数値化した指標であり、企業の売上高、安定性、待遇などが総合的に高いと高くなります。
しかし、偏差値が低いCランクやDランクの企業には、ニッチな市場で高いシェアを持つ優良企業、急成長中のスタートアップ、地域社会に深く貢献している企業など、独自の魅力を持つ会社が数多く存在します。
例えば、Cランクの中小企業でも、若手社員の裁量が大きく、2年目で新規事業を任されるような「成長機会」に恵まれているケースは多いです。
偏差値に惑わされず、あなたの価値観(成長性、裁量、社風など)に合っているかという視点で企業を評価することが重要です。
売上高が低くても、就職偏差値が高い企業があるのはなぜですか?
はい、売上高は低くても高偏差値となる企業は存在します。
この現象の主な理由は、「急成長性」と「専門性の高さ」です。
例えば、創業数年のITスタートアップや、特定の最先端技術を持つベンチャー企業は、売上高の規模はまだ小さくても、将来的な成長ポテンシャルや、業界を変えるイノベーションへの期待から、優秀な学生からの人気が爆発的に高まることがあります。
また、経営コンサルティングファームや外資系の投資銀行のように、採用人数が極端に少なく、選考で非常に高度な専門性や地頭を求める企業も、結果として採用難易度が上がり、高偏差値となります。
売上高は「現在の規模」を示しますが、就職偏差値には「未来への期待値」も反映されるため、このような逆転現象が起こり得るのです。
偏差値の高い企業に落ちた場合、どのように気持ちを切り替えるべきですか?
高偏差値企業からの不採用通知を受け取ると、大きなショックを受けるのは当然のことです。
しかし、そこで立ち止まるのではなく、不採用を「次の内定」のための貴重なデータとして捉え、気持ちを切り替えることが重要です。
まずは、「高偏差値企業は競争率が非常に高かった」という事実を受け入れ、自己否定に陥らないようにしましょう。
その上で、選考プロセス全体を振り返り、「自己分析のどの部分が浅かったか」「面接での論理的な説明に不足があったか」など、具体的な改善点を冷静に分析してください。
企業との相性が合わなかった、タイミングが合わなかったという要因も大いにあります。
「企業規模を少しだけ下げたBランクやAランク企業で、自分の強みが活かせる分野」に焦点を当てて再挑戦することで、すぐに内定を獲得できる可能性は高まります。
まとめ
本記事では、企業の売上高という客観的な指標を軸に、就職偏差値ランキングをSSランクからDランクまで具体的に解説し、それぞれの企業群が持つ特徴や採用傾向について深掘りしました。
就職偏差値は、企業の人気や採用難易度を知るための一つの有効な「目安」となりますが、それがあなたの就職先の良し悪しを決める絶対的な基準ではありません。
重要なのは、あなたが「何を重視して働くのか」という自己の価値観です。
SSランクの企業が持つ「安定性」や「大きな仕事のスケール」に魅力を感じる人もいれば、BランクやCランクの企業が提供する「若手からの裁量権」や「経営との距離の近さ」にやりがいを見出す人もいます。
高偏差値企業への内定を目指すには、「徹底した企業研究」と「論理的思考力を伴う自己分析」が不可欠です。
この記事で学んだ業界ごとの傾向と具体的な対策を参考に、あなたの強みとキャリアビジョンを自信を持ってアピールできるように準備を進めてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート