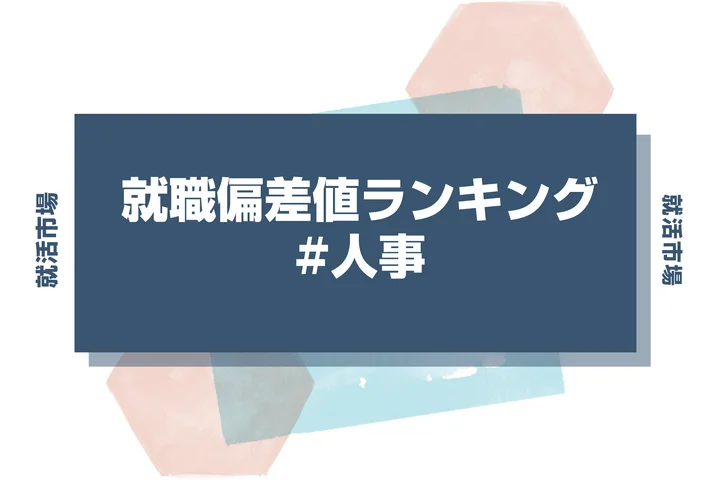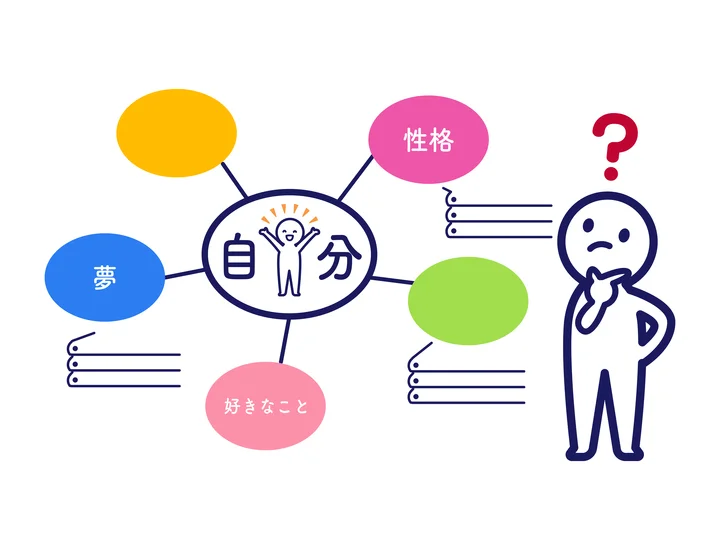目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
人事の就職偏差値ランキング
人事職は、企業の「人」に関わるすべての活動を担う、極めて重要なポジションです。
そのため、企業の規模や業界、そして任される業務範囲によって、その採用難易度、すなわち就職偏差値は大きく変動します。
一般的に、人事職の偏差値が高い企業は、単に人気が高いだけでなく、採用戦略の立案や高度な制度設計といった、経営戦略に直結する専門性の高い業務を任される傾向にあります。
特に大手企業や外資系企業、成長著しいメガベンチャーの人事部門は、企業の競争力を左右する「人財」の獲得・育成・配置を担うため、優秀な人材を求める競争も激化し、必然的に偏差値が高くなります。
このセクションでは、具体的な偏差値ランクと、そのゾーンに含まれる人事職の特徴について詳しく解説していきます。
【人事】SSランク(就職偏差値75以上)
- 外資系企業・大手上場企業の人事で、採用戦略全体の設計を任される
- データ分析・採用マーケティング・制度設計など高度な専門性が必要
- 優秀層との面接が多く、論理思考力とコミュニケーション力が必須
- 異動サイクルが速く、採用・育成・制度など幅広い領域を短期間で経験する
【80】外資系テック企業(採用・HRBP)
【78】メガベンチャー(全社採用戦略部門)
【75】大手総合商社の人事部(制度設計・採用企画)
SSランクは経営層に近い立場で人事戦略を担うため、事業理解の深さやデータ分析力が強く求められる。
単なる面接対応ではなく、採用市場の調査や人事制度の企画、社員育成の設計まで幅広く携わる。
またHRBPの役割を担う場合、事業部と並走しながら組織課題の解決に取り組むことも多い。
専門スキルの習得が必要で難易度は高いが、その分キャリア価値は非常に高いゾーンである。
【人事】Sランク(就職偏差値70〜74)
人事の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、人事の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ人事の就職偏差値をチェックしましょう!
- 大手企業や大規模ベンチャーの人事部で、採用領域を中心に担当
- 母集団形成・面接対応・イベント企画など多様な業務を経験できる
- 研修制度が整っており、成長スピードが速い
- 配属後の教育が手厚いため、新卒でも人事スキルを身につけやすい
【74】大手メーカーの人事部(採用チーム)
【72】大手IT企業(人材開発・育成領域)
【70】大手金融・インフラ企業の人事部
Sランクは大手企業の人事として、採用業務から育成、人事企画まで幅広いキャリアを積める環境が揃っている。
特に新卒向けの採用は年間スケジュールが整備されており、OJTを通じて体系的に学べる点が魅力である。
一方で人気も高く、応募者数が多いため倍率は上がりやすい。
安定した環境で専門性を磨きながらキャリアを積みたい学生に向いたゾーンといえる。
【人事】Aランク(就職偏差値65〜69)
- 中堅企業や準大手企業で、採用領域を中心に幅広く担当
- 採用広報・説明会運営・面接調整など実務が多い
- 社員との距離が近く、現場の課題を把握しやすい
- スピード感を持って業務を回す柔軟性が求められる
【69】中堅規模メーカーの人事採用担当
【67】IT中堅ベンチャーの採用担当
【65】サービス企業の採用・研修担当
Aランクは採用を中心に幅広い実務に関わるため、現場の理解を深めながらスピード感ある働き方が求められる。
募集媒体の管理、説明会やインターン企画、面接対応など業務範囲は多岐にわたる。
大手と比べ制度面は整っていない場合もあるが、その分裁量が大きく若手でも企画に挑戦しやすい。
手触り感のある人事業務を通じてキャリアを作りたい学生に適したゾーンとなる。
【人事】Bランク(就職偏差値60〜64)
- 小〜中規模企業の人事で、採用アシスタントとしてスタートすることが多い
- 説明会準備・応募者管理・面接日程調整などの事務対応が中心
- 採用広報やSNS運用など、軽めの広報業務を担当する場合もある
- まずは人事領域の入口として実務を学べる環境が多い
【64】中小企業の採用アシスタント
【62】地域密着企業の人事事務
【60】ベンチャー企業の採用サポート
Bランクは採用事務や面接調整などのサポート業務が中心で、人事領域のベーススキルを身につけたい学生に向いている。
専門性が高い業務は少ないが、人材管理システムの運用や応募者対応など基礎を学ぶには十分な環境である。
企業規模により業務範囲が広がる場合もあり、幅広い役割を担当できるケースもある。
まずは人事として経験を積みたい学生にとって、入り口として選びやすいゾーンといえる。
【人事】Cランク(就職偏差値55〜59)
- アルバイト採用や新人研修補助など、限定的な業務が中心
- 採用媒体の更新や応募者管理などの事務作業が多い
- 面接対応よりバックヤード業務がメインとなる
- 人事経験を積むステップとして利用されることが多い
【59】アルバイト採用・研修補助
【57】採用サポート専門会社の事務職
【55】人材サービス会社の内勤アシスタント
Cランクは採用補助や事務作業が中心で、人事としてのキャリアに触れる入口として選ばれやすいゾーンである。
役割は限定的だが、応募者管理や求人媒体の運用といった基本的な業務は経験できる。
将来的に採用担当や育成担当へ広げるための準備段階として活用しやすい。
事務能力を活かしながら、人事領域へゆるやかにキャリアを伸ばしたい学生に向いている。
【人事】Dランク(就職偏差値50〜54)
- データ入力や書類作成など、人事事務の中でも基礎的な業務が中心
- 応募者対応よりもバックオフィス業務に比重がある
- 人事の専門業務に触れる機会は少ない
- 未経験者でも入りやすい反面、キャリアアップには工夫が必要
【54】人事事務・データ入力
【52】中小企業のバックオフィス担当
【50】人材会社の運用アシスタント
Dランクは専門性よりも一般事務に近い業務が中心で、人事の周辺領域からキャリアを始めたい人に向いている。
応募者や社員と関わる場面は少ないが、人事システムやバックオフィスの運用を学べる環境はある。
経験を積みながら採用補助や研修運営へ広げることでキャリアアップにつなげられる。
未経験から事務スキルを磨きつつ、人事職への一歩を踏み出したい学生が選びやすいゾーンといえる。
人事の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
人事職を目指す就活生の皆さんにとって、業界によって人事部門の特性や採用難易度がどのように異なるのかを知ることは、志望企業選びの重要なヒントになります。
一概に「人事」といっても、その組織文化や求められるスキルは、属する業界のビジネスモデルや企業規模によって大きく変わってくるからです。
例えば、技術革新が速いIT業界と、安定した基盤を持つ金融業界では、採用戦略や人材育成の考え方が全く異なります。
偏差値ランキングは、そうした業界ごとの特性が採用競争率という形で反映された結果といえます。
このセクションでは、主要な業界を取り上げ、人事職の就職偏差値から読み取れる業界別の傾向と、どのような学生がフィットしやすいのかを具体的に解説していきます。
IT・Web業界の人事:変化への適応力とスピード感が求められる
IT・Web業界は、技術の進歩と市場の変化が非常に速いため、人事職の就職偏差値は総じて高い水準にあり、特に採用領域の競争が激しい傾向があります。
高い偏差値を持つメガベンチャーや大手IT企業の人事では、エンジニアやクリエイターといった専門職を迅速かつ大量に確保するための採用戦略の企画力と実行力が求められます。
単に面接を行うだけでなく、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングなど、最新の採用手法を取り入れた経験や知見が重視されるため、論理的思考力に加え、マーケットの変化に対応できる柔軟性やスピード感を持つ学生が評価されやすいです。
また、フラットな組織文化を持つ企業が多いため、年功序列ではなく実力や成果に基づいた制度設計に関わるチャンスも多く、若手でも高い専門性を身につけやすい環境といえます。
金融・インフラ業界の人事:安定した基盤と制度設計の専門性
金融(メガバンク・証券など)やインフラ(電力・ガス・鉄道など)といった伝統的な大手企業の人事部門は、全体的に安定志向の学生に人気が高く、S〜Aランクに位置する企業が多いです。
これらの業界では、何十年も働く社員のための公平で堅固な人事制度の設計・運用が主要な業務となり、高度な専門知識と、組織全体を動かす調整能力が求められます。
採用においても、企業文化やコンプライアンスを重視する傾向が強いため、組織のルールを理解し、誠実に対応できる真面目さや、高い倫理観を持った学生が内定を得やすい傾向にあります。
制度設計や労務管理といった専門性の高い領域でのキャリアを安定的に築きたいと考える学生にとって、特に魅力的な選択肢となるでしょう。
メーカー業界の人事:グローバルな視点と多様な人材マネジメント
自動車、電機、化学などの大手メーカーの人事も、SランクからAランクに位置する企業が多く、安定した人気を誇ります。
これらの企業は、国内外に多数の拠点を持ち、研究開発職、技術職、営業職など多様な職種の社員をマネジメントする複雑な人事システムを持っています。
そのため、人事部門は、グローバル化に対応するための制度改革や、技術者育成のための専門研修プログラムの企画・運用など、幅広い業務を体系的に学ぶ機会に恵まれています。
入社後に様々な部署を経験し、組織全体を見渡せる広い視野と、現場のニーズを的確に把握するヒアリング能力を培いたい学生にとって最適な環境です。
堅実さ、論理的な思考力、そして長期的な視点でキャリアを考えられる学生が求められる傾向にあります。
総合商社の人事:経営戦略と連動したタフな人財戦略
総合商社の人事職は、SSランクに位置することも多く、非常に高い就職偏差値を示します。
これは、総合商社の「人」こそが最大の資産であり、経営戦略の実現に直結する人財戦略が極めて重要視されているためです。
海外駐在者のマネジメント、M&A後の人事統合(PMI)、そして世界中で活躍できるタフで多様な人材の採用・育成など、業務は多岐にわたり、経営層に近い視点と高度な戦略性が求められます。
内定を得るためには、高いレベルのロジカルシンキング、ストレス耐性、そして何よりも事業や組織に対する強いコミットメントを示す必要があります。
タフな環境で、事業を動かす中核人材を支える醍醐味を感じたい学生にとって、最高の舞台となるでしょう。
人事の就職偏差値が高い理由
人事職の就職偏差値が高い企業が多いのには、明確な理由があります。
単に「人気があるから」という漠然とした理由だけでは、就活生が対策を立てることはできません。
人事という仕事が企業経営においてどのような役割を担い、なぜそこまで採用難易度が上がるのか、その本質を理解することが、高偏差値企業の内定に近づく第一歩です。
特にSSランクやSランクに位置する企業の人事部門は、企業の未来を左右する「人財」の調達、育成、活用の戦略を担っており、その重要性は計り知れません。
このセクションでは、人事職の採用難易度が高くなる構造的な理由と、企業が人事担当者に求める能力について、具体的な視点から掘り下げて解説していきます。
理由1:経営戦略の根幹を担う「ヒト」への影響力が大きい
人事部門は、採用、配置、評価、報酬、育成といった、企業の最も重要な資産である「ヒト」に関する全てを司る部署です。
特に高偏差値企業の人事は、単なる事務処理ではなく、経営層と連携し、事業成長のための人事戦略そのものを立案・実行します。
例えば、新規事業を成功させるための組織体制の構築、優秀な人材を引きつけるための報酬制度の設計など、その決定一つ一つが企業の未来に直結します。
そのため、企業は「ヒト」に対する影響力の大きさを理解しているからこそ、高い論理的思考力と専門性を持つ優秀な人材を採用しようとします。
結果として、競争が激化し、就職偏差値が押し上げられる構造になっています。
理由2:専門性が高く、かつ幅広い知識と経験が求められる
人事職は、採用、人材育成、人事制度企画、労務管理(法務知識も含む)など、極めて多岐にわたる専門知識を必要とします。
特にSS・Sランクの人事は、これらの領域を高いレベルで横断的に扱い、さらに「HRテック」と呼ばれるデータ分析能力まで求められるようになっています。
採用市場の動向を分析し、最適な母集団形成戦略を立てたり、従業員のエンゲージメントデータを解析して組織改善に繋げたりと、文系職種でありながらデータサイエンス的な視点も不可欠です。
このような広範な知識と高度な専門性を新卒に求めるため、選考では潜在的な学習能力や、これまでの経験から得た多角的な視点が厳しくチェックされ、内定の難易度が上がります。
3:企業文化の番人としての高い倫理観とコミュニケーション能力
人事担当者は、社員の機密情報を取り扱い、評価や昇給といった社員のキャリアを左右する重要な決定に関わります。
そのため、高い倫理観と機密保持能力、そして公平性・公正性が何よりも求められます。
また、経営層、現場社員、そして入社前の候補者といった、多様なステークホルダーと円滑にコミュニケーションを取る能力も不可欠です。
例えば、厳しい評価制度を社員に納得感を持って伝える、事業部のリーダーの組織課題の相談に乗るなど、高度な対人スキルと感情のコントロールが常に求められます。
このような「人」と「組織」の間に立って、中立的な立場で問題を解決する能力の高さが、選考を通じて厳しく見極められるため、偏差値が高くなるのです。
人事の高偏差値企業に内定するための対策
人事職の中でも、特に就職偏差値が高いSS・Sランクの企業への内定を目指すには、一般的な就活対策以上の戦略的な準備が必要です。
単に「人が好き」という志望動機や、「縁の下の力持ちになりたい」といった漠然とした目標だけでは、厳しい選考を突破することはできません。
高偏差値企業の人事部門は、将来の経営戦略を担えるレベルのポテンシャルを持った人材を求めています。
そのため、選考プロセスでは、人事領域への深い理解、論理的な問題解決能力、そして企業文化へのフィット感が徹底的に試されます。
このセクションでは、皆さんが高偏差値企業の人事職に内定を掴むために、具体的に何をすべきかを、対策ステップに沿って解説します。
対策1:HR領域の専門知識とトレンドを徹底的にインプットする
高偏差値企業の人事では、入社直後から「なぜこの制度が必要なのか」「どうすれば採用力が上がるのか」といった戦略的な議論に参加することが期待されます。
そのため、人事の機能(採用、育成、制度設計、労務など)を理解するだけでなく、最新のHRトレンドを把握しておくことが必須です。
具体的には、「HRBP(HRビジネスパートナー)」「タレントマネジメント」「エンゲージメント」といった専門用語の意味を理解し、「なぜ今その考え方が重要なのか」を自分の言葉で説明できるようにしましょう。
例えば、「貴社で今後進めるべき採用ブランディング戦略」など、具体的な施策について提案できるレベルまで、知識を深めることが重要です。
対策2:論理的思考力と課題解決能力を具体的な経験で示す
高偏差値の人事職の選考では、ESや面接で「学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)」を問う際も、単なる努力や成果だけでなく、そのプロセスで発揮した論理的思考力と課題解決能力が厳しく評価されます。
例えば、サークル活動のリーダー経験を語るにしても、「目標達成のために、まず現状をデータで分析し、ボトルネックを特定、その上で具体的な施策を立案し、実行した」という一連の論理的な流れを明確に伝えましょう。
「この課題に対してどのようなフレームワークでアプローチしたか」を説明することで、入社後も複雑な組織課題に対応できるポテンシャルを示すことができます。
対策3:企業文化への深い理解と「フィット感」をアピールする
人事の仕事は、その企業の文化や価値観を体現し、社内外に伝えていく役割も担っています。
そのため、高偏差値企業は、「どれだけ自社のカルチャーにフィットし、それを推進できるか」を非常に重視します。
OB・OG訪問を通じて、社員の方々の働く姿勢、行動規範、そして会社の雰囲気を肌で感じ取り、「なぜ自分は、この会社のこの文化の中で、人事をやりたいのか」を具体的に言語化しましょう。
例えば、「貴社の『挑戦を奨励する文化』は、私の考える人事の理想像(失敗を恐れず新しい採用手法を試すこと)と完全に合致しています」のように、企業文化と自身の価値観を結びつけた独自の志望動機を構築することが、内定を勝ち取る鍵となります。
対策4:人事業務を意識した長期インターンシップへの参加
書類選考や面接で「人事としての具体的な業務理解度」を示すためには、実際に人事業務を経験するのが最も効果的です。
特に採用領域や研修サポートに携われる長期インターンシップへの参加を強く推奨します。
短期のインターンでは得られない、年間を通じて採用活動がどのように進むのかという全体像や、応募者管理の難しさ、社員とのコミュニケーションの取り方といった「リアルな人事の仕事」を経験することで、ESや面接での発言に説得力が増します。
実践的な経験は、高偏差値企業が求める専門性への意欲を示す最も強力な証拠となるでしょう。
人事の就職偏差値に関するよくある質問
人事職の就職偏差値やキャリアパスに関する疑問は、就活生から非常によく寄せられます。
特に、「専門職」としての人事を目指すからこそ、「未経験で本当に大丈夫なのか」「将来的にどのくらい給料がもらえるのか」といった、具体的な不安を抱える人も多いでしょう。
偏差値が高い企業ほど、選考プロセスも複雑になり、情報も限定的になりがちです。
ここでは、人事職を目指す皆さんが抱きやすい就職偏差値やキャリアに関する具体的な質問に、就活アドバイザーの視点からお答えしていきます。
これらの情報を参考に、皆さんの人事職就活における不安解消と次のアクションに繋げてください。
質問1:新卒で人事職に就くために、大学で何を専攻すべきですか?
結論から言うと、特定の学部学科が必須ではありません。
法学部(労務・コンプライアンス)、経済学部・経営学部(制度設計・組織論)、心理学部(人材開発・モチベーション)などは有利に働く場合もありますが、高偏差値企業の人事職は、それ以上に「ロジカルシンキング」「コミュニケーション能力」「企業や事業への関心」といったポータブルスキルを重視します。
実際に、SS・Sランク企業の人事部門には、文理問わず多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。
重要なのは、専攻分野で培った「学びの深さ」や「問題解決のアプローチ」を、人事業務にどう活かせるかを明確に説明できることです。
例えば、理系出身であれば「実験で培ったデータ分析能力で、採用プロセスを科学的に改善したい」といったアピールが有効です。
質問2:就職偏差値が高い企業の人事と低い企業の人事では、仕事内容は具体的にどう違いますか?
就職偏差値が高い企業の人事(SS〜Sランク)は、「戦略人事」の傾向が強く、採用戦略の企画、高度な人事制度の設計、経営層への提言など、経営に近い上流工程の仕事が中心となります。
一方で、就職偏差値が低い企業の人事(C〜Dランク)は、「管理・事務人事」の傾向が強く、データ入力、給与計算、面接の日程調整、研修補助といった定型的なルーティンワークや事務作業が中心になることが多いです。
高偏差値企業ほど、業務に裁量と専門性が伴い、若手でも企画立案に携われる機会が増えるため、仕事の難易度とやりがいが大きく異なります。
質問3:高偏差値企業の人事部門は、激務になりやすいのでしょうか?
人事部門は、企業の採用活動や制度運用に直結するため、繁忙期には一時的に激務になることがあります。
例えば、新卒採用の本格スタート時期、期末の評価・昇給シーズン、大規模な制度変更の準備期間などは、残業が増える傾向にあります。
特にSSランクの外資系やメガベンチャーでは、スピード感が求められるため、プロジェクトの進捗によっては高い負荷がかかることもあり得ます。
しかし、大手企業やSランク以上の企業では、近年働き方改革やHRテックの導入により、業務効率化が進んでいる企業も多く、一概に激務とは言えません。
内定前にOB・OG訪問などで、具体的な繁忙期や年間スケジュールを聞き、現実的な労働環境を把握することが大切です。
質問4:将来的に人事としてキャリアアップするために、新卒で重視すべき点は何ですか?
人事としてキャリアアップを目指すなら、新卒で入社する企業を選ぶ際に「業務の専門性と裁量権」を重視すべきです。
具体的には、「採用」や「制度設計」といった特定の専門領域に、若手のうちから深く関われる環境を選ぶと良いでしょう。
単なる事務作業に留まらず、「なぜそうするのか」という戦略的な思考を求められる企業で働くことが、将来的にHRBPや人事コンサルタントといったキャリアに進むための土台となります。
また、研修制度が整っているか、異動で幅広い人事業務を経験できるかなど、体系的なスキルアップをサポートする体制が整っているかも重要なチェックポイントです。
まとめ
本記事では、「人事」という職種に焦点を当て、その就職偏差値ランキングの構造から、高偏差値企業に内定するための具体的な対策までを詳しく解説しました。
人事職の偏差値が高いのは、単に人気があるからではなく、企業の「ヒト」に関する戦略を担うという、極めて経営に直結した重要な役割があるためです。
SSランクやSランクといった高偏差値企業の人事部門は、高い専門性と論理的思考力、そして企業文化を推進する情熱を持った学生を求めています。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート