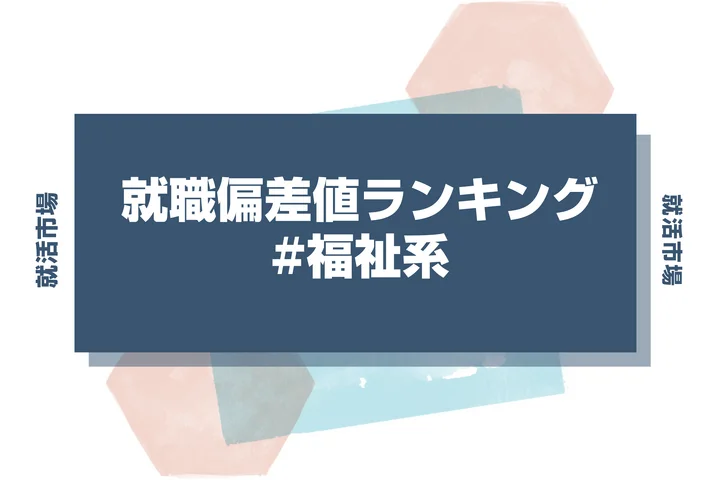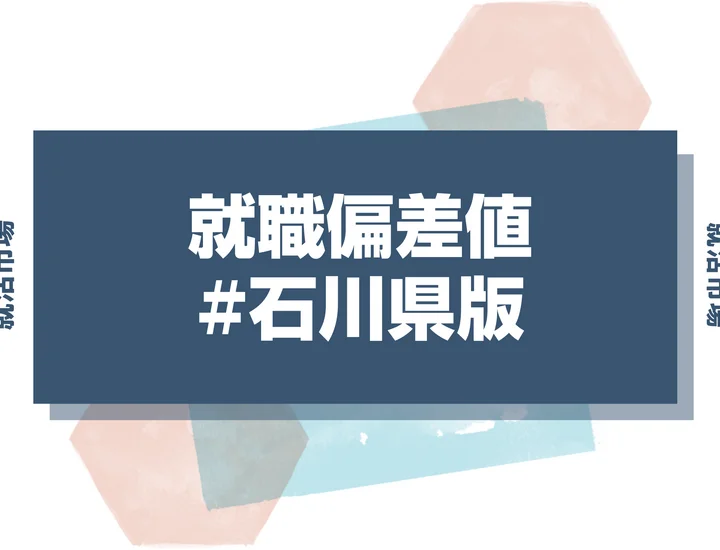目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
企業の人気や採用難易度を偏差値形式で数値化した指標です。
学生の間での志望度、企業の採用倍率、業界での地位などを総合的に加味して算出されます。
特に人気企業や大手企業ほど高い数値となる傾向があり、毎年注目されています。
就職先を選ぶ際の目安として活用されることが多いですが、あくまで参考指標のひとつに過ぎません。
福祉系の就職偏差値ランキング
福祉系の就職偏差値は、一般企業とは異なる特徴があります。
その最たるものが、「資格の有無」と「公的機関」の強さです。
ランキング上位には、安定した待遇と高い専門性が求められる地方自治体の福祉職や児童相談所、公立の相談支援センターなどの公的機関やそれに準じる機関が並びます。
これらの職種は、採用枠が限られている上に、専門資格や高度なケースワーク能力が求められるため、自ずと難易度が上がり高偏差値となる傾向があります。
一方で、介護・生活支援を中心とする民間施設は、採用の門戸が広い分、偏差値は中程度に位置づけられます。
しかし、これは「入りやすい」という意味合いが強く、現場での専門性やキャリアアップの可能性が低いわけではありません。
福祉職は専門性の領域が広いため、目指すキャリアによって偏差値の捉え方が変わる点に注意が必要です。
まずは自分がどのような分野で、どのような支援に携わりたいのかを明確にすることが、偏差値にとらわれずに最適な就職先を見つけるための第一歩となるでしょう。
【福祉系】SSランク(就職偏差値72以上)
- 行政系の福祉職として採用され、専門資格と高い判断力が求められる
- 生活困窮、児童虐待、障害支援など高度なケースワークに対応
- 法律・制度の深い理解が必須で、責任の重さも大きい
- 倍率が高く、筆記試験・論文・人物評価の総合力が求められる
【75】地方自治体の福祉職(市役所・県庁)
【74】児童相談所(児相)
【72】公立障害者支援センター(相談支援専門員)
SSランクは行政系を中心とした高度専門職で、採用倍率の高さと求められる専門性が就職難度を押し上げている。
ケース対応では判断力や法制度の理解が求められ、責任を伴う。
待遇や安定性が高いため学生人気が強く、毎年競争率が高い。
社会福祉士や精神保健福祉士を志す学生の最難関領域といえる。
【福祉系】Sランク(就職偏差値68〜71)
福祉系の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、福祉系の就職偏差値ランキングをはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。
会員登録をして今すぐ福祉系の就職偏差値をチェックしましょう!
- 社会福祉法人や医療法人で相談支援を担う専門職
- 病院・地域包括支援センターで多職種連携を行う
- 利用者への計画作成、関係機関との調整など高度なスキルが必要
- 資格必須の求人が多く、総合力が評価されやすい
【71】地域包括支援センター(主任ケアマネ補助)
【69】医療ソーシャルワーカー(総合病院)
【68】社会福祉法人の相談支援専門員
Sランクは相談支援や計画作成など専門性の高い業務が中心で、多職種との連携調整力が評価の鍵となる。
病院や地域包括などの中核機関で働くため、対応領域が広い。
利用者の課題を把握し、解決策を導く力が特に重視される。
資格を活かしつつ専門職としてキャリアを構築したい学生向けの層である。
【福祉系】Aランク(就職偏差値63〜67)
- 福祉施設の支援員として生活支援や個別支援計画に関わる
- 障害・高齢・児童分野で現場の中心として働く
- チームケアの中で観察力やコミュニケーション力が求められる
- 資格加点はあるが、未経験でも採用されやすい幅広い求人がある
【67】障害者支援施設(生活支援員)
【65】児童養護施設(指導員)
【63】高齢者福祉施設(介護職兼務支援員)
Aランクは現場の支援員として生活支援・個別支援を担い、利用者との関わりを深く持ちながら働ける点が特徴である。
支援計画に関わる機会もあり、福祉の基礎を学ぶには最適な環境である。
資格の有無にかかわらず採用の門戸が広く、多様な人材が活躍している。
福祉の現場経験を積みたい学生に人気が高い領域である。
【福祉系】Bランク(就職偏差値58〜62)
- 高齢者施設・障害者施設での生活支援が中心業務
- 医療行為は少なく、生活全般のサポートが中心
- シフト勤務が多いが、職場によって働きやすさは高い
- 未経験採用が多く、チームワークが重視される
【62】特別養護老人ホーム
【60】グループホーム・小規模多機能型施設
【58】デイサービス(通所介護)
Bランクは生活支援が中心で、福祉業界の入り口として多くの人が挑戦しやすい層である。
利用者と日常的に関わり、信頼関係を築く経験が積める。
身体介助を行う場面もあるため、体力や観察力が求められる。
福祉の現場を基礎から経験したい学生に向いている。
【福祉系】Cランク(就職偏差値53〜57)
- 福祉事務やサポート業務が中心で専門性が比較的低い
- 送迎・事務補助・簡単な支援など幅広いサポートを担当
- 日勤中心の職場が多く働きやすい
- 資格がなくても応募できる求人が多い
【57】相談支援補助(事務中心)
【55】デイサービス事務職
【53】障害福祉サービスの事務補助
Cランクは専門性よりもサポート能力が重視され、働きやすさを重視する学生に人気がある。
生活支援の補助や書類対応が中心で、身体介助は少ない。
福祉の現場を身近に感じながら負担を抑えて働ける点が魅力である。
未経験で福祉業界に入る入口としても最適なポジションである。
【福祉系】Dランク(就職偏差値50〜52)
- 軽作業・送迎・見守りなど専門性の低い業務が中心
- 資格不要で採用されやすい職場が多い
- 責任範囲は限られ、サポート的な役割が中心
- キャリアアップよりも働きやすさ重視の職場が多い
【52】見守りスタッフ(高齢者施設)
【51】送迎ドライバー(デイサービス)
【50】事務補助・生活サポートスタッフ
Dランクは専門スキルが必要ない業務が中心で、初めて福祉の現場に触れる学生が挑戦しやすい。
責任範囲は限定的で負担が少ないため、短時間勤務や柔軟な働き方が可能である。
まずは働きやすい職場で福祉の雰囲気を知りたい層に適している。
本格的な専門職へ進む場合は後から資格取得が必要になる。
福祉系の就職偏差値ランキングから見る業界別の傾向
福祉系の就職偏差値ランキングを分析すると、一般的な民間企業のランキングとは異なる、この業界特有の傾向が見えてきます。
それは、「公的な安定性」と「専門性の高さ」が偏差値を決定づける大きな要因となっている点です。
単に企業の規模が大きいから偏差値が高いというわけではなく、その仕事が持つ社会的な責任の重さや、必要とされる専門資格、そして制度的な安定性が強く反映されています。
この傾向を理解することは、福祉系企業への就職を目指す上で、自分の目指すキャリアと照らし合わせ、適切な企業選びをする上で非常に重要です。
公務員系(行政職・公的機関)は専門性と安定性で最上位
就職偏差値のSSランク〜Sランクの上位を占めるのは、地方自治体の福祉職や児童相談所、公立の相談支援センターなどの公的機関です。
これらの職種は、公務員としての安定した身分と待遇に加え、生活困窮者支援や児童虐待対応など、極めて高度な専門知識と判断力が求められます。
特に地方公務員の採用試験は、筆記試験、論文、面接のすべてにおいて高いレベルの総合力が問われるため、採用難易度が最も高くなっています。
また、福祉系公務員は行政の窓口として福祉サービス全体をコーディネートする役割も担うため、社会的な影響力も大きく、学生からの人気も非常に高いのが特徴です。
医療・地域包括系は多職種連携能力が求められる
SランクからAランクにかけては、医療ソーシャルワーカー(MSW)や地域包括支援センターの相談員といった、病院や地域の中核施設で多職種連携を担う専門職が位置しています。
これらの仕事は、医師や看護師、ケアマネジャーなど、さまざまな専門職と協力しながら、利用者の抱える複合的な課題を解決に導く役割です。
そのため、単に福祉の知識だけでなく、コミュニケーション能力や調整力、そして問題解決能力が特に重視されます。
社会福祉士などの専門資格が必須とされるケースが多く、専門性に加えてチームワークを重んじる姿勢が採用においては評価されます。
施設支援系(生活支援・介護)は現場での実践力が評価軸
AランクからBランクにかけては、特別養護老人ホームや障害者支援施設、児童養護施設といった現場での生活支援・個別支援を担う職員が中心です。
これらの施設は、利用者と日常的に深く関わり、その人の生活全体を支えることが仕事であり、共感力や観察力、そして日々の体調や変化に気づく実践的な力が求められます。
資格の有無よりも、福祉への熱意や利用者への接し方、チームでの協調性が採用において重要視される傾向があります。
特に、施設規模が大きく、研修制度が整っている社会福祉法人などは学生からの人気も高く、Aランクに位置することが多いです。
サポート・事務系は働きやすさが主な魅力
CランクからDランクは、デイサービスの送迎ドライバーや福祉施設の事務補助など、専門的な対人援助よりもサポート業務や事務作業が中心の職種です。
これらの職種は、専門資格が不要である場合が多く、福祉業界への入り口として比較的挑戦しやすいポジションです。
また、夜勤や身体介助が少ないため、ワークライフバランスや働きやすさを重視する学生に人気が集まる傾向があります。
キャリアアップを目指す場合は、働きながら上位の専門資格を取得することが次のステップとなるでしょう。
福祉系の就職偏差値が高い理由
福祉系の就職偏差値が高い背景には、一般的な企業選びの基準に加えて、「公的役割」と「専門性」という福祉業界特有の要因が深く関わっています。
多くの学生が安定や高い専門性を求める一方で、その職に就くための門戸が狭く、採用競争が激しくなっていることが、偏差値を押し上げる主な理由です。
福祉業界特有の事情を理解することで、なぜその企業や職種が人気なのか、そしてそこを目指すためにどのような準備が必要なのかを明確にすることができます。
行政・公的機関の高い人気と採用枠の少なさ
SSランクやSランクの上位に位置する地方自治体の福祉職や公的機関は、公務員としての給与や福利厚生の安定性から、多くの学生の志望度が高いことが偏差値が高い最大の理由の一つです。
しかし、その採用枠は民間企業と比較して非常に少なく、倍率は数十倍になることも珍しくありません。
また、採用試験では、専門知識を問う筆記試験や、高度な論理的思考力を試す論文試験が課されるため、民間企業の選考とは異なる、徹底した受験対策が必要になります。
結果として、競争が激化し、必然的に偏差値が高くなります。
資格取得の難易度と専門職の需要の高さ
福祉系の高偏差値の職種、特に相談援助系の仕事(社会福祉士、精神保健福祉士など)は、難易度の高い国家資格が必須、または強く推奨されます。
これらの資格は、大学での専門課程の履修と、高い合格率の試験を突破することが求められ、資格取得自体が高い専門性を示す指標となります。
企業や施設側も、これらの専門資格を持つ人材を中核として採用したいと考えるため、採用の際も資格取得者や取得見込み者に人気が集中し、結果として求職者間での競争率が上がり、偏差値が高くなります。
社会的責任の重さと業務の公共性の高さ
福祉の仕事は、人々の生活や生命に深く関わるものであり、特に児童虐待対応や生活困窮者支援など、社会的な責任が非常に重い業務が多く含まれます。
このような高い公共性と責任を担う仕事であるため、採用側も学生に対して、単なるスキルだけでなく、倫理観や使命感、そしてストレス耐性といった人間的な資質を厳しく見極めます。
この選考の厳しさが、採用のハードルを上げ、就職偏差値を押し上げる要因の一つとなっています。
キャリアパスの明確さと専門職としての成長性
高偏差値の職種は、キャリアパスが比較的明確であることも魅力の一つです。
例えば、行政の福祉職であれば、部署異動を通じて多様な福祉分野を経験し、管理職へと昇進していく道筋があります。
また、医療ソーシャルワーカーであれば、病院内で専門性を深めながらチーム医療の中心的な役割を担うことができます。
このように、長期的な成長と安定が見込めるため、自身のキャリアを慎重に考える優秀な学生からの応募が集まりやすく、結果として競争が激しくなります。
福祉系の高偏差値企業に内定するための対策
福祉系の高偏差値企業や公的機関の内定を勝ち取るためには、一般的な就職活動対策に加えて、「専門性」と「人間性」の両面を磨き上げる必要があります。
これらの企業は、単に知識があるだけでなく、「福祉の現場でどう活かせるか」「利用者や多職種とどう関わるか」という実践的な視点を重視します。
そのため、表面的な対策ではなく、自身の福祉への熱意と、それを裏付ける具体的な行動や経験を示すことが内定への鍵となります。
専門資格の早期取得と活用経験の明示
SSランクやSランクの企業・職種を目指すのであれば、社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格の取得は必須級の対策です。
特に地方公務員系の福祉職では、資格の有無が採用の前提となることも少なくありません。
また、資格を取得するだけでなく、大学の実習やボランティア活動を通じて、学んだ専門知識を現場でどう応用したかを具体的に語れるように準備しましょう。
単に「資格を持っている」ではなく、「この資格を活かして、〇〇な課題解決に貢献したい」といった具体的なビジョンを示すことが重要です。
公務員試験・筆記試験対策を徹底する
行政系の福祉職(市役所・県庁など)は、公務員試験という独自の採用プロセスを経ます。
この試験では、福祉の専門科目だけでなく、教養科目や時事問題、そして論述試験が課されます。
民間企業の選考と並行して対策を行うのは非常に負担が大きいですが、早めに計画を立てて専門学校の講座を活用したり、過去問を徹底的に分析したりする対策が不可欠です。
福祉系公務員は安定志向の学生が多く集まるため、筆記試験での高得点が一次選考通過の絶対条件となります。
質の高い実習経験とそれを言語化する訓練
福祉系の採用では、大学時代の実習経験が最も重要な評価ポイントの一つになります。
実習で「何を学び、何を考え、どのように行動したか」を深く掘り下げておく必要があります。
面接では、「実習中に直面した困難と、それをどう乗り越えたか」「チームの中でどのような役割を果たしたか」といった、実践的な思考力と対人スキルを問う質問が多く投げかけられます。
実習日誌を見返し、自分の行動と思考のプロセスを整理し、具体的で感情が伝わる言葉で表現できるように訓練しましょう。
企業・職種研究に基づく強い志望動機の構築
「福祉に貢献したい」という抽象的な志望動機では、高偏差値企業の内定は得られません。
目指す企業や職種が、福祉サービスの中でどのような役割を担い、どのような理念を持っているのかを深く理解し、「なぜ、この法人・この職種でなければならないのか」を明確にすることが必要です。
例えば、児童養護施設であれば「なぜ施設支援ではなく、行政の児童相談所なのか」といった、職種間の違いを理解した上での志望理由を語れるようにしましょう。
説明会への参加やOB・OG訪問を通じて得た具体的なエピソードを交えることで、あなたの熱意と本気度を伝えることができます。
福祉系の就職偏差値に関するよくある質問
就職活動を進める中で、福祉系の就職偏差値について、多くの学生が抱える疑問や誤解があります。
福祉業界の特殊性から、一般的な民間企業とは異なる視点が必要となるため、これらの疑問を事前に解消しておくことは、適切な企業選びと対策を進める上で非常に重要です。
偏差値はあくまで一つの指標であり、あなたが福祉の仕事に求める価値観と、企業の提供する環境が合致しているかを冷静に見極めることが成功への近道となります。
「偏差値が低い=ブラック企業」ということですか?
一概に「偏差値が低い=ブラック企業」とは言えません。
福祉系の就職偏差値は、主に採用の難易度や人気度、そして公的安定性を反映しています。
例えば、デイサービスや一部の高齢者施設(C・Dランク)は、大規模な公的機関と比較して採用の門戸が広いため偏差値は低くなりますが、これは人手が不足している分野であるという事情も大きく関わっています。
小規模でも、利用者と密接に関われるアットホームな職場で、質の高いサービスを提供している法人は数多く存在します。
大切なのは、偏差値の数字に惑わされず、「その法人の離職率、給与水準、研修制度、そして現場の雰囲気」を個別に確認することです。
資格なしで高偏差値の企業に入社することは可能ですか?
一部の例外を除き、非常に難しいのが現状です。
特にSSランクの行政系福祉職やSランクの医療ソーシャルワーカーなどの専門職は、採用要件として社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を必須としている場合がほとんどです。
これらは「資格があってこそ初めて高度な専門業務に従事できる」という職種であるためです。
ただし、福祉系の法人の中には、新卒を総合職として採用し、入社後に資格取得を全面的にサポートする制度を設けている企業もあります。
資格がない場合は、まずはそうしたサポート体制が充実した法人を探し、入社後にスキルアップを目指すキャリアプランを志望動機で示すことが現実的です。
施設支援と相談支援、どちらがキャリアアップしやすいですか?
これは目指すキャリアの方向性によって答えが異なります。
施設支援員(A・Bランク)は、現場での生活支援を通じて利用者一人ひとりの生活に寄り添う実践力が身につき、将来は施設の管理者やリーダー職を目指すキャリアパスが一般的です。
一方、相談支援専門員(SS・Sランク)は、制度や法律に基づき、多職種連携をコーディネートする高度な専門知識が求められ、将来は地域包括支援センターや行政での専門職、独立した相談支援事業所の立ち上げなど、より専門的な分野での活躍が期待されます。
どちらもキャリアアップは可能ですが、あなたが「現場での直接支援」と「制度的な側面からの調整」のどちらに魅力を感じるかで、選ぶべき道が変わってきます。
就職偏差値のランキングはどこで確認できますか?
就職偏差値のランキングは、実は公式に発表されているものではなく、主に就職情報サイトや就活コミュニティ、匿名掲示板など、学生間の口コミや投票に基づいて作成された非公式の指標です。
そのため、情報源によって数値が異なる場合や、情報の信頼性にばらつきがあることに注意が必要です。
就活市場のようなメディアで公開されるランキングは、多くの情報を集約・分析していますが、あくまで「学生からの人気」や「採用難易度」を相対的に示したものとして捉え、鵜呑みにしないことが重要です。
参考程度に留め、必ずご自身で企業の採用情報や説明会、口コミサイトなどを多角的にチェックすることをおすすめします。
まとめ
本記事では、福祉系の就職偏差値ランキングを深く掘り下げ、ランキング上位の企業がなぜ高偏差値となるのか、そしてそこに内定するための具体的な対策について解説しました。
福祉系の就職偏差値は、「公的機関の安定性」や「高度な専門資格の有無」といった、この業界特有の要因によって大きく左右されることがお分かりいただけたかと思います。
SS〜Sランクの企業・職種は、公務員試験対策や国家資格の取得といった、非常にハイレベルな専門対策が必須となります。
一方で、A〜Dランクの施設や事業所でも、利用者と深く関わる実践的な支援経験を積むことができ、福祉の基礎を固める上で非常に価値のあるキャリアパスが用意されています。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート