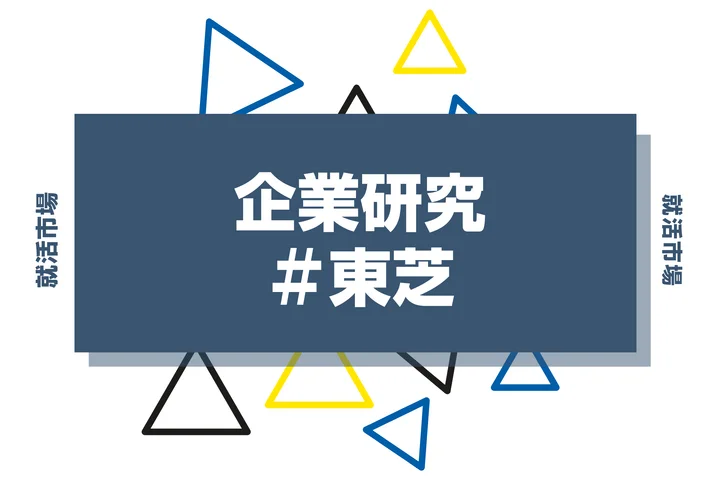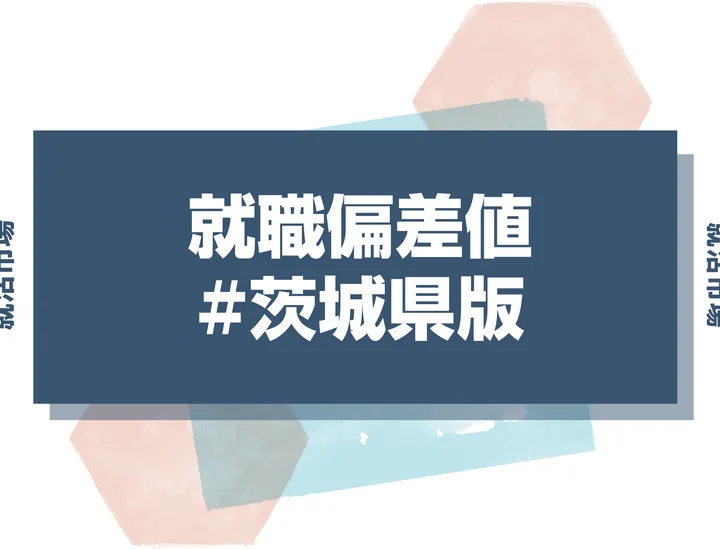はじめに
日本を代表する大企業の一つですが、「具体的になんの会社なのか、どんな仕事をしているのかよく分からない…」と悩む就活生も少なくありません。
この記事では、そんな皆さんの疑問を解消し、東芝の企業研究から選考対策までを徹底的に解説します。
この記事を読めば、東芝の「今」が分かり、自信を持って選考に臨めるようになります。
【東芝はなんの会社】東芝はどんな会社なのか
東芝は、140年以上の歴史を持つ、日本を代表する「総合電機メーカー」です。
かつてはテレビやパソコンなどの家電(BtoC)でも有名でしたが、現在は事業構造を大きく変え、主に社会インフラやエネルギー、半導体といった、社会の基盤を支えるBtoB(企業向け)事業に注力しています。
具体的には、発電所などのエネルギーシステム、鉄道や上下水道などの社会インフラシステム、そしてEV(電気自動車)や産業機器の省エネに不可欠な「パワー半導体」などが現在の主力です。
「人と、地球の、明日のために。
」 というスローガンを掲げ、最先端の技術で世界中の社会課題解決に取り組んでいる企業、と理解すると良いでしょう。
【東芝はなんの会社】東芝の仕事内容
「総合電機メーカー」と聞いても、事業領域が広すぎて、入社後にどんな仕事をするのか具体的にイメージしにくいかもしれませんね。
東芝は、社会の基盤を支える大規模なシステムから、最先端の電子デバイスまで、非常に多岐にわたる製品やサービスを提供しています。
そのため、そこで働く社員の仕事内容も実に多様です。
皆さんの専攻や興味が、どの分野で活かせるのかを想像しながら読み進めてみてください。
ここでは、東芝を支える代表的な職種を「技術系」と「事務系」に分けて、それぞれの具体的な仕事内容とやりがいを紹介していきます。
自分が将来どのように活躍したいか、その解像度を上げるヒントがきっと見つかるはずです。
東芝という大きな舞台で、あなたの力がどのように社会に貢献できるかを考えてみましょう。
技術系(研究開発・設計)
東芝のイノベーションを最前線で支えるのが、研究開発(R&D)と設計の仕事です。
研究開発部門では、数年後、数十年後を見据えた最先端技術(例えば、量子技術や次世代のAIなど)の基礎研究や、既存技術を応用した新製品・新サービスの開発を行います。
一方、設計部門では、お客様のニーズや仕様に基づき、製品(例えば発電所のタービンやパワー半導体)の具体的な構造や機能、性能を決定し、図面や仕様書を作成します。
どちらも、世の中にまだない価値を生み出すという大きなやりがいがあります。
この仕事には、自身の専門分野に関する深い知識はもちろん、課題を発見し、粘り強く解決策を探求する論理的思考力と探究心が不可欠です。
社会の課題を自らの技術で解決したいという強い情熱を持つ人に向いている職種です。
技術系(生産技術・品質保証)
製品を生み出す「研究開発・設計」があれば、それを高品質かつ効率的に「製造」するプロセスも欠かせません。
生産技術は、いわば工場の「頭脳」です。
設計図面を基に、どのような設備や工程で製品を作れば、最も効率的で高品質なモノづくりができるかを考え、製造ラインを構築・改善していく仕事です。
海外工場との連携も多く、グローバルな視点も求められます。
一方、品質保証は、完成した製品が社内や法的な基準をクリアしているか、そして何よりお客様が満足する品質であるかを厳しくチェックし、保証する役割を担います。
東芝が扱う製品は、社会インフラなど人々の安全に直結するものが多いため、品質保証は会社の信頼を守る「最後の砦」とも言えます。
モノづくり全体を最適化したい人や、高い責任感を持って製品の安全を守りたい人にとって、非常に重要な仕事です。
事務系(営業・マーケティング)
事務系の花形とも言えるのが営業・マーケティングです。
東芝の営業は、BtoB(企業向け)が中心で、扱う商材は発電所や鉄道システム、半導体デバイスなど非常に大規模なものが多いのが特徴です。
単に製品を売るのではなく、顧客企業や官公庁が抱える課題(例:「工場の消費電力を減らしたい」「安定した電力供給システムを構築したい」)をヒアリングし、自社の技術や製品を組み合わせて解決策を提案する「ソリューション営業」が主体です。
そのため、顧客の懐に深く入り込む関係構築力と、技術部門と連携して最適な提案を練り上げる調整能力が求められます。
マーケティング部門では、市場のニーズを分析し、将来的にどんな製品やサービスが求められるかを予測し、新事業の企画や既存製品の販売戦略を立案します。
文系であっても、世の中の最先端技術に触れながらダイナミックなビジネスを動かしたい人に最適です。
事務系(企画・管理部門)
会社全体の運営を支え、舵取りを行うのが企画・管理部門(コーポレート部門)です。
具体的には、会社全体の中長期的な戦略を練る「経営企画」、事業活動に必要な資金を管理・調達する「財務・経理」、契約書のチェックやコンプライアンスを担う「法務」、そして「人」に関わる全て(採用、育成、制度設計)を担当する「人事」などがあります。
これらの部門は、直接製品を作ったり売ったりするわけではありませんが、会社という組織がスムーズかつ健全に機能するために不可欠な存在です。
例えば、人事は「求める人物像」で後述するような、東芝の変革を担う人材を採用・育成する重要な役割を担います。
広い視野を持って会社全体を支えたい、あるいは特定の分野(財務、法務、人事など)で高度な専門性を身につけて貢献したいという人に向いています。
【東芝はなんの会社】東芝が選ばれる理由と競合比較
総合電機メーカー業界には、日立製作所や三菱電機といった強力なライバルが多数存在します。
その中で、就活生が「なぜ東芝を選ぶのか」を明確に語ることは、志望動機を作成する上で非常に重要です。
面接でも「なぜうち(東芝)なの?」という質問は必ず聞かれるでしょう。
そのためには、東芝が持つ独自の強みや特徴を深く理解し、競合他社と何が違うのかを自分なりに整理しておく必要があります。
東芝は近年、事業の選択と集中を進めており、その事業ポートフォリオ(事業の組み合わせ)にも特徴が出ています。
ここでは、東芝ならではの優位性はどこにあるのか、そして主要な競合他社とどう異なるのかを比較しながら解説していきます。
強み:社会インフラを支える技術力
東芝の最大の強みは、なんといっても長年にわたり培ってきた社会インフラ分野での高い技術力と実績です。
特に、火力・水力・地熱などの発電システムや、電力を安定供給するための送配電システムといった「エネルギー事業」は、国内外で高いシェアを誇ります。
また、鉄道の運行システムや上下水道の水処理プラント、ビルの管理システムなど、私たちの生活に欠かせない公共インフラも幅広く手掛けています。
これらの事業は、一度導入されると数十年単位で使われ続けるため、高い信頼性と長期的な運用・保守ノウハウが求められます。
社会貢献性が非常に高く、人々の生活基盤を根底から支えているという実感を得やすいのが、東芝で働く大きな魅力の一つと言えるでしょう。
強み:パワー半導体や量子技術への注力
歴史あるインフラ技術だけでなく、未来を切り開く最先端技術へ積極的に投資している点も東芝の強みです。
特に注力しているのが「パワー半導体」です。
これは、電力の制御や変換(直流・交流の変換など)を行う半導体で、EV(電気自動車)や再生可能エネルギー設備、産業機器の省エネ化に不可欠なキーデバイスです。
東芝はこの分野で世界トップクラスの技術力を持っており、今後の脱炭素社会の実現に向けて、ますます需要が高まることが予想されます。
さらに、究極のセキュリティ技術と言われる「量子暗号通信」など、未来の社会基盤となり得る分野の研究開発にも力を入れています。
伝統的な強みを持ちつつも、こうした成長領域へ果敢に挑戦している点は、競合他社と比較する上での重要なポイントです。
競合比較:日立製作所との違い
東芝とよく比較されるのが、日立製作所です。
日立は、東芝と同様にエネルギーやインフラを手掛けていますが、近年は「Lumada(ルマーダ)」というデジタルソリューション事業を核に据え、ITの力で社会課題を解決するという側面を強く打ち出しています。
日立グループには日立建機や日立金属(現在はプロテリアル)なども含まれ、事業領域が非常に幅広いのが特徴です。
一方、東芝は家電事業や医療機器事業などを売却し、現在はエネルギー、インフラ、デバイス(半導体など)の領域にリソースを集中させています。
デジタル化へのアプローチも、日立がIT起点であるのに対し、東芝は現場(発電所や工場など)の知見や製品(モノ)を起点としたDX(デジタルトランスフォーメーション)を得意としている点に違いが見られます。
競合比較:三菱電機との違い
三菱電機も、強力なライバル企業です。
三菱電機は、工場の自動化を支えるFA(ファクトリーオートメーション)機器や、エレベーター・エスカレーターなどの昇降機で世界的に高いシェアを持っています。
また、「霧ヶ峰」ブランドのエアコンなど、家電分野(BtoC)でも強みを持っているのが特徴です。
東芝もFAや昇降機に関連する事業を持っていますが、現在の主力は(家電事業売却後は特に)電力システムや公共インフラといった、より大規模な「重電」分野にあります。
両社とも社会インフラを支えていますが、三菱電機は「工場の自動化」や「ビルの快適性」に強みを持ち、東芝は「エネルギーの創出・供給」や「公共システムの構築」により軸足を置いていると整理できるでしょう。
【東芝はなんの会社】東芝の求める人物像
企業研究において「求める人物像」を理解することは、志望動機や自己PRを作成する上で絶対に欠かせません。
企業側が「どんな人と一緒に働きたいか」を知ることで、皆さんが持つ経験や強みのうち、何をアピールすべきかが見えてくるからです。
特に東芝は、近年、経営再建や事業再編など、大きな変革のまっただ中にあります。
だからこそ、単に学歴やスキルが高いだけでなく、今の東芝の理念や価値観に共感し、これからの東芝を一緒に創っていける人材を強く求めています。
ここでは、東芝が公式に掲げているバリュー(価値観)や、近年の状況から読み取れる、採用選考で重視されるであろう人物像について具体的に解説していきます。
「誠実(Integrity)」と「変革への情熱(Passion for change)」
東芝が現在、採用において最も重視している価値観の一つが「誠実(Integrity)」です。
過去の不祥事を深く反省し、再生に向けて歩む東芝にとって、法令遵守はもちろんのこと、顧客や社会に対して誠実であることは、企業活動の揺るぎない土台となっています。
そのため、就活生の皆さんにも、真面目に物事に取り組む姿勢や、困難なことでも正直に向き合う強さが求められます。
そして、それと同時に強く求められるのが「変革への情熱(Passion for change)」です。
歴史ある大企業ですが、現状維持を良しとせず、自ら課題を見つけて新しいことに挑戦する意欲が不可欠です。
受け身の姿勢ではなく、「自分が東芝を変えていくんだ」というくらいの情熱を持った人材が、今の東芝には必要とされています。
高い当事者意識と実行力
変革期にある組織では、「誰かがやってくれるだろう」という他人任せの姿勢では何も進みません。
求められるのは、「自分がやるんだ」という高い当事者意識(オーナーシップ)です。
与えられた仕事だけをこなすのではなく、自分の役割や責任を深く理解し、周囲で起きている問題に対しても「自分事」として捉えて行動できる人が評価されます。
そして、当事者意識を持つだけでなく、困難な課題に直面しても諦めず、周囲の人々(上司、同僚、他部署、顧客など)を巻き込みながら、最後まで粘り強くやり遂げる力(実行力)も同時に重要です。
学生時代の部活動やアルバイト、研究活動などで、自ら問題意識を持って行動し、結果を出した経験があれば、それは大きなアピールポイントになるでしょう。
グローバルな視点と多様性への理解
東芝は、世界各国で事業を展開し、多くのグローバル企業や政府と取引をしています。
また、社内にも多様な国籍やバックグラウンドを持つ社員が働いています。
そのため、世界中の社会課題を解決するという視点を持って仕事に取り組むことが求められます。
単に英語が話せるという語学力だけでなく、文化や価値観の違いを理解し、尊重した上で、異なる背景を持つ人々と円滑にコミュニケーションを取り、協働できる能力が重要です。
これを「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)」と呼びます。
留学経験がなくても、日本国内で多様な人々と関わった経験や、グローバルなニュースに関心を持ち、自分なりの考えを持っていることも、面接などでアピールできる要素となります。
【東芝はなんの会社】東芝に向いてる・向いていない人
「求める人物像」は分かったけれど、結局のところ「自分は東芝に合っているんだろうか?」と不安に思う人もいるでしょう。
企業と学生には「相性」があります。
どれだけ優秀な学生でも、企業の社風や働き方とミスマッチが起きてしまえば、入社後に苦労することになりかねません。
それは皆さんにとっても、企業にとっても不幸なことです。
ここでは、これまでに解説した東芝の事業内容や求める人物像を踏まえて、どのようなタイプの人が東芝で力を発揮しやすいか、逆にどのようなタイプの人はギャップを感じる可能性があるかを、就活アドバイザーの視点から具体的にお伝えします。
自己分析の結果と照らし合わせながら、自分との相性をチェックしてみてください。
向いている人:社会貢献性の高い大規模プロジェクトに携わりたい人
東芝の主力事業は、エネルギーや公共インフラなど、人々の生活や社会活動の基盤を支えるものです。
そのため、仕事のスケールが非常に大きく、自分が関わった仕事が社会に与える影響力の大きさを実感しやすい環境です。
目先の利益や華やかさよりも、「社会基盤を支える」という使命感にやりがいを感じる人や、数年、数十年単位の長期的な視点で物事を捉え、コツコツと努力を積み重ねられる人に向いています。
また、こうした大規模プロジェクトは決して一人では成し遂げられません。
個人の成果を追求するよりも、チームメンバーと協力し、一体となって大きな目標を達成することに喜びを感じるタイプの人に最適です。
向いている人:変化をポジティブに捉え、学び続けられる人
前述の通り、東芝は今まさに大きな変革期を迎えています。
事業の再編や組織変更、新しい事業への挑戦など、会社全体が常に動いている状態です。
こうした「変化」を不安要素としてネガティブに捉えるのではなく、「新しいことに挑戦できるチャンス」「自分が成長できる機会」とポジティブに捉えられる柔軟性が求められます。
また、東芝が扱う技術は日進月歩で進化しています。
入社後も、現状の知識に満足せず、新しい技術や市場の動向を継続的に学び続ける意欲がある人は、東芝で大きく成長できるでしょう。
学生時代の専攻分野はもちろん、それ以外の分野にも好奇心を持ってアンテナを張れる人が活躍できます。
向いていない人:安定志向が強すぎる人
「東芝=日本の大企業だから安泰」というイメージを持っていると、入社後に大きなギャップを感じる可能性があります。
もちろん、企業としての基盤はしっかりしていますが、現在は変革と競争のまっただ中にいます。
過去の成功体験や従来のやり方が通用しない場面も多く、常に「もっと良い方法はないか」と自ら考えて行動することが求められます。
「会社が守ってくれる」という意識ではなく、「自分が会社を支える、変えていく」という気概が必要です。
指示待ちの姿勢で、与えられたルーティンワークだけをこなしていたい、という安定志向が強すぎる人にとっては、厳しい環境と感じるかもしれません。
向いていない人:個人の裁量を早期から強く求める人
東芝は長い歴史を持つ大企業であり、多くの社員が関わる大規模プロジェクトを動かすための組織構造やルール、意思決定のプロセスが確立されています。
そのため、入社1年目から全てを自分の判断で進めたい、というように個人の裁量を早期から強く求める人にとっては、もどかしさを感じる場面があるかもしれません。
もちろん、若手のうちから意見を求められ、挑戦する機会は多くありますが、ベンチャー企業のようなスピード感や、個人の裁量が全て、という働き方とは異なります。
チームワークを重んじ、上司や先輩、関係部署と丁寧に合意形成を図りながら仕事を進めるプロセスを重要視する風土があることは理解しておく必要があります。
【東芝はなんの会社】東芝に受かるために必要な準備
ここまで東芝の企業研究を深めてきましたが、いよいよ選考対策です。
東芝は、その技術力や事業の社会貢献性の高さから、理系・文系問わず多くの就活生が応募する人気企業です。
内定を勝ち取るためには、付け焼き刃の対策ではなく、「東芝に特化した」入念な準備が不可欠です。
自己分析や業界研究はもちろん、東芝が選考で何を見ているのかを理解し、的確にアピールすることが合否を分けます。
小手先のテクニックに走るのではなく、なぜ自分は東芝で働きたいのか、どう貢献できるのかを本質的に突き詰めることが重要です。
ここでは、東芝の選考を突破するために、今から具体的に何をすべきかを4つのポイントに絞って解説します。
「なぜ東芝か」を徹底的に深掘りする(競合比較)
面接で必ず問われるのが、「なぜ他の総合電機メーカー(日立、三菱電機など)ではなく、東芝なのですか?」という質問です。
これに説得力を持って答えるためには、本記事の「競合比較」セクションで解説したような、各社の違いを明確に理解しておく必要があります。
「社会インフラに携わりたい」だけでは、他の会社でも良いのでは?と思われてしまいます。
そうではなく、「東芝が特に強みを持つ〇〇(例:パワー半導体、地熱発電)の技術に惹かれた」「変革期にある貴社で、自分の〇〇という強みを活かして貢献したい」というように、東芝でなければならない理由を、自分の言葉で論理的に説明できるように準備してください。
「変革」と「誠実さ」をアピールするエピソード準備
東芝が求める人物像として挙げた「変革への情熱」と「誠実さ」。
これを裏付ける具体的なエピソードを、学生時代の経験から探し出しましょう。
「変革」については、例えば「サークルの非効率な運営方法を、自分が中心となって改善した経験」や「アルバイトで新しい施策を提案し、売上向上に貢献した経験」など、現状維持を良しとせず、自ら行動した事実をアピールします。
「誠実さ」については、「ルールを厳守して信頼を得た経験」や「困難な状況でも正直に報告・対処した経験」などが考えられます。
どちらも、「課題→行動→結果→学び」のプロセスを明確にして、具体的に語れるように整理しておくことが重要です。
技術系は研究内容、事務系はガクチカの論理的説明
選考では、皆さんの「論理的思考力」も厳しくチェックされます。
技術系の学生は、自身の研究内容について、専門外の面接官にも理解できるように分かりやすく説明する練習が必須です。
「なぜその研究を選んだのか」「研究の中で最も苦労した点は何か、どう乗り越えたか」「その研究が東芝でどう活かせるか」を簡潔にまとめましょう。
事務系の学生は、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」について、「なぜその課題に取り組んだのか」「目標達成のためにどんな仮説を立て、何を優先して実行したのか」といったプロセスを、論理的に説明できるように準備してください。
どちらも、前述の「当事者意識」や「実行力」が発揮されたエピソードを選ぶと効果的です。
OB・OG訪問やインターンシップへの積極的参加
企業の採用ホームページや説明会だけでは得られない「生の情報」に触れることは、企業研究を深め、志望動機を強固にする上で非常に有効です。
可能であれば、インターンシップに参加し、実際の職場の雰囲気や仕事内容を肌で感じてみてください。
インターンシップでの経験は、面接で語るエピソードとしても強力な武器になります。
また、OB・OG訪問も積極的に行いましょう。
大学のキャリアセンターなどを通じて、実際に東芝で働いている先輩に、「仕事のやりがい」や「大変なこと」、「社内の雰囲気」といったリアルな声を聞くことで、入社後のイメージが具体的になりますし、その行動自体が熱意のアピールにも繋がります。
【東芝はなんの会社】東芝の志望動機の書き方
エントリーシート(ES)や面接で、最も重要かつ、多くの就活生が頭を悩ませるのが「志望動機」です。
特に東芝のような人気企業では、ありきたりな内容では採用担当者の心に響きません。
「貴社の高い技術力に惹かれました」「社会貢献性の高さに魅力を感じました」といった抽象的な理由だけでは不十分です。
重要なのは、「数ある企業の中で、なぜ東芝でなければならないのか」、そして「自分が入社したら、東芝にどう貢献できるのか」という2点を、具体的な根拠とともに論理的に結びつけることです。
ここでは、ライバルに差をつけるための、説得力のある志望動機の組み立て方を、4つのステップに分けて解説します。
結論ファースト:「なぜ東芝を志望するのか」を明確に
ESでも面接でも、まずは結論から述べることが鉄則です。
採用担当者は非常に多くの志望動機に目を通すため、最初に「この学生が何を言いたいのか」を明確に伝えましょう。
「私は、貴社の〇〇という事業(または技術)を通じて、〇〇という社会課題を解決したい(または〇〇を実現したい)と考え、強く志望いたします。
」のように、自分が東芝で成し遂げたいことを具体的に示します。
単なる「憧れ」ではなく、「貢献したい」という能動的な姿勢を見せることがポイントです。
抽象的な「社会貢献」ではなく、「脱炭素社会の実現」や「安定したエネルギー供給」など、東芝の事業と直結する言葉を選びましょう。
具体性:「東芝のどの事業・技術」に魅力を感じたか
次に、結論で述べた「なぜ東芝か」の具体的な理由を説明します。
ここで、企業研究で得た情報が活きてきます。
「貴社のエネルギー事業」といった大雑把な表現ではなく、「世界トップレベルの効率を誇るガスタービン技術」や「EVの普及に不可欠なパワー半導体デバイス」のように、東芝独自の強みや具体的な製品・技術に言及しましょう。
そして、なぜ自分がその技術や事業に強く惹かれたのか、その背景(例えば、自身の原体験や問題意識など)を簡潔に付け加えると、より説得力が増します。
他社ではなく、東芝のその点に魅力を感じている、ということが明確に伝わるように意識してください。
自己PRとの連動:「自分の強みをどう活かせるか」
志望動機は、企業へのラブレターであると同時に、「自分を採用するメリット」を提示する場でもあります。
東芝の魅力的な点を挙げただけでは、「ただのファン」で終わってしまいます。
そこで、自分が学生時代に培ってきた経験やスキル(強み)が、志望する事業や職種でどのように活かせるのかを具体的にアピールします。
例えば、「研究活動で培った粘り強さを、貴社の長期的な研究開発プロジェクトで活かしたい」や、「サークル運営で発揮した調整能力を、大規模なインフラプロジェクトのチームワークで活かしたい」といった形です。
自分の強みと、東芝の求める人物像(例:変革への情熱、当事者意識)とを自然に結びつけることが重要です。
入社後の貢献:「将来どのようなことを成し遂げたいか」
志望動機の締めくくりとして、入社後の意気込みや将来のビジョンを述べます。
「自分を採用すれば、こんな活躍が期待できますよ」という将来性を採用担当者に感じてもらいましょう。
「まずは〇〇部門の技術者として基礎を徹底的に学び、将来的には〇〇といった新しい技術開発をリードする存在になりたい」や、「営業として顧客の課題解決に貢献し、将来的には貴社のグローバルなインフラプロジェクトを牽引したい」など、具体的なキャリアプランを語れると熱意が伝わります。
東芝という舞台で、自分がどのように成長し、貢献していきたいかをポジティブに伝えることで、「この学生と一緒に働きたい」と思わせることを目指しましょう。
【東芝はなんの会社】東芝についてよくある質問
企業研究を進めたり、選考の準備をしたりする中で、「これはどうなんだろう?」と素朴な疑問や不安が湧いてくることもあると思います。
特に東芝は、近年、経営再建に関するニュースや上場廃止といった大きな動きがあったため、就職先として考えたときに気になる点が多い学生もいるかもしれません。
こうした疑問を放置したまま選考に進むのは不安ですよね。
ここでは、就活生の皆さんからよく寄せられる東芝に関する質問をピックアップし、就活アドバイザーの視点から分かりやすく回答していきます。
面接などで関連する質問をされた場合の、受け答えのヒントにもなるはずです。
最近のニュース(上場廃止など)は就活に影響しますか?
2023年末に東芝が上場廃止となったことは、多くの就活生が気にしている点だと思います。
この背景には、外部の株主(いわゆる「モノ言う株主」)の影響を排し、経営の自由度を高め、中長期的な視点で大胆な変革を迅速に進めるという狙いがあります。
これが直ちに、新入社員の採用活動や給与、待遇、あるいは現在進めている事業活動に大きなマイナス影響を与えるものではありません。
むしろ、会社として「本気で変わるんだ」という強い意志の表れと捉えることもできます。
面接でこの件について聞かれた場合は、ニュースを理解していることを示した上で、「だからこそ、変革期にある貴社で自分の力を発揮したい」といったポジティブな意欲に繋げて回答できると良いでしょう。
福利厚生や研修制度は充実していますか?
歴史ある大手企業として、福利厚生制度は非常に手厚い部類に入ります。
例えば、独身寮や社宅、家賃補助といった住居に関するサポート、社員食堂、選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)など、社員が安心して働ける環境が整っています。
また、人材育成のための研修制度も充実しています。
新入社員研修はもちろんのこと、配属後のOJT(実務を通じた指導)、階層別研修、専門スキルを磨くための技術研修、語学研修など、多岐にわたるプログラムが用意されています。
特に技術系の社員は、社内で学べる機会が多いのが特徴です。
ただし、制度が「ある」ことと「利用しやすい雰囲気か」は別問題ですので、OB・OG訪問などで実態を確認してみるのも良いでしょう。
勤務地や配属はどのように決まりますか?
配属先や勤務地は、選考過程で伝えられる皆さんの希望や、専攻分野、適性、そして会社の事業計画(どの部門にどれだけの人員が必要か)を総合的に考慮して決定されます。
技術系の場合、研究開発拠点である「研究開発センター」(神奈川県川崎市)や、各事業の主力工場(例:府中事業所、横浜事業所、四日市工場など)への配属が多くなります。
事務系の場合は、本社機能が集まる「浜松町ビルディング」(東京都港区)や、各事業所が勤務地となることが一般的です。
必ずしも第一希望通りになるとは限りませんが、面接などの場で「なぜその事業(または勤務地)を希望するのか」を具体的に説明し、熱意を伝えることは非常に重要です。
女性の働きやすさ(産休・育休など)はどうですか?
大手企業として、法律で定められた産休・育休制度はもちろん整備されており、制度の利用実績も多数あります。
育休からの復職をサポートするプログラムや、子育てと仕事を両立するための短時間勤務制度、フレックスタイム制度なども導入されています。
近年は、女性の活躍推進(ダイバーシティ&インクルージョン)にも力を入れており、女性管理職の登用も積極的に進めようとしています。
ただし、これも正直なところ、部署の雰囲気や上司の理解度によって、制度の利用しやすさに差が出る可能性は否定できません。
もし可能であれば、インターンシップやOB・OG訪問の機会に、実際に働いている女性の先輩社員に、リアルな働き心地を聞いてみることをお勧めします。
まとめ
今回は、東芝が「なんの会社か」という基本的なところから、具体的な仕事内容、競合他社との違い、求める人物像、そして選考対策や志望動機の書き方まで、幅広く解説してきました。
東芝は、140年以上の歴史で培った高い技術力を武器に、エネルギーや社会インフラという社会の根幹を支える企業であると同時に、経営再建を経て、今まさに大きな変革に挑んでいる企業でもあります。
この記事で得た知識を土台にして、さらに自分で調べたり、OB・OG訪問をしたりすることで、あなただけの「なぜ東芝なのか」という答えが見つかるはずです。
企業研究を深め、自信を持って選考に臨んでください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート