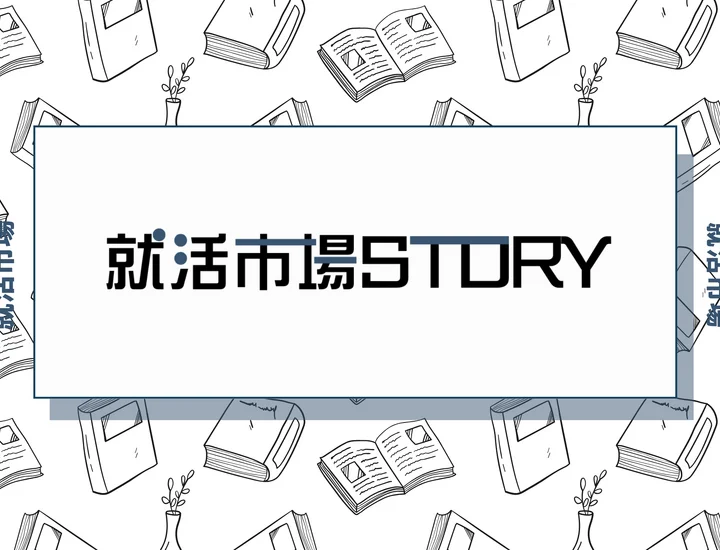就職活動を進める中で、「マイナビ」という名前を聞かない日はないでしょう。
多くの就活生が利用する就職情報サイト「マイナビ」を運営している会社ですが、「具体的にどんな会社なの?」「どんな仕事をしているの?」と疑問に思う方も多いはずです。
この記事では、就活生なら誰もが知る「マイナビ」という企業の実態について、事業内容から働き方、選考対策まで徹底的に解説していきます。
目次[目次を全て表示する]
【マイナビはなんの会社】マイナビはどんな会社なのか
株式会社マイナビは、「マイナビ新卒」や「マイナビ転職」といった人材情報サービスを中核としながら、進学、ウエディング、ニュース、農業など、非常に幅広い分野で事業を展開している総合情報サービス企業です。
「一人ひとりの可能性と向き合い、未来を切り拓く」ことをパーパス(存在意義)に掲げ、人々の人生の岐路や企業の成長に寄り添う多様なプラットフォームを提供しています。
就活生の皆さんにとっては「就職情報の会社」というイメージが強いですが、実際には人生の様々なシーンをサポートする多角的な事業を持つ企業であると理解しておくと良いでしょう。
【マイナビはなんの会社】マイナビの仕事内容
マイナビと聞くと、多くの学生さんは「マイナビ新卒」の運営や、企業の採用活動を支援する「営業職」をイメージするかもしれません。
もちろん、それはマイナビの根幹をなす重要な仕事です。
しかし、実際にはその裏側で、また全く異なる事業領域で、多種多様なプロフェッショナルが活躍しています。
例えば、Webサイトやアプリをより使いやすく改善するエンジニアやデザイナー、新たなサービスを企画するマーケティング担当、そして会社全体の運営を支えるコーポレート部門など、その職種は非常に多岐にわたります。
ここでは、マイナビという大きな船を動かす、代表的な仕事内容をいくつかピックアップして、具体的にどのようなミッションを担っているのかを深掘りしていきます。
自分の強みや興味がどの分野で活かせるか、想像しながら読み進めてみてください。
企業の採用課題に向き合う「ソリューション営業(RA)」
マイナビの営業職、特に新卒採用領域では「リクルーティングアドバイザー(RA)」と呼ばれる役割を担います。
この仕事のミッションは、単に「マイナビに求人広告を載せませんか?」と提案することではありません。
企業の経営者や人事担当者と深く向き合い、「どんな人材を採用したいのか」「採用活動で今何に困っているのか」といった本質的な課題をヒアリングすることから始まります。
その上で、「マイナビ」というプラットフォームをどう活用するか、合同説明会への出展は有効か、あるいはダイレクトリクルーティングサービスを併用すべきかなど、その企業にとって最適な採用戦略を企画・提案します。
採用成功は企業の将来を左右する重要な経営課題であり、そのパートナーとして伴走できるのが大きなやりがいです。
顧客の課題解決に向けて論理的に考え、粘り強く関係性を築けるコミュニケーション能力が求められる仕事と言えるでしょう。
学生と社会の接点を創出する「企画・マーケティング職」
皆さんが利用する「マイナビ」のサイトやアプリ、そして大規模な合同説明会イベント。
これらがスムーズに運営され、多くの学生と企業が出会えるよう企画・実行しているのが、この部門です。
企画・マーケティング職は、最新の就活トレンドや学生のニーズを分析し、「どうすればもっと使いやすいサイトになるか」「どんなイベントがあれば学生の役に立てるか」を考え抜きます。
例えば、WebサイトのUI/UX改善、効果的なプロモーション戦略の立案、イベントのコンテンツ企画や当日の運営ディレクションなど、業務は多岐にわたります。
自ら企画したものが形になり、多くの人の「キャリアの第一歩」に影響を与えることができるのは、この仕事ならではの醍醐味です。
変化する市場のニーズを的確に捉え、新しい価値を生み出す発想力と実行力が試されます。
人材領域以外の多様な「メディア・サービス運営職」
マイナビの強みは、就職や転職といった「人材領域」だけにとどまらない点です。
「マイナビ進学」「マイナビウエディング」「マイナビ農業」など、人々のライフイベントや特定の分野に特化した多様なメディア・サービスを展開しています。
これらの部門では、それぞれの業界の特性を深く理解し、ユーザー(学生、カップル、就農希望者など)とクライアント(学校、式場、農家など)の双方にとって価値ある情報やサービスを提供します。
営業活動はもちろん、メディアの編集・制作、イベント企画、新規事業の開発など、まるで独立した専門会社のように事業が運営されています。
人材領域で培ったノウハウを活かしつつ、全く異なるフィールドで新たな挑戦ができる環境があるのは、マイナビの大きな特徴です。
特定の分野への強い興味や専門性を活かしたい人にとっても魅力的な選択肢となるでしょう。
組織を内側から支える「コーポレートスタッフ」
数千人規模の従業員がそれぞれのフィールドで最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、会社全体の基盤を支えるのがコーポレートスタッフ(管理部門)の役割です。
具体的には、人事(採用、育成、制度設計)、総務(ファシリティ管理、法務)、経理・財務(予算管理、決算)、経営企画(中長期戦略の立案)、広報(社外への情報発信)など、多岐にわたる専門職種が存在します。
これらの仕事は、直接的に売上を生み出すわけではありませんが、組織が健全に成長し続けるために不可欠な機能を担っています。
例えば、人事部門であれば、社員が働きやすい環境や成長できる仕組みを整えることで、組織全体の活性化に貢献します。
高い専門性と広い視野を持ち、会社全体を俯瞰して課題解決に取り組むことが求められる、まさに縁の下の力持ちと言える存在です。
【マイナビはなんの会社】マイナビが選ばれる理由と競合比較
人材業界には、マイナビの他にも多くの強力なプレイヤーが存在します。
その中で、なぜ多くの企業や就活生が「マイナビ」を選ぶのでしょうか。
また、最大のライバルであるリクルートや、近年台頭している他のサービスとは、具体的に何が違うのでしょうか。
企業研究において、競合他社との比較は、その企業独自の強みや立ち位置を理解する上で絶対に欠かせません。
マイナビが長年にわたり築き上げてきたブランド力や事業の幅広さ、そしてリクルートをはじめとする他社とのビジネスモデルや社風の違いを明確にすることで、「なぜ自分はマイナビを志望するのか」という問いに対する答えも、より具体的になるはずです。
ここでは、マイナビが選ばれる理由と、主要な競合との違いを比較検討していきます。
自分の価値観と照らし合わせながら、マイナビの独自性を探ってみましょう。
圧倒的な知名度と「マイナビ」ブランドの信頼性
マイナビが選ばれる最大の理由の一つは、やはり「マイナビ」というブランドが持つ圧倒的な知名度と信頼性です。
特に新卒採用の領域において、「就活といえばマイナビ」と想起する学生や企業は非常に多く、長年にわたって築き上げてきた強固な基盤があります。
このブランド力は、単なる広告宣伝の結果ではなく、全国各地の大学との連携、きめ細やかな企業サポート、そして使いやすいプラットフォームの提供といった地道な活動の積み重ねによって培われてきました。
企業にとっては「マイナビに掲載すれば多くの学生に見てもらえる」という安心感があり、学生にとっては「マイナビを使えば必要な情報が揃う」という利便性があります。
この「当たり前」のインフラとして機能していることこそが、マイナビの競争優位性の源泉であり、他社が容易に追随できない強みとなっています。
人材領域に留まらない「多角的な事業ポートフォリオ」
マイナビのもう一つの大きな強みは、その事業領域の広さです。
前述の通り、マイナビは新卒や転職といった人材サービスだけでなく、進学、ウエディング、ニュース、農業、さらには地方創生支援など、人々のライフサイクル全般に関わる多様な事業を手がけています。
これは、一つの事業が市況の影響を受けたとしても、他の事業がカバーできるという「リスク分散」の効果をもたらします。
それ以上に重要なのは、これらの多様な接点を通じて得られる膨大なデータとノウハウが、既存事業の強化や新規事業の創出に活かされている点です。
例えば、進学領域で得た学生の動向データを、新卒採用サービスの改善に役立てるといったことが可能です。
安定した経営基盤の上で、幅広いキャリアの可能性に挑戦できる環境は、働く側にとっても大きな魅力と言えるでしょう。
競合「リクルート」との違いは?
就活生の皆さんにとって、最も気になるのが「リクルートとの違い」ではないでしょうか。
両社は人材業界の二大巨頭ですが、その戦略や社風には明確な違いがあります。
リクルートは「ホットペッパー」や「SUUMO」など、日常消費に近い領域でも強いメディアを持ち、圧倒的な営業力と「個」の力で新規事業を次々と生み出す文化が特徴的です。
一方、マイナビは「マイナビ新卒」を筆頭に、「人材」という領域で深く、手堅くシェアを拡大してきた歴史があります。
社風としても、リクルートが「圧倒的当事者意識」を掲げ個人がドライブする側面が強いのに対し、マイナビはチーム全体で目標を追い、着実に成果を積み上げる協調性を重んじる傾向があると言われます。
どちらが良い悪いではなく、自分の志向性がどちらの環境にフィットするかを見極めることが重要です。
「ダイレクトリクルーティング」サービスとの比較
近年、「OfferBox」や「dodaキャンパス」(ベネッセとパーソルの合弁)といった、企業側から学生に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」サービスが急速に普及しています。
従来の「マイナビ」のような就職ナビサイトが、学生が企業を探して応募する「待ち」のスタイルであるのに対し、ダイレクトリクルーティングは「攻め」のスタイルと言えます。
マイナビももちろん「スカウト機能」などを強化していますが、ビジネスモデルの主軸は依然としてナビサイトです。
ナビサイトの強みは、網羅性(多くの企業情報を一覧できる)と効率性(一括エントリーなど)にあります。
一方、ダイレクトリクルーティングは、思わぬ企業との出会いや、個別の強みを評価してもらえる可能性があります。
マイナビを志望する際は、このナビサイトというビジネスモデルの社会的価値や、今後の可能性について自分なりの考えを持っておくと良いでしょう。
【マイナビはなんの会社】マイナビの求める人物像
多くの事業領域で「人と企業の成長」を支援するマイナビでは、一体どのような人材が求められているのでしょうか。
企業の採用ページや理念を見ると、「主体性」「利他性」「誠実さ」といったキーワードが浮かび上がってきます。
マイナビのビジネスは、無形の「情報」や「サービス」を扱うため、最終的には「人」そのものが最大の資本であり、競争力の源泉です。
だからこそ、単にスキルが高いだけでなく、同社のパーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来を切り拓く」という価値観に共感し、それを体現できる人材を求めていると考えられます。
ここでは、マイナビが掲げる理念や事業内容から推測される、具体的な「求める人物像」を3つの側面に分けて解説していきます。
自分の経験や強みが、これらの要素とどう結びつくかを考えながら、自己PRや志望動機に活かしていきましょう。
自ら考え行動する「主体性」と「当事者意識」
マイナビの仕事は、既存のサービスを運営するだけでなく、常に変化する市場や顧客のニーズに応え、新しい価値を生み出し続けることが求められます。
そのため、指示されたことをこなすだけではなく、「どうすればもっと良くなるか」「今、本当に必要なことは何か」を自ら考え、行動に移せる主体性が不可欠です。
例えば、営業職であれば、顧客から言われた通りの広告を掲載するのではなく、「その採用ターゲットなら、こちらのプランの方が効果的ではないか」と一歩踏み込んだ提案をする姿勢が求められます。
また、企画職であれば、トレンドを追いかけるだけでなく、自らトレンドを創り出すような発想が必要です。
自分の仕事に責任を持ち、当事者意識を持って取り組める人材が、マイナビでは高く評価されるでしょう。
学生時代のアルバートやサークル活動で、自ら課題を見つけて改善に取り組んだ経験などは、この「主体性」をアピールする絶好の材料となります。
顧客や仲間のために動ける「利他性」と「誠実さ」
マイナビの事業の根幹には、「人」や「企業」の成長を支援するという想いがあります。
そのため、自分の利益や成果だけを追求するのではなく、顧客の成功や社会の発展、そして共に働く仲間のために行動できる「利他性」が非常に重要視されます。
採用支援であれば、目先の売上のために企業に合わないプランを無理に勧めるのではなく、長期的な視点に立って誠実に課題解決をサポートする姿勢が信頼に繋がります。
また、マイナビの仕事は多くの場合、営業、企画、制作、開発など、異なる職種のメンバーと連携するチームプレーです。
仲間を尊重し、チーム全体の成果を最大化するために貢献できる協調性や誠実さも、同様に求められる資質です。
誰かのために一生懸命になった経験や、チームの中で潤滑油のような役割を果たしたエピソードは、この点をアピールする上で有効です。
高い目標に粘り強く挑む「目標達成意欲」
マイナビは人材業界のリーディングカンパニーであり、その地位を維持・発展させていくためには、常に高い目標を掲げ、それを達成し続ける必要があります。
特に営業部門などでは、個々人やチームに明確な目標(数値目標)が設定されることも多いでしょう。
もちろん、目標達成のプレッシャーはありますが、それを「成長の機会」と捉え、困難な状況でも諦めずに粘り強く取り組めるタフさが求められます。
なぜなら、その目標の先には、支援を待つ企業や学生がいるからです。
単に「数字に強い」ということではなく、「顧客の課題解決」という本質的な目標に向かって、泥臭く努力を続けられるかどうかが問われます。
部活動や研究、資格取得などで、高い壁にぶつかりながらも、工夫と努力で乗り越えた経験は、この「目標達成意欲」を示す強力な根拠となるはずです。
【マイナビはなんの会社】マイナビに向いてる・向いていない人
ここまでマイナビの事業内容や求める人物像を見てきましたが、それを踏まえて、具体的にどのようなタイプの人がマイナビで活躍でき、逆にどのような人がミスマッチを感じやすいのでしょうか。
企業選びにおいて、「何をやっているか」だけでなく、「誰と働くか」「どんな文化か」という相性は非常に重要です。
マイナビは、人の人生に深く関わる社会貢献性の高い事業と、目標達成に向けてチームで取り組む文化を併せ持つ企業です。
「人の役に立ちたい」という想いと、「ビジネスとして成果を出したい」という意欲の両方を満たしたい人にとっては、非常にやりがいのある環境でしょう。
一方で、安定やルーティンワークを最優先する人にとっては、変化のスピードや求められる成果の大きさに戸惑う場面もあるかもしれません。
ここでは、マイナビへの適性を「向いている人」と「向いていない人」の両面から具体的に見ていきましょう。
向いている人:人の「転機」を支援することにやりがいを感じる人
マイナビが手がける事業の多くは、「就職」「転職」「進学」「結婚」といった、人々の人生における重要な「転機」に関わるものです。
自分の仕事が、誰かの人生をポジティブな方向へ導くきっかけになるかもしれない。
このことに強いやりがいや使命感を感じられる人は、マイナビの仕事に非常に向いています。
例えば、採用支援の営業であれば、自分の提案で入社した新入社員が活躍していると聞いた時、大きな喜びを感じられるでしょう。
また、キャリアアドバイザーであれば、悩んでいた学生が自分のキャリアに自信を持てた瞬間に立ち会えます。
もちろん、責任の重い仕事でもありますが、「誰かの役に立っている」という実感を日々のモチベーションに変えられる人にとって、マイナビは最高の舞台の一つと言えるでしょう。
向いている人:チームで協力し、高い目標を達成したい人
マイナビは個人プレーよりも、チーム全体で目標に向かって進む文化が強いと言われています。
営業、企画、制作など、異なる役割を持つメンバーが連携し、それぞれの専門性を持ち寄って一つのプロジェクトを成功に導きます。
そのため、一人で黙々と作業するよりも、仲間とコミュニケーションを取りながら協力して物事を進めるのが好きな人に向いています。
また、業界のトップランナーとして、常に高い目標が設定されます。
その目標達成のプロセスを「キツい」と捉えるか、「チームで乗り越えるべきチャレンジ」と捉えるかで、働きがいは大きく変わるでしょう。
困難な課題に対しても、チームで知恵を出し合い、一体感を持って取り組むことに喜びを感じる人は、マイナビで大きく成長できる可能性が高いです。
向いていない人:安定志向で、変化や挑戦を好まない人
マイナビは安定した経営基盤を持つ大手企業ですが、その内実は、常に市場の変化に対応し続ける「ベンチャーマインド」も併せ持っています。
特に人材業界は、景気の動向やテクノロジーの進化によって、顧客のニーズが目まぐるしく変わる分野です。
「一度やり方を覚えたら、あとは同じことの繰り返し」といったルーティンワークを期待していると、ミスマッチを感じる可能性が高いでしょう。
新しいサービスの導入、組織体制の変更、目標数値の見直しなどは日常的に起こり得ます。
そうした変化を「面倒だ」と感じるのではなく、「新しいスキルを身につけるチャンス」と前向きに捉えられる柔軟性が必要です。
安定した環境で、決められた業務をコツコツとこなしたいという志向性が強い人は、他の業界や企業の方が合っているかもしれません。
向いていない人:社内外とのコミュニケーションを避けたい人
マイナビの仕事は、その多くが社内外の「人」との関わりの中で成り立っています。
営業職であれば顧客との折衝、企画職であれば関連部署との調整、コーポレート職であっても社員とのやり取りが日常的に発生します。
そのため、できるだけ人と話さず、PCに向かって集中して作業したいというタイプの人にとっては、ストレスを感じる場面が多いかもしれません。
もちろん、エンジニアやデザイナーなど、比較的専門スキルに集中できる職種もありますが、それでもプロジェクトを前に進めるためには最低限の連携や意思疎通は不可欠です。
「人と関わること」そのものが仕事の推進力になると理解し、積極的にコミュニケーションを楽しめる姿勢がなければ、マイナビで活躍し続けるのは難しいかもしれません。
【マイナビはなんの会社】マイナビに受かるために必要な準備
マイナビは、その知名度と事業の魅力から、毎年非常に多くの就活生が応募する人気企業です。
多くのライバルの中から内定を勝ち取るためには、付け焼き刃の対策ではなく、しっかりとした準備が不可欠になります。
選考フローは、エントリーシート(ES)、Webテスト、複数回の面接(グループディスカッションが実施される場合もあり)というのが一般的です。
特に面接では、「なぜ人材業界なのか」「なぜリクルートではなくマイナビなのか」「学生時代に何に力を入れてきたのか」といった定番の質問が、深く、具体的に掘り下げられる傾向にあります。
単に企業の情報を暗記するだけでなく、それらの情報と自分自身の経験・価値観をどう結びつけ、自分の言葉で語れるかが合否を分けるポイントになります。
ここでは、マイナビの内定獲得に向けて、最低限準備しておくべきことを4つのステップに分けて解説します。
「なぜマイナビか」を語るための徹底した企業研究
マイナビに受かるための第一歩は、競合他社、特にリクルートとの違いを明確に理解することです。
前述の通り、事業領域の広さ(特に進学やウエディング等)、新卒領域での圧倒的なシェア、そしてチームで協働する社風などがマイナビの特徴として挙げられます。
これらの特徴を踏まえ、「自分はリクルートの〇〇という点よりも、マイナビの△△という点に強く惹かれている」と具体的に説明できる必要があります。
例えば、「個の力で突き進むよりも、チームで知恵を出し合い、顧客に誠実に向き合うマイナビの姿勢に共感した」といった形です。
そのためには、マイナビの採用サイトやIR情報だけでなく、リクルートや他の人材企業の動向も研究し、自分なりの「マイナビを選ぶ理由」を確立することが極めて重要です。
求める人物像に合致する「ガクチカ」の整理
マイナビが求める「主体性」「利他性」「目標達成意欲」といった人物像。
これらをアピールするために、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)のエピソードを整理しましょう。
重要なのは、単に「サークルのリーダーでした」という事実ではなく、その経験の中で「どのような課題」に対し、「自らどう考え、行動」し、「チームや他者にどう働きかけ」、「最終的にどんな成果」を出したのかを具体的に語ることです。
例えば、「アルバイト先で、新人スタッフの離職率が高いという課題に対し、自らマニュアル改善と面談の仕組みを提案・実行し、定着率を〇%改善した」といったエピソードは、主体性と利他性の両方をアピールできます。
自分の経験をマイナビの求める人物像に紐づけて言語化する作業を徹底的に行いましょう。
人柄と論理性を伝える「面接(深掘り)対策」
マイナビの面接では、ESやガクチカの内容について「なぜそう思ったの?」「その時、他にどんな選択肢があった?」「今振り返って、改善点は?」といった形で、思考のプロセスや人柄を深く掘り下げる質問が多くなされます。
これは、学生が「主体性」や「誠実さ」を本当に持っているのか、その場限りの言葉でないかを見極めるためです。
この深掘りに対応するには、自己分析を徹底し、自分の行動原理や価値観を理解しておく必要があります。
また、結論から先に述べ、その理由や具体例を簡潔に説明する「PREP法」を意識し、論理的に話す練習も欠かせません。
友人や大学のキャリアセンター、就活エージェントなどに協力してもらい、模擬面接を繰り返すことが最も効果的な対策となります。
早期からの接点を持つ「インターンシップへの参加」
もし可能であれば、マイナビが実施するインターンシップや早期のイベントに参加することは非常に有効です。
インターンシップに参加するメリットは大きく二つあります。
一つは、実際の業務に近いワークショップを通じて、マイナビの仕事の面白さや難しさ、社風を肌で感じられること。
これにより、企業研究が深まり、志望動機に説得力を持たせることができます。
もう一つは、早期選考ルートに乗れたり、面接で「インターンに参加して〇〇と感じた」という具体的なエピソードを話せたりする可能性がある点です。
もちろん、インターンに参加しなければ受からないわけではありませんが、早期からマイナビへの熱意を行動で示すことは、選考においてプラスに働くことは間違いありません。
募集情報は早めにチェックしておきましょう。
【マイナビはなんの会社】マイナビの志望動機の書き方
エントリーシートや面接で必ず問われる「志望動機」。
これは、就活生が「どれだけ自社を理解しているか」そして「どれだけ自社で活躍してくれそうか」を判断するための最も重要な質問の一つです。
特にマイナビのような人気企業では、「マイナビのサービスが好きだから」といった漠然とした理由だけでは、他の学生との差別化は図れません。
なぜ数ある人材会社の中でマイナビなのか、そして入社後に自分の強みをどう活かして貢献したいのかを、論理的かつ情熱的に伝える必要があります。
ここでは、マイナビの人事担当者に「この学生と一緒に働きたい」と思わせるような、説得力のある志望動機を構築するための3つのステップと、陥りがちなNG例について解説します。
自分の経験を棚卸ししながら、オリジナルの志望動機を練り上げてください。
Step1:「なぜ人材業界で、なぜマイナビなのか」を明確にする
志望動機の核となるのは、「業界の理由」と「企業の理由」です。
まず、「なぜ金融でもメーカーでもなく、人材業界を志望するのか」を自分の原体験に基づいて説明する必要があります。
例えば、「アルバイトのリーダー経験で、人の成長を支援することにやりがいを感じたから」といった具体的なエピソードが有効です。
その上で、「なぜ同業他社(リクルートなど)ではなく、マイナビなのか」を明確に述べます。
ここで効いてくるのが企業研究です。
「新卒領域での圧倒的なシェアと信頼性」「人材以外の多角的な事業展開」「チームで協働する社風」など、マイナビ独自の強みと自分の価値観が合致する点を具体的に示しましょう。
「人の成長支援ならどこでも良い」のではなく、「マイナビの〇〇という環境だからこそ、自分の力が最大限発揮できる」という論理構成を目指してください。
Step2:具体的な「原体験」とマイナビの事業を結びつける
志望動機に説得力を持たせるためには、あなたの「想い」がどこから来ているのかを示す「原体験」が不可欠です。
例えば、「部活動で、個々の強みを活かすチームビルディングに苦心した経験から、企業の採用課題解決に関心を持った」や「地方出身で、進学先の情報収集に苦労した経験から、マイナビ進学のような情報プラットフォームの重要性を感じた」など、あなた自身のリアルな経験を盛り込みましょう。
そして、その経験から得た課題意識や学びが、マイナビのどの事業(新卒、転職、進学など)で、どのように活かせるのかを具体的に結びつけます。
この「原体験→課題意識→マイナビの事業との接点」という流れがスムーズであるほど、志望動機は深く、共感を呼ぶものになります。
Step3:「入社後にどう貢献したいか」で熱意を伝える
志望動機の締めくくりは、「入社後に自分がどう活躍し、貢献したいか」という未来へのビジョンです。
ここでは、あなたの強み(例えば、ガクチカでアピールした「主体性」や「目標達成意欲」)を活かして、マイナビのどのような課題解決に貢献したいかを具体的に述べましょう。
例えば、「私の強みである『課題発見力と巻き込み力』を活かし、ソリューション営業として、中堅・中小企業の採用課題に粘り強く向き合い、伴走型の支援で企業の成長に貢献したい」といった形です。
単に「頑張ります」という精神論ではなく、自分の強みをどう事業に活かすかを具体的に提示することで、入社後の活躍イメージを採用担当者に持ってもらうことが狙いです。
ここが明確な学生は、「自社で活躍してくれそうだ」と高い評価を得やすくなります。
志望動機で避けたい「NG例」とは?
説得力のある志望動機を考える一方で、避けるべき「NG例」も知っておきましょう。
最も多いのが、「企業理念に共感しました」とだけ述べてしまうパターンです。
なぜ共感したのか、その理念と自分の原体験がどう結びつくのかが語られなければ、中身のない志望動機になってしまいます。
また、「マイナビのサービスを学生時代に使っていて便利だったから」という理由も、消費者目線に留まっており、働く側としての視点が欠けています。
「なぜ便利だと感じたのか」「そのサービスをどう改善・発展させたいか」まで踏み込む必要があります。
最後に、「リクルートも受けています」と正直に話しつつ、両社の違いを明確に説明できないのもマイナス評価に繋がります。
企業研究が浅いと見なされるため、競合比較は徹底的に行いましょう。
【マイナビはなんの会社】マイナビについてよくある質問
ここまでマイナビの全体像や選考対策について解説してきましたが、就活生の皆さんの中には、まだ具体的な働き方や社風について、細かな疑問や不安が残っているかもしれません。
「実際のところ、営業はきついんじゃないか?」「ワークライフバランスは取れるの?」といった、リアルな声は非常に気になりますよね。
企業説明会やOB・OG訪問では聞きにくいこともあるかもしれません。
このセクションでは、就活生から特によく寄せられるマイナビに関する質問をピックアップし、就活アドバイザーの視点から、できる限り実態に近い情報や考え方をお伝えしていきます。
もちろん、部署や時期によって状況は異なりますが、企業選びの判断材料として参考にしてみてください。
Q. 営業職はノルマがきついですか?
A. 人材業界、特に営業職であれば、目標(ノルマ)が設定されるのは一般的であり、マイナビも例外ではありません。
目標達成に向けたプレッシャーが全くないとは言えません。
しかし、マイナビの特徴として、個人に過度な負担をかけるというよりは、チーム全体で目標達成を目指す文化が根付いていると言われます。
達成が難しい場合は、上司や先輩が一緒になって「どうすれば達成できるか」を考え、サポートしてくれる体制が整っていることが多いようです。
また、その目標は単なる売上のためではなく、「顧客の採用成功」という本質的な価値提供に基づいています。
目標達成のプロセスを通じて、顧客の課題解決能力や営業スキルが磨かれるため、それを「成長の機会」と捉えられる人にとっては、ポジティブな環境と言えるでしょう。
「きつい」かどうかは、個人の捉え方や目標達成への意欲次第な側面が強いです。
Q. 残業やワークライフバランスは実際どうですか?
A. ワークライフバランス(WLB)は、就活生にとって非常に関心の高いテーマですね。
マイナビは全社的に残業時間の削減や有給休暇の取得促進に取り組んでおり、業界内でも比較的WLBは取りやすい企業とされています。
例えば、フレックスタイム制の導入(部署による)や、ノー残業デーの設定など、制度面での整備は進んでいます。
ただし、実態としては、部署や時期による繁閑の差が大きいのも事実です。
特に、新卒採用の繁忙期(春先)や、大きなイベント前、メディアの締め切り前などは、一時的に業務が集中し、残業が増える傾向にあります。
とはいえ、かつてのような長時間労働が常態化しているわけではなく、メリハリをつけて働く文化が醸成されつつあります。
OB・OG訪問などで、希望する部署のリアルな声を聞いてみるのが最も確実です。
Q. 配属はどのように決まりますか?
A. マイナビの新卒採用は、多くの場合「総合職」として一括採用され、入社後の研修を経てから各部署への配属が決定されます。
配属先の決定プロセスは、本人の適性、希望(配属面談などでヒアリングされる)、そして各部門のニーズ(人員計画)を総合的に勘案して行われます。
必ずしも第一希望の部署に配属されるとは限りませんが、マイナビは「進学」「ウエディング」「転職」など事業領域が非常に広いため、様々なキャリアパスを描ける可能性があります。
また、入社後も「社内公募制度」や定期的な「異動希望調査」など、自らキャリアを切り拓くチャンスが用意されています。
まずは配属された場所で成果を出すことが、将来的に希望のキャリアを実現するための近道となるでしょう。
Q. 競合のリクルートと比べて社風はどう違いますか?
A. これは非常によく聞かれる質問であり、企業選びの軸として重要ですね。
あくまで一般論ですが、両社の社風は対照的と評されることが多いです。
リクルートは「個」の力が強く、若手にも大きな裁量が与えられ、新規事業への挑戦が推奨される「起業家精神」の強い文化と言われます。
一方、マイナビは「組織」や「チーム」での協働を重んじ、着実に物事を進める堅実さや、社員同士の面倒見の良さ、温和な雰囲気があるとされます。
「リクルートは体育会系、マイナビは文化系」と例えられることもありますが、これはあくまでイメージです。
どちらの社風が自分に合うかは、完全に個人の価値観によります。
インターンシップや社員座談会などで、実際に働く人の雰囲気を自分の目で確かめ、どちらの環境で自分が最もパフォーマンスを発揮できそうかを見極めることが大切です。
まとめ
今回は、就活生の皆さんにとって最も身近な企業の一つである「マイナビ」について、その事業内容から仕事、選考対策までを深掘りしてきました。
「マイナビ」が単なる就職情報サイトの運営会社ではなく、人材領域を核としながらも、進学やウエディングなど、人々の人生の様々なシーンを支える総合情報サービス企業であることがお分かりいただけたかと思います。
マイナビを志望する際は、「なぜリクルートではなくマイナビなのか」という問いに対し、事業の多角性やチームで協働する社風といった特徴と、自分自身の経験・価値観を結びつけて語ることが不可欠です。
この記事を参考に、ぜひあなた自身の言葉で、マイナビへの熱い想いを伝えてください。
応援しています!
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート