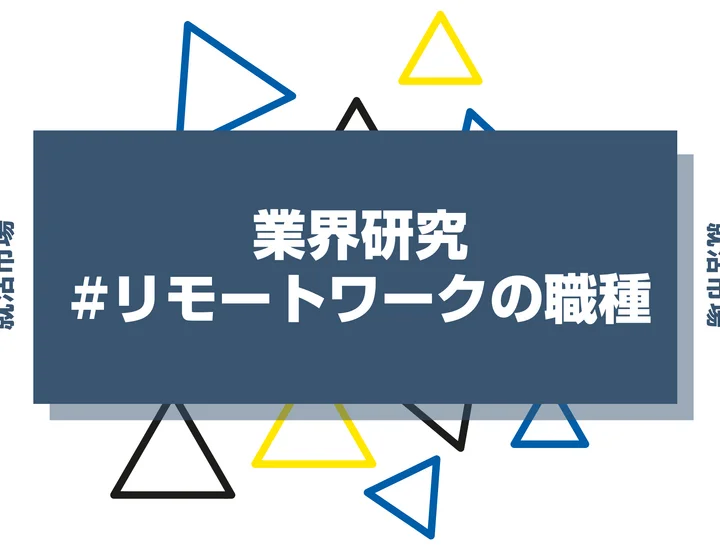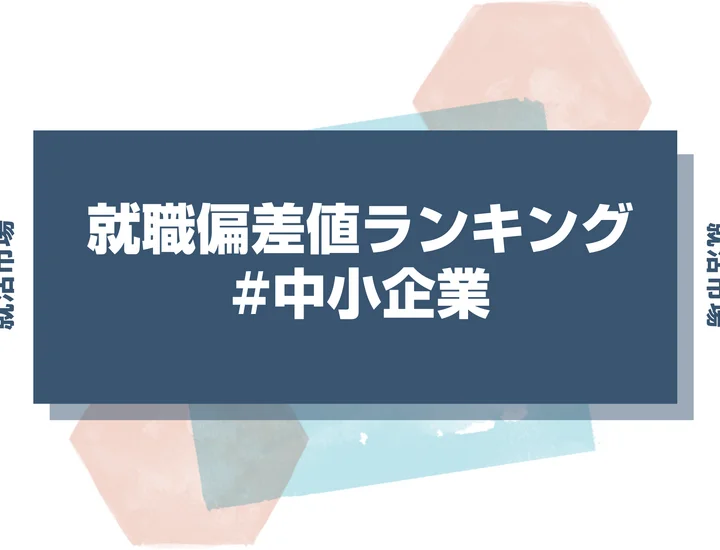目次[目次を全て表示する]
【短所の見つけ方】なぜ短所が書けないのか?
多くの人が自己PRやエントリーシートで短所を書く際に悩みます。
その原因の一つは自己分析が十分にできていないことです。
自分の性格や行動パターンを客観的に理解できていなければ、具体的な短所を言語化するのは難しいです。
また、短所を伝えることに抵抗を感じる人も多く、悪い印象を与えたくないという気持ちから短所を避けてしまう傾向があります。
これらの心理的な壁が、短所を明確に書けない理由として挙げられます。
自己分析不足
短所を具体的に書くためには、まず自己理解が必要不可欠です。
自己分析が不足していると、自分の性格や行動のクセ、改善すべきポイントに気づけません。
日常生活や仕事、学校での経験を振り返らず、表面的な自己評価だけで短所を考えようとしても、抽象的で漠然とした内容になりがちです。
たとえば「頑固」や「短気」といった単語だけで終わってしまうと、面接官に響く説得力のある短所にはなりません。
自己分析とは、自分の過去の行動や感情の動きを丁寧に振り返り、パターン化する作業です。
具体的には、失敗体験や周囲からのフィードバックを整理し、その原因を深掘りしていきます。
例えば、なぜそのときトラブルになったのか、自分はどんな態度を取ったのか、どう感じたのかなどを具体的に思い出すことが重要です。
短所を伝えることに抵抗がある
多くの人が短所を伝えることに強い抵抗を感じる理由は、短所=悪い部分と捉えがちだからです。
面接やESで短所を質問されると、「マイナス評価されるのではないか」と不安になり、避けたい気持ちが働きます。
結果として、短所を書かずに済ませたり、「短所はありません」と言ったり、あるいはあまりにポジティブすぎる短所を並べてしまうケースも多く見られます。
しかし企業は、短所を通して応募者の自己理解度や成長意欲、仕事に対する姿勢を見極めようとしています。
つまり短所は、ネガティブな要素を伝える場ではなく、「自分の課題を認識し、改善に努めているかどうか」を示す絶好のチャンスなのです。
そのため、短所を正直に伝えることはむしろプラスに働くことがあります。
この心理的抵抗は、短所の捉え方を変えることで軽減されます。
短所は「欠点」ではなく「課題」や「改善点」として捉え、自分の成長を促す材料とする視点を持つことが大切です。
また、短所を伝える際には、「改善に向けてどのような行動をしているか」や「どう活かしていきたいか」をセットで話すことがポイントです。
こうすることで、短所がマイナス評価に結びつくのではなく、前向きな姿勢を示す強みとなります。
【短所の見つけ方】短所は悪いところを聞くものでない
多くの人は短所というと「悪い部分」や「欠点」をイメージしがちですが、実際にはそうではありません。
企業が短所を質問する目的は、単にマイナス面を知ることではなく、応募者の自己理解や成長意欲を把握するためです。
短所は自分の課題や伸びしろを示すものであり、自分らしさを表す大切なヒントにもなります。
このような捉え方を理解することで、短所を前向きに捉え、適切に伝えやすくなります。
短所=ダメな部分という思い込みを手放す
短所は「自分のダメなところ」や「悪い部分」と考えられがちで、多くの人がそれを伝えることに抵抗を感じています。
就職活動や面接で短所を聞かれると、評価を下げられるのではないかという不安から、隠そうとしたり、無難な答えでごまかしたりするケースが少なくありません。
しかし、企業が短所を尋ねる本当の意図は、単に悪い面を見つけることではなく、応募者が自己理解をどれだけ深めているか、課題にどう向き合っているか、そして成長の意欲があるかを確認することにあります。
このため、短所をただの欠点や失敗として捉え続けるのは誤解です。
短所とは自分の課題や改善すべきポイントを指し、成長のためのヒントや糧として前向きに捉えるべきものです。
短所を「悪い」と決めつけてしまうと、伝えるのが怖くなり、自己理解の浅さを印象付ける結果になってしまいます。
反対に、短所を自分の課題として認識し、どう改善しようとしているかを語れる人は、謙虚さと成長意欲を持つ魅力的な人材として評価されます。
短所を伝えることに抵抗を感じる場合は、まず短所に対する固定観念を見直すことが大切です。
短所は欠点ではなく、努力や工夫で改善できる可能性のあるポイントです。
自己分析や他者からのフィードバックを活用して、自分の短所を正しく理解し、改善に向けた姿勢を示すことが、面接で好印象を与えるコツになります。
こうした考え方の変化が、短所を自然に伝える第一歩です。
短所は伸びしろとして語るもの
短所は単にマイナスの特徴を並べるだけではなく、自己成長のための伸びしろとして語ることが非常に重要です。
面接官は短所を聞くことで、その人が自分の課題をどれだけ把握し、具体的に改善に取り組んでいるかを見ています。
したがって短所を伝える際は、単なる欠点の羅列に終わらせず、改善のプロセスや努力をセットで伝えることが評価されるポイントです。
例えば優柔不断という短所を挙げる場合、ただ決断が遅いと話すのではなく、なぜそうなるのか、どうして慎重になるのかを説明し、さらに決断力を高めるために情報収集や優先順位付けの訓練をしていることを伝えると良いでしょう。
このように短所と改善策をセットにして話すことで、短所が単なるマイナスではなく、成長に向けた課題として捉えられ、前向きな印象を与えられます。
また、短所を伸びしろとして語ることは、自己理解の深さと自己改善への意欲の高さを示します。
社会人としての成長意識は非常に評価されるため、短所を正しく伝えることは長期的なキャリア形成にもプラスになります。
さらに改善努力の具体例を伝えることで説得力が増し、面接官の共感や信頼を得やすくなります。
このように、短所は成長の可能性を示す大切な要素であり、それをどう活かし改善していくかを明確に伝えることが、就活における短所の伝え方の核心と言えます。
自分らしさを表すヒントになる
短所は単なる欠点や課題だけでなく、自分らしさを表す大切なヒントとして捉えることができます。
人はそれぞれ性格や価値観、考え方や行動のパターンが異なり、短所やそれに対する向き合い方は個人の特徴や個性を色濃く反映します。
企業は応募者の社風との相性やチームへの適合性を判断するために、こうした個性の表れである短所を重要視します。
例えば几帳面すぎる性格は「細かいことにこだわりすぎる」という短所になることがありますが、一方で「仕事を丁寧に行う」という長所も併せ持ちます。
このように短所と長所は表裏一体であり、どのように短所を認識し、どう改善や工夫をしているかが個性や成長意欲の表れとなります。
自己理解が深い人はこの両面をバランスよく把握しているため、面接官からは信頼されやすくなります。
また短所を自分らしさとして受け入れることで、他の応募者との差別化が図れます。
同じ短所でも捉え方や改善策は人によって違うため、オリジナリティあふれる自己PRが可能になります。
自分の強みと弱みを理解し、課題に前向きに取り組む姿勢を示すことで、企業はあなたが組織に良い影響を与える人材だと判断します。
短所は恥ずかしいものでも隠すべきものでもありません。
自分の個性を知り、成長を続けるための貴重な材料として前向きに捉え、適切に伝えることが就活成功の鍵となります。
【短所の見つけ方】短所を見つけるためのポイント
短所を見つけることに悩む人は多いですが、効果的な探し方があります。
まずは自分が苦手だと感じることや、困った経験から短所を掘り下げてみることが大切です。
また、長所の裏返しに短所が隠れている場合も多く、自分の強みを別の視点から見直すことで新たな発見があります。
さらに、診断ツールを活用することで、自分では気づきにくい性格傾向や特徴を客観的に知ることができ、短所のヒントに役立ちます。
自分の苦手なところから探す
短所を見つけるための最も基本的で効果的な方法は、自分が苦手だと感じることや、過去にうまく対処できなかった経験を振り返ることです。
例えば、グループでの意見調整が苦手で対立を避けてしまったり、締め切りに間に合わず焦った経験があれば、その場面での自分の行動や気持ちを細かく分析してみましょう。
なぜうまくいかなかったのか、何が自分にとって難しかったのかを具体的に考えることで、自己の短所が浮かび上がってきます。
苦手なことに正面から向き合うのは簡単ではありませんが、そこにこそ成長のヒントが隠されています。
苦手を認めることは、自分の弱さを受け入れる勇気であり、自己理解の第一歩です。
さらに、苦手な部分を自覚することで、どのように改善すれば良いか具体的な行動計画を立てることができます。
たとえば、コミュニケーションが苦手ならば、意識的に人と話す機会を増やしたり、話し方の研修を受けたりするなどの対策が考えられます。
また、苦手なことに直面した際の失敗体験や反省点は、面接やエントリーシートで短所を伝える際に説得力のあるエピソードになります。
単なる抽象的な短所ではなく、具体的な場面を交えて話すことで、人事担当者に誠実さや成長意欲をアピールできるのです。
このように自分の苦手なところから短所を探すことは、自己理解を深めると同時に、効果的な自己PRの材料を見つける手段として非常に有効です。
長所を裏返す
短所は、しばしば自分の長所の裏返しとして現れます。
例えば、責任感が強い人は仕事を完璧にこなそうとするあまり、細部にこだわりすぎてしまい、融通が利かないと評価されることがあります。
また、慎重な性格の人は、物事をよく考える反面、決断が遅れるという短所が生まれやすいです。
このように、長所と短所は表裏一体であり、どちらも自分らしさの一部と言えます。
この視点を持つことで、短所を単なるマイナス面として捉えるのではなく、長所の強みを活かしながら改善すべき点として理解できます。
たとえば、几帳面さが過剰になると細かいことにこだわりすぎる短所になるが、その几帳面さが仕事の品質を高める長所にもなり得ます。
こうしたバランス感覚を持つことは、面接での自己PRにも役立ちます。
さらに、長所の裏返しという考え方は、自己分析の幅を広げるきっかけにもなります。
自分の強みだけでなく、その裏に潜む課題を見つけ出すことで、よりリアルな自己理解が可能になります。
そして、その短所に対して具体的にどう取り組んでいるかを伝えられれば、成長意欲の高さも示せます。
短所と長所をセットで理解し伝えることが、説得力のある自己PR作成に欠かせないポイントです。
診断ツールを使用する
自分ではなかなか気づきにくい短所を見つけるには、性格診断や適性検査といった診断ツールを活用するのも非常に有効です。
エニアグラム、16パーソナリティ、ストレングスファインダーなど、多様な診断方法があり、自分の性格傾向や行動パターンを客観的に把握できます。
これらのツールは、自分が無意識に取っている行動や感じ方のクセを明らかにし、改善すべき点のヒントを与えてくれます。
診断ツールは結果に一喜一憂するものではなく、自己理解を深めるための参考資料として使うことが大切です。
診断結果をもとに、家族や友人、同僚など信頼できる第三者に意見を聞くことで、自分の特徴を多角的に把握できます。
第三者の視点からのフィードバックは、自分では気づきにくい短所を教えてもらう貴重な機会です。
また、診断ツールを通して得た自分の性格や行動パターンを理解することで、面接での自己PRや短所の伝え方にも説得力が生まれます。
例えば「完璧主義で細かいところまでこだわりが強い」といった結果が出た場合、その短所をどう仕事に活かし、どのように改善しているかを話すことができます。
こうした具体的なエピソードが面接官の印象に残りやすくなります。
【短所の見つけ方】その他の短所が見つかる自己分析方法
短所は自分一人で探すのが難しい場合もあります。
自己理解を深めるためには、多角的な方法で自分と向き合うことが重要です。
ここでは、自分の短所を見つけるために役立つ5つの具体的な自己分析方法を紹介します。
これらを組み合わせて活用することで、思い込みや偏りを防ぎ、より正確に自分の課題や特徴を把握できるようになります。
①一覧表から選ぶ
短所を見つける第一歩として、「短所一覧表」などのリストから選ぶ方法は非常に有効です。
思いつきに頼るのではなく、あらかじめ用意された多くの選択肢から気になるものをピックアップすることで、自分でも気づかなかった側面を発見できます。
特に、「優柔不断」「飽きっぽい」「神経質」など、一見ネガティブに聞こえる言葉も、適切に説明すれば誠実さや繊細さといった強みに変えられます。
気になるキーワードをいくつかピックアップし、過去の経験に照らして「そういえば自分もこうだったかもしれない」と掘り下げていくことで、具体的なエピソードにもつながっていきます。
特定の職種や業界においては許容される短所もあるため、一覧表を見ながら「自分に当てはまるか」「面接官にどう映るか」を想像しながら進めることがコツです。
②長所を書き出す
自分の短所がどうしても見つからない場合は、逆に長所を書き出してみるのも効果的なアプローチです。
なぜなら、長所と短所は表裏一体の関係にあるからです。
たとえば、「計画的に物事を進められる」という長所を持つ人は、裏を返せば「急な変化に弱い」や「柔軟性に欠ける」といった短所を持つ可能性があります。
自分の良い面をできるだけたくさんリストアップし、それぞれに対して「もし悪く出たらどうなるか?」と考えてみることで、自然と短所が見えてくるでしょう。
この方法の良いところは、短所に対するネガティブなイメージが減ることです。
もともと自分の強みだったものが原因で起こる課題であれば、それを受け入れ、今後どう補っていくかという前向きな視点が持てます。
③他己分析をする
自分では気づかない短所は、他人の視点を借りることで見えてくることがあります。
家族や友人、アルバイトの同僚、ゼミやサークルの仲間など、普段から接点のある人に「私の短所ってどんなところだと思う?」と率直に聞いてみましょう。
意外と自分が気にしていない行動や口癖などが、周囲には短所として映っている場合があります。
また、指摘された内容が思い当たる節だったときには、その場面を振り返ることで、改善点や短所として言語化できる材料が得られます。
注意点としては、質問する相手は信頼できる人に絞ること、そして指摘に対して防御的にならず、受け止める姿勢を持つことです。
他己分析は、自分の視野を広げるだけでなく、人間関係における自分の立ち位置や特徴を再発見する良い機会にもなります。
④モチベーショングラフを書く
モチベーショングラフとは、人生の中でモチベーションが上がったり下がったりした出来事を時系列で整理したグラフのことです。
縦軸にモチベーションの高さ、横軸に年代や時期を取り、グラフ化することで自分の心の動きや変化が可視化されます。
グラフが大きく落ち込んだ場面や、モチベーションが上がらなかった場面には、自分の苦手な状況や短所が関係していることがあります。
たとえば「集団での議論についていけなかった」「責任のある立場で緊張しすぎてしまった」といった体験から、自分が緊張しやすい、または周囲に頼れないという傾向を発見できることもあります。
モチベーショングラフは、表面化していなかった感情を掘り起こすきっかけとなり、短所を内面から理解することにつながります。
また、どんな場面でやる気を失いやすいかを客観視できるため、今後の対策も立てやすくなります。
⑤自分史をまとめる
最後に紹介するのは、自分史をつくるという方法です。
小学校から現在に至るまでの出来事を、成功体験だけでなく失敗体験やつまずいた場面も含めて振り返り、文章としてまとめてみます。
特に、困難だった場面で自分がどのように感じ、どう行動したかを詳細に書き出すことで、自分の思考パターンや苦手傾向が浮かび上がってきます。
たとえば「人前で意見を言うのが苦手だった」「指摘されると過剰に反応してしまう」といった、自分にしかない短所の芽が見えてくるのです。
自分史をつくる作業には時間がかかりますが、これまでの人生を俯瞰的に見ることで、性格や価値観の変化にも気づけます。
さらに、その過程で得た気づきは、ESや面接での説得力のある自己PRにもつながります。
短所だけでなく、自分の成長プロセスを語るうえでも非常に有益な方法です。
【短所の見つけ方】短所を言語化する方法
短所を伝えるためには、自分の中にある曖昧な「苦手意識」や「行動の癖」を、他人にも伝わる明確な言葉に変える必要があります。
そのためには、感情や行動のパターンを観察し、思考を整理しながら、自分自身の性格的傾向を言語化するプロセスが不可欠です。
この過程を経ることで、単なる自己否定ではなく、成長意欲や人柄の一部としての「短所」を相手に伝えることができます。
以下の4ステップで解説します。
1.物事の観察
短所を言語化する第一歩は、自分の行動や感情のパターンを日常の中で観察することです。
短所は突然現れるものではなく、日々の選択や反応の積み重ねの中に現れます。
たとえば、会議で意見を求められた際に毎回黙ってしまう、やるべきことを先延ばしにして後悔する、相手の顔色を過度に気にして疲れる、など、些細なことに見えても、自分の傾向を映し出す重要な手がかりです。
この段階では、「良い悪い」という評価はひとまず置いておきます。
目的は、自分自身のパターンを把握することです。
そのためには、感情が動いた場面や、上手くいかなかった経験を振り返り、何が起きて、どう感じ、どんな行動を取ったのかを書き出してみると効果的です。
特に、「同じような失敗を何度も繰り返している」「なぜか毎回うまくいかない」と感じるシーンは、短所のヒントが眠っている可能性が高いです。
このように、自分の行動や反応を客観的に観察することで、日常の中に埋もれている「短所の種」に気づくことができるのです。
2.思考・整理
行動や感情を観察して見つけたパターンを、そのまま短所として伝えるにはまだ不十分です。
次のステップでは、それらの出来事の背景にある「考え方のクセ」や「性格傾向」を整理する必要があります。
たとえば、「人前で話すのが苦手」という行動の裏には、「失敗したくない」「完璧に話さなければならない」という思考パターンがあるかもしれません。
このように、自分の行動の背後にある「なぜ?」を探ることで、より本質的な短所が見えてきます。
感情や行動を単に記録するだけでなく、それを引き起こした内面の反応を理解しようとする姿勢が重要です。
頭の中だけで整理しようとすると曖昧になりがちなので、紙に書き出したり、マインドマップのように視覚的にまとめるのも効果的です。
また、複数のエピソードを並べてみると、「共通するパターン」が浮かび上がってきます。
「優柔不断」「心配性」「遠慮しがち」など、自分に合った言葉を探すヒントにもなります。
このステップは、短所を「一時的なミス」ではなく「自分らしさの一部」として捉える上で欠かせません。
3.言葉への変換
思考の整理ができたら、それを他者に伝わる言葉に落とし込んでいきます。
ここで大切なのは、抽象的すぎる言葉や、曖昧な表現を避けることです。
たとえば「自分に自信がない」ではなく、「新しいことに挑戦する場面で躊躇してしまう」と具体的に言い換えることで、聞き手にとっても理解しやすくなります。
また、「短所=悪いこと」と捉えず、行動に結びつく形で表現することが望ましいです。
たとえば「完璧主義すぎる」→「細部にこだわりすぎて全体の進行が遅れてしまうことがある」といった具合に、自分の傾向を明確に示します。
自分で言葉を作るのが難しい場合は、短所一覧表や就活サイトの例文集を参考に、自分に合った言い回しを見つけるのも一つの手です。
ただし、どんなに上手な言い回しでも、自分の体験や性格とズレていれば逆効果です。
自分の実感に基づいた表現を選ぶことが、信頼性のある短所として伝えるために欠かせません。
言語化の目的は、取り繕うことではなく、自分を理解してもらうことです。
4.相手が理解しやすい表現
最後のステップは、伝える「相手」を意識して表現を整えることです。
就活で短所を聞かれる場面の多くは、面接やエントリーシートなど、評価される状況です。
そのため、単に短所を述べるのではなく、「短所をどのように受け止め、改善しようとしているか」までを含めて語ることが求められます。
たとえば、「優柔不断です」とだけ言ってしまうと、マイナス印象で終わってしまいますが、「慎重に考えすぎて決断に時間がかかることがあります。
ただ、最近はまず行動してから軌道修正することも大事だと意識するようになり、以前より判断が早くなりました」と続けることで、成長の姿勢が伝わります。
また、伝える言葉には、自分がどんな人物であるかを相手がイメージできるような「具体性」と「誠実さ」が必要です。
あまりにも前向きすぎて現実味がない表現や、実体験のない改善エピソードは逆効果になりかねません。
相手にとって分かりやすく、かつあなたらしさが伝わる短所の伝え方は、「等身大の自分を前向きに受け入れている」ことを示す絶好の機会です。
最終的には、短所を語ることを通して、あなたの人柄や価値観が伝わるように工夫しましょう。
【短所の見つけ方】伝え方について
短所を伝える際は、単に自分の欠点を並べるだけでなく、相手に理解されやすく、かつ前向きな印象を与える工夫が必要です。
自己分析を踏まえた上で、なぜその短所が現れるのか理由を明確にし、具体的なエピソードを交えて伝えることで説得力が増します。
さらに、改善に向けた取り組みや成長意欲も合わせて示すことで、短所を成長のチャンスとして印象づけることが可能です。
適切な伝え方で、自分の魅力を引き出しましょう。
P(結論)
短所は、選考においてあえて隠すべきものではなく、素直に伝えた方がかえって好印象につながることが多いです。
なぜなら、企業が短所を質問する目的は、その人の欠点をあぶり出すためではなく、自己理解の深さや、課題に向き合う姿勢を知るためだからです。
つまり、短所そのものよりも、それにどう向き合っているのか、どう改善しようとしているのかを見ています。
そのため、無理に「短所はありません」や「完璧主義です」などと伝えるよりも、自分なりに苦手な部分を言語化し、誠実に伝えることで、信頼感が生まれます。
短所を伝えることは、自分の課題を理解し、成長しようとしている姿勢を見せることにもつながります。
自己理解の深さや成長意欲の高さを伝えるためにも、短所は正直に、そして前向きに伝えることが大切です。
R(理由)
短所を正しく伝えることによって、あなたの人間性や成長力が評価されやすくなります。
採用担当者は、どんな人にも弱みや苦手なことがあるという前提で面接をしています。
その中で、自分の短所に気づいていない、あるいはそれを言語化できない応募者は、自己分析が不十分と判断されやすく、信頼性を欠くと受け取られてしまうこともあります。
一方で、短所をきちんと伝えた上で、それを改善するために工夫しているエピソードや努力の過程を示すことで、あなたが自分を客観的に見て成長を志向している人物であることを印象づけられます。
短所を隠すのではなく、どう向き合っているかを語ることで、単なる欠点ではなく「伸びしろ」としてアピールすることができます。
その結果、信頼感が高まり、「この人なら入社後も成長してくれるだろう」と思ってもらえるのです。
E(エピソード)
エピソードは、短所を伝える際に説得力を高める重要な要素です。
単に「短所は〇〇です」と言うだけでは、面接官に実感が伝わりにくいため、具体的な経験を交えて話すことで、自分の課題や改善努力を具体的に示せます。
例えば、短所が「マイペース」なら、グループ作業で自分のペースで進めた結果、チームに迷惑をかけたエピソードを話し、その後どのように改善したかを説明します。
エピソードを用いることで、短所がただの欠点でなく、自己理解の結果であることや成長のプロセスが伝わりやすくなります。
また、具体的な事例は記憶に残りやすく、面接官の印象に強く残る効果もあります。自分の言葉で、具体的な状況や行動、そこから得た学びを分かりやすく伝えることが大切です。
P(結論)
短所を伝えることは、ネガティブな要素をさらけ出すことではなく、自分をより深く理解し、成長する意欲があることを示すチャンスです。
面接やエントリーシートで短所を問われたときは、自分なりの課題を明確にし、それに対してどのように向き合ってきたのかを丁寧に伝えることが大切です。
伝える際には、単なる「欠点」として語るのではなく、「改善のために取り組んでいること」や「学んだこと」をセットにすることで、前向きな印象を与えられます。
PREP法を活用して、結論・理由・エピソード・再結論の流れを意識することで、論理的かつ説得力のある短所の伝え方が可能になります。
短所を隠さずに、成長意欲を伝える手段としてポジティブに活用していきましょう。
【短所の見つけ方】例文
短所はネガティブに見えがちですが、工夫次第で誠実さや成長意欲を伝える絶好の機会になります。
ここでは、「マイペース」「頑固」「心配性」といった一般的な短所を取り上げ、それぞれの伝え方例文を紹介します。
PREP法を活用し、論理的に伝えることで、自分の特性をポジティブに印象づけることができます。
マイペース
私の短所はマイペースなところです。
他人と比較して行動を急がないため、周囲との歩調が合わないと感じられる場面がありました。
特にチームで協力して作業する際には、自分のペースで物事を進めようとしすぎてしまい、全体の進行に影響を与えることがありました。
大学のグループワークでは、資料作成に時間をかけすぎた結果、他メンバーとのすり合わせが遅れてしまい、相手に不安を与えてしまったことがあります。
その経験から、私は周囲との情報共有を頻繁に行い、進捗を確認し合う習慣をつけるよう努めました。
また、自分の作業スピードが遅めであることを認識したうえで、余裕を持ったスケジュールを設定し、チームの足を引っ張らないよう心がけています。
今では、マイペースさを活かして、冷静で安定した判断力が求められる場面で力を発揮できるようになりました。
これからも周囲との連携を大切にしながら、自分らしさを活かしていきたいと考えています。
頑固
私の短所は頑固なところです。
一度決めたことに固執してしまい、周囲の意見を柔軟に受け入れるのが難しいときがあります。
大学のゼミ活動では、自分の仮説に自信があったため、他のメンバーの異なる視点をうまく受け入れられず、議論が停滞してしまった経験があります。
そのときに、指導教員から「一人で考えるのではなく、全体で答えを探すことも大切だ」と助言をいただき、チームワークの重要性に気づきました。
以来、自分の意見を主張する前にまず相手の意図を理解するよう心がけ、他者の意見に対しても「なぜそのように考えたのか」を掘り下げる姿勢を意識するようになりました。
頑固さが時に芯の強さとして評価される一方で、柔軟な姿勢を身につけることで、より多様な意見に耳を傾けられるようになったと感じています。
今後も、自分の考えを持ちながらも、チームとして最適な結論を導けるよう努めていきたいと考えています。
心配性
私の短所は心配性なところです。
物事に対して必要以上に準備をしてしまい、結果として行動までに時間がかかってしまう傾向があります。
例えばアルバイト先でイベントの準備を任された際、念のために備品を何度も確認しすぎてしまい、他の作業の準備が遅れてしまったことがあります。
その経験から、自分の心配性は「念には念を入れる」という長所にもつながる一方で、優先順位を見誤る可能性もあると気づきました。
そこで、行動前にタスクを整理し、どこまで準備が必要かをあらかじめ明確にするようにしました。
また、不安になったときには周囲に相談することで、過剰な準備に陥らずに済むよう心がけています。
現在では、丁寧さを保ちつつもスピード感を意識した行動ができるようになり、同僚からも「安心して任せられる」と言われるようになりました。
今後も、心配性の特性を冷静な判断力に変換し、より的確な行動につなげていきたいと考えています。
【短所の見つけ方】まとめ
短所は自分の弱点を正直に伝えるものではありますが、それ以上に「自分をどう理解し、どう成長させようとしているか」を示すチャンスでもあります。
苦手なことや行動の癖を丁寧に振り返り、長所との関係性や改善の姿勢を含めて伝えることで、単なるマイナス要素ではなく、ポテンシャルとして受け取ってもらえる可能性が高まります。
自分の経験を振り返り、客観的に捉える習慣が、納得感のある短所の言語化につながります。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート