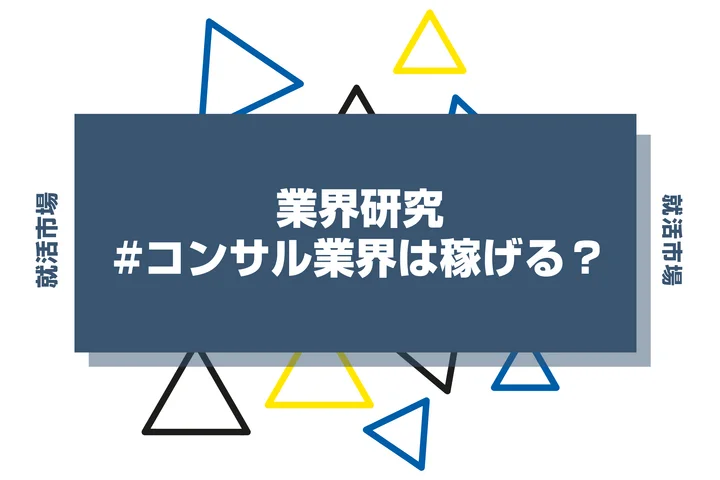はじめに
「コンサル業界が稼げるのは本当?」
「コンサルに就職して高年収を目指したい」
「コンサルに就職するために必要なスキルは?」
上記のように、コンサル業界に強い入社意欲を持った就活生は多いでしょう。
コンサル業界は、単価が高い仕事になるため、必然的に年収も高くなります。
この記事では、コンサル業界が稼げる理由と制度、仕事内容について解説します。
【コンサル業界は稼げる】年収の実態
コンサルは、深い専門知識と付加価値の高さから、高年収になりやすい業界です。
また、成果主義であるため、新卒からでも高年収が狙えます。
とくにM&Aや人事コンサルタントのような、経営の根幹に関わる職種は高年収です。
本章では、コンサル業界の年収の実態について解説します。
年収に重きをおいている就活生は、ぜひ最後までご覧ください。
他業界と比較したり、同業他社で迷ったりした際に役立ちます。
平均年収と他業界との比較
コンサルの平均年収は以下の通りです。
厚生労働省が運営するjobtagが公表しているデータを参考にし、表を作成しています。
| 職種名 | 平均年収 |
| ITコンサルタント | 752.6万円 |
| M&Aコンサルタント | 902万円 |
| 広報コンサルタント | 591万円 |
| 人事コンサルタント | 903.2万円 |
| 経営コンサルタント | 903.2万円 |
職種によってばらつきはあるものの、コンサルの年収は約600〜900万円になります。
国税庁が公表した令和5年分民間給与実態統計調査では、日本の平均年収は460万円です。
つまり、コンサル業界の年収は一般的な職種の平均額より大きな数字になります。
参考:職業情報提供サイトjobtag|厚生労働省
参考:令和5年分民間給与実態統計調査|国税庁
新卒からでも高年収を目指せるのか
コンサルは、新卒からでも高年収が目指せる業界です。
コンサル転職に特化した株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアが公表した記事では、新卒の年収は約400万円〜600万円でした。
一方で、厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると大卒の初任給平均は約24万8千円です。
大学院卒は大卒より多く約28万7千円になります。
年収に換算すると大卒が約297万円、大学院卒は約344万円です。
つまり、コンサル業界は、新卒の時点から高年収の業界です。
ただし、平均年収はどの職種に就くか、残業時間、賞与の有無などで大きく変化します。
そのため、あくまで参考程度に留めてください。
参考:【コンサル初任給ランキング】新卒コンサルタントはいくらもらってる?|株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
参考:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
成果主義と職位別の給与構造
コンサル業界は、成果主義かつ職位別の給与構造になっているため、高年収を獲得するチャンスがあります。
コンサル業界は、結果さえ残せれば年齢や入社年数に関係なく、評価される業界です。
さらに、活躍に応じて役職もアップします。
役職が上がれば、基本給も上がるため、必然的に年収が高くなります。
コンサル業界の役職は、アナリストからコンサルタントやマネージャー、ディレクターなどです。
役職が1つ上がるだけでも100万円単位で年収が変わります。
新卒の若手であっても、早期から活躍し、成果を残すことで高年収に近づけるでしょう。
【コンサル業界は稼げる】高収入の職種トップ7
コンサル業界は、職種によって得られる年収が変わります。
コンサル業界のなかでも、とくに高収入が稼げる職種を7つ紹介します。
「自分の価値観にあった職種に就きたい」「自分の強みを活かしたい」と考えている就活生は、ぜひ参考にしてください。
確かに年収は大切ですが、自分の気持ちも大切にしましょう。
適切な職種を選ぶことで、安定した状態での高収入が見込めます。
戦略コンサルタント
戦略コンサルタントは、企業の最も根幹をなす経営戦略の策定を支援する職種です。
たとえば、新規事業参入やM&A戦略、グローバル展開、事業ポートフォリオの見直しなどです。
企業の将来を左右する高付加価値かつ、大きな責任がともなう業務が中心です。
徹底した市場分析から競合分析や財務分析を通じて、クライアントが成長できる箇所を発見し、具体的なアクションプランを提案します。
扱うテーマが企業の存亡に関わるほど重要であるため、プロジェクトは高単価です。
その分、高度な論理的思考力や分析力、コミュニケーション能力が求められます。
これらの特性から、コンサル業界のなかでも年収は常にトップクラスです。
ITコンサルタント
ITコンサルタントは、企業のIT戦略立案からシステム導入、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進など、ITとビジネスの橋渡し役を担います。
単なるシステムエンジニアとは異なり、クライアント企業の経営課題をITの側面から解決することが仕事です。
最新のテクノロジー動向を把握しつつ、業務プロセス変革や新たなビジネスモデル構築に貢献するため、ITに関する深い専門知識が求められます。
さらに、クライアントのビジネスへの理解力や課題解決能力が不可欠です。
近年、DXの加速により需要が急増しており、技術とビジネスの両面を理解する専門性が、高収入に直結する職種として注目されています。
総合系コンサルタント
総合系コンサルタントは、戦略立案からITシステム導入や組織・人事改革、業務プロセス改善など、幅広い領域をカバーする存在です。
特定の専門分野に特化せず、クライアント企業の抱える多様な課題に対して、包括的な解決策を提供します。
プロジェクトごとに異なる業界やテーマに携わる機会が多く、さまざまなスキルや知識を横断的に習得できる点が大きな魅力です。
とくに、キャリアの初期段階で幅広い経験を積むことで、自分の専門性を見つけたり、将来的に独立したりする道が開けます。
総合系コンサルタントは、キャリアパスの多様性から、着実にスキルアップし、年収を高められる職種です。
財務・会計コンサルタント
財務・会計コンサルタントは、企業の財務戦略やM&A支援、企業再生などを担当する仕事です。
ほかにも、事業再編や企業価値評価、不正会計調査など、高度な財務・会計知識を駆使してクライアントを支援します。
とくにM&Aや企業再生といった案件では、複雑な会計処理や税務、法務といった専門知識が必要です。
深い知識を活用し、課題を解決することで、給与に反映されます。
また、企業の資金調達や投資判断に大きな影響を与えるため、責任は大きいです。
しかし、案件の規模や難易度に応じて高額なインセンティブが得られる傾向にあります。
活躍するには、公認会計士やMBAなどの資格があると効果的です。
人事・組織コンサルタント
人事・組織コンサルタントは、クライアント企業の人と組織に関する課題解決が専門です。
具体的には、人事制度設計(評価制度、報酬制度など)や組織開発、リーダーシップ開発、人材育成、組織文化変革などが挙げられます。
企業が持続的に成長するためには、優秀な人材の確保と育成、そして組織全体の活性化が不可欠です。
そこで、人事・組織コンサルタントは、企業の根幹を支える役割を担います。
しかし、社員のモチベーションを向上させたり、新しい価値観を定着させたりするのは困難です。
一方で、人材は企業の競争力強化に直結するため、専門性と貢献度は高く評価され、相応の報酬が期待できます。
医療・ヘルスケアコンサル
医療・ヘルスケアコンサルタントは、病院や製薬会社などに対し、経営戦略から新規事業開発、業務効率化、デジタル化推進をコンサルティングします。
ほかにも、医療機器メーカーや政府機関を支援することもあります。
医療分野は、高度な専門知識(医療制度、薬事法規、疾患理解など)が不可欠です。
そのため、さまざまな企業を支援するコンサル業界であっても参入障壁が高くなります。
しかし、高齢化社会の進展や医療技術の進化により、市場規模が拡大している状況です。
そこで、医療分野への専門性の高いコンサルタントへの需要が高まっています。
医療・ヘルスケアコンサルは、社会貢献しながら高付加価値サービスを提供できるため、仕事のやりがいと収入の両方を追求できる職種です。
リスクマネジメントコンサル
リスクマネジメントコンサルタントは、企業が直面するさまざまなリスクを特定し、対策を立案・実行する職種です。
主に不正アクセスやサイバーセキュリティ、自然災害、コンプライアンス違反、法的リスクなどが挙げられます。
実際の業務としては、内部統制システムの構築やガバナンス強化、危機管理体制の整備、不正調査、情報セキュリティ対策などです。
企業の評判や存続に関わる重大なリスクを未然に防ぎ、あるいは発生時の影響を最小限に抑えなければなりません。
そのため、リスクマネジメントコンサルは、法的知識や倫理観、危機管理能力が必要です。
業務の責任は大きいですが、企業価値の低下を防ぐ役割は非常に高く評価され、高収入につながる傾向があります。
【コンサル業界は稼げる】なぜ稼げるのか?仕組みを解剖
コンサル業界は、販売する商品の単価が高いため、社員の年収も比例して高くなります。
しかし、適当な商品を販売しているわけではありません。
高い単価に見合った専門性や知識をクライアントに提供します。
本章では、コンサル業界がなぜ稼げるのかについて、詳しく解説します。
コンサル業界の仕組みを理解することは、選考を突破するうえで欠かせません。
コンサル業界を志望する就活生は、ぜひ参考にしてください。
クライアント単価が高いビジネスモデル
コンサルティング業界の大きな特徴は、クライアントから受け取る報酬が非常に高額であることです。
一般的な企業は、商品やサービスを一つ売るときの値段が決まっています。
たとえば、メロンパンは150円、あんぱんは130円などです。
しかし、コンサル業界は、特定の企業の大きな悩みを解決するために、数週間から数ヶ月、時には数年かけて専門家チームが取り組みます。
特定の企業のためだけのオーダーメイドの解決策には、数千万円から数億円といった非常に高い価値がつけられます。
その結果、社員はこの高額な報酬の一部を給料として受け取るため、年収も自然と高くなる仕組みです。
専門性と知的労働に対する対価
コンサルタントは、特定の分野について深い知識や複雑な問題を整理して解決する特別なスキルを持っています。
たとえば、会社の戦略やITシステム、人事の仕組みなどです。
企業が自分で解決できないような難しい問題に直面したとき、コンサルタントは身につけた深い知識とスキルを使って、最適な解決策を見つけ出します。
コンサルタントが提供する商品は、ただ物を売る仕事ではなく、頭を使って知恵を出すという知的労働です。
つまりクライアントは、高度かつ専門的な知恵を得る対価として高いお金を払うため、コンサルタントの年収も高くなります。
コンサル業界が、理由もなく高い金額を要求しているわけではないため、勘違いしないようにしてください。
プロジェクト型で成果が明確
コンサルタントの仕事は、通常「プロジェクト」という形で進められます。
クライアントの課題解決に必要な人材をイチから集めるからです。
たとえば、新事業を始めるための計画を作るといったプロジェクトがあったとします。
クライアントの事業計画によって、いつまでに何をどのように進めるかがあらかじめ決められています。
そして、プロジェクトが終わる頃には新事業計画書が、目に見える成果物がクライアントに納品されます。
つまり、自分たちが何を成し遂げ、クライアントに対してどう貢献したかが可視化されます。
その結果、コンサルタント一人ひとりの働きぶりが評価されやすく、給料やボーナスに直結しやすい仕組みになっています。
【コンサル業界は稼げる】収入を伸ばすために必要なスキル
コンサル業界で収入を伸ばすために必要なスキルは、以下の3つです。
論理的思考力と課題解決力
クライアント対応力と信頼構築力
専門知識と継続的な学習姿勢
コンサル業界は、高い収入を得るには、相応のスキルを身につける必要があります。
「新卒から活躍して収入をアップさせたい」と考えている就活生は、目標達成の足がかりにしてください。
スキルを身につける方法も解説するので、最後まで読むことをおすすめします。
論理的思考力と課題解決力
コンサルタントとして収入を伸ばすには、論理的に考え、問題を解決する力が重要です。
クライアントが抱える課題は千差万別です。
似たような事例はあっても、まったく同じ状況の企業はありません。
そこで、クライアントの課題を見つけ出すのに論理的思考力が求められます。
さらに、課題に対して、具体的な解決策を導き出すのに課題解決力が必要です。
これらのスキルがあれば、どんなに難しい状況でも、冷静に状況を分析し、最適な答えを導き出せるでしょう。
論理的思考力と課題解決力は、コンサルタントとしての土台です。
まずは、しっかりと身につけることで、高い報酬につながる案件が担当できます。
クライアント対応力と信頼構築力
コンサルタントには、クライアント対応力と信頼構築力も欠かせません。
クライアントに最適だと考える解決策を伝えても、受け入れてもらえなければ意味がありません。
そのため、クライアントの気持ちを理解し、信頼関係を築く力は収入アップに不可欠です。
たとえば、クライアントの言葉の裏にある本当のニーズをくみ取れば、安心して任せられる存在になれます。
その結果、次の仕事にもつながります。
また、クライアントとの人間関係をスムーズにし、「この人に任せれば大丈夫」と思わせるコミュニケーション能力や細やかな気配りも重要です。
信頼を積み上げた先に、より大きなプロジェクトや長期的な関係性を生み出し、高収入へとつながります。
専門知識と継続的な学習姿勢
コンサルタントで高収入を得るには、専門知識と継続的な学習姿勢が必要です。
特定の分野における深い専門知識を持っているコンサルタントは、非常に重宝されます。
たとえば、財務やIT、法務などに関する知識などです。
専門知識があれば、より難易度が高く、単価の高い案件を担当できるようになります。
しかし、知識だけでは不十分です。
世の中は常に変化しており、新しい技術や情報、法改正などが次々と生まれます。
そのため、常に学び続け、知識をアップデートしていく継続的な学習姿勢が非常に大切です。
高い専門性と学習意欲が、コンサルタントとしての市場価値を高め、結果として収入を大きく伸ばす要因になります。
【コンサル業界は稼げる】仕事のリアルと業界の特徴
続いて、コンサル業界のリアルと特徴について解説します。
コンサル業界は、成果主義の世界です。
そのため、年齢や勤続年数よりも成果が重要視されます。
「コンサル業界で早くから活用したい」と考えている就活生は、本章の解説が役に立つでしょう。
コンサル業界の特徴を理解することで、適切な対策ができます。
その結果、スムーズに選考が突破できるでしょう。
成果主義で昇進スピードが速い
コンサル業界は、年齢や入社時期に関係なく、個人の働きぶりや成果によって評価される成果主義が根付いています。
あなたがどれだけ会社に貢献し、クライアントに良い結果をもたらしたかが、昇進や昇給の決め手となります。
たとえば、20代のうちからマネージャーになることも珍しくありません。
役職が上がれば、それに応じて任される仕事の責任も大きくなりますが、年収も大幅にアップします。
自分の成果が直接年収に反映されるため、高いモチベーションを保つことが可能です。
コンサル業界は、早くから高収入を目指せるのが大きな特徴です。
勤務時間が長く体力勝負になりやすい
コンサル業界は、勤務時間が長くなりがちで、体力や気力が必要になる場面が多いです。
クライアントの課題解決というゴールに向かって、短期間かつ集中的に働くからです。
とくにプロジェクトが忙しい時期や締め切りが迫っている時には、夜遅くまで働いたり、休日出勤が必要になったりすることもあります。
また、プロジェクトの進捗状況やクライアントの要望によってスケジュールは大きく変わるため、常に柔軟に対応しなければなりません。
もちろん、残業代や代休を取得することは可能です。
しかし、年収ばかりを追い求めると体調を崩すかもしれません。
そこで、高収入に魅力を感じた就活生は、忙しさがあることを考慮し、健康管理やストレス解消の方法も用意しておきましょう。
成長環境とプレッシャーの両立
コンサル業界は、短期間で非常に多くのことを学び、大きく成長できる環境です。
さまざまな業界の企業や多様な課題に触れることで、幅広い知識や問題解決スキルが身につきます。
その反面、常に高いレベルの成果が求められるため、大きなプレッシャーが存在します。
クライアントの期待を超えるように提案したり、難しい課題を解決したりするには、ベストを尽くす必要があります。
ほかにも、上司やメンバーからのプレッシャーは精神的に苦労するでしょう。
しかし、プレッシャーを乗り越えることで、自分の能力を最大限に引き出し、より早く成長することが可能です。
自分の成長意欲とプレッシャーを比較し、乗り越えられる環境か見極めておきましょう。
【コンサル業界は稼げる】福利厚生や社風は?
コンサル業界の福利厚生は高待遇です。
また、社員の成長を促す環境や制度が充実しています。
社風としては、実力社会が挙げられます。
高収入を得るには、見合った成果を残さなければなりません。
本章では、コンサル業界の福利厚生、社風の側面から解説します。
職種や特徴に加えて、上記の2点も理解しておきましょう。
競合他社と比較したり、複数社から内定をもらったりした場合の判断材料になります。
外資系は高年収だが成果主義が強い
外資系のコンサルティング企業は、その名の通り海外に本社を持つ企業がほとんどです。
日本企業と比較して、高い年収が期待できる点が大きな特徴です。
しかし、高い報酬に見合うような成果主義が徹底されています。
どれだけ企業に貢献し、クライアントに具体的な結果を出したかが、年収や昇進に反映する考え方があるからです。
年齢や勤続年数は関係なく、個人の実力が重視されるため、若くても大きな成果を出せばどんどん昇進できます。
一方で、結果が出なければ厳しい評価を受けることもあり、常に高いパフォーマンスが求められる実力勝負の世界といえます。
「自分の力を試したい」「もっと成長したい」と考える就活生は、挑戦する価値がある業界です。
日系大手は教育制度や長期育成が充実
日系のコンサルティング企業、とくに大手企業では、社員をじっくり育てていく長期育成の考え方が強い傾向にあります。
外資系企業にはない考え方です。
長期育成は、日本の企業文化に根ざした仕組みです。
新入社員が段階的にスキルを身につけられるよう、充実した教育制度や研修プログラムが用意されています。
また、未経験でコンサル業界に入った人でも、体系的な学びを通じて着実に成長できる環境が整っています。
すぐに大きな成果を求められる可能性は低いです。
時間をかけてコンサルタントとしての基礎を固め、将来的には企業の中心として活躍できる人材になることが求められます。
ただし、外資系企業と比較した場合の仕組みです。
一般的な日本企業と比較すると、やはり実力かつ成果主義の文化が強くなるため注意してください。
資格取得支援や表彰制度の有無
コンサル業界は、資格取得を支援する制度が充実している企業が多く存在します。
社員の専門性を高め、より多くの成果を残してもらうためです。
たとえば、MBA(経営学修士)の取得費用を補助したり、会計士や税理士、IT関連の専門資格などの受験費用を負担したりするケースがあります。
これは、社員一人ひとりのスキルアップが、企業全体の提供価値向上につながるという考えが根付いているからです。
また、優れた業績を上げた社員やチームを表彰する制度を設けている企業も多く、努力や成果が正当に評価され、報われる仕組みが整っています。
これらの制度は、社員のモチベーション向上にもつながる重要な福利厚生になります。
【コンサル業界は稼げる】向いている人・向いていない人
コンサル業界は高年収が得られるものの、ハードワークが予想されます。
「仕事一筋で頑張りたい」「大きな成果を出したい」のような強い気持ちを持っておく必要があります。
もし、ワークライフバランスを重要視する場合、コンサル業界とは価値観が合わないかもしれません。
本章では、コンサル業界に向いている人と向いていない人について解説します。
自分がコンサル業界に適した人材か、確かめる材料にしてください。
成果主義の環境にモチベーションを感じられる人
成果主義の環境にモチベーションを感じられる人は、コンサル業界に向いています。
コンサル業界は、年齢や経験よりも、あなたがどれだけの成果を出したかが重要です。
「頑張った分だけ評価されたい」「若いうちからレベルの高い仕事がしたい」と考える人に適した環境です。
さらに、成果が直接的に昇進や収入に結びつくため、仕事のやりがいにもつながります。
ただし、常に能力を試され、結果を出すことが求められる業界です。
逆境やプレッシャーを乗り越えるためには、高い目標と日々の努力が欠かせません。
そのため、高い向上心と競争心を持つ人が大きく成長し、成功を収められるでしょう。
ハードワークや変化を楽しめる人
コンサルタントの仕事は多忙です。
また、プロジェクトごとに仕事の環境が大きく変わります。
たとえば、ある日は製造業のコスト削減、次の日はIT企業の新規事業立ち上げ、といったように扱う業界や課題、チームメンバーが頻繁に変わります。
環境の変化を「大変だ」と捉えるのではなく、「新しいことに挑戦できる」「さまざまな経験を積める」と前向きに捉えてください。
忙しい環境を楽しめる人ほどコンサル業界で活躍できます。
予測不可能な状況にも柔軟に対応し、常に新しい知識を吸収しようとする好奇心旺盛な人にとって、変化の多いコンサル業界は良い職場になるでしょう。
安定や定型業務を重視する人は不向き
コンサル業界は、安定した働き方や決まったルーティンワークを求める人には、あまり向いていません。
プロジェクトごとにクライアントや課題は変わるからです。
また、求められるスキルや解決策も異なるため、仕事の内容も働き方も非常に流動的です。
決まった時間に出社して、毎日同じ業務をこなすことを好む人にとっては、ストレスの原因となる可能性があります。
また、コンサル業界は常に新しい問題に直面し、正解のない問いに答えを出さなければなりません。
そして、過去にうまくいったからといって、今回も同じ方法が通用かは不明です。
もし「安定した環境で着実に仕事をしたい」と考える就活生には合わないでしょう。
【コンサル業界は稼げる】内定を取るにはどうすればいい?
コンサル業界の内定を得るには、コンサル業界に特化した対策が必要です。
コンサル業界は、書類選考やグループディスカッションに加えて、ケース面接が存在します。
一般的な企業の面接とは大きく内容が異なります。
コンサル業界の内定を取るための方法やポイントは、以降の章を参考にしてください。
コンサル業界にフォーカスした内容を解説しています。
ケース面接や論理力対策が必須
コンサル業界の内定を勝ち取るためには、ケース面接と呼ばれる独特の面接形式を対策する必要があります。
さらに、ケース面接で問われる論理的な思考力も必要不可欠です。
たとえば、ケース面接では「A社の売上を2倍にするにはどうするべきか?」といった抽象的なお題が出されます。
就活生は、その場で問題を分析し、解決策を発表しなければなりません。
面接官は、解決策を導き出す思考プロセスをチェックし、合否を決める材料にします。
単に答えを出すだけでなく、どのように情報を整理し、考え、結論に至ったか丁寧に説明する力が必要です。
ケース面接の対策を怠ると、どんなに優秀な就活生でも不採用の可能性が高まります。
ケース面接の過去事例を参考にして、思考力を磨くことが内定への近道となります。
インターンや選考直結型イベントに参加する
コンサル業界を目指すなら、インターンシップや選考に直結するイベントに積極的に参加しましょう。
インターンでは、実際のコンサルティング業務に近い体験ができたり、現役のコンサルタントと直接交流したりする機会が得られます。
公式ホームページや募集要項だけでは得られない情報もあるでしょう。
また、コンサル業界への理解を深めるだけでなく、自分の適性を確かめることが可能です。
さらに、イベントでの活躍が本選考の優遇につながることもあります。
イベントへの参加自体が内定への大きな一歩となるかもしれません。
そこで、インターンやイベントに参加する就活生は、情報を集めつつ、入社意欲と理解度を企業にアピールしましょう。
志望動機で業界理解と自己適性を語る
コンサル業界の選考は「なぜコンサルなのか」「なぜこの会社なのか」などの志望動機が重要です。
ただ「高収入だから」といった表面的な理由では、深い業界理解がないと見なされます。
その結果、高い評価を得るのは困難です。
コンサル業界の研究を徹底し、コンサルティングが社会や企業にどのような価値を提供しているのか、適切に理解することが大切です。
さらに、自分の経験や強みが、コンサルタントとしてどのように活かせるのか、なぜ自分がこの仕事に向いているのかを具体的に説明してください。
志望動機が、客観的に証明できれば、面接官は好印象を持つでしょう。
その結果、ほかの就活生と比較して、有利に選考が進められます。
まとめ
この記事では、コンサル業界が稼げる理由と仕組みについて解説してきました。
コンサル業界は成果主義です。
新卒であっても成果を残せば、高収入が得られます。
ただし、深い知識と専門性が求められるため、常に勉強する必要があります。
そこで、インターンやイベントに参加し、自分がコンサル業界に適性のある人材か確かめておきましょう。
無理にコンサルを希望すると、入社後に後悔する可能性があります。
納得したうえで入社できるよう、この記事の解説を参考にしてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート