目次[目次を全て表示する]
6月の就活解禁ってなんのこと?
6月の就活解禁という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、毎年6月1日を境に企業の新卒採用選考が本格的にスタートするという、就職活動における重要な区切りを指す言葉です。
ただ、実はこのルールはすべての企業に共通しているわけではありませんし、現在では一部内容が変化しています。
背景には、経団連(日本経済団体連合会)が定めてきた採用に関する指針がありますが、それも近年では見直され、柔軟な採用活動が進んでいます。
この記事では、6月の就活解禁とはそもそも何なのか、なぜそうした日程が設定されているのか、そしてそれが今の就活生にどのような影響を与えるのかについて、順を追ってわかりやすく解説していきます。
特に26卒・27卒としてこれから選考に臨む皆さんにとって、スケジュールを理解することは対策を立てる上での第一歩です。
不安を感じる場面もあるかもしれませんが、情報を正しく理解すれば、きっと自分に合った道が見えてくるはずです。
経団連が定めた選考解禁日
6月の就活解禁とは、かつて経団連が定めたガイドラインに基づき、加盟企業が6月1日から選考活動を正式に開始することを指していました。
つまり、企業がエントリーシートの選考や面接を始めてよいとされる時期がこのタイミングだったのです。
多くの学生が6月に集中して面接を受ける理由は、このルールに従って企業側が一斉に選考をスタートしていたからです。
このルールは、学生が学業に集中できるようにという配慮から生まれたものですが、実際にはそれ以前から水面下での動きがあったり、一部の企業はスケジュールを前倒しして独自に動いたりするケースも見られました。
現在も6月1日を節目として選考をスタートする企業は多くありますが、これはあくまで目安となっており、絶対的なルールではありません。
3月は経団連が定めた広報活動解禁日
大学3年生の3月1日は、企業が新卒採用に関する広報活動を一斉にスタートする日です。
これは経団連が長年定めてきたルールに基づくもので、説明会の開催や採用ページの公開、インターン経験者への案内メールなど、学生に向けた情報発信が一気に活発化するタイミングです。
この時期は、就活生にとって本格始動の合図とも言えます。
多くの学生が3月からエントリーを始め、自己分析や業界研究を一気に進めるのもこの頃です。
企業側も3月にあわせてさまざまな説明会や座談会を用意し、学生との接点を増やそうとします。
ただし、3月からすぐに選考が始まるわけではありません。
この時点では、あくまで情報収集の期間であり、企業と学生のマッチングを深めるプロセスが中心です。
そのため、この時期にどれだけ多くの情報を得られるかが、後の選考対策に大きく影響します。
焦らずに、自分の軸や興味を明確にしながら、気になる企業を見つけていくことが大切です。
3月の段階では、まだ方向性が定まっていなくてもまったく問題ありません。
むしろ、この時期を活用して視野を広げておくことが、納得のいく就活につながる第一歩になります。
2021年にルールは撤廃されている
これまで経団連が示してきた採用選考に関する指針ですが、実は2021年春入社の学生を最後に、このルールは撤廃されています。
現在では、経団連加盟企業であってもこのガイドラインに縛られる必要はなく、各企業が自由に採用スケジュールを設定できるようになりました。
ただし、完全な自由競争になったわけではありません。
経団連がルール策定から手を引いた後は、政府が主導する形で一定の目安が示されており、多くの企業はこれを参考にスケジュールを組んでいます。
そのため、引き続き3月の広報解禁、6月の選考解禁という流れは一定程度維持されています。
このルール撤廃により、企業ごとの採用活動の時期が多様化しました。
特に外資系企業やベンチャー企業、IT業界などでは早期選考や通年採用を導入するところも多くなり、学生側にも情報の早さと行動力がより求められるようになっています。
とはいえ、ルールが変わったからといって焦る必要はありません。

大切なのは、自分のペースを見失わず、自分に合った企業・時期を見極めて動くことです。今後ますます多様化していく就職活動において、自分自身の判断軸を持つことが、納得のいく内定への近道となるでしょう。
一般的な就活スケジュール
就職活動には明確なゴールがありますが、そこに至るまでの道のりは人それぞれです。
ただ、多くの企業が採用活動を進める時期には一定の傾向があり、それに沿って準備を進めることで、スムーズに就活を進めやすくなります。
ここでは、大学3年生から4年生の秋までの一般的な就活スケジュールについて、時期ごとの流れを順を追って解説していきます。
今がどのフェーズにあたるのかを確認し、次に何をすべきかを整理しておくことで、焦ることなく、自分のペースで就活を進めていけるはずです。
大学3年生夏〜 サマーインターンへの参加
大学3年生の夏は、多くの学生にとって就活の入り口となる時期です。
このタイミングで実施されるサマーインターンは、業界研究や自己分析の第一歩として非常に有効です。
特に大手企業を中心に、多種多様なインターンシップが開催されており、早い人では6月ごろからエントリーが始まります。
インターンを通じて企業の雰囲気や業務内容を体験することで、自分の適性や興味のある業界を知るきっかけになります。

企業によってはインターン参加者を対象にした早期選考につながる場合もあり、早期内定を目指す上でも見逃せないチャンスです。この時期に重要なのは、できるだけ多くの業界に触れてみること。最初から志望業界を一つに絞るのではなく、広い視野を持ってインターンに参加することで、将来の選択肢を広げることができます。
大学3年生秋〜 秋冬のインターン・早期選考への参加
夏のインターンがひと段落した後、秋から冬にかけてもさまざまなインターンや選考付きのイベントが開催されます。
この時期のインターンは、より選考に直結しやすい傾向があり、企業によってはここで評価された学生を早期選考に招くケースも増えてきています。
また、外資系企業やベンチャー企業では、この時期に本選考をスタートさせる場合もあるため、志望企業によっては本格的な選考対策が求められることもあります。
特に外資系はESやWebテスト、英語面接などの対策を早めに始める必要があるため、スケジュールをしっかり確認しておくことが重要です。
秋冬のインターンは、夏に比べて少人数制のものも多く、より実務に近い体験ができる点が特徴です。
企業理解を深めるだけでなく、自己PRや志望動機の精度を高める絶好の機会となりますので、積極的に参加を検討してみましょう。
大学4年生1月〜 本選考準備
年が明け、大学4年生を目前に控えた1月頃からは、いよいよ本選考に向けた準備を本格化させる時期です。
自己分析や企業研究を深めると同時に、エントリーシート(ES)の作成や面接対策、筆記試験の練習など、実際の選考に向けた具体的な準備を進めていきます。
この段階では、すでに早期選考に参加している学生もいますが、そうでない場合も焦る必要はありません。
1月からの準備が、本選考本番での成功に大きくつながります。
特にESや面接では、これまでの経験や価値観をどう言語化するかが問われるため、過去の体験を振り返り、自分の強みやアピールポイントを整理しておくことが大切です。

模擬面接やキャリアセンターの活用、OB・OG訪問などもこの時期に進めておくと、実戦力が身につき自信を持って本番に臨めるようになります。
大学4年生3月〜 本選考エントリー
3月1日は、経団連加盟企業が一斉に広報活動を開始するタイミングであり、就活生にとってはいよいよ本番が始まるという節目でもあります。
各企業が採用ページをオープンし、エントリー受付が本格化します。
この時期は、複数の企業にエントリーをする学生が多く、スケジュール管理が重要になります。
説明会の参加、エントリーシートの提出、適性検査の受験など、やるべきことが一気に増えるため、しっかりと計画を立てて行動することが成功の鍵です。
エントリー数=内定数ではありませんが、複数の企業に応募することで、自分に合った企業を見極める機会が広がります。
過度に数を増やす必要はありませんが、業界や企業規模に偏りがないよう、バランスを意識してエントリーを進めるとよいでしょう。
大学4年生4月〜 本選考の面接、内定獲得
4月に入ると、多くの企業で面接が本格的にスタートします。
グループディスカッションや個人面接、最終面接など、企業によって選考の進め方は異なりますが、ここからがまさに勝負どころです。
この時期は、選考を受けながら他社のエントリーや説明会にも参加しなければならず、体力的にも精神的にもハードな期間になります。
だからこそ、しっかりと自己管理を行い、心身のバランスを崩さないよう注意しましょう。
内定が出る学生も増えてくる一方で、なかなか結果が出ずに焦りや不安を感じる方もいるかもしれません。
なぜ落ちたのか、自分に何が足りないのかと悩むこともあると思いますが、選考の結果だけで自分の価値を決めつける必要はありません。
一つひとつの経験を糧にして、次へとつなげていくことが大切です。
大学4年生の10月 内定式
10月1日は、多くの企業が内定者を正式に迎える内定式を行う日です。
この式は、企業との結びつきを改めて確認する場であり、同時に社会人としてのスタートに向けた準備期間の始まりでもあります。
内定式では、同期となるメンバーとの初対面の場であったり、社長や人事からのメッセージを受け取ったりすることが多く、ここに入社するんだという実感が湧いてくる時期です。
一方で、内定をまだ得られていない学生にとっては、精神的にプレッシャーを感じやすい時期でもあります。
しかし、10月以降も採用活動を継続する企業は多く存在し、特に中小企業やベンチャー、外資系企業、公務員などではまだまだチャンスが残されています。
自分のペースで納得のいく就職活動を続けていくことが何よりも大切です。

内定式が終わったからといって就活が終わりではなく、自分に合った企業との出会いはこれからでも十分に間に合います。焦らず、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
【大学3年生】6月にやるべきこと
大学3年生の6月は、本格的な就職活動に向けた助走期間ともいえる大切な時期です。
まだ就活は先のことと感じている方も多いかもしれませんが、このタイミングでしっかりと準備を始めることで、後の動きが格段にスムーズになります。
特に6月は、自己分析や業界研究に加えて、夏のインターンへのエントリーが始まる重要なタイミングです。
ここからの行動が、志望業界の絞り込みやインターン選考突破、そして本選考へのつながりに直結します。
早めに動き出すことは、自分の将来に対する選択肢を広げることにもつながりますので、焦らず、でも確実に一歩を踏み出していきましょう。
自己分析をして就活の軸を決める
まず最初に取り組みたいのが自己分析です。
自分の価値観や興味関心、大切にしたい働き方を明確にすることで、将来どんな仕事に就きたいのか、どのような企業が自分に合っているのかといった就活の軸が見えてきます。
この軸が定まっていないと、企業選びや志望動機の作成にも迷いが生じ、結果としてミスマッチが起きてしまうこともあります。
たとえば、なぜ働くのか、自分がやりがいを感じる瞬間はどんな時か、これまでどんな経験に熱中してきたかなどを振り返ると、自分らしさのヒントが見つかります。

他者からのフィードバックを受けることで、自分では気づいていなかった強みに気づけることもあります。自己分析は一度で完了するものではなく、就活を進めながら何度も見直していくものです。6月の時点では、まず自分を知ることにじっくり時間を使ってみてください。
しっかりとした土台があれば、今後の選択にも迷いが少なくなります。
業界研究・企業研究をする
自己分析と並行して進めたいのが、業界研究・企業研究です。
自分が興味を持っている業界には、どのような特徴があるのか、どんな仕事が存在しているのかを具体的に調べていくことが大切です。
また、業界ごとに求められる人物像や働き方も異なるため、そこに自分がフィットするかどうかを見極めることも重要です。
この時期は、経済紙や業界マップ、企業の採用ページなどを活用しながら、幅広く情報を収集するのがおすすめです。
志望業界がまだ定まっていない場合は、あえて異なる業界を比較してみると、自分の関心の方向性が見えてくることもあります。
また、気になる企業があれば、過去のインターン実施内容や選考情報、社員インタビューなどもチェックしてみましょう。
なぜこの企業に興味を持ったのかと言語化することで、志望動機の土台にもなっていきます。
6月の段階では、広く業界を見る姿勢を持ちながら、自分の関心に合った分野を深掘りしていくことが成功のカギとなります。
夏のインターンにエントリーを始める
6月になると、多くの企業でサマーインターンの募集がスタートします。
インターンは、実際の業務を体験できるだけでなく、企業や業界に対する理解を深める貴重な機会です。
また、選考付きのインターンでは、参加を通じて早期選考や内定に直結することもあるため、就活において非常に重要な位置づけとなっています。
エントリーが集中する人気企業では、6月中に募集が締め切られることもありますので、気になる企業がある場合は早めのチェックと応募が大切です。
そのためにも、事前にESや自己PRの準備を進めておくとスムーズに対応できます。
インターンの選考では、企業が学生の素の姿を見たいと考える傾向があるため、無理に取り繕うのではなく、自分らしさを意識してアピールしましょう。

インターンは失敗を恐れずチャレンジする場でもあります。経験を積むことが何よりも大切なので、自信がなくても一歩踏み出す勇気を持って臨んでみてください。きっと、将来の選択肢を広げる大きな一歩になるはずです。
【大学3年生】6月の就活の注意点
6月は、就活のスタートラインに立つ時期ともいえる大切なタイミングです。
インターン情報が公開され、就活関連のイベントも増えはじめるため、動かなきゃと焦りを感じる方も多いかもしれません。
しかし、だからこそ注意しておきたい点もあります。
就活は長期戦です。
初期段階で無理をしすぎてしまうと、後の本選考時期にモチベーションや体力を保てなくなる可能性もあります。
この章では、6月に就活を進める上で気をつけておきたい3つのポイントをご紹介します。
効率よく、そして自分らしく動いていくために、あらかじめ意識しておくとよいでしょう。
就活に時間を使いすぎない
6月はたしかにインターンエントリーなどの準備が始まる時期ですが、だからといって就活に全力を注ぎすぎるのは考えものです。
この時期にできることはまだ限られており、自己分析や企業研究といった土台づくりが中心になります。
将来的な本選考や学業とのバランスを考えると、時間の使い方には注意が必要です。
特に、周りが動き出しているから不安という理由で、むやみにエントリー数を増やしたり、情報収集ばかりに時間を使ったりすると、気づかぬうちに疲弊してしまうこともあります。

今のうちから、自分の1週間や1日のスケジュールの中で、どこに就活の時間を組み込むかを決めておくと、効率的に動けるようになります。無理なく継続できるリズムを作ることが、長期的に見て最も効果的な就活の進め方です。焦らず、コツコツと進めていくことを大切にしましょう。
一人で就活を進めない
就活はどうしても個人戦のように感じられがちですが、実はチーム戦とも言える面があります。
一人で悩み、考え、決断を繰り返していると、視野が狭くなってしまいがちです。
特に6月のような情報収集段階では、第三者の視点が大きな支えになります。
たとえば、大学のキャリアセンターや就活支援セミナー、OB・OG訪問、さらには同級生との情報交換など、他人の意見を取り入れることで、自分では気づけなかった視点や選択肢に出会えることも多いです。
また、自己分析や志望動機を人に話してみることで、自分の考えが整理され、言語化の精度が高まります。

誰かに頼ること=弱さではありません。むしろ、必要なときにサポートを求められる柔軟さは、社会に出たあとにも必要とされる力です。一人で抱え込まず、周囲のリソースをうまく活用しながら進めていきましょう。
サマーインターンの募集締め切りはメモしておく
6月は、サマーインターンの情報が一斉に公開されるため、エントリー先や締め切りが重なるケースも少なくありません。
企業によっては、6月中に募集を締め切るところもあり、気づいたときには締め切りが過ぎていた…という事態になりがちです。
特に複数の企業を並行して見ている場合は、情報の整理が非常に重要になります。
そのため、エクセルやスプレッドシート、就活用のアプリなどを活用して、企業名・応募締切日・選考ステップなどを一覧にまとめておくことをおすすめします。
視覚的に整理することで、スケジュール管理がしやすくなり、優先順位もつけやすくなります。

締切の直前はエントリーが集中するため、サーバーが混雑して提出できない…という事態も想定して、余裕を持って応募しておくと安心です。情報はただ集めるだけではなく、整理して使える状態にしておくことが、就活をスムーズに進めるポイントです。早めの行動で、チャンスを確実につかんでいきましょう。
【大学4年生】6月にやるべきこと
大学4年生の6月は、就職活動が一段落しはじめる人と、これから巻き返しを図る人が混在する時期です。
すでに内定を獲得した方にとってはこのまま就活を終えてよいのかを考え始める頃であり、まだ内定を得ていない方にとってはこれからどう動くかが大きなテーマになります。
また、夏休みを控えているこの時期は、学生生活の締めくくりとしての時間も大切にしたいですね。
ここでは、大学4年生が6月に取り組んでおきたい3つのことについてご紹介します。
内定の有無にかかわらず、それぞれの状況に応じて一歩先の行動につなげていきましょう。
内定を獲得した企業をさらに深く調べる
すでに内定を得ている方は、その企業に本当に入社するべきかどうかを、改めて冷静に見直す時期に入ります。
嬉しい気持ちと同時に、この企業で本当にいいのだろうか?と迷いが生まれるのも自然なことです。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、ここでしっかりと企業研究を深め、自分の将来を具体的にイメージしてみることが大切です。
たとえば、仕事内容やキャリアステップ、福利厚生、社風、評価制度など、初回の企業研究では見えてこなかった部分に目を向けてみましょう。
可能であれば、内定者懇親会や社員訪問、インターン時代のつながりなどを活用し、現場で働く人の声を直接聞いてみるのも有効です。

納得して入社を決めることが、社会人生活のスタートに大きく影響します。勢いで決断するのではなく、今だからこそ時間をかけて吟味してみてください。
より良い内定先を目指して就活を続ける
もし今持っている内定先に不安や違和感があるなら、無理に就活を終える必要はありません。
6月以降も採用活動を続ける企業は多数存在し、特に中小企業やベンチャー企業、外資系、官公庁などではこれからが選考本番というケースも少なくありません。
内定があるのに就活を続けてもいいのだろうか…と迷う方もいるかもしれませんが、自分が納得できる選択をすることのほうが、ずっと大切です。
内定は選べる立場にあるという強みでもあります。
選択肢がある中で、自分に最も合った企業を見つけるための行動は、前向きな就活の一つです。

ダラダラと就活を続けるのではなく、この夏で決めきるといった明確な目標を持つことが大切です。再スタートを切るのであれば、自己分析の見直しや志望企業の再検討など、基礎から整えていきましょう。
大学生最後の夏を謳歌する
6月は、就活の動きに加えて、大学生活の集大成とも言える夏休みの計画を立て始める時期でもあります。
就職活動に区切りがついた方にとっては、思い切りリフレッシュし、学生最後の夏を心から楽しむことも大切な時間です。
旅行やアルバイト、ゼミ活動、趣味への挑戦など、やり残したことに取り組める貴重な期間です。
特に社会人になると、長期休暇を自由に使える機会は限られてきますので、この夏は自分のために時間を使うことを意識して過ごしてみてください。
一方で、まだ就活中の方も、計画的に動くことで就活とプライベートの両立は十分に可能です。
メリハリをつけることで、気持ちにも余裕が生まれ、選考にも良い影響が出てきます。
焦らず、前向きに、そして思い出に残る夏を過ごしてくださいね。
【大学4年生】6月の就活の注意点
大学4年生の6月は、就活の山場を迎える学生と、これから巻き返しを図る学生とで状況が大きく分かれる時期です。
周囲からは内定が出たという声も聞こえ始め、焦りやプレッシャーを感じる方も少なくないでしょう。
しかし、6月時点で就活が終わっていないことは決して遅れではありません。
ここからどのように動くかが、今後の結果を左右します。
この時期に気をつけたいのは、視野を狭めないことと社会人に向けた準備を意識することです。
少し視点を変えるだけで、新しい可能性や出会いに繋がることもあります。
以下の3つのポイントを意識して、6月の就活を前向きに進めていきましょう。
大手企業以外も広くみる
6月に入ると、大手企業を中心に選考が一段落し、エントリー受付を終了する企業が増えてきます。
もし、まだ志望していた企業の選考を受けられていない場合は、大手にこだわらず、視野を広げて他の選択肢にも目を向けてみましょう。
中堅・中小企業、ベンチャー企業、公務員、外資系など、まだまだ採用活動を継続している企業は数多く存在します。
こうした企業の中にも、将来性があり、個人の裁量や成長機会が大きいところはたくさんあります。

知名度やブランドだけで判断せず、自分にとって本当に働きやすい環境とは何かを基準に企業選びをしてみましょう。エントリー可能な企業は日々変わりますので、こまめに情報をチェックすることも忘れずに。
業界・業種を広げてみる
これまで興味のなかった業界や職種にも目を向けてみると、意外な発見があるかもしれません。
たとえば、営業は向いていないと思っていたけど、実は人と話すのが得意だった、技術職にこだわっていたけれど、企画やマーケティングにも関心が出てきたなど、業界や職種を広げることで、自分の可能性に気づくこともあります。
就活では、やってみないと分からないことが多くあります。
自分の知らない世界に一歩踏み出すことは勇気がいりますが、その一歩が将来の選択肢を大きく広げるきっかけになるかもしれません。
企業説明会や業界研究セミナーなども活用し、柔軟な姿勢でさまざまな分野に触れてみましょう。
思いがけない出会いが、あなたの就活を前向きに変えてくれることもあります。
ビジネスマナーに気を配る
選考が進むと、面接や企業とのやり取りの中で、ビジネスマナーが自然と求められるようになります。
言葉遣いやメールの書き方、服装、身だしなみなど、基本的なマナーは社会人になってからも必ず役立つスキルです。
自分はまだ学生だから…と思ってしまうかもしれませんが、面接官や企業の担当者はあなたを将来の同僚として見ています。
だからこそ、社会人としての基本的な姿勢が見られているのです。6月の段階で、あらためて自分のマナーを見直してみましょう。

メールの返信速度や敬語の使い方、面接時の立ち居振る舞いなど、小さなことの積み重ねが、信頼や評価に大きく影響します。就活を通じて身につけたマナーは、入社後の自分を助けてくれる財産になります。
まとめ
大学4年生の6月は、就活を締めくくる時期であると同時に、新たに再スタートを切るタイミングにもなり得る大切な時期です。
内定の有無にかかわらず、自分が納得できる選択をするために、今一度立ち止まり、視野を広げて行動してみましょう。
大手企業や特定の業界にこだわりすぎず、柔軟な発想でさまざまな選択肢を探ること。
社会人に向けた準備として、ビジネスマナーや情報整理の力を身につけること。
このふたつを意識することで、これからの就活や人生に役立つ力が自然と養われていきます。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート



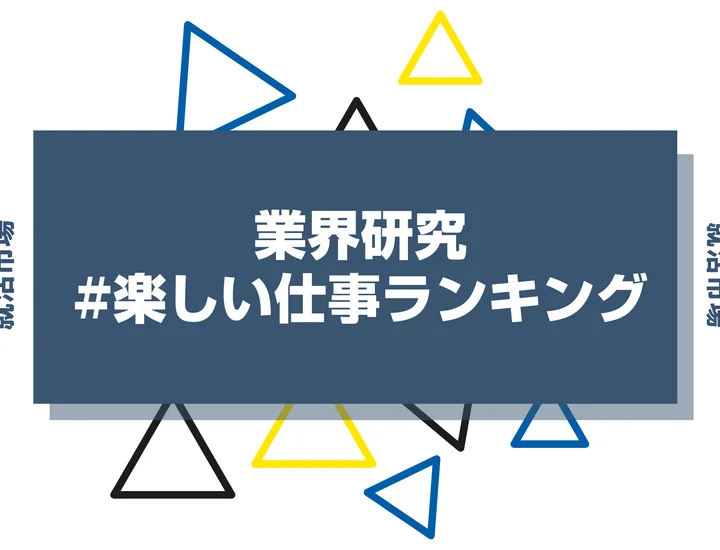








柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
6月は企業側も本腰を入れて採用活動を展開する時期であるため、就活生にとっては重要なタイミングです。これまでのエントリーや説明会を経て、ここからはいよいよ自分をアピールする場に移行していきます。不安もあるかもしれませんが、事前にしっかりと準備をしておくことで、自信を持って選考に臨むことができます。