
AIと磨く、 圧勝ガクチカ。
あなたのガクチカが、
採用担当者に響く最強の武器に変わる。
高性能AIが、エントリーシート通過レベルの
ガクチカ添削・改善を完全サポート。
会員登録後、すぐに全ての機能が使えます
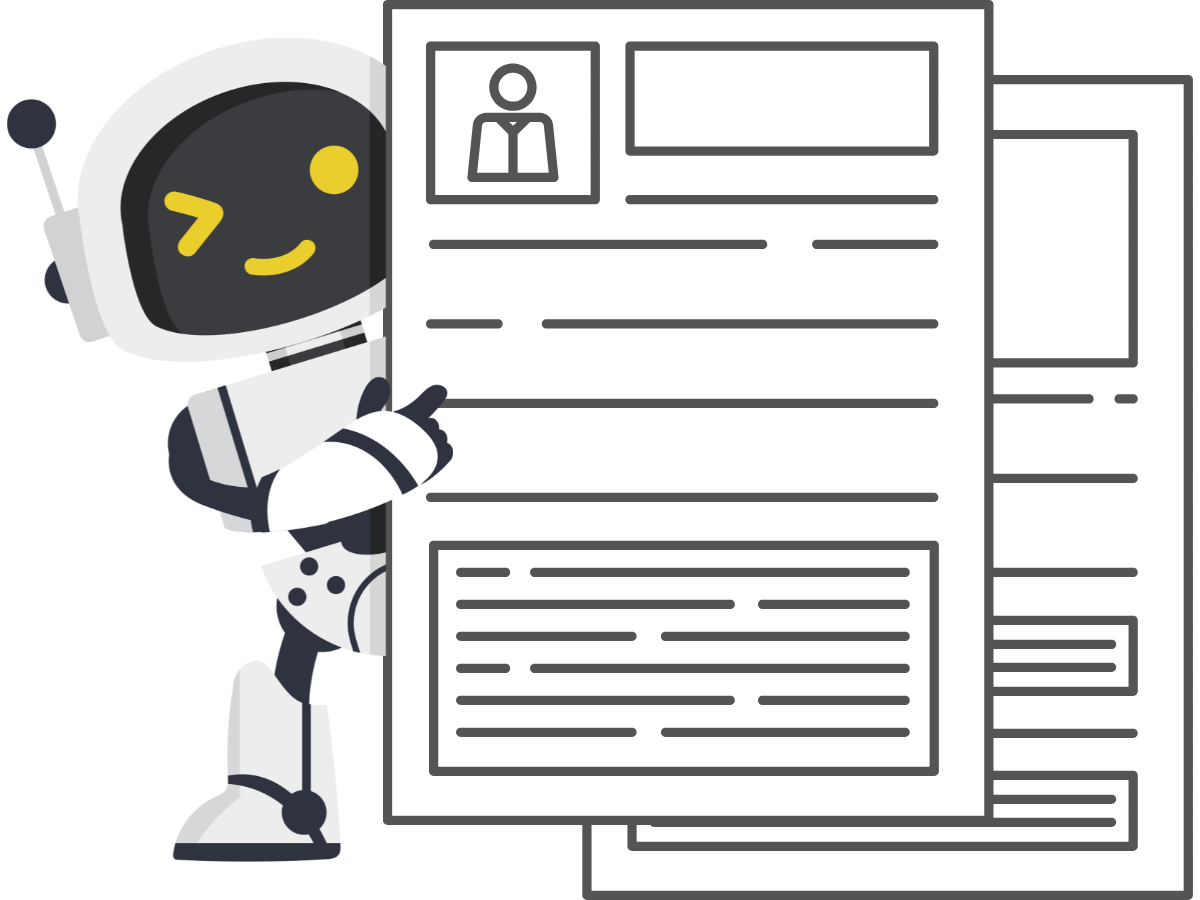
書いたガクチカ、これで本当に大丈夫ですか?
採用担当者に響くか不安…
どう改善すればいいか分からない…
自分のガクチカの弱点が見えない…
その悩み、AIガクチカ添削ツール
がすべて解決します!
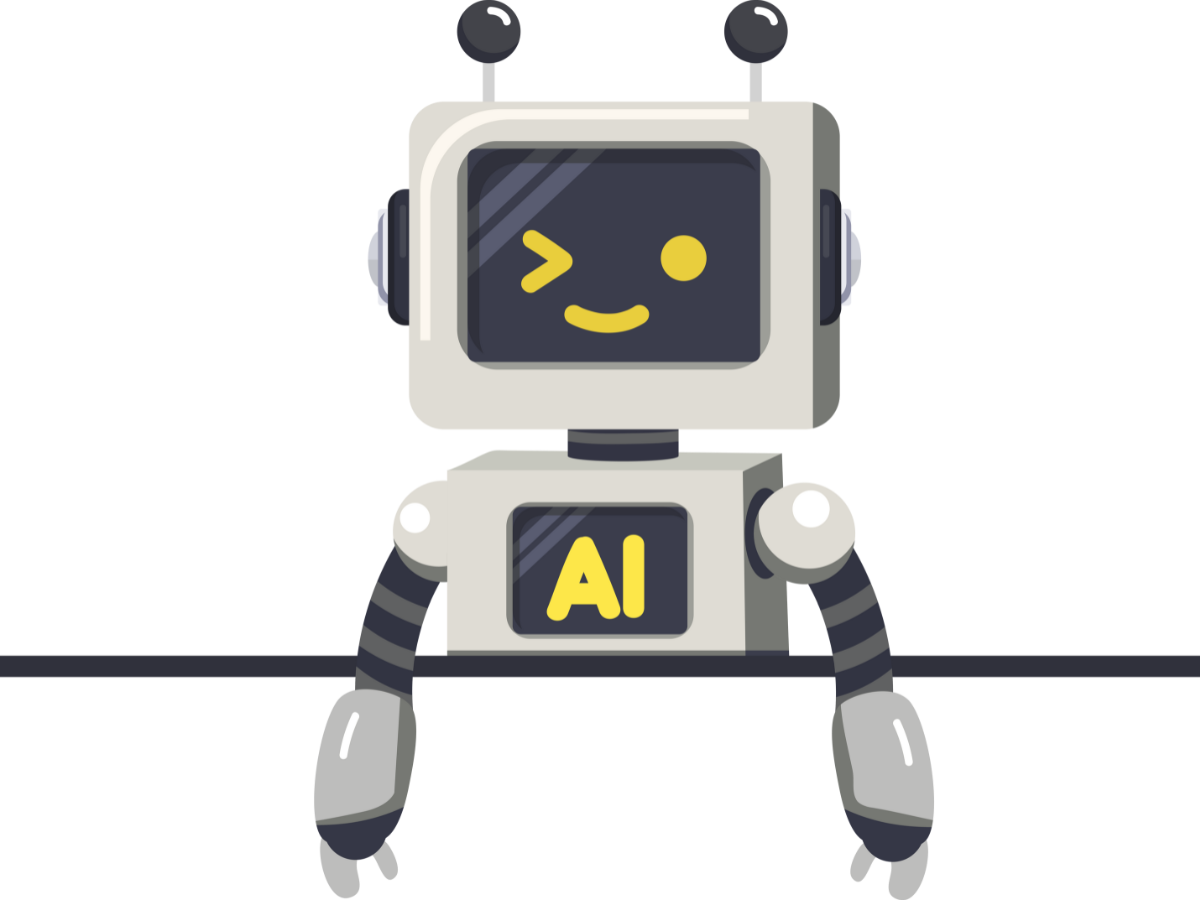
もう一人で悩む必要はありません。当ツールは、単なる添削ツールではないのです。
ガクチカ作成〜添削の全プロセスを、高性能AIが強力にサポートします。
ガクチカ添削を加速させる
4つの主要機能
ガクチカ自動作成
キーワードや簡単なエピソードを入力するだけで、AIが論理的な構成案と、魅力的なガクチカの文章を自動で生成します。添削のたたき台として、執筆時間を大幅に短縮できます。
AI採点
完成したガクチカを、採用担当者の視点で100点満点でスコアリング。「主体性」など5つの項目で評価し、客観的な完成度を測定します。
エピソード探し
AIとの対話を通じて、あなたの経験を深掘り。「すごい経験」がなくても、あなただけの強みとなるエピソードを発見するお手伝いをします。
AI添削
作成したガクチカをAIが徹底的に添削。より伝わる表現への言い換えや、アピールポイントを強調するための具体的な改善案を提案します。
直感的な操作で、
誰でも簡単に傑作を。
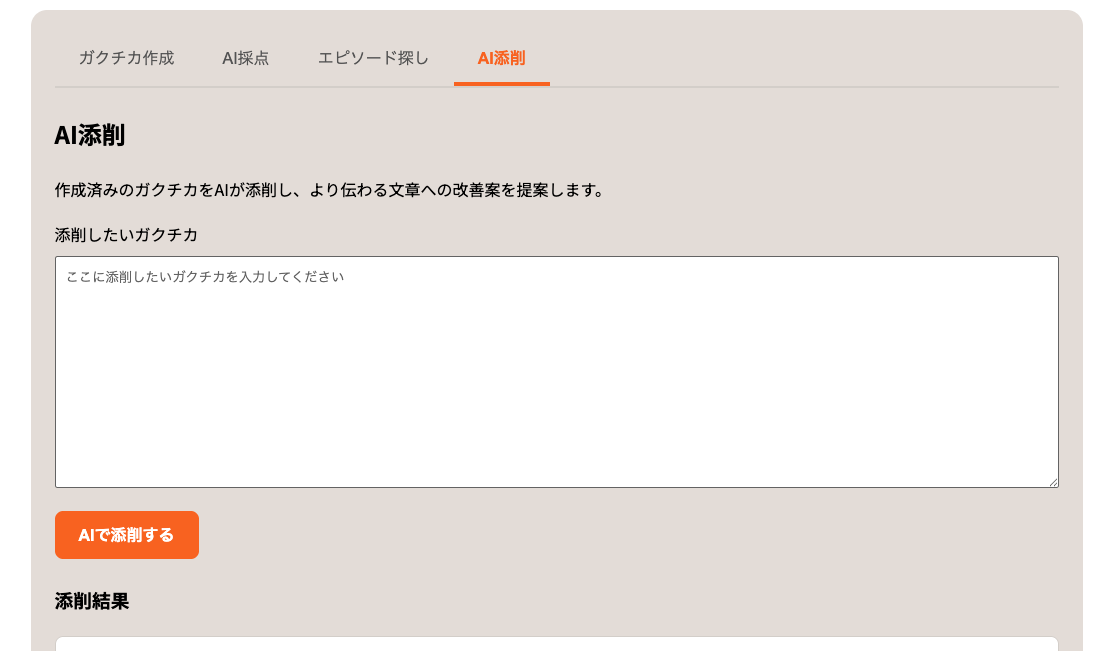
シンプルなインターフェースで、あなたの思考を妨げません。
集中して最高のガクチカ作成に取り組めます。
ご利用の流れ

簡単 会員登録
メールアドレスとパスワードだけで登録完了。すぐに利用を開始できます。
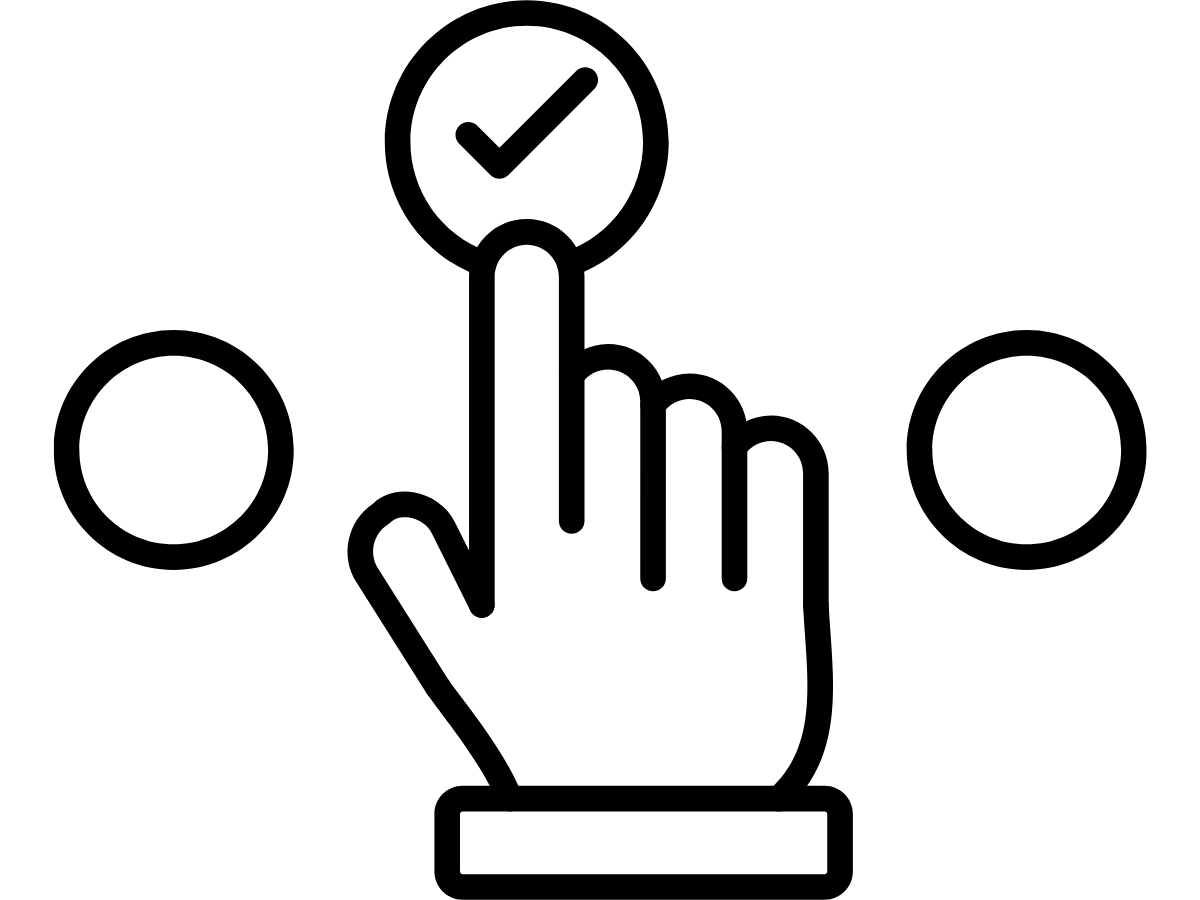
ガクチカを準備・選択
添削したいガクチカを準備し、「AI添削」機能を選択します。
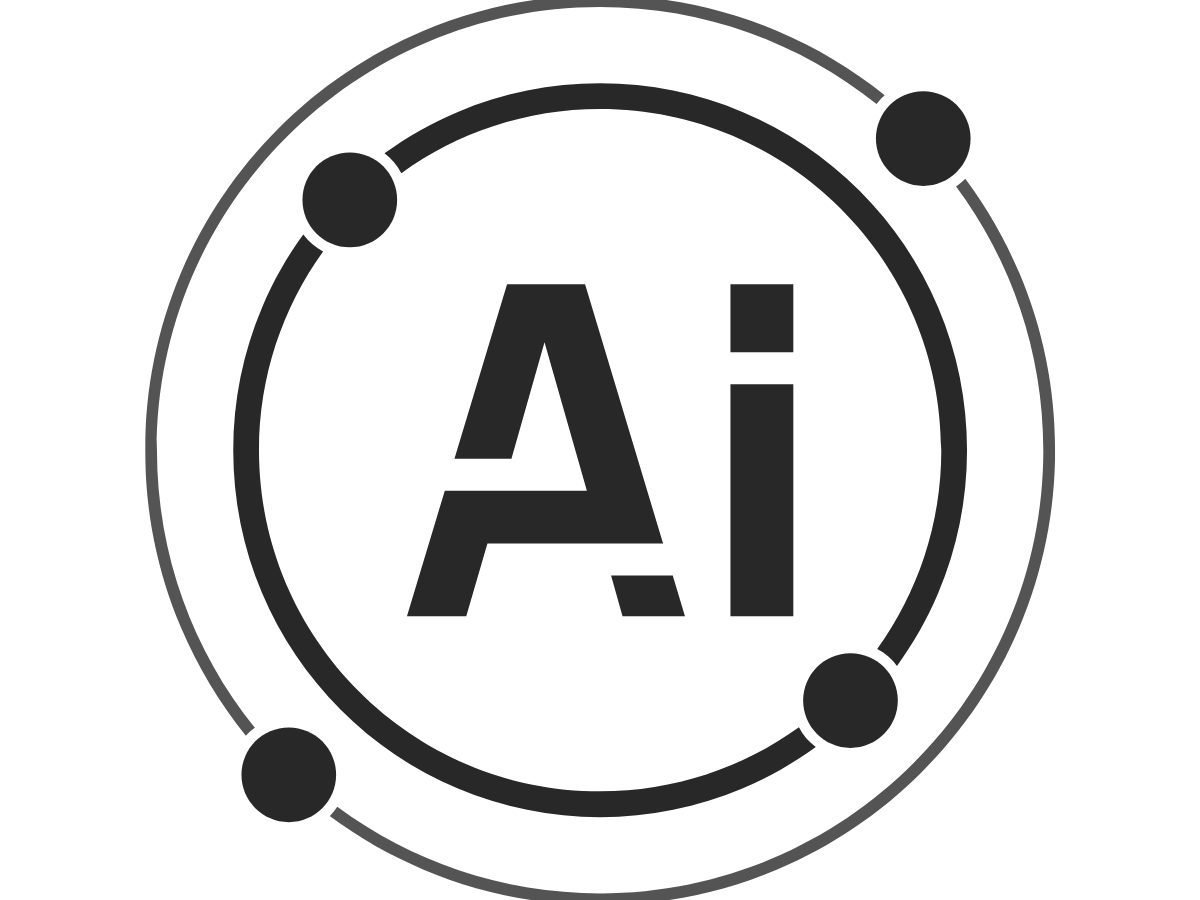
AIとガクチカ添削
就活サポートに特化したAIのサポートを受けながら、最強のガクチカに磨き上げましょう!
さあ、AIと共に、
最高のガクチカを。
今すぐ無料で始めて、ライバルに差をつけよう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート




_720x550.webp)






