
人事が作成した、 最強ガクチカ作成AI。
あなたの経験が、
採用担当者に響く最強の武器に変わる。
最先端のガクチカ作成 AIが、エントリーシート通過レベルの
ガクチカ文章の作成を完全サポートします。
会員登録後、すぐに全ての機能が使えます
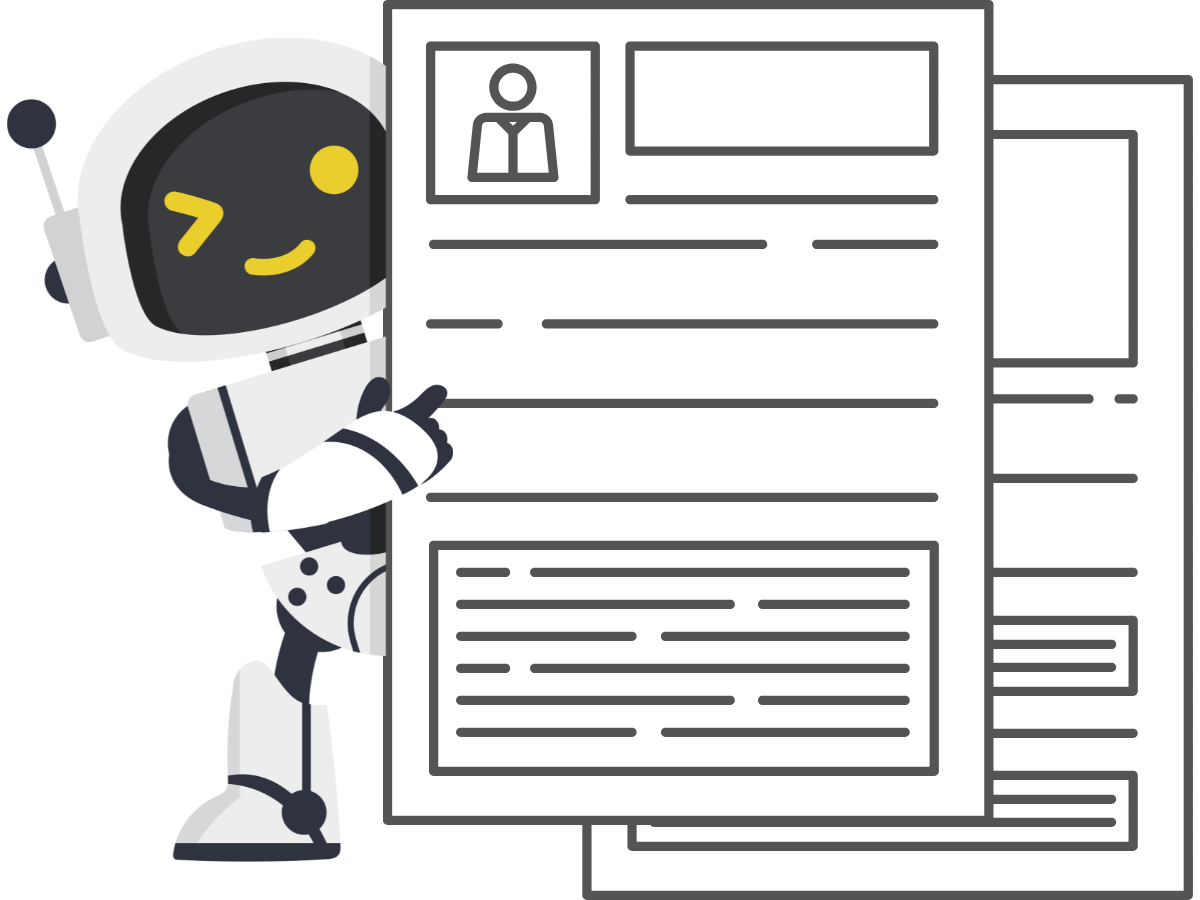
ガクチカ作成の壁に、
ぶつかっていませんか?
伝えたいことがまとまらない…
アピールできるか不安…
ありきたりな内容になってしまう…
その悩み、AIガクチカ作成ツール
がすべて解決します!
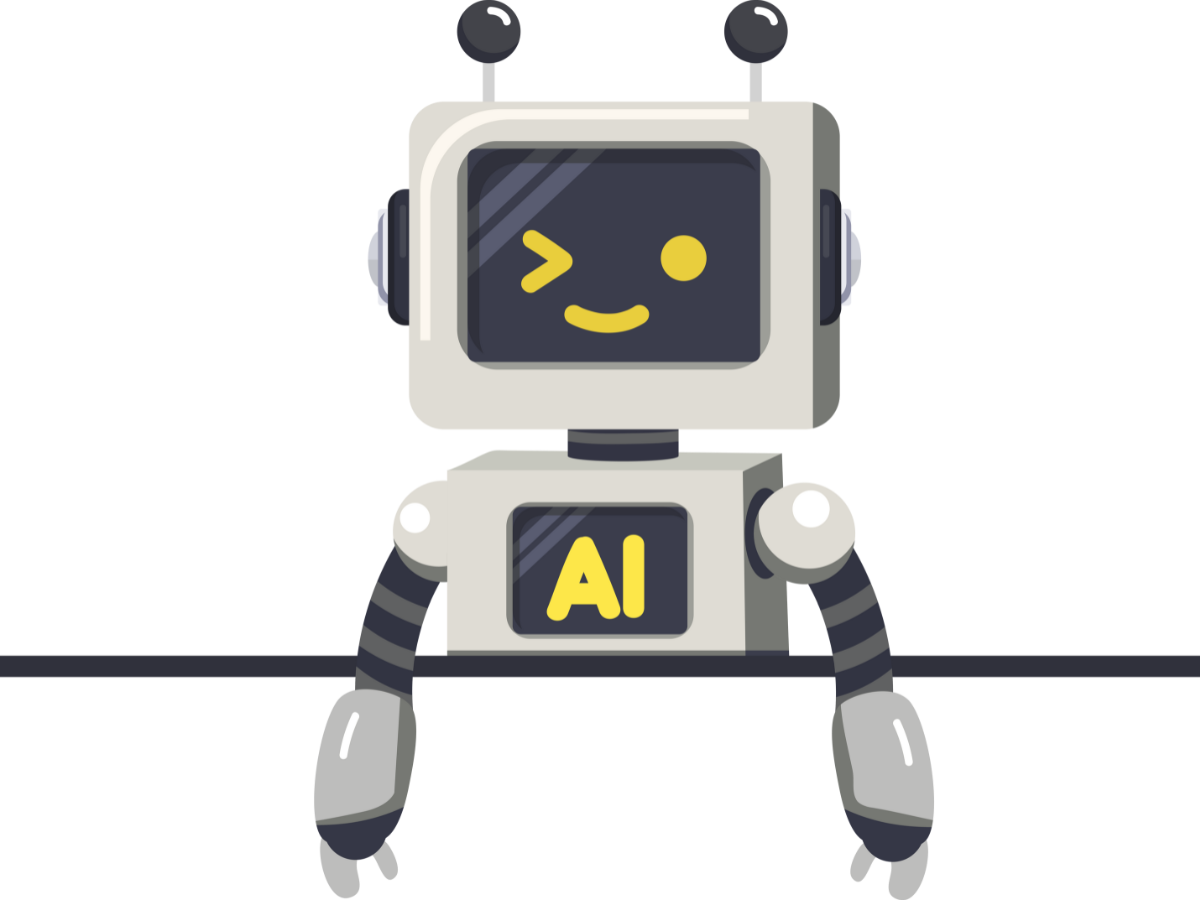
もう一人で悩む必要はありません。当ガクチカ作成 AIは、単なる作成ツールではありません。
ガクチカ作成の全プロセスを、最先端のガクチカ作成 AIが強力にサポートします。
ガクチカ作成を加速させる
4つの主要機能
ガクチカ自動作成
キーワードや簡単なエピソードを入力するだけで、ガクチカ作成 AIが論理的な構成案と、魅力的なガクチカの文章を自動で生成します。ガクチカ作成 AIのたたき台機能で、執筆時間を大幅に短縮できます。
AI採点
完成したガクチカを、採用担当者の視点で100点満点でスコアリング。「主体性」など5つの項目で評価し、客観的な完成度を測定します。
エピソード探し
ガクチカ作成 AIとの対話を通じて、あなたの経験を深掘り。「すごい経験」がなくても、ガクチカ作成 AIがあなただけの強みとなるエピソードを発見するお手伝いをします。
AI添削
作成したガクチカをガクチカ作成 AIが徹底的に添削。ガクチカ作成 AIがより伝わる表現への言い換えや、アピールポイントを強調するための具体的な改善案を提案します。
直感的な操作で、
誰でも簡単に傑作を。

シンプルなインターフェースで、あなたの思考を妨げません。
集中して最高のガクチカ作成に取り組めます。
ご利用の流れ

簡単 会員登録
メールアドレスとパスワードだけで登録完了。すぐに利用を開始できます。
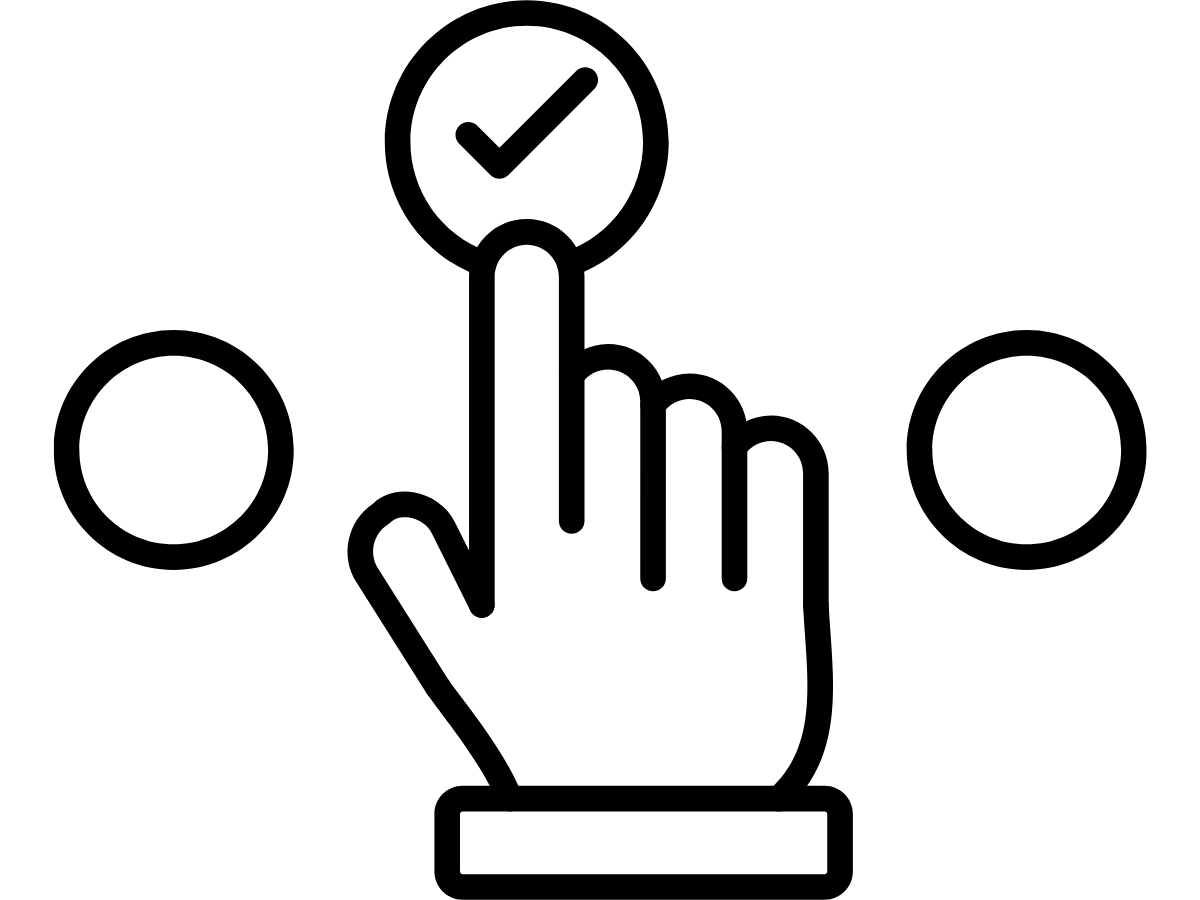
使いたい機能を選択
「ガクチカ作成」「AI採点」など、目的に合わせて使いたい機能を選びます。
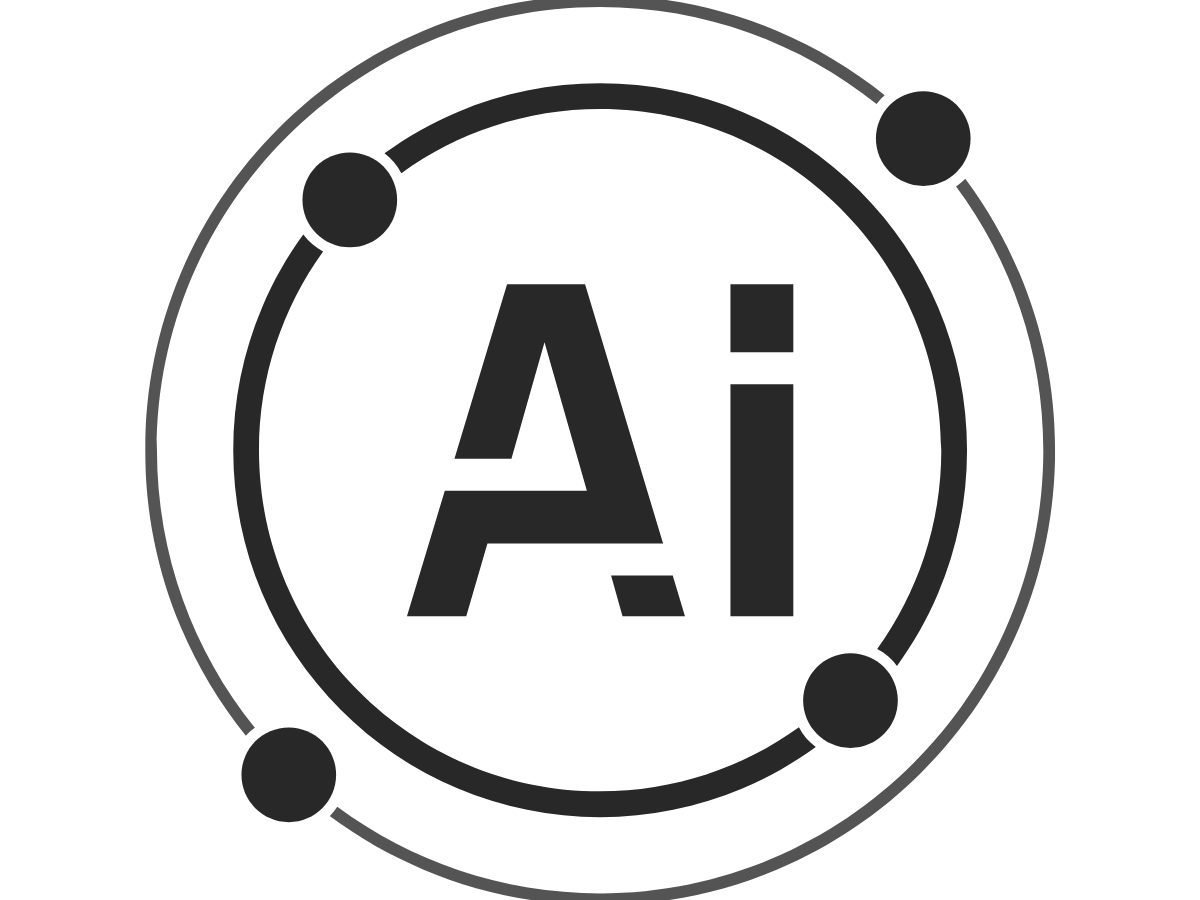
AIとガクチカ作成
就活サポートに特化したガクチカ作成 AIのサポートを受けながら、最強のガクチカを完成させましょう!
さあ、AIと共に、
最高のガクチカを。
今すぐ無料で始めて、ライバルに差をつけよう。
AIでガクチカを効率的に
作成する方法を完全ガイド
学生時代に力を入れたこと(略称ガクチカ)を作成したいが、文章が思いつかず苦労している就活生は多いでしょう。
本記事では、ガクチカ作成 AIでガクチカを作成する方法と無料で使えるガクチカ作成 AI生成ツールを紹介します。
ガクチカは、就活において自分の魅力を面接官にアピールする貴重な機会です。
ガクチカ作成 AIで効率よく文章を作成することで、企業分析や面接練習に時間が使えるでしょう。
ガクチカ作成 AIを使用したガクチカ作成のやり方に迷っている方は参考にしてください。
【AIでガクチカ自動作成】ガクチカとは

ガクチカとは、就職活動でよく質問される項目の1つです。
「学生時代に力を入れたこと」の略称として利用されています。
志望動機や自己PRと並び、就活では頻出の質問です。
自分の経験や学びに重点を置くため、自己分析をしっかりと行いましょう。
ガクチカと自己PRの違いとは
ガクチカと自己PRの違いを解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ガクチカ | 学生時代の経験 |
| 自己PR | 自分の強み |
| 焦点 | 学生時代の経験 / 自分の強み |
| 目的 | 経験から得た学びを伝える / 求める人物像とマッチさせる |
| 企業が見るポイント | 成長性、困難の乗り越え方 / スキル、性格、価値観 |
ガクチカと自己PRは、似ているように見えますが、企業がチェックしているポイントは大きく異なります。
両方の面から、採用する価値のある人物か見極めていることを理解しましょう。
【ガクチカ作成 AIで自動作成】ガクチカはガクチカ作成 AIで叩き台を作成するのがおすすめ
近年、就職活動においてガクチカ作成 AIの活用が広まりつつあります。
特にガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の作成においては、ガクチカ作成 AIを活用することで効率的に文章の叩き台を作成できるようになっています。
就活生の多くが何を書けばよいかわからない、自分の経験に自信が持てないといった悩みを抱える中、ガクチカ作成 AIはその悩みを軽減する心強いツールとなっています。
ガクチカ作成 AIを活用すれば、自分の経験をもとにした構成案や表現の提案を得ることができるため、ゼロから考えるよりも格段に進めやすくなります。
もちろん、完成品として提出する前には自分らしい表現や具体的なエピソードを加えることが必要ですが、最初の一歩を踏み出すための手段としてガクチカ作成 AIを使うことは、非常に有効です。
ガクチカ作成にガクチカ作成 AIを利用する就活生は3人に1人
ある調査結果によると、就職活動でガクチカ作成 AIツールを活用している学生は年々増加しており、特にガクチカ作成にガクチカ作成 AIを利用している就活生は約3人に1人にのぼるというデータもあります。
この数字は、ガクチカ作成 AIによる文章生成が就活生にとって一般的な手段となりつつあることを示しています。
多くの学生が時間の短縮になる、自分では思いつかない表現が得られるといった理由からガクチカ作成 AIを使っています。
【AIでガクチカ自動作成】AIでガクチカを自動生成するメリット
AIでガクチカを自動作成するメリットは、以下の3つです。
- ガクチカ作成 AIで短時間で作成できる
- ガクチカ作成 AIが文章の型に当てはめてくれる
- ガクチカ作成 AIによる思考の整理にも役立つ
AIの登場により、ガクチカの作成方法が大きく変化しました。
自分で最初から最後まで、考える方法もありますが、AIの力を借りることで、さまざまな恩恵が受けられます。
本章では、AIを利用してガクチカを作成するメリットについて解説します。
AIを利用するか迷っている就活生は、参考にしてください。
短時間で作成できる
AIを利用することで、ガクチカが短時間で作成できます。
AIにガクチカの作成を指示することで、与えられた情報をもとに瞬時に文章を生成してくれるためです。
もし、ガクチカを作るのに1社あたり15分かかったと仮定します。
AIを利用することで、1社あたりにかかる時間が5分以内に短縮できるでしょう。

就活は同時進行で進むものです。そのため、同じ締切日で複数の企業にガクチカを提出しなければならない場合もあるでしょう。ガクチカを丁寧に作成することは大切ですが、時間をかけ過ぎるとほかの部分で支障が出ます。そこで、AIのガクチカ作成ツールを使用することで、時間をかけずに質の高いガクチカが作成可能です。
文章の型に当てはめてくれる
AIはガクチカを作るにあたって、文章の型に当てはめます。
AIはPREP法やSTAR法といった、効果的な文章構成を理解しているからです。
そのため、面接官に自分の強みや経験が伝わりやすい文章を作成してくれます。
PREP法とは、結論から述べることで自分の主張を明確に伝える手法です。
また、STAR法は状況を具体的に説明し、自分の行動や経験をわかりやすく伝える文章構成です。
PREP法とSTAR法を利用するには慣れる必要があります。
しかし、AIを活用することで、自然な形でガクチカに盛り込んでくれます。
ガクチカの型を覚えるのに最適なパートナーになってくれるでしょう。
思考の整理にも役立つ
AIは、思考の整理にも役立ちます。
自分では気がついていない点をAIが分析し、可視化してくれるからです。
たとえば、学生時代のエピソードを短文で入力してください。
AIがどの点があなたの魅力になるのか、アピールするべきポイントなどをアドバイスしてくれます。
自分では気がついていなかった魅力や強みを発見することが可能です。

就活を始めて、自分の強みがどこにあるのか見つけられず、苦戦している就活生は多いでしょう。自分の強みに関して考えた経験が少ない人にとっては、難しい課題に見えます。しかし、AIを活用することで、自分を客観的に見ることが可能です。就活を始めたてで、思考がまとまっていない就活生は、AIを利用してみましょう。
【AIでガクチカ自動作成】AIでガクチカを自動生成するデメリット
AIでガクチカを自動生成するデメリットは、以下の3つです。
- オリジナリティがなくなる可能性がある
- 内容が浅くなる可能性がある
- 実際の経験と整合性が保てなくなる可能性がある
AIを使ってガクチカを作成する場合、デメリットについても理解しておくことが重要です。
AIによって作成されたガクチカを使用したからといって、必ず選考を通過するわけではありません。
デメリットをきちんと把握したうえで、活用しましょう。
オリジナリティがなくなる可能性がある
AIを使ったガクチカはオリジナリティがなく、テンプレート的な文章になりがちです。
ほかの就活生と似たような表現になってしまう可能性があります。
AIは、膨大なデータを参考にガクチカを作成します。
その結果、無難で一般的な文章が完成するでしょう。
一般的な文章では面接官の印象に残りません。
面接官は、採用を開始すると1日に何十人ものガクチカを読みます。
そのため、同じようなガクチカを提出してしまうと、面接官から高評価を獲得するのは困難です。

就活は、自分の魅力をアピールし、面接官の目に留る必要があります。AIは便利かつ、短時間で作成できる一方で、オリジナリティのないガクチカになるデメリットを理解しておきましょう。
内容が浅くなる可能性がある
AIを用いたガクチカは、内容が薄くなる可能性があります。
AIは、表面的な情報を集め、作成するのが得意です。
一方で、深い内容が盛り込まれた文章の生成は苦手です。
もし、あなたが事前に入力した情報が浅いものだったとします。
AIは、入力された情報をもとにガクチカを生成するため、完成するガクチカも浅い文章になるでしょう。
もちろん、AIなりに予測したり、文章を構築したりします。
しかし、あなたの内面や思考などへの洞察がおろそかになりがちです。

あなたが取り組むことにした背景や理由などの深掘りも苦手です。そこで、AIを利用する際は、感情や思考などをフォローするようにしましょう。
実際の経験と整合性が保てなくなる可能性がある
最後のデメリットは、実際の経験と整合性が保てなくなる可能性があることです。
AIが生成した文章は、あなたの経験内容と異なる事実が含まれていたり、現実離れした表現が含まれたりする可能性があります。
さらに、AIが「より良く見せよう」として、情報を追加することがあります。
その結果、本来の実績よりも誇張したガクチカになるかもしれません。

誇張表現は、面接官の印象に残りやすい効果があります。しかし、面接が進むにつれて誇張していたことが面接官にバレる危険があります。面接では同じ質問が角度を変えて問われたり、深掘り質問がなされたりするからです。実際とは異なる内容のガクチカは、面接官の信用を失うため注意してください。
【AIでガクチカ自動作成】知っておくべきガクチカの正しい構成
AIを使ってガクチカを作成する際にも、基本となる構成を理解しておくことが大切です。
ガクチカでは、ただ出来事を羅列するだけでなく、何を考え、どう行動し、何を学んだかを論理的に伝えることが求められます。
この章では、ガクチカの構成要素ごとに、押さえるべきポイントを丁寧に解説していきます。
構成をしっかりと理解することで、AIの生成した文章を自分らしく仕上げるための視点が持てるようになります。
以下の各要素を意識しながら、自分の経験に当てはめて見直していきましょう。
ガクチカが何か(結論)
文章の冒頭では、まず私が学生時代に力を入れたのは〇〇です。
といった形で、どのような活動に取り組んだのかを端的に伝えましょう。
この結論部分が曖昧だと、読み手に内容が伝わりにくくなってしまいます。
活動内容は、アルバイト、部活動、ゼミ、ボランティアなど、どのようなものであっても構いません。
初めに結論を示すことで、その後の説明が理解しやすくなり、文章全体の印象も明確になります。
まずは自信を持って、自分が力を注いだことを一文で表現しましょう。

活動を選んだ理由や背景に触れても良いでしょう。なぜその活動に取り組んだのかという思いや、自分にとっての意味づけを加えることで、より伝わる内容になります。結論部分で読み手の関心を引くことができれば、その後の内容にも興味を持ってもらいやすくなります。
どんな目標や課題があったのか
活動を紹介した後は、その活動の背景や目的、そして直面した課題について詳しく述べましょう。
目標が明確であるほど、その後の行動や成果に説得力が生まれます。
なぜその活動に取り組んだのか、どんな課題を抱えていたのかなどを丁寧に説明することで、読み手が状況を理解しやすくなります。
例えば、新しい参加者を増やす必要があった、活動がマンネリ化していたなどの具体的な課題があると、リアリティが増し、自分の考えや姿勢も伝わりやすくなります。
この段階で、問題意識や目標設定の能力を示しましょう。
加えて、課題に対する当初の気持ちや戸惑いがあった場合は、そのエピソードを入れることで、より人間らしい描写になります。
目標に対する真剣さや熱意を見せることで、評価されやすい文章になります。
どんな行動をしたのか
課題に対して、自分がどのような行動を取ったかを説明する部分では、工夫や努力、主体性を強調することが大切です。
どのような手順で問題解決に向けて取り組んだのかを、できるだけ具体的に記述しましょう。
定例ミーティングを導入した、SNSを活用したプロモーションを行ったなど、実際の行動を明確に記すことで、自発的な姿勢や実行力が伝わります。
誰でも実践できることではなく、自分だからこそできた工夫や工夫の背景も一緒に述べると、説得力が高まります。

行動の過程で何度も試行錯誤を繰り返した場合は、その過程も加えてみてください。最初はうまくいかなかったが、原因を分析して改善したといったエピソードは、成長の証として強い印象を与えることができます。
その結果は何か
次に、その行動によってどのような結果が得られたのかを記述します。
ここでは、数字や変化を交えて成果を具体的に示すと、読み手にインパクトを与えることができます。
参加者数が2倍になった、アンケートの満足度が上昇したなどの実績があると、効果的です。
もちろん、成果が思うように出なかった場合でも、その経験から得た教訓や改善点を前向きに伝えることができます。
失敗から〇〇を学んだという姿勢を見せることで、成長意欲や柔軟性をアピールすることができます。
成果を説明する際には、なぜその成果が出たのかという分析を加えると、より説得力のある内容になります。
また、結果に対する周囲の反応や、自分自身の気づきにも触れることで、深みのある文章に仕上がります。
取り組みから何を学んだか
成果の後は、その経験を通じて得た学びをしっかりと言語化しましょう。
この部分は、読み手にこの人がどんな人物かを伝えるための重要な要素です。
自分の成長や価値観の変化、今後に活かせる力について触れてください。
計画通りにいかない状況でも、冷静に分析し対策を講じる力がついた、チームの意見を尊重するリーダーシップの重要性を実感したといったように、経験から得た気づきを具体的に伝えることがポイントです。
企業にとっての魅力ある人物像を意識して書きましょう。

その学びがどのように自分の将来像に影響しているかを述べると、読者の理解がより深まります。自己成長のエピソードを織り交ぜることで、この人と一緒に働いてみたいと感じてもらえる可能性が高まります。
志望企業の業務に結びつける
最後に、取り組みで得た学びが志望企業の業務にどのように活かせるかを述べると、より完成度の高いガクチカになります。
ここは必須ではありませんが、志望動機や企業理解をアピールする上で大きな効果を発揮します。
この経験を通じて身につけた提案力を、貴社の営業職で活かしたいと考えていますなど、自分の強みと企業の求める人物像をリンクさせる表現を使うと、採用担当者の印象にも残りやすくなります。
文章全体を通じて、自分の価値を自然に伝えるように意識しましょう。

企業のビジョンや方針に共感していることに触れれば、より熱意が伝わります。私は御社の〇〇という理念に共感し、この経験で得た××を活かして貢献したいと考えていますといった形で締めくくると、説得力のある自己アピールが完成します。
【AIでガクチカ自動作成】人気なガクチカAI生成ツール
ここからは人気のガクチカAI生成ツールを6つ紹介します。
- 就活市場
- 就活AI byジェイック
- 内定くんAI
- PROPEN
- ChatGPT
- 就活Craft
どのツールもガクチカを作成するのに役立つツールなため、使い方や自分に合ったツールを使用していきましょう。
それぞれ、特徴などを含めて解説をしていきます。
就活市場
就活市場は累計ツール利用者数10万人を突破している学生応援メディアで、ガクチカや自己PRの作成に役立つAIツールなど就職活動のノウハウを提供しており、LINE登録者数は累計10万人を超えているので、就職活動の対策や準備に活用できます。
信頼度はもちろんのこと、ツールの精度も高く、多くの方に使われていて、各業界や職種に対応しているのが大きな特徴です。
私は学生時代に力を入れたことはアルバイトです。3年以上、店長補佐として勤務し、新人スタッフの育成に注力してきました。 当時、新人スタッフの習熟に時間がかかっていることが課題でした。そこで、私は新しいスタッフの育成マニュアルを作成し、効率的なトレーニング体制を導入しました。このマニュアルには、業務のステップや注意点が体系的にまとめられ、新人スタッフの理解を深めました。 その結果、新人スタッフの習熟スピードが大幅に向上し、店舗運営の効率化に貢献しました。この経験を通じて、問題点を分析し、効果的な解決策を導き出す問題解決力が強化されました。 また、スタッフ間の連携を強化するために、定期的なミーティングやチームワーク研修を実施しました。これにより、スタッフ間のコミュニケーションが円滑になり、業務効率の向上につながりました。 アルバイトでの経験を通じて、問題解決能力、コミュニケーションスキル、チームワークの重要性を学び、社会人としての基礎を培うことができました。この経験が、今後のキャリアにおいても活かされると確信しています。
就活AI byジェイック

就活AI byジェイックは、就職活動を効率化するために開発されたAIツールです。
自己分析やエントリーシートの添削、模擬面接のアドバイスなど、就活の各ステップをサポートしてくれます。
利用者の性格や希望に基づいた企業提案や、AIを活用した選考対策が特徴です。
ジェイックの豊富な就活支援実績を活かし、短期間で内定獲得を目指す方にはおすすめです。
無料で利用可能で、オンライン完結型なので忙しい学生でも手軽に始められる点が大きなメリットです。
内定くんAI

内定くんAIは、就活生を内定獲得までサポートするAI搭載ツールです。
3分で内定レベルの自己分析やエントリーシートが作成でき、LINEに送るとAIが無料で添削、作成をしてくれます。
AIが適性や志向に合った企業を提案し、ミスマッチを防ぎます。
無料で使える上、オンライン対応で場所や時間を問わず利用可能です。
ビックデータの活用と実績に基づいたアドバイスで、初めての就活でも安心して進められる点が大きな魅力です。
PROPEN

PROPENは、設問カテゴリを選択し、必要な情報を入力するだけで、AIが適切なエッセイを作成してくれます。
ガクチカ、自己PR、強み自己分析や志望動機など、就活のあらゆる場面をカバーし、的確なエッセイの作成が可能です。
AIは完璧ではないので、最後に自分で確認が必要ですが、エントリーシートなどに記載する文章を考えるのに役立つツールです。
ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した高度なAIチャットボットで多様なタスクに対応できる柔軟性が特徴です。
自然な会話が可能で質問への回答や文章作成、情報収集など、幅広い用途に活用できます。
膨大なデータを基にした高精度な応答に加え、24時間利用可能な利便性が魅力です。
専門的な知識にも対応でき、個別のニーズに応じたカスタマイズが可能です。
初心者からプロフェッショナルまで、多くの人が効率的にタスクを進めるための強力なツールです。
就活Craft

就活Craftは、LINE追加だけで利用できるガクチカ作成/添削アプリです。
2024年4月にリリースされたばかりの新しいサービスで、就活craftの公式LINEで質問に答えるだけでガクチカの文章が自動で生成されたり、添削をしてくれます。
ガクチカだけに限らず、志望動機の添削も可能で、面接時に人事が指摘しそうなポイントを踏まえて添削をするなど、企業目線を取り入れたガクチカ添削をできるようになっています。
【AIでガクチカ自動作成】AIが得意なこと苦手なこと
本章ではAIが得意なことと苦手なことについて詳しく解説します。
AIは完璧な存在ではありません。
そのため、なんでもできるツールと認識していると、思うような結果が得られない可能性があります。
AIを正しく利用し、最大限の効果を得るためにも、以降の解説を参考にしてください。
ガクチカの作成をすべてAIに任せるのではなく、頼れる相棒として利用することをおすすめします。
AIが得意なこと
AIが得意なことは以下の4つです。
| 得意なこと | 得られる効果 |
| 文章構成の整備 | 入力された情報をもとに、フォーマットを利用した文章作成ができる |
| 言葉遣いの調整 | ビジネスシーン、カジュアルな会話など、目的に応じた適切な表現や敬語の使い分けができる |
| PREP法などの適用 | PREP法やSTAR法といった特定の文章構成フレームワークを理解し、それに沿った形で情報が整理・出力できる |
| 似た事例からの例題作成 | 大量のデータ学習により、似たような状況や課題に対する具体例やテンプレートが生成できる |
AIは与えられた情報をもとにした文章を作成するのが得意です。
AIを活用する際は、あらかじめ十分な情報を提供し、ガクチカを作成させることで、魅力的な文章が完成するでしょう。
AIが苦手なこと
AIが苦手なことは以下の4つです。
| 苦手なこと | 苦手な理由 |
| 感情の理解 | AIは文章から感情を推測できないため、感情を理解した文章が作成できないから |
| 柔軟な対応 | 予期せぬトラブルのような、あらかじめ与えられていない情報には対応できないから |
| 道徳的な判断 | ルールやデータにない複雑な情報を判断できないから |
| ゼロからの創造 | 既存のデータや与えられた情報をもとに生成するから |
AIは感情や人間性、細かなニュアンスなどの表現が苦手です。
ほかにも、自分の成長や反省のような「リアリティがある描写」などは、人間の手で加える必要があります。
AIでも生成できますが、AIらしい文章となりガクチカで評価を受けるのは困難です。
【ガクチカAI作成】AIを使った実際の書き方
AIを使った実際の書き方は、以下の4つです。
- 自己分析をして入力情報を整理する
- 業界・企業研究を参考にアピールポイントを決める
- ガクチカ作成に使用するツールを選ぶ
- 面接官の目線で文章添削をする
AIに丸投げするのではなく、自分で準備・対策することで魅力的なガクチカになります。
自己分析をして入力情報を整理する
まずは、自己分析をして入力情報を整理しましょう。
AIにガクチカを書かせるには、入力情報や文章の方向性が必要です。
事前にあなたの特性や強みが発揮されたできごとを振り返って情報を整理してください。
たとえば「友人の喧嘩を仲裁した」「アルバイトで新人を教育した」などです。
次に、ガクチカとしてアピールしたいポイントとエピソードを選定しましょう。
AIにポイントとエピソードを作成することも可能ですが、自分で選んでください。
AIは企業が求める人物像を知らないからです。
あなたが調べた企業情報と過去のエピソードを比較して、マッチしたものにしましょう。
業界・企業研究を参考にアピールポイントを決める
志望する業界・職種・企業にあわせてアピール内容を変えましょう。
入社意欲や志望動機の高さを伝えられるからです。
たとえば、海外企業と取引がある企業にエントリーした場合、語学力のアピールはプラスに働きます。
一方で、地元の企業同士のつながりで商売している場合、語学力の優先度は低くなるでしょう。
そこで、あなたが志望する業界・職種・企業に合ったポイントをチョイスしてください。
ポイントを見極めるには業界・企業研究がおすすめです。
公式ホームページや就活サイト、企業説明会などに参加することで、効率よく情報が収集できます。
とくに企業説明会は、担当者と直接会話できるチャンスです。
志望動機を作成するきっかけになるでしょう。
ガクチカ作成に使用するツールを選ぶ
次にガクチカ作成に使用するツールを選んでください。
ツールによって指示の出し方が異なるため、自分に合ったツールを探して使用することが重要です。
ツールによっては、質問に回答するだけでガクチカを作成してくれるものがあります。
一方で、自分で言葉やキーワードを入力するタイプもあります。
ほかにも、直感的に操作できるものやスマートフォンに対応しているかなど、さまざまな違いがあるため、あらかじめ確認することが重要です。
以下の章では、実際のガクチカAI生成ツールを紹介しています。
それぞれの特徴や魅力について、解説しているので、使いやすそうなものから選択してください。
面接官の目線で文章添削をする
AIで作成したのち、面接官の目線で文章を添削してください。
AI作成による文章の違和感や誤字をチェックするためです。
たとえば、以下の項目に当てはまっていないか確かめてください。
- 抽象的な表現が多い
- 一般論を並べているだけ
- 文章に感情や変化がない
面接官が読んだときに採用したいと思える文章に修正しましょう。
また、面接で同じ質問をされることも想定しながら添削してください。
あまりにも説明が足りていないとアピールになりません。
おすすめの添削タイミングは、書き上げた直後ではなく時間をおいてから添削することです。
時間をおくことで冷静な状態で文章をチェックできます。
【ガクチカAI作成】AIを使う際のコツ
AIを使う際のコツは、以下の3つです。
- 誤字脱字などはこまめにチェック
- 一番伝えたいことを指示
- 繰り返し添削
AIは、うまく利用することで魅力的なガクチカが完成します。
本章で解説するコツを理解、実践し内定獲得に役立ててください。
誤字脱字などはこまめにチェック
コツの1つ目は、誤字脱字などはこまめにチェックすることです。
AIは高度な文章を作成してくれる便利なツールです。
しかし、完璧な文章を出力してくれるわけではありません。
AIを信じ切り、確認を怠ると誤字脱字を生む原因になります。
そこで、章や段落ごとに誤字脱字や文法のチェックを指示してください。
こまめにチェックすることで、不自然な文章や文法の誤りに気がつく可能性が高くなります。
一番伝えたいことを指示
AIには一番伝えたいことを指示してください。
AIは指示が曖昧だと、意図しない方向性の文章を生成してしまうからです。
最初に文章の目的、読み手、伝えたい内容などを正確に指示してください。
たとえば「ガクチカを作成して」と伝えるだけでは曖昧な指示です。
あなたの強みが主体性であれば、一番伝えたい要素が主体性だと伝えてください。
要点を絞ることでAIは文章を作成しやすくなります。
また、面接官も内容を理解しやすくなるのでおすすめです。
繰り返し添削
AIで作成した文章は繰り返し添削しましょう。
細かく指示を出すことで、自分が理想とするガクチカに近づくからです。
また、AIは一度の生成で完璧な文章は作成できません。
あなたからのフィードバックと修正指示を繰り返すことで、完成度が高くなります。
また、他者からの添削を受けるのも重要です。
友人や就活エージェントに読んでもらうことで、客観的なアドバイスがもらえます。
さらに、添削によって自分らしい表現を加えるとオリジナリティがあるガクチカになります。
第三者の目線を取り入れる
AIをうまく利用するには、第三者の目線を取り入れてください。
AIには気付けない「印象の弱さ」や「伝わりにくさ」などがチェックできるからです。
たとえば、大学のキャリアセンターや就職エージェントの利用がおすすめです。
プロ目線でガクチカを見てもらうことで、効果的なアドバイスが得られます。
また、AIを用いたことを指摘された場合、面接官も同じ印象を高い確率で持つでしょう。
事前に修正し、提出することで効率よくガクチカが完成できます。

第三者にガクチカを読んでもらうのは緊張するかもしれません。しかし、就活は人に見られるものです。早い段階から人に見られることに慣れておくことで、面接で実力を発揮しやすくなるでしょう。
【AIでガクチカ自動作成】ガクチカAI作成ツールを使うときの注意点
AIを活用したガクチカ作成ツールは、就職活動の効率化やクオリティ向上に大いに役立ちます。
一方で、AIが作成した文章をそのまま使うのでは、十分な説得力や自分らしさを欠いてしまうこともあります。
このツールを正しく活用するには、AIの特徴や限界を理解し、自分の経験や意図に合わせて使いこなすことが重要です。
ここでは、ガクチカAI作成ツールを使う際に注意しておきたいポイントを紹介します。
過剰な依存を避ける
AIで作成したものを修正を加えずにそのまま提出してしまうとあなたらしさが薄れてしまいます。
AIは補助的なツールであり大枠を作ることはできますが、最終調整やエピソード選定は必ず自分で行う必要があります。
また採用担当者は今までにいくつものエントリーシートを見て選考をした経験があります。
その中でAIで作成したガクチカは違和感を感じさせてしまうことでしょう。
過度に依存することなく自分の言葉を活かすように心がけましょう。
正確な情報を入力する
ガクチカAI作成ツールを活用するときは必ず正確な情報を入力しましょう。
入力する内容が曖昧だったり事実と異なったりすると生成される文章も信用度を欠く内容になってしまいます。
正確で詳細な情報を提供することが重要です。
バランスを意識する
AIの文章作成が便利だからと言って、自分の経験や個性を薄めないようにしましょう。
AIツールで作成したガクチカは自分の言葉と適切に合わせていくとより自然な文章を作ることができます。
何事にもバランスは大事です。
最初の段階でガクチカを形にするのが難しい人は大枠を作ってもらい、オリジナリティを追加してもいいでしょう。
また自分で作ったけどもう少しブラッシュアップしたい人もより効果的に使いこなしてみましょう。
誇張や嘘をしない
AI作成ツールを使用するにあたって、誇張や嘘はつかないでください。
書類選考ではバレませんが、面接の質問で矛盾が生じる可能性があります。
面接官は就活のプロです。
誇張や嘘が発覚すると信頼を失う可能性があります。
自分の価値を高めるために、成果を魅力的にしたくなる気持ちは理解できます。
しかし、エピソードの誇張や捏造、嘘をつくのは避けましょう。
とくに学歴を偽った場合、経歴詐称となり採用が取り消される可能性があるので注意してください。
抽象的な表現を避ける
AIに作成を指示する際、抽象的な表現を避けましょう。
ガクチカに説得力がなくなるからです。
たとえば「アルバイトを頑張りました」と述べるだけでは、説得力のないガクチカになります。
AIはわざと出力したわけではないので、指示内容を変えることが大切です。
ガクチカ内に具体的なエピソードや数字を盛り込むように指示しましょう。
具体的な経験や実績がある人は、指示段階で記入しておきましょう。
出力される文章に説得力が生まれます。
企業との関連性を意識
魅力的なガクチカにするために、企業との関連性を意識しましょう。
企業が求める人物像にマッチしたガクチカにすることで、選考が有利に進むからです。
チャレンジ精神を歓迎する企業に対して、慎重な性格をアピールしても高評価を得る可能性は低いでしょう。
そこで、志望企業の情報を研究し、求める人物像をAIに指示してください。
情報収集には公式ホームページや就活サイト、インターンがおすすめです。
さまざまな角度から調査することで、精度の高い情報が手に入ります。
個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いには注意してください。
AIに入力した内容は、学習材料にされるからです。
個人情報など不特定多数の人の目に触れるべきではない情報は、入力しないでください。
AIに指示する際は、曖昧にしておき、完成後に自分で加筆修正しましょう。
また、ガクチカ作成ツールを利用する前に利用規約やプライバシーポリシーをチェックし、個人情報の取り扱いに問題がないか調べることをおすすめします。
【AIでガクチカ自動作成】よくある質問
AIを使いガクチカを作成しようと考えている就活生が疑問に思うことをまとめました。
これからAIを活用する就活生にとって同じ悩みを抱えている人が大勢いることを理解し、安心する材料にしてください。
また、AIは非常に便利なツールの1つです。
就活を効率よく進めるためには欠かせません。
しかし、使い方を誤ると本来の効果が得られず、かえって逆効果になる可能性があります。
以下の質問と回答を参考に対策してください。
AIで作成したガクチカは他の就活生と差別化できますか?
自分なりのエピソードや言い回しを工夫することで差別化できます。
AIを活用してできあがった文章は似たような表現や言い回しになりがちです。
そのため、完成した文章をそのまま利用するのは避けてください。
面接官は面接のプロです。
読んだ瞬間にガクチカでAIを利用していることを見抜きます。
あくまでAIはガクチカ作成のサポート役と捉えて、完成した文章を自分の言葉に置き換えましょう。
差別化を意識するのであれば、自己分析が大切です。
自分が体験した内容に当時の感情を加えることでオリジナリティある文章になります。
効率よくAIを使うことでスムーズに就活が進められるでしょう。
自分の経験がうまく表現されない場合は?
より具体的な内容や情報を加えることで、自分が思い描く文章に近づきます。
詳しい内容をAIに指示していないと、どこかで見たような文章ができあがるでしょう。
例えば「苦労した点と解決方法について詳しく表現して」「エピソードから得た経験を強調して」と指示することで、AIがより自分の経験を中心にした表現が可能です。
一度で完璧な文章が完成することは難しいため、何度も修正しながら自分が思い描く内容にしていきましょう。
AIに指示するポイントは、AIに対してどうしてほしいのか明確に伝えることです。
内容を膨らませてほしい箇所、もっとアピールしたい場所は必ず伝えましょう。
AIにガクチカを作成させたらバレますか?
ガクチカをAIが作成した文章をそのまま提出してしまうとすぐにバレるでしょう。
面接官は、大勢の就活生のガクチカを読んだり聞いたりしているため、違和感に気が付きやすいです。
AIはガクチカが思いつかない就活生が序盤に使用するツールです。
すべてが就活に利用できるものではないため注意してください。
AI自体を就活で使用するのは問題ありません。
しかし、面接官に「AIを使用した」と思われないようにすることが大切です。
完成した文章を何度も読み込み、AI独特の表現や言い回しになっていないか提出前に確認しましょう。
自分の好きな言い回しや文章表現にすることで面接官にAIを使用したことがバレにくくなるでしょう。
AIが生成する内容の信頼性や品質はどうでしょうか?
AIは膨大な量のデータをもとに作成しているため、標準的な品質の文章ができあがります。
しかし、機械的な表現になりやすいため、完成後は必ず自分の目で確認してください。
自分で読み直すことでAI特有の文章表現に違和感を感じるため、修正する箇所が明らかになります。
例えば「〜しました」が連続で使用されている場合があります。
単調な表現となり人間らしい文章から離れてしまうでしょう。
他にも、前後の文章に関係性があるかチェックしてください。
AIが作るガクチカの文章の中には、突然内容が変わるものや関係のない話しを展開していることがあるためです。
一度でも目を通しておけば気が付く点なので忘れずに確認しておきましょう。
完全にAIに任せて大丈夫?
あくまでAIは「補助ツール」であり、最終的な仕上げは自分で行うことが大切です。
AIにすべて任せてしまうと、自分の魅力が面接官に伝わらない可能性があります。
AIは、与えられた情報を膨らませながらガクチカを作成しています。
そのため、実際に当てはまらない文章を作成するかもしれません。
そのままガクチカを提出してしまうと、間接的に嘘をついていることになるでしょう。
もし、面接で質問された場合、回答に困る可能性があります。

面接官は、面接のプロです。表情や仕草から嘘だと見抜くでしょう。AIを利用することで、ガクチカ作成は簡単にできます。しかし、すべてをAIに任せるのではなく、自分でもガクチカを読み、内容に問題がないかチェックしましょう。
【AIでガクチカ自動作成】まとめ
AIでガクチカが簡単に作成できるツールと使用する前に知っておきたいメリット・デメリットについて解説してきました。
AIを効果的に活用することで時短となり、他の準備に時間がかけられるようになります。
一方で自分が作成していないことがバレると面接官の評価が悪くなるリスクもあります。
独自のエピソードを追加したり、言い回しを修正するようにしてください。
AIを有効活用して納得のいく就活にしましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)













柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
自己分析が不十分な段階でも、AIにキーワードや経験を入力することで、自分の強みや活動を客観的に捉えるヒントが得られる点も魅力の一つです。効率的な準備を進めたい学生にとって、AIは非常に頼りになる存在となっています。