- 大学3年の2月は情報解禁前の重要な時期
- 2月には自己分析、業界研究をはじめとした就活準備を充実させるべき
- ESや面接などの選考対策も進めていくことが大切
大学3年生の2月は、本格的に就職活動を行う一歩手前の大切な時期になります。3月からは実際に一部上場企業などでは情報が解禁となってエントリー受付が始まり、徐々に余裕のある期間はなくなります。そのためにも今から少しでも就活の準備を進めておくことが必要です。
アルバイトをされている方もシフトは控えめにし、自分としっかり向き合う時間を作りましょう。この期間の準備ができているかいないかで、その後内定のときに差が出てきます。
本記事では、大学3年生の2月から就活を始めるのはもう遅いのか、また2月からの就活では何をすべきなのかという点について徹底解説していきますので、ぜひ今後の就活の参考にしてください。
目次[目次を全て表示する]
大学3年生の2月から就活を始めるのはもう遅い?
就活を3年生の2月からスタートさせるのは、正直、かなり出遅れていると言わざるを得ません。一般的に就活開始は3年生の始め頃が望ましいとされているため、そういった標準のペースを考えれば、遅れていることで「良い状況とはいえない」ことは確かです。
しかしながら、2月初旬であれば、3月に来る情報解禁のタイミングまで約1か月あります。徹底的に準備を進めればエントリーには間に合うため、「もう就活終わったかも…」と悲観せず、しっかりと就活と向き合うことが大切です。
本記事のポイントを十分に押さえ、できる限りの対策を行いましょう。
26卒の2月1日時点の内定獲得率
先日、リクルートやNHKの調査により、26卒就活生の2月1日時点の就職内定率があきらかになりました。
26卒の2月時点の内定獲得率は以下のとおりです。

26卒の2月1日時点の就職内定率は39.3%で、25卒の内定獲得率と比べて15.4ポイント増加する結果となっていました。
年々早期化している就活ですが、今年もその傾向は強いことがわかります。
しかし、逆に言えばまだ6割もの学生が内定を獲得できていない状況ということです。内定を獲得する学生が最も多くなるのは例年3月から6月にかけてなので、2月から就活を始めるのは出遅れているとはいえまだまだ間に合うともいえるでしょう。
大学3年生の2月が就活で重要な理由
大学3年生の2月は、就職活動において極めて重要な時期です。多くの企業が3月のエントリー解禁を控えており、事前準備の差がその後の選考結果に大きく影響します。
- 企業の採用情報が出そろう
- 選考対策のラストスパートが必要
- 早期選考が本格化する

この時期に自己分析を深め、志望業界や企業を明確にすることで、エントリーシートや面接対策をスムーズに進めることができます。早期選考を実施する企業では2月中に本選考が始まることもあるため、選考フローを確認し、万全の準備を整える必要があります。
限られた時間を有効に活用し、3月以降の本格的な選考に備えることで、希望する企業への内定獲得の可能性を高めることができるでしょう。
大学3年生の2月からやるべき就活対策11選
3月からエントリーなど本格的に始まってしまうので、その後は面接などで本当に時間がなくなってしまいます。
3年生の2月というのは、最後のチャンスといっても過言ではありません。少しでも時間を作り、しっかりと集中して就職の対策を行っておきましょう。
1.就活情報サイトへの登録
大学3年生の2月は、就職活動の準備を本格化させる時期です。その中でも、まず取り組むべきなのが就活情報サイトへの登録です。
- 就活市場
- Digmedia
- ベンチャー就活ナビ
多くの企業は3月から本選考のエントリーを開始します。事前に情報サイトへ登録しておくことで、企業の募集情報や説明会の日程をスムーズに確認できるだけでなく、早期選考の案内や特別なイベントの招待が届くこともあります。

サイトによってはエントリーシートや面接対策のコンテンツ、過去の選考情報が充実しており、効率的に就職活動を進めることができます。特に志望業界が定まっていない場合は、複数のサイトを活用することで視野を広げることができるでしょう。
就職活動のスタートをスムーズに切るためにも、2月のうちに必要なサイトへの登録を済ませておくことをおすすめします。
2.自己分析のやり直し
もうすでに大学でも就活へ向けた取り組みが始まっていて、自己分析はすべて終わった方もいるかもしれません。しかしこの自己分析は後から気が付く点なども出てきますし、何回しても無駄がないくらい大切な部分といえます。
- 自分史を作る
- モチベーショングラフを作る
- 他己分析をする
自己分析なくして就活を行っても、本当にやりたいと思っていた仕事に就けない可能性が高くなります。過去の経験については、どんな些細なことでも良いので思い出しておきましょう。

大したことのないエピソードのように思えても、そこに自分の価値観が詰まっていて軸を探せるかもしれません。良いエピソードだけでなく、挫折して悔しかったことなども思い出してみましょう。よく面接では、5年後、10年後はどのようになっていたいか問われます。企業側でも学生がどんな未来を描いて、仕事をどのように取り組んでいきたいと思っているのか気になっているのです。ここでしっかりとビジョンが確定していれば、面接で問われてもイメージしながら話せます。
3.業界研究・企業研究を行う
2月には必ず、業界研究・企業研究を行いましょう。
業界研究とは、業界について市場規模や事業内容、どんな会社があるのかなどを詳しく調べることです。 それに対して企業研究は、企業ごとの事業内容や職種、働き方、売り上げや年収まで細かく調べることとなります。
- 業務内容
- 社風、MVV
- 業界内での立ち位置と競合他社
業界研究と企業研究を行う目的は、自分に合う業界・企業を見つけることにあります。 これを怠った状態で就活を進めて内定を獲得したとしても、その業界、企業のことを理解していなければ「思った雰囲気と違う」「想像と違う仕事しかしていない」といった理由からミスマッチを感じて早期離職につながってしまいかねません。
せっかく人生に一度の就活をするのですから、将来長く働ける企業に入社したいですよね。 そのためにも、業界研究・企業研究は念入りに行いましょう。

3月になると就活スケジュールがパンパンになって、業界研究・企業研究どころではなくなる可能性も高いです。 今のうちにやっておくことをおすすめします。
4.就活の軸を決める
何が軸になっているのかはその人によって違いがあります。だからこそ大切に考えたい部分です。
軸がブレてしまうと、仕事を始めてから後悔しずっと働くことが苦しくなってしまいます。
自分がこうでありたいというビジョンを考えることも重要なのですが、企業側がどのようなビジョンを持っているかを調べることも大切です。

すべて自分で決めるだけではなく、他人からのアドバイスを求めることも重要になってくるでしょう。その際には就活エージェントを利用すると効率的に進められます!
5. 志望動機・自己PR・ガクチカのひな形を作る
2月中には、ESや履歴書、面接で求められることが多い、志望動機や自己PR・ガクチカのひな形を作っておきましょう。
この3項目は、就活中に何度も求められ、何度も書いたり伝えたりすることになります。そのため毎回文章を一から考えていては、時間が無くなってしまいますし、文章をブラッシュアップしていくこともできません。
ひな形をあらかじめ作っておいて、選考の度に文章を少しづつ良いものにしていくことで、3月以降に受けることになる本命の企業の選考の際に、通過率をぐっとあげることができます。
6.OBOG訪問
大学3年生の2月は、OBOG訪問を始める絶好のタイミングです。実際に企業で働く先輩の話を聞くことで、業界や職種への理解を深めることができます。
OBOG訪問では、仕事内容や企業の雰囲気、入社前と後のギャップなど、就活サイトや説明会では得られないリアルな情報を知ることができます。また、実際に働く人のキャリアの考え方や仕事のやりがいを聞くことで、自分に合った企業選びの参考にもなるでしょう。
訪問の際は、事前に質問を準備し、限られた時間で有意義な話ができるようにすることが大切です。特に、志望業界が定まっていない場合は、さまざまな業界のOBOGに話を聞くことで視野を広げることができます。
早めに動き、できるだけ多くの先輩に話を聞くことで、より納得のいく企業選びができるでしょう。
7. Webテスト・筆記試験の対策
2月は、Webテストや筆記試験の対策に時間を使える最後のチャンスだと考えてください。
3月以降の本選考では、倍率がグンと上がるため、Webテスト・筆記試験を使って就活生を振り子にかける企業も少なくありません。しかし、ほとんどのWebテストや筆記試験はぶっつけ本番で高得点が取れるものではなく、また他の就活生も対策をしてきているため、対策をしない状態で試験に望んでは大きく出遅れてしまいます。
自分が本命としている企業ではどのような形式のWebテスト、筆記試験を採用しているのかを早めに調べた上で、2月中に十分に対策をしましょう。
なお、代表的なテストであるSPI3の概要と対策については、以下の記事をチェックしてみてください。
8.面接練習
2月の就活では、実践的な選考対策として、面接練習も欠かせません。面接練習では、事前に質問内容を予測して回答を準備し、本番でしっかり答えられるように練習することが大切です。
- 自己PRやガクチカ、志望動機の想定回答を作る
- 模擬面接を行う
- 話している様子を録画する
- 面接対策セミナーや勉強会に参加する
質問に対する答えをしっかりと用意し、それをはきはき答える練習を重ねておけば、緊張を減らした状態で自信をもって本番に臨めます。

まずは、志望企業の面接における質問の傾向をつかんだうえで、面接官に魅力を感じてもらう回答をじっくり準備しましょう。どのような質問をされるのかという情報は、キャリアセンターでの相談やOBOG訪問を通じて詳しくリサーチするなどの方法があります。模擬面接を行う際は、友人・家族などに面接官役を務めてもらい、回答内容や受け答えの態度についてフィードバックをもらうと良いでしょう。なお、面接の定番質問については、以下の記事をぜひチェックしてみてください。
9.就活エージェントへの登録
2月の就活では、準備をより万全にするために、就活エージェントに登録することがおすすめです。2月は情報解禁まで時間がないため、準備が不足している状態では、有利に就活を進められません。
情報解禁までに、書類作成や面接練習の質を少しでも高めるなら、就活エージェントへの相談が適しています。就活エージェントでは、一人ひとりに担当者が付くため、書類添削や模擬面接などの選考対策を納得いくまで行ってもらえます。
ほかには、さまざまな求人を提案してもらえるので、自分に合った企業・職種を見つけるうえでも就活エージェントには大きな強みがあります。
なお、就活エージェントへの登録・相談は基本的に無料です。時間がない中でも効率よく準備を進めるためにも、情報解禁までには、ぜひ就活エージェントへの登録を済ませておきましょう。
10. 3月以降に受ける企業候補の選定
2月からの就活で本格的に準備を進める際は、3月以降にエントリーする企業の候補をしっかりと選定しておく必要があります。
3月には多くの企業が新卒採用の情報解禁を行いますが、それに先立ち、2月中には情報を少しずつ出し始める企業も少なくありません。そのため、採用情報の情報収集は、3月に入る前から始めることができます。早いうちから情報収集を徹底的に行っておけば、自分に合う企業を見極めやすくなります。
3月に入ってからでは、選考対策も含めて何かとバタバタすることが多くなるため、大事な情報を見逃してしまう恐れもあります。忙しい中で企業選びを行うと、落ち着いて自分の適性や興味関心を判断できない可能性もあるため、余裕をもって選べるという意味でも候補選びは早めのほうがおすすめです。
少しでも気になる企業があれば、早めに情報をキャッチしておきましょう。
11. 外資系やベンチャー企業の選考を受ける
2月から就活を始める際は、外資系やベンチャー企業の選考を受けておくことも大事です。外資系やベンチャー企業は選考のタイミングが通常より早いため、3月以降の本選考に先立って選考を受けておけば、エントリーシート作成や面接に慣れることができます。
事前に選考を受けて場数を踏んでおけば、3月以降の本命の選考でも落ち着いて対応できるようになります。特に緊張しやすい人や、選考を受けるうえで不安が大きい人などは、前もって経験を積めるという対策は非常に有効です。

結果として早期選考で内々定が出れば、内定を持った状態で3月以降の本選考に臨めるため、ある程度気持ちにゆとりを持つこともできるでしょう。外資系やベンチャー企業の選考は、2月よりもさらに前の12月や1月にも実施されるケースもあるため、本選考前に場数を踏みたい人は積極的に情報をチェックしておきましょう。
企業の一般的な就活スケジュール
就職活動のスケジュールは、企業が経団連(日本経済団体連合会)に加盟しているかどうかによって異なります。経団連加盟企業は政府の指針に沿ったスケジュールを採用することが多い一方で、非加盟企業は独自のスケジュールで採用活動を進めることが一般的です。
以下で具体的に解説していきます。
経団連に入っている場合
政府の就活ルールに従い、多くの企業が以下のスケジュールで動きます。
- 大学3年生 6~8月:インターンシップ開催
- 大学3年生 3月:採用情報の公開・エントリー受付開始
- 大学4年生 6月:面接・選考開始
- 大学4年生 10月:内定解禁
経団連に入っていない場合
外資系企業やベンチャー企業を中心に、経団連非加盟の企業は独自のスケジュールで採用活動を行います。
- 大学3年生 夏~秋:インターンシップを通じた早期選考開始
- 大学3年生 秋~冬:本選考開始(ES提出・面接実施)
- 大学3年生 冬~大学4年生春:内定出し
外資系企業やコンサル、投資銀行などは、大学3年生の秋から選考を始め、年内に内定を出すケースもあります。早期から企業研究を進め、自分が志望する企業のスケジュールを確認しておくことが重要です。
【参考】25卒の一般的な就活スケジュール
就職活動のスケジュールは、国主導で方針が定まっています。そのため、経団連に加盟している大企業は国が決めた方針に沿った就活スケジュールで動いています。
25卒の学生の一般的な就活スケジュールは以下の通りでした。
- 大学3年3月:企業の広報活動解禁
- 大学3年3~大学4年5月:エントリー、説明会への参加、ESの提出
- 大学4年6月:面接など選考活動の開始
- 大学4年10月:内定式
早期選考などを含めるとこの通りではないですが、やはり就職活動の本格的なスタートは大学3年生の3月からであったことがわかります。
情報収集や企業の絞り込みを2月のうちに行うことを意識できれば、3月以降の就活がより有効になるといえるでしょう。
次章では、26卒の就活スケジュールについてより細かく解説をしていきます。
26卒の一般的な就活スケジュールにおける2月の位置付け
ここまで、2月まで、そして2月からやるべき就活対策について解説してきました。
ここでは、26卒の一般的な就活スケジュールにおける2月の位置付けを見ていきましょう。
2月が就活全体においてどのような時期にあたるのかを理解することで、2月にどんな就活をするかが重要である理由を理解していただけるかと思います。
選考スケジュール、内定獲得率、就活スタート時期の3点に重点をおいて解説をしていきます。
大学3年生の2月の選考スケジュール
大学3年生の2月は、多くの企業が本選考を本格的にスタートさせる直前の時期です。
特に大手企業の場合、エントリーの締め切りが迫っていたり、説明会やセミナーの開催頻度が増える時期でもあります。このため、2月は情報収集とエントリーを進める上で非常に重要なタイミングということになります。
また、早期選考を行う企業やインターンシップ参加者を対象にした特別早期選考が進む時期でもあるため、もしチャンスを手にした場合はこうした機会を逃さないよう注意が必要です。

業界、企業によって実際の選考スケジュールはかなり異なります。例えば、外資系企業、ベンチャー企業であれば2月よりももっと前に選考をスタートしていることもある一方で、商社や広告業界は3月からスタートする企業が多い傾向にあります。
自分がいきたい業界、企業の選考スケジュールを事前に把握した上で計画的に動きましょう。
大学3年生の2月の内定獲得率

*就活みらい研究所の調査より
2025年度卒業学生の2月1日時点での内定率は、23,9%と、前年までの内定率を上回る結果となりました。
これは、就活の早期化が進んでおり、3月の情報解禁以前に選考を進めていく企業、就活生の数が増えていることが理由だと考えられます。
大学3年生の2月から就活を始めるのはやや遅い
2月から就活を本格的にスタートする場合、やや遅れているといえます。既に自己分析や企業研究を終え、エントリーやインターンを経験している就活生も少なくないため、差が明確に現れてくる時期といえます。
しかし、まだ焦る必要はありません。限られた時間を有効活用するために、本記事で紹介している就活準備をひとつひとつ丁寧にこなしていきましょう。
特に優先してほしいのは、以下の3つです。
- 自己分析をして自分が進むべき業界、企業の目星をつける
- 業界研究、企業研究をして自分に本当に合う業界、企業を見つける
- 説明会に実際に参加して就活の雰囲気をつかむとともに、早期選考チャンスを狙う
2月以降の活動が今後の就活の成功に大きく影響するため、効率的な計画を立てて進めていくことが重要なポイントとなります。
2月のおすすめの就活スケジュールと過ごし方
- 〜1週目:自己分析・企業研究
- 〜3週目:志望動機、自己PR、ガクチカの作成
- 3月直前:説明会、選考参加のための準備
ここまで解説してきたように、2月は本選考前の事前準備期間であり、この時期にやるべきことを整理して計画的に就活を進めることが就活成功の鍵です。そこで、どのような計画で2月をすごせば良いのか、おすすめの就活スケジュールや過ごし方をここで紹介します。
あくまで目安ですが、ぜひ参考にして自分の2月の就活スケジュールを組んでみてください。
2月の1週目までの過ごし方
- 自己分析
- 業界研究、企業研究
- 受ける企業の絞り込み
2月の1週目までには、自己分析と業界研究・企業研究をある程度進めておく必要があります。
自己分析では、自分の強み、弱み、興味のあることなどを明確にし、将来のキャリアプランを具体的に考えられるように準備しておきましょう。
また業界研究・企業研究では、業界の動向や企業の事業内容、募集されている職種、求める人物像などを調べ、志望企業を絞り込んでいきます。
3月1日になってから説明会や選考を受ける企業を選んでいては、どの企業の選考に進めばいいかよくわからない状況で就活を進めることになってしまいます。
2月中にある程度志望企業を絞り込んでおくことで、3月以降の就活に自信を持って、かつスムーズに取り組めるようにしておきましょう。
2月の2〜3週目の過ごし方
- 志望動機、自己PR、ガクチカの作成
- Webテスト、筆記試験の対策
2月の2〜3週目には、志望動機や自己PR、ガクチカなどの作成に取り組みましょう。
自己分析や業界研究・企業研究の結果を踏まえ、自分の強みや経験をどのように企業にアピールするかを考え、説得力のある文章を作成することがポイントです。
また、Webテストや筆記試験の対策も、遅くとも3週目までには始めましょう。

2〜3週目には選考対策をおもに進めていただきたいのですが、ここで重要になってくるのが業界研究・企業研究です。自分が行きたい業界、企業ではどのような人物像が求められているのかを十分に把握して、それに合わせたアピールができるように準備しておくことが選考突破の鍵となるからです。
逆に言えば、選考対策を見越した業界研究、企業研究をすることが大切とも言えます。
3月の情報解禁直前の過ごし方
- リクルートスーツ、証明写真の用意
- 交通手段の確認
- エントリー企業の締切の最終確認
3月の情報解禁直前には、説明会や選考に参加するための準備をしましょう。リクルートスーツや証明写真の用意、交通手段の確認など、当日に慌てることがないように、事前に準備しておくことが大切です。
また、3月1日からエントリーする企業の締切がいつあるのかを再度確認しておきましょう。何度重ねて確認しても損することはありません。漏れがないよう、カレンダーやメモ帳にしっかり記録しておきましょう。

2月から3月にかけては、普段の生活から面接のポイントを意識して過ごすこともポイントです。結論ファーストで話すことや、言葉遣いや口癖を認識して矯正すること、話を聞く時の姿勢を正すことなどがあげられます。
普段の過ごし方から意識しておくことで、面接のとっさの場面でもボロを出すことなく高評価がもらえる可能性が高くなります。
2月に焦っている学生向けの就活対策
2月になり、周りの就活生が準備を進めているのを見て焦りを感じる人も多いかもしれません。しかし、今からでも対策を進めれば十分に間に合います。ここでは、出遅れたと感じたときにやるべきことや、短期間で効率よく準備を進める方法を紹介します。
出遅れたと感じたらやるべきこと
就活が2月に差し掛かり、周りの進捗を見て「出遅れた」と感じることもあるかもしれません。しかし、焦ることはありません。まずは冷静になり、現状を整理することが大切です。
まだ選考が開始していない企業をリストアップし、自分がどの程度準備を進めているのかを振り返りましょう。その上で、エントリーシートの作成や自己分析、業界研究など、今からでもできることをリスト化します。

志望企業のスケジュールやエントリー情報は早めにチェックし、3月のエントリー開始に向けて準備を整えましょう。就活情報サイトに登録し、企業の採用情報を逃さずキャッチすることも重要です。慌てずに、最低限必要な準備を優先的に進めることで、焦る気持ちを抑えて、着実にステップアップできます。
- 現状を把握する
- 最低限やるべきことをリストアップする
- 優先順位を決めて行動する
今からでも間に合う就活の進め方
2月になってから就活を本格的に進める場合でも、まだ十分に間に合います。
まず最初に就活の全体像を把握し、就活情報サイトに登録し、企業のエントリー開始時期を確認しましょう。その後、企業の選考スケジュールやインターンシップ情報もチェックして、効率的に応募を始める準備を整えます。
並行して、自己分析や業界研究を進めておくことが重要です。自己分析を通じて自分の強みや志望動機を整理し、エントリーシートを作成しましょう。

エントリーシートの作成は、自分の考えを簡潔に表現する力を高めるため、他の企業にも活用できるようにします。面接対策も始めておきましょう。面接対策では過去の質問例を調べ、模擬面接を通じて実践的な準備をしておくことが、就活をスムーズに進めるための鍵です。
- 就活情報サイトに登録し、企業の選考スケジュールを確認する
- エントリーシート(ES)作成を最優先で進める
- 自己分析と面接対策を並行して進める
- OBOG訪問や説明会に参加し、企業理解を深める
- エントリーを進めながら、短期間でブラッシュアップ
志望企業の早期選考が終わってしまったら
志望していた企業の早期選考が終わってしまったとしても、まだ諦める必要はありません。まず、その企業の追加募集や二次選考があるかどうか確認しましょう。また、早期選考に参加できなかった場合でも、他の企業の選考スケジュールや早期選考情報をチェックし、次のチャンスに備えることが大切です。

志望業界や職種にこだわり過ぎず、少し視野を広げて他の企業に目を向けてみましょう。特に、OBOG訪問や企業説明会に参加することで、その企業の内情や採用の傾向を把握できることがあります。
もし早期選考を逃したと感じても、他の企業でチャンスを見つけることは可能です。
選考が始まる前に、情報収集をしっかりと行い、次のステップに向けて準備を整えることが重要です。
- 追加募集や二次選考がないか確認する
- 他の企業にも視野を広げ、似た業界・職種を探す
- OB訪問などを活用し、次回のチャンスに向けた情報を得る
短期間で選考対策を仕上げる方法
短期間で選考対策を仕上げるには、効率的に準備を進めることが不可欠です。
まず、エントリーシートや自己PR文を早めに作成し、企業ごとに少しずつカスタマイズする方法を取ります。ESはテンプレートを活用して、必要に応じて修正を加えることで時間を短縮できます。
また、面接対策を進める際は、過去の質問例を調べ、頻出の質問に対する自分の答えを整理しておくことが重要です。面接練習を行うことで、自信を持って臨むことができ、短期間でも対応力を高めることができます。

選考情報を収集し、企業ごとの傾向や求める人物像を把握することが、効果的な対策につながります。限られた時間でも、しっかりと準備を進めることで、選考を通過する力をつけることができます。
- ESはテンプレを活用し、複数企業に対応できる形にする
- 面接対策は頻出質問に絞って、具体的なエピソードを整理
- 過去の選考情報を調べ、企業ごとの傾向を把握する
- 模擬面接を活用し、短期間で改善点を洗い出す
就活を始めるやる気を出す方法
就活を始めることに対してやる気が出ないと感じる人も多いでしょう。就活の情報解禁は一般的に3月であるため、2月の今始めておけば、3月から始めようとしている学生に比べると有利に進めることができると考えましょう。
そして「とにかく何か一つでも始める」ことが効果的です。例えば、就活情報サイトに登録するだけでも、気持ちが少し楽になるかもしれません。
次に、友人や先輩と情報交換をすることで、就活の進め方や考え方に刺激を受けることができます。また、自分が本当にやりたいことや目指す業界について考える時間を持つことも、モチベーションを高める一因になります。
さらに、小さな目標を設定し、それを達成することで自信をつけ、次のステップに進む気力が湧いてきます。最初の一歩を踏み出すことが、就活のやる気を引き出す鍵となります。
- 簡単なタスクから始める
- 就活イベントや説明会に参加し、雰囲気を感じる
- 友人と情報交換をし、刺激を受ける
- 小さな成功体験を積み、モチベーションを上げる
大学3年生の2月にある就活イベント
- 冬期インターンシップ
- 早期選考
就活のイベントは大切にし、4年生の時にしっかりと内定を決められるようにしておきましょう。特に就活のイベントは3年生になると増えていくので、自分なりにスケジュール管理も必要となります。
気になっている企業がいくつかあると、同じ日程で重なってしまうケースもあります。狙っている企業があれば、極力すべて参加できるようにスケジュール管理を怠らないようにしましょう。
冬期インターンシップ
特に第一候補である場合や数ある中でもやっぱりここで働きたいと思う企業がある場合はインターンシップに参加しましょう。
夏にもあるのですが、特に冬期インターンシップでは今後の就活や採用活動に直結する内容となっていますので外せません。企業側でもただ面接だけに来られるよりも、早い段階からインターシップにも参加してくれる学生を大切にしたいと思っています。
気持ちが強いともっとその企業について知りたいと思いますし、それがこういったインターンシップへの参加など行動に表れます。
早期選考
2月には、早期選考が実施される場合があります。早期選考は、実施している企業と実施していない企業に分かれるため、あくまで企業によることを覚えておきましょう。
そのためまずは、志望企業が実施しているかどうかを、事前にチェックすることが大切です。
ちなみに早期選考は、インターンに参加した就活生の中から、優秀な人だけに与えられるチャンスである場合も多いです。その際はエントリーの募集がかかるわけではなく、エントリーできるかどうかは、インターン中の取り組み・態度が関わっているといえます。
そのため、早期選考参加を目指す際は、インターンに積極的に参加するなどの対策が欠かせません。タイミングも早いため、とにかく気になった時点で早めに動くことも重要です。
なお、大学3年生で内定をもらう方法や具体的なポイントについては、以下の記事をぜひ確認してみてください。
大学3年生の2月からの就活を成功させるコツ
- 内定がなくても焦らない
- 業界や企業は絞っておく
- プレエントリーの締切に注意する
- 就活に必要なものをそろえる
- ニュースを見る習慣をつける
大学3年生の2月からの就活は、早いとは到底いえず、むしろ準備を始める時期としてはかなり遅いといえます。
しかし、前述のとおり情報解禁までにはまだ時間が残されているため、コツを押さえたうえで対策を徹底することが重要です。
2月という切羽詰まった時期だからこそ、就活成功のコツは徹底的に実践しましょう。
内定がなくても焦らない
2月に就活を進めていると、周囲の学生の中には早い段階で内定を獲得している人も出てきます。特に、1月までに内定を得ている友人がいると、自分の進捗に不安を感じる場合も多いでしょう。
しかし、この段階で焦る必要はありません。2月はまだ準備期間であり「就活本番はこれから始まるのだ」という意識を持つことが重要です。
焦ることで準備が不十分なまま応募を進め、興味のない業界にエントリーしてしまうと、良い結果にはつながりません。むしろ、2月を有効活用し、自己分析や企業研究をさらに深め、志望動機や自己PRを磨くことに集中しましょう。
就活はマラソンのようなもので、途中で力尽きることがないよう、長期的な視点を持つことが重要です。
業界や企業は絞っておく
2月の段階で焦る必要はありませんが、できれば業界や企業はこの段階で絞っておくことが重要です。インターンシップに参加したり、自己分析を深めたりして、自分の志望動機や強みを明確にしている学生が多いからです。
志望する業界を2つから3つ程度に絞り、それぞれの業界の中で大手企業、中小企業、さらにベンチャー企業など、規模の異なる企業をリストアップしておくことが重要です。
この際、企業選びの基準を明確にすることも忘れてはなりません。自分の価値観や将来のビジョンに合った企業を選ぶことで、志望動機や面接での回答に一貫性が生まれます。

安定した環境で長期的に働きたい場合は大手企業を中心に調べることを推奨しますし、裁量権を持って若いうちから挑戦したい場合は、ベンチャー企業や成長中の中小企業を選ぶと良いでしょう。
プレエントリーの締切に注意する
2月から就活をスタートさせる際は、プレエントリーの締切にくれぐれも注意してください。3年生の2月には、3月本選考開始の企業のプレエントリーが順次始まっていきます。
企業によっては、プレエントリーを済ませなければ本選考へのエントリーができないケースがあるため、注意が必要です。
就活に必要なものをそろえる
2月の就活で失敗しないためには、まず、遅くならないうちに就活に必要なものをそろえておくことがおすすめです。証明写真やスーツなど、就活で必ず使うものがしっかりそろっていない状態だと、3月以降の選考の際にトラブルになる可能性があります。
直前になってあわてて準備をすると、必要なものを間違えたり、書類作成などその他の準備が遅くなったりする原因にもなります。そのため、不足しているものがある人は、2月のうちにしっかり準備しておきましょう。
就活でそろえるべきアイテム
- リクルートスーツ一式
- 腕時計やベルトなどの小物
- 就活用の手帳
- 証明写真
- 履歴書の書式
なお、2月はまだ気候的に寒いため、就活の際もコートが必要になる場合も少なくありません。コートなどの防寒アイテムの準備については、意外と見逃してしまうことが多いため注意しましょう。
それ以降の3月~4月は、春先とはいえ冷える日も多いため、必要に応じて春用の就活コートを用意することも大事です。
就活のコートのマナーや選び方については、以下をチェックしておきましょう。
ニュースを見る習慣をつける
2月の就活を成功させるには、今の時点で、ニュースを見る習慣をつけると良いでしょう。なぜなら、積極的にニュースを見て世の中の動きをチェックしておくと、時事ネタが関わる質問などにもスムーズに対応できるからです。
また、ニュースではさまざまな業界や企業の動向をつかむこともできます。今流行っているものや問題になっていることなどを知れば、それに合わせて各企業がどのように動いているのかも見えてくるでしょう。
時事ネタに関心を持つようになれば、自然と各業界・各企業の動きにも敏感になってくるものです。
しかし、付け焼き刃的に時事情報の知識を入れても役には立たないため、2月の段階からニュースに関心を持つ習慣づけが必要になります。
毎朝の食事の際はニュースを見る、ニュースアプリをスマホに入れて積極的にチェックするなどの行動は、積極的に習慣づけましょう。
アルバイトのシフトを調整する
2月からの就活を成功させるためには、事前に、就活にコミットしやすい状況を作っておくことが重要です。中でも注意したいのは、アルバイトのシフトです。
アルバイトのシフトに多く入っていると、3月以降の本選考で、スケジュールをうまく調整できない可能性があります。また、3月に入ってからシフトの相談をするのでは、アルバイト先も困ってしまうでしょう。そのため、アルバイトのシフトの調整は2月中に行っておくことが賢明です。
「就活に専念するためシフトを減らしたい」などと相談すれば、アルバイト先もある程度配慮して3月以降のシフトを組んでくれるでしょう。
なお、大学3年生の2月以降のアルバイトについては、以下の記事もチェックしてみてください。
大学3年生の2月以降の就活のポイント
大学3年生の2月から就活を始める際は、情報解禁のタイミングに差し掛かるため、さまざまな点に注意が必要といえます。事前に就活のポイントをチェックし、乗り切るための対策を立てましょう。
2月からの就活は、確かにスタート時期としては遅いですが、ポイントを押さえれば効率的に内定獲得を目指せます。本項目では、大学3年生の2月以降の就活のポイントを、月ごとにチェックしていきます。
では、それぞれを詳しく解説していきます。
3月のポイント
まずは、3月のポイントを見ていきましょう。3月の就活は、本選考のエントリー開始のタイミングを迎えるため、状況が急に進む点に注意しましょう。
一つひとつの展開がスピードアップし、目まぐるしく状況が変わることで戸惑ってしまう人も少なくありません。そのため、3月は少しでも余裕をもって行動できるように、できる限り予定を空けておくことを心がけてください。
急に予定が埋まることが多いため、予定が空いていれば柔軟に対応できることで、就活を進めやすくなります。
また、目まぐるしく変化する就活の進行状況に対して就活以外のことが忙しいと、非常に疲れてしまうことも多いです。
4月のポイント
続いて、4月の就活のポイントをまとめていきます。4年生になる頃の4月には、ESを提出し選考に受かった企業の面接がスタートしていきます。
そのため、基本的に4月以降は面接対策が必要不可欠です。徹底的に実戦につながる面接対策を行い、時間がないからこそ一気に面接のシーンに慣れていく必要があります。
なお、通過した企業とのやり取り・面接は丁寧にこなすことが肝心なので、4月を乗り切るには精神力や体力が重要です。
そして、4月は新たに学校の履修を組む季節でもあります。就職するためにはそもそも卒業しなければならないため、学業と就活のバランスは間違えないようにしましょう。
5月のポイント
4年生になり、5月を迎える頃には、就活を終了している同期も出てきます。そのため人によっては極端に焦ってしまい、プレッシャーから、かえって失敗が続くことで就活がより泥沼化してしまうことも多いです。
しかし、やはり焦りは禁物です。そもそも、内定が決まる時期や選考の進むペースなどは業界によって大きく異なります。
周りが内定を獲得しているからといって、自分も焦って就活を終えようとするのではなく、満足いくまで十分に応募を重ねていくことが大切です。
大学4年生が2月から内定を得る方法
大学4年生の2月は、卒業を間近に控えたタイミングのため、大部分の同級生が就職先や進路を決めている状態になります。時期的に大学4年生の2月は、もはや就活の時期ではなく、春からの入社のためにさまざまな準備を重ねている時期になります。
そのため現実的なことをいえば、今からの採用はかなり厳しい状況であり、就職浪人を考えている人も多いでしょう。
しかしながら、2月の段階で4年生に内定を出す企業もあるため、春からの就職を目指すならとにかく最後まで諦めないことが大切です。

今まで内定をもらえなかったことには、選考対策が足りない・自己分析や企業研究が不十分など、さまざまな原因があることでしょう。そういった原因をしっかりと分析したうえで、効率的かつ徹底的に対策を講じるためにも、就活エージェントなどの支援サービスは積極的に活用するようにしてください。
大学1、2年生が2月にできる就活対策
大学1、2年生の方が2月にできる就活対策についても紹介します。
以下の対策は早い段階から取り組むことができるため「就活本番で焦りたくない」という方はぜひ以下の2つの対策を取り込んでください。
冬インターンへの参加
大学1年生、2年生が2月にできる就活対策の1つに、冬インターンへの参加があります。3年生を対象としたものが多いと思われがちですが、1年生や2年生でも参加可能なものも存在します。
企業が若い学年の学生に早い段階で会社の魅力を伝えることを目的とするプログラムでは、学年の制限がない場合が多いです。このようなインターンに参加すれば、他の学生よりも早く社会の現場を知り、仕事理解を深められるでしょう。
また、若い学年でインターンに参加することでビジネスの基本的なマナーやコミュニケーション能力、課題解決能力など、就活に必要なスキルを早い段階で身につけられます。そして、インターンの経験を通じて自己分析を進め、自分がどのような業界や職種に向いているかを明確にするきっかけにもなるでしょう。
このように、冬インターンへの参加は後の就活をスムーズに進めるための貴重な準備段階なのです。
長期インターンへの参加
長期インターンは1年生や2年生の方にとって特におすすめの就活準備の一環です。冬や夏に開催される短期のインターンとは異なり、長期インターンは募集が年中行われていることが多いことが特徴です。
学年を問わず応募可能な場合が多いため、早い段階から実際の業務に携わりたいと考えている方にとって理想的な選択肢と言えます。
長期インターンは短期のプログラムとは異なり、社員と同様の仕事に携われる機会が与えられることも少なくありません。営業やマーケティング、補助業務、企画書作成、データ分析など、実際の業務を通じて実践的なスキルを磨くことが可能です。
このような経験は、履歴書に書けるアピールポイントになるだけでなく、自分自身の成長にも大きく寄与します。
社会人としての責任感や時間管理能力、チームでの協調性といったスキルが自然と身につくでしょう。
2月の就活に関するよくある質問
最後に、2月の就活についてよくある質問を紹介していきます。
2月の就活は、3月の情報解禁がすぐそこまで迫っているタイミングだからこそ、さまざまな不安や疑問が生まれる時期ともいえます。そのため、よくある質問をチェックし、わからないことはしっかりと解消しておきましょう。
よくある質問は、以下のとおりです。
大学3年生の2月という時期は、周りの学生が動き始めていることもあり、遅れを感じる人もいるかもしれません。
しかし、結論から言えば「遅くない」と言えます。
特に、2月は本選考開始前の準備期間として重要なタイミングです。この時期から効率的に準備を進めることで、巻き返すことが可能です。
2月は就活スケジュールが本格化する時期で、多くの学生にとって忙しい時期になります。
企業説明会やインターンシップのエントリー締切、エントリーシート(ES)の提出、さらには本選考が始まる企業も多く、スケジュール管理が大変になる時期でもあります。
特に、大手企業や人気企業を目指す場合、この時期はスケジュールがタイトになりがちです。
結論から言うと、2月の時点で就活の準備が進んでいない場合、遊びや旅行に行くことはあまりおすすめできません。
なぜなら、2月は就活が本格化する重要なタイミングであり、この時期に準備を始めないと後々焦る可能性が高いためです。特に人気企業を目指している場合や就活スケジュールが読みにくい場合、今から準備を始めることが必要です。
ただし、もちろん全く遊ばない方が良い、というわけではありません。適度にリフレッシュはしつつ、就活準備を進めましょう。
まとめ
3年生の2月というのは、これから大手のエントリーが始まりまだ実際に大きく就活のムードが出ていない時期でもあります。だからこそ、就活の準備が後回しになってしまう可能性もあるかもしれません。
ただ就活から内定までをスムーズに行いたいと思ったら、このまだ本格化していない時期が非常に重要になります。何もしていなさそうな友人も、実は自宅でしっかりと就活の準備をしているかもしれません。
本格的に就活がスタートしたときに大きな差が出ますので、内定を手にするためにも早めに準備をしましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート







_720x480.webp)














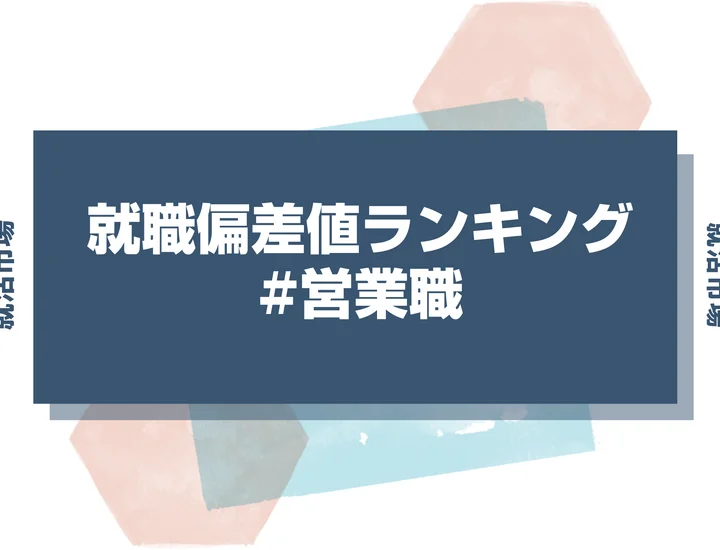

_720x550.webp)






柴田貴司
(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)
柴田貴司
(就活市場監修者)
大学3年生の2月は就職活動において極めて重要な時期で、3月から企業の選考が本格化し、エントリーシートや面接が始まるため、2月は準備を整える最後のチャンスと言えます。準備が不足したまま3月を迎えるとエントリーシートや面接対策に追われ、十分な準備時間を確保できない状況に陥る可能性が高まるのです。したがって、2月中に基本的な就活対策を終えることが求められます。