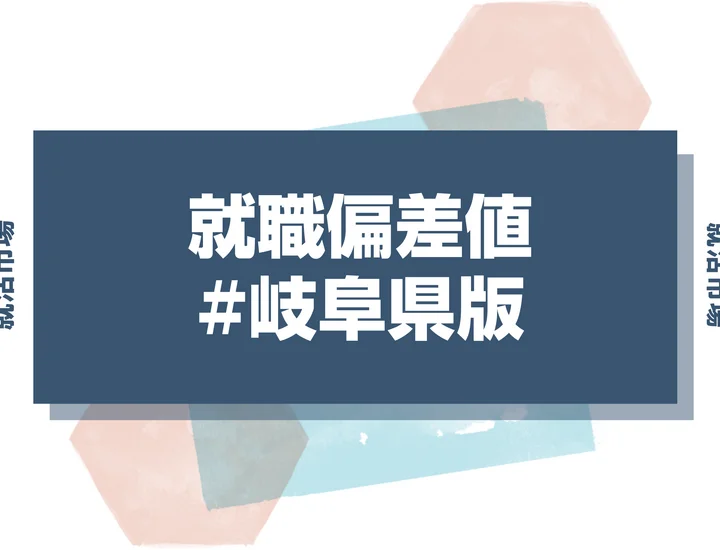はじめに
日本を代表する大手企業であることは知っていても、「結局、なんの会社なの?」「自分にも挑戦できる?」と疑問に思っている人もいるかもしれませんね。
この記事では、そんな富士通のリアルな姿を、企業研究から選考対策まで分かりやすく解説していきます。
【富士通はなんの会社】富士通はどんな会社なのか
富士通は、ひと言でいうと「日本を代表する総合ITベンダー」です。
主に法人(BtoB)や官公庁向けに、情報システムやネットワーク、最先端のテクノロジー(AIやクラウドなど)を活用したソリューションを提供しています。
皆さんの生活に直接触れる製品(昔はPCなども有名でしたね)よりも、社会インフラや企業のビジネスを裏側から支える、「社会のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進企業」と捉えると分かりやすいでしょう。
【富士通はなんの会社】富士通の仕事内容
富士通と聞くと「SE(システムエンジニア)」のイメージが強いかもしれませんが、実際には非常に多様な職種が連携してビジネスを動かしています。
文系・理系問わず、活躍のフィールドが広いのが特徴ですね。
社会インフラを支える大規模なシステム開発から、最先端技術の研究、そしてそれらを社会に届ける営業活動や会社の基盤を支えるスタッフ業務まで、多岐にわたる仕事があります。
自分自身の強みや興味がどの分野で活かせるか、具体的な職種を知ることで、入社後のイメージも湧きやすくなりますよ。
ここでは、新卒採用で募集されることが多い主要な職種をピックアップして、その具体的な仕事内容を見ていきましょう。
各職種がどのように連携しているのかを理解することも、企業研究の大切なポイントです。
ソリューションエンジニア(SE)
ソリューションエンジニア、いわゆるSEは、富士通のビジネスの中核を担う職種です。
お客様である企業や官公庁が抱える課題をヒアリングし、それを解決するための最適なITシステムを設計・開発・構築、そして運用・保守まで一貫して担当します。
単にプログラミングをするだけでなく、お客様の業務内容を深く理解し、どうすればIT技術でビジネスをより良くできるかを考える、コンサルタント的な側面も強い仕事です。
例えば、「在庫管理を効率化したい」「新しいオンラインサービスを立ち上げたい」といった要望に対し、AIやクラウドなどの最新技術を組み合わせて具体的な形にしていきます。
大規模なプロジェクトが多く、チームで協力しながら社会に大きなインパクトを与えるシステムを創り上げるやりがいがあります。
営業(ビジネスプロデューサー)
富士通の営業職は、近年「ビジネスプロデューサー」と呼ばれることも増えています。
これは、単にモノやサービスを売るのではなく、お客様のビジネスそのものをプロデュースし、成功に導くパートナーとしての役割が期待されているからです。
彼らはお客様の最も身近な窓口として、潜在的なニーズや経営課題を引き出し、前述のSEや研究開発部門と連携しながら最適なソリューションを企画・提案します。
例えば、ある製造業のお客様に対して「DXを進めて生産性を上げませんか」とアプローチし、具体的な導入プランを練り上げ、契約から導入後のフォローまで、プロジェクト全体を牽引していく役割です。
社内外の多くの人を巻き込み、ビジネスを創出するダイナミズムが魅力の職種と言えるでしょう。
研究開発
富士通の未来を創るのが、研究開発職です。
AI、セキュリティ、5G/6G、スーパーコンピュータ「富岳」に代表されるコンピューティング技術など、世界トップレベルの最先端技術の研究と、それを活用した新しいサービスや製品の開発を行います。
すぐにビジネスにならなくても、5年後、10年後の社会を見据えた基礎研究から、実用化に近い応用研究まで、その領域は広大です。
例えば、より高度な画像認識AIを開発したり、環境負荷の少ない新しいコンピューティング技術を模索したりします。
世界中の優秀な研究者と競い合いながら、まだ世の中にない価値を創造したい、技術をとことん追求したいという人に向いている職種です。
コーポレートスタッフ
企業活動を円滑に進めるために不可欠なのが、コーポレートスタッフです。
人事、財務・経理、法務、知的財産、広報・IR、購買・SCM(サプライチェーンマネジメント)など、その役割は多岐にわたります。
例えば、人事部門であれば、採用活動や社員の育成、働きやすい環境づくり(リモートワーク制度の整備など)を通じて、会社の「人」という最も重要な資産を支えます。
財務部門であれば、会社の資金調達や投資戦略を立て、経営の舵取りをサポートします。
直接お客様と接する機会は少なくても、経営陣に近い視点を持ち、会社全体の成長戦略を支える重要なポジションです。
専門性を高めながら、会社全体を動かす仕事に携わりたい人に向いています。
【富士通はなんの会社】富士通選ばれる理由と競合比較
富士通はSIer(エスアイヤー:システムインテグレーター)と呼ばれる業界に属していますが、この業界には多くの競合企業が存在します。
日立製作所、NEC、NTTデータなどが代表的なライバルですね。
就職活動では、「なぜ他の会社ではなく富士通なのか」を明確に説明できることが非常に重要です。
そのためには、富士通ならではの強みや特徴を、競合他社と比較しながら理解しておく必要があります。
各社の得意分野や注力している領域には微妙な違いがあり、それが社風や将来性にも影響してきます。
ここでは、富士通がなぜ選ばれるのか、その強みと、代表的な競合他社との違いについて掘り下げていきましょう。
この比較を通じて、富士通の立ち位置を客観的に把握してください。
強み:国内トップクラスのITサービス提供力
富士通の最大の強みは、長年にわたって培ってきた国内トップクラスのITサービス提供力にあります。
特に、官公庁や金融、医療、製造業など、社会の基盤となる重要分野の大規模システム構築において、圧倒的な実績とノウハウを持っています。
これは、単に技術力が高いだけでなく、お客様の業務を深く理解し、信頼関係を築いてきた証拠です。
また、スーパーコンピュータ「富岳」の開発に象徴される高い技術力を持ちながら、それを実際のビジネスソリューションに落とし込む力も兼ね備えています。
全国を網羅するサポート体制も万全で、システム導入後の運用・保守までワンストップで提供できる総合力が、多くのお客様から選ばれ続ける理由です。
競合比較:NECとの違い
富士通とNECは、国内SIerとして長年のライバル関係にあります。
両社ともITサービス全般を手掛けていますが、得意分野に違いが見られます。
富士通が幅広い業種向けのシステム開発やDX支援に強みを持つのに対し、NECは通信キャリア向けのインフラ構築や、顔認証をはじめとする生体認証技術、AI技術に強みを持っています。
富士通は「サービス(お客様のDX支援)」に近年大きく舵を切っている印象ですが、NECは「技術(特に通信と認証)」を軸にしたビジネス展開が特徴的です。
どちらも官公庁に強いという共通点もありますが、得意とする技術領域やソリューションの方向性に違いがあると理解しておくと良いでしょう。
競合比較:日立製作所との違い
日立製作所もまた、富士通の強力な競合です。
日立の最大の特徴は、「IT(情報技術)」だけでなく、「OT(制御・運用技術)」と「プロダクト(製品)」の三位一体でソリューションを提供できる点にあります。
例えば、鉄道システムや発電所といった社会インフラ設備(プロダクト・OT)そのものを製造しており、そこにITを組み合わせて高度なソリューション(Lumada事業)を展開しています。
一方、富士通は近年、ハードウェア事業(PCや携帯電話など)を切り離し、ITサービスとソフトウェア、DX支援に経営資源を集中させています。
日立が「モノづくり×IT」の総合力で勝負するのに対し、富士通は「ITサービス・DXのプロフェッショナル」として特化していく戦略、という違いがあります。
将来性:DXとサステナビリティへの注力
富士通の将来性を考える上で重要なキーワードが「DX」と「サステナビリティ」です。
現代のあらゆる企業・団体にとって、デジタル技術を活用した変革(DX)は避けて通れない課題であり、富士通はそこを支援する「DXパートナー」としての地位を確立しようとしています。
AIやクラウド、セキュリティなどの分野に積極的に投資し、自社内でも大規模なDXを推進している点は強みです。
また、富士通はパーパス(存在意義)として「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」ことを掲げています。
単なる利益追求ではなく、環境問題や社会課題の解決にIT技術でどう貢献するかを重視しており、こうした姿勢が中長期的な成長の鍵となると考えられます。
【富士通はなんの会社】富士通の求める人物像
多くの企業研究を進めていると、「求める人物像」がどこも似たように見えてしまうことがあるかもしれません。
しかし、富士通が掲げる人物像には、同社のパーパス(存在意義)や「Fujitsu Way」と呼ばれる行動指針が色濃く反映されています。
ただ優秀なだけでなく、富士通というプラットフォームで何を成し遂げたいのか、その価値観がマッチしているかが重要視されます。
選考では、あなたの過去の経験が、富士通の求める人物像とどのように重なるのかを具体的にアピールすることが求められます。
ここでは、富士通が公式に発信している情報や採用の傾向から、特に重視される4つの要素を解説します。
自分自身と照らし合わせながら、自己分析のヒントにしてください。
「挑戦」:自ら考え行動できる人
富士通は今、自らを変革しようとする大きな渦中にあります。
伝統的なSIerから、お客様のDXを牽引するパートナーへと生まれ変わろうとしています。
そのため、既存の枠組みや常識にとらわれず、新しい価値を創造するために自ら考え、主体的に行動できる「挑戦」の姿勢が強く求められています。
学生時代の経験で言えば、前例のないことに取り組んだ、困難な課題に対して自分なりの工夫で乗り越えた、といったエピソードがアピール材料になります。
言われたことをやるだけでなく、常に「もっと良くするためには?」と考え、行動に移した経験を整理しておきましょう。
「信頼」:多様な人々と協働できる人
富士通の仕事は、そのほとんどがチームで行われます。
社内のエンジニアや営業、研究者だけでなく、お客様、パートナー企業など、非常に多くのステークホルダー(利害関係者)を巻き込んでプロジェクトを進めていきます。
そのため、異なるバックグラウンドや専門性を持つ人々と、誠実に対話し、信頼関係を築きながら協働できる能力が不可欠です。
「信頼」はFujitsu Wayの重要な要素でもあります。
サークル活動やアルバイト、グループワークなどで、多様なメンバーと目標達成に向けて協力した経験や、意見の対立を乗り越えてチームをまとめた経験は、大きな強みとなるでしょう。
「共感」:パーパスに共感できる人
富士通は「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパス(存在意義)を掲げています。
これは、富士通が何のために存在するのかを示す根本的な考え方です。
選考では、あなたがこのパーパスにどれだけ「共感」できるかが問われます。
なぜなら、同じ目的に向かって進める仲間を求めているからです。
単に「IT技術で稼ぎたい」ではなく、「IT技術を使って、より良い社会や持続可能な世界を実現したい」という想いを持っていることが重要です。
自分が過去に取り組んできた社会貢献活動や、社会課題に対する問題意識と、このパーパスを結びつけて語れると説得力が増します。
「お客様起点」:顧客の成功にコミットできる人
富士通のビジネスは、常にお客様(法人や官公庁)の課題解決から始まります。
そのため、常に「お客様起点」で物事を考え、お客様のビジネスの成功、その先にある社会の発展に最後までコミットできる姿勢が求められます。
これは、単にお客様の言う通りにするという意味ではありません。
時にはお客様自身も気づいていない本質的な課題を見抜き、専門家として最適な提案をし、困難なプロジェクトでも最後までやり遂げる責任感を指します。
アルバイトでの接客経験や、研究活動でお客様(共同研究先など)の期待に応えようと努力した経験などが、この素養を示す材料になるかもしれません。
【富士通はなんの会社】富士通に向いてる・向いていない人
企業研究と自己分析が進んできたら、次は「自分と富士通との相性」を客観的に見極める段階です。
どれだけ優れた企業であっても、自分の価値観や働き方の希望とミスマッチがあれば、入社後に苦労することになってしまいます。
富士通は、最先端の技術力と大きな組織力を持ち、社会に大きなインパクトを与える仕事ができる魅力的な会社ですが、その特性がすべての人に合うとは限りません。
大企業ならではの文化や仕事の進め方が、自分にとってプラスに働くか、それともマイナスに働くかを冷静に考えることが大切です。
ここでは、富士通の事業内容や社風、求める人物像を踏まえて、どのような人が活躍しやすいか、逆に向いていない可能性があるか、その特徴を具体的に見ていきましょう。
向いている人:最先端技術で社会課題を解決したい人
富士通は、AI、クラウド、スーパーコンピュータなど、世界最先端の技術に触れられる環境があります。
もしあなたが「最新のテクノロジーを学ぶのが好きだ」「その技術を使って、環境問題や医療、教育といった具体的な社会課題の解決に貢献したい」と強く願うなら、富士通は非常にやりがいのあるフィールドとなるでしょう。
特に富士通は「サステナビリティ」を経営の中心に据えており、ビジネスを通じて社会をより良くしようという意識が強い会社です。
自分の技術力や知識が、目に見える形で社会の役に立つ瞬間に大きな喜びを感じる人にとって、これ以上ない環境と言えます。
向いている人:大規模プロジェクトでチームワークを発揮したい人
富士通が手掛けるのは、官公庁の基幹システムや、大企業の経営を支えるシステムなど、社会的影響力が非常に大きい大規模なプロジェクトが中心です。
こうしたプロジェクトは、一人で完結することは決してなく、社内外の多くの専門家と協力して初めて成し遂げられます。
そのため、「個人で成果を出すよりも、チーム全員で大きな目標を達成することに喜びを感じる」「多様な意見を調整し、一つの方向にまとめていくプロセスにやりがいを感じる」といった協調性やチームワークを重視する人に向いています。
大きな船をみんなで動かしていくようなダイナミズムを求める人には最適な環境です。
向いていない人:安定志向が強すぎる人
かつては「大企業=安定」というイメージがありましたが、近年の富士通は大きく変わろうとしています。
年功序列的な人事制度から、個人の成果や挑戦を評価するジョブ型雇用への移行を進めています。
「一度入社すれば安心」という考え方や、「できるだけ変化せず、言われたことだけを静かにこなしたい」という安定志向が強すぎる人には、今の富士通は少し息苦しく感じるかもしれません。
むしろ、自ら学び、新しいスキルを身につけ、変化を恐れずに挑戦し続けることが求められる環境へとシフトしています。
向いていない人:BtoCの製品やサービスに携わりたい人
富士通のビジネスは、そのほとんどがBtoB(法人向け)またはBtoG(官公庁向け)です。
つまり、お客様は企業や政府機関であり、一般消費者が直接名前を知っている製品やサービスに携わる機会は多くありません。
(かつてはPCや携帯電話も手掛けていましたが、現在は別会社化されています)。
もしあなたが「自分が企画したアプリがヒットする」「一般の人々に使ってもらえる製品を作りたい」といった、BtoCビジネスに強い関心がある場合、富士通ではやりたい仕事とのミスマッチが生じる可能性があります。
自分の仕事の成果を、一般ユーザーの反応としてダイレクトに感じたい人には、他の業界の方が向いているかもしれません。
【富士通はなんの会社】富士通に受かるために必要な準備
富士通は日本を代表する人気企業の一つであり、内定を獲得するためには十分な準備が欠かせません。
選考プロセスは、エントリーシート(ES)の提出、適性検査(Webテスト)、そして複数回の面接(近年はジョブマッチング形式が中心)という流れが一般的です。
付け焼き刃の知識や対策では、他の優秀な学生たちに埋もれてしまいます。
大切なのは、富士通という会社を深く理解し、自分がいかにその会社で活躍できるかを論理的に、そして情熱を持って伝えることです。
選考の各ステップには明確な意図があります。
ここでは、富士通の選考を突破するために、就活生が今すぐ取り組むべき具体的な準備内容を4つのステップに分けて解説します。
これらを着実に実行することが、内定への近道となります。
企業研究:「Fujitsu Way」とパーパスの深い理解
まず最も重要なのが、富士通の企業理念である「Fujitsu Way」と、その中核をなす「パーパス(存在意義)」を深く理解することです。
パーパスとは、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」という富士通の使命を指します。
なぜ富士通がこれを掲げているのか、そして、このパーパスを実現するために具体的にどのような事業(例えば、DX支援やサステナビリティ関連のソリューション)に力を入れているのかを、自分の言葉で説明できるレベルまで落とし込みましょう。
単に暗記するのではなく、IR情報(投資家向け情報)や中期経営計画などを読み解き、その背景にある戦略まで理解することが、他の就活生との差をつけるポイントになります。
自己分析:求める人物像とのマッチング
企業研究と並行して行うべきが、徹底した自己分析です。
特に、富士通が求める人物像である「挑戦」「信頼」「共感」といったキーワードと、あなた自身の過去の経験とを紐づける作業が不可欠です。
「挑戦」であれば、困難な目標に自ら取り組んだ経験、「信頼」であれば、チームで何かを成し遂げた経験、「共感」であれば、社会課題の解決に関心を持ったキッカケなど、具体的なエピソードを掘り下げてください。
なぜその時そう考え、どう行動し、何を学んだのか。
そのストーリーが、あなたが富士通の社風や価値観とマッチしていることを示す強力な証拠となります。
選考対策:エントリーシート(ES)の具体性
ESは、あなたの第一印象を決める重要な書類です。
「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」や「志望動機」は、必ず問われる質問です。
ここでのポイントは「具体性」です。
ガクチカでは、課題に対してどのような仮説を立て、どう行動し、結果どうなったか、そして何を学んだかを論理的に記述しましょう。
志望動機では、「なぜIT業界か」「なぜ富士通か」「入社後何がしたいか」の3点を明確にすることが重要です。
特に「なぜ富士通か」では、競合他社(NEC、日立など)との比較を踏まえ、富士通のパーパスや事業のどこに魅力を感じているのかを具体的に書く必要があります。
選考対策:面接(特にジョブマッチング)と逆質問
富士通の選考、特に理系やSE志望の場合、「ジョブマッチング」という形式で、希望する部門の現場社員と面談するケースが多いです。
これは、お互いのミスマッチを防ぐための重要なステップです。
ここでは、ESの内容を深く掘り下げられると共に、あなたの専門性や仕事への理解度が問われます。
自分が希望する職種(例:○○業界向けのSE)が、具体的にどんな仕事をしているのか、どんな技術を使っているのかを事前に調べておきましょう。
また、面接の最後にある「逆質問」は、あなたの志望度と理解度を示す絶好のチャンスです。
給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「○○様が感じる富士通の変革のスピード感は?」など、一歩踏み込んだ質問を用意しておきましょう。
【富士通はなんの会社】富士通の志望動機の書き方
就職活動において、志望動機は合否を分ける最も重要な要素の一つです。
特に富士通のような大手企業では、毎年何千人もの学生がエントリーします。
その中で「この学生に会いたい」「この学生と一緒に働きたい」と思わせるためには、熱意と論理性を兼ね備えた志望動機が不可欠です。
「ITの力で社会貢献したい」といった漠然とした理由だけでは、採用担当者の心には響きません。
なぜ数あるIT企業の中で富士通を選んだのか、あなた自身の経験や価値観と、富士通のパーパスや事業がどう結びついているのかを、具体的な言葉で伝える必要があります。
ここでは、説得力のある志望動機を構築するための4つの重要なステップを解説します。
このフレームワークに沿って、あなただけの志望動機を練り上げてください。
なぜIT業界か、なぜSIerか
志望動機の土台として、まず「なぜIT業界を志望するのか」を明確にする必要があります。
例えば、「大学の研究でデータ分析の面白さに目覚めたから」「ITが社会インフラに不可欠であり、その根幹を支える仕事に魅力を感じたから」など、あなた自身の原体験や問題意識に基づいた理由を述べましょう。
その上で、なぜIT業界の中でも「SIer(システムインテグレーター)」なのかを説明します。
「特定の製品やサービスに縛られず、お客様の課題に応じて最適な技術を組み合わせてソリューションを提供できる点に魅力を感じた」といった理由は、SIerを志望する上で有効な切り口です。
なぜ競合ではなく「富士通」か
ここが最も重要な差別化ポイントです。
SIer業界にはNEC、日立、NTTデータなど多くの競合が存在します。
その中で、なぜあなたは富士通を選ぶのか、その理由を明確にしなければなりません。
ここで活きてくるのが企業研究です。
例えば、「競合他社がハードウェアやインフラに強みを持つのに対し、富士通は『イノベーションによって社会をより持続可能にしていく』というパーパスに共感し、DXとサステナビリティ領域のソリューションに特に注力している点に惹かれた」といった、具体的な比較に基づいた理由が求められます。
富士通のパーパスや「Fujitsu Way」への共感を、自分の言葉で表現しましょう。
入社後に実現したいこと
富士通というプラットフォームを使って、あなたが何を成し遂げたいのか、具体的なビジョンを示すことも重要です。
これは、あなたのキャリアプランと富士通の事業とのマッチングを見るための質問でもあります。
「入社後は、ソリューションエンジニアとして、特に金融業界のDX推進に携わりたい。
貴社の最先端のセキュリティ技術と私の粘り強さを活かし、お客様のビジネス変革を支えたい」というように、希望する職種や事業領域(もしあれば)と関連付けて、入社後の貢献イメージを具体的に語りましょう。
実現したいことが明確であればあるほど、あなたの熱意と本気度が伝わります。
自身の強みと経験の活かし方
最後に、あなたの強みや学生時代の経験が、富士通の仕事でどのように活きるのかを論理的に結びつけます。
これは、あなたが入社後に活躍できる人材であることの根拠を示すものです。
例えば、「学生時代、飲食店アルバイトのリーダーとして、スタッフの意見を調整し、オペレーションを改善した経験がある。
この『多様な意見をまとめ、課題解決に向けて行動する力』は、お客様やチームメンバーと協働するSEの仕事で必ず活かせると考えている」といった具合です。
求める人物像(挑戦、信頼、共感)と関連付けながら、あなたのポテンシャルをアピールしましょう。
【富士通はなんの会社】富士通についてよくある質問
企業研究や選考対策を進める中で、企業の公式情報だけでは分からない、リアルな疑問も出てきますよね。
「実際のところ、年収はどれくらい?」「社風はやっぱり堅いの?」といった質問は、就活アドバイザーである私のところにも多く寄せられます。
こうした疑問を解消しておくことは、入社後のミスマッチを防ぐためにも非常に大切です。
ただし、ネット上の口コミや噂は玉石混交であり、中には古い情報や偏った意見も含まれます。
ここでは、就活生の皆さんが特に気になるであろう「よくある質問」について、複数の情報源や近年の動向を踏まえ、できるだけ客観的に解説していきます。
あくまで一つの参考情報として、あなたの企業選びに役立ててください。
平均年収や福利厚生は?
富士通の平均年収は、有価証券報告書(2023年度)によると約879万円と公表されています。
ただしこれは全従業員の平均であり、年齢や役職によって幅があります。
新卒の初任給も近年引き上げ傾向にあり、国内の大手メーカーやIT企業の中でも高水準であると言えます。
福利厚生に関しては、大企業ならではの手厚い制度が整っています。
家賃補助や家族手当(現在はジョブ型移行に伴い見直しが進んでいる部分もあります)、保養所、そして「カフェテリアプラン」(付与されたポイントを旅行や自己啓発などに自由に使える制度)など、非常に充実しています。
ワークライフバランスを支える制度が整っている点は、大きな魅力の一つでしょう。
社風や働き方は?(リモートワークなど)
社風については、「伝統的な日系大企業」というイメージを持つ人が多いかもしれません。
確かに、大規模な組織であるため、意思決定に時間がかかる側面や、部門間の縦割りを感じる場面はあるかもしれません。
しかし、近年は「Fujitsu Way」のもとで変革を強く推進しており、年功序列から成果・ジョブ型への移行、若手の登用なども進んでいます。
働き方に関しては、コロナ禍を機にリモートワークが全社的に強力に推進されました。
「Work Life Shift」というスローガンを掲げ、オフィス出社とリモートワークを柔軟に組み合わせるハイブリッドワークが定着しています。
フレックスタイム制も導入されており、自律的に働ける環境は整いつつあると言えるでしょう。
採用大学(学歴フィルター)はある?
結論から言うと、明確な「学歴フィルター」は無いと考えられます。
富士通は毎年非常に多くの新卒を採用しており、その採用実績校は、旧帝大や早慶といった最難関大学から、GMARCH、関関同立、地方国立大学、そして私立大学まで、非常に幅広くなっています。
もちろん、技術系の研究開発職などでは、大学での研究内容や専門性が重視されるため、結果として特定の大学院からの採用が多くなることはあります。
しかし、SE職や営業職、スタッフ職など多くの職種では、学歴そのものよりも、個人の能力、経験、そして富士通のパーパスへの共感度が重視される「人物本位」の選考が行われているとみて良いでしょう。
英語力は必要?
富士通はグローバルに事業を展開しており、海外売上高比率も高い企業です。
そのため、英語力は「あった方が良い」スキルであることは間違いありません。
特に、海外の顧客や拠点のメンバーとやり取りする部門、研究開発職で海外の論文を読む必要がある場合、また将来的に幹部候補を目指す上では、ビジネスレベルの英語力が求められます。
ただし、新卒採用の応募時点で、すべての人に高い英語力が必須というわけではありません。
国内のお客様を担当するSEやスタッフ職であれば、入社後に学ぶ機会も多くあります。
とはいえ、TOEICのスコアなど、学習意欲をアピールできる材料があれば、選考でプラスに働く可能性は高いでしょう。
まとめ
今回は、日本を代表するIT企業「富士通」について、事業内容から求める人物像、選考対策まで詳しく解説してきました。
富士通が、単なるシステム開発会社ではなく、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパスの実現に向けて、DXとサステナビリティを軸に変革を続ける企業であることを理解いただけたかと思います。
この記事を読んで、「富士通の仕事に魅力を感じた」「自分の強みが活かせそうだ」と感じた方は、ぜひさらに深く企業研究を進め、自信を持って選考にチャレンジしてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート