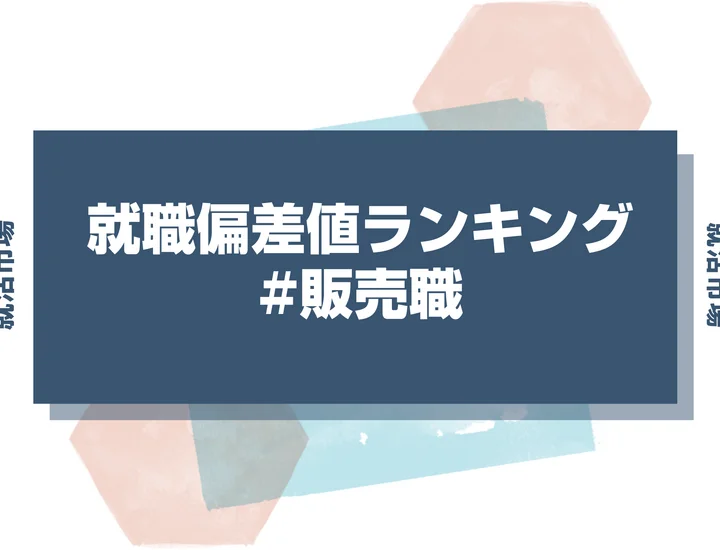「就活の軸を社風に決めたはいいが、どう伝えれば良いのか」と悩んでいる人もいることでしょう。
軸を決めていても、伝えたいことが明確になっていなければ、熱意が企業側に響かず「どこの会社でも良いのではないか」と思われてしまう可能性があります。
この記事では、就活の軸を社風にした場合に焦点を当て、軸にする際のポイントや注意点などについてくわしく解説しています。
軸を社風にした、または社風にしようと悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
就活の軸を社風にするのはあり?
社風とは、企業独自の価値観や、社員全体で大切にしているものの方向性を示すものです。
「どこも同じじゃないのか」と思うかもしれませんが、企業によって毛色はさまざまです。
企業の方針が自分に合っていると感じて興味を抱くことは、長く働いていくには欠かせない部分と言えるでしょう。
また、社風が自分に合っていないと、やりたいことができないと感じて苦しくなったり、後悔してしまったりする可能性も否めません。
会社の雰囲気に合わず、入社後にすぐ辞められてしまうのは、企業にとっても非常に問題です。
社風を用いてうまくアピールができれば、企業のことを理解しているというアピールにもつながります。
そのため、就活の軸を社風にするというのは問題ないと言えるでしょう。
就活の軸を社風にするメリット
就活の軸を「社風」にする場合は、まず、具体的なメリットを整理しておきましょう。
あらかじめ就活の軸を社風にするメリットを理解しておけば、実際に就活の軸を設定した際に、どのような利点があるのかわかりやすくなります。
就活の軸を決めるうえで迷っている人は、特に判断しやすくなるでしょう。
具体的なメリットは、以下の2つがあります。
自分に合う社風の企業に就職できる
自分の価値観が企業に伝わりやすい
いずれも重要なメリットなので、就活の軸を社風にすれば、就活を進めるうえでさまざまな利点があることがわかります。
では、メリットを具体的にチェックしてみましょう。
自分に合う社風の企業に就職できる
就活の軸を社風にすれば、自分が求める社風の企業に就職しやすくなります。
志望先企業を見つけるうえで、毎回社風をチェックしながら選ぶため、求める社風の企業に巡り会いやすくなるということです。
社風に注目して企業を選べば、自分が理想として掲げる働き方のイメージ像が浮かぶため、どのような場所でどのように働きたいのかが明らかになります。
それによって、自ずと選ぶべき企業も絞られてくるため、自分にとって快適さを感じられる企業を見つけやすくなります。
そのため、働き方や職場の雰囲気などをとにかく大事にしたい、という人には就活の軸を社風にすることはおすすめといえます。
快適な環境で仕事ができれば、総合的にストレスを感じにくく、安定的に長く働き続けられます。
入社後、早期離職してしまうケースにも至りにくいでしょう。
自分の価値観が企業に伝わりやすい
就活の軸の軸を企業の社風にすれば、自分の価値観が、より明確に企業に伝わるようになります。
企業は就活の軸について質問することで、学生と自社との相性を見極めようとしています。
そのため、社風をアピールすれば、企業と価値観が一致している・近いことを明確に示せるでしょう。
結果、採用担当者からは好印象を獲得でき、積極的に「入社してもらいたい」と思ってもらえます。
企業が学生を採用するうえで、企業と相性が合うかどうかは重要なポイントです。
企業の考え方・方針・理念などに共感できなければ、快適に働くこと、積極的に貢献して成果を出すことは難しいからです。
だからこそ企業は、社風に触れて自社との相性の良さをアピールしてくれる学生には、積極的に興味を持ちます。
「こういう学生なら、入社後に活躍してくれそうだ」という期待も高まりやすいでしょう。
就活の軸を社風にするデメリット
就活の軸を社風にすることは「あり」ですが、とはいえ、就活の軸を社風にすることにはいくつかのデメリットも伴います。
そのため、就活の軸を社風にして良いか迷った際は、メリットだけでなくデメリットも確認しておきましょう。
デメリットとして主に注意したいことは、以下の2つです。
他の学生と差別化ができない
そもそも社風を知ることが難しい
それぞれ十分に注意すべきポイントといえるため、ネックに感じられる場合は、就活の軸の考え方をより慎重に定めるべきでしょう。
では、2つのデメリットの詳細を解説していきます。
他の学生と差別化ができない
就活の軸を社風にする場合、ほかの学生と差別化しにくくなる点に注意が必要です。
というのも、就活の軸として社風を伝える学生は、決して少なくないからです。
そのため、面接などで就活の軸を聞かれた際は、ほかの学生と似通った回答になりやすいことが難点といえます。
企業との相性の良さ・マッチ度の高さをアピールするうえで、就活の軸は非常にわかりやすいトピックだからです。
しかし、回答の内容がほぼ同じである状態では、当然採用担当者の印象には残りません。
「伝えやすそう」という気持ちから、安易に就活の軸を社風にしているイメージもゼロではないため、聞かれた際の回答の仕方には要注意です。
就活の軸に限らずいえることですが、面接で質問された際は、差別化を意識したうえで具体的に内容を伝える必要があります。
そのため就活の軸を伝える場合は、ほかの学生と被りやすいことを認識し、エピソードなどで少しでもオリジナリティのある内容を考えることが大事です。
そもそも社風を知ることが難しい
就活の軸を社風にする際は、そもそも、企業の社風を知ることが難しいこともデメリットの一つになります。
企業が明確に「社風は〇〇である」と定めていればまだ理解はしやすいですが、そうでない場合は、自分自身で志望先企業の社風について解釈しなければなりません。
しかし、中途半端な解釈では、「理解が追いついておらず、企業分析不足だ」ととらえられる可能性があります。
結果、あまり良い印象にはならないため、選考通過は難しくなってしまうでしょう。
そういった事態を避けるためには、まずはしっかりと企業研究・分析を行い、社風について理解を深める必要があります。
社長の言葉・企業の歴史・経営理念などを調べると、どのような経緯をもって今の社風になったのかがわかってきます。
また、ほかにはインターンに参加したり、OBOG訪問を通じて情報を共有してもらったりする対策も考えましょう。
くれぐれも、社風についてはあいまいな解釈をしないように注意し、企業研究・分析を通じて総合的に理解を深めることが大切です。
就活の軸を社風にする際の注意点
ここからは、デメリットのほかの気をつけたいポイントとして、就活の軸を社風にするときの注意点をいくつか紹介していきます。
特に、就活の軸を考える際は、ほかの学生との差別化が重要です。
差別化を意識しなければほかの学生と内容が被る可能性が高くなり、せっかくのアピールも、印象に残らず台無しになってしまいます。
そのため、差別化を意識したうえで注意点は、以下の4つがあります。
企業の社風を正確に理解する
その企業でないといけない理由を明確にする
自分のエピソードを交える
その社風だからこそ、貢献できる要素を加える
これらを意識して就活の軸を決めれば、差別化が実現され、内定につながりやすくなる回を用意できます。
では、注意点の詳細を一つずつ見てみましょう。
企業の社風を正確に理解する
就活の軸を社風にする場合は、まずは、何よりも企業の社風を正確に理解する必要があります。
明確に社風について書かれていない状態では、企業のことをよく知らなければ、社風を正確につかめません。
自分で解釈した結果、その解釈に誤りがあれば、間違ったかたちで自分の適性や企業との相性の良さをアピールしてしまうことになります。
なお、正確に志望先企業の社風を理解するためには、OBOG訪問など、現場社員の生の声を聞くことが重要です。
OBOG訪問では、リアルな職場の雰囲気などの内部事情を直接教えてもらえるため、社風を理解するうえで良い機会になるでしょう。
表面的に見て判断する社風と、現場社員から教えてもらった情報に基づいて判断できる社風では、やはり後者のほうが正確性が高いといえます。
就活の軸を社風にする際は、積極的にOBOG訪問の機会を作り、志望先企業の社風についてよりリアルに理解を深めてください。
その企業でないといけない理由を明確にする
その企業でなければならない熱意を伝えることは、非常に大切です。
「社風が魅力的だと思った」と一言で言っても抽象的になってしまい、どの部分に対して何魅力を感じたのかが第三者には伝わりません。
ありきたりな言葉を使ってしまうと説得力に欠け「ほかの企業でも良いのでは?」と思われてしまいます。
また、その企業でなければならないという熱意が伝わらなければ「入社してもすぐに辞めてしまうのではないか」という不安を企業に与えてしまう可能性もあります。
それらを避けるためには、なぜ応募先の企業の社風が自分に合うと思ったのかという部分を、具体的に説明できるよう準備をしておく必要があるでしょう。
企業研究をしっかりと行い、その企業で働きたいと思った理由を明確にしてください。
自分のエピソードを交える
就活の軸を社風にする場合は、ほかの学生と差別化を行ううえで、自分のエピソードを交えることが必要不可欠となります。
自分のエピソードを交えて就活の軸が社風であることを伝えれば、ほかの人とはかぶらない背景・根拠などをアピールでき、回答が具体化されることで採用担当者の印象に残りやすくなります。
企業の社風を気に入り、エントリーを決めている学生はたくさんいるため、シンプルに社風が就活の軸だとアピールすることは良い手とはいえません。
そのため、採用担当者にインパクトを与えるうえでは、細かいエピソードに基づいたアピールが重要です。
過去にどのような経験があり、それがどうきっかけとなって企業の社風に魅力を感じているのか、などのアピールにつなげればより具体性と説得力のある内容になります。
自分が経験したエピソードは自分だけのものなので、差別化も実現しやすくなるでしょう。
その社風だからこそ、貢献できる要素を加える
注意したいのは、あくまで、社風は手段でしかないという点です。
就活の軸が社風ゆえに志望先企業を選んだことはわかっても、最終的に、自分を採用させたい理由にはなりません。
就活は、最終的には自分の魅力を売り込んで内定を獲得する場なので、自分を採用することで企業にはどのようなメリットがあるのか伝える必要があります。
そのため、その社風だからこそ自分にはどのような貢献・活躍が可能なのか、具体的に示すことは忘れないようにしましょう。
入社したあとの自分の将来の姿を、社風に絡めて効果的にアピールすることで、企業からは「会社のメンバーに加わってほしい」と思ってもらえるものです。
単純に就活の軸が社風であり、自分の考え方と企業の価値観が共通していることを伝えるのみでは、事実に触れるだけで終わってしまいます。
最後は自分を採用するメリットを示し、内定獲得につながるアピールを行いましょう。
就活の軸の答え方
就活の軸を聞かれた際にスムーズに対応するためには、具体的な答え方を知っておくことが重要です。
答え方のポイントや流れを理解しておけば、要点を押さえてわかりやすく就活の軸を述べられ、良い評価を獲得しやすくなります。
就活の軸の答え方は、以下の3ステップになります。
結論から述べる
具体的なエピソードを話す
どのように企業に貢献するのか話す
上記の流れで就活の軸を回答すれば、就活の軸が社風であることをより魅力的に伝えられるでしょう。
就活の軸の答え方がわからないときは、ぜひ参考にしてみてください。
では、以下からステップごとに重要なポイントなどをまとめていきます。
結論から述べる
就活の軸を答える際は、結論から述べることが肝心です。
というのも、先に結論に触れて伝えたいことの要旨をはっきりさせたほうが、面接官も内容をスムーズに理解できるようになるからです。
これは就活における適切な回答方法として、基本的にすべての質問の答え方に当てはまるため、しっかり覚えておきましょう。
就活の軸の場合は、「私の就活の軸は〇〇です」という答え方で始めます。
もし先に結論の根拠やエピソードなどを話してしまうと、面接官にとっては、何を伝えたいのかわからないまま話がスタートすることになります。
結果、伝えたいことをつかむことに集中できなくなるため、「わかりにくかった」という印象ばかりが強くなってしまうものです。
なお、結論は短く端的に伝えるほど、聞いている人の印象に残りやすくなります。
そのため、就活の軸について話し始める際は、自分の就活の軸が何なのか簡潔にまとめるようにしましょう。
具体的なエピソードを話す
面接などで就活の軸を述べる際は、先に結論をはっきり伝えたうえで、具体的なエピソードを話しましょう。
エピソードは、ほかの学生との差別化を実現できる大事なポイントです。
エピソードを交えて話さなければ、具体性に欠けるせいでほかの人の回答と似た回答になってしまい、印象が薄くなります。
なぜその社風が自分の就活の軸なのか、過去にどのような経験があり、なぜその社風が良いと感じているのかなどを詳しく説明していきましょう。
自分が実際に体験しているエピソードを交えたアピールには、説得力があり、わかりやすさもアップします。
自分だけのオリジナリティも加わるため、面接官にとってはインパクトの強いアピールになり、高評価につながります。
なお、せっかくエピソードを入れても、具体性が足りなければ本末転倒です。
「誰が」「何を」「どこで」「何をした」などの具体的な内容は、しっかり盛り込むようにしましょう。
どのように企業に貢献するのか話す
就活の軸の答え方では、最後に、どのように企業に貢献するのかアピールすることが大事です。
これは、自分を採用することは、企業にとってどのようなメリットがあるのか示す重要なポイントになります。
その社風の中で働くことで、自分・企業双方にとってwin-winの結果になることを明確に伝えましょう。
その社風があるからこそ自分はこのような貢献ができる、そのため企業にとってもメリットがある、ということを伝えなければ自分を採用してもらう決め手にはなりません。
社風を気に入っていることをアピールしても、それは自分だけに都合の良い話であり、企業にとっては何もメリットを感じられないものです。
そのため、就活だからこそ自分を売り込まなければならない点を認識し、貢献・活躍の仕方を明確に伝えることが重要となります。
就活の軸の答え方についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
就活の軸を社風にする際の例文5選
チャンスは誰にでも平等にある社風
私は、御社の「新しいものを生み出すチャンスは誰にでも平等にある」という風通しの良い社風にひかれ、志望しました。
インターンシップに参加させていただいた際は、さまざまな意見を出し合いながら、全員で1つのものを作り上げていくという社員の方々のイキイキとした姿を拝見いたしました。
その分け隔てなくコミュニケーションを取れる御社の風通しの良さは、周囲と連携を取り、協力しながら目標を達成するときに力を発揮する性格の私にとって、伸び伸び働ける環境であるのではないかと強く感じています。
また「ものづくりで人々に貢献し、想像の未来を創造で実現する」という経営方針は、ものづくりで未来に貢献したいと強く考える私にとって、とても感銘を受けるものでした。
入社した際には、チームで力を発揮する性格と現在持っているスキルを活かし、さらなるスキルアップを目指しながら自由な発想や意見を絶やすことなく、御社の創造と未来に貢献したいと心から思っています。
上司との距離が近く、コミュニケーションがしやすい社風
私の就活の軸は、上司との距離が近く、コミュニケーションがしやすい社風の企業で働くことです。
私が所属していた高校テニス部は、強豪校ゆえの厳しさがあり、上下関係もしっかりしていました。
そのため、先輩のいうことが絶対的である雰囲気が強く、上下関係のマナーを身につけられた部分は良かったものの、息苦しさを感じるときはありました。
しかし大学テニス部は、高校時代と雰囲気が全く異なり、学年関係なく意見を交わし合うことを大事にしています。
私はギャップに衝撃を受け、全員でコミュニケーションを取りながら円滑に部を回すことの快適さに感動しました。
練習方法も学年関係なく皆で相談できるため、意見を言いやすい環境で、練習にも集中しやすいことが大学テニス部の魅力だと考えました。
就職後も、このようなコミュニケーションを交わしやすい環境で、スキルを積極的に伸ばすことを望んでいます。
部活で培った集中力には自信があるため、入社後は御社の社員同士の距離が近い環境にいち早くなじみ、積極的に業務に集中し成長を遂げたいと考えます。
成長意欲が高い社風
私の就活の軸は、成長意欲が高い社風の会社で働くことです。
私は大学時代に、コールセンターのアルバイトを経験し、電話での法人営業を経験しました。
新規顧客獲得のためには自分なりにトーク方法を工夫する必要があり、最初こそうまくいかず悩むこともありましたが、徐々に試行錯誤を繰り返しながら成果につなげていくことにやりがいを感じるようになりました。
そのように感じるようになったきっかけには、アルバイト先の雰囲気が、全体的に成長意欲が高かったためです。
成績の上がらない従業員には良いトーク方法を共有したり個別にミーティングしたりするなどの配慮があったため、私は刺激を感じながら、自分の成長を楽しむことができました。
就職後も、成長意欲の高い現場で積極的に業務に関わり、成長を遂げていきたいと考えています。
そのため御社に入社した際は、アルバイトで鍛えた営業スキルを活かしながら、将来的には成績1位を目指したいです。
若手からの意見をよく取り入れようとする社風
私の就活の軸は、若手からの意見をよく取り入れようとする社風の会社で働くことです。
私は先日、Web制作会社で長期インターンを経験し、ホームページ制作の業務に携わりました。
インターン先の企業は、成長促進を目的として若手の意見を重視しており、私自身も意見を求められたことはたくさんありました。
最初は何をいえば良いかわからず戸惑いましたが、積極的に考えて発言したデザインが採用された際は、強いやりがいを感じられました。
また、それと同時に思考力や発想力の成長を感じ、業務に関わる機会をもらえることは自身の効率的な成長につながることを実感しました。
そのため就職後も、若手の意見を積極的に取り入れようとする企業で仕事をすることを希望しています。
貴社に入社した際は、意見を聞いてくださる環境に自ら溶け込んでいき、若手のうちから迅速に成長したいと考えています。
チームワークを重視する社風
私の就活の軸は、チームワークを重視する社風の会社で仕事をすることです。
私は大学でボランティア活動に力を入れており、町のゴミ拾い活動に頻繁に参加しています。
私がよくゴミ拾いに参加する地域は、町の性質上、路上のゴミが多い地域のため、チームワークを意識しながら効率よく動くことが求められます。
先日参加した際は、普段と比べてゴミの量がさらに多かったため、集中して周りと連携を取ることを心がけ、一つひとつの作業を行う際のコミュニケーションを欠かさないように徹底しました。
このことで作業はスムーズに進み、皆がいつも以上にチームワークを意識して行動したからこそ、通常よりも早く作業が完了しました。
私はこのようにチームワークを意識して動くことで、大変な作業もトラブルなく、かつ効率よく終えられることに、いつも気持ち良さを感じています。
そのため、就職後もチームワークを重視する環境に身を置きたいと考えます。
入社後は培った協調性やコミュニケーション能力を活かし、チームワークを形成することで、お客様へ迅速にサービスを提供したいです。
就活の軸を社風にするときは熱意を伝えよう!
就活の軸を社風にする際は、自分の熱意や、他社にはないその企業の魅力を自分なりに伝えることが重要です。
言葉に説得力が出るように、企業研究や自己分析をおこたらず、どんな社風が自分に合っているのか・どんな企業で働きたいのかなど、何度も繰り返し見つめ直してください。
社風を理解するには、まず自分をきちんと理解する必要があります。
これまでに紹介したポイントや注意点を参考にしながら、良い結果を出せるように準備していきましょう。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート




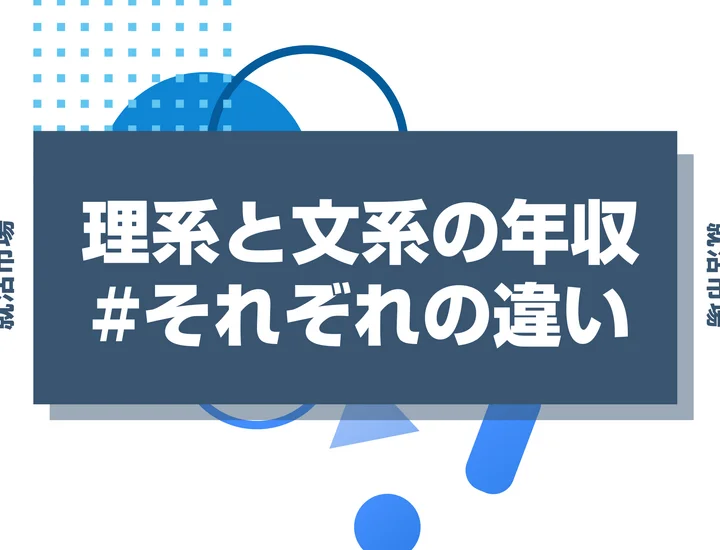
_720x550.webp)